- Home
- エミール・デュルケーム
- エミール・デュルケームまとめ
エミール・デュルケームまとめ
- 2016/3/27
- エミール・デュルケーム
- コメントを書く
Contents
エミール・デュルケームとは
プロフィール
デュルケームは「現代社会学」の建設者として、マックス・ウェーバー、ゲオルク・ジンメルと並び称される。ユダヤ教ラビの息子に生まれたそうだが、棄教して高等師範学校へ進んだ。本来ならばデュルケームは宗教者になるはずだったらしい。1893年に『社会分業論』、1895年に『社会的方法の基準』、1897年に『自殺論』を書いた。
エミール・デュルケーム(Émile Durkheim、1858年4月15日 – 1917年11月15日)は、フランスの社会学者。デュルケム、デュルケイムなどと表記されることもある。オーギュスト・コント後に登場した代表的な総合社会学の提唱者であり、その学問的立場は、方法論的集団主義と呼ばれる。また社会学の他、教育学、哲学などの分野でも活躍した。(wiki)
社会唯名論と社会有機体論(社会実在論)の違い
| 社会唯名論:実在するのは個人であり、社会はたんなる形式にすぎない |
社会有機体論:社会は個人に還元できない有機的存在 ->個人を超えた社会が実在していることを前提に社会を考える(社会実在論) |
人間が社会をつくるのか、社会が人間を作るのかという問題でもある。個人の心理に還元するのか、社会的要因を見出すのか。社会が先なのか、個人が先なのか。アメリカ社会学の場合では「個人」が先であり、ヨーロッパ社会学の場合では「社会」が先と考える傾向があるそうだ。
この二つは対立している。そしてこうした問題はなぜ生まれたのか。「危機の時代」だからだ。伝統的・農村的社会が崩壊し、工業的・都市的社会へ移行していく中で、今までの秩序が崩れ、新たな秩序が模索されている時代だからこそ、こうした問題関心が生じたといえる。ヨーロッパの「古典的な近代の枠組み」が危機にひんしていたのである。知のパラダイムの転換期であるといえる。
方法論的個人主義と方法論的集団主義の違い
方法論的個人主義:個人を起点に社会を考える。個人の意思決定の集積が社会を形成する。 ex社会唯名論:社会は存在せず、存在するのは個人の集合だけ。 マックス・ウェーバーの「理解社会学」がその代表。理解社会学とは、社会的事象を説明するには、外面的な因果関係を捉えるだけでは不十分で、行為者にとっての意味や動機が問われなければならないと考え方。 |
方法論的集団主義:個人を超えた社会が実在していることを前提に社会を考える。 ex社会実在論:前述 デュルケームの社会学主義が代表。個人の外にあって個人を拘束する、集団に共有された行動・思考様式を「社会事実」よ呼んで、これを研究するのが社会学であるとした。 |
近代社会学の知の枠組みと、デュルケームの知の枠組みの違い
近代社会学の知の枠組み:個人を実在する実体と考え、社会を個人から導き出し説明する考え方(社会唯名論) ex功利主義(功利主義に関する記事)、アダム・スミスの経済学、ヘーゲルの哲学、ホッブズやルソーの社会契約説 個人の行動に制限を加えるために、社会が生み出される。 |
現代社会学の知の枠組み(デュルケームの社会学主義):社会が個人に還元できないという立場。個人の外にあって個人を拘束する、集団に共有された行動・思考様式を「社会事実」と呼んで、これを研究するのが社会学であるという考え方(社会実在論、社会有機体論)。 現代社会学は基本的に、社会は個々人の集まり以上のものだという考えを前提としている。 デュルケームは社会契約説等の社会唯名論的な考え方を、神話的であり、思弁的(思考や論理にのみ基づいているさま)であるとして、経験科学としての社会科学としてみれば説得力がないと考えた。 |
社会的分業とはなにか。機械的連帯と有機的連帯の違い、アノミー的連帯(『社会的分業論』)
デュルケームにとって社会とは、「人々の相互作用を統合する道徳的な力」である。デュルケームの関心は社会を統合する道徳力としての社会にある。
社会的分業
社会的分業とは:社会の内部における産業や職業の職能的専門分化 (他の定義)労働が社会のさまざまな生産分野に専門化することによってつくりだされる社会経済的編成。歴史的にみて工業,農業,商業等の経済部門への分割は一般的な社会的分業,鉱業・機械工業・繊維工業等の部門内専門分割はより特殊的な社会的分業といえる。 |
たとえば料理をつくるときに、野菜を切る人、炒める人、食器を洗う人といったように分業する。役割がそれぞれにあたえられると、「責任感」が生まれ、「作業の能率や効率」が上がることがあり、同時に「連帯感」が生まれる。このように、責任感や連帯感を生み出す分業をデュルケームは「社会的分業」と呼んだ。社会的分業を通してできあがる、ある種の規範によって結びついた「連帯」を「道徳的連帯」という。
機械的連帯
| 機械的連帯とは:人々が同質的でそれぞれが没個性的な活動しかしないことによって存立する社会諸関係の様式 |
伝統的な社会では個人は社会に埋没し、個性をもつことは少なかったという。日本でも「ムラ社会」のように、出る杭は打たれ、個性よりも同質性が重んじられていたことからわかる。あるいはみんな稲作をするし、狩りもするといったような同質性が考えられる。機械的連帯は、類似的な個人の連帯なのである。このように、個人が社会に従属する連帯を機械的連帯といい、機械的連帯が優位する社会を「環節的社会」と呼ぶ。同じ形の機能を持つ環節が寄せ集められている社会である。
わかりやすい説明をみつけたので引用する。
機械的連帯というのは、ベルトコンベアーの脇にずらりと人が並んで、もくもくと単純作業を繰り返すような、没個性的なロボット的な連帯のあり方を指す。換わりならいくらでもいるんやで、ってなもんだ。同質性ゆえの連帯。
一方、有機的連帯というのは、ひとりひとりの個人が、その人らしさを発揮させて、むしろ個々の違いがあるからこそ連帯して、適材適所で力を発揮させようとするような在り方を指す。異質性ゆえの連帯だ。(引用元)
代替可能性と、代替不可能性と考えるとわかりやすい。恋愛もそうではないだろうか。君じゃなくても別にいいと、君じゃなきゃだめなら「責任感」や「連帯」の強さが違う。
有機的連帯
| 有機的連帯とは:分業による相互依存によって有機的な全体を生み出す社会諸関係の様式 |
環節的社会の人々が、それぞれの能力や個性によって異なる役割を担うようになると、それぞれの利点を活かした「分業」が発達するようになる。社会全体の結びつきはより「複雑」になっていく。分業によって複雑になった連帯を「有機的連帯」という。
「産業社会(工業化の進展した社会)」において、個人は個性化し、互いに異なる機能をはたすようになり、その活動は相互に依存する傾向を強めるようになる。昔は肉屋、魚屋、服屋、公務員、弁護士、医者、外科、内科、歯医者、パスタ専門店、パスタを作る人、パスタの原料を作る人、・・・考えればいくらでも溢れて出てくるような分業はなかっただろう。医者はひとりで全てひとりでやっていただろう。肉と魚は同じ店で売られていたかもしれない。米を作る人、狩りをする人、という大まかな二種類しかなかったかもしれない。工業化社会においては、ネジを作る人、ネジを組み立ててパーツを作る人、パーツを使って車を作る人、車を売る人など多様な分業体制が整っている。多様性、複雑性が増大する社会である。依存的というのは、たとえばネジがなければ部品がつくれないというように、相互依存的であるといえる。有機的連帯が優位する社会を「有機的社会」という。
機械的連帯から有機的連帯へ
| デュルケームの主張:社会内部の相互作用の密度が増大するにつれて分業は増大し、機械的連帯は有機的連帯へ移行していく。 |
デュルケームは人々の結びつきを複雑で強固にする社会的分業が発達すればするほど、社会はより「道徳的な性質」を帯びるようになると考えていた。道徳とは、一般的には「自分の良心によって、善を行い悪を行わないこと」という意味だ。デュルケームの文脈においては、責任感や連帯感によって生じる「規範」によって結びついていることを意味する。規範とは一般的に「判断・評価・行為などの、拠(よs)るべき規則・規準」を意味する。たとえば、なにが正しいか、正しくないかといった基準だ。デュルケームにとって「社会の進化」とは、社会の内部に「多様性」が生み出され、個人の間に多様な差異が生ずることである。社会を維持するためには多様性を統合する作用(分業)が必要なのだ。
アノミー(無規制)的分業
| アノミー(無規制)的分業とは:有機的連帯の異常状態。無規制的な産業化のために諸機能の相互依存よりも不統合が、有機的連帯よりも弱肉強食の対立・抗争が、むしろ支配的になっている分業体制を意味する。 |
メモ:相互依存の対義語は「不等号」。連帯の対義語は「対立・抗争」。
経済が穀物から鉄へ、農業から工業へと重心をうつし、工業化する中で、分業による連帯は弱まり、制限されていくようになった。その結果、道徳的な結びつきも弱くなっていったのである。車の比喩で言えば、ネジを作る人、部品を作る人、組み立てる人、車を売る人など分業体制が工業化の結果生じてきていたが、各々の担当の人は自分のやっている作業が全体のなかでどのような作業かわからず、孤立してしまってきている状態だ。それぞれの担当同士のつながりが薄れ、連帯感や責任感、やる気もなくなっていってしまうような状態だ。
デュルケームが生きた時代は19世紀末であり、「近代資本主義」の爛熟期であった。宗教や職業組織などの「規範力」は力を失いつつあり、人々は自己の「欲望」のコントロールを失いつつあったのである。デュルケームにとってアノミーとは、「社会による欲望の無規制状態」を意味する。社会による「道徳規制」が弛緩すると、個人の欲望が拡大してしまうのだ。食べ過ぎはよくない、みだらな性生活はよくない、いらないものを買い過ぎることはよくない、遅刻してはいけない。こうした道徳による規制が、宗教への不信、共同体の解体などによって機能しなくなれば、人々は渾沌の中に投げ込まれ、何をしたらいいのかがわからなくなってしまう。「どこへ行けばいいのか」状態である。昔なら村の長や、牧師、両親が進むべき方向性や守るべき道徳を教えてくれたのだ。
個人主義とアノミー(無規制)的分業
アノミー的状態を打破するためには、「個人を尊重する」という新しい道徳が必要だとデュルケームは論じている。いわゆる「個人主義」だろう。個人主義は「道徳的連帯」も可能にするのだ。
個人主義とは、ここでは「個人の自由を増大させる立場」と考えていい。個人の自由を増大させれば、諸個人は有機的連帯を強め、それにともなって社会の道徳的密度も増大するとデュルケームは考えた。
(なぜ個人の自由が増大すると有機的連帯を強めるのか?)
おそらく機械的連帯において、個人の自由は制限されている。出る杭は打たれるように、均質的だ。制限された個人の自由を増大させると、人々が自分の能力にあった仕事をすることができる。つまり多様性が増大し、互いに異なる機能をはたすようになる。その結果、相互に依存するようになり、連帯感や責任感が強くなり、連帯が有機的になる。
デュルケームは有機的連帯という概念が、共同体の解体が進行する産業社会で必要だと考えた。
代替可能性と、代替不可能性と考えるとわかりやすい。恋愛もそうではないだろうか。君じゃなくても別にいいと、君じゃなきゃだめなら「責任感」や「連帯」の強さが違う。機械的連帯においては、君じゃなくても別にいい状態なのだ。有機的連帯において人々は自分の能力に合った仕事を自由にすることができる。君じゃなきゃだめだ、が生じやすい連帯である。米を作るのはだれだって大差がない。しかし絵かきはひとりひとり個性があるし、車のデザインだってそうだ。ひとりひとり違う。コロッケの揚げ方一つとってもそうかもしれない。「君じゃなきゃダメだ」が強ければ強いほど「つながり」も強いし、道徳的な意識も強くなる。浮気しないでおこう、デートに遅刻しないでおこう、罪を犯さないようにしようとなる。
しかし工業化が進み、大量生産の時代になると、「君じゃなくても代わりがいる状態」になってしまった。バイトなどはそうではないだろうか。単純作業に多い。責任感も持てないし、つながりもよわく、道徳的意識も弱い。個人主義、個人の自由を増大させるといっても、お金があるかどうかで大学にいけるかどうか、事業が展開できるかどうかも左右される。「われわれはどこへいけばいいのか」、「ほんとうのわたしとはなにか」、「つながりがよわいわたし」、「誰でも代わりがいる存在」などの空気が強くなると、デュルケームがいったような無規制状態になり、欲望が際限なく増大する。殺人は起こるし、盗みは起こるし、自殺は起こるし、ニートは出るし、引きこもりやいじめも増える。
社会的事実と集合意識、理論、『社会学的方法の基準』
社会的事実
| 社会的事実とは:集合的なものとして把握された集団の諸信念、諸傾向、諸慣行、集合意識 |
社会的事実とは、固定化されていると否とを問わず、個人の上に外部的な拘束をおよぼすことができ、さらに言えば、固有の存在をもちながら所与の社会の範囲内に一般的にひろがり、その個人的な表現物からは独立しているいっさいの行為様式のことである。(『社会学的方法の基準』)
簡単にいえば、個人の外にあって個人を拘束する、集団に共有された行動・思考様式が社会的事実である。有名なのはデュルケームの自殺論だろう。自殺は「個人心理や経済状況」では説明できないものがあり、戦争が起きている社会においては自殺が減ったり、カトリックよりプロテスタントのほうが自殺が多かったりする。個人の心理でなく、いうならば社会の心理において自殺が生じるのであり、社会が病気であるから、個人も病気になるといえる。
デュルケームは社会が「実在」していると考える。たとえば「統計」によって個人を超えた社会的動向を見出そうとする。カトリックよりプロテスタントのほうが自殺者が多いというのは、統計によって可視化することができる。
システムと経験科学
社会的事実はのちの「システム概念」につながるものである。集合意識が個人の意識に「内在」しつつ、かつ「外在」しているという表現は当時の人にはたやすく理解されることではなかったそうだ。システム概念を通した社会学はタルコット・パーソンズ、ニコラス・ルーマンへとつながっていく。社会システムとは、「パーソナリティ・システムとは区別される相互作用の独自の秩序」である。
社会的事実(集合意識)とは単なる「観念論(現実に基づかず、頭の中で組み立てた考え・論)」ではない。実在している。社会的事実とは行為システムから「分析的」に抽象された社会システムなのである。なぜデュルケームが「実在性」を強調するのかというと、「個人」と「社会」のシステムを分離しなければならないからである。社会的事実が社会学の対象として捉えられ、社会学は独自の対象を持つ「経験科学」として出発することになった。
経験科学とは、現象を対象とし実証的な方法で研究する学問。自然科学や社会科学など。数学・形式論理学、また規範学のような学問に対する語。
実証的の用語解説 – [形動]思考だけでなく、体験に基づく事実などによって結論づけられるさま。
(デジタル大辞泉)
実証主義、客観性
デュルケームは「社会的事実」を「物」のように、つまり「実在」しているものと考えた。社会システムは他のシステムから独立した対象なのである。デュルケームの言葉でいえば、社会的事実の「客観性」である。社会的事実を客観的な対象として扱うということは、社会学者に対して客観的な方法態度をようきゅうすることになる。デュルケームの客観性とは、個人意識と集合意識を区別するための方法的な概念であり、一般的に理解されているような客観性とは異なる概念である。
正常と病理の区別、客観性
「もっとも一般的な諸形態を示している事実を正常的と呼び、他方を病態的もしくは病理的と名付けることにしよう。((社会学的方法の基準))」
このように区別する理由は、「正常/病理の区別を研究者が事前にもつあらゆる倫理的・観念的な先入観から解放するため」である。未開社会では正常な現象が、文明社会では病理的な現象であることがある。具体例はなんだろうか。たとえば文明社会では合理性を重視することが一般的になっているが、未開社会では合理性への執着が病理的であると捉えられる。
デュルケームによれば、当時のフランスにおいて「犯罪」は正常な現象であったという。犯罪は健康な社会にとって不可欠であり、犯罪のない社会は存在しないという点からも、犯罪は正常な現象なのだ。現象が「それ自体」として犯罪なのではなく、社会の集合的・道徳的感情が犯罪という意味を現象に与える。もし意味を与えないような社会があるとすれば、たとえば殺人や窃盗という現象が犯罪とみなされない。そうした社会は「異常」であると区分できる。犯罪が存在しないということは、集合意識や道徳意識の衰弱であるとデュルケームは考える。
(メモ:疑問点)
犯罪が起こることと、現象が犯罪として認識されることは異なるのではないか。たとえば窃盗事件は起こらないが、窃盗が犯罪として認識されていることが道徳的意識の衰弱であるとは考えられない。通常犯罪とみなされるであろう現象が起こっているにも関わらず、ある社会ではそれが犯罪という意味付けがなされないことが異常であるということか。現象が犯罪として認識されているにもかかわらず、犯罪が起こることのほうが道徳的意識の衰弱ではないか。あるいは現象が起こることで、その現象に対して「その現象は犯罪だよね」という意識が共有されている状態が、道徳的意識の健全さを示すということか。犯罪という現象は現象が犯罪であるという意識を喚起させるという機能をもつということか。
目的論的分析に対する機能分析の優位
| 目的論的分析:ある現象を分析する際に、それらが形成された目的を分析する方法 |
| 機能分析:現実の相互作用の中である現象を分析する方法 |
デュルケームは機能分析の優位を論じた。
『自殺論』について
自殺とは、「他のだれとも交換できない、個人的で一回限りの体験」である。また、自殺した本人でさえ知らないことがある。なぜ自殺を避けることができなかったのかだ。もちろん経済的な困窮や個人の心理情愛で説明できる自殺もあるが、説明できない自殺もある。そうした自殺について説明しようとした人物がデュルケームである。
自殺は正常/異常の区分でいうと、正常である。それぞれの社会においてある期間に生じる自殺がおよそ一定だからだ。自殺が全く起きないような社会はその意味で異常である。自殺という現象を分析するためには、個人の心理だけに着目するのではなく、宗教、家族、政治、経済等の複合的な相互関係から分析する必要がある。
自殺論の意義は、統計データを用いることによって相互行為のシステムにおける社会システムの領域を分析的に抽出した点にある。統計は、見えないモノを可視化する(「近代の降霊術」)
自己本位的自殺(suicide egoiste)
| 自己本位的自殺とは;社会のつながりを絶たれて自殺する |
社会実在論において、個人は社会の産物であり、社会的存在としてはじめて生の存在も有意味なものとなる。したがって、社会の統合が弱体化すると、個人を生へ結びつける「絆(きずな)」もゆるんでしまう。自己本位的自殺は個人主義が行き過ぎた場合に生じやすい。
集団本位的自殺(suicide altruiste)
| 集団本位的自殺とは:社会の統合力が強すぎて自殺する |
義務的であることを特徴とし、自己本位的自殺とは逆に、社会に対する個人の地位が未発達な場合に生じる自殺である。未開社会に多く、殉教や殉死などの「自己犠牲」などが例としてあげられる。日本における「神風特攻」もこの累計ではないだろうか。
アノミー的自殺(suicide anomique)
| アノミー的自殺とは:社会が指針を与えられなくなって自殺する |
社会が急激に変化すると、人々を縛っていたさまざまな規制が弱くなり、社会は無規制状態(アノミー)に陥ってしまう。人々はそれまで抑えつけられていた欲望を解放させるが、肥大した欲望を満足させる手段がない場合、生きる気力を失い、自殺してしまう。
宗教革命、産業革命などはまさに社会が急激に変化した変わり目だったのではないだろうか。神様が私を救ってくるから、自殺はよくないと思っていたのに、「神は死んだ」と人々が叫びはじめると、なにが正しいのかがわからなくなる。自殺しても地獄に落ちないなら、自殺してもいいじゃないか、となる。あるいは神なんていないのだから悪さをしてもいいじゃないか、欲望を解放しても良いじゃないか、あるいは生きている意味なんてないのではないか、となる。「万国博覧会」などの社会が発展するときにも統計的に自殺は増えているそうだ。戦争の時には逆に自殺が減っている時期もあった。国のために頑張らなければいけないのだから、自殺は不道徳であるという道徳的な意識が、集合的に共有されるからではないだろうか。
このように、社会による道徳的規制が緩むと、個人の欲望が際限なく(無限に)拡大する状態が、アノミー的状態である。こうしたアノミー的状態は社会が困窮している時だけではなく、繁栄していくような急激な変化のときに起こる混乱である。欲望が歯止めなく拡大していくと、個人の精神的な安定は失われてしまうのだ。個人の生活に「統合」を与えていた宗教・政治・伝統的な権威が崩壊し、産業は生活の手段ではなく、自己目的化されるようになった時代である。
カトリックとプロテスタントの自殺の違いについて
カトリックよりもプロテスタントのほうが自殺率が高い。他にも、農民より商工業、女より男、軍人より市民、既婚者より独身に自殺率が高い。カトリックよりもプロテスタントのほうが社会の結合力が弱いということだ。
自殺を減らすにはどうすればいいのか
家族は小さくなって存続性を失っている。核家族化がその例だ。宗教は力を失っている。いまは魔術なんてほとんどの人が信じていない。地域共同体は統合力がないし、故郷が存在しえない。教育や宗教は社会の反映にすぎず、教育や宗教で社会を作ることが出来ない。国家は大きすぎて、つながりの実感や親近性を期待できない。
個人、統合、進歩(自由、平等、友愛)、どれも社会の存続に必要だが、バランスが崩れると自殺が生じてしまう。
デュルケームは職業集団や同業組合によって結束力を高めることを主張した。旧時代のギルドの弊害を改め、公認機関化し、国家が有機的連結を整備するべきだとした。
『宗教生活の原初形態』
デュルケームは宗教を「社会的事実」として研究の対象としました。宗教に対して興味を持ったのは、宗教が道徳力と深く結びついているからだ。キリスト教を高度な宗教と考え、未開の宗教を低級なものとする「西欧中心主義」的な偏見をデュルケームは退けた。いかなる宗教もその民族の生活と信仰を反映したものであり、上下関係はないからだ。デュルケームはもっとも単純な「原始宗教」を研究に対象とした。単純なだけにその特質がわかりやすいからだ。
聖と俗
デュルケームは宗教の本質を、世界を「聖」と「俗」に二分した。この二つの領域は共通する点を持たない。禁止(タブー)によって隔てられている。また、宗教は教会というかたちにおける「集合現象」である。特定の個人に還元することが出来ない、非人格的で神聖な力である。こうした力の源泉は集合生活の生み出す道徳的な力であり、「社会の力」であるとした。社会は諸個人を超越する力であり、個人を拘束する道徳的な力であり、個人によって崇拝の対象となるものである。聖なるものの本質は「社会」にあり、宗教とは「社会現象」である。
共同生活と価値基準を与える宗教をデュルケームは主張したが、宗教の冒涜として批判を浴びた。聖なる物の本質が社会であり、宗教とは社会現象であるというのは、冒涜として受け止められたのだ。
社会化について
社会化とは
| 社会化:社会的な動物とするべく、親が子供に施す教育 |
デュルケムによれば社会化は個人に対して一方的に働きかける拘束力をもった作用である。もし同調せずに抵抗しようとすると、強制として現れる。社会化への抵抗は周囲からの反感や報復、あるいは刑罰を招く。
ガブリエル・タルドによるデュルケーム批判
社会化される個人の側にも、自発的に社会を引き受ける契機があり、社会化はあくまでも対等な相互関係の中で行われるものと主張した。
デュルケームが与えた影響
| 構造主義 |
| 社会システム論 |
| 多元主義 |
| 現象的社会学 |
参考文献
・『社会学クロニクル』、有斐閣
・『本当にわかる社会学』、日本実業出版社
・デュルケームの『自殺論』、『社会学的方法の基準』、『宗教的生活の原初形態』
・ギデンズの『社会学』他
コメント
この記事へのトラックバックはありません。









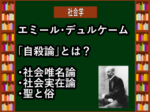


この記事へのコメントはありません。