- Home
- エミール・デュルケーム
- 【基礎社会学第三八回(4)】エミール・デュルケムの「集団本位主義的自殺」を解説
【基礎社会学第三八回(4)】エミール・デュルケムの「集団本位主義的自殺」を解説
- 2025/1/30
- エミール・デュルケーム
- コメントを書く
Contents
はじめに
動画での説明
・この記事の「概要・要約」はyoutubeの動画の冒頭にありますのでぜひ参照してください。
よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m
エミール・デュルケムとは、プロフィール
エミール・デュルケム(Émile Durkheim,1858-1917):フランスの社会学者。デュルケームと翻訳されることもある。マックス・ウェーバー、ゲオルク・ジンメルとともに社会学の創設者として扱われている。社会学の機関紙『社会学年報』(1898年)を創刊し、デュルケーム学派を形成した。甥には人類学者のマルセル・モースがいる。代表作は『社会分業論』(1893)、『社会学的方法の規準』(1895)、『自殺論』(1897)、『宗教生活の原初的形態』(1912)であり、社会学の古典となっている。
前回の記事
【基礎社会学第一回】エミール・デュルケームの「社会的事実」について
【基礎社会学第二回】エミール・デュルケームの「社会的分業」とはなにか?
【基礎社会学第三回】エミール・デュルケームの「自殺論」、「聖と俗」、「機能主義」とはなにか?意味
【基礎社会学第三六回(1)】エミール・デュルケムの社会学とはなにか、学ぶ意味や価値はあるのか
【基礎社会学第三六回(2)】エミール・デュルケムの「機械的連帯と有機的連帯の違い」を解説
【基礎社会学第三六回(3)】エミール・デュルケムの「集合意識と集合表象の違い」を解説
【基礎社会学第三六回(4)】エミール・デュルケムの「非契約的要素」を解説
【基礎社会学第三六回(5)】エミール・デュルケムの「拘束的分業とアノミー的分業の違い」を解説
【基礎社会学第三七回(1)】エミール・デュルケムの「社会的事実を物のように考察せよ」を解説
【基礎社会学第三七回(2)】エミール・デュルケムの「実証主義(合理主義)」を解説
【基礎社会学第三七回(3)】エミール・デュルケムの「社会学主義」を解説
【基礎社会学第三七回(4)】エミール・デュルケムの「社会実在論/社会唯名論」を解説
【基礎社会学第三八回(1)】エミール・デュルケムの『自殺論』の目的を解説
【基礎社会学第三八回(2)】エミール・デュルケムの「自殺の恒常性」を解説
【基礎社会学第三八回(3)】エミール・デュルケムの「自己本位主義的自殺」を解説
【基礎社会学第三八回(4)】エミール・デュルケムの「集団本位主義的自殺」を解説(今回の記事)
【基礎社会学第三八回(5)】エミール・デュルケムにおいて自己犠牲は自殺か?
【基礎社会学第三八回(6)】エミール・デュルケムの「アノミー的自殺」を解説
【基礎社会学第三八回(7)】エミール・デュルケムの「宿命論的自殺」を解説
【基礎社会学第三八回(8)】エミール・デュルケムの「統計の使い方」を解説
【基礎社会学第三八回(9)】エミール・デュルケムの『自殺論』は現代でも有効か?
自殺の四類型:集団本位主義的自殺
集団本位主義的自殺とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説
集団本位主義的自殺(仏:Suicide altruiste):社会の統合が強まりすぎ、過度に個人化が未熟になってしまう時に生じる自殺の型。
・社会の統合が強まりすぎてしまっているとはどのような状態か
デュルケムの表現で言えば「自我が自由ではなく、それ以外のものと合一している状態、その行為の基軸が自我の外部、すなわち所属している集団におかれている」状態である。
キーワード:集団本位主義的自殺
「集団規範への服従または集合的価値への強い一体感の結果として生じる自殺の型。伝統社会にみられる殉死、涅槃、極楽浄土などをめざす現世からの離脱、名誉を守り恥辱を逃れるための軍人の自殺などが、その例として挙げられている。」
「社会学小辞典」,290p「エゴイズム(自己本位)の対極にあるのがアルトゥルイズム(集団本位主義)である。社会の統合が弱すぎるために引き起こされるのがエゴイズム的自殺であったが、社会の統合は強すぎても自殺を引き起こすのである。エゴイズム的自殺が過度の個人化から生じるものであったとすれば、アルトゥルイズム的自殺は未発達な個人化が原因である。
ここでは、『自我が自由ではなく、それ以外のものと合一している状態、その行為の基軸が自我の外部、すなわち所属している集団におかれている』(『自殺論』266p)。したがって、これは未開社会によくみられる自殺である(二八八頁)。現代においては、おもに、現代社会のなかの未開社会ともいえる軍隊でみられる。」中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,65p
未開社会のタイプによくみられる自殺のタイプ
未開社会によくみられるタイプの自殺であるとデュルケムはいう。
たとえば前近代的な、ある部族を想定してみる。個性を出して転職したり、別の神を信仰したり、他の部族の異性と結婚したりすることが簡単ではないような社会である。そのような自我(エゴ)を出すような人間に対してその社会は極端な場合、追放処分を行ったり、体罰を行ったりするかもしれない。
日本的に言えば「村八分」である。もっとも、そのような体制が習慣化しているような社会では「自我を出したい」と思うことも稀なのかもしれない。デュルケムの言葉で言えば「大した理由もなく平気で個人に死を求める」社会である。
キーワード:未開社会
「第二に、集団本位的自殺であり、未開社会にしばしばみられる自己犠牲や殉死などである。それは義務的であることを特徴とし、自己本位的自殺の場合とは逆に、社会に対する個人の地位が未発達な場合に生ずる自殺である。」
『クロニクル社会学』,31pキーワード:「大した理由もなく平気で個人に死を求める」
「第2のパターンは集団本位的自殺であり、自己本位的自殺とは対照的に統合が弱い状態で起きる自殺のパターンである。ここでデュルケイムが想定しているのは、病気や老衰を恥辱と考えそこから逃れるために自殺をしたり、後追い自殺を慣行として推奨する民族、宗教的な理由から個人的な存在を脱しようとして集団的な自殺を図ろうとしたりするケースである。デュルケイムによれば、そうした社会、状況では、成員の生活、観念、感情、生業が同質的、共通であり、生きる権利を含めて、個人はその権利が一切認められない。そこでは集合的な監視により、個人間に異質性が生じることを妨げる一方、集合的な要求から個人が守られることなく、「大した理由もなく平気で個人に死を求める」(Durkheim1897=1985:260-291)。」
津崎克彦「日本における労働と自殺をめぐる社会学的研究 予備的考察」(2019),201p
「未発達な個人化という一般的状態」という社会的次元
ものすごく極端に、皮肉的に言えばロボットのようなものである。ロボットが我慢しているとはいえないだろう。ロボットは命令通りに動くのであり、自我を出さない。同じように、統合が過度な個人はほとんど集団の命令と自動的に一致して動くのである(それが良いか悪いかは簡単には判断できないことに注意)。
「個性を出そう」という発想がそもそも生じにくく、個性が社会と同一化しているような、没個性的な状態で集団本位主義的自殺は生じやすい。
機械的連帯が優勢な環節社会では非個性的、同質的な意識」が重視される。ある特定の個人が個性的かどうかというような個別の次元ではなく、社会的次元としてそもそも「未発達な個人化という一般的状態」が存在しているのである。
没個人主義とは?
デュルケムは「没個人主義」という表現は不純正語法だとしている。
なぜなら、集団本位的な社会では、「個人」という概念そのものが社会の一部として完全に吸収されており、「個人」が「没個人主義」を担うという論理が矛盾するからであるという。
「自由な欲求を持ち、比類のない個性を発展させる自律的な存在」が社会的に規制されて没個人主義を選択しているというようなニュアンスではないということである。
そもそもそのような「自由や個性を発展させる個性」を生み出す、あるいは保証するものが特定の社会の型(組織的社会)であり、社会より先に先天的に自由で個性的な個人があるわけではない。
キーワード:没個人主義
「デュルケムは,「没個人主義(impersonnalisme)」なる表現が「不純正語法」だと明言している(Durkheim:1897,259=訳,287)。つまり,集団本位主義を内面化した個人的存在など,デュルケムにとっては論理的に矛盾した概念なのである)。集団本位的自殺を産み出す社会においては,〈個人〉が「それ自身では価値のない」形象である以上,統合は,社会と個人の外的な二者関係としては決して成立しえないのである。集団本位主義が支配的である社会では,「集団の各部分」が「固有の存在の姿をしめしていない」という指摘(Durkheim:1897,237=訳,264参照)は,個人と社会との関係ではなく,集団(社会)自体の「一般的状態」(Durkheim:1897,145=訳,168)を指示しているのである。同様に,自己本位的自殺の要因である「過度の個人化」(Durkheim:1897,238=訳,265)と集団本位的自殺の要因である「あまりにも未発達な個人化」(同所)の違いも,個としての存在の内容の次元にあるのではなく,社会的存在たる人間の存在様式の相違,要するに社会的な次元の問題なのである。社会の「構造類型」が異なるがゆえに,そこに内属する人々が社会に結びつけられる様式も異なるということである。」
薬師院仁志「自殺論の再構成」,53p
集団本位主義的自殺の具体例
前近代的な社会における集合本位主義的自殺では具体的に殉死、涅槃、極楽浄土などをめざす現世からの離脱が考えられる。
殉死とは一般に「特定の人物が死んだ後、その死を共にするために、自発的または命じられて他の人が命を絶つこと」を意味する。古代エジプトなどでみられている。
近代以降においても集団本位主義的自殺は、少ないが存在するという。デュルケムが挙げている数少ない例は「軍隊における自殺」である。ただし、個人の内部において葛藤があるのか、それともその葛藤がなく、自ら進んで自殺するのかといった考察はないという。
これは自殺の定義に「意図」が含まれていないこととも関連するだろう。対照的にギデンズのような社会学者はそのような意図、個人の内省、葛藤こそを重視し、デュルケムを批判する。
家族が食べていくために生命保険をかけて死ぬような場合も、集団本位主義的自殺に近いのだろうか。これは思ったよりも難しい問題である。
なにをもって区別できるのか。自己本位/集団本位の区別の他に、自己本位とアノミーの区別、そして集団本位の下位類型の区別の問題もある(この下位類型や区別の難しさについては次の項目のコラムで扱う)。また、「家族」というように限定することにデュルケムは意義をみなしているのだろうか。
家族との結びつきが過度であり、家族のためにという気持ちが走ってしまい、対話もなく自殺する場合は集団本位的に見える。
一方、家族との結びつきが不足しすぎても、対話によって協力したり、自分の不甲斐なさにエゴが満足できないという理由で自殺する場合は自己本位的にも見える。いずれのケースでも外形的に一緒の場合がありうる。その場合は個別の要素ではなく、より抽象的な社会の一般状態から演繹させて家族や集団の状態を考えていくことも有用だろう。
キーワード:軍隊
「次に、集団本位とは何か。この類型の自殺は、デュルケームによれば近代社会にはほとんどありません。しかし、伝統社会にはよくある。たとえば、殉死です。主君に殉じるとか、あるいは宗教的な理由での集団自殺などがあります。崇拝する他人のためとか、集団の大義のための、しばしば義務的な自殺を、集団本位的な自殺と呼びます。現代にはあまりないが、軍隊においてのみ稀に見られると、デュルケームは書いています。」
大澤真幸『社会学史』,231-232p
もしあなたの大切な人が自殺をするかもしれないとしたら、あなたはどうするか
デュルケムはたしかに「心理的要因」を重要視せず、巨視的な態度をとる。しかし、「もしわたしたちの大切な人が自殺をするかもしれない状況である」と仮定してみる。
「社会が自殺を規定するのだから、私個人にできることはない、まずは社会を変えなければならない」という態度をとることはできるだろうか。なんとかして個人の働きかけによって自殺を食い止めようとする手段はないか、と模索するはずである。
デュルケムは「社会からひとりの人間が減ったからといって、それがどうだというのか」と述べたことがある。
しかし「大事な人間がひとり減った社会なんてないのもの同じだ」という態度をとることもできる。これはたしかにエゴかもしれないが、しかし巨視的になりすぎて具体的な他者を救えないような態度を私はとりきれる自信がない。
大事な一人を救うことで他の千人が犠牲になったとしても私はその一人を救うかもしれない(これを拡大すれば、愛ゆえの戦争が生じる)。多くの人はこうしたマクロとミクロの緊張関係を考慮したうえで現実的に生きていく必要がある。
もちろん、そうした危機に陥る前に巨視的な視点で社会を改善するべきであり、微視的になっている場合ではないという点は理解できる。事後対処よりも事前対処が、継ぎ接ぎよりも根本的な認識論と社会構造、制度の変革が必要であることも理解できる。
とはいえ、個人の心理的要因を知っておくことは無意味ではないのであり、社会との葛藤をミクロから理解することは意義のあることであると言える。重要なのは両者を対立的に考えることではなく、相補的に考えることではないだろうか。どちらかが正しいというものではなく、アプローチの相違にすぎない。
もっとも、助けてあげたいと思う気持ちがすでに社会からの規定(統合力の強さ)だと言われたらすこし困ってしまう。いずれにせよ、統合力の現われとしての「助力の動機」があっても「手段の研究」が不足していたら役に立ちにくい(むしろ悪影響を及ぼしうる)。そのためにもミクロの研究を欠かすことはできないだろう。
参考文献リスト
今回の主な文献
エミール・デュルケム: 社会の道徳的再建と社会学 (シリーズ世界の社会学・日本の社会学)
エミール・デュルケム: 社会の道徳的再建と社会学 (シリーズ世界の社会学・日本の社会学)
エミール・デュルケム「自殺論 (中公文庫 テ 4-2) 」
汎用文献
佐藤俊樹「社会学の方法:その歴史と構造」
大澤真幸「社会学史」
新睦人「社会学のあゆみ」
本当にわかる社会学 フシギなくらい見えてくる
アンソニー・ギデンズ「社会学」
社会学
社会学 新版 (New Liberal Arts Selection)
クロニクル社会学
社会学用語図鑑 ―人物と用語でたどる社会学の全体像
参考論文
・津崎克彦「日本における労働と自殺をめぐる社会学的研究 予備的考察」(2019)[URL]
『自殺論』の概要としてわかりやすい解説
・阪本俊生「< 寄稿論文> デュルケムの自殺論と現代日本の自殺: 日本の自殺と男女の関係性の考察に向けて」(2011)[URL]
現代的な『自殺論』の意義の解説
・横山裕一「デュルケームの集団的意識による個人行動の拘束の理論および自殺論の解説―飲酒問題の理解のための新しい手引きとして」(2018)[URL]
宿命論的自殺関連
・薬師院仁志「自殺論の再構成」(1998)[URL]
主にベナールからのデュルケムへの批判
宿命論的自殺関連
・杉尾浩規「デュルケムの自殺定義に関する一考察: アルヴァックスとの比較を通して」(2014)[URL]
・杉尾浩規「自殺と集団本位主義: デュルケム 「集団本位的自殺」 に関する一考察」(2013)[URL]
集団本位的自殺についての解説
・米川茂信 「デュルケム・アノミーの概念的分析」(1980)[URL]
アノミー関連
・合田 正人「西田幾多郎と「模倣」の問題 タルドへの小さな言及の波紋」(2018)[URL]
タルド関連
・中倉智徳「ガブリエル・タルドの『経済心理学』における労働概念について」(2008)[URL]
タルド関連
その他
・奥村隆「ジンメルのアンビヴァレンツ」(2008)(URL)
・奥村隆「距離のユートピア──ジンメルにおける悲劇と遊戯──」(2012)[URL]
・野中 亮「『宗教生活の原初形態』における「俗」の位置――デュルケーム宗教社会学の動学化のために――」(1997)[URL]
・米川茂信「アノミーの規範分析: デュルケム・アノミー概念のマートン・アノミー概念における継受と展開」(1983)[URL]
・村田裕志「社会学的機能主義系 「社会システム論」 の視角 (I)」(2008)[URL]
・盛山和夫「<特集><社会調査の社会学>説明と物語:社会調査は何をめざすべきか」(2005)[URL]
・江原由美子「『ジェンダーの社会学』と理論形成」(2006)[URL]
・赤坂真人「社会システム論の系譜(Ⅲ)──ヘンダーソンとパーソンズ;科学方法論をめぐって──」(1994)[URL]
コメント
この記事へのトラックバックはありません。






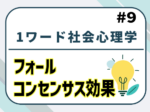
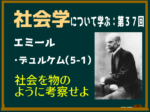
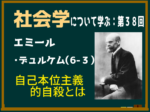
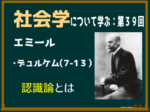
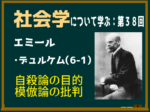
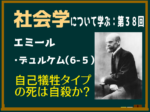
この記事へのコメントはありません。