ゲオルク・ジンメルとは
Contents
プロフィール
ゲオルク・ジンメル(Georg Simmel、1858年3月1日 – 1918年9月26日)は、ドイツ出身の哲学者(生の哲学)、社会学者である。ジムメルと表記されることもある。ドイツ系ユダヤ人(キリスト教徒)。
社会学の黎明期の主要人物としてエミール・デュルケーム、マックス・ウェーバー、カール・マルクスなどと並び称されることが多い。(wiki)
形式社会学(純粋社会学)とは~『社会学の根本問題(1917)』
社会唯名論と社会実在論への批判
エミール・デュルケームの記事で「社会唯名論」と「社会実在論」について触れたが、ジンメルはその両方を批判している。個人のみが実在であるとするのが社会唯名論で、社会を諸個人には還元しえない実在とみなすのが社会実在論である。
| 社会唯名論の欠点:われわれはいかなる場合にも与えられたものを形象にまとめあげて認識するという事情を見落としている |
社会実在論の欠点:あらゆる個人の存在と行為を社会に規定されているとみなすことは、人間に関する科学はすべてに社会に関する科学であると主張することになってしまう。諸科学を一つのツボに入れただけの綜合社会学の立場。 ジンメル「諸科学の全体をひとつの壺の中に投げ入れて、これに社会学という新しいレッテルをはるだけではなんにもならない。『社会学の根本問題』1917) A.コントやH.スペンサーらの百科全書的な綜合社会学の立場への批判です。コントは社会学という名前を作った人物で、社会学の創始者的な立ち位置にいる人物です。 |
社会唯名論と社会実在論の違いは、「距離のとり方の違い」にすぎない。両者の違いは観察や判断をする際の立場(見地)にすぎない。つまり、近くで見るか、遠くから見るかの違いである。近くで見ると個人が見え、離れてみると者かぎ編みてくる。ジンメルはこうした見地ではなく、新たな見地である「心的相互作用」という社会像を提唱した。
心的相互作用の形式
| 心的相互作用とは:人間が目的や意図をもって他者と関わる行為のあり方のことであり、具体的には、愛情による親密な関係、憎悪に基づく敵対関係、社会的地位によって結ばれる上下関係などが挙げられる(wiki)。 |
デュルケームは社会学固有の研究対象を「社会的事実」であるとしたが、ジンメルは人と人との「心的相互作用の形式」にあるとした。人と人は互いに作用しあっている。たとえば、社交、営利、援助、愛、攻撃、防御などといった目的や衝動を原動力として互いに作用しあっている。「関係の形式」であるといってもいい。
心的相互作用の「内容」と「形式」は区別される。個々の内容のとる「形式」が社会学固有の対象なのである。「内容」については他の社会科学も対象としている。社会科学とは、人類学、考古学、経済学、地理学、歴史学、法学、言語学、政治学、経済学、法学・・・と多種多様にあるのだ。そうしたものの寄せ集めを総合的に考える学問が、社会学であるとコントらは主張し、個人には還元できない社会を考える学問が社会学であるとデュルケームは主張した。そしてジンメルは、「形式」を考える学問が社会学であるとした。
宗教と心的相互作用
<従来の研究者>
教団や信者の生活を観察し、そこにある独特の生活態度を発見する。研究者はそうした生活態度は、宗教上の信仰内容によって説明しようとする。たとえば虫を殺さないというような生活態度を観察したら、生物を無駄に殺すなかれという宗教の教えがあることによって説明するかもしれない。
<形式に着目する研究者>
宗教的とみなされた生活態度が、必ずしも宗教的内容に結びつくものではない。たとえば、他の集団や生活にも同じような生活態度が見いだされると考える。いわば一般的な「形式」を見出そうとするのが形式に着目する研究者である。人々を結びつける心的相互作用から、上位と下位、支配と服従といった「関係の形式」を取り出すことができるのだ。
「内容」が異なるにもかかわらず、「形式」が同じであることが重要である。そうした相違と相似が併存しているものは、さまざまな現象の中にみることができる。両親が子供を叱ることと、警察が犯罪者を捕まえることは、「内容」が違う。しかし、秩序の回復、支配と服従、あるいは教育の「関係の形式」は同じであると考えることができる。
(+解釈)形式と内容の区別は、プラトンやアリストテレスの区別と類似している。プラトンはすべてのものは永遠普遍の本質(イデア)を実体とし、現実はその仮像であると考えた。たとえば我々の前にりんごや田中さんがいるとする。しかしそうしたものは本質ではなく、仮像であると考える。仮像とは影のようなものである。現実にあるのはそれぞれバラバラの形をしたりんごであり、りんごそのものを我々は見ることができない。イデアを「普遍」とした場合、仮像は「個別」である。
アリストテレスはそうした普遍(イデア)と個別(仮像)を区別したプラトンを批判する。個別と普遍を切り離し、普遍を上に置いて分離できないと考えたのである。りんごの例えでいうならば、個別のりんごのなかに本質が宿っていると考えていい。プラトンは本質は現実に存在しないと考えたが、アリストテレスは本質が現実に存在していると考えたのだ。アリストテレスは質料因(ヒュレー)と形相因(エイドス)にわけ、質料因と形相因の結合によって個々のものが生まれると考えた。質料因とは例えるならば木材であり、形相因は設計図である。職人の手や道具は「動力因」であり、何を作るかというものが「目的因」である。人間でいうと、質料因は魂になり、設計図にである。イスは木から出来ているし、木も何かから出来ている。そうやって遡っていけば、「霊魂」が残るとアリストテレスは考えた。最終的に残った形相は、単なる個体の構成要素ではなく、「不動の動者」であり、「霊魂」である。ちなみに、人間の霊魂は分類され、栄養能力、欲求能力、運動能力、思考能力となる。アリストテレスは人間だけが理性を持つ生物であるとした。
イデアと仮像、質料因と形相因、内容と形式は同じような関係にあると理解できる。しかし形式はより実証的になっているといえる。
形式社会学
| 社会を個人間の心的相互作用として捉え、その諸形式を対象とするものを「形式社会学」と呼ぶ。 |
「心的相互作用」が社会を社会たらしめているのである。形式社会学は、純粋社会学とも呼ばれる。
社交性 ~『社会学の根本問題(1917)』
社交性とは
社会学的には、社会を成り立たせる原点として捉えられる。ドイツの社会学者ゲオルク・ジンメルは、諸個人間の相互作用によって集団や社会が生成される過程、すなわち社会化(Vergesellschaftung)に関して、その形式における純粋型を想定し、それを社交として概念化している。それは、ジンメルの表現を使えば、「社会化の遊戯的形式」である。つまり、社交の本質は「具体的な目的も内容ももたない」自己目的性にある。したがって、社交の外部にある現実的世界を持ちこむことも、社交の外部に何かをもたらすために社交を営むことも、社交を破壊させるものとして考えられる(wiki)。
ジンメルは『社会学の根本問題』で形式社会学の例として「社交性」を取り扱っている。「社交」の一般的な定義は、「と人との交際、世間のつきあい(wiki)です。wikiの文章は分かりにくい。上に引用した説明で分かる人は少数だろう。
wikiによれば、社会化とは「諸個人間の相互作用によって集団や社会が生成される過程、すなわち社会化(Vergesellschaftung)に関して、その形式における純粋型」である。解体して解釈していこう。
まず社会とは、諸個人の心的相互作用であることを我々は確認してきた。心的相互作用とは、人と人は互いに作用しあっていることである。たとえばある人が支配し、ある人が服従しようとしている。この両者は互いに作用しあっている。こうした心的相互作用は、支配と服従という「関係の形式」としてもみることができる。このような心的相互作用によって社会が生成される。警察と犯罪者、親と子供、商人と客などの関係、あるいは心的相互作用のあつまりが社会を生み出すと考えることができる。社会化の純粋、つまりもっともわかりやすい例が社交の「形式」ということである。
社交の形式とは「社会化の遊戯的形式」であるという。要するに社交性とはゲームだ。コンパやパーティーなどの社交においては、「皆が対等であるかのように、互いを尊敬しあっているかのように」振る舞う。つまり演じているのである。社交では人々がこのような「人工の世界」、「観念的な社会学的世界」を作り上げていく。お互いに役割を演じるという、関係の形式であるということもできる。そしてこの形式は、諸個人を一定の行動をするように要請する。この場合、お互いに対等であるかのように演じることを、形式は諸個人に要請しているのである。諸個人を一定の行動をするように要請することは、「社会化」と言い換えることができる。社会人は、常識をわきまえているというイメージがある。常識を形式と置き換え、形式に基づいた行動をするような人物、つまり社会化された人物を社会人として捉えれば、ジンメルの言いたいことがわかりやすい。電車で人々は大きな声でしゃべらない。これは形式が行動を要請していると解釈することができる。
軸の回転とは
| 軸の回転:現実の生活の中で本能や目的に従って展開される諸形式が自律し、独自の生命をもって逆に人々の行動を規定しはじめるという事態 |
形式が内容を離れ、、形式自体のために存在するようになってしまう事態が、「軸の回転」である。社交性はある種の「本能」であるという。人間の「生」は本能によって、社会化の形式である社交性を身につけるのである。生から生み出された諸形式が生から独立し、自己の権利を主張するように成る。こうした軸の回転を聴いて思い出すのは、貨幣の自己目的化である。はじめはお金を稼ぐことが、神による救済の確信に繋がるといったプロテスタントの教義が内容を失い、お金を稼ぐという形式だけが残ってしまうような状況だ。お金を稼ぐという形式は人々の行動を規定する。時は金なりというように、時はお金によって理解されるようになり、愛はお金で買えると思う人も出てくる。
社交の形式とは「社会化の遊戯的形式」であった。社交という事態に、「軸の回転」という現象が見られるとしたら、ゲーム形式が自律しているということになる。ここでいうゲームとは遊戯であり、人々が「平等であるというようなデモクラシー的構造」という原理を元に、人々が演じているという状態である。うちとけた楽しい話し合いという「目的」、あるいは「内容」がなくなり、人々を平等に扱う、外部性を排除するという「形式」だけが残り、人々を規定するようになってしまうのである。「目的」に従って展開されたはずの「形式」が生命を持って人々を規定しているのである。
ジンメルはこうした「内容」から分離された「形式」を社会学の対象であると主張した。
『大都市と精神生活(1903)』、『貨幣の哲学(1900)』
大都市と倦怠について
| 倦怠(けんたい):高密な刺激に対してそれに相応しいエネルギーをもって反応できないという、無能力のこと。 |
「高密な刺激」について:大都市の生活は刺激に満ちているということだ。それゆえに、大都市的な個性の典型は「神経生活の高揚」という心理的基礎をもつ。国籍が違う人々がたくさんいるし、いろいろな店はあるし、確かに刺激はたくさんありそうだ。田舎と比較すると、刺激を受ける人物は多いかもしれない。また、インターネットが発展した現代において、大都市の役割をインターネットが一部担うようになってきているのかもしれない。
「エネルギーをもって反応できない」について:「主知主義*的」・「悟性*的」性格を大都市生活者はもつようになるからだ。
(*前提知識:M・ウェーバーの主知主義について)
可能性としてはなにごとでも知性で解明できる、割り切れるはずだという信念のことを主知主義という。理屈に合わないものや非合理なものを一切信用しません。
(*前提知識:I・カントの悟性について)
人間の認識能力の一つ。論理的な思考力。特に理性と区別して、経験界に関する知性。感性に受容された感覚内容に基づいて対象を構成する概念の能力。
倦怠の本質とは
| 倦怠の本質:事物の相違に対する無感覚 |
さまざまな事柄や物がそれぞれ違っている、つまり多様性に対して無価値であると感じてしまうことだ。相対主義は一人一人それぞれ真理があるというものですが、ひとりひとり違うゆえに、自分の考える真理など無価値なのではないか、と思ってしまうのと似ている。
ジンメルは『貨幣の哲学』で以下のように述べている。
貨幣は、事物のあらゆる多様性を等しく尊重し、それらのあいだのあらゆる質的相違をいかほどかという量の相違によって表現し、そしてその無色彩性と無関心性とによって、すべての価値の公分母にのしあがる。そうすることによって貨幣は、もっとも恐るべき平準器となり、事物の核心、その特性、その特殊な価値、その無比性を、望みなきまでに空洞化する(『貨幣の哲学』)。
たとえば工事現場で肉体を使って働く労働が一時間1000円だとする。一方で、仕事をさぼりながらデスクに向かって仕事をしているふりをするだけでも、一時間1000円だとする。労働の質は相違しているが、お金という量に換算すると、同じ金額だ。したがって、労働には多様な職業があるという多様性を等しく尊重しているが、量で比較すると違いがない。私はこんなに一生懸命なのに、量で比較されるとおなじになってしまうと感じ、自分の行為を空虚であると感じてしまう。このようなイメージができる。大都市とは、資本主義社会の中心であり、一番貨幣が渦巻く地域である。田舎なら物々交換もできるし、貨幣が都市ほど中心ではない。また、労働の種類も少ない。
こうした「倦怠感」は、大都市生活の内容と形式に適応するためにそれらの反応を拒否するという、一種の自己保存的な現象である。大都市生活における多くの刺激に対して、すべて反応していたら人間は崩壊してしまう。それゆえに、「反応の拒否」という適応が発生するのである。たとえば、電車にのっていると多様な人々、多様な音、多様なニオイがある。しかし人々はロボットのように、そうした事物に対して無反応だ。これは一種の自己保存的な適応であるといえる。こうした外的世界にたいして「無関心」という反応を示すことは、同時に自己の人格に対しても無関心になっていってしまう。
大都市と自由について
ジンメルによると、大都市生活は他に例をみないほどの「個人的自由」を人々にもたらすという。
| 個人の自由の本質:各人が所有している特殊性と無比性が生の形態に表現されること |
大都市がどのようにして個人的自由を人々にもたらすのか:一つ目に、「集団の規模拡大」であり、二つ目に「経済的分業」が考えられる。二つ目の経済的分業はデュルケームの記事でも触れている。
集団の規模拡大:大都市においては、集団の規模拡大が起こっている。多くの集団があり、その規模も大きい。たとえば韓国人の集団、日本人の集団、富裕層の集団、貧困層の集団、高学歴の集団、低学歴の集団、ヤンキーの集団、ギャルの集団がある。田舎よりも、都市の方が集団の規模が大きい。集団の規模が大きいと、多くの集団と接する頻度が高い。田舎の場合、同じような集団が多いので、接する頻度は低い。自らの集団と異なる集団と接すると、もっと違う種類の生き方があるのではないかと考えだし、活動の自由や特殊性が増大する。
経済的分業:大都市はその量的大きさと質的多様さから、多種多様な仕事を受け入れ、個人の仕事の専門家を促す。最近はスーパーがさまざまな役割を包括してしまっている気もするが、肉屋、魚屋、八百屋、文房具店、本屋、弁当屋、服屋と様々な分業が大都市では行われている。さらに、服屋の中でも、綿をつくる工場があり、肉屋の中でも牛を飼う農場がある。多様な分業があるからこそ、多様な仕事をすることができるという自由がある。田舎だったら、米を作るか、野菜をつくるか、牛を飼うかの三択くらいしかない地域もあるだろう。そこでは自由が都市よりもない。しかし、都市ほど価値の相違に関する「無関心」という反応はない。
大都市という舞台について
大都市は「すべての人格的なものを超えて成長する文化固有の舞台」であるとジンメルはいう。大都市は「集団の規模拡大」と「経済的分業」によって自由度を高め、「高密な刺激」と「主意主義・悟性的」によって価値に対して無関心度を高める。自由度が高まり、多様性が増大するゆえに、刺激が大きくなり、多様性に対して無関心になってしまうのだ。あるいは無関心とは逆の方向、つまり特色と特殊性を極端に呼び起こす場合がある。奇抜はファッションなどがその例だろう。
三者関係
| ジンメルは社会(集団)を考える際には、「二人」の人間ではなく、最低「三人」の人間同士の関係に注目する必要があると主張した。 |
・三者関係(三人以上の関係)に注目した理由:二者関係と三者関係では、関係の質が全く異なるから。
・どのように質が異なるのか:三者関係の中では、二者関係にはない「分離」と「結合」という二面的な関係が生まれる。
・ 具体例:夫婦と子どもという三者関係。。夫婦だけの関係が濃密な二者関係が不可能になり(分離)、子どもとの間で三者関係という結合が生じる。
個人と集団
私と私が二者関係では生じるが、三者関係においては「我々」と「あの人」や、「私」と「彼ら」といった、二者関係にはなかった新たな関係が生まれます。つまり、「個人」と「集団という関係が新たに生じます。
自分と他の二人の意見が食い違ったときに、「みんながそういうなら、しようがない」といったように、自分を集団に合わせるというような現象も生じます。
大都市と三者関係
大都市には三人以上、何百万人といる。その全てと「結合」という関係を結ぼうとすれば、苦痛を伴って関係が破綻してしまう。結合の反対概念である「分離」という関係、つまり他者に対して一定の無関心を維持する限りで、他人との結合がむしろ可能になると。ジンメルによれば、「個人的自由」は大都市でこそ流布しうるのは、分離による結合のおかげだという。
異邦人としてのジンメル
ジンメルの問題関心は「個人と社会の葛藤」であり、社会や他者との関係の中で、いかにして個人は個人であり得るのかである。ドイツで迫害されていたユダヤ人という異邦人(よそもの)だったジンメルだからこその関心だったといえる。
影響を与えた人物
・都市社会学者 パーク
・ドラマツルギー ゴフマン
・ミクロ社会学 ホマンズ
参考文献
・『貨幣の哲学』
・『社会学の根本問題』
・『社会学クロニクル』、有斐閣
・『本当にわかる社会学』、日本実業出版社
・ギデンズの『社会学』他
コメント
この記事へのトラックバックはありません。








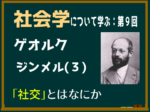

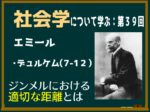

この記事へのコメントはありません。