- Home
- エミール・デュルケーム
- 【基礎社会学第三八回(3)】エミール・デュルケムの「自己本位主義的自殺」を解説
【基礎社会学第三八回(3)】エミール・デュルケムの「自己本位主義的自殺」を解説
- 2025/1/30
- エミール・デュルケーム
- コメントを書く
はじめに
動画での説明
・この記事の「概要・要約」はyoutubeの動画の冒頭にありますのでぜひ参照してください。
よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m
エミール・デュルケムとは、プロフィール
エミール・デュルケム(Émile Durkheim,1858-1917):フランスの社会学者。デュルケームと翻訳されることもある。マックス・ウェーバー、ゲオルク・ジンメルとともに社会学の創設者として扱われている。社会学の機関紙『社会学年報』(1898年)を創刊し、デュルケーム学派を形成した。甥には人類学者のマルセル・モースがいる。代表作は『社会分業論』(1893)、『社会学的方法の規準』(1895)、『自殺論』(1897)、『宗教生活の原初的形態』(1912)であり、社会学の古典となっている。
前回の記事
【基礎社会学第一回】エミール・デュルケームの「社会的事実」について
【基礎社会学第二回】エミール・デュルケームの「社会的分業」とはなにか?
【基礎社会学第三回】エミール・デュルケームの「自殺論」、「聖と俗」、「機能主義」とはなにか?意味
【基礎社会学第三六回(1)】エミール・デュルケムの社会学とはなにか、学ぶ意味や価値はあるのか
【基礎社会学第三六回(2)】エミール・デュルケムの「機械的連帯と有機的連帯の違い」を解説
【基礎社会学第三六回(3)】エミール・デュルケムの「集合意識と集合表象の違い」を解説
【基礎社会学第三六回(4)】エミール・デュルケムの「非契約的要素」を解説
【基礎社会学第三六回(5)】エミール・デュルケムの「拘束的分業とアノミー的分業の違い」を解説
【基礎社会学第三七回(1)】エミール・デュルケムの「社会的事実を物のように考察せよ」を解説
【基礎社会学第三七回(2)】エミール・デュルケムの「実証主義(合理主義)」を解説
【基礎社会学第三七回(3)】エミール・デュルケムの「社会学主義」を解説
【基礎社会学第三七回(4)】エミール・デュルケムの「社会実在論/社会唯名論」を解説
【基礎社会学第三八回(1)】エミール・デュルケムの『自殺論』の目的を解説
【基礎社会学第三八回(2)】エミール・デュルケムの「自殺の恒常性」を解説
【基礎社会学第三八回(3)】エミール・デュルケムの「自己本位主義的自殺」を解説(今回の記事)
【基礎社会学第三八回(4)】エミール・デュルケムの「集団本位主義的自殺」を解説
【基礎社会学第三八回(5)】エミール・デュルケムにおいて自己犠牲は自殺か?
【基礎社会学第三八回(6)】エミール・デュルケムの「アノミー的自殺」を解説
【基礎社会学第三八回(7)】エミール・デュルケムの「宿命論的自殺」を解説
【基礎社会学第三八回(8)】エミール・デュルケムの「統計の使い方」を解説
【基礎社会学第三八回(9)】エミール・デュルケムの『自殺論』は現代でも有効か?
自殺の四類型:自己本位主義的自殺
自己本位主義的自殺とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説
自己本位主義的自殺(仏:suicide égoïste):社会の統合が弱まりすぎ、過度に個人化が進み、個人が孤立化するとき生じやすい自殺の型。
キーワード:自己本位主義的自殺
「デュルケムの設定した自殺の類型の一つ。社会の統合が弱まって過度に個人化が進み、個人が孤立化するとき生じやすい自殺の型とされた。カトリック社会に比べて個人化の度合いの高いプロテスタント社会や、家族の規模が小さく、その絆の弱い地域などの自殺率の高さが、この型によって説明された。」
「社会学小辞典」,224p
社会的統合とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説
まず第一の原因に「社会の統合が弱まる」という事態から見ていこう。
「社会的統合」とは一般に、個人同士の結びつきや一体感を意味する言葉である。「繋がり」、「紐帯」や「凝集」なども類似した言葉である。
社会的統合:個人の行為において、個人の目的よりも集団の目的が優先される度合いのこと。もし個人の目的が優先されるなら統合は弱く、集団の目的が優先されるなら統合は強いということになる。実際は、グラデーションを帯びるものであり、過度/適度/不足の三つに単純化することができるだろう。
「ここでは、統合と規制、それぞれの概念を、行為の目的と手段との関わりから整理したい。まず、統合とは、個人の行為の目的に関わる概念であり、デュルケイムは個人の行為において、集団の目的(規範)よりも個人的な目的が優先される状況を「統合が弱い」状態、逆に個人の目的よりも集団の目的が優先される状況を「統合が強い」状態と呼んだ。」
津崎克彦「日本における労働と自殺をめぐる社会学的研究 予備的考察」(2019),200p
社会的拘束とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説
「社会的拘束」も個人の結びつきを示す言葉ではあるが、統合が自発的な要素が強いのに対し、拘束は押し付けられる、規制される、意思に反してでも守らせられる(強制)というニュアンスが強い。
拘束:個人が有する手段の有無に応じて個人が抱く目的(欲望など)が規制される状況。規制が強ければ拘束が強く、規制が弱ければ拘束が弱いということになる。
たとえば社長がお金を自分の欲望のためにギャンブルに用いることは必ずしも規制されないが、貧窮者が自分の生活資金を自分の欲望のためにギャンブルで用いることは規制されるケースがありうる(程度にもよるが)。
この場合、手段(この場合は経済力)に応じて目的が規制されることになる。
日本では生活保護者が投資やギャンブルをすることに対して批判がある。これは経済力というより、デュルケム的に言えば「職業ごとにふさわしい生活の快適度を求める規範がある」ということになるのだろう(生活保護者が職業といえるかは微妙だが)。
たとえ経済力があったとしても、宗教家や政治家がギャンブルに浸っていることは拘束されるだろう。常識的には良いこととされるボランティアや寄付であったとしても、自分の生活を著しく貧窮させるほどの過剰さであるとすれば、「あなたの身の丈にあっていない」というような何らかの拘束をうけるかもしれない。
※拘束や規制、規定といった細かい用語のニュアンスの違いはアノミーを扱うときに整理する。
キーワード:規制、拘束
「また、規制とは個人の行為の目的と手段との関係に関わる概念であり、個人が有する手段の有無に関わらず、個人が抱く目的が規制されない状況を「弱い規制」、逆に個人が有する手段の有無に応じて、個人が抱く目的が規制される状況を「強い規制」と表現した。」
津崎克彦「日本における労働と自殺をめぐる社会学的研究 予備的考察」(2019),200pキーワード:規範
「『事実,歴史の各時期には,それぞれの社会的職務の相対的な価値や、各職務に与えられるべき相対的な報酬,したがって,それぞれの職業の一般の従事者にふさわしい生活の快適度などを定める,漠然としたある感情が,その社会の道徳意識のなかにひそんでいる。それぞれの職能は,このように世論のなかにおいて序列づけられていて、各職能に与えられるべき幸福の度合いも、その序列のなかに占める地位の上下によって定められている。・・必ずしも法的形式こそとらないが,社会の各階級が正当に追求することのできる快適さの限度を、とにかくも比較的厳密に定めた実際の規定が存在するということである。』36)(傍点筆者)。
このように把握される規範規定が前項で述べた「職能の序列」の規定であることは,すでに明らかである。こらして,デュルケムは,まず,「職能の序列」の規定によって欲望ないし欲求あるいは幸福の追求が職能つまり手段と相応的に決定されることを明らかにする。」米川茂信 「デュルケム・アノミーの概念的分析」,77p
統合が弱い社会の具体例:カトリックとプロテスタント社会の比較
では、統合が弱いような社会とはどのようなケースだろうか。
デュルケムが挙げている「自己本位主義的自殺」のケースでは、「プロテスタントがカトリックよりも自殺が多いのは、プロテスタントの教会がより統合が弱いからだ」というように説明される。
プロテスタント:一般に、聖書のみを信仰の基盤とし、教会の権威よりも個人の信仰を重視するキリスト教の宗派のこと。聖書の自由な検討、解釈が許されている。
カトリック:一般に、教会の伝統や教皇の権威を重要視し、聖書だけでなく教会の教えを信仰の指針とするキリスト教の宗派のこと。聖書の自由な検討、解釈が許されていない。
なぜプロテスタントは社会的統合がカトリックより弱いのか。
カトリックの場合はプロテスタントよりも教会の権威が強く、礼拝が重視され、信者の集まりもより多い。自由な聖書解釈が許されないので教会の指導者の説教が重視される。一方、プロテスタントは教会の権威が弱く、基本的にすべての信徒は神の前で平等であると考える。
聖書の解釈は自分ひとりの責任で行うものであり、仲間や自分より地位の上の人に頼るわけにはいかない。このように考えると、横のつながりや縦のつながりがカトリックよりも弱いといえるのかもしれない。
「自由検討」が「社会的統合の弱さ」を生み出したのか、その逆かというのもポイントだろう。相互関係にあるのも確かだろうが、個別的な自由検討が社会的要因として第一に重視されているわけではない。そもそも社会の統合力が弱いから自由検討を許すような事態になってしまったのだ、と大きな要素(全体、マクロ)から小さな要素(部分、ミクロ)を説明していく方向にデュルケムの特徴があるといえそうだ。
キーワード:カトリック、プロテスタント
「キリスト教的には、カトリックだろうがプロテスタントだろうが自殺はいけないことです。ではなぜ、カトリックとプロテスタントの間で、自殺率に大きな差が出るのか。
カトリックとプロテスタントの違いはどこにあるのかというと、最も大きな違いは――デュルケームの考えでは――、プロテスタントは個人主義的だという点にあります。たとえば、プロテスタントは自分独りで聖書を読む。勝手に読んで、自分で自由に解釈するのです。しかしカトリックはそれをやってはいけない。聖書の自由検討をカトリックは許しません。だから、読めなくてもいいわけです。しかし、プロテスタントは自分で、自らの責任において解釈しなければいけない。そういうかたちで、プロテスタントは個人主義的な態度が形成される。」
大澤真幸『社会学史』,230p「デュルケムによれば、プロテスタンティズムとカトリシズムのもっとも本質的な違いは、『自由検討』ということを認めているか否かである。プロテスタントは、カトリックとは違って、聖書解釈について強制されない。信者にまかせられているのである。自殺率の違いはこのことと関係ありそうだ。しかし、よく考えてみると、『自由検討』が出てくるのは教会が指導力を弱めた結果にすぎないだろう。『自由検討』が先にあるのではない。プロテスタントがカトリックよりも自殺が多いのは、プロテスタントの教会の統合がより弱いからなのだ。デュルケムは、さらに家族や政治についても調べてみることによって、自殺の増減は一般に社会の統合の強さに反比例している、と主張したのである。」
中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,30p
社会的統合が弱くなった根本的な原因はなにか
では、「社会的統合が弱くなった根本原因はなにか」と疑問が生じるはずである。これは、「なぜ宗教革命が生じたのか(なぜプロテスタント一派が力を増したのか)」という歴史的な背景とも深く関わる問題であり、人口の増加や都市の発展、貨幣の誕生など複雑な事象が関わっている。
統合の強弱はより複雑な原因が単なる足し算ではなく掛け算的に関わっているのだろう。かなり抽象的に言えば「急激な社会の価値観の変化」などともいえるのかもしれない。たとえば人口が増加し、人々の異国間の交流が増えれば今までの伝統的価値観がそのままというわけにはいかない。
いずれにせよ自殺率が高くなったということは社会的連帯(絆)が適切に維持されていないということであり、その原因に統合の過剰な強弱や拘束の過剰な強弱があると推測することができそうだ。
それをよりミクロにみていけば、宗教、経済、法や家族のあり方の違いなど、「社会構造」といわれるものを見ていくことになる。それを見ていくツールとして「統計」が用いられるのだろう。
キーワード:急激な社会の価値観の変化
「困窮にせ繁栄にせよ、それは社会の急激な変化であり、混乱である。このとき、諸個人を統合し道徳を与える社会は弱体化してしまう。」
『クロニクル社会学』,32p
利己主義とエゴイズムの違いとはなにか、意味、定義、わかりやすく解説
統合が弱まった結果、「過度な個人化」が進むとはどういうことだろうか。
「過度な個人化」をフランス語でいうと「エゴイズム」であり、日本語では自己中心主義や利己主義と翻訳されることがある。中島道男さんは「利己主義」と「エゴイズム」を分けて定義しているので紹介したい。
利己主義:人の迷惑を顧みずあくまで自分の利益を追求する態度のこと。
エゴイズム:自分以外に献身対象がなくなり、個人の自我が過度に肥大してる態度のこと。異常な個人主義のこと。
大村英昭さんも同様に、エゴイズムは、日本語の利己主義にはかならずしも当たらないという。
「個人を超越した献身対象を見失って、生きる目標をもてない意気消沈ないし憂鬱の状態というニュアンスが強いから、むしろニヒリズムに近い」と述べている。
ここでいう個人を超越した献身対象は神であったり、社会であったりする。具体的に言えば家族、友人や恋人、近所の人達、自国民などであるが、それらの単なる集合ではない。
大澤真幸さんの説明によれば、「プロテスタントの場合には、自分で孤独に世界と自らを見つめ直し、反省することが中心になる」から個人主義的になりやすい(個人化しやすい)という。これが過剰になればエゴイズムへと至るのかもしれない。
キーワード:利己主義、エゴイズム
「これは、いわゆる利己主義、つまり人の迷惑を顧みずあくまで自分の利益を追求するということとは異なって、自分以外に献身対象がなくなり、個人の自我が過度に肥大してる状態、常軌を逸した個人主義のことである。」
中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,30p「デュルケムのいう『エゴイズム』は、日本語の利己主義にはかならずしも当たらない。個人を超越した献身対象を見失って、生きる目標をもてない『意気消沈』ないし憂鬱の状態というニュアンスが強いから、むしろニヒリズムに近い。」
「社会学のあゆみ」,98p
「だがなぜ集団に統合されていないひとが自殺しやすいのか。それは先に述べた意味での『エゴイズム』にひとが陥る結果だとデュルケムは考える。道徳的共同体に献身することなくして、『自身だけを目標としては生きられない』のだと。自由という理想も、集合意識から乖離すれば、このように『自己のみじめさあるいは虚無よりほかに反省の対象すら見いだせない状態』にひとを追い込む。」
「社会学のあゆみ」,99p
マックス・ウェーバーの脱呪術化について
私がここで思い出すのはM・ウェーバーの「脱呪術化」という表現である。重要なのは、世界が呪術的な説明から解放され、合理性や科学的思考が支配的になる過程が、「宗教革命」と深く結びついているという点だ。
この宗教革命は、プロテスタントの誕生と重なる時期にあたり、カトリックに対する批判を軸に展開された。プロテスタントは神との直接的な関係や信仰の合理化を強調し、その結果、呪術的な世界観からの脱却を加速させたといえる。
脱呪術化(脱魔術化,魔法からの解放):①呪術(神強制)から宗教(神奉仕)へ移行すること。②宗教から呪術的(非合理的)要素が徹底的に排除されていくこと。③主知主義的合理化していくこと(呪術も宗教も非合理的なので排除されていく)。
「世界を呪術から解放するという宗教史上のあの偉大な過程、すなわち、古代ユダヤの預言者とともにはじまり、ギリシャの科学的思考と結合しつつ、救いのためのあらゆる呪術的方法を迷信とし邪悪として排斥したあの呪術からの解放の過程は、ここに完結を見たのだった。」(『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』、157P、マックス・ウェーバー、大塚久雄訳、岩波文庫、1989初版、2006年第39版)
宗教的な精神が薄まってきている現代では、神を献身の対象としきることもできず、かといって周囲の人びととつながりをもつ機会もカトリックに比べて少ないので、自分のことだけを過剰に考えてしまうのかもしれない。
【基礎社会学第二十回】マックス・ウェーバーの「職業としての学問と神々の闘争」とはなにか
個別の偶然的な心理的原因よりも、社会の統合力の強さを重視
失恋や失業、家族の死などはたしかに個人の自殺の原因になりうるが、もし社会へと適切につながりを保てていれば、落ち込んだときに慰めてくれる重要な他者がいるはずであり、自殺という道を選ぶ可能性は小さいかもしれない。
あるいは自分が死ぬことによって社会になんらかの迷惑をかけるというような精神が自殺を思いとどまらせるのかもしれない。
個別の偶然的な心理的原因よりも、社会の統合力の強さという社会的原因をデュルケムは重視する。「自殺の原因はあくまでもエゴイズムであって、私生活上の出来事は偶然的な原因にすぎない」というわけだ。
ここでいうエゴイズムとはエゴイスティックな個人が多いというより、「社会のあり方がエゴイスティックな状態だ」というようなニュアンスのほうがわかりやすい。
より具体的な例で言えば、核家族よりも大家族のほうが自殺率が低いようなケースを考えることができる。
家族では、構成員が互いに支え合う密接な関係が築かれており、これが個人の孤独感を軽減し、社会的統合を強化する。核家族の場合は成員が少なく、孤立しやすいため、社会的統合が弱まりやすいといえる。地方よりも都市のほうが近所の付き合いが少ないため、統合が弱いと言えそうだ。近所の人の顔や名前すら知らない人もいる。
もちろんこれは分析の一側面にすぎず、都市部や核家族の自殺率が高い理由は他にも複雑に関わっているだろう。
デュルケムの話とは少し違うが、G・ベイトソン的に言えば「コミュニケーションが閉鎖的なために分裂病も核家族で生じやすい」と推定できる点に興味がある。ここで分裂病という精神病が遺伝的なものだけに還元されず、社会的な相互作用が重視されるという点にある(従来、精神病は主に遺伝的なものに限定されて考えられてきた)。
デュルケムは「人間は個人を超えた対象に結びついていないことには生きられない」という前提を主張している。
社会的統合が全くないような人間は生きていくことができないのである。そもそもまったく他者と結びついていない人間などこの世界にほとんどいない。コンビニで物を買うだけで、街を歩くだけでなんらかの関わりを持つのである。大事なのはその強弱であり、弱すぎるつながりは人間を自殺へと至らせやすいということである(その逆もしかりだが)。
水でいっぱいのコップに風がふいたり、振動が加えられたり、別の物がいれられたりすると溢れてしまう。
キーワード:私生活上の出来事、「人間は個人を超えた対象に結びついていないことには生きられない」
「デュルケムは、人間は個人を超えた対象に結びついていないことには生きられないという前提を立てている。集団の統合が弱体化して人々が集団にもはや結びついていないという状態は、人間がいつ自分の生命を絶ってもおかしくはないような状態におかれているのと同じなのである。そういう状態にすでにさらされているならば、ちょっとした私生活上の出来事でも、人をかすかに社会に結びつけていた絆を容易に断ち切ってしまおう。自殺の原因はあくまでもエゴイズムであって、私生活上の出来事は偶然的な原因にすぎない。」
中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,31p
統合の弱体化は数滴しかないからからのコップの水
大事なのは個別的な要因、つまり風や振動といったものではなく、そもそも「水でいっぱいのコップという状態」なのである。その反対に、数滴しかないコップが風ですぐ乾いてなくなってしまった場合、たしかに原因は風にもあるが、大事なのは「数滴しかないという状態」のほうだろう。
集団の統合が弱体化して人々が集団にもはや結びついていない(水が数滴しかない)という状態は、人間がいつ自分の生命を絶ってもおかしくはない(完全に乾いてしまう)ような状態におかれているのと同じであるとデュルケムは危惧していると比喩的に解釈できる。
もちろん水(物)とおなじ抽象レベル(論理階型)で社会が存在しているわけではないという点は気をつける必要がある。あくまでもこれは説明のための比喩である。これは個人と社会の関係も同様であり、社会はより上位の(一種独特の)抽象レベルに属しており、実在している(単に葡萄と果物の違いではなく、果物以上のなにかであるともいえる)。
統計分析例
以下のものがデュルケムの統計分析例である。ただし、分析対象は主に19世紀のヨーロッパである(集団本位主義的タイプだけにしぼっているわけではない)。
・経済発達した地域に自殺が多く、その逆は少ない
・富裕層に自殺が多く、その逆は少ない
・景気が改善されても自殺はあまり減らず、増加することがある
・教育を高く受けている人ほど自殺が多く、その逆は少ない
・男性に自殺は多く、女性は少ない
・戦争や政変においては自殺率が低下する
・農民より商工業者に自殺率が高い
参考文献リスト
今回の主な文献
エミール・デュルケム: 社会の道徳的再建と社会学 (シリーズ世界の社会学・日本の社会学)
エミール・デュルケム: 社会の道徳的再建と社会学 (シリーズ世界の社会学・日本の社会学)
エミール・デュルケム「自殺論 (中公文庫 テ 4-2) 」
汎用文献
佐藤俊樹「社会学の方法:その歴史と構造」
大澤真幸「社会学史」
新睦人「社会学のあゆみ」
本当にわかる社会学 フシギなくらい見えてくる
アンソニー・ギデンズ「社会学」
社会学
社会学 新版 (New Liberal Arts Selection)
クロニクル社会学
社会学用語図鑑 ―人物と用語でたどる社会学の全体像
参考論文
・津崎克彦「日本における労働と自殺をめぐる社会学的研究 予備的考察」(2019)[URL]
『自殺論』の概要としてわかりやすい解説
・阪本俊生「< 寄稿論文> デュルケムの自殺論と現代日本の自殺: 日本の自殺と男女の関係性の考察に向けて」(2011)[URL]
現代的な『自殺論』の意義の解説
・横山裕一「デュルケームの集団的意識による個人行動の拘束の理論および自殺論の解説―飲酒問題の理解のための新しい手引きとして」(2018)[URL]
宿命論的自殺関連
・薬師院仁志「自殺論の再構成」(1998)[URL]
主にベナールからのデュルケムへの批判
宿命論的自殺関連
・杉尾浩規「デュルケムの自殺定義に関する一考察: アルヴァックスとの比較を通して」(2014)[URL]
・杉尾浩規「自殺と集団本位主義: デュルケム 「集団本位的自殺」 に関する一考察」(2013)[URL]
集団本位的自殺についての解説
・米川茂信 「デュルケム・アノミーの概念的分析」(1980)[URL]
アノミー関連
・合田 正人「西田幾多郎と「模倣」の問題 タルドへの小さな言及の波紋」(2018)[URL]
タルド関連
・中倉智徳「ガブリエル・タルドの『経済心理学』における労働概念について」(2008)[URL]
タルド関連
その他
・奥村隆「ジンメルのアンビヴァレンツ」(2008)(URL)
・奥村隆「距離のユートピア──ジンメルにおける悲劇と遊戯──」(2012)[URL]
・野中 亮「『宗教生活の原初形態』における「俗」の位置――デュルケーム宗教社会学の動学化のために――」(1997)[URL]
・米川茂信「アノミーの規範分析: デュルケム・アノミー概念のマートン・アノミー概念における継受と展開」(1983)[URL]
・村田裕志「社会学的機能主義系 「社会システム論」 の視角 (I)」(2008)[URL]
・盛山和夫「<特集><社会調査の社会学>説明と物語:社会調査は何をめざすべきか」(2005)[URL]
・江原由美子「『ジェンダーの社会学』と理論形成」(2006)[URL]
・赤坂真人「社会システム論の系譜(Ⅲ)──ヘンダーソンとパーソンズ;科学方法論をめぐって──」(1994)[URL]
コメント
この記事へのトラックバックはありません。








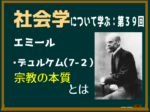


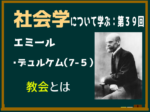

この記事へのコメントはありません。