- Home
- エミール・デュルケーム
- 【基礎社会学第三九回(10)】エミール・デュルケムにおける「集合的沸騰」とは
【基礎社会学第三九回(10)】エミール・デュルケムにおける「集合的沸騰」とは
- 2025/4/24
- エミール・デュルケーム
- コメントを書く
Contents
はじめに
動画での説明
・この記事の「概要・要約」はyoutubeの動画の冒頭にありますのでぜひ参照してください。
よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m
エミール・デュルケムとは、プロフィール
エミール・デュルケム(Émile Durkheim,1858-1917):フランスの社会学者。デュルケームと翻訳されることもある。マックス・ウェーバー、ゲオルク・ジンメルとともに社会学の創設者として扱われている。社会学の機関紙『社会学年報』(1898年)を創刊し、デュルケーム学派を形成した。甥には人類学者のマルセル・モースがいる。代表作は『社会分業論』(1893)、『社会学的方法の規準』(1895)、『自殺論』(1897)、『宗教生活の原初的形態』(1912)であり、社会学の古典となっている。
【基礎社会学第一回】エミール・デュルケームの「社会的事実」について
【基礎社会学第二回】エミール・デュルケームの「社会的分業」とはなにか?
【基礎社会学第三回】エミール・デュルケームの「自殺論」、「聖と俗」、「機能主義」とはなにか?意味
【基礎社会学第三六回(1)】エミール・デュルケムの社会学とはなにか、学ぶ意味や価値はあるのか
【基礎社会学第三六回(2)】エミール・デュルケムの「機械的連帯と有機的連帯の違い」を解説
【基礎社会学第三六回(3)】エミール・デュルケムの「集合意識と集合表象の違い」を解説
【基礎社会学第三六回(4)】エミール・デュルケムの「非契約的要素」を解説
【基礎社会学第三六回(5)】エミール・デュルケムの「拘束的分業とアノミー的分業の違い」を解説
【基礎社会学第三七回(1)】エミール・デュルケムの「社会的事実を物のように考察せよ」を解説
【基礎社会学第三七回(2)】エミール・デュルケムの「実証主義(合理主義)」を解説
【基礎社会学第三七回(3)】エミール・デュルケムの「社会学主義」を解説
【基礎社会学第三七回(4)】エミール・デュルケムの「社会実在論/社会唯名論」を解説
【基礎社会学第三八回(1)】エミール・デュルケムの『自殺論』の目的を解説
【基礎社会学第三八回(2)】エミール・デュルケムの「自殺の恒常性」を解説
【基礎社会学第三八回(3)】エミール・デュルケムの「自己本位主義的自殺」を解説
【基礎社会学第三八回(4)】エミール・デュルケムの「集団本位主義的自殺」を解説
【基礎社会学第三八回(5)】エミール・デュルケムにおいて自己犠牲は自殺か?
【基礎社会学第三八回(6)】エミール・デュルケムの「アノミー的自殺」を解説
【基礎社会学第三八回(7)】エミール・デュルケムの「宿命論的自殺」を解説
【基礎社会学第三八回(8)】エミール・デュルケムの「統計の使い方」を解説
【基礎社会学第三八回(9)】エミール・デュルケムの『自殺論』は現代でも有効か?
【基礎社会学第三九回(1)】エミール・デュルケムにおける「『宗教生活の原初的形態』の目的」を解説
【基礎社会学第三九回(2)】エミール・デュルケムにおける「宗教の定義」を解説
【基礎社会学第三九回(3)】エミール・デュルケムにおける「信念、聖と俗」とはなにか
【基礎社会学第三九回(4)】エミール・デュルケムにおける「儀礼」を解説
【基礎社会学第三九回(5)】エミール・デュルケムにおける「教会」を解説
【基礎社会学第三九回(6)】【コラム】プラグマティズムに対するデュルケムの評価
【基礎社会学第三九回(7)】エミール・デュルケムにおける「トーテミズム」を解説
【基礎社会学第三九回(8)】エミール・デュルケムにおける「神と社会はひとつである」を解説
【基礎社会学第三九回(9)】エミール・デュルケムにおける「トーテミズムの儀礼の具体例」
【基礎社会学第三九回(10)】エミール・デュルケムにおける「集合的沸騰」とは(今回の記事)
【基礎社会学第三九回(11)】【コラム】聖なる時間/俗なる時間
【基礎社会学第三九回(12)】【コラム】ジンメルにおける「適切な距離」
【基礎社会学第三九回(13)】エミール・デュルケムにおける「認識論」とは
【基礎社会学第三九回(14)】【コラム】「来たるべき社会とその聖」をベイトソンから考える
【1】聖なる期間とは
聖なる期間とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説
聖なる期間(聖なる生活、聖なる世界):一定の場所に多くの人々が集中して宗教的祭儀やコロボリーを行う期間のこと。集中性と非日常性に特徴がある。
コロボリーは宗教的な儀礼ではなく、娯楽的な行事、儀礼である。祭りのようなものだろう。
たとえば女性やイニシエーション(通過儀礼)を済ませていない若者でも参加できるという。氏族の成員が集まり、歌ったり踊ったりするという。
キーワード:聖なる期間、俗なる期間
「オーストラリアの社会生活には二つの形相がみられる。小集団に分散して各地で狩猟や漁労をおこなう期間と、一定の地点に人々が集中して宗教的祭儀やコロボリー――イニシエーションを済ましていない者や女でも近づける点で、固有の宗教的祭儀からは区別される――をおこなう期間である。前者においては、経済活動が主であり、完全に変化のない沈滞した生気に乏しい生活が続く。後者においては、状況は一変する。『ひとたび諸個人が集合すると、その接近から一種の電力が放たれ、これがただちに彼らを異常な激情の段階へ移す』(389p)。『強烈な超興奮状態』がもたらされるのである。日常の性行動の規則が破られたりもする。これが、『集合的沸騰』と呼ばれる社会形相である。」
中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,80p
キーワード:コロボリー
「第2編、第7章、第3節で扱われるコロボリーは、宗教とはあまり関係のない娯楽的な行事であり、……」
門口充徳「アボリジニ社会から構造主義へ 3: 土地と親族をめぐるアボリジニ社会の構造」(2014),217p
【2】俗なる期間とは
俗なる期間とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説
俗なる期間(俗なる生活、俗なる世界):小集団に分散して各地で狩猟や漁労をおこなう期間のこと。分散性と日常性に特徴がある。
経済活動が主であり、完全に変化のない沈滞した生気に乏しい生活が続くという。いわゆる日常生活であり、生活手段を得ることに努める期間である。
俗なる期間においては聖なるものに関わることが禁止されており、たとえばトーテム動植物を食べたり、トーテム動植物が置かれている場所を訪れることも禁止されている。
集団で活動することもあるが、規模は小さいという。たとえば家族という単位で狩りをしたりするイメージであり、氏族全体が、多くの家族が一斉に一つの場所に集まるイメージではない。
【3】集合的沸騰の定義
集合的沸騰とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説
集合的沸騰:集団が同じ場所で同じ目的を持って集まることによって、非常に強い感情的なエネルギーや一体感が生じている状態のこと。
【4】儀礼における集合的沸騰のプロセス
時系列
- (T1)人々が集合し、同質的な運動を介して緊密的・近接的な相互作用が生じる。
- (T2)各人の意識が変容し、集合的感情、集合的力が発生する。
- (T3)集合的感情を説明しようとする欲求によって、感情の発生源を象徴するような「目に見える物(象徴物)」に関連付ける。
- (T4)その象徴物が「聖なるもの」として認識される。
- (T5)その象徴(シンボル)が「聖なるもの」として認識される。
キーワード:集合的沸騰のプロセス
「①人々が集合し同質的な運動を介してなされる緊密な相互作用:「集中しているということそれ自体が例外的に強力な興奮剤として働くのである。ひとたび諸個人が集合すると、その接近から一種の電力が放たれ、これがただちに彼らを異常な激動の段階へ移すのである。
表明された感情は、それぞれに大いに外界の印象に鋭敏な全員の意識の中で抵抗なしにこだまする。すなわち、そのいずれもが交互に他のものに反響し合う。このようにして、根本的な衝動は反射されるにつれて拡充していく。進むにつれて雪崩が大きくなるようにである。そしてまた、このように強烈で、このようにあらゆる統制を脱した情熱は、自ら外部へ拡大せざるをえないので、所々方々で激しい所作・真実の叫び・あらゆる種類の耳を聾する騒音となる。そして、これらの情熱が現わす状態を強めるのに寄与する」(pp.308-9:上389頁)。②結果としての各人の意識の変容と不定形な集合的感情の発生:「このような激動の状態に達したら、人はもはや何も知覚しなくなる。それは容易に推測できることである。人は、自分自身をいっもとは異なって考えさせ、働かせる一種の外的力能に支配、指導されている、と感じ、当然にもすでに彼自身ではなくなったという感銘をうける。彼にはまったく新しい存在になったように思われる」(p.312:上393頁)。
③この感情を「説明」しようとする欲求により、感情の発生源を象徴物に固着させる:「自分の感じるきわめて特殊な印象を説明するため、人は、もっとも直接に関連している事物に、事物の持たない特性、俗的経験の対象がもたない例外的な力能、功徳を付与する」(p.603:下333頁)
④それは聖物となる:「われわれは、現在においても過去においても、社会があちゆる断片から聖なる事物を創造するのをみる」(p.304:上383頁)、「この感情は客観化するためにある対象に固着する。こうしてこの対象は聖となる」(p.327:上411頁)。
⑤象徴の喚起力により集合的感情の永続化が可能となる:「象徴がなかったなら、社会的感情は束の間しか存在しえないであろう。……これらの感情が表される運動が永続する事物に記入されると、感情それ自体が永続的になるのである」(pp.330-1:上415-6頁)。」
小川伸彦「デュルケームの儀礼論への一視角.二つの規範と「社会」の実在性」,37-38p
集合力とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説
オーストラリアの未開社会における積極的儀礼は氏族や部族が集合して共に行為することであり、第一のプロセスに当てはまっている。歌ったり踊ったり、雨乞いの儀式をしたりするわけである。次に、人々が集合した結果、「集合力」が生じる。
集合力:集合的沸騰状況で人間の個我意識を超えた大きな力の経験として生まれ、宗教的象徴と結合してタブー・道徳規範などの規制力になり、あるいは革新的な象徴と結合して既存秩序を脱構築する力にもなるもの。
キーワード:集合力
「デュルケムの用語。社会的事実、集合意識の作用をエネルギーの面から捉えた観念。その『自殺論』(1897)では集合力は、自殺傾向など世論の潮流の働きとして説明された。また『宗教生活の原初的形態』(1912)で集合力は、集合的沸騰状況で人間の個我意識を超えた大きな力の経験として生まれ、宗教的象徴と結合してタブー・道徳規範などの規制力になり、あるいは革新的な象徴と結合して既存秩序を脱構築する力にもなるとされる。」
「社会学小辞典」,281p
内なる社会と外なる社会が意識されるプロセス
第二プロセスでは「内なる社会」と「外なる社会」が強く意識され、強化されると捉え直すことが可能だろう。
自分の内側において外なる社会が内面化されるのと同時に、自分の外側において外なる社会が実在化しているという意識が強化されるわけである。
デュルケムは第二プロセスの状態を「自分自身をいつもとは異なって考えさせ、働かせる一種の外的力能に支配、指導されている、と感じ、当然にもすでに彼自身ではなくなったという感銘をうける。彼にはまったく新しい存在になったように思われる」と表現している。
「新しい存在」とはすなわち個人的存在ではなく、社会的存在のことであるといえる。人間の2つの側面のうち、社会的存在の比重が大きく偏ることにより、自分自身ではないように感じ、忘我状態になるというわけである。これが各自に生じる変化であり、この変化を起こさせたのが集合的力である。アドラーの「共同体感覚」と重なる点で興味深い。
創造発見学第三回:「アドラー心理学と創造性」(7)アドラー心理学の哲学(共同体感覚)とはなにか
デュルケムは「意識の前景にあるのは社会である。行為を支配し、指導しているのは、社会である。これは、そのときは、社会が、世俗的なときより、さらに溌剌とし、さらに活動的、したがって、またより実在的であるということになる。このように、人が、この瞬間に、自分たちの外部に、再生する何物かが、再び活気づく力が、目覚める生命があると感じるとき、自分を欺いているのではない。この更新は何ら空想的ではなく、しかも、個人自らがその恩恵に浴しているのである。なぜなら、各人が自分の中におびている社会的な存在の一部分は、必然的に、この集合的革新に参与するからである。個人の魂も、自分が生命を克ちえた源泉そのものに再び浸って更生する。」と述べている。
「自分たちの外部に、再生する何物かが、再び活気づく力が、目覚める生命がある」とデュルケムが述べるときには「外なる社会」の側面が強調されている。
「自分の中におびている社会的な存在の一部分」とデュルケムが述べるときには「内なる社会」の側面が強調されている。
したがって、集合的沸騰の機能は内なる社会と外なる社会の活性化であり、「周期的再創造」であるといえる。そして儀礼の本質はこの集合的沸騰にあるといえる。
「この議論で登場しているものこそ、社会にほかならない。儀礼は社会を周期的に再創造するのである。普段、人々の意識を支配しているのは『功利的な個人的な配慮』である。他方、儀礼のために人々が集合し、接触を頻繁にするとき、人々の意識を占めているのは、『共通の信念・共通の伝承・大祖先の追憶、大祖先を権化とする集合的理想』、つまり社会的事物である。デュルケムは次のように述べている。
『意識の前景にあるのは社会である。行為を支配し、指導しているのは、社会である。これは、そのときは、社会が、世俗的なときより、さらに溌剌とし、さらに活動的、したがって、またより実在的であるということになる。このように、人が、この瞬間に、自分たちの外部に、再生する何物かが、再び活気づく力が、目覚める生命があると感じるとき、自分を欺いているのではない。この更新は何ら空想的ではなく、しかも、個人自らがその恩恵に浴しているのである。なぜなら、各人が自分の中におびている社会的な存在の一部分は、必然的に、この集合的革新に参与するからである。
個人の魂も、自分が生命を克ちえた源泉そのものに再び浸って更生する。』(306-307p)、と。インティチュマ儀礼がいかに物理的・物質主義的な効果を目的としたものにみえようとも、その機能は、なによりも、社会の周期的再創造にほかならない。」中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,85p
トーテムが生じるプロセス(あるいはトーテムの力が強化されるプロセス)
T3においては、内なる社会や外なる社会といった「力」の源を説明しようとする欲求から、その力の源の原因をなにかの外的事物に彼らは関連付けるとある。
外的事物とは、今までみてきた「トーテム(トーテム動植物)」である。特定の動植物や天候、無機物がわれわれに力を与えてくれたと考えることで納得するイメージだろうか。それらをさらに「記号化(シンボル化)」し、石や船、武器や身体に彫って刻んでいくことで、その力を忘れずに保持するメカニズムが整っていくことになる。それらが体系化し、ルールが生じ、周期的に集まりが開催されるようになると、宗教が構成されてくる。
デュルケムは「同じ生活に連盟している若干数の接近が、結果として、各自を変形する新しい精力を引き出すのだ、とは彼らはしらない。彼が感じるのは、ただ、自らの限界をこえて高められ、平素過ごしているのとは異なった生活をしているということだけである。だが、これらの感覚を、その原因となる何かの外的事物に彼は関連付けなければならない」と述べている。
そして、トーテムについては、「すべてが、あたかも、この画像が情緒を直接吹き込んだかのように行われる」と述べられている。
「自分の感じるきわめて特殊な印象を説明するため、人は、もっとも直接に関連している事物に、事物の持たない特性、俗的経験の対象がもたない例外的な力能、功徳を付与する」ともデュルケムは述べている。
このようにして単なる事物に聖なる力が与えられ、それは聖物となるのである。
もちろん、始原的な儀礼においてはじめて聖物となったのであり、それ以降はそれが聖物であることの再確認のための儀式だということになるのだろう。しかし初めて儀礼に参加する若者が、言い伝えられているから聖物だとすぐに実感できるわけではなく、参加することによって「集合的力」を内にも外にも感じ、それゆえにそれが聖物であると一層、確信することが可能になるのだろう。
「象徴がなかったなら、社会的感情は束の間しか存在しえないであろう。……これらの感情が表される運動が永続する事物に記入されると、感情それ自体が永続的になるのである」とデュルケムはいう。
トーテムという象徴は集団の力の維持や再創造、強化として機能しているといえる。
「このように、氏族という集団が、人々を支配し高揚させる力を生み出しているのである。まさに神と社会は一つなのである。ただし、彼らはこの力が集合体に起因するとは考えてもいない。『同じ生活に連盟している若干数の接近が、結果として、各自を変形する新しい精力を引き出すのだ、とは彼らはしらない。彼が感じるのは、ただ、自らの限界をこえて高められ、平素過ごしているのとは異なった生活をしているということだけである。だが、これらの感覚を、その原因となる何かの外的事物に彼は関連付けなければならない』(397-398p)。そこで彼らが見いだすのが、トーテム画像である。この画像は、いろいろな形で周囲にある。それゆえ、『すべてが、あたかも、この画像が情緒を直接吹き込んだかのように行われる』」(398p)。
中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,81p
「自分の感じるきわめて特殊な印象を説明するため、人は、もっとも直接に関連している事物に、事物の持たない特性、俗的経験の対象がもたない例外的な力能、功徳を付与する」(p.603:下333頁)
「象徴がなかったなら、社会的感情は束の間しか存在しえないであろう。……これらの感情が表される運動が永続する事物に記入されると、感情それ自体が永続的になるのである」(pp.330-1:上415-6頁)。
【5】保守的な沸騰と革新的な沸騰
保守的側面
儀礼における集合的沸騰には、すでに創られていた集合的な力や聖なる世界を「強化」、「再創造」するという保守的な側面が強調されることが多い。では実際に「最初の宗教」がいかなるプロセスを経て創られたのか、あるいはまるで違う宗教へと変動していくのかを実証的に検討しているわけではない。
そのため、保守的・静態的・循環的であると受け取られがちになってしまう側面がある。パーソンズに対して「価値規範の生成論的な説明ができていない」、「恒常性の説明に留まっている」と批判があったことと類似する。
【基礎社会学第十九回】タルコット・パーソンズの「主意主義的行為理論」とはなにか
革新的側面
一方で、デュルケムは集合的沸騰に「革命的または創造的時代の特質」をも見出しているという。
デュルケムはその具体例としてフランス革命(1789-1799)を挙げている。フランス革命とは、一般に、フランスの絶対王政を倒し、自由・平等・市民権を掲げる近代国家への移行を促した政治・社会変革のことを意味する。「社会が自ら神となり、あるいは神々を創造する傾向を、フランス革命の初年においてほど明らかに見うるところはない」とデュルケムは述べている。
フランス革命では集合的興奮が生じており、今までとは異なる新たな理想、新たな「聖なるもの」が生じたという。
「演説者と群集は『交霊の状態』に入り、祖国、自由、理性が『聖物』に変換された」とデュルケムはいう。今まで俗的だと思われたものが聖的に変換されるのはたしかに革新的な側面であるといえる。
キーワード:フランス革命
「たとえば、ジンメルが18世紀的な個人主義の例証としてあげたフランス革命は、デュルケムにとって重要な参照点であった。『宗教生活の原初形態』で彼はこう述べる。「社会が自ら神となり、あるいは神々を創造する傾向を、フランス革命の初年においてほど明らかに見うるところはない」(Durkheim1912=1941,42:上385)。
革命時に人々が会合して「犠牲と自己放棄」に走ったさい、演説者と群集は「交霊の状態」に入り、祖国、自由、理性が「聖物」に変換されたとデュルケムはいう(ibid.:上379)。しかし、彼が目前にしていた現在は「過渡期と道徳的凡庸との段階」にあり、「古い神々は、老い、あるいは、死に、しかも、他の神々は生まれていない」(ibid.:下342)。これに対してデュルケムは、「道徳的再建」を強く志向する。「創造的興奮の時限を、われわれの社会が再び知る日がくるであろう」(ibid.:下343)。
そのためには集合的感情と集合的観念を強固にする機会が必要であり、これは「集合・会合・教団」を手段にしてのみ得られるだろう(ibid.:下341)。最晩年のデュルケムは、フランス革命における「創造的興奮」の復活を求め、その参考資料としてオーストラリアのトーテミズムを研究したといえるだろう。」
奥村隆「距離のユートピア──ジンメルにおける悲劇と遊戯──」(2012),138p
集合的沸騰のメカニズムの問題点
一方で、たとえば門口充徳さんは、「経験は誤謬や錯誤に何世紀も耐えられないというかれの哲学的主張を読むと、間違った社会は存続しえず、安定的・統合的社会がすでに前提とされた見解であることに思い至る」と述べている。
野中亮さんは「『原初形態』の最重要論点の一つである集合的沸騰のメカニズムについて、いまだ十分な理論的説明がなされていない」と述べている。
AによってBが帰結しているように見えるとする。この場合、Aの機能はBという結果から推測することができる。
「人々が集まる(A)」と「聖なる力が維持・強化(B)」ないし「聖なる力が創造(C)」されるわけである。Bの場合はオーストラリアの原始社会の積極的儀礼のケースを出し、Cの場合はフランス革命のケースを出している。
しかし具体的に、どのように維持されるのか、改革されるのかというメカニズムが実証的に検討されているかどうかという問題がある。「(聖と俗の)対照の激しさこそが、聖の感覚を最初に噴出させるのに必須でなかったか」といったように抽象的に言及されることが多い。
人々の「内面(感覚)」も絡んでくる問題であり、レヴィ・ストロースのようにデュルケムを心理学主義的であると批判する人も出てくるわけである。「なるほど、そうかもしれない」と確かに「理解」を促すが、しかし因果的、実証的な説明になっているかどうかというと怪しいというイメージだろうか。
もっとも、当時の資料では限界があったのかもしれない。進歩した社会ではより社会が複雑であり、そのプロセスもわかりにくい(システム理論などで現代は分析が試みられているといえる)。
「前述のウォルンカ蛇の祭儀が事例として提示され、忘我と狂熱と野蛮な宗教的祭儀は、凡庸な日常生活の俗にたいする聖の形相とされている。つまり宗教的観念や聖の感覚は、この激昂した社会環境から、あるいは日常と祭儀の著しい対照から、噴出していると説かれている。こうしてみると集合的沸騰の議論も、儀礼の社会的機能の議論とほぼ同じような機能主義的説明になっていることが判明する。社会の生産も再生産も区別されておらず、社会事象間の機能的関係はデュルケムの解釈に依存しており、社会学的研究への示唆としては意義深いといえるが、観察データからの帰納・検証は不十分ということになる。
また第4節で、錯乱や陶酔も社会の実在を足場としており、経験は誤謬や錯誤に何世紀も耐えられないというかれの哲学的主張を読むと、間違った社会は存続しえず、安定的・統合的社会がすでに前提とされた見解であることに思い至る。」
門口充徳「アボリジニ社会から構造主義へ E・デュルケム著 『宗教生活の原初形態』 の位置づけ」(2012),127p
「集合的沸騰は社会の生命性が極大になるときだといえよう。この二つの形相は、比較のできないほど異質の世界である。デュルケムは、「宗教的観念が生まれたと思われるのは、この激昂した社会的環境における、この激昂そのものからである」(393p)と述べている。対照の激しさこそが、聖の感覚を最初に噴出させるのに必須でなかったかというのである。」
中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,80p
【6】現代における宗教
道徳的再建は、集合・会合・教団を手段としてのみ得られる
例えばデュルケムは「道徳的再建は、集合・会合・教団を手段としてのみ得られる。そこで、個人たちは密接に結合し、彼らに共通な感情を協同して再確認する。」、「……ユダヤ教徒の会合と、新しい道徳的憲章の制定、または、国民生活の何かの重大事変を記念する市民たちの集会との間に、どんな本質的な差異があろうか」と述べている。
とはいえ、そうした代替物が充全に機能をはたしているかというと、そういうわけではないのかもしれない。フランス革命後の理想も過渡期のものであり、充全な理想が生じたとはデュルケムには考えていないようだ。
「とはいえ、沸騰は長続きしない。社会は、一定の期間ごとに、その集合的感情と集合的観念とを生き返らせなければならない。『この道徳的再建は、集合・会合・教団を手段としてのみ得られる。そこで、個人たちは密接に結合し、彼らに共通な感情を協同して再確認する。』(『宗教生活の原初的形態』,341p)……『一つの社会は、それと同時に理想を創造しないでは、自らを想像することも、再創造することもできない』(334p)。」
中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,88p
新たな理想、新たな神について
デュルケムは「『過渡期と道徳的凡庸との段階』を経過しつつあるわれわれの社会では、『古い神々は、老い、あるいは、死に、しかも、他の神々は生まれていない』」と述べているからである。新興宗教やカルトの勃興もまた、聖なるものにたいする飢えとして解釈することも考えることができるかもしれない。
「あるものは美しくもなく、神聖でもなく、また善でもないかわりに真ではありうるということ、いな、それが真でありうるのはむしろそれが美しくも、神聖でも、また善でもないからこそであるということ、──これはこんにちむしろ常識に属する。だが、これらは、こうしたもろもろの価値秩序の神々の争いのなかでももっとも単純なばあいにすぎない。」とウェーバーが言ったこととも重なってくる。
ウェーバーならば預言者(新たな聖)を待ち焦がれるのではなく、日々の要求に従えと諭すのかもしれない。要するに現実(俗)を見て真面目に働いたり学んだりするということだ。
宗教の力は弱まっていくが、しかしかつての宗教の力を十分に代替するような、等価的な機能をもつものは未だ生まれていない。もちろん分業なども等価的な機能をもっているが、十分ではない。その証左としてアノミーやエゴイズムが生じてしまっているのであり、自殺率が増加している。重要なのは「既存の宗教の再建」ではなく、「適切な集合力(道徳力)の再建」である。
デュルケムは悲観と同時に希望ももっている。デュルケムは「新たな理想が発露し、しばらくは人類の指南となる新たな方式が見出される創造的沸騰の時限を、われわれの社会が再び知る日がくるであろう」と述べているからである。中島道男さんはこの「新たな理想」を道徳的個人主義と関連付けて解釈していた。
「『過渡期と道徳的凡庸との段階』を経過しつつあるわれわれの社会では、『古い神々は、老い、あるいは、死に、しかも、他の神々は生まれていない』(『宗教生活の原初形態』,342p)。しかし、社会再建の道筋だけは見えている。『新たな理想が発露し、しばらくは人類の指南となる新たな方式が見出される創造的沸騰の時限を、われわれの社会が再び知る日がくるであろう』とデュルケムは述べている(343p)。ドレフェス事件のことが念頭にあったのかもしれない。――『これらの事件が起こした道徳的興奮は消えていない。そして、私は、それを消えさせてはならないと考える者のひとりである。というのは、それは必要であるから、異常であり危険を構成していたのは、かつてのわれわれのアパシーである』と(『社会科学と行動』222p)。デュルケムによれば、文明が立脚している偉大な理想が構成されるのは、集合的沸騰のときである。宗教革命もルネサンスも革命時代もみな、こうした集合的沸騰にほかならない(『社会科学と哲学』125-126p)。」
中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,88p
道徳的個人主義と理想、人格の尊厳との関連
道徳的個人主義:「人間の尊厳」を中心にした価値観に基づく思想のこと。
デュルケムによると、個人は他者や社会との関係において「人間の尊厳」を尊重し、行動することが求められる。これは、単なる自己中心的な行動ではなく、他者との調和を大切にする社会的な道徳である。昨今ではパワハラやセクハラなどでニュースが大きく扱われているが、これもまた人格の尊厳であり、昔よりもその基準は著しく高くなっていると言える。
人格の尊厳:個人が持つ固有の価値、つまりその人が他の人から軽視されず、平等に尊重されるべきだという考え方のこと。
人格の尊厳が尊重されることによってどのような機能が期待できるのだろうか。たとえば人々がこの価値を守ることで、社会的連帯が強化され調和の取れた社会が形成されると解釈することができる。
人格の尊厳の歴史
(T1)歴史の初期段階では、個人の人格や尊厳はあまり重視されていなかった。極端にいえば個人の個性は0である。個人の行動も思考も、社会全体の意向に従うものであった。
しかしこうした社会でもそれなりに機能していたのであり、問題がない時代もあったといえる。たとえば原始的共同体や奴隷制度があった社会において個人の人格は現代よりも軽視されていると考えることができる。しかしそれを絶対的悪とみなすのではなく、なんらかの社会的機能があったとみなすことも可能である。全体の構造がXのときに要素Aは問題を生じさせないが、Yのときに要素Aが問題を生じさせることがあると考えていくのである。
(T2)社会が発展していくつにれて、人口が増えたり都市化が進んだり、技術が発展したりして社会の規模が大きくなり、複雑化していく。
経済では分業が進み、宗教の力は弱まり、個人間の役割や差異も増え、共通点が減り、個性が増大していく。そうした状況のもとでもはや奴隷制度や人種差別は許されず、個性を圧迫するような宗教も軽視されていくことになる。構造が変化すれば要素の受け入れられ方も変化せざるをえない。
(T3)社会全体の連帯感を保つために、諸個人の個性の増大と矛盾しない形で「聖なるもの」と諸個人が結びつく必要がある。
新しい形の連帯である分業だけでは、現代の自殺の増加などの危機を解消することは難しい。かといって旧来の宗教をそのままのかたちで復活させることも難しい。したがって、「新たな聖なるものとしての人格」がその象徴として採用され、人格こそが社会全体にとって、集合意識として最も大切で崇高なものとして価値を持つと考えられるようになる。
人々が人格を尊重し、またそれが社会全体の目的となることによって、社会的連帯が維持されるということである。人格の尊重、個性の尊重は社会の中で「宗教的な性質」を持つようになるという点がポイントである。
人格は「個人を超えた価値」を持つようになるのであり、また「崇拝の対象」ともなるのである。人々が個性的になっていくと共に、「かけがえのない個人」としての尊厳や自由、平等が価値をもっていく。いわば「世界宗教、普遍宗教」のようなものだろう。
個人化に対するデュルケムの評価の変遷
たしかにデュルケムは前期の『分業論』(1893)のとき、すでにこうした個人化を「無数の個人の分裂が許容され、個人がある種の宗教の対象となり、個人主義が現代の集合意識である」とみなしていた。
しかし、こうした信仰は「社会に個人を結びつけるのではなく、個人と個人を結びつけるものであり、真の連帯を形成するものではない」と低く評価されていた。
ドレフェス事件(1894)や、宗教に関する啓示などを経て、デュルケムは個人主義(個人化)を積極的に評価するようになる。
「個人主義と知識人」(1899)では「人間性の尊敬は人間が同時に信仰者であり神である宗教である。」、「人間の崇拝は理性の自律をその第一の教義とし、自由な探究の信条をその第一の儀礼とする。」とまでいわれ、個人主義が高く評価されるようになる。
デュルケムは道徳的個人主義を「今後はわが国の道徳的統一を確立する唯一の信条体系である」とまで言い切っている。
重要なのは「単なる個人化」、「単なる自由」、「単なる平等」が重視されているわけではないという点である。外なる社会と個人とを結びつけ、個人に内面化させるような継起として「個人化」が位置づけられており、社会と無関係に個性的であればあるほどよいとされているわけではない。ある変数の無限な増大が目指されるのではなく、社会というシステムの中で調和を保つ限りでの変数の増大が目指されているのである。
新カント派の考えでは「個人が自らの社会的な実在を自覚することで、真の意味での個人の主体性が発揮され、創造力が生かされる」という。
社会とのつながりの中でこそ個性が、個人化が、そして平等や自由が意味をもつのであり、そうした文脈を、そして体系を失ってしまったら「アノミー」や「エゴイズム」が生じてしまうのである。体系との調和の中で要素が価値をもつのであり、要素が孤立して価値をもつわけではない。そうした思想を私はデュルケムに感じる。
「18世紀来の思想的伝統をもつ人間性尊重の個人主義を,ルソーやカントから導き出して論述する「個人主義と知識人」(L’individualisme et les intellectuels,1898)の論文では,「人間性の尊敬は人間が同時に信仰者であり神である宗教である。」「人間の崇拝は理性の自律をその第一の教義とし,自由な探究の信条をその第一の儀礼とする。」とまで言い切る。功利主義的次元を乗り越え,人間一般の人間性に立脚する道徳的個人主義を,デュルケムは合理主義によって社会の連帯的原理に体系づけている。彼の道徳的個人主義は,一方で社会理論として有機的連帯の近代社会の機能的要件であるが,他方において近代社会の宗教のイメージを理念的に表現している。それは単なる社会連帯主義思想でもないし理神論でもない。しかし,彼の宗教的観念が表明されていることは確かである。この理論と観念の拮抗状態は宗教研究にもちこされる。理性と信仰の関係に実践志向の価値評価的態度を移す。デュルケムは彼の社会理論の展開にそって,宗教を次第に組織的体系的にとらえるようになる。
「集合表象は個人表象と全く別個の性質をもっている。……集合生活を営んでいる人間だけが宗教的な思惟をもつ。……宗教制度は社会の性質のいかんによって異なっている。・…・個人に畏敬を強いる力,また彼の崇拝の対象となった力は社会であって,そもそも神とは,社会の実体化された形態に外ならない。宗教は要するに社会が自らを意識するための象徴の体系であり,集合的な存在の固有の思惟様式である。」
寺林脩「デュルケム宗教論の展開」(1981),40-41p「機械的連帯と有機的連帯の二分法の消滅という問題は、現代社会における個人主義をどう位置づけるかという問題ともかかわっている。『分業論』においても、人格の尊厳が現代社会の共同信仰になることは指摘されている。集合意識は全面的に消失するのではなく、しだいに一般的かつ抽象的になり、無数の個人の分裂を許容するようになる。そして、個人がある種の宗教の対象となるのである。この意味での個人主義が、現代の集合意識である。しかし、これをいかに評価するかをめぐって、デュルケムにはためらいがある。『この共同信仰は、集合意識のうちでも、まったく例外的な状況を示す。……この共同信仰はその社会にわれわれを結びつけるのではない。われわれどうしを結びつけるだけなのである。したがって、それは真の社会的紐帯をつくりあげはしない』(『分業論』167頁)。これが、『分業論』でのデュルケムの個人主義評価である。この評価はのちに修正されることになるけれども、個人主義評価にあたって、『われわれを社会に結びつける』かどうかがメルクマールになっている点は、デュルケム理解にとって見過ごすことはできない。」
中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,62p
二元論を超えて
(追記:このようにタイトル付けをすると、「ダブルバインドを超えて」と読み替えることもできるのかもしれない。あるいはヘーゲル的な止揚(アウフヘーベン)を感じる。)
たとえば寺林脩さんはデュルケムの思想を二元論と考え、その矛盾の解決を目指していると考えている。たとえば個人の自律化と社会の連帯の維持は一見矛盾するように見えるが、しかしお互いが相補的になりうることが『分業論』では主張された。
「社会的には有機的連帯の理想的実現(分業などだろう)、人間的には道徳的個人主義がデュルケムの解答であった」と寺林さんはいう。しかし、「聖なる宗教的生活や道徳的個人主義が俗なる世俗的生活や功利主義的個人主義を超克する契機やプログラムは明確には示されない」とも寺林さんは解釈している。これは現代の我々が真剣に考えなければいけない課題である。
現代においてすら男女差別や人種差別がまだ強く残っている地域もあり、必ずしも集合意識となっているとはいえないだろう。
また、そもそも価値を置く単位を、聖なるものとみなす単位を「個人」や「性別」、「国」とするのは健全なのか、という観点が問題になる。たとえば人格の尊厳の単位が「国」であれば、他の敵対する国の人格は踏みにじっていいということになりかねない。だからこそ戦争で子供が殺されたりするのである(実際に2025年の4月の今、ロシアとウクライナの戦争で起こっていることである)。
「人間が神であり信仰者である」というデュルケムの発言部分を理論的にもう少し改良する必要があるのではないだろうか。
このあたりは最後のコラムで扱う予定である。先取りすれば、人間は大きなシステム(神、生態システム)の中のサブシステムであるという意味で神であり、人間は大きなシステムそれ自体ではなく、大きなシステムへ信仰を持つという意味で信仰者なのではないだろうか。サブシステム同士(個人であれ国であれ性別の集団であれ)で傷つけ合うことは、神を傷つけることであり、また自分たちを傷つけることでもある(核兵器を使えば回り回って自分たちの食べるものも汚染される)。それゆえにお互いに尊厳が必要になる、謙遜が必要になるという態度にもっていくことはできないだろうか。
「個人においても集団においても理想化する力は宗教力であり,それはいずれにとっても生存の条件である。まさに社会が社会のために宗教を創造した。
近代社会においても,社会が新しい信念や理想の表象の源泉である。今やその集合的感情は道徳的個人主義をおいて外にない。それは象徴的に道徳的共同体に投影されて,その普遍的原理の中核をなす。それに対する信念とそれを更新する儀礼によってのみ,それは生じ維持され再創造される。
デュルケムの近代社会における宗教と理想的社会像は,道徳的個人主義と道徳的共同体においてイメージされる。ところで,彼において,聖なる宗教的生活や道徳的個人主義が俗なる世俗的生活や功利主義的個人主義を超克する契機やプログラム明確には示されない。
後者は伸張こそすれ減少できず,前者との弁証法的な止揚が強調されていた。だが,近代社会における宗教が実際にどのようなものになるかは,彼自ら不問に帰している。」寺林脩「デュルケム宗教論の展開」(1981),46-47p
『我々は諸個人として考える能力と普遍的非個人的に考える能力をもっている。前者を感受性と呼び,後者を理性と呼ぶ。……人間の二元主義(魂と肉体)は常に宗教的な形で表現される。……魂は聖なるもの,肉体は俗なるものと考えられている。……この二元性はあらゆる宗教の基盤である聖俗の事物の分割の単なる一特殊例である。それは同じ原理に基づいて説明される。……聖なるものはそれ自体が物質的対象物に固定した単なる集合的理想である。……集合性によって作られた観念や感情は諸個人を支配し養う道徳的諸力の形でそれらを表現するために,それらを考え信じる特定の諸個人を生じさせる。……我々が集合的理想に帰す特別の価値は,科学的に分析できる非常に創造的な精神作用の単なる結果にある。その作用によって多くの個人意識はコミュニオンに入り,共同意識に融け込む。……我々の内なる社会的存在の規則は歴史の進歩につれて重要なものとなるので,今後増加するであろう我々の内なる二存在間の争いに対して,我々自身の努力を強いるだろう。』
社会的存在への離脱は本性からのある程度の離脱であり,苦痛に満ちた緊張を避けることはできない。」
寺林脩「デュルケム宗教論の展開」(1981),46pキーワード:神
「18世紀来の思想的伝統をもつ人間性尊重の個人主義を,ルソーやカントから導き出して論述する「個人主義と知識人」(L’individualisme et les intellectuels,1898)の論文では,「人間性の尊敬は人間が同時に信仰者であり神である宗教である。」「人間の崇拝は理性の自律をその第一の教義とし,自由な探究の信条をその第一の儀礼とする。」まで言い切る。功利主義的次元を乗り越え,人間一般の人間性に立脚する道徳的個人主義を,デュルケムは合理主義によって社会の連帯的原理に体系づけている。彼の道徳的個人主義は,一方で社会理論として有機的連帯の近代社会の機能的要件であるが,他方において近代社会の宗教のイメージを理念的に表現している。それは単なる社会連帯主義思想でもないし理神論でもない。しかし,彼の宗教的観念が表明されていることは確かである。この理論と観念の拮抗状態は宗教研究にもちこされる。理性と信仰の関係に実践志向の価値評価的態度を移す。デュルケムは彼の社会理論の展開にそって,宗教を次第に組織的体系的にとらえるようになる。
「集合表象は個人表象と全く別個の性質をもっている。……集合生活を営んでいる人間だけが宗教的な思惟をもつ。……宗教制度は社会の性質のいかんによって異なっている。・…・個人に畏敬を強いる力,また彼の崇拝の対象となった力は社会であって,そもそも神とは,社会の実体化された形態に外ならない。宗教は要するに社会が自らを意識するための象徴の体系であり,集合的な存在の固有の思惟様式である。」
寺林脩「デュルケム宗教論の展開」(1981),40-41p
参考文献リスト
今回の主な文献
中島道男「エミール・デュルケム: 社会の道徳的再建と社会学 (シリーズ世界の社会学・日本の社会学)」
中島道男「エミール・デュルケム: 社会の道徳的再建と社会学 (シリーズ世界の社会学・日本の社会学)」
エミール・デュルケム「宗教生活の基本形態(全) ──オーストラリアにおけるトーテム体系 (ちくま学芸文庫) 」
エミール・デュルケム「宗教生活の基本形態(全) ──オーストラリアにおけるトーテム体系 (ちくま学芸文庫) 」
グレゴリー・ベイトソン 「精神と自然 生きた世界の認識論 (岩波文庫 青N604-1) 」
グレゴリー・ベイトソン 「精神と自然 生きた世界の認識論 (岩波文庫 青N604-1) 」
グレゴリー・ベイトソン「精神の生態学へ (上) (岩波文庫 青N604-2) 」
グレゴリー・ベイトソン「精神の生態学へ (上) (岩波文庫 青N604-2) 」
モリス・バーマン「デカルトからベイトソンへ ――世界の再魔術化」
モリス・バーマン「デカルトからベイトソンへ ――世界の再魔術化 」
真木 悠介 「時間の比較社会学 (岩波現代文庫 学術 108)」
真木 悠介 「時間の比較社会学 (岩波現代文庫 学術 108) 」
汎用文献
佐藤俊樹「社会学の方法:その歴史と構造」
大澤真幸「社会学史」
新睦人「社会学のあゆみ」
本当にわかる社会学 フシギなくらい見えてくる
アンソニー・ギデンズ「社会学」
社会学
社会学 新版 (New Liberal Arts Selection)
クロニクル社会学
社会学用語図鑑 ―人物と用語でたどる社会学の全体像
参考論文
門口充徳「アボリジニ社会から構造主義へ: E・デュルケム著 『宗教生活の原初形態』 の位置づけ」(2012)[URL]
・『宗教生活の原初的形態』の全体的な要約となっている。批判的な言及が多い。
門口充徳「アボリジニ社会から構造主義へ 2: 空間が時間を超越することによる因果律の打破」(2013)[URL]
門口充徳「アボリジニ社会から構造主義へ 3: 土地と親族をめぐるアボリジニ社会の構造」(2014)[URL]
野中亮「『宗教生活の原初形態』における「俗」の位置」(1997)[URL]
酒井健「聖なるものの行方: 社会学研究会とそれ以後のバタイユ」(2013)[URL]
・教会の定義
・バタイユの話は面白い
太田健児「デュルケム後期道徳論における認識論問題:『宗教生活の原初形態』 のカテゴリー論と学説史再編問題を手がかりとして」(1999)[URL]
・主にカテゴリー(範疇)論、カントなどとの関連
ヅァイトリン,山田隆夫(翻訳),「エミール・デュルケーム (VII)-自殺-: 宗教生活の原初形態」(1990)[URLなし]
・デュルケムの主張の理解の補強に使える。ただし、マルクスとの対比が目的であるかのように全体が構成されていることに注意。
内藤莞爾「晩年のデュルケム (上)」(1983)[URL]
内藤莞爾「晩年のデュルケム (下)」(1984)[URL]
内藤莞爾「デュルケムにおける宗教概念の形成 (1)」(1983)[URL]
内藤莞爾「デュルケムにおける宗教概念の形成 (2)」(1984)[URL]
望月哲也「デュルケーム社会理論における宗教社会学の位置」(2000)[URL]
清水強志「デュルケームの 「プラグマティズム」 講義」(2007)[URL]
清水強志「デュルケーム社会学におけるシンボルの役割」(2011)[URL]
寺林脩「デュルケムの宗教論 (序説)」(1980)[URL]
寺林脩「デュルケム宗教論の展開」(1981)[URL]
奥村隆「距離のユートピア──ジンメルにおける悲劇と遊戯──」(2012)[URL]
・ジンメルとデュルケムの比較の参考、集合的沸騰について
堀圭三「デュルケムのジンメル評価について」(1999)[URL]
小川伸彦「デュルケームの儀礼論への一視角 : 二つの規範と「社会」の実在性」[URL]
・『宗教生活の原初的形態』について極めてわかりやすく整理され、定義づけられ、一般化されているいい論文。
椎野信雄「遊びとゲーム: 遊びの貧困の所以 (特集 1 ゲームの時代)」(2011)[URL]
松浦雄介「知と信の社会理論」(2000)[URL]
加藤雄士「認識論のレビューに関する一考察: 人材開発の手法の理解に役立てるために」(2016)[URL]
中村恵子 「構成主義における学びの理論 : 心理学的構成主義と社会的構成主義を比較して」[URL]
沼上幹「われらが内なる実証主義バイアス」[URL]
コメント
この記事へのトラックバックはありません。







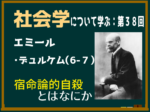
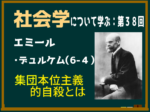

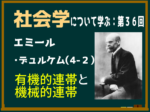

この記事へのコメントはありません。