- Home
- エミール・デュルケーム, ゲオルク・ジンメル
- 【基礎社会学第三九回(12)】【コラム】ジンメルにおける「適切な距離」
【基礎社会学第三九回(12)】【コラム】ジンメルにおける「適切な距離」
- 2025/4/24
- エミール・デュルケーム, ゲオルク・ジンメル
- コメントを書く
はじめに
動画での説明
・この記事の「概要・要約」はyoutubeの動画の冒頭にありますのでぜひ参照してください。
よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m
エミール・デュルケムとは、プロフィール
エミール・デュルケム(Émile Durkheim,1858-1917):フランスの社会学者。デュルケームと翻訳されることもある。マックス・ウェーバー、ゲオルク・ジンメルとともに社会学の創設者として扱われている。社会学の機関紙『社会学年報』(1898年)を創刊し、デュルケーム学派を形成した。甥には人類学者のマルセル・モースがいる。代表作は『社会分業論』(1893)、『社会学的方法の規準』(1895)、『自殺論』(1897)、『宗教生活の原初的形態』(1912)であり、社会学の古典となっている。
前回の記事
【基礎社会学第一回】エミール・デュルケームの「社会的事実」について
【基礎社会学第二回】エミール・デュルケームの「社会的分業」とはなにか?
【基礎社会学第三回】エミール・デュルケームの「自殺論」、「聖と俗」、「機能主義」とはなにか?意味
【基礎社会学第三六回(1)】エミール・デュルケムの社会学とはなにか、学ぶ意味や価値はあるのか
【基礎社会学第三六回(2)】エミール・デュルケムの「機械的連帯と有機的連帯の違い」を解説
【基礎社会学第三六回(3)】エミール・デュルケムの「集合意識と集合表象の違い」を解説
【基礎社会学第三六回(4)】エミール・デュルケムの「非契約的要素」を解説
【基礎社会学第三六回(5)】エミール・デュルケムの「拘束的分業とアノミー的分業の違い」を解説
【基礎社会学第三七回(1)】エミール・デュルケムの「社会的事実を物のように考察せよ」を解説
【基礎社会学第三七回(2)】エミール・デュルケムの「実証主義(合理主義)」を解説
【基礎社会学第三七回(3)】エミール・デュルケムの「社会学主義」を解説
【基礎社会学第三七回(4)】エミール・デュルケムの「社会実在論/社会唯名論」を解説
【基礎社会学第三八回(1)】エミール・デュルケムの『自殺論』の目的を解説
【基礎社会学第三八回(2)】エミール・デュルケムの「自殺の恒常性」を解説
【基礎社会学第三八回(3)】エミール・デュルケムの「自己本位主義的自殺」を解説
【基礎社会学第三八回(4)】エミール・デュルケムの「集団本位主義的自殺」を解説
【基礎社会学第三八回(5)】エミール・デュルケムにおいて自己犠牲は自殺か?
【基礎社会学第三八回(6)】エミール・デュルケムの「アノミー的自殺」を解説
【基礎社会学第三八回(7)】エミール・デュルケムの「宿命論的自殺」を解説
【基礎社会学第三八回(8)】エミール・デュルケムの「統計の使い方」を解説
【基礎社会学第三八回(9)】エミール・デュルケムの『自殺論』は現代でも有効か?
【基礎社会学第三九回(1)】エミール・デュルケムにおける「『宗教生活の原初的形態』の目的」を解説
【基礎社会学第三九回(2)】エミール・デュルケムにおける「宗教の定義」を解説
【基礎社会学第三九回(3)】エミール・デュルケムにおける「信念、聖と俗」とはなにか
【基礎社会学第三九回(4)】エミール・デュルケムにおける「儀礼」を解説
【基礎社会学第三九回(5)】エミール・デュルケムにおける「教会」を解説
【基礎社会学第三九回(6)】【コラム】プラグマティズムに対するデュルケムの評価
【基礎社会学第三九回(7)】エミール・デュルケムにおける「トーテミズム」を解説
【基礎社会学第三九回(8)】エミール・デュルケムにおける「神と社会はひとつである」を解説
【基礎社会学第三九回(9)】エミール・デュルケムにおける「トーテミズムの儀礼の具体例」
【基礎社会学第三九回(10)】エミール・デュルケムにおける「集合的沸騰」とは
【基礎社会学第三九回(11)】【コラム】聖なる時間/俗なる時間
【基礎社会学第三九回(12)】【コラム】ジンメルにおける「適切な距離」(今回の記事)
【基礎社会学第三九回(13)】エミール・デュルケムにおける「認識論」とは
【基礎社会学第三九回(14)】【コラム】「来たるべき社会とその聖」をベイトソンから考える
社会学的悲劇とは
社会学的悲劇とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説
以前、社会学的悲劇を動画で扱った。今回はデュルケムの集合的沸騰との関連を探っていくためにもう一度扱いたい。奥村隆さんの論文を参考に検討していく。
【基礎社会学第七回】ゲオルク・ジンメルの「社会学的悲劇」について学ぶ
社会学的悲劇:人々が一つの場所に集まることによって感情の昂揚が生まれ、個人の次元の高い知性を押し流し、分別や道徳という批判的抑制を消失させ、個々人をその集団の「最低の価値の基準」に引き下げてしまうという知性の喪失に対する悲劇のこと。
感情の昂揚:個人単体では説明のつかないような感情の高まりが集団(社会)によって生じているような状況のこと。
具体例:政治的な集会などで感情が高まり、個人単体ではしないような暴力的活動をしてしまうケース。学校のいじめや会社での隠蔽もこの例に近いかもしれない。
個人の活動と社会の活動の違い
社会学的悲劇が生じている状況では、「道徳や分別という批判的抑制」が簡単に消えてしまうという。一体なぜか。
まず、社会の活動のほうが個人の活動よりも「合目的性」が高いという。たとえば戦争において弱い味方を放って置くことは勝利という目的に適合している行動である。しかし、個人の次元では「正義に反する」という感情から、弱い味方を救おうとして全体を危険にさらすこともある。この場合は勝利という目的に不適合な行動といえるかもしれない。
追記:その反対に、「極悪非道であり、絶対できない」と個人では考えるようなことも集団では平気でできてしまうこともありえる。とくに戦争ではそうしたことが多いと言える。実際、単に勝つという目的に対して、極悪非道であればあるほど有効な場合もある(敵の首を切って敵地に吊るしてさらしておくなど)。
ただし、これは社会の活動が個人の活動よりも複雑で進歩的であるということを意味していない。ジンメルによればむしろその逆であり、社会の活動は単純で原始的ゆえに、合目的な行動に至りやすいのである。
たとえば生存の確保などの単純な目的にそって集団的な行動が行われるといえる。またこの単純さは、あらゆる個人がもっているような「共通の領域」という点がポイントになる。ジンメルはこうした社会的な活動を「優雅や精神という点では低級な要素」と形容している。
個人の活動は「新しいもの、稀なもの、個性的なもの」といった特性をもつ。つまり、個人的な活動は「優雅や精神という点では高級な要素」と形容されることになる。
個人の活動は価値が高いが、しかしその特性ゆえに他者と類似することを困難にするわけである。大縄跳びでは最も早くジャンプできる人はもっとも遅いジャンプのひとに合わせる必要があることを想像すればすこしわかりやすい。集団的水準によって個人的水準の価値は、低い人々の地位へと引き下げられるのであり、「平均ではなく最低」だという点がポイントである。
デュルケムとジンメルの違い
理想と悲劇の対称性
- デュルケムは社会的水準における力を「集合的沸騰」とし、集合的理想が新たに作られたり、維持されたりする機能の側面に着目し、高く評価している。
- ジンメルは社会的水準における力を「感情の昂揚」とし、個人水準の高い価値が集団水準の低い価値へと貶められてしまう事態の側面に着目し、低く評価している(悲劇であると評価)。
共通点は、どちらも「一つの場所に集まった人々」という点である。ただし、デュルケムはそうした人の集まりをル・ボンのいうような「大衆」とは考えておらず、また彼らが常に賢い選択をするとも考えていないという点でジンメルと共通するものがある。
たとえばデュルケムは、「集団は過ちをも犯すと」言及している。手放しであらゆる集団的な行為を高く評価しているわけではない。道徳と結びつく限りの個人化、そして社会化が評価されているのであり、集団的な行為それ自体が単独で評価されているのではない。
「社会が自らを意識するのは、共同的活動によってである。デュルケムにとって、集合的沸騰は、同時代人ル・ボンの群集心理学がとらえるような群衆ではない(ただし、デュルケムは集合的行為が善悪いずれの方向にも発展することは認めている――『群衆は容易に殺人を犯す』『道徳教育論』,31p)。社会が感じられるのは、ここにおいてである。ここでこそ、社会は神となり、あるいは神々を想像する(『宗教生活の原初的形態』,385p)。デュルケムは社会の本質を集合的沸騰のなかにみてとっているのである。こうした論点をひとことでいえば、『社会は宗教現象である』(パーソンズ)ということになろう。」
中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,87p
アプローチの違い
デュルケムのアプローチ
そもそもジンメルとデュルケムでは「アプローチ」のレベルで大きく異なっている。デュルケムは社会の「構造」が個人の行動に与える影響を強調している。たとえば社会の凝集性という社会の一般性、比較的固定的な諸関係である構造が個人を拘束するものとして捉えている。
例えば社会の凝集性が低いと、その社会集団の自殺率も高くなるというような分析が行われる。マクロ的な発想である。また、凝集率が自殺率に関係するという視点はどの社会にも共通するものとみなされ、特殊的な発想ではない。
デュルケムにとって社会は諸個人の単なる集まりではなく、またそれぞれの行動に還元できない、一種独特の機能を有した実在であるとみなされている。デュルケムにとって社会の水準は極めて価値が高く、「聖なるもの」とさえ表現されるものであり、それに対して個人の水準は「俗なるもの」とされている。
個人の自由や人格といった高い価値でさえ社会に起源をもち、また社会が個人に与えるもの、分有するものであるとされている。個人が先天的に聖なるものを有しているわけではない。一方、デュルケムは後期になって「社会化の過程」にも興味をもったという点で、ジンメルに近づいていったともいえる。
ジンメルのアプローチ
一方、ジンメルは社会を構造ではなく「過程」として捉えている。構造が個人の行動に影響を及ぼすという対比ではなく、「個人と個人の相互作用によって社会が形成されるミクロな過程」に重きがおかれている。もっとも、個人の要素や内容が重視されるのではなく、個人と個人の社会的関係、形式、いわゆる「心的相互作用」が重視されるという点は重要になる。例えば競争関係や支配関係などがその例である。
ジンメルには社会はある人とある人の視線が合ったちょっとした瞬間に生じ、またすぐに消えていくような、流動的なものであるというミクロな視点がある。こうした視点はのちのルーマンの社会システム理論にも引き継がれていく(コミュニケーションの連鎖が社会である)。
空間の大小と遠近
なぜ社会的水準で生じる事態が悲劇に陥りやすいかを「空間」によってジンメルは説明している。
【1】空間が広いか狭いか
集団で集まるときは、一人でいるときよりも広い空間にいるときが多い。大きな空間は「移動の自由の感情、未定のものへの拡張可能の感情、より以上の目標の不確かな設定の感情」を抱かせるという。
【2】空間的に接触しているか分離しているか
(1)「近い距離に基づく関係」は、集団の諸個人を緊密な関係へともたらたすという。
しかし、耐え難い圧迫をもたらすこともあり、反感や理想化の脱落などを生むことがあるという。原始的な社会や、自我と周囲が未分化の状態の子どもなどによくある関係だという。
トーテミズムの例
ジンメルがオーストラリアのトーテミズムの例をとりあげ、「まったく別々に活動している集団の諸個人を緊密な関係へもたらし、原始的な意識にあってはたんに外面的な接触のみが、内面的な接触の担い手である」と表現している点はデュルケムとの関連ではポイントであろう。
空間的な近接性が仲間意識を生じさせるのであるという視点はデュルケムの視点とも近い。
キーワード:トーテミズム
「まず彼は、空間的な近接/分離と「所属」の関係を論じ、意識の抽象能力の低い原始的な段階では、「空間的に分離しているものの共属」と「空間的に接近しているものの非共属」を表象できないという(ibid.:下243)。子どもにおいて自我と周囲は未分化状態にあるが、このとき感覚的な近接が「相互所属の意識」に決定的なものとなる。つまり、近くにいる者は仲間、遠くにいる者は仲間ではない、ととらえられるというわけだ。これは「オーストラリア黒人」(!)での「同じトーテム団体への共属」でも同じであり、「この共属はオーストラリア黒人のあいだにおいて、まったく別々に活動している集団の諸個人を緊密な関係へもたらし……原始的な意識にあってはたんに外面的な接触のみが、内面的な接触……の担い手である(ibid.:下244)」。これに対し、現代の大都市においては人々は抽象に慣れており、「空間的にもっとも近い人びとに対する無関心と、空間的にきわめて遠い人びととの緊密な関係」が存在しうるとジンメルはいう(ibid.:下244)。」
奥村隆「距離のユートピア──ジンメルにおける悲劇と遊戯──」(2012),124p
知性的な距離
(2)「遠い距離に基づく関係」では空間的にもっとも遠い人々に対して緊密な関係を結び、もっとも近い人々に対して無関心を抱く関係が存在しうるという。
このような関係が可能になるのは大都市などであり、一定の「知性」を必要とするという。このような距離をジンメルは「知性的な距離」と表現している。空間的に分離した人々が「知性」によって関係を結び、近接に伴う悲劇を防ぎながら共属を達成するような社会の水準をジンメルは評価している。たとえば我々は貨幣を用いて見ず知らずの他人と世界中でコミュニケーションを行えるが、原始的な共同体ではそのようなコミュニケーションは難しいと言える。
ここでいう知性とは感情から距離をとる冷静さ、抽象的思考能力、合理的態度などを意味していると推測できる。客観的な視点を重んじる態度といえばマンハイムの相関主義とも重なってくるものがある。欲望や一過性の感情に支配されがちな社会学的悲劇における性質とは真逆といえるのかもしれない。
【基礎社会学第三十二回】カール・マンハイムの「相関主義」と「自由に浮動するインテリゲンチャ」とはなにか
キーワード:知性的な距離
「この『社会学』での「空間の社会学」についての考察を、『社会学の根本問題』での「個人と社会」をめぐる議論と近づけるなら、以下のようにいえるだろう。「個人の水準」と対比される「社会の水準」にはふたつの違った局面がある。ひとつは、ひとつの場所に集まって空間的に近接する人々が「感情の放射」によって「社会学的昂奮状態」に陥り、分別や道徳を喪失し「もっとも低い人々」の地位に引き下げられて一体化する「社会の水準」。ここに「社会学的悲劇」が発生するだろう。もうひとつには、空間的に分離した人々が「知性」によって関係を結び、近接にともなう反感や紛糾を防ぎながら「共属」を達成する「社会の水準」。この知性的な距離において、「社会学的悲劇」はおそらく発生しがたいだろう。」
奥村隆「距離のユートピア──ジンメルにおける悲劇と遊戯──」(2012),124p
インターネットの登場による社会学的悲劇
ジンメルの時代ではインターネットは発達していなかった。昨今ではその真実性や正当性はともかく、インターネットの中で集団が集合し、沸騰しているような場面が多い。遠い距離ゆえに人々は沸騰し、ときには集団で人を傷つけたり、デマを拡散したりする「社会学的悲劇」も生じているのではないだろうか。
匿名性という新たな視点も加えると面白いのかもしれない。人と人との空間的な距離が遠いゆえに人々は責任をもちにくくなり、知性が最低にまで落ちるケースもありうる。インターネットのケースは「空間的に遠くの距離にいるのに近くにいるかのように錯覚する」ともいえるのかもしれない。
もちろん、インターネットによって生まれたさまざまな創造的なケースも考慮するべきではある。たとえば井庭崇さんがいうような「複数人によるコラボレーションが、個々人を越えた付加価値を生み出す」というケースもインターネットによってより容易になっているのかもしれない。単に技術の問題だけではなく、悲劇の根としての世界観の、認識の枠組みの問題を深く探っていく必要がある。
適切な距離について
デュルケムにおいては「空間的に分離している俗なる世界は気分がすぐれない、退屈な日常」である。
ジンメルにおいては「知性によって結びつき、悲劇を防ぐことができる理想的な世界」である。
ジンメルは「大都市と精神生活」(1903)において、大都市の冷淡さは「嫌悪・憎悪・闘争や完全な無関心を防ぎ、かすかな反感を孕みながら多様な人々と関係を結ぶことを可能にし、さらには『個人的自由』を生み出す」という。知性的な距離が「自由」を生み出すというわけである。
デュルケムもジンメルも「適切な距離」を探しているという点では同じであり、そこには「中庸」の視点がある。拘束されすぎても、されなすぎても、近すぎても、遠すぎてもその過剰な距離特有の悲劇を生み出しかねない。デュルケムにとってその悲劇の表現のひとつが「自殺」であったといえる。
大事なのは中庸であり、両義性への視点であり、矛盾の解消であり、どちらか一方だけが存在すればいいと簡単にいい切れるものではないという視点がジンメルにはあるのだろう。個人と社会の関係が重要であり、どちらか一方に傾いてしまうとよくない。デュルケムもまた、社会に前期で重きを置きすぎたがゆえに、後期で個人に重きを置いてバランスをとろうとしたのではないだろうか。
デュルケムは前近代的な社会においても集団本位的な自殺が生じるという不幸のケースをとりあげているのであり、両義性にも目を向けている。つまり、集団本位主義的自殺は一種の悲劇であるという視点があったのではないだろうか。
また、「個性、自由、平等、尊厳」といった諸価値がいかなる時代、いかなる社会においても絶対的に価値をもつかといえばそうではなく、それらの価値が適合する諸条件、諸構造(コンテクスト)というものにもデュルケムは目を向けていたといえる。つまり、社会相対的な視点をもっていたのである。
たとえば人口や交流が増大すれば、それに伴った(適合する)経済形態(分業など)が生じ、個性や自由が経済において必須の要素となっていくという説明もその一種だろう。社会的条件や自然的条件がその都度、ある価値を適切かどうか、バランスの取れたものかどうかを判定する尺度となるのである。「いつの時代でもバランスはとるべきである」というのは絶対的な主張であるが、それだけでは何も言っていないに等しく、具体的で相対的な諸条件の組み合わせの中でそのバランスを説明する必要がある。
やがてまた別の形態が、構造が登場し、あらたな価値が高く評価されることもありうる。たとえばAIの登場によって「個性」への評価が変わっていく可能性もあるだろう。
「繰り返しになるが、このふたつの「社会の水準」の位置づけは、デュルケムと正反対に見える。デュルケムにとって分離している俗なる世界は「物憂い日常」であり、人々が一箇所に集合して「その接近から一種の電力が放たれ」る昂奮状態こそ、宗教的観念を生み出し「社会」を再生させるものであった。ここで、「共通の信念」や「集合的理想」が人々に共有されるのであり、これを創造せずには社会は存在しえない。ジンメルにとってこの宗教生活の「原初形態」は、知的な抽象能力を欠いた「原始的な段階」を示すものだった。「オーストラリア黒人」のように(この例が偶然なのか、意図的に引かれたのかわからないが)、人々は近接していることによって「感覚」に振り回され、「知性」を失い、「理想化」を脱落させる。ジンメルはこれよりも、「遠くにいるものの共属」を可能にする「距離」と「知性」を明らかに評価する。デュルケムが「理想」を見出した近接にジンメルは「悲劇」を見出し、デュルケムが「物憂い日常」を見出した分離にジンメルは「知性」を見出す。この対比で、ジンメルがとらえた「個人と社会」問題を検討したこの節を閉じることにしよう。これを見て、多くの人は彼の有名な1903年の講演「大都市と精神生活」を連想するだろう。そこで彼は、大都市の「冷淡さ」は、嫌悪・憎悪・闘争や完全な無関心を防ぎ、かすかな反感を孕みながら多様な人々と関係を結ぶことを可能にし、さらには「個人的自由」を生み出す、というのだから(Simmel1903=1976)5)。」
奥村隆「距離のユートピア──ジンメルにおける悲劇と遊戯──」(2012),124-125p
ジンメルの自由の定義と、デュルケムの犯罪の定義の共通性
大都市という構造に適した距離、原始的共同体という構造に適した距離をそれぞれ分析するのは「特殊的な事例」であり、大都市において適切な距離が、原始的共同体において適切とは限らない。その逆も同じである。
また、ジンメル的な視点で言えば、自由や平等というのも相対的なものである。つまり概念(観念)が強く関わる問題であり、ビリヤードの玉同士のように、単なる物理的な因果関係で語ることのできる世界ではない。自由と感じるとか、平等と感じるとかいう次元は我々が解釈によって創り出す観念であり、観念体系(シンボル体系)に依存するのである。そして観念体系は社会によって与えられるものである。
自由:他者との関係の中で、束縛から解放へと移行したときに感じる相対的な状態・感情のこと。解放から束縛へと移行すれば「不自由」だと感じることになる。
自由は孤立した主体の純粋に内的な性質ではなく、いかなる相手もそこにいなければその意味を失う相関現象であるとジンメルはいう。自己と他者の距離において関係に生じる、あるいは帯びる性質だというわけである。社会的状況や物理的環境においても関係の内実は変わりうるといえる。
ベイトソン的にいえば自由や個性だけではなく、そもそも人間の「性格」というものがそもそも他者との関係によって意味をなすものであるということになる。
ジンメルの「自由」の定義はデュルケムの「犯罪」の定義と似ている。デュルケムは犯罪を「内的な性質」ではなく、社会関係で定義づけた。人々が共同感情に反すると感じるからある行為が犯罪なのである。
自由も犯罪も、その社会に根ざした、集合意識に根ざしたものとなる。たとえばほとんどの人間が農業を行っている社会において、職業選択の自由が解放されたところで、その人達に「自由」が強く感じられることは少ないだろう。また、ある宗教を強く信じている原始共同体の人に対して、どんな宗教を信じることも今日からは自由だといったところで、それがいったいどんな自由を人々に感じさせるのだろうか。
キーワード:自由
「ジンメルはまず「自由」とはなにかを論ずる。そして、完全な自由などないと彼はいい、これまでの義務が新しい義務に取り換えられる「義務の交替」において、それまでの圧迫が脱落したと感じるとき「自由」が感じられるのではないかという(ibid.:301)。「個人的自由は、けっして孤立した主体の純粋に内的な性質ではなく、いかなる相手もそこにいなければその意味を失う相関現象である」。自由もまた相互作用のなかに位置づけられる。「人間のあいだのいっさいの関係が、接近の要素と距離の要素から成り立つとすれば、独立とは、距離の要素がなるほど最大になってはいるが、しかし……完全には接近の要素が消滅してしまうことのできない関係である」(ibid.:319)。このように、「接近と距離」のあいだに「自由」はあり、どちらかが消滅するゼロ点などはない。われわれの状態はあらゆる瞬間に、「ある程度の拘束とある程度の自由から合成される」(ibid.:320)。」
奥村隆「距離のユートピア──ジンメルにおける悲劇と遊戯──」(2012),132p
適切な按配について
ジンメルは(われわれの状態は)「ある程度の拘束とある程度の自由から合成される」と述べている。この塩梅が適切であれば、それは適切な自由であるといえる。
デュルケムは人間の健康と「ある程度の拘束」を強く関連付けている。完全に拘束を排除しようとする傾向、規範などによる拘束を病理的と見る傾向は不健全だということである。人間はある程度拘束されるからこそ健康でいられるのであり、常に完全に開放されているような状態では「移行」がそこにはなく、自由は感じられないのではないか。
我々はしばしば、特定の価値観が唯一絶対の正解であると考えがちである。
例えば、「男女は平等に扱われるべきだ」、「職業は自由に選択できるべきだ」という考えは、現代において広く共有されている。そして、過去の時代の価値観を、単に知性や文化の未熟さゆえの(絶対的な)誤りと見なしてしまう傾向がある。
絶対的な正解がないと仮定することは簡単だ。しかし、我々はその社会ごと、時代ごと、空間ごとに「最適な拘束と自由のバランスを体系的に判断できる理論」を持っているだろうか。つまり、「相対的な正解と判断できる論拠」を我々はほんとうにもちあわせているのだろうか。
もし特定のシステム、特定の位相において、ある要素と要素の関係が安定的であると判断できるならば、そのシステムに限っては特定の現象を正常(健康)とみなすことができる。しかし、そのような理論は果たして存在するのだろうか。この理論については最後のコラムで扱いたい。
量的個人主義/質的個人主義
量的個人主義とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説
量的個人主義(唯一性の個人主義):「あらゆる人々に平等に、普遍的に内在する真の人格=自己」を追求することが自由であり、唯一の個性であるという考え方。
18世紀の個人概念:諸個人の差異ではなく、諸個人に普遍的に、平等に共通する真の人格性を意味する。
【具体例】カント(1724-1804)の場合:「自我」は万人において平等であるべき。認識や道徳の主体としての「人間」は、すべての人に共通する普遍的な存在でなければならない。
【具体例】ルソー(1712-1778)の場合:個々の違いを捨てて「自己自身」に深く立ち戻るべき。すべての人の内に同じ「善意と幸福の泉」がある。人間は本来的に道徳的な存在であり、それを純粋な形で取り戻すことが理想。ルソーのスローガンは「自然に帰れ」であり、社会の因襲から脱して、人間本来の状態にかえろうではないかという呼びかけを意味する。
カントやルソーは、「人間には先天的なカテゴリーが備わっている」と考えたのであり、その点でデュルケムの批判の対象となる。
デュルケムは後天的に、つまり社会によって獲得されると考えているからである。一方で、後天的に獲得される対象である「人格の尊厳、自由、平等」などは目指されるべき対象であり、道徳的であり、聖なる性質をもっているという点が重要になる。もっとも、社会に起源をもつその性質からして「絶対的」という意味での普遍性をもってはいないだろう。あくまでも、ある社会において共通に意識され、価値があるものと信じられている限りにおける「聖なるもの」であり「理想」なのであり、流動的で相対的なものであるといえる。
キーワード:量的個人主義
「この「理想的な人間」「統一性」を実現するとき、人は「絶対的自由」を獲得するとともに「平等の理想」を実現することができる。カントのいう定言命法、「汝の意志の格率が同時に一般的立法の原理として妥当するように行為せよ」は、私は他人とは違うという「手前勝手な空想」ではなく、「何人たるかを問わぬ」道徳律の前における平等を意味し(ibid.:113)、これを実現する「道徳的な人間だけが自由」である(ibid.:114)。
ジンメルは、こうした考察から、18世紀の「個性概念」とは、すべての人間に含まれている真の「人格」はまったく平等であって、人格的自由は平等を排除せずむしろこれを包含するという個性概念である、と主張する(ibid.:114)。これを彼は、「量的個人主義」「単一性の個人主義」とも呼ぶ(ibid.:126)。ひとつの「普遍」へと平等に到達する自由を個々人が追求すること、これが18世紀的な個性であり、個人主義であるというのだ。」
奥村隆「距離のユートピア──ジンメルにおける悲劇と遊戯──」(2012),137p
「ジンメルは、18世紀の個人主義と19世紀の個人主義を次のようにも対比する。18世紀の個人主義は「原理的に無差別とされた原子的な諸個人」から出発し、多種多様なメンバーの統一による「有機体としての全体性という観念」には絶対に到達できなかった。これは「自由競争の精神史的基盤」であるだろう。」
奥村隆「距離のユートピア──ジンメルにおける悲劇と遊戯──」(2012),138p
質的個人主義とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説
質的個人主義(唯一性の個人主義,19世紀の個人概念):個人が他者と比較して平等であることよりも、それぞれの個性や唯一性が重要視される考え方。
たとえばシュレーゲル(1772-1829)は「個性こそ、人間における根源的なものであり、永遠のものである。人格は余り問題ではない」と述べ、シュライエルマッハー(1768-1834)は「人間の平等でなく、差異もまた道徳的義務であるという」と述べていることをジンメルは紹介している。
「この理想は、18世紀でもレッシング、ヘルダーらに見られるというが、ゲーテの『ヴィルヘルム・マイスター』において最初の完成に達した、とジンメルはいう。そこでは諸個人はそれぞれの独自性によって建設・組織され、どれだけ他の人々と接触しようとも「究極の根源において異なっているという意味」は変わらない。この考え方は「自由平等な人格という理想と絶対的に対立する」ものだろう(ibid.:124)。シュレーゲルは「個性こそ、人間における根源的なものであり、永遠のものである。人格は余り問題ではない」といい、シュライエルマッヘルは「人間の平等でなく、差異もまた道徳的義務であるという」思想を世界観の転回点とした(ibid.:125)。この「質的個人主義」あるいは「唯一性の個人主義」は、ロマン主義によって「感情や体験」という基礎を与えられることになる(ibid.:126)。そして、その社会像は以下のようなものとなるだろう。「各個人が他の個人との差異により、また、自己の存在と活動との唯一性により、はじめて自己の生存――個人的にも社会的にも――の意味を見出す、そういう社会像の安定を表現する」(ibid.:127)。」
奥村隆「距離のユートピア──ジンメルにおける悲劇と遊戯──」(2012),137p
自由の基盤となった量的個人主義
量的個人主義においては「差異」が表面的なものにすぎず、「同じ(平等、普遍)」であることが本質的なものとして重要視される。
規範(道徳、平等、普遍的なもの)へ向かって志向(追求)すること自体を自由であると考えている点で、自由と平等が両立すると考えられている。カント的な考え方はデュルケムにも「道徳的個人主義」として受け継がれていると言えるだろう(後天性が強調されるが)。
たとえばこうした規範への追求は、ギルド・家柄・教会からの個人の解放へとつながっていくことになる(それらは個人の自由や平等の障壁となるから)。18世紀のフランス革命もこの論点に関わるだろう。ジンメルは量的個人主義は「自由の基盤」となったと解釈している。
「ジンメルは、18世紀の個人主義と19世紀の個人主義を次のようにも対比する。18世紀の個人主義は「原理的に無差別とされた原子的な諸個人」から出発し、多種多様なメンバーの統一による「有機体としての全体性という観念」には絶対に到達できなかった。これは「自由競争の精神史的基盤」であるだろう。」
奥村隆「距離のユートピア──ジンメルにおける悲劇と遊戯──」(2012),138p
分業の基盤となった質的個人主義
質的個人主義においては「差異」こそが本質的なものであり、平等よりも不平等が、そして自由が重視される。つまり、自由と平等はもはや両立しないとみなされているのである。
歴史的にはフランス革命などによってさまざまな不平等・不自由が解消されていった。人は自由で平等になると、こんどは「個性(差異、不平等)」を求めるようになるのである。
ジンメルは「もはや自由な個人という問題ではなく、特別な人間、独自の人間という問題である」と述べている。
「平等な人格という理想」ではなく、「かけがえのない個性的な人格という理想」へとシフトしていくのである。そして両者の理想は対立するという。「質的個人主義」では差異が重視されるので、個性、独自性、専門性を重視する「分業」と相性がいい。ジンメルは質的個人主義を「分業の基礎」であるという。
創造性が大事であると日本では小学校の頃から繰り返し我々は教え込まれている(文部科学省の総則には「豊かな心や創造性の涵養」とある)。単に道徳的だからというより、創造性の発展は経済的な国力という意味で死活問題でもあり、必要不可欠となっている。
「生きた姿は、孤立した平等の諸個人の総和として生れるものではなく、分業的相互作用からのみ生れ、しかも、この相互作用の上に一つの統一体……として聳え立つものである」とジンメルは分業を高く評価している。
人々の違いを尊重した上で共同生活を送っている状態を評価しているのである。分業のポジティブな道徳的側面、機能はデュルケムとも重なる。また、先天的な要素の総和ではなく「相互作用」、つまり「後天的な社会プロセス」からポジティブなものが生まれると考える点でデュルケムとも近いと言える。
「これに対し、19世紀の個人主義は「相互的補充」を必要とし、協力的な作用・反作用を含む全体的有機体を招き入れる。この個人主義、つまり「差異の個人主義、個性が深められて人間の独自性、課せられた仕事の独自性に至るという個人主義」は「分業の基礎」であり「分業の形而上学」である。そして、ここには具体的な社会の生きた姿がある、とジンメルはいう。「生きた姿は、孤立した平等の諸個人の総和として生れるものではなく、分業的相互作用からのみ生れ、しかも、この相互作用の上に一つの統一体……として聳え立つものである」(ibid.:128┡9)。一方には「万人の平等だけが社会的理想」とする考え方がある。他方には「人間間の差異や距離こそ、社会的生活形式における究極の、還元すべからざる、その自ら正当な価値」とする考え方がある(ibid.:115)。ジンメルはこの章(つまり『社会学の根本問題』全体)の末尾に、前者すなわち「全く自由な人格という観念」も、後者すなわち「全く独自な人格という観念」も、個人主義の最後の言葉ではない、と記す。個人主義にはさらに多数で多様な形態が生じることになるだろう。」
奥村隆「距離のユートピア──ジンメルにおける悲劇と遊戯──」(2012),138p
量的個人主義の問題点について
量的個人主義(18世紀の個人主義)は、理想には到達できなかったとジンメルは解釈している。
「原理的に無差別とされた原子的な諸個人から出発し、多種多様なメンバーの統一による有機体としての全体性という観念には絶対に到達できなかった」という。抽象的過ぎて何を言っているのかわかりにくい。
「原理的に無差別とされた原子的な諸個人」とは、要するに「生まれながらに人間は本質的には平等であり、独立している」というわけである。
したがって、社会は「孤立的な個人の単なる総和、集合」にすぎない。社会が個人に後天的に能力を付与するのではなく、先天的に能力が備わっているとされているのである。それゆえに社会は個人の能力の発展を邪魔しないように、そして個人の自由を奪わないようにしなければならないという考えになる(だからこそ、自由の基礎になるのである)。
「ジンメルは、18世紀の個人主義と19世紀の個人主義を次のようにも対比する。18世紀の個人主義は「原理的に無差別とされた原子的な諸個人」から出発し、多種多様なメンバーの統一による「有機体としての全体性という観念」には絶対に到達できなかった。これは「自由競争の精神史的基盤」であるだろう。」
奥村隆「距離のユートピア──ジンメルにおける悲劇と遊戯──」(2012),138p
違えば違うほど同じ
「多種多様なメンバーの統一による有機体としての全体性」とはどういう意味か。
量的個人主義における「真の人格(個性)」は、いわゆる「個人の性格が一人一人違う」といったものではない。たとえばジンメルの表現で言えば「自己自身であればあるほど万人が同一であるもの」である。個性的であればあるほど、他の人と同じような人格になるというわけである。違えば違うほど同じになる、多様になればなるほど一様になるというわけである。
諸個人がそれぞれ個性的になればなるほど、自己を追い求めていけば行くほど、それぞれに共通した普遍的なものが共有され、人々が繋がり、一体となるというのが量的個人主義の理想というわけだ。
しかし現実はそううまくいかないという。
量的個人主義の考えが浸透し、人々は自由や平等をある程度勝ち取っていく。人格の尊厳が重要視され、社会的な拘束から解放されていく。
そのまま「表面的な違い」が軽視され、「みんな自由で平等でいいよね、つながろう」とはいかない。むしろ自由や平等を獲得したからこそ、それゆえに「表面的な違い」が「本質的な違い」と見なされ、無際限の欲求が加速していったとも言える。
また、そうした「表面的な違い」を煽るような経済システム(資本主義)も関係しているのだろう。他者との「違い」がなければ物やサービスは売れないのである。人に喜んでもらえるかどうかといった本質こそが表面的なものとみなされてしまう(儲かればいい)。
「万人の完全な自由は万人の完全な平等があるところに初めて生まれる」
理想としては全ての人間が自由かつ平等であるべきだということになる。しかし現実の人間には生まれ持った身長や才能、容姿といった差異、つまり「不平等」が存在する(カントたちからすれば表面的な要素なのだが)。たとえ社会的な制度として自由や平等を謳っていたとしても、現実には能力が高いものがより多くの自由を勝ち取り、能力のないものは不自由を被ることになる。「身分としての不平等」はなくなるかもしれないが、「能力としての不平等」は存在する。
「万人の完全な自由は万人の完全な平等があるところに初めて生まれる」のであり、現実はそうではない以上、自由と平等は矛盾し、「平等を伴う自由」は成り立たないとジンメルはいう。
「だが、この自由への要求は矛盾を孕んでいる。
というのは、「この要求は、社会が全く同じ強さの、心身に全く同じ才能を恵まれた諸個人で成り立っていてこそ円滑に実現するものであるから」である。
しかし人間の力は「質的にも量的にも、最初から不平等」であるから、この完全な自由を求めると才能に恵まれた人間による不平等の利用という結果が生じ、人間の力量の差異が地位の差異として現われることになる。
だから「一般的制度が与える自由は、人間的関係によって再び幻想になる」(ibid.:103)。
端的にいって、「万人の完全な自由は、万人の完全な平等があるところに初めて生まれることが出来る」(ibid.:104)のだが、ここには「自由と平等との深刻な矛盾」を見出すことができるだろう(ibid.:105)。」
奥村隆「距離のユートピア──ジンメルにおける悲劇と遊戯──」(2012),135p
自由なき平等と平等なき自由
「自由なき平等」と「平等なき自由」とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説
18世紀では「普遍性という理想による絶対的自由」によって、楽観的に自由と平等の矛盾が解決できると信じられていた。
しかし、19世紀では個性概念が2つの理想に分裂したという。それが「自由なき平等」と「平等なき自由」である。
自由なき平等:平等を重視するあまり、個人の自由が制限される状態。[具体例]社会主義では平等を重視するが、起業家や学者など一部の人にとっては自由を制限することになる。また、社会主義において、高い地位につく人が高い能力をもっているかというと、必ずしもそうではないという。それゆえに人々は自由が制限されていると感じるようになる。
平等なき自由:自由の実現において平等を重視せず、むしろ「不平等」を前提として個々の独自性や特別性を尊重する考え方のこと。
「さきに述べた「自由」と「平等」の矛盾を、18世紀は「普遍性」という理想による「絶対的自由」によって解決しようとした。では、19世紀はどうだったのだろうか。ジンメルは、19世紀になると「個性概念は二つの理想に分裂する」という。すなわち、「自由なき平等」と「平等なき自由」というふたつの傾向である(ibid.:114)。前者は「社会主義」に見られるものであり、これは「平等の理想」を優先するといえるだろう(ibid.:115)。ジンメルは、社会主義とは「全く普遍的な平等の理想を求める性質の人々」を大部分な支持者を得ているように見える、という(ibid.:116)。より詳細に見ると、社会主義においては「相対的平等と自由との関係」という面倒な問題が存在する。一般的に平等化が起ったとして、餓死寸前だった労働者にとってはそれが大きな自由を与えることになるが、企業家、金利生活者、芸術家、学者、指導的人物にとっては著しい自由の制限になるだろう。社会主義思想は平等と自由のこの矛盾に苦しむが、結果としては平等に力点が置かれ、社会主義政党はこのふたつの理想の敵対関係を無視してきた(ibid.:117)。」
奥村隆「距離のユートピア──ジンメルにおける悲劇と遊戯──」(2012),137p
ジンメルにおける理想
奥村さんによれば、ジンメルは「自由なき平等」よりも「平等なき自由」を高く評価しているという。
こうした「唯一性の個人主義=差異の個人主義」を可能にするメディアが貨幣であり、価値観が距離であり、行為が社交であるということになる。
- 距離:人と人の間に適度な距離があることで、過度な同一化や画一性を避け、独自性が保たれる。
- 社交:形式的な関わりの中で、人々が適度な関係性を持ちつつも、自律した個として存在できる。
- 貨幣: 経済的な交換が、固定的な身分制度とは異なり、自由な個人の関係を生み出す。
社交や貨幣には「人を自由にする」機能が存在する。しかし、社交や貨幣が「転回」し、生命のリアリティから切り離された空虚さに陥る可能性もジンメルは両義的に指摘する。
たとえば貨幣が単なる手段ではなく「究極的な目的」に昇格するとき、吝嗇(けち)や浪費、冷笑主義や倦怠といった現象が生じるという。これはデュルケムのエゴイズムやアノミーと重なるものがあるのだろう。
ジンメルは「幸福な時代が来て、こういう多様性が美しく調和するに至れば、あの活動における衝突や闘争が残っていても、それは人類にとって単に障碍ではなく、却って、人類に呼びかけて新しい力を開発させ、人類を新たなる創造へ導くことになるのであろう」と希望的に述べている。この希望観はデュルケムとも重なる。
しかし、いったいいかなる理論に基づいて多様性が調和できていると判定することができるのだろうか。これはデュルケムが「中庸」を述べるときとも似ている。より体系的な広い視野からバランスを論じることはいかにして可能か、その期待を最後のコラムで検討する。
「「社交」は人を自由にする。それは内容と形式を分離して、個人の「内容」を捨て去らせ、「内面性」をその外部に放置する。ここで人々は「社交的人間としては平等」になるが、これはあくまで「平等であるかのように」なのであって、だからこの外部で人々は差異がある者たちのままでいることができる。「貨幣」は人を自由にする。それは「純粋な道具」としてあらゆる目的から人に距離をとらせることを可能にし、衝動を客観化して自己を制御することを可能にする。このとき「人格」は交換される事物から切り離され、差異のある者たちはそのまま交換へとはいっていくことができる。もちろん「社交」と「貨幣」がもたらす「転回」は、生命のリアリティから切り離された「空虚な虚偽」を帰結する危険も孕んでいる。しかしこの「転回」によって生まれた「形式」によってこそ、人々は差異あるまま自由に生きることができる。ジンメルがいう「結合の自由とも呼ぶべき社会的理想」は、「社交」や「貨幣」や「距離」を媒介に、「差異の個人主義」と結びつく。」
奥村隆「距離のユートピア──ジンメルにおける悲劇と遊戯──」(2012),139p「幸福な時代が来て、こういう多様性が美しく調和するに至れば、あの活動における衝突や闘争が残っていても、それは人類にとって単に障碍ではなく、却って、人類に呼びかけて新しい力を開発させ、人類を新たなる創造へ導くことになるのであろう」(ibid.:130)。こう述べて、この著書は結ばれるのである。」
奥村隆「距離のユートピア──ジンメルにおける悲劇と遊戯──」(2012),138p
参考文献リスト
今回の主な文献
中島道男「エミール・デュルケム: 社会の道徳的再建と社会学 (シリーズ世界の社会学・日本の社会学)」
中島道男「エミール・デュルケム: 社会の道徳的再建と社会学 (シリーズ世界の社会学・日本の社会学)」
エミール・デュルケム「宗教生活の基本形態(全) ──オーストラリアにおけるトーテム体系 (ちくま学芸文庫) 」
エミール・デュルケム「宗教生活の基本形態(全) ──オーストラリアにおけるトーテム体系 (ちくま学芸文庫) 」
グレゴリー・ベイトソン 「精神と自然 生きた世界の認識論 (岩波文庫 青N604-1) 」
グレゴリー・ベイトソン 「精神と自然 生きた世界の認識論 (岩波文庫 青N604-1) 」
グレゴリー・ベイトソン「精神の生態学へ (上) (岩波文庫 青N604-2) 」
グレゴリー・ベイトソン「精神の生態学へ (上) (岩波文庫 青N604-2) 」
モリス・バーマン「デカルトからベイトソンへ ――世界の再魔術化」
モリス・バーマン「デカルトからベイトソンへ ――世界の再魔術化 」
真木 悠介 「時間の比較社会学 (岩波現代文庫 学術 108)」
真木 悠介 「時間の比較社会学 (岩波現代文庫 学術 108) 」
汎用文献
佐藤俊樹「社会学の方法:その歴史と構造」
大澤真幸「社会学史」
新睦人「社会学のあゆみ」
本当にわかる社会学 フシギなくらい見えてくる
アンソニー・ギデンズ「社会学」
社会学
社会学 新版 (New Liberal Arts Selection)
クロニクル社会学
社会学用語図鑑 ―人物と用語でたどる社会学の全体像
参考論文
門口充徳「アボリジニ社会から構造主義へ: E・デュルケム著 『宗教生活の原初形態』 の位置づけ」(2012)[URL]
・『宗教生活の原初的形態』の全体的な要約となっている。批判的な言及が多い。
門口充徳「アボリジニ社会から構造主義へ 2: 空間が時間を超越することによる因果律の打破」(2013)[URL]
門口充徳「アボリジニ社会から構造主義へ 3: 土地と親族をめぐるアボリジニ社会の構造」(2014)[URL]
野中亮「『宗教生活の原初形態』における「俗」の位置」(1997)[URL]
酒井健「聖なるものの行方: 社会学研究会とそれ以後のバタイユ」(2013)[URL]
・教会の定義
・バタイユの話は面白い
太田健児「デュルケム後期道徳論における認識論問題:『宗教生活の原初形態』 のカテゴリー論と学説史再編問題を手がかりとして」(1999)[URL]
・主にカテゴリー(範疇)論、カントなどとの関連
ヅァイトリン,山田隆夫(翻訳),「エミール・デュルケーム (VII)-自殺-: 宗教生活の原初形態」(1990)[URLなし]
・デュルケムの主張の理解の補強に使える。ただし、マルクスとの対比が目的であるかのように全体が構成されていることに注意。
内藤莞爾「晩年のデュルケム (上)」(1983)[URL]
内藤莞爾「晩年のデュルケム (下)」(1984)[URL]
内藤莞爾「デュルケムにおける宗教概念の形成 (1)」(1983)[URL]
内藤莞爾「デュルケムにおける宗教概念の形成 (2)」(1984)[URL]
望月哲也「デュルケーム社会理論における宗教社会学の位置」(2000)[URL]
清水強志「デュルケームの 「プラグマティズム」 講義」(2007)[URL]
清水強志「デュルケーム社会学におけるシンボルの役割」(2011)[URL]
寺林脩「デュルケムの宗教論 (序説)」(1980)[URL]
寺林脩「デュルケム宗教論の展開」(1981)[URL]
奥村隆「距離のユートピア──ジンメルにおける悲劇と遊戯──」(2012)[URL]
・ジンメルとデュルケムの比較の参考、集合的沸騰について
堀圭三「デュルケムのジンメル評価について」(1999)[URL]
小川伸彦「デュルケームの儀礼論への一視角 : 二つの規範と「社会」の実在性」[URL]
・『宗教生活の原初的形態』について極めてわかりやすく整理され、定義づけられ、一般化されているいい論文。
椎野信雄「遊びとゲーム: 遊びの貧困の所以 (特集 1 ゲームの時代)」(2011)[URL]
松浦雄介「知と信の社会理論」(2000)[URL]
加藤雄士「認識論のレビューに関する一考察: 人材開発の手法の理解に役立てるために」(2016)[URL]
中村恵子 「構成主義における学びの理論 : 心理学的構成主義と社会的構成主義を比較して」[URL]
沼上幹「われらが内なる実証主義バイアス」[URL]
コメント
この記事へのトラックバックはありません。








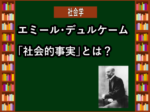
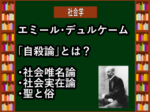


この記事へのコメントはありません。