- Home
- カール・マンハイム, 宮台真司
- 【基礎社会学第三十二回】カール・マンハイムの「相関主義」と「自由に浮動するインテリゲンチャ」とはなにか
はじめに
動画での解説・説明
・この記事のわかりやすい「概要・要約・要旨・まとめ」はyoutubeの動画の冒頭にありますのでぜひ参照してください。
よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m
カール・マンハイムの論文整理
『世界観解釈の理論への寄与』(1921~1922)
『文化社会学的認識の特性について』(1922)
『文化とその認識可能性についての社会学理論』(1924) 草稿
『知識社会学問題』(1925)
『保守主義的思考』(1927)
『世代の問題』(1928)
『精神的なるものの領域における競争の意義』(1929)
『ドイツにおける社会学の問題性について』(1929)
『イデオロギーとユートピア』(1929)→第一論文(3つの論文が合わさった著作)
『学問としての政治は可能か?』→第二論文
『ユートピア意識』→第三論文
『知識社会学』(1931)
『インテリゲンチアの社会的及び政治的意義』(1932)
『ドイツ社会学』(1934)
『変革期における人間と社会』(1935)
→「自由のための計画」
『現代の診断』(1943)
カール・マンハイムとは
カール・マンハイム(1893-1947):ハンガリー生まれの社会学者。ドイツへ亡命し、さらにイギリスへと亡命していった。主著は『イデオロギーとユートピア』(1929)。マルクス主義的イデオロギー論を克服しようと新しいイデオロギー論を唱えた。また、「自由のための計画」を掲げ、自由に浮動しつつ「時代診断」をする知識人像を提唱した。知識社会学ではロバート・マートン、ピーター・バーガー、トーマス・ルックマンなどに影響を与えている。また、ミルズやカルチュラルスタディーズの分野に影響を与えたとも言われている。
「ハンガリー出身の社会学者。ドイツでフランクフルト大学教授となったが、ナチスの脅威が強まるなかでイギリスに亡命し、ロンドン大学へと移った。ジンメルに師事した。一九二九年に出版した『イデオロギーとユートピア』(一九二九、一九三六年)では、マルクス主義的イデオロギー論を克服しようとし、一躍脚光を浴びた。『自由のための計画』を掲げ、自由に『浮動』しつつ『時代診断』をする知識人像を提唱した。」
井庭崇、他「社会システム理論」145P
(1)相関主義
相関主義とはなにか、意味
(マンハイムにおける)相関主義(英;relationism,独;Relationismus):・知識や認識が社会的存在に拘束されているということを認めつつ、それぞれの拘束された相対的な知識や認識を相互に関連付けることで、視野の拡大と補完の開放性を目指す立場のこと。
こうした相関主義の立場の担い手になりうるのが「知識人(自由に浮動するインテリゲンチャ)」である、というのがこの動画の結論。ただし、相関主義の定義だけを見てもなかなか頭に入ってこない。ゆっくりと理解していく必要がある。知識とはなにか、イデオロギーとはなにかについての詳細は前回の動画を参照。メイヤスーに関する相関主義には今回触れられない。
[相関主義]「マンハイムの知識社会学の主要概念の一つ。一定の立場からする、展望的なものとしての認識の部分性を、相互に関連付けて総合的に評価することにより、その時代に最も妥当性のある認識に到達することが可能であるという主張。」
「社会学小辞典」385P
「マンハイムは次のように述べている。『相関主義が意味しているのは、ただあらゆる意味的要素の相互の関連性、そしてそれらの意味的要素が互いに基礎づけあいながら、あるひとつの特定の体系のうちで意味をもつということにすぎない。しかしこの体系は、ある特定の種類の歴史的存在にとってのみ可能であり、妥当するにすぎないし、それがこの歴史的存在の適切な表現であるのはしばらくのあいだのことでしかない。存在が変位すれば、以前にそこから『うみだされた』規範体系もまた疎遠なものとなる。同じことは認識についても、歴史的視野についてもあてはまる』したがって、相関主義とは、知識や認識に限らず、意味をになうあらゆる要素がそもそも有意味なものとなりうるのは、特定の意味的・社会的存在の関係性のうちにおいてのみであるとする立場である。」
澤井敦「カール・マンハイム」、東信堂,72P
「このことは再び,つぎの問題を提起する。「知識社会学は,真理が,『相対的』である」,すなわち,「認識主体の主観的な立場そして、社会的状況(the subjectivest and point and the social situation of the knower)に依ること」を意味するのであろうか。マンハイムのこれに対する答えは,否定的である。というのは,知識社会学の観点からの歴史研究は,いかなる絶対的真理をも明らかにしないからであるから,このことは,「相対主義」ではなくて、「相関主義」を意味するからである。観察者,認識主体の視座構造は,その社会的立場とともに変化するであろう可能性は大きいものがある。しかし,「どの社会的立場が,真理の最適の条件(anoptinum)に到達する最善の機会であるか」という問題は,やはり残っているのである。(p.71)不幸なことに,マンハイムはさらに進んで,真理と妥当性の「相関主義」の意味をさらに明らかにしなかった。彼は要するに問題を解決していなかったと,自覚していた。」
山田隆夫「カール・マンハイム研究(4):《イデオロギーとユートピア》《インテリゲンチヤ》《現代の診断》《エピローグ》」,168P
「一九二九年二月に、ハイデルベルク大学において開かれたA・ヴェーバーとの合同セミナーの席上でマンハイムが述べているように、「知識社会学は、いくつかの思考の立場がイデオロギー闘争において互いに盲目になり、それぞれが唯一の真理の名のもとに対抗しあっている段階の克服を意味している」(1929b:300-1-J190)。そして、マンハイムが重要視するのは、こうした相対化をへて、各々の立場が、自らの立場に閉塞するのではなく、逆に、自らの立場の部分性を他の立場をつうじて補完することに開かれてあり、視野を拡大していくということである。『イデオロギーとユートピア』において、マンハイムは次のように述べている。「われわれの時代における・・・・・・歴史的研究の役割は、まさしくこうした一時的な必要のために余儀なくされる不可避の自己実体化をくり返し後退させ、自己神化をたえまない対抗運動のなかでくり返し相対化すること、こういう仕方で、自己を補完してくれるものにたいして開かれてあることを強いるという点にある」(1929a:40=J197)。「全体性とは、部分的な視野を自らのうちに受けいれつつ、不断にそれを越えていこうとする、全体への志向を意味するものである。この志向は、認識の自然な進行のなかで一歩一歩自己を拡大していく。そのさい目標として切望されるのは、時間を超えて妥当する最終的結論ではなく、われわれにとって可能な、最大限の視野の拡大である」(1929a:63=J217)。ここで述べられているのは、いわば、「補完への開放性」、「視野の拡大」といった、規範的要請である。すなわち、自己絶対化に向かうことなく、自己の立場の部分性を認識し、自己を相対化すると同時に、自らの部分的な視野にとどまることなく、他の視野に開かれてあり、それによって自らを補完し、自らの地平を拡大していくこと、いわば「自己相対化と自己拡張の連動」が求められることになる。こうした精神的態度のなかで、新しい社会的・政治的方向性を探り出していくことが、ここのマンハイムの基本的姿勢であった。「相関主義」や「白山に浮動するインテリゲンチア」というよく知られた概念も、このような精神的態度を体現するものにほかならない。」
澤井敦「マンハイムとラジオ」,6-7P
「「全体性とは,したがってわれわれの意味では,直接に一挙に対象を見ぬく直観によってとらえられているものではない。そういう直観はただ,神のような目にだけ期待できるだけである。〔中略〕全体性とは,部分的な見方を自己のうちに受けいれっつつ,不断にそれを打ち破り,一歩一歩,認識の自然の歩みにつれて自己を拡大してゆく,全体への志向を意味する。そこで目標としてひたすら追求されるのは,時代にかかわりなく当てはまる結論をつけることではなく,われわれにとって可能な,最大限の視野の拡大である」(Mannheim1936=1979:217)。このような考え方は相対主義とも見えるが,マンハイム自身は自らの立場を「相関主義」(relationism)と呼び,相対主義から厳に区別している。「相関主義というものは,討論においては決着はなんら存在しないことを,意味するものではなく,むしろ絶対的にではなく,立場に制約された視座構造のうちにのみ定式化しうるのだというのが,特定の陳述の本質をなすものだということを,意味するものである」(Mannheim1964=1975:320)。」
保田卓「社会学者の立場: マンハイム, グールドナー, ルーマン」,64-65P
「知識社会学を提唱したカール・マンハイムがいう「相関主義」である。これは、普遍的なるものの存在を捨て去り、他方で相対主義の悪循環も克服しようとする概念である。相関主義は知識や認識の部分性(文脈拘束性)を認めながらも、それらを相互に関連づけるこで、到達可能な地平まで視野を拡大することを目標にする」
木村光豪「グローバル・サウスと人権:「人権のヴァナキュラー理論」の可能性(2)」,252-253P
相対主義と相関主義の違いとはなにか
相対主義とはなにか、意味
相対主義(relativism):・一般に、人間の認識や評価はすべて相対的であるとし、真理の絶対的な妥当性を認めない立場を意味する。正しい原理は人によって、社会によって、文化によって、時代によって変わるのであり、変わらない原理は存在しないと考えていく立場。絶対主義の反意語。
「何が真理かは、人の数だけある(人それぞれ)」というような言葉でよく語られる立場。絶対主義とは対立する概念。たとえばキリスト教では、この世界の神はヤハウェだけであり、他の宗教の神々を認めないという立場をとるので、絶対主義的だといえる。相対主義では価値観の併存や共存を認めるので、キリスト教の神が唯一考えるのも正しい、同様にほかの宗教が自分たちの神が唯一だと考えるのも正しい、神がいないと考えるのも正しい(あるいはどれも正しいと言えない)、ということになる。
マンハイムの言葉では、相対主義は「誰もが正しい、あるいは誰もが正しくないということになる」という。
1:神を信じるのも、信じないのも相対的に正しいといえる。ここでいう相対的とは、「対等」であることを意味する。いずれかの立場が客観的に優位という話ではないということ。あるいは相対的を「特定の個人や社会との関連において」考える場合もある。たとえばある村では「暴力」が正しく、ある村では「暴力」が正しくない、というように、人や社会、文化にそれぞれ規定、依存、拘束されているにすぎず、一切規定されないような普遍妥当な真理はない、という意味合い。
2:絶対的な真理はないけれども、相対的な真理を肯定する立場(広義の相対主義)と、絶対的な真理はなく、またそれゆえにどの相対的な真理も否定する立場(懐疑論的相対主義)にわけることもできる。たとえば「あなたの考えも私の考えもそれぞれ正しい」という立場は、相手の立場や自分の立場を必ずしも否定的に判断し、疑っているわけではない。
懐疑論的な相対主義とはなにか、意味
懐疑論的な相対主義(読み):・あらゆる真理や道徳の存在を否定し、疑い、最終的には自己の主張をも切り崩してしまう立場のこと。一切の断定的判断を差し控える立場。懐疑論とは、人間は普遍的な真理を認識することができないとする哲学的立場のことで、独断論に対立する言葉。
1:絶対的な真理はありえず、どの立場も対等に正しい(あるいは正しくない)
2:「絶対的な真理がある」という絶対主義も、相対主義と対等に正しいことになってしまう。そうすると、相対主義の主張を整合的に維持することが難しくなる。つまり、自己の主張をも切り崩してしまう。
相対主義と相関主義の共通点とは
「普遍的・絶対的な真理や道徳は存在しないと考えている」という点が、相対主義と相関主義の共通点である。
いつ、いかなる場合も当てはまるような真理は存在しないというわけである。
たとえば古代ギリシャのプロタゴラスは、「人間は万物の尺度である」という有名な言葉を残している。風が温かいと感じるか、冷たく感じるかは人によって異なり、誰にでもあてはまるような答え(絶対的な共通認識)はなく、基準は人間の主観や感覚にあるという話。
マンハイムも何が妥当な知識や認識であるかは社会的存在に依存すると主張している(ただし単位は個人というより、世代や党派など、集団のニュアンスが強い)。たとえばあらゆる時代のあらゆる民族、あらゆる世代に共通の真理などないという話。あるのはある特定の時代の、ある社会に依存し、またその社会の枠組みで妥当と考えられている知識にすぎない。
相対主義と相関主義の相違点とは
相関主義は「特定の真理や道徳義務は、存在相対的に把握可能であり、定式化される」と考えている。(懐疑論的)相対主義は客観的価値が存在しないゆえに、道徳的義務は存在しないと考えている。
いったいどういうことか。端的に言えば相関主義はあらゆる真理や道徳義務の存在を否定しているわけではない、という話。しかしどのような意味で肯定しているのかが分かりにくい。
「相関」とは一般的には「 一方が変化すれば他方も変化するように、相互に関係しあっていること」を意味する。例えば植物の場合、根が栄養不足になれば、葉も栄養不足になる。
同じように、社会的存在が変化すれば、人間の考え方(認識)も変わっていく。たとえば日本やアメリカでは「時間は節約するもの、消費するもの」という考えをもつが、アフリカのある部族ではそもそもそのような考えをもっていないという(真木悠介『時間の比較社会学』)。時間は消費するものという価値観は私達には「あたりまえ(自明)」すぎてなかなか自覚できない。
他にも、上下関係に厳しい会社に属していれば上下関係に厳しくなり、ゆるい会社にいればゆるくなるというような身近な変化もあるかもしれない。具体的に上司に上下関係に厳しくするように指示されていなくても、そうしなければ会社が倒産してしまうような環境もありうる。この場合、上下関係という秩序は社会の維持に機能しているという考え方ができる。宗教的な価値観が薄れていったのも、社会の変化がまずあったなど。たとえば人口増大に伴って合理的な科学技術が必要とされたというような時代背景も考えることができる。
特定の真理とはなにか
1:相関主義では絶対的真理の存在を否定している。
2:相関主義では相対的真理(特定の真理)の存在を肯定している。それゆえに、そこから導き出される道徳的義務も存在するということになる。
3:相関主義では、真理や道徳的価値は、ある特定の意味的・社会的存在に共属する人々にとっての真理や価値という意味においてのみ可能であるとされる。そのような特定の社会的条件において真理(知識)を考えることを「定式化」と表現する。いかなる場合においても当てはまるような絶対的真理が仮にあるとすれば、このように逐一定式化する必要は無駄な行為になる。
たとえば「キリスト教の神は存在する」というのは相対的真理であるとする。それゆえに、そこから導き出される「隣人愛」という道徳的義務も相対的に存在するということになる。
隣人愛という義務は、特定の時代の、特定の人たちにとって道徳的価値があり、有意味であると思われているという限りにおいて、相対的な真理であり、相対的な道徳的義務であるといえる。
たとえばある部族や社会では、隣人愛がむしろ自立を阻害する反道徳的価値であると思われている可能性もある。有名な例では、「右頬を打たれたら左の頬を出せ」と「目には目を歯には歯を」という道徳的価値は対立している。
たとえばニーチェはキリスト教の隣人愛などを、弱者から強者への恨みとし、強者を悪しきものと見なすことによってキリスト教徒の道徳的価値が生まれたと心理分析していたのはなかなか面白い。
ある社会集団が強者によって虐げられていた場合、強者を悪とするような、平等や助け合いが善となるようなものが真理や道徳として定式化されるというイメージ。バビロン捕囚などの悲惨な出来事が起こった時代を想像するとわかりやすい。
真理や道徳的義務が単に「相対的にすぎない」という考え方なら相対主義と同じではないのか
1:懐疑論的な相対主義は、あらゆる真理や道徳の存在を「否定」する立場である。絶対的真理なんてものはなく、全ては恣意的、任意的なので「くだらない」と疑って考えるようなイメージ。ニヒリスティック(虚無的)な考え方。無神論や不可知論にむすびつく場合がある。
2:相関主義では、あらゆる真理や道徳の存在を「肯定」する立場ではあるが、それらの真理や道徳は社会的存在によって拘束されていると考える立場であり、それらとの関係によって定式化し、把握しようとする立場のことである(特定の真理を分析する立場というよりは、知識と社会的存在の関係、構造を明らかにする立場である)。
3:「どの社会的立場が真理の最適の条件に到達する最適の機会であるか」と考える差異がある
単に社会的存在(状況)に知識(真理)が規定されるというだけではない、という点が相対主義との相違である。
では一体最適の条件とはいったいなにか。その条件のもとで得られる真理が妥当な真理だとして、それはどういう真理なのか。
山田隆夫さんによれば、マンハイムは真理の妥当性の問題を解決できなかったという。もともと知識社会学はある特定の真理が妥当かどうかという分析をするものではないとマンハイムは述べている。であるとするならば、先程の例のように、「命は大切にするべき」と「患者の利益を大切にするべき」のどちらの真理が妥当かという分析を知識社会学ですることはできない。
とはいえ、特定の真理だけが絶対と考えたり、決断したりすることをマンハイムは否定し、「視野の拡大」や「補完の開放性」を重視している。このようなスタンスによって、真理が妥当であるかという判断はできなくとも、ある真理が絶対主義よりも総合的に考えられていると考えることはできる。
また、ある特定の真理、知識、認識がどのような文脈で、社会的存在によって拘束されているかを分析することは、潜在的なものを意識(顕在)的なものにするという意味をもっている。
たとえば、なぜ「命は大切にするべき」と人間は考えているのか、それはどのような社会的存在、条件によって拘束されているのか、なぜ命よりも個人の利益を重視すべきとまるで違う考えの人がいるか、などを考えていく。多様な集団の立場を分析し、より多角的に視野を広げて総合し、物事を考えていく。
「そして、マンハイムは、『イデオロギーとユートピア』において、こうした存在論的決定として、二つの道が可能であると述べる。第一は、歴史の彼岸に、いわば『充実した無』としての絶対的なるものを想定し、それによってあらゆる歴史的事象の常なる不確実性をそのまま肯定する神秘主義である(ブダペスト時代のマンハイムの、神秘主義への傾倒が思い起こされるだろう)。そして第二に、この神秘主義と対比させつつマンハイムが自らのものとして述べるのが、『さまざまな意味的要素の普遍的な関係性』を説く立場である。」
澤井敦「カール・マンハイム」、東信堂70-71P
「しかし、マンハイム自身は、たとえば『精神的なる者の領域における戦争の意義』(一九二九)において、相対主義と相関主義を対比しつつ次のように述べている。『特定の認識の「存在相対性」というこの洞察は、……誰もが正しい、あるいは誰も正しくないということになる相対主義にではなく、むしろ特定の(質的な)諸真理は、存在相対的に把握可能であり、定式化されるるものであるとする相関主義へとつうじる』(一四四)、また、一九三四年に公表された論文『ドイツ社会学』においては次のように述べられている。『相対主義が意味するのは、客観的価値は存在せず、それゆえ道徳的義務は存在しえないということであろう。他方、相関主義が強調するのは、道徳的義務は存在する。しかしその義務は、それが関係している具体的状況から導きだされてくるという事実である』(二四〇)。このように、普遍妥当的な真理は存在しないとする点で、相関主義と相対主義は共通している。しかし、相関主義から、懐疑論的な相対主義におけるような、真理や道徳的価値についての決定不可能性が導きだされてくるわけではない。論文『知識社会学』(一九三一)においては次のように述べられている。『だからここでもまたあらゆる主張の任意性という意味での相対主義が結果としてでてくるわけではない。むしろわれわれのいう意味での相関主義は、あらゆる言明が本質からしてただ相関的にのみ定式化されうるということを示唆している。そしてこの相関主義が相対主義へと転化してしまうのは、ただそれが永遠の、脱主観化された、非パースペクティヴ的な真理というより古い静的な理想と結びつけられて、相関主義とは乖離したこうした(絶対的真理という)理想によって判断される場合のみである』(一九二)」
澤井敦「カール・マンハイム」、東信堂72~73P
「このことは再び,つぎの問題を提起する。「知識社会学は,真理が,『相対的』である」,すなわち,「認識主体の主観的な立場そして,社会的状況(the subjective standpoint and the social situation of the knower)に依ること」を意味するのであろうか。マンハイムのこれに対する答えは,否定的である。というのは,知識社会学の観点からの歴史研究は,いかなる絶対的真理をも明らかにしないからであるから,このことは,「相対主義」ではなくて,「相関主義」を意味するからである。観察者,認識主体の視座構造は,その社会的立場とともに変化するであろう可能性は大きいものがある。しかし,「どの社会的立場が,真理の最適の条件(an optinum)に到達する最善の機会であるか」という問題は,やはり残っているのである。(p.71)不幸なことに,マンハイムはさらに進んで,真理と妥当性の「相関主義」の意味をさらに明らかにしなかった。彼は要するに問題を解決していなかったと、自覚していた。そして、結局,彼の立場は,「観念とその妥当性の社会的基礎分析は,相対的に別個の二つの問題である」ということであったようである。社会的分析は,妥当性の決定には、全く無関係ではないけれども,まさに何が,これと関係しているのかは,マンハイムは明らかにしなかったのである。」
山田隆夫「カール・マンハイム研究(4):《イデオロギーとユートピア》《インテリゲンチヤ》《現代の診断》《エピローグ》」,168P
【コラム】カール・ポパーにおける相対主義と相対化主義
相対化主義(relativizationism):・何ものも絶対化せず、自分の見解も含めた多様な見解を相対化し、誤りがあれば修正・改善することによって、より正しい見解を探究していこうとする立場。批判主義ともいう。
カール・ポパーは相対主義と相対化主義を区別している。相対主義は修正や改善の余地がないものであり、相対化主義は修正や改善の余地があるものだという。
ポパーいわく、相対主義の場合は「それぞれの真理が同様に正しい」と考える立場であり、相対化主義の場合は「それぞれの真理が同様に誤っているかもしれない」と考える立場である。ただ誤っているかもしれない、というような懐疑主義ではなく、ポパーは具体的に主張の誤りを指摘することを要求している。ポパーは相対化主義を「批判主義」とも呼ぶ。
マンハイムの文脈では、「それぞれの真理が正しい、あるいは正しくない」というように相対主義と相対化主義が一緒に「相対主義」として扱われている。相関主義はどちらかといえば相対化主義に近いと思われる。相対化主義は絶対化を否定するが、理念としての真理を探究するというスタンスは否定されていない。相関主義も、解決可能性を疑っておらず、より視野を広げて、妥当な真理を探してこうという姿勢がある。
「(1)絶対主義(absolutism):絶対的真理の存在の肯定1)肯定的絶対主義(positiveabsolutism):絶対的真理を獲得しているという立場2)否定的絶対主義(negativeabsolutism):理念としての真理を探究する立場(2)相対主義(relativism):絶対主義を否定し,相互に異なる見解が(それぞれの社会,文化,歴史において)正しいとみなす立場。因みに,個別の見解を(それぞれの社会,文化,歴史において)正しいものとして,それを絶対化する絶対化主義(absolutizationism)でもある。局所的絶対主義(localabsolutism)とも呼びうる。相対主義によれば,修正や改善の余地はない。他方,相互に異なる見解が(それぞれの社会,文化,歴史において)間違っているとみなす立場は相対主義ではなく,(次に述べる)相対化主義である(どんな見解も誤りがあれば,修正・改善をめざすからである)。(3)相対化主義(relativizationism):何ものも絶対化せず,自分の見解も含めた多様な見解を相対化し,誤りがあれば修正・改善することによって,より正しい見解を探究していこうとする立場。相対主義と同様,肯定的絶対主義は否定するが,相対主義とは異なり,絶対化主義・局所的絶対主義ではなく,他方,理念としての真理を探究する(否定的)絶対主義は否定しない立場である。」
立花希一「 相対主義と相対化主義 」,32P
【コラム】多元主義と相対主義の違いについて
- 多元主義:「複数の原理のどれもが正しいことがある」と考える立場
- 一元主義:「正しい原理は一つに絞られる」と考える立場
- 相対主義:「正しい原理は人(社会、文化、時代)によって変わり、変わらない原理は存在しない」と考える立場
- 絶対主義:「正しい原理は人(社会、文化、時代)によって変わらない」と考える立場
1:多元主義と相対主義は区別しておいた方がいい
2:多元主義or一元主義、相対主義or絶対主義の組み合わせで、4通りの立場が考えられる。
たとえば正しい原理はひとつであり、時代によって変わらないと考える一元主義的絶対主義がある。正しい原理は時代によって変わるが、それぞれの時代ごとに正しい原理はひとつに限られると考えれば、一元主義的相対主義になる。複数の原理が時代によって変わらないと考えれば多元主義的絶対主義、正しい原理は時代によって変わり、それぞれの時代にとって正しい原理は複数あると考えれば多元主義的相対主義になる。
たとえば倫理学では、患者が重病で死を望んでいる場合、いわゆる「安楽死」のケースで問題になることがある。「患者の利益を優先すべき(だから安楽死を許すべき)」という説明原理と、「命は大切にすべき(だから安楽死を許すべきではない)」という説明原理のどちらが正しいのか。M・ウェーバーはこのような価値観の対立を「神々の争い」と呼んでいた(いわゆる価値相対主義)。
こうした対立する原理に、唯一の正解があるのか。時代ごと、社会ごとによって、つまりコンテクスト(文脈)によってどちらが正しいか変わっていくのか。それともどの時代や社会でも正しいものはひとつであり、一方が常に間違っているのか。多数決原理(国会における法律の作成・変更)で現代では決められているが、そもそも多数決原理自体も時代ごとの説明原理にすぎないのではないか。
極端な相対主義では「そんなものはわからない」と考え、人は〇〇するべきだというような道徳義務を疑い、肯定せず、軽視していく。相関主義ではどのように考えていくのか。そんなものは人間の能力では分からないと結論付け、そこで止まってしまうのか。
M・ウェーバーの名言が心に突き刺さるので、紹介しておく。
「これは各人が、各人なりに解決しなくてはならない課題です。もちろんそれは一気に解けるようなものではなく、各人が一生かけて色々と経験を積みながら解決してゆくべき問題です。君がいま初めて自分に提起されたこの課題をどう解くか、それはもっぱら君自身の問題であり、君の良心(Dein Gwwissen)と君の知性(Dein Verstand)、君の心(Dein Herz)が責任を負うべき事柄です。」
「ある人間が本当に望んているものが何であるかは、これぞわが『究極の』立場だと称するその人の言い訳からではなく、およそ言抜けを許さぬその時々のまったく具体的な問題にたいして、というところの『究極の』立場からして、その人が実際にどう対処するかによってのみ確かめられるのだ、と。」
こうした姿勢は、マンハイムの相関主義と通底するところがある。自分の良心や知性、心が責任を負うことができたと言い切るためには、自分だけの狭い認識から自分が正しいと価値や知識を絶対化するのではなく、他人の立場になって物事の視野を広げる必要というものが方法的に出てくる。
頭の中で抽象的に、絶対的に真理はこうだ、などと考えていくのではなく、具体的な時代、具体的な社会、具体的な状況において、これは妥当な真理ではないのか、と多角的に考えていくべきだという話です。多角的に考えるためには、知識が社会的条件に拘束されているという事実をまずは自覚する必要があり、その構造を分析する「知識社会学」はそれゆえに必要であるという話になります。近代以降特に顕著な価値分裂はいつ頃、なぜ生じてきたのか、という分析も面白い。科学革命や宗教革命など、さまざまな要因、歴史的背景がそれぞれの視点から、現在分析されている。
※詳細は以前作成したウェーバーの記事を参照
「規範的判断を根拠づけるそれ以上さかのぼれない原理は、たったひとつであるとは限りません。複数の原理が、それぞれ、他の原理に根拠づけられることなく、並存している場合もあります(もし他の原理に根拠づけられているなら、それはじつは「原理」ではありません)。このように、《複数の原理のどれもが正しいことがある》と考える立場を、原理に関する「多元主義」といいます。これに対し、《正しい原理はひとつに絞られる》と考える立場は「一元主義」です。多元主義と一元主義は「それ以上さかのぼれない原理はひとつなのか複数なのか」という問題をめぐって対立します。*なお、多元主義とよく混同される立場に「相対主義」があります。「相対主義」とは《正しい原理は人(社会、文化、時代)によってすべて変わり、変わらない原理は存在しない》と考える立場のことです。相対主義は、《人(社会、文化、時代)を通して変わらない正しい原理がある》と考える「絶対主義」に対立します。つまり、相対主義と絶対主義は「原理の妥当性は絶対的なのか相対的なのか」という問題をめぐって対立しています。多元主義と相対主義は、問題にしている論点が異なるので、必ずしも重なりません。多元主義と相対主義をめぐる立場としては、多元主義か一元主義か、相対主義か絶対主義か、の組み合わせで、2×2=4通りの立場がありえます。」
マンハイムのパラドックスとは、意味
マンハイムのパラドックス:・知識は相対的(被拘束的)であるという主張が、絶対的真理として主張されているというパラドックスのこと。マンハイムへの批判として言及されることがある。
こうしたパラドックスは古くからあるものであり、プラトンの『テアイテトス』でも言及されている。
(命題1)いかなる命題も絶対に正しいということはない
(命題2)命題1も絶対に正しいということはない
命題1を認めれば、命題2が帰結する。命題2を否定しようとすれば、命題1が間違いとなってしまう。絶対主義者の立場から相対主義の立場への批判として知られている。
C・W・ミルズはマンハイムの主張が矛盾しているように見えるのは、批判者が「絶対的真理」を前提している場合であるという。
澤井敦さんいわく、むしろそれは「絶対主義のジレンマ」だという。
もし絶対的真理が存在するという前提をもって批判していれば、相対主義と相関主義の差は大差がないことになる。どちらも絶対的真理が存在しないと疑っている(懐疑している)からである。
もし絶対的真理など存在しないという前提をもって批判していれば、批判者も相対主義や相関主義と立場は同じである。相違点が別の点にあることを示せば、(懐疑論的)相対主義と相関主義は異なるものだと呈示することができる。
相関主義の主張:絶対的真理などない。
相関主義に対する批判:それでは懐疑論的な相対主義と同じではないか。絶対的真理や道徳がなく、あるのは人それぞれ、社会それぞれ、時代それぞれの相対的な真理や道徳のみであり、それらは疑いをもって接し、否定すべきものではないか。
批判に対する反論:相対的な真理や道徳的価値は肯定している。どんな時代、社会、状況にも当てはまるような絶対的、普遍的、妥当性のある真理というものは確かにないが、しかしその時々の状況によって当てはまるような真理はある。したがって道徳もあり、また道徳の義務も存在している。したがって、相対的だからといって即座に疑うべきもの、否定すべきものとはならない。ただし、より広い視野をもって、真理とはなにかを総合的に考える姿勢はもつべきだと考えている。
「相関主義の主張が懐疑論的にみえてしまうのは、それをみる者が、普遍妥当性を有する絶対的な真理や道徳の存在を前提としている場合である。C・W・ミルズがかつて述べたように、相関主義の矛盾とみえるものは、マンハイムの議論自体の矛盾ではなく、むしろ『絶対主義者のディレンマ』なのである。」
澤井敦「カール・マンハイム」、東信堂74P
「かのパラドックスについても、それは、絶対的真理の存在を前提とした場合にのみ生じる問題、いわば『絶対主義者のディレンマ』なのであって、知識社会学の主張を、知識社会学自体の真理条件の基に立てることは十分正当であると論じ、マンハイムの立場を擁護している。」
澤井敦「カール・マンハイム」、東信堂135P
「これまでマンハイムの知識社会学にたいする最も一般的な批判として,「マンハイムのパラドックス」(知識の存在拘朿性というその中心的テーゼ自体が存在拘束的=相対的なものであることになるという矛盾)がくりかえマンハイム自身はかなり初期の時点して語られてきたこうしたパラドックスをはっきりと意識しており,それを間題視していたのである。結果的には,相対主義を相対主義的にたてるという現代の科学論,科学社会学に見られる立場にマンハイムが到達していたことが明らかにされている、,こうして「相関主義」という立場が構築されること.そして「自山に浮動するインテリゲンチャ」という概念も知識人の現状を肯定するものではなく,むしろ,相関義の延長線上で知識人のあるべき姿を示す規範的要請であることが,強調されたのである。」
澤井敦「マンハイム知識社会学の研究」,第五章
「マンハイムのバラドックス,それは「知識は存在拘東的=相対的である」という主張(=知識)自体が普遍的妥当性を有する真理として主張されている.というパラドックスである。こうしたバラドックスをめぐる議論がとりあげられてしる。」
澤井敦「マンハイム知識社会学の研究」,第五章
相関主義にはニヒリズムか
ニヒリズム:・一般に、一切の既成の価値・秩序・権威を否定する立場のこと。虚無主義と訳される。ニーチェなどがニヒリズムを主張した人物として知られている。
たとえば真理などはすべて仮説にすぎず、絶対的・普遍的な正解などないのだから無駄なのではないかと考えていく。ニーチェの「神は死んだ」という言葉がイメージしやすい。
真木悠介さんは『時間の比較社会学』で、「時間のニヒリズム」とは自分が死んだ後、あるいは人類が滅亡した後にはすべてが消え去っている以上、現在のあらゆる物事が無意味だという感覚の取り方だと主張している。
こうした感覚の取り方は特に近代以降特有のものである、という主張が面白い。
さて、本題はマンハイムの相関主義がニヒリズムなのか、という点である。
1:マンハイムは「相関主義はニヒリズムとわずかなりともかかわりあうものではない」と主張している。
2:相関主義は相対主義のように自分の殻の中へ閉じこもることを可能な限り克服しようとして作られたものである。
3:たとえば何が正義かといったような問題、危機が生じたとしても人それぞれと殻に閉じこもるのではなく、解決可能性を疑わないことが重要になる。そのためには「視野の拡大」や「補完の開放性」を知識社会学を通して身につける手法がある。ただしなにがその時々において相対的に妥当な真理なのかについての基準は明確にされていないことに注意。
「私が弁護する動的な相関主義は、ニヒリズムとわずかなりともかかわりあうものではない。動的な相関主義は、あらゆる立場においてみいだされる狭量さ、自分の殻のなかへの閉じこもりを可能なかぎりで克服しようとしたさまざまな諸傾向から生じてきたものである。ここにおいてまずもって重要であるのは、われわれの存在・思考の危機の解決可能性を断固として疑わず、それゆえニヒリスティックになりえないような方法、むしろ今日すでに可能である自己拡張のために、あらゆる立場にたいして一度自らの立場を問題視し、思考上の習慣としてあたりまえのこととなっている自己実体化を停止してみるよう要請すること、このことを試みるような方法である」
カール・マンハイム『ドイツにおける社会学の問題性について』,620P
「『イデオロギーとユートピア』の根底にはニヒリズムがあるとするE・R・クルティウスの批判に答えて、マンハイムは、一九二九年の『ドイツにおける社会学の問題性について』で、次のように述べる。『私が弁護する動的な相関主義は、ニヒリズムとわずかなりともかかわりあうものではない。動的な相関主義は、あらゆる立場においてみいだされる狭量さ、自分の殻のなかへの閉じこもりを可能なかぎりで克服しようとしたさまざまな諸傾向から生じてきたものである。ここにおいてまずもって重要であるのは、われわれの存在・思考の危機の解決可能性を断固として疑わず、それゆえニヒリスティックになりえないような方法、むしろ今日すでに可能である自己拡張のために、あらゆる立場にたいして一度自らの立場を問題視し、思考上の習慣としてあたりまえのこととなっている自己実体化を停止してみるよう要請すること、このことを試みるような方法である』(六二〇)」
澤井敦「カール・マンハイム」、東信堂76P
(2)自由に浮動するインテリゲンチャ
自由に浮動するインテリゲンチャとはなにか
自由に浮動するインテリゲンチャ(英;free-floating intellectuals,独;freischwebende Inteligenz):・知識が存在拘束的でありながらも、社会的条件からみて他と比較すると、自らの存在拘束性から相対的に自由になっている知識人のこと。
「自由に浮動する」と「インテリゲンチャ」を分けて、その両方を掘り下げていきたい。
インテリゲンチャとはなにか、意味
インテリゲンチャ:・「知識階層」と訳される。ラテン語で「理解力のある人」を意味するinteligensに由来するロシア語。
日本では「インテリ」と呼ばれたり、文化人、知識人と類義語的に用いられることがある。
知識人は一般的には、文化的・知的生産に従事する者の総称を指している。たとえば学者、弁護士、芸術家、ジャーナリスト、医師、技術士などである。
自由に浮動するとはなにか、意味
自由に浮動する:・相対的にみて階級を欠いているという意味。知識が存在拘束的でありつつも、知識人以外と比較して、相対的に自らの存在拘束性に自由になっているということ。アルフレート・ウェーバーの表現を借りたものであり、「社会的に浮動する」インテリ層とも呼ばれることがある。
たとえばある企業の社長は、自分の会社の利益にならないような主張をすることは難しく、また無意識に染み込んでいるかもしれない。一方で、大学等の学者はそのような制約が社長と比べて自由だということができる。いざとなったら大学を辞めて別の大学へ移ることもできる。もちろん、絶対的に自由だというわけではない。大学の顔色を伺うこともあるだろうし、政府の助成金が必要で、自由にならない部分もあるかもしれない。インターネット社会における知識人、たとえばユーチューバーなどは大学の教授と比較してより固定した地位を持たない、より自由に浮動する階層なのかもしれない。一方で、責任感のなさが問題になるのかもしれない。
[知識人]「一般的には文化的・知的生産に従事する者(学者・弁護士・芸術家・ジャーナリスト・医師・技術士など)の総称。この意味ではいつの時代にも存在した文化的・知的機能の社会的担い手である。しかし、知識人概念は、ロシアにおけるインテリゲンチャ(inteligentsiya)、フランスにおけるアンテレクチュェルという用語の登場に見られるように、近代的性格をもつものとして、むしろ重要である。すなわち、近代以後の資本主義の発展、国民国家の形成過程で高等教育が普及し、文化的・知的生産に従事する社会階層が広範に形成されるに至ってはじめて、知識人の問題が社会的に注目されたのである。マンハイムの有名な社会的に『自由に浮動する』インテリゲンチア(freischwebende Inteligenz)という規定も、こうした現実を基盤としている。」
「社会学小辞典」430P
[浮動的インテリゲンチャ]「A.ウェーバーが創始し、マンハイムが重用した用語。知識人は特定の階級に属さず、諸階級のあいだを自由に遍歴し、さまざまな立場に身を置くことができ、それゆえ、思想や文化の調停者・総合者たりうるものである、とする知識人像。」
「社会学小辞典」537P
「ここでいう『自由に浮動する』とは、自らの存在拘束性から完全に自由になっているという意味での『絶対的な』自由を意味するものではない。マンハイムが、『相対的にみて階級を欠いた』であるとか、さらには、『相対的にみて自由に浮動する』などと常々述べるように、これは、存在拘束的でありながらも、なおかつ、その者がおかれている社会的条件からみて、他と比較すると、自らの存在拘束性から相対的に自由になっているということである。具体的には、生産過程に直接参加し、組織上の制約を受けざるをえない人々などと比べると、知識人は、相対的にみて自由浮動的であるということである。」
澤井敦「カール・マンハイム」、東信堂87P
「したがって、『自由に浮動するインテリゲンチア』という概念によって、マンハイムが主張しているのは、このように肯定的な側面もあれば否定的な側面もある自由浮動性という社会的条件を、肯定的な方向において、つまり先にみた意味での『教養』を身につけるという方向において、いわば有効に活用すべきだということである。この意味で、くり返せば、『自由に浮動するインテリゲンチア』をめぐる議論は、事実的認識というよりは、むしろ、知識人にたいする規範的要請であるといえる。」
澤井敦「カール・マンハイム」、東信堂88P
階級と階層の違いとはなにか
階級という場合、マンハイムの文脈においてはマルクスにおける階級を想定している。たとえば「ブルジョワ階級(資本家)とプロレタリアート階級(労働者)の対立」というような言い方をするように、主に経済的なカテゴリーとして考えられている。
階層という場合、マンハイムの文脈においては「様々な経済的・社会的基盤をもつ成員により構成されている人々」を意味する。
たとえば全くお金をもっていないような貧乏な学生であったとしても、「自由に浮動するインテリゲンチャ」に、つまり知識人階層になりうる。
学者だけ、技術者だけ、お金に余裕のある利子生活者だけ、学生だけといったように特定の階級や党派、集団に固定されるようなものではない。学生でも知識人階層とはいえない人もいれば、いえる人もいる。主婦(主夫)でも同様に知識人階層といえる人もいれば、いえない人もいる。ある企業の会社の社長だからといって知識人階層ではない、ともいえないし、またある政治団体の議員や党員だからといって知識人階層ではない、ともいえない。もちろんある集団に知識人階層が多い、少ないという差はあるかもしれないが、それだけで区別できないのである。
「マンハイムは,こうした総合の担い手は「比較的階級色をもたない,社会的空間の中でそれほど固定した地位をもたない階層」であるとし,アルフレート・ウェーバーの表現を借りて,この階層を「社会的に浮動するインテリ層」と呼んでいる。実際,この階層は,様々な経済的・社会的基盤をもっ成員により構成されているので,これを経済的なカテゴリーである「階級ないし階級の付属物として把握」することはできない(Mannheim1936=1979:270)。」
保田卓「社会学者の立場: マンハイム, グールドナー, ルーマン」,60P
「マンハイムは書いている。
「しかしながら,これらの連携のほかに,知識人は,つぎの事実によって動機づけられている。知識人の訓練は、数個の遠近法で,時代の問題を,彼が直視するように準備することである。彼の時代の論争の参加者がそうするように,たった一つの遠近法においてではない。われわれは,言った。知識人は,単一の遠近法ではなくて,数多くの遠近法で,時代の問題を見通すことができるように訓練されている。一つの場合から他の場合に,党支持者として行動し,ある階級と連合する場合がある。」(p.105)3.ここで強調されていることは,社会現象,社会問題に対して,数多くの遠近法を用いる教養ある人間の潜在的能力である。マンハイムは,再び強調する。「知識人は階級の上にある身分の高い層ではない。そして、彼等自身の階級的付属品(attachment)を克服する能力を,他のグループよりもさらに多く賦与されているわけでもない。」(p.105)
初期論文のころ,彼は,アルフレト・ウェーバー(AlfredWeber)から借りてきた,相対的に結びついていないインテリゲンチャという語(relativelyunattachedintelligentia)で,「相対的に(relatively)」という概念は,「いかなる空虚な語でもない(noemptyword)」と説明する。この表現は,勤労者がするように,「ねばりづよく」,あたえられた問題に知識人が反作用しないという周知の事実に言及しているだけである。(p.106)ところで,いわゆるインテリゲンチヤの一員になるということは,妥当性についていかなる構造的保証を与えるものではない。あるいは、そのことが「啓示に関与」することでもない。マンハイムが,インテリゲンチヤについて,このテーゼで伝えたいことは,あきらかに,「知識人の一定のタイプは,社会的に有効な見通しをテストしたり採用したりする,そして,見通しの不一致を体験したりする最大限の機会をもっているということ」であった。(p.108)。正しいか誤っているかはともかく,これは,彼の批判者が帰せしめているよりもさらに控え目なおだやかなテーゼである。」
山田隆夫「カール・マンハイム研究(4):《イデオロギーとユートピア》《インテリゲンチヤ》《現代の診断》《エピローグ》」,172-173P
「知識人は階級の上にある身分の高い層ではない。そして、彼等自身の階級的付属品(attachment)を克服する能力を、他のグループよりもさらに多く賦与されているわけでもない。」
カール・マンハイム『イデオロギーとユートピア』,105P
知識人の範囲
マンハイムでは初期においては自由に浮動するインテリゲンチャとして、第一に知識社会学者が念頭に置かれている。
次に社会学者、学者一般、公務員層や自由業者などが挙げられていく。
そして最終的には、学生、さらに社会を構成する人々全体へと広がっていく。知識人と一般人を区別する垣根がなくなっていくのである。ただし、両者を区別する基準がないわけではない。どのような階級であってもあっても「ある基準」を満たせば知識人階層であるといえる、という点が重要である。
「さて、このような一連の精神的態度をになうのは、少なくとも『イデオロギーとユートピア』においては、まずもって知識社会学者であり、また広い意味では社会学者、さらに学者一般であったといえる。ただ、『イデオロギーとユートピア』においても、インテリゲンチアに属する者として、たとえば公務員や自由業者があげられている。そもそも、ここで問題となっているのが精神的態度であり、精神的な次元での規範的要請であるとすれば、その担い手は狭義の知識人に必ずしも限定されないはずである。実際、一九三〇年の『一般社会学』講義では、たとえば『われわれがそのなかに、しかもインテリゲンチア層としておかれている、われわれ自身の精神的状況の問題』(110)、といった言い方で、聴衆である学生を含めたかあちで、インテリゲンチアという言葉が使われている。さらに一九三二年の『インテリゲンチアの社会的および政治的意義』では、銀行家やジャーナリスト、ボヘミアンなども知識人層に属する者としてあつかわれている。ドイツからイギリス時代へと進むにつれて、マンハイムのいう『知識人』と、『一般人』を区別する垣根は徐々に取り払われ、両者の差異がはっきりしたものではなくなってくるという傾向がみられる。」
澤井敦「カール・マンハイム」、東信堂89-90P
「次節以降の議論を先取りしていえば、この規範的要請がなされる対象が、狭義の知識人に限定されなくなり、むしろ最終的には社会を構成する人々全体へと拡張されていく、またそうでなければナチスのような独裁的勢力に抗することはできないという考え方が、マンハイムにおいてこの時期以降強くなっていくのである。」
澤井敦「カール・マンハイム」、東信堂93P
教養とは
教養とはなにか、意味
教養:・存在拘束的でありながらも、同時に、さまざまな文化的傾向に開かれてあり、自らの視野をたえず拡大していく精神的態度
Q いったい何が知識人階層とそうではない階層を区別するのか
A 「教養」を身につけているかどうかで区別する。
教養が知識人を結び合せる基礎となる。財産の大小といった差異で区別できない。大学を卒業しているか、なにか専門的な資格や知識があるかどうかといったものでも区別できない。
たとえば大学で「一般教養科目」といえば、哲学、歴史、文化、自然科学、語学などがある。
二桁の掛け算ができなかったり、沸騰が何℃で起こるか知らなかったり、挨拶がきちんとできなかったりすると、「教養がない」というように日常会話では使われている。
しかし、マンハイムが使う「教養」はこのような意味合いではない。ここまでいけば教養がある、習得できるというような「量」的なものではなく、「質」的な「精神的態度」にある。世界で一番多くの知識を手に入れている人であったとしても、知識人であるとは限らない。
「このように、教養文化に関する議論において、『教養』とは、広範な知識の集積などというものではない。むしろそれは、存在拘束的でありながらも、同時に、さまざまな文化的傾向にたいして開かれてあり、自らの視野をたえず拡大していく精神的態度を意味するものである。もちろん、教養文化の特質は、時として、ある種の軽薄さ、飽きっぽさをうみだすこともあるかもしれない。しかしマンハイムによれば、『教養文化の好ましい面は、そこにおいて『教養を身につけること』ができるという点にある。そのさい、『教養を身につける』とは、ある種の運動性、精神的空間の拡大、向上した感受性を意味している』(三二一)。後の『イデオロギーとユートピア』においてもマンハイムは次のように述べる。『かくして近代的教養とは、はじめからいきいきとした抗争であり、社会的空間のなかで互いにあい争うさまざまな意志や傾向の縮小された模写なのである。それに応じて、教養ある人は、彼の精神的地平に関していえば、多面的に決定されていることになる。』(二七一)。さらに、一九三〇年の『一般社会学』講義では、次のように述べられている。『近代的教養の本質とは、根本的には、それが、多様な視野の可能性をそのうちに含み持っているということなのです。本当に教養を身につけているということが意味しているのは、見たり考えたりするさいの、あらゆる可能性を吟味していくということなのです。』(93)。そして、一九三二年の『イテンリゲンチアの社会的及び政治的意義』でも、真に教養を身につけた者とは、現実を他者の立場から見る能力と機会を有する者であると述べられる。他者の視点を理解できるからこそ、教養ある者は、多様な視野を理解し、時に応じてそこから選択することもできる。」
澤井敦「カール・マンハイム」、東信堂85~86P
「マンハイムによれば,このように多様な階級的出自をもつ成員からなるインテリ層に凝集性を与えているのは「教養」である。ここで言われる教養とは,ある特定の階層によって独占される前近代的な「教養」ではなく,「社会という場面で衝突しあうさまざまな意志や傾向の縮小版」としての「近代的教養」である(ebd.:271)。教養によって,インテリの問に「ある共通の土俵」(ebd.)が作り出される。ここにおいて,存在披拘束的な諸認識は等しく「距離化」され,それぞれの背景となっている歴史的・社会的諸条件へと「関係づけ」られ,そしてより包括的な視点から「総合」されるのである。」
保田卓「社会学者の立場: マンハイム, グールドナー, ルーマン」,60P
「教養を身につけるということは、知識人にたいして、とりわけまずは知識社会学や相関主義の担い手となり、総合的な観察の担い手となる知識人にたいして、マンハイムがなす規範的な要請なのである。」
澤井敦「カール・マンハイム」、東信堂87P
視野の拡大と補完の開放性、実験的生活
視野の拡大:・自分の部分的な視野が絶対だと思わずに、相対的であることを意識し、常に視野を拡大していく態度。
補完の開放性:・自分の部分的な視野に留まることなく、他の視野に開かれている態度。
実験的生活(Das experimentale Leben):・さまざまな存在の可能性を試験的に採用し吟味することを普段(不断)に試みる生活のこと。さまざまな視野の可能性を試行する態度のこと。
重要な点は、自らにとって自明な意味解釈から距離を取るという態度であり、マンハイムは「生からの距離化」と呼んでいる。こうした態度はフッサールのエポケー(判断保留)にも通じるものがあり、実際マンハイムは現象学を学んでいる。
また、「反省によって別様でもありえたひとつの可能性として自己を見つめる」という実験的生活の態度は、ルーマンの「等価機能主義(他である可能性の模索)」に通じるものがある。あるいはメイヤスーの「非理由律(偶然性の必然性、別様である可能性の絶対化)にも通じるものがあるのかもしれない。それぞれに共通しているのは、独断的なものの否定であると言える。
「マンハイムによれば、近代化の進行にともない社会的分化が進行するにつれて、単独の世界観によって覆われていた原始的社会とは異なり、世界解釈や意味連関も分化し、それらが相互に相対化される契機がうまれてくる。さまざまな意味解釈の多元性、また各々の部分性が明白になるということは、近代社会に生きる人間にとっての基本的な条件となる。こうした状況は、そこに生きる個人にも、自らにとって自明な意味解釈から距離をとるという態度、すなわち『生からの距離化(LIVENSIDISTANZIERUNG)』を可能とする。個人はいわば、自己自身を反省的に見つめる観客となり、別様でもありえたひとつの可能性として自己を見つめることができるようになる。こうした状況を前提として、さまざまな存在の可能性を試験的に採用し吟味することを普段に試みる『実験的生活(Das experimentable Laben)』という生活態度が可能となる。」
澤井敦「カール・マンハイム」、東信堂78P
「しかし他方、こうした状況はまた、場合によっては耐え難いほどの精神的な不安感を人々にもたらす。そしてこのことが、『再原始化(Reprimtivisierung)』を呼び起こすとマンハイムは考える。これは、原始的な精神の状態から脱却し、意識の相対化の度合いが高まっていくことが、逆に原始的な段階への意識の反転をもたらすという現象である。ある意味では、こうした反転へと向かう傾向は、相対化へと向かう近代社会の傾向のなかにすでに孕まれており、その出現は一種の内的必然性を有している。」
澤井敦「カール・マンハイム」、東信堂78~79P
「こうした批判の拠り所、相関主義自体が含み持つ規範的要請を、『補完への開放性』、『視野の拡大』という語で特徴づけることができるだろう。『イデオロギーとユートピア』において、マンハイムは次のように述べている。
『われわれの時代における……歴史的研究の役割は、まさしくこうした一時的な必要のために余儀なくされる不可避の自己実体化をくり返し後退させ、自己神化をたえまない対抗運動のなかでくり返し相対化すること、こういう仕方で自己を補完してくれるものにたいして開かれてあることを強いるという点にある』(一九七)」
『全体性』とは、部分的な視野を自らのうちに受けいれつつ、不断にそれを越えていこうとする。全体への志向を意味するものである。この志向は、認識の自然な進行のなかで一歩一歩自己を拡大していく。そのさい目標として切望されるのは、時間を越えて妥当する最終的結論ではなく、われわれにとって可能な、最大限の視野の拡大である」(二一七)。自己絶対化に向かうことなく、自己の立場の部分性を認識し、自己を相対化すると同時に、自らの部分的な視野にとどまることなく、他の視野にも開かれてあり、それによって自らを補完し、自らの地平を拡大していくこと、いわば『自己相対化と自己拡張の連動』が、こうした規範的要請によって求められることになる。」
澤井敦「カール・マンハイム」、東信堂、75P
真に教養を身につけた者とは、意味
真に教養を身につけた者:・現実を他者の立場から見る能力と機会を有する者
他者の立場から見る自分を見る、というミードの話とも通底するものがある。人間は無意識的にそうして他者の立場に立って見ているが、意識的に見ることによってより、視野を広げることができるといえる。
「そして、一九三二年の『イテンリゲンチアの社会的および政治的意義』でも、真に教養を身につけた者とは、現実を他者の立場から見る能力と機会を有する者であると述べられる。他者の視点を理解できるからこそ、教養ある者は、多様な視野を理解し、時に応じてそこから選択することもできる。」
澤井敦「カール・マンハイム」、東信堂、86P
教養文化とはなにか、意味
教養文化(Bildungskultur):・都市において形成される、ある特定の狭く限定された生活共同体とその存在上の拘束性から、相対的にみて、独立したものとなった文化
Q 教養とはなにかはわかったが、どのような環境でそのような教養を身につけられるのか
A 「教養文化」において教養は身に着きやすい
直観的に考えて、地方よりも都市のほうが多様な価値観をもった人が比較的多く生活している、というのはイメージしやすい。現代ではインターネット社会が広がっているので、地方でも教養文化を体験できる機会が多いのではないだろうか。全く別の文化、価値観をもった人と話す機会、環境は格段に増えている。
日本では「村社会」などと呼ばれ、閉鎖的で一面的、排他的な要素が否めない。たとえば「年功序列がほんとうに正しいのか」などという問題提起をしたら、その村では無視されてしまう、というようなケースもあるかもしれない。
マンハイムは教養文化を、「既存のさまざまな生活共同体の文化的傾向から成るポリフォニー」だと考えている。
ポリフォニーとは、複数の独立した声部からなる音楽のことであり、単一の旋律だけが続いているモノフォニーの対義語である。
「東京は田舎者の集まり」などと呼ばれることもあるが、多くの地域のそれぞれ異なる地方出身者の集まりであり、多様な価値観が併存している共同体であると考えることもできる。
たとえば地方出身者が都市の大学で、いろいろな価値観の人と触れ合うケースを考えてみる。それまで周りに男尊女卑の思想しかなかった人が男女平等思想の人と触れ合い、こういう価値観もあるんだ、というように「視野拡大」をしていく。そういう機会を得られる可能性が相対的に、比較的高いのがとりわけ「都市」であるということである。都市といえば近代化がまさに生じる大きな要因であったことも見逃せない。真木悠介さんの時間のニヒリズムも、都市がその原因に大きく関わっている。また、ジンメルの「都市論」もなかなかおもしろい。
「マンハイムによれば、教養文化とは、都市において形成される、『ある特定の狭く限定された生活共同体とその存在上の拘束性から、相対的にみて、独立したものとなった文化』(三一九)である。都市には、さまざまな生活共同体の人々が流入し、それにともなってさまざまな文化的傾向やその萌芽が流入する。ただそこで生じる教養文化自体から、新しい文化的傾向が生み出されることはない。教養文化は、既存のさまざまな生活共同体の文化的傾向から成るいわばポリフォニーによって構成される。この意味で、『教養文化もまた自由不動的ではない』。しかし他方、教養文化において、さまざまな文化的傾向は、それが生じてきた生活共同体から相対的に見て解き放たれている。」
澤井敦「カール・マンハイム」、東信堂,84P
前近代的な教養と近代的な教養
前近代的な教養:特定の階層によって独占される教養。たとえば貴族だけに独占される教養などが挙げられるかもしれない。平民にはどうせ芸術はわからない、というような対立というより排他的な態度に近い。
近代的な教養:社会という場面で衝突しあうさまざまな意志や傾向の縮小版。たとえばお金持ちも庶民も、政治家も商人も農家も、さまざまな価値観をもって衝突したり、共有したりしている。こうした多様な価値観、立場の衝突をマンハイムは「生き生きとした抗争」と表現し、多様な視野の可能性として捉えている。
知識人と「行動」や「現実」との関連について
1:知識人は自己満足に終始したり、自分たちを無力で余分な存在であり、価値がないと思ったりするべきではない。また、概念や理論だけで真理をつかんだと信じきることや、言葉遊びに終始するべきではないという。
2:知識人は組織や党派に自ら「参加」していくべきだという。たとえば政治団体や利益団体、その他の組織に一切関わらず、孤独に内にこもる態度が教養というわけではない、という話。
3:ただし、組織や党派に参加しつつも、自らを完全にアイデンティファイするべきではないという。
たとえば、自分の主張と違っても自分の所属する政党の主張に自分の主張を必ず合わせていく、というような態度をとることは好ましくないといえる。
かといって、自分の主張と違うからと言って相手の主張を断固拒否するという態度でもない。柔軟に、相手の立場にたって、なぜそのような主張をするのかというような社会的条件なども含めて考え、より視野を広げて、総合的に考えていくような態度が必要とされている。
4:「現実」に背を向けるのではなく、自らの時代の「文化」へとかかわっていくことが必要だという
マンハイムは文化は「個々人相互のコミュニケーションを可能にし、それによって人々の連帯を生み出す役割をになっている」という。
「現実」を重視するという点は、フッサールが学問の危機を唱え「直観」を重視していく姿勢とも重なっていく。
「たとえば、一九三〇年の『一般社会学』講義や、一九三二年の『インテリゲンチアの社会的及び政治的意義』において、マンハイムは、知識人にたいして、自己満足に終始したり、自分たちを無力で余分な存在だと蔑んだりするだけでなく、むしろ、組織や党派に自ら参加していくべきだと呼びかける。ただ同時に、マンハイムは、そうした組織や党派と、自らを完全にアイデンティファイするべきではない、とも述べる。組織や党派のうちにあっても、知識人は、いきいきとした思考の自由を維持すべきであるし、実験的な態度において、さまざまな視野の可能性を施行し、視野の拡大につとめるべきである。」
澤井敦「カール・マンハイム」、東信堂91P
「神秘主義に共感しつつも、マンハイムはそれを全面的に肯定していたわけではない。先に述べた精神科学自由学院の開講講義、『魂と文化』において、彼は、神秘主義が時として帯びる『現世逃避的』な傾向を批判している。自己のの内面に沈潜し、内側にこもることで、結果として現実に背を向けるのではなく、自らの時代の文化へとかかわっていくことの必要性をマンハイムは説く。マンハイムによれば、文化は、本来、個々人相互のコミュニケーションを可能にし、それによって人々の連帯をうみだす役割をになっている。」
澤井敦「カール・マンハイム」、東信堂10P
知識社会学における三段階の過程について
知識社会学の手法:・存在被拘束的な認識(知識)の一面性、部分性を克服すること
保田卓さんによれば、マンハイムの知識社会学の手法には3つの過程があるという。
1:距離化の過程
認識主体が自分の属する特定の歴史的・社会的状況からいったん距離をとり、他の状況に身を置いてみることによって、はじめの認識の自明性を疑うことができるというもの。
フッサールのエポケー(判断保留)に似ているところがある。実際、マンハイムは現象学を学んでいた。
2:関係づけの過程
認識主体は、距離化によって自明性を失った認識と、その認識を規定している状況との関係を見出すことにより、その認識の部分性を明るみに出すことができるというもの。
ジンメルの「形式社会学」に似ている。形式社会学とは、「社会を個人間の心的相互作用としてとらえ、その諸形式を対象とする学問」のことである。マンハイムはジンメルに学んでいるという点も重要。
3:総合の過程
個々の存在披拘束的認識の部分性を暴露するだけでは、部分的・一面的な認識が並立的に存在するという状況を生み出すのみである。しかし、複数の認識が同じ対象に対してもつ見方やそれぞれの認識によってしか捉えられない事象を一つの枠組の中で整序していくことでより全体的な認識を得ることができる。
ヘーゲルの「弁証法」に似ているところがある。ヘーゲルは肯定すべき概念の定立(テーゼ)と、その概念を否定するような定立(アンチテーゼ)があり、この2つの概念を統合する概念として「総合定立(ジンテーゼ)」というものを考えている。弁証法が繰り返し行われていくことで認識が深まる、という構造と似ている。ただし、ヘーゲルのように絶対者の存在、いわゆる「絶対精神」というものをマンハイムは念頭に置いていないという差異がある。あくまでもマンハイムの目的は、視野の増大であり、より全体的な認識の獲得である。マンハイムはマルクスを学んでいたので、当然ヘーゲルにも通じていると思われる。
「マンハイムによれば,存在被拘束的な認識の前述したような一面性・部分性を克服するのが,知識社会学の方法であるという。知識社会学の方法は,要約すると次の三段階の過程を経て実行される。①「距離化」の過程:認識主体が自分の属する特定の歴史的・社会的状況からいったん距離をとり,他の状況に身を置いてみることによって,はじめの認識の自明性を疑うことができる。②「関係づけ」の過程:認識主体は,距離化によって自明性を失った認識と,その認識を規定している状況との関係を見出すことにより,その認識の部分性を明るみに出すことができる。③「総合」の過程:個々の存在披拘束的認識の部分性を暴露するだけでは,部分的・一面的な認識が並立的に存在するという状況を生み出すのみである。しかし,複数の認識が同じ対象に対してもつ見方やそれぞれの認識によってしか捉えられない事象を一つの枠組の中で整序していくことでより全体的な認識を得ることができる。この三段階の過程を不断に実行することにより,完全に全体的で普遍妥当的にはならないにせよ,認識に包括性を増大させていくことができる。」
保田卓「社会学者の立場: マンハイム, グールドナー, ルーマン」,59-60P
(3)知識人のあるべき姿について
マンハイムの知識人像
・マンハイムは知識人の理想とする姿を「自由に浮動するインテリゲンチャ」と表現している
宮台真司さんによれば、自由に浮動しなければいけない理由は、何かに帰属すると利害当事者(ステークホルダー)になるからだという。
そして普通は「中立性を保つために自由に浮動することが不可欠だ」と説明する。たとえば特定の企業のために言論活動をおこなうのではなく、忖度なしに、中立的に言論活動をおこなうために、中立的になる必要がある、という言い方である。しかし、マンハイムが言いたいことは中立性を保つためではなく、「全体性に近づくために不可欠な位置取り」だという。
全体性とはなにか、意味
全体性:・部分的な見方を自己に受けいれつつ、不断にそれを打ち破り、一歩一歩、認識の自然の歩みにつれて自己を拡大してゆく全体への志向。視野の拡大をマンハイムは重視している。
1:全体性は時代に関係なく適用可能な結論ではない。神の目のように、直接、一挙に対象を見抜くような直観ではない。
2:可能な限りの最大限の視野の拡大であり、一歩一歩進んでいくものであり、その時代ごとに行っていくべきもの
3:自然科学(実証科学)が「全体性」への関心を哲学に頼っていること、また全体の状況との接触点を失っていることをマンハイムは批判している。
4:全体性、視野の拡大、補完の開放性、実験的生活、相関主義など、それぞれ類似した意味
宮台さんによれば、マンハイムは世界の全体性(ヘーゲル)とは別に、「社会の全体性」を問題にした最初の人だという。
そして「全体性」を参照するような学問をヴィッセンシャフト(学)といい、サイエンス(科学)とは区別されるものだという。
宮台さんが区別しているこのヴィッセンシャフトとサイエンスの区別は、おそらくマートンのヨーロッパ種とアメリカ種の区別を前提としている。あるいは理論派と実証派、人文科学と自然科学とも区別されることがあり、社会学はよく中間に置かれている。
「すなわち,マンハイムにとって「全体性」とは,「部分的な見方を自己に受けいれつつ,不断にそれを打ち破り,一歩一歩,認識の自然の歩みにつれて自己を拡大してゆく全体への志向」をさす。そしてそこで追求されるものは、時代に関係なく適用可能な結論ではなく、可能な限りの『最大限の視野の拡大』である。すわち、上述したように、マンハイムは、科学が究極的価値判断をなしえないことを認める。しかし,彼の現実に対する危機意識は,科学が単に事実関係の把握にのみ止まることを許さなかった。彼は『意欲する意志』を現実化さす方途を提示せざるをえなかったのである。」
馬居政幸「「知識社会学」 再考 (1)」、8P
「マンハイムは,実証科学が「より高次」の方法という美名のもとに「全体性」への関心を哲学に明けわたし,部分認識のみにしがみついていること,他方,その役割を与えられた哲学は「より高列の領域にしがみつき,「全体の状況」との接触点を失っていることを非難する。I.U.,S.9o~91(215頁」
馬居政幸「「知識社会学」 再考 (1)」、53P
「ヨーロッパの大学の知的システムは、ヴィッセンシャフトリッヒです。『学的』とか『学問的』と訳します。アメリカの知的システムは、サイエンティフィックです。『科学的』と訳せます。ヴィッセンシャフトリッヒとサイエンティフィックの違いはどこか。ウェーバーから二、三〇年後に活躍したカール・マンハイムの『知識人』の定義が役立ちます。マンハイムは、あるべき知識人を『浮動するインテリゲンチュア』だとします。そのなかでトータリテート(全体性)という概念を出します。あるべき知的存在がフロート(浮動)しなければならない理由は、何かに帰属するとステークホルダー(利害当事者)になるからです。そうならないよう絶えずフロートする必要があるのです。普通は『中立性を保つためめに不可欠だ』と言うところですが、マンハイムは『全体性に近づくために不可欠な立場取りだ』と言うのです。マンハイムは、哲学で一般的ヘーゲル的な全体性概念──<世界>──の全体性とは別に、<社会>の全体性を問題にした最初の人だと思います。マンハイムが出した全体性という概念は、三十年後、先ほど紹介したフランクフルターが繰り返し参照する概念になります。ヴィッセンシャフトリッヒ(学)という概念は、全体性を参照しようとするオリエンテーション(志向)に裏打ちされた知的営みを指します。サイエンス(科学)という概念は、全体性という概念とはインディファレント(無関連)です。そうでなく、エクスパートが知るエクスパーティーズ(専門知識)──なかでも実証科学の方法に裏打ちされたもの──が科学なのです。だから、同じ社会学でも、ヨーロッパ的伝統と、アメリカ的伝統では、方向性が違います。」
井庭崇,他「社会システム理論」73P
「一九二九年二月に、ハイデルベルク大学において開かれたA・ヴェーバーとの合同セミナーの席上でマンハイムが述べているように、「知識社会学は、いくつかの思考の立場がイデオロギー闘争において互いに盲目になり、それぞれが唯一の真理の名のもとに対抗しあっている段階の克服を意味している」(1929b:300-1-J190)。そして、マンハイムが重要視するのは、こうした相対化をへて、各々の立場が、自らの立場に閉塞するのではなく、逆に、自らの立場の部分性を他の立場をつうじて補完することに開かれてあり、視野を拡大していくということである。『イデオロギーとユートピア』において、マンハイムは次のように述べている。「われわれの時代における・・・・・・歴史的研究の役割は、まさしくこうした一時的な必要のために余儀なくされる不可避の自己実体化をくり返し後退させ、自己神化をたえまない対抗運動のなかでくり返し相対化すること、こういう仕方で、自己を補完してくれるものにたいして開かれてあることを強いるという点にある」(1929a:40=J197)。「全体性とは、部分的な視野を自らのうちに受けいれつつ、不断にそれを越えていこうとする、全体への志向を意味するものである。この志向は、認識の自然な進行のなかで一歩一歩自己を拡大していく。そのさい目標として切望されるのは、時間を超えて妥当する最終的結論ではなく、われわれにとって可能な、最大限の視野の拡大である」(1929a:63=J217)。ここで述べられているのは、いわば、「補完への開放性」、「視野の拡大」といった、規範的要請である。すなわち、自己絶対化に向かうことなく、自己の立場の部分性を認識し、自己を相対化すると同時に、自らの部分的な視野にとどまることなく、他の視野に開かれてあり、それによって自らを補完し、自らの地平を拡大していくこと、いわば「自己相対化と自己拡張の連動」が求められることになる。こうした精神的態度のなかで、新しい社会的・政治的方向性を探り出していくことが、ここのマンハイムの基本的姿勢であった。「相関主義」や「白山に浮動するインテリゲンチア」というよく知られた概念も、このような精神的態度を体現するものにほかならない。」
澤井敦「マンハイムとラジオ」,6-7P
「「全体性とは,したがってわれわれの意味では,直接に一挙に対象を見ぬく直観によってとらえられているものではない。そういう直観はただ,神のような目にだけ期待できるだけである。〔中略〕全体性とは,部分的な見方を自己のうちに受けいれっつつ,不断にそれを打ち破り,一歩一歩,認識の自然の歩みにつれて自己を拡大してゆく,全体への志向を意味する。そこで目標としてひたすら追求されるのは,時代にかかわりなく当てはまる結論をつけることではなく,われわれにとって可能な,最大限の視野の拡大である」(Mannheim1936=1979:217)。このような考え方は相対主義とも見えるが,マンハイム自身は自らの立場を「相関主義」(relationism)と呼び,相対主義から厳に区別している。「相関主義というものは,討論においては決着はなんら存在しないことを,意味するものではなく,むしろ絶対的にではなく,立場に制約された視座構造のうちにのみ定式化しうるのだというのが,特定の陳述の本質をなすものだということを,意味するものである」(Mannheim1964=1975:320)。」
保田卓「社会学者の立場: マンハイム, グールドナー, ルーマン」,64-65P
宮台真司さんの知識人像
・宮台真司さんの知識人像
ヴィッセンシャフト:全体性を参照しようとする志向に裏打ちされた知的営みのこと。ヨーロッパ的伝統に分類される。
サイエンス:全体性という概念とは無関連な、専門知識のなかでも実証科学の方法に裏打ちされた知的営みのこと。アメリカ的伝統に分類される。社会調査などが例として挙げられる。
そして重要なのは、マンハイムの知識社会学はヴィッセンシャフトであるということである。宮台真司さんはルーマンの社会システム論がヴィッセンシャフトであるという議論を展開していくが、ここでは扱えない。
宮台さんいわく、ヴィッセンシャフトでは「全体性を十分に参照しうる能力を身につけた者だけが知的営みに関われるという共通了解」があるらしい。
そしてサイエンスのように、訓練されて方法に習熟すれば誰でもできるように、アクセスできるものだとは思われていないそうだ。たとえばゲーム理論によって現象を分析することは、習熟すれば誰にでもできる。数学のようなものだ。しかし、全体性を参照するという営みは、訓練されれば誰にでもできるようなものではないそうだ。
マンハイムが「視野の拡大」や「補完の開放性」という規範的な要請をかかげるのはわかる。しかし、実際になにをどのようにして、どういう立場を具体的にとっていくかなど、それぞれの時代、それぞれの社会によって異なる手法があり、それらを見つけ出していくのはたしかに「センス」のようななにかが必要なのかもしれない。大学受験で暗記すれば正解できるような歴史や英語の勉強の領域とは別のものが要求されてくる。
センスで思い出す話は、佐藤俊樹さんのマックス・ウェーバーとタルコット・パーソンズの比較である。
タルコット・パーソンズは理論を重視するヨーロッパ的、ヴィッセンシャフト的な人物であったが、同時にアメリカ人だった。そして、佐藤さんはウェーバーは「熟練技的な解決」であり、パーソンズは「誰でも社会について考えられるような一般理論の導入(AGIL図式)」として比較している。
「常識を上手く手放す」ことがうまくできていたのがウェーバーだったという。この手放し方を「だれでも」できるようにしたかったのがパーソンズということになる(成功したかどうかは議論がわかれている)。
宮台さんがルーマンの議論の中で、「ルーマンにとって発見的に働くツールが、他の人にとっても発見的に働く保証はない」と語っていたのが印象的だった。
また、宮台さんはマンハイムの「浮動性」にくわえて、「閉鎖性」も必要だと主張している。
今の日本ではヴィッセンシャフトよりもサイエンスよりであり、全体性を参照できる人間が減っているという。だれでも学べば習得できるようなサイエンスだけではなく、より閉鎖的なヴィッセンシャフトも必要だという話。なぜなら、知識人を支える「われわれ」、知識人が代表とする「われわれ」という関係が不足してしまうからだという。中間や下層からの知識人に対するリスペクトが減ると、全体性を参照する人間が減ってしまう。学ぼうと思えば学べるような学問ではリスペクトが減ってしまう。
「……ヨーロッパの学的伝統では、全体性を十分に参照しうるコンピタンス(能力)を身につけた者だけが学的営みに関われるという共通了解があります。これは帰属主義的とも言えますし、閉鎖的だとも言えます。訓練されて方法に習熟すれば誰にでもアクセスできるものだとは考えられていません。他方、元々はヨーロッパ的閉鎖性を嫌うエグゾダスが作った国アメリカには、ヨーロッパとは異なる知的伝統があります。閉鎖性や密教性を嫌って、できるだけ手順を明示化し、徹底的にルール化しようとする『わかる人にだけわかる』ようなものを排除するのです。ヨーロッパはむしろ逆。手順をオーバーヒート(顕在的)することで暗黙知やジェントルメンズ・アグリーメント(黙契)がスポイルされてしまうことを気にするわけです。」
井庭崇,他「社会システム理論」74P
「でも、僕自身が立っている立場は、『政治的なものについて思考するとき、ゲーム理論のドリルによって底辺を上げ、万人が共有可能なものを広げるというかたちでは、対処できない問題がある』というものです。日本は田吾作平等主義的なメンタリティが支配するので、ヴィッセンシャフトリッヒな枠組を使わないと頂点がどんどん下がってしまいます。アメリカの場合は、万人に理解できるプラットフォームを作ろうといいながら、できる人間をどんどん特別扱いして密教的な伝達へとシフトアップすることを含めて、頂点が下がらない仕組みを用意しています。ところが日本では、以前僕が『アエラ』でコメントしたとおり(笑)、『東大生が馬鹿ばかり』になっています。簡単に言えば、『全体性からますます遠ざかった輩だらけ』なのです。」
井庭崇,他「社会システム理論」76P
「逆にいえば、もし構造機能主義が正しければ、社会といわれてきた事象がどんなもので、どのように動くのかが、近似的にせよわかる。『社会が社会をつくる』しくみを解明した構造機能主義を学べば、『常識をうまく手放す』のがそれほどうまくなくても、誰でも社会について考えられる。一般理論という思想を導入することで、パーソンズはウェーバーの熟練技的な解決と逆の方向に、社会学をひっぱった。何しろ、4つの要件のみたされ具合がわかれば、社会の大きな動きがつかめるというのだから。」
佐藤俊樹「社会学の方法」203P
ロバート・マートンの知識人像
ヨーロッパ種(ヴィッセンシャフト):壮大な理論を好む人々。「われわれのいうことが真実かどうかは分からないが、すくなくとも重要な意義をもっている」と考える人たち。知識社会学者などもこの種に該当する。マンハイムやパーソンズなど。意義を事実に優先させる。仮説演繹法を重視する。哲学的な洞察から出発し、仮説をたて、理論に好都合な事実を集めて議論を組み立てる。
アメリカ種(サイエンス):実質的に証拠としての価値があるデータを集めることに重点をおく人たち。「われわれのいうことに意義があるかどうかはわからないが、少なくともそれは真実である」と考える人たち。事実を意義に優先させる。帰納演繹法を重視する。アメリカ種は経験的で確実な事実を集めていけば、いつかは重要な科学的発見に行きつくと考えている。
マートンは両者の統合を目指しているという。今回は扱えないが、興味ある人はマートンの議論を参照してみるといいかもしれない。
マンハイムの文脈で重要なのは、マートンがマンハイムをヨーロッパ種に分類し、かつその用語の定義の曖昧さについて批判しているということである。たとえば「階級階層」、「社会的政治的意義」、「進歩集団」、「ユートピア的力」、「知識」といった概念をマンハイムは使うが、厳密に定義されたり、検証可能な命題として提示されていないという。哲学的、文学的であり、魅力的な言葉ではあるが、定義することが難しいという。重要なのは「現実の社会生活で検証できるか」であり犬飼祐一さんの言葉で言えば「まるで空中戦のような議論」になってしまうという。
マンハイムは一方的に「現実」を軽視しているわけではないが、たしかに抽象的な用語、議論が多いような印象も同時に受ける。それは私がフッサールを学んでいる際も、同時に受けた印象である。現実をなによりも重視しているフッサールの議論も、難解な用語や定義、曖昧な用語の羅列によって抽象的な思弁に見えてしまいがちです。
宮台さんいわく、アメリカではルーマンの評価が低いそうだが、「アメリカ人の頭では理解できないさ」という問題にすぎないらしい。たしかにヨーロッパ的な伝統を踏まえて、デカルト、カント、ニーチェ、フッサール、フーコー等々の関連を理解し、その上で全体性にアクセスするべきだ、という言い分も理解できる。しかし一方で、アメリカ的な経験的調査や数値化も重要だという言い分も理解できる。
宮台さんはアメリカ種のものも、たとえばゲーム理論のようなものの有用さを認めている。
しかし、「ゲーム理論のドリルによって底辺を上げ、万人が共有可能なものを広げるというかたちでは、対処できない問題がある」ともいう。それが全体性へアクセスできることによって対処できる種類の問題だという話。
おそらくアメリカ種からいわせれば、曖昧でふわっとした、捉えがたい言葉として「全体性」が理解されてしまう。たしかに私も「全体性」のふわっとした意味合いしかわかっておらず、日本社会における現在の「全体性」とはなにかについて聞かれたら閉口してしまう。多種多様な学問を通じて他の人の立場や理論、事実(データ)を理解し、視野を広げ、また同時に社会に参加して現実と関連付けながら補完の開放性をめざすような実験的生活を伴って、はじめてなにか光のように解釈のヒントのようなものが得られていくものなのだと思う。
マンハイムはイギリスでは事実の収集に社会学を限定する動きがあると批判していた。
もし理論がないと、統計的調査やフィールドワークの結果は「ただの事実やおもしろい逸話の寄せ集め」になってしまうという。
マンハイムは「諸事実に歩調を合わせる理論と、理論の光の下で解釈される諸事実のみが、知識への道を開く」と述べている。ここでいう理論とは、「諸事実を解釈する枠組み」だという。また、こうした枠組みを研究することだけに没頭すればいいというのではなく、マンハイムは社会や現実へとはたらきかけていくことも重視しているという点も重要であるといえる。
「マートンによると、「〔ヨーロッパの〕知識社会学はたいてい規模壮大な理論を好む人々のやる仕事であって、彼らは精巧な思弁や印象主義的な結論を超克する可能性が差当りあるかどうかを、時には全く顧慮せずに、ただ問題が広く重要でさえあれば、専ら理論に没頭していてもいいのだと考える。大体、知識社会学者は、「われわれのいうことが真実かどうかは分からないが、少くともそれは重要な意義をもっている。』という旗印を高く掲げた人達であった」(四〇〇頁)。これに対して、「世論とマス・コミュニケーションの研究をやっている〔アメリカの〕社会学者や心理学者は、それと反対の経験主義者の陣営に多く見られ、その旗印には幾分違ったモットーが書かれている。すなわち、「われわれのいうことに特に意義があるかどうかはわからないが、少くともそれは真実である』と。ここでは一般的主題に関係のあるデー夕、換言すれば実質的に証拠としての価値があるデータを蒐集することに重点がおかれていた。しかし最近までは、これらのデータが理論的問題に対して意義があるかどうかについては殆ど関心がもたれず、ただ実際的な情報を蒐集しさえすれば、ただちに科学的に適切な事実観察を蒐集したことになる、というように誤解されていた」(四〇〇ー四〇一頁)とのことである。知識社会学は規模壮大な理論を好み、マスコミ研究者は経験主義者で、ともかく事実を収集する。ヨーロッパ系知識社会学は、意味(意義)を事実(真実)に優先させ、対するアメリカ系マスコミ研究は、意義(意味)よりも真実(事実)を優先するというわけである。科学論や科学哲学の用語で言い換えるならば、ヨ1ロッパ種は仮説演繹法を信奉し、アメリカ種は経験帰納法を信頼する。大雑把に言えば、方法がまるつきり異なっているのである。ヨーロッパ種は哲学的な洞察から出発して、「仮説」を立て、おのれの理論に好都合な事実を集めて議論を組み立てるのに対し、アメリカ種はともかくも経験的で確実な事実を集めていけば、いつかは重要な科学的発見に行き着くと考えている。」
犬飼裕一「コミュニケーション研究のヨーロッパ種とアメリカ種 上 : マートン知識社会学の研究」7-8P
「ところが、マートンの議論を注意深く観察していくと驚かされるのは、通常の場合は相互不干渉の住み分けのようになっている「ヨーロッパ種」と「アメリカ種」を、何とかして統合しようと努力していることである。マートンがいうように、両者の違いはそれぞれが発展した社会的背景ー「社会的構造」ーの違いに結びつけて論じることが可能であろう。社会理論と社会構造の関係という、それ自体が高度に知識社会学的な問題である。ただし、ここでのマートンの主題は、この種の知識社会学的な、あるいは「ヨーロッパ的な」問題ではなくて、両者を統合することなのである。当人の言葉を借りれば、「両者の科学的長所を備えながら、しかも両者の不必要な欠陥をもたない巧みな組合せを目指して、これらの関連しあった社会学的研究領域の統合を提唱すること」(四〇一頁)である。」
犬飼裕一「コミュニケーション研究のヨーロッパ種とアメリカ種 上 : マートン知識社会学の研究」9P
「ただ、イギリス社会学をも含めた当時のイギリスの学問的趨勢は、マンハイムからみると、必ずしも満足のいくものではなかった。たとえば、一九三六年におこなわれた公園の記録である『人間の価値判断の社会学的性質における若干の具体例』において、マンハイムは、イギリスでは事実の収集に社会学を限定しようとする動きがあるが、理論がないと、統計的調査やフィールドワークの結果は、ただの事実やおもしろい逸話の寄せ集めになってしまうと述べる。マンハイムにいわせれば、『諸事実に歩調をあわせる理論と、理論の光の下で解釈される諸事実のみが、知識への道を開く』(236)。ここでいう理論とは、抽象的な一般論図式というよりは、むしろ、諸事実を解釈する枠組みとなる。社会の状勢・動向に関する理論である。そしてこうした理論への要請は、とりわけ第二次大戦開戦以降、マンハイムにおいて、狭義の学問の制度的枠組みのなかにとどまらず積極的に社会へとはたらきかけていこうとする指向と結びあわされていく。諸事実についての知識を基礎として、社会全体の動向を診断する理論的領野を開き、さらにはそれをもって積極的に処方箋をしめしていこうとする指向は、マンハイムにおいてこれ以降、ますます強くなっていく」
澤井敦「カール・マンハイム」、東信堂,36-37P
マックス・ウェーバーにおける知識人像とは
1:マックス・ウェーバーは『宗教社会学』で「知識人」とはなにかについて書いている
2:マックス・ウェーバーによれば、「知識人」は日常を幸せに生きられないという。日常を幸せに生きられない人の多くは宗教に行くが、たまたま行かなかった学問の世界に行くという。
3:宮台真司さんは、こうした知識人を「超越系」と呼び、日常を幸せに生きられる人を「内在系」と呼んでいる。
「マックス・ウェーバーが『宗教社会学』という本で『知識人』とは何かを書いているんです。彼によれば『知識人』は日常を幸せに生きられません。日常を普通に生きるだけでは幸せになれないのです。ボクはこういう人たちを『超越系』と名付け、逆に、日常を幸せに生きるだけで幸せになれる人を『内在系』と呼びます。ウェーバーは一〇〇年ほど前に生きた人ですが、彼によれば、僕が超越系と呼ぶ『日常を生きるだけでは幸せになれない人』は大方宗教に行くのだが、たまたま宗教に行かなかった場合に学問の世界に行くのです。これがウェーバーの『知識人』定義になるんです。わかりやすく言えば、知識人とは、超越系なのに宗教に行かなかった人がする営み。それが学問です。」
井庭崇,他「社会システム理論」72P
【コラム】ベイトソンと知識像
最後に、モリス・バーマンやグレゴリー・ベイトソンとの関連について少しだけ触れて終わる。
個人的な関心であり、詳細には説明できず、忘備録に近い。
1:バーマンは相対主義のような結論、つまりあれもこれも等しく真であり、絶対の真理など存在しないというような結論に至らないような方法を探している。
2:バーマンはそのような相対主義を「根底的相対主義」と呼び、近代科学が採った特異な態度から生じていると分析している。特に16世紀の「科学革命」が念頭に置かれている。社会や経済が変化したから、そのような認識(相対主義的なもの)が生じたのではないか、という話。
3:バーマンは近代以降のパラダイムを「デカルト的パラダイム」と呼ぶ。あるいは「デカルト的二元論」という言葉で表現されている。
4:バーマンはこのような「デカルト的二元論」を超えるためには、ベイトソンの「全体論」が重要だと考えている。全体論は関係がまずはじめにある、全体は部分にはない特性をもつ、というような主張(他にもサイバネティクスなど重要な概念がたくさんあるが、今回は扱えない)。
重要なのは、近代科学は自らの近代科学を分析するような能力はないという点である。科学の有効性を分析する科学自体の有効性はいったいどのように保証されるのか。社会学の有効性を分析する社会学自体の有効性はどうなるのか。バーマンは「その方法を方法自体に適用してもその有効性が崩れないような体系」が求められているという。さきほどのマンハイムのパラドックスとも関連する問題である。また、バーマンは自然科学における知識の被拘束性については「英雄的とも言える頑固さで生涯見ようとしなかった」と批判している。
5:社会だけ、人間の知識だけではなく、その両者の「(拘束)関係」を考えていこうとするマンハイムとベイトソンは通じている。
あるいはフッサールの志向性、つまり意識作用と意識内容・対象との関係を考えていこうとすることとも通じている。
いずれの場合も「関係(相関)」や「コンテクスト」、「相互作用」などがキーワードになっていく。
5:マンハイムは個々の文化領域の構造を分析し、その結果を総合することをつうじて、「新しい形而上学」が出現することを期待していた
6:バーマンはベイトソンの全体論を「新しい形而上学」と表現している。
つまり、新しい形而上学をベイトソンの文脈で考えたうえで、知識の社会学の位置づけや方法論を考えていくのも面白そうだという話。
「さて、これまで私はゲシュタルト理論の立場から論を進めてきた。事実とは流動的な、理論的枠組によって『作られる』ものであり、その枠組自体もまた、社会・経済的文脈との関係から出てくるものなのだ。科学革命とその方法論もまた、より大きな歴史の流れの一部分であるという視点から論じてきたわけである。とすれば、ここで我々は我々を不安に陥れずにおかないひとつの問いに直面する──世界の本質は、文化の構築物にすぎないのだろうか?ガリレオのさまざまな発見は、不動の科学的データなどではなく、ひとつの局部的現象にすぎない世界観の産物以上のものではないのだろうか?いままでの分析が暗示しているように、もしその答えがイエスだとすれば、我々は、根底的な相対主義の海をさまよう漂流者ではないか。絶対の真理などどこにも存在せず、あるのはただ、あなたの真理、わたしの真理、この時の真理あの場所の真理だけではないのか。知識社会学と一般に呼ばれる学問が示唆しているのは、まさにこのことである。知識と意見、科学とイデオロギーとの間の区別は消滅し、何が正しいかは多数決の問題、『群集心理』の問題にすぎなくなる。客観的知識がどこにも存在せず、すべての基礎をなす不動の現実という概念も無効であるとすれば、近代科学であれ占星術であれ魔術であれアリストテレスであれマルクス主義であれ、すべては等しく真である、というわけだ。このような結論に至らないための方法はないのだろうか?この問いに対する私の答えはこうである。根底的相対主義は、序章で触れた『参加する意識』に対して近代科学が採った特異な態度から生じるのである。とすればまずは必要なことは、参加する意識とは何かを詳しく検討することだろう。そのためには、知識社会学を頼りに、科学革命の物語における、忘れられた一章に光をあてなければならない。すなわち、オカルトの世界に。」
モリス・バーマン「デカルトからベイトソンへ」,68~69P
「『世界についてのあらゆる認識、知覚、知識につはつねに「参加」が入り込んでいることをひとたび認めれば、根底的相対主義の問題は自然に消滅するはずである』この根底的相対主義の問題は、以下のように要約することができる。科学的方法は、一見、反駁不可能な法則や事実を発見するように見える。たとえば重力、投射体運動を規定する方程式、惑星の楕円軌道といったように。しかし歴史を振り返れば、その方法は近代初期のヨーロッパ固有の社会・経済的プロセスのイデオロギー的一面にすぎないのであり、その方法によるさまざまな発見にも同じことが言えるのである。カール・マンハイムの言うように、すべての知識は『状況に束縛された』ものであるとすれば(いわゆる『存在被拘束性』)、ひとつの概念体系が他のいかなる体系よりも認識的に優っていると主張することは難しい。科学もまた例外ではありえない。このような視点から、第二章において私は、歴史のある『時期にのみ適切な思考体系として科学を捉えることの必要性を論じ、科学が何か絶対的な、文化の枠組みを超えた真理であるという思い込みを捨てなければならないと説いた。こうした議論をつきつめれば、固定した現実、すべての土台となる真理などというものは存在せず、あるのは卒愛的な真理、言い換えれば知識を生み出した環境に見合った知識でしかない、ということになるだろう。こうして、歴史科学・社会科学の方法を用いて科学自体を分析することによって、科学の有効性が問われることになる。だがさらに具合の悪いことに、科学の有効性に疑問符をつきつける歴史的分析それ自体もまた、その有効性を問われなければならないことになってしまうのである。科学に限らず、ある概念体系がこうした逆説的・自己破壊的な結果を回避するにはどうしたらよいのか?この逆説から逃れうる認識論とは、自然と人間との関係において内在的な真理もしくは秩序が存在することを証明できるものでなければならず、また、自己分析によって崩壊しないものでなければならないだろう。言い換えれば、その方法を方法自体に適用してもなおその有効性が崩れないような体系でなければならないのだ。」
モリス・バーマン「デカルトからベイトソンへ」,165P
今回の主な文献
カール・マンハイム「イデオロギーとユートピア」
※私が使っているのは旧訳です
澤井 敦「カール・マンハイム―時代を診断する亡命者 (シリーズ世界の社会学・日本の社会学) 」
澤井 敦「カール・マンハイム―時代を診断する亡命者 (シリーズ世界の社会学・日本の社会学) 」
汎用文献
佐藤俊樹「社会学の方法:その歴史と構造」
大澤真幸「社会学史」
新睦人「社会学のあゆみ」
本当にわかる社会学 フシギなくらい見えてくる
アンソニー・ギデンズ「社会学」
社会学
社会学 新版 (New Liberal Arts Selection)
クロニクル社会学
社会学用語図鑑 ―人物と用語でたどる社会学の全体像
参考論文
前回の論文リストは以下の記事の最下部にリストアップしています。
【基礎社会学第三十一回】カール・マンハイムの「イデオロギー」とはなにか
基本的に前回と引き続き、同じ論文を参照しています。
以下、新しく追加、あるいは特に今回多く参照したものです。
1:保田卓「社会学者の立場: マンハイム, グールドナー, ルーマン」(URL)
2:木村光豪「グローバル・サウスと人権:「人権のヴァナキュラー理論」の可能性(2)」(URL)
→相関主義の定義の参考に
3:山田隆夫「カール・マンハイム研究(4):《イデオロギーとユートピア》《インテリゲンチヤ》《現代の診断》《エピローグ》」(URL)
→知識人における「相対性」とはなにか、教養とはなにか、全般的なマンハイム知識について
4:立花希一「 相対主義と相対化主義 」(URL)
→カール・ポパーによる相対化主義について参考に
コメント
この記事へのトラックバックはありません。

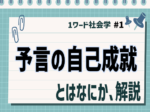
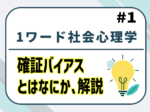
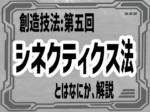
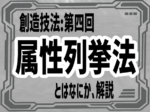
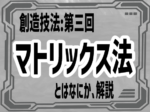
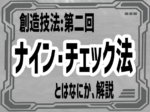



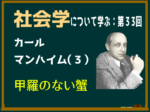

この記事へのコメントはありません。