- Home
- マックス・ウェーバー, マルティン・ルター
- 【社会学】マルティン・ルターの天職思想とはなにか
【社会学】マルティン・ルターの天職思想とはなにか
- 2021/7/25
- マックス・ウェーバー, マルティン・ルター
- コメントを書く
Contents
はじめに
この記事の目的
この記事の個人的な目的はマックス・ウェーバーの「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」を理解することにあります。その理由は、創造につながると私は考えるからです。
この著書の中にマルティン・ルターが登場するので、マルティン・ルターを理解する必要があったのです。したがって、私の関心はこの著書との関連においてのマルティン・ルターということになります。
つまり、マルティン・ルターの思想の中でも「天職思想」が関心の中心となり、理解するべき要素となります。
私は要旨をまとめ、できるだけ自分の言葉で(これが難しい)記事にすることで知識をその血肉とすることを目指します。また動画にすることで、耳でもまた理解を促し、その記憶の定着を目指します。マックス・ウェーバーの書籍の翻訳は難しい言葉が多いです。より平易な言葉で説明し、理解をすこしでも易しくすることをめざします。あるいはその補助資料を付け加えたいです。
引用以外の、歴史等の客観的な事実は基本的にWikipediaから情報を取得しています(例えばマルティン・ルターの経歴など)。
この記事の要約
- ルターにおける天職とは:「世俗的な職業」と「神の召命」という2つの意味合いがある言葉。ルターの聖書翻訳をきっかけに生まれた。
- ルターの天職思想とは:「世俗的な職業における労働」こそ唯一、宗教的な価値があり、それのみが「神の召命」と考えること
- 資本主義の精神へとの関連について:「世俗内禁欲(天職義務)」に影響を与え、それが資本主義の精神へとつながった。
動画での解説・説明
・この記事のわかりやすい「概要・要約・要旨・まとめ」はyoutubeの動画の冒頭にありますのでぜひ参照してください。
よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m
ぜひチャンネル登録をよろしくおねがいします。励みになりますm(_ _)m
マルティン・ルターの天職思想とは
マルティン・ルターとは
・マルティン・ルター(Martin Luther、1483-1546):ドイツの神学者、聖職者。ローマ・カトリック教会を批判した。プロテスタントを誕生させるきっかけとなる宗教革命の中心人物。1517年に『95ヶ条の論題』をヴィッテンベルクの教会に提出する。内容は主に贖宥状(しょくじゅうじょう)の濫用についての批判である。日本では免罪符とも呼ばれている。
天職という言葉の意味と翻訳の問題について
まず大前提として、マルティン・ルターはドイツ語のベルーフ(Beruf)という言葉を使っています。このベルーフが日本語で「天職」と訳されているわけです。しかし、別の翻訳ではベルーフが「職業」と訳されることもあります。
──実は、このBerufには梶山力訳以来、そしてわれわれの前回の翻訳でも、『職業』という訳語を当ててきました。それは、日本語にはBerufとまったく意味内容を同じくするような語がないためで、したがってできるだけ誤解を防ぐためにもと、その周辺にさまざまな意訳を加えて参りました。が、しかしどうしてもかなりの重要な誤解を伴わないわけにはいきませんでした。それで、今回は思い切ってBerufに『天職』の訳語をあててみることにしました。この方が誤解を少なくするだろうと考えたからです。
(「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」、398P、マックス・ウェーバー、大塚久雄訳、岩波文庫、1989初版、2006年(第39版))
翻訳者の大塚久雄によれば、ドイツ語のベルーフの意味と合致する言葉が日本語にはないそうです。
ベルーフ(天職)という言葉の意味について:日本における天職との違いとベルーフの意味合いの起源
「さて〔「職業」を意味する〕ドイツ語の「ベルーフ」》Beruf《という”語”のうちに、また同じ意味合いをもつ英語の「コーリング》calling《という語のうちにも一層明瞭に、ある宗教的な──神からあたえられた”使命”(Aufgabe)という──観念がともにこめられており、個々の場合にこの語に力点をおけばおくほど、それが顕著になってくることは見落とし得ぬ事実だ。しかも、この語を歴史的にかつさまざまな文化国民の言語にわたって追求してみると、まず知りうるのは、カトリック教徒が優勢な諸民族にも、また古典古代の場合にも、われわれが〔世俗的な職業、すなわち〕生活の地位、一定の労働領域という意味合いをこめて使っている》Beruf《「天職」という語と類似の語調をもつような表現を見出すことができないのに、プロテスタントの優勢な諸民族の場合には”かならず”それが存在する、ということだ。さらに知りうるのは、その場合何らか国語の民族的特性、たとえば「ゲルマン民精神」の現れといったものが関与しているのではなくて、むしろこの語とそれがもつ現在の意味合いは”聖書の翻訳”に依存しており、それも原文の精神では”なく”、翻訳者の精神に由来しているということだ。
ルッタ-の聖書翻訳では、まず『ペン・シラの知恵』〔旧約聖書外典中の一書〕の一箇所(十一章二○、二十一節)で現在とまったく同じ意味に用いられているように思われる。その後まもなくこの語は、あらゆるプロテスタント諸民族の世俗の用語の中で現在の意味をもつようになっていったが、それ以前にはこれら諸民族の世俗的文献の”どれ”にもこうした語義の萌芽はまったく認められ”ない”し,宗教的文献でも、われわれの知りうるかぎり、ドイツ神秘家の一人のほかにはそれを認めることができない。この神秘家がルッタ-に及ぼした影響は周知のとおりだ。」
(「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」、95-96P、マックス・ウェーバー、大塚久雄訳、岩波文庫、1989初版、2006年(第39版))
マックス・ウェーバーがいうには、ベルーフというドイツ語はもともと職業という意味をもっていたそうです。このベルーフに、神から与えられた使命(Aufgabe,アウフガーベ)という意味合いが含まれるようになったそうです。
日本では「職業」と聞くと、医者、会計士、会社員、自営業、公務員等々といったイメージですよね。つまり世俗的なイメージをもつはずです。世俗的とは英語では「Secular」ともいいます。その意味には「(霊的な と区別して)俗界の、世俗、現世の、(宗教的な と区別して)非宗教的な、宗教と関係のない、修道院に住まない、教区付きの」とあります。
つまり、世俗的とは、非宗教的な意味合いがあるということです。それに対し、「神の召命」は宗教的な意味合いがあります。
つまり、ベルーフという言葉の中に、非宗教的な意味合いの世俗的な労働と、宗教的な意味合いの神の召命という2つの意味合いがあることになります、天職という言葉は、天(神の召命)の職(世俗的な職業)という意味合いで翻訳されたのだと思います。たしかに職業、あるいは神の召命と翻訳するよりはわかりやすいです。
ただ、日本で「天職」というと”一般には”「この仕事をするために生まれてきた!と思えるような職業」というような意味で使われます。自分の性質にぴったりと合うというように多くの場合使われ、宗教的な意味合いは薄いです。ある人が自分の天職は漫画家だ!と表現した場合に、神からこの仕事を使命として与えられているという思想が含有されていることは少ないと思います。
つまり、日本において「天職」という言葉は非宗教的な意味合いで使われることが多いということです(私の主観ですが)。日本では天職という言葉が、自分に合った世俗的な労働という意味で使われるケースが多いということです。
日本では「マジ神ゲー」といった言葉を使う際に、そこに宗教的な意味合いを込めるケースは少ないですよね。すごい面白い、すごい優れているという比喩として使われるはずです。それと同じように天職も使われているのだと思います。
しかし、マルティン・ルターにおいてはこうした意味合いとは違います。比喩ではないのです。また上記に引用した文章にある通り、マルティン・ルターが聖書を翻訳する以前は、ベルーフという言葉には元々世俗的な職業という意味合いしかありませんでした。つまり、マルティン・ルターが聖書を翻訳する際に、初めてベルーフという言葉に世俗的な職業と神の召命という2つの意味が含まれるようになったということになります。
すこしややこしいですね。ドイツ語でBerufはもともと「世俗的な職業」を意味していました。そこからルターが翻訳の過程でBerufという言葉に「世俗的な職業」という意味合いだけではなく、「神の召命」という意味合いを付け加えたということです。ドイツ語では「世俗的な職業」もBerufといい、マルティン・ルター的な「世俗的な職業+神の召命」もBerufといいます(プロテスタント諸民族の間では特に)。しかし日本語では「世俗的な職業」を職業といいますが、「世俗的な職業+神の召命」を職業とはいいません。また、「世俗的な職業+神の召命」を天職とも言わないのです。マルティン・ルター的なBerufを職業と訳すことも、天職と訳すことも本来は誤りだということです。どちらも誤解が生じる可能性があると翻訳者自身が言っていました。
マルティン・ルターのベルーフ思想とでもいっておけばいいのかもしれません。
マルティン・ルターの天職思想とは
それはともかく、次の一事はさしあたって無条件に新しいものだった。すなわち、世俗的職業の内部における義務の遂行を、およそ道徳的実践のもちうる最高の内容として重要視したことがそれだ。これこそが、その必然の結果として、世俗的日常労働に宗教的意義を認める思想を生み、そうした意味での天職(Beruf)という概念を最初に作り出したのだった。つまり、この『天職』という概念の中にはプロテスタントのあらゆる教派の中心的教義が表出されているのであって、それはほかならぬ、カトリックのようにキリスト教の道徳誡(どうとくげん)を》praxepta《「命令」と》consilia《「勧告」とに分けることを否認し、また、修道的禁欲を世俗的道徳よりも高く考えたりするのではなく、神によろこばれる生活を営むための手段はただひとつ、各人の生活上の地位から生じる世俗内的義務の遂行であって、これこそが神からあたえられた「召命」》Beruf《にほかならぬ、と考えるというものだっ
ベルーフ(天職)という言葉の中に、世俗的な職業と神の召命という2つの要素の意味合いがあることは先程触れました。次は、この2つがどのような関係にあるかということがポイントです。
ウェーバーによれば、「世俗的日常労働に宗教的意義を認める思想」が天職思想(天職概念)だそうです。
普通に解釈しようとすれば、非宗教的な行為にこそ、宗教的な意義があると一見矛盾したように見えます。マルティン・ルターは世俗的な職業における義務の遂行、つまり世俗的な労働にこそ宗教的な価値があり、それこそが神からあたえられた使命(召命)だと考えたのです。世俗的な職業内の労働が唯一、神によろこばれるとまでいっています。宗教的な労働、たとえば”宗教的禁欲”のようなものは価値がないということになりますよね。宗教的な労働といよりも、修道院の生活のようなイメージです。一般的な価値観では、教会の神父さんを「職業」としてあまり捉えていないのではないでしょうか。むしろ職業の対置にあるような感覚が私にはあります。ボランティアとは違いますが、対価を得るためではなく、神に仕えるために、神のために、神の召命によってといったイメージがあります。
マルティン・ルターが宗教革命を行った当時は「贖宥状(しょくゆうじょう)」とうものが濫用されていました。日本ではよく「免罪符」という言われ方をしますが、罪が免じられるのではなく、罰を免じたものです。罪は改悛(かいしゅん)、つまり過ちを認めて心を入れ替えることによって免じられます。それに対して、罰は「善行」によって免じられるそうです。「善行」は祈り、断食、献金などです。
マルティン・ルターはこのような贖宥状の現状にたいして反発し、宗教革命を起こしました。宗教革命は教会による信徒への締め付けがきついことによるものではなく、緩いものによるものだといえます。たしかにお金を払えば罪が免じられるというのは緩いしめつけですよね。
マルティン・ルターは『ドイツ国民のキリスト教貴族に与う』にてカトリックについて以下の批判を行っている。教皇、司教、司祭、修道士たちは教会的身分で王侯、貴族、手工業者、農民などは世俗的身分と偽りの区別を行っているが、キリスト教徒はすべて教会的身分に属するのであって互いに職務上以外の面からは区別されない。コリントの信徒への手紙一12章12-13節にあるようにおのおのが固有のわざをもっていて、それによって奉仕し合う関係である。また、万人祭司はペトロの手紙一2章9節、ヨハネの黙示録5章9-10節からも支持されるとしている。司教による聖職者の叙品は同じ権能を持つ人々の集まり全体の代理として選び出し、権能の行使を委ねることである。
プロテスタントの教理のひとつである「万人祭司( the universal priesthood)」というものを知っておくといいかもしれません。プロテスタントではカトリックのような「聖職者」の役割や呼称がないそうです。かわりに教職者(牧師)という存在はあります。万人祭司とあるように、教皇などの特別な身分の人間だけが聖職者なのではなく、全員が祭司(聖職者)だということですね。修道院の生活、つまり非世俗的な行為には道徳的な価値がないと考えるルターにとって、宗教的身分といったものは愚かなものなのかもしれません。教皇、司教、司祭、修道士といった教会的な身分の区別をするべきではなく、職業的区別(百姓、鍛冶屋等)のみをするべきだとルターは言っています。
マルティン・ルター以前の労働に対する価値観
最初ルッタ-は徹頭徹尾、たとえばトマス・アクイーナスに代表されているような中世の支配的な伝統にしたがって物事を考えていたので、世俗的労働は、神の意志によるものだが被造物的で、飲食と同じく信仰生活の不可欠な自然的基礎だとしても、それ自身としては道徳に関わりのないものだとしていた。ところが、彼の》sola-fide《「信仰のみ」の思想がますます明白な形に徹底化され、その結果として『悪魔に口伝えされた』カトリック修道士の『福音的勧告』に対する反対がいよいよ鋭く強調されるとともに、世俗内的職業のもつ意義はいよいよ大きなものになっていった。修道院にみられるような生活は、神に義とされるためにはまったく無価値というだけでなく、現世の義務から逃れようとする利己的な愛の欠如の産物だ、とルッタ-は考えた。それどころか彼は、世俗の職業労働こそ隣人愛の外的な現れだと考えたのだが、しかしその基礎づけはおそろしく現実ばなれしたもので、とくに分業は各人を強制して他人のために労働させるということが指摘されていて、有名なアダム・スミスの命題に比べると奇怪なほどの相反を示している。
(「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」、110P-111P、マックス・ウェーバー、大塚久雄訳、岩波文庫、1989初版、2006年(第39版))
そもそもルター以前には世俗的な労働はどのような価値として認識されていたのでしょうか。ウェーバーはルター以前の労働に対する認識を、「中世の支配的な伝統」としています。どのような伝統かというと、世俗的労働はそれ自体としては道徳に関わりのないものという価値観です。
ルターも初期の頃は、このような伝統を受け入れていたようです。ルターが生きていた時代も中世であり、ルターの時代ではそのような認識が一般的だったと言えます。ルターの天職思想では、むしろ世俗的労働こそが唯一道徳に関わりのあるものです。正反対の価値観ですよね。
「信仰のみの思想」というのもポイントだと思います。ルターはとにかく信仰を重視した人です。信仰を重視する思想は、信仰義認(しんこうぎにん,by faith alone)ともいわれます。プロテスタント信仰において重要な原理のひとつであり、宗教改革の三大原理(聖書のみ、恵のみ(万人祭司)、信仰のみ)の一つです。
信仰義認は行為義認の否定であります。行為義認とは、善行によって神は人を義とするという考えです。カトリックにおける善行には献金も含まれ、その例が先程出た「贖宥状(免罪符)」でした。人は善行ではなく信仰によってのみ義とされるという思想です。義(ぎ,justice)とされるとは、神の目の前で正しくあるということです。抽象的ですいません。禁欲的な生活(非世俗)や善行(行為)によって義と認められるという認識が中世では一般的でしたが、ルターはそれを否定したのです。そのような認識の転換は「塔の体験」ともいわれるそうです。
それにしても「修道院にみられるような生活は、神に義とされるためにはまったく無価値というだけでなく、現世の義務から逃れようとする利己的な愛の欠如の産物」というのは凄まじい批判ですね。労働しないで偉そうに禁欲的な修道生活を送っているだけじゃないか!働け!といったようにも聞こえます。「労働が現世の義務」というのは日本の憲法における三大義務(教育、勤労、納税)とも似ていますね。
天職思想と禁欲との関係について
キリスト教的禁欲とは
ウェーバーがこの『キリスト教的禁欲』を、別の個所では『行動的禁欲』(aktive Askese)というふうに呼んでいますが、このことがよく示しているように、我々日本人が想像しがちな禁欲ではなくて、たいへん”行動力を伴った”生活態度あるいは行動様式なのです。ちょうどパウロが新約聖書に収められていrう彼の手紙のなかで、自分たちの日々の伝道生活の営みをオリンピックのマラソン競走にたとえている、あれです。他のことがらへの欲望はすべて抑えてしまって──だから禁欲です──そのエネルギーのすべてを目標達成のために注ぎ込む、こういう行動様式が行動的禁欲なのです。この行動的禁欲は歴史上キリスト教のなかではじめて生まれてくる。まず、カトリックの修道院生活のなかで、ギリシャ的な合理的思考という要因をも加えながら、しだいに成長し、ひとまずそこでほぼ完成された姿にまで到達した、あの『祈りかつ働け』の死そうです。
※本文ではなく、大塚久雄さんの訳者解説の引用です
(「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」、400-401P、マックス・ウェーバー、大塚久雄訳、岩波文庫、1989初版、2006年(第39版))
訳者の解説がものすごくわかりやすくて助かるので、引用しておきます。たしかに禁欲といえば、”何かをしないこと”というイメージがすごく強かったです。キリスト教的な禁欲は、行動的禁欲なんですね。
禁欲によって、宗教的な理想を実現するという試み自体は古くからさまざまな宗教でみられるそうです。たとえば仏教の僧院でも断食などを行います。いわゆる煩悩(ぼんのう)を否定し、解脱に至るというものです。「なにかをしないこと」によって「なにかを実現する」という論理ですよね。キリスト教的な禁欲は「なにかをしないこと」によってエネルギーを蓄え、「本当に大事なことをする」ことで宗教上の理想にたどりつくということかもしれません。
すなわち、非行動的な態度ではなく、行動的な態度なのです。禁欲は手段のための手段という2次的なものかもしれません。たとえば小麦と米を両方作りたいと思っている農家がいたとします。しかし、どちらかしか生産できないとします。農家は小麦を作りたいという欲を抑え、米を作ることにしました。なにかを禁欲することで、他のなにかの行為に集中できるのです。こうした態度は非行動的な態度というより、行動的な態度ですよね。
何かを買うために貯金などの節制をする、これも行動的な禁欲です。しかし、ただ何も買わないようにして節制をするのは非行動的な禁欲ですよね。
卑近なたとえ話があまりうまくできずにすいません。しかしなんとなくイメージはできますよね。仏教でも解脱するために断食をするわけですが、解脱をするというのはある意味では状態であり、行為では有りません。断食を行い、エネルギーを蓄え、解脱という行為に集中するわけでは有りませんよね。断食などの行為をしないことで、ある状態(解脱など)へと至るわけです。
ところでキリスト教でも断食を行いますが、かわりにどういった行為をしていたか気になりますよね。先程の引用文で言えば「祈りかつ働け」です。祈ること、働くことは「行為」ですよね。
プロ倫の文脈で言えば、利益の増大といったような欲望を抑え(禁欲)、ひたすら働くこと(行為)へと集中させていったということになります。禁欲を行い、ひたすら労働するとお金が余りますよね。そうしたお金はピューリタンなどは自分たちでお金を使わずに、寄付などをしていたそうです。またそうしたことが「救いの確信」ともつながったそうです。
しかし労働の合理化が進むと、利益(お金儲け)が倫理的な義務として扱われるようになっていきます。利益を出さないと経営は続けられないですよね。また利益を出さないとお金が余りません。そうすると「救いの確信」が得られません。もともとキリスト教的な禁欲は反営利的な性格をもっていましたが、資本主義の発達や合理的産業経営を土台にして、営利と結びついてしまったのです。
禁欲を行い、労働に集中することが神に救われたという確信につながって言ったわけですが、労働に集中するためには利益が必要になり、利益こそが大事だという発想(資本主義の精神)へと変わっていってしまったのです。
歴史概略
| 年代 | 内容 |
|---|---|
| 1517年 | マルティン・ルターらによるカトリック教会の改革を求める宗教改革運動 |
| 1524年 | ドイツ農民戦争が勃発。マルティン・ルターは最初は農民の反乱を支持していたものの、鎮圧の側に回り、地方の農民の支持を失い、彼らの間ではカトリックが主流となる。領主階級はルター派を支持するようになる。 |
| 1529年 | ルター派の諸侯や都市が神聖ローマ帝国皇帝カール5世に対して宗教改革を求める「抗議書(プロテスタティオ)」を送る。 |
| 1541年 | スイスでも宗教改革運動が起こる。ジャン・カルヴァンがスイスにおける宗教改革者となり、カルヴァン主義を形成する。 |
| 1555年 | アウクスブルクの和議により、プロテスタントもカトリック教会と同様に信教の自由の地位を保証されることになる。デンマーク・スウェーデン・ノルウェーなどでルター派のプロテスタントが国境となる。 |
| 16世紀末 | イギリス国教会の内部で、ピューリタンと呼ばれる改革派教会への方向へ改革を求める人々が現れる。ピューリタンはカルヴァン派のグループのひとつである。 |
| 17世紀 | イギリスで独立教会制度を提唱した会衆派を独立派という。信団(ゼクテ)が形成されるようになる。 |
| 18世紀 | イギリス全土でメソジスト(方法派)が広まる。 |
| 1760年代 | イギリスで世界最初の産業革命が始まる。 |
| 1790年 | アメリカでベンジャミン・フランクリンの「フランクリン自伝」が出版される。 |
| 1830年 | イギリスで産業革命が終わる |
プロテスタンティズムについて
プロテスタントのイズムで、プロテスタンティズムという言葉ですよね。イズムは主義や説を意味する英語の接尾語「ism」からきています。
プロテスタントはキリスト教の教派のひとつで、カトリック教会から分離したものです。その誕生はルターが中心となった宗教改革が誕生の発端となります。カトリック教会に抗議(ラテン語: prōtestārī)したことが由来だそうです。
プロテスタントの考え方は時代によって違います。プロテスタンの中にも様々な「諸派(しょは)」があります。ルターの考えを引き継いだルター派の他にも、カルヴァン派、メソジスト、パイエティズム(敬虔派)、信団(Sekte)、ピューリタニズム(カルヴァン派のグループのひとつ)などが関係してきます。他にも多くの諸派があります。
私にとって、そしてプロ倫でとりわけ重要なのが先程あげた諸派です。すなわち、カルヴァン派、メソジスト、敬虔派、新団、ピューリタニズム等です。一般にプロテスタンティズムというとき、どの派閥の主義主張を意味しているか特定的ではなく、おそらく総称として扱うのだと思います。そう考えればマルティン・ルターの主義主張もプロテスタンティズムであり、カルヴァンの主義主張もプロテスタンティズムになります。
世俗内的金欲について
ルターのプロテスタンティズムは世俗内的禁欲(いわゆるプロテスタンティズムの倫理)として確立しなかった
このようにして、ルッターの場合、天職概念は結局伝統主義を脱するにいたらなかった。世俗的職業なるものは神の導き(Fugung)として人が”甘受し”、これに『順応』するべきものであって、──こうした色調のかげにかくれて、職業労働は〔天職として〕神から与えられた使命、否むしろ”使命そのもの”だとする彼のいま一つの思想は色あせてしまった。しかも、正統ルッター派の発展はこの傾向にさらに拍車をかけた。こうしてこの派がもたらした唯一の倫理的収穫はさしあたって消極的なもの、すなわち、禁欲的義務を強調すれば世俗内的義務を軽視するようになる、といった〔カトリック的〕態度を除去したというだけで、それのみかこれに結びついて政府への服従と所与の生活状態への順応が説かれるようになったのだった。
(「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」、125P、マックス・ウェーバー、大塚久雄訳、岩波文庫、1989初版、2006年(第39版))
世俗内的禁欲と、世俗外的禁欲についてまずは理解する必要があります。世俗内を非宗教的、世俗外を非宗教的と読み替えたほうが理解しやすいと思います。ルターが「世俗内の職業労働こそ、唯一宗教的・道徳的な価値があり神の召命だと考えた(天職思想)」ことは前に説明しました。
修道士は、修道誓願を行い、禁欲的な修道生活を送る人々のことである。西方教会ではさらに修道会に所属し、その規則にしたがうことが求められる。東方教会でも多く修道院に籍をおき、長老や院長・掌院の指導に従う。
起源は3世紀のエジプトにさかのぼる。当時のエジプトでは熱心な男性キリスト教徒たちが世俗を離れて砂漠で孤独な生活を送る習慣が生まれた。彼らは隠遁者などと呼ばれたが、これが修道士の原型となった。聖アントニウスがしばしばこの生活の創始者であるとされる。個人で生活していた隠遁者たちだが、徐々に信心業を集まっておこなうようになっていった。その中からさらに信心業だけでなく全生活を共におこなうようになるグループが生まれていった。ここから修道院の原型ともいうべきものが生まれた。この生活はローマ帝国の東方に広まっていった。
ルターにとって、世俗”外”、たとえば修道院の生活における禁欲は無価値とみなされています。世俗外的禁欲とは、たとえば食事は菜食主義で豚や牛などの肉を食べないこと、生涯独身、人々への奉仕、断食等々です。カトリック教会の修道生活ではとりわけ貞潔、清貧、従順が重視されます(いわゆる修道誓願)。結婚しないこと、私的財産をもたないこと、上司の(正統な)命令を聞くことです。
たしかにシスターや司祭は禁欲的なイメージがありますよね。欲望を抑えているイメージがあります。
世俗内禁欲と資本主義の精神
「今日では、禁欲の精神は──最終的にか否か、誰が知ろう──この鉄の檻から抜け出してしまった。ともかく勝利をとげた資本主義は、機会の基礎の上に立って以来、この支柱をもう必要としない。……『天職義務』の思想はかつての宗教的信仰の亡霊として、われわれの生活の中を徘徊している。そして、『世俗的職業を天職として遂行する』という、そうした高位を直接最高の精神的文化価値に関連させることができないばあいにも──あるいは、逆の言い方をすれば、主観的にも単に経済的強制としてしか感じられないばあいにも──今日では誰もおよそその意味を詮索しないのが普通だ」
(「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」、356-366P、マックス・ウェーバー、大塚久雄訳、岩波文庫、1989初版、2006年(第39版))
世俗内禁欲も欲望を抑えるという点では世俗外禁欲と似ています。たとえば、プロテスタントの人たちは節制を徹底したそうです。無駄遣いをしないのです。物欲を抑えているので、余計な物も買いません。お金が余るので、ピューリタンの人たちは寄付などをしたそうです。
それでも余ったお金はさらに投資に使い、工場などを大きくしていきます。産業の規模が大きくなっていき、合理化を徹底させていくと、規模が小さい会社や合理化が不徹底な会社は潰れていきます。潰れないように人々は節制し、投資し、合理化し、勤労するのです。得た利益を投資に回さないと会社が回らなくなり、やがて利益、つまりお金儲けが重要視されるようになっていきます。
お金儲けを目的としないこと、”金”欲を”禁”じることも世俗内禁欲のひとつだったはずですが、資本主義のシステムが大きくなるにつれて、お金儲けが倫理的な義務とみなされるようになってくるのです。世俗内禁欲の「反営利的な性格」が「営利的な性格」へと変わっていったということです。
そしてこの「営利的な性格」こそが、資本主義の精神なわけです。神に救われているという確信を得るために、つまり自分の意思で、心で世俗内禁欲を行ってきたのに、いつのまにか資本主義の社会機構が人々にお金儲けを強いるようになってきたのです。そうしないとやっていけないからです。今ではそうした労働をするのか、その意味を宗教的に問う人は少ないかもしれませんね。
さいごに
生きるために労働する、結婚するために労働する、欲しい物があるから労働する、親に言われたから労働する。じゃあ、そもそもなぜ生きるべきなのか?と哲学的な質問を投げかけると、おそらく昔のキリスト教の人々なら「死んだ後に神に救われるために」というのでしょうか。カルヴァン派では予定説と言って救われているかどうかは人間が産まれる前に決定されていると考えました。それでも、労働することで救いの確信を得ようとしたのです(昨日のニューカムのパラドックスとも深い関連があります)。
なぜ人間は生きるべきなのか。宗教的な意味付けを失った場合、それに答えるのは難しい。学問的な、つまり理論理性ではそれに答えることは難しい。きっとなぜ生きるべきか、労働するべきかといった考えが生じないほどに、人間関係が充実し、具体的な他者や自然とともに在り、生が充実していれば問題がないのだと思う。そうした充実がない人は、なぜ生きるべきか、労働するべきかという問題を提起してしまう。
ニーチェなら、神は死んだ!超人になれ!というかもしれない。ウェーバーなら「自分の仕事に就き、そして『日々の要求』に──人間関係のうえでもまた職業のうえでも──従おう。」というかもしれない。
自分の考えではやっぱり「人間関係の充実にこそ、生の充実がある」と思う。しかしサルトルがいったように、「地獄とは他人のこと」かもしれない。人間関係でこそ人は最も苦しむ可能性がある。たとえば恋人と付き合っているときは生を謳歌している人も、別れるときには生を呪っているかもしれない。他人の目を気にして、自分がみじめになってしまうかもしれない。
だからこそ、やはりなんらかのバランスはとっておくべきだとおもう。西部邁のいうところの「平衡(へいこう)感覚」をもつべきだとおもう。しかしどうやってもつべきだろうか。この問いは私の生涯で最も関心のある問いのひとつだ。
やはり「趣味」だろうか。いざというときの逃げ場でもいい。たとえば絵を描くのもいい。絵を描けば、人間関係へとつながることもある。仮に人間関係が悲惨になったときにも、君にはまだ「趣味」があるじゃないかといえる。
やはりそうした趣味の安全領域は、生への助けになると思う。そう願いたい。こうして記事を書いていることが、だれかの「趣味」の助けになればいいと思っている。これも一つの、ある意味では「天職」かもしれないなと思った。
参考文献
マルティン・ルターの天職思想/caption]
コメント
この記事へのトラックバックはありません。






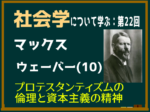

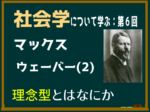
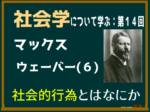
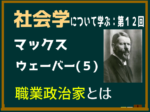
この記事へのコメントはありません。