- Home
- ジャン・カルヴァン, マックス・ウェーバー, マルティン・ルター
- 【社会学】カルヴィニズムの予定説とはなにか。天国か地獄か、生まれる前から決定されている。
【社会学】カルヴィニズムの予定説とはなにか。天国か地獄か、生まれる前から決定されている。
- 2021/8/2
- ジャン・カルヴァン, マックス・ウェーバー, マルティン・ルター
- コメントを書く
はじめに
この記事の要約
- ジャン・カルヴァンは中世の神学者であり、宗教改革(プロテスタント誕生)の中心人物の一人。
- ジャン・カルヴァンもしくはカルヴァン派の教理をカルヴィニズムともいう(ジャン・カルヴァン自身の教理とカルヴァン派の教理は必ずしも同じではない。カルヴァン派は後継者やインスパイアが含まれる。)。
- カルヴィニズムの教理は5つある。全的堕落、無条件的選び、制限的・限定的贖罪、不可抵抗的恩恵、聖徒の堅忍の5つ。「無条件的選び」は予定説であり、カルヴィニズムの中心的な教義である(諸説ある)。
- カルヴィニズムの予定説とは、人間が現世で善行をしても、懺悔(ざんげ)をしても、聖礼典を行っても、すでに誰が救われるかは決定されているので、人間に自由意志はなく、救済には一切関わりがないとする立場(派閥に違って解釈は多少異なるが、純粋なカルヴィニズムの教理はそう)。
- (この記事で詳説はしないが)カルヴァン派の「予定説」などの教理は、プロテスタント的な禁欲(世俗内禁欲、天職義務、労働こそが救済の確信等)につながり、やがて「資本主義の精神」へとつながった。
動画での解説・説明
・この記事のわかりやすい「概要・要約・要旨・まとめ」はyoutubeの動画の冒頭にありますのでぜひ参照してください。
よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m
カルヴァンとは
ジャン・カルヴァンとは
・ジャン・カルヴァン(Jean Calvin、1509年-1564年):フランス出身の神学者であり、キリスト教宗教改革初期の指導者。カルヴァンの思想と、カルヴァンに影響を受けたカルヴァン派の思想(カルヴィニズム)は異なる部分があるので注意したほうがいいです。
カルヴィニズムとは
・カルヴィニズム(Calvinism):キリスト教の教派のひとつである「プロテスタント」の改革派教会の教義。中世の神学者であるジャン・カルヴァンにちなんで名付けられた。カルヴァン主義ともいう。
カルヴィニズムの特徴は、ドルト信仰基準という1618年のドルトレヒト会議で決められた信仰基準がわかりやすい。カルヴァン派にはさまざまな派閥がありますが、カルヴィニズムの特徴を5つの特質として明確にしました。頭文字をとってTURIP(チューリップ)の神学というそうです。
- 全的堕落(Total depravity) – 堕落後の人間はすべて全的に腐敗しており、自らの意志で神に仕えることを選び取れない。
- 無条件的選び(Unconditional election) – 神は無条件に特定の人間を救いに、特定の人間を破滅に選んでいる(予定説)。
- 制限的・限定的贖罪(Limited atonement) – キリストの贖いは、救いに選ばれた者だけのためにある。
- 不可抵抗的恩恵(Irresistible grace) – 予定された人間は、神の恵みを拒否することができない。
- 聖徒の堅忍(Perseverance of the saints) – いったん予定された人間は、最後まで堅く立って耐え忍び、必ず救われる
予定説とは
意味
・予定説(よていせつ,Predestination):人間が現世で善行をしても、懺悔(ざんげ)をしても、聖礼典を行っても、すでに誰が救われるかは決定されているので、人間に自由意志はなく、救済には一切関わりがないとする立場。
ウェストミンスター信仰告白における「予定説」
意味
・ウェストミンスター信仰告白(びこつ,Westminster Confession of Faith):1646年に、イングランド国教会のためにウェストミンスター会議で作成された信仰告白。これにより、イングランド国教会はカルヴァン派の教理と礼拝を採用した。清教徒革命(1642-1649年、別名ピューリタン革命)中に作成され、イングランド及びスコットランドで教条(教会が公認した教義)として宣言された。1660年には王政復古によって廃止されたが、スコットランド国教会のみ、再度採択された。
重要なのはウェストミンスター会議は清教徒革命中に開催されたということです。ピューリタン、つまりカルヴァン派で多くが構成される「議会派」とピューリタンの影響が小さく、国王を支持する「国王派」の対立が清教徒革命です。しかも、ピューリタン側が内戦で勝利し、優勢だったというのもポイントです。ピューリタン側が優勢だからこそこのような会議が成立し、国王の権力が復活した1660年にイングランドで廃止されたといえます。
参考資料
歴史補足:清教徒革命概略
清教徒革命はピューリタン(プロテスタントであり、カルヴァン派のグループのひとつ)の勢力が中心となったそうです。市民革命とは、市民階級(ブルジョアジー)が封建制を打破する戦いのことです。封建制とは日本でいえば徳川家康が各地の大名に土地を与え、大名がその土地に住む農民を身分的に支配するといった感じでしょうか。
清教徒革命後に王政はなくなりましたが、1660年のブレダ宣言により王政は復活します(信仰の自由などは認められないまま)。1688年のイギリスで起きた名誉革命では再び市民革命が成功します。1689年には「権利宣言」が提出されます。王権に対する議会の有利が宣言されたものであり、また臣民の権利および自由を宣言したものでもあります。日本では(一般的な意味では)鎌倉幕府成立から江戸幕府の崩壊までが封建制度の時代らしいです。
イギリスでは清教徒革命当時、農民(ヨーマン)がより裕福になっていくものと、より貧しくなっていくものに二極化していったそうです。この当時すでに、封建領主制からブルジュワ的土地経営への移り変わりの時期にあったようですね。支配階級に支配されて農作をするのではなく、商契約に基づく労働というふうに変わっていったそうです。
当時のイギリスの国王はチャールズ1世です。収入が寄生地主や富農の手に留まり、国家まで上がってこなかったこと等が原因で財政難に陥り、徴税を強化したそうです。今でいうところの税金の値上げですね。現代では国会で議決されて民主的に税金の値上げがされます。しかし、当時のチャールズ1世は王権神授説(王権は神から付与されたもので、王権は神以外の何人によっても拘束されない)を信じており、議会の承認を経ずに徴税し、反対するものは投獄したそうです。
結局議会は開かれますが、議会内で王への抗議文(議会の大諫奏)が僅差で可決されます。議会内では王を支持する国王派と、王を支持しない議会派が対立し、市民を巻き込み内戦・革命へとつながっていきます。国王軍は議会軍に負け、チャールズ1世は処刑されます。これが清教徒革命の概略です。
重要なのは、王を支持しない議会派の中の多くがピューリタン(清教徒)だったということであり、カルヴァン派だったということです。
参考資料
ウェストミンスター信仰告白引用文
第九章(自由意志について)
第三項 人間は罪の状態への堕落によって、救いをもたらすべき霊的善へのすべての意思能力を全く喪失してしまった。従って生まれながらの人間は、全く善に背反し罪のうちに死したもので、みずからの力で悔い改めあるいは悔い改めにいたるようみずから備えることはできない。
第三章(神の永遠の決断について)
第三項 神はその栄光を顕さんとして、みずからの決断によりある人々……を永遠の生命に予定し(predestinated)、他の人々を永遠の死滅に予定し給うた(foreordained)。
第五項 神は人類のうち永遠の生命に予定された人々を、世界の礎の据えられぬうちに、この永遠にして不変なる志向と、みずからの意思の見ゆべからざる企図と専断にもとづいて、キリストにあって永遠の栄光に選び給うた。これはすべて神の自由な恩恵と愛によるものであって、決して信仰あるいは善き行為、あるいはそのいずれかにおける堅忍、あるいはその他被造物における如何なることがらであれ、その予見を条件あるいは理由としてこれを為し給うのではなく、かえってすべて彼の栄光にみちた恩恵の賛美たらしめんがためである。
第七項 神は自らの被造物に対する主権に栄光あらしめたるため、聖意のままに恵みをあたえ、あるいは拒み給う測るべからざる意思に彼の栄光にみちた義の賛美たらしめることを喜び給うた。
第十章(有効なる召命について)
第一項 神は生命に予定された人々、しかも彼らのみを、みずから定めかつ善しとし給うた時期に、みずからの言と魂をもって有効に召命することを喜び給う。……こうして神は彼らの頑固な心をとりさって柔順な心をあたえ、また彼らの意思を新たにして、その全能の力によりこれを善きことへと定め給う。
第五章(摂理について)
第六項 神が正しい審判者として、その過去の罪ゆえに盲目にし頑なにし給う悪しき、不信仰な人々についていえば、神は彼らに恩恵を拒み、これによって彼らの悟性が照らされ心を動かされることを無からしめ給うのみでなく、また時には彼らのもてる賜物(たまもの)をもとりさり、その頽廃(たいはい)が罪の機会を作るにいたるべきことがらに近づけ、それによって彼らをみずからの欲望と世の誘いとをサタンの力に委ね給う。その結果彼らは、神が残余の人々を柔順にし給うと同じ手段によってさえも、みずからをますます頑固とするのである。
(「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」内で引用されている「ウェストミンスター信仰告白」、146 -147P、マックス・ウェーバー、大塚久雄訳、岩波文庫、1989初版、2006年第39版)
予定説:人間が生まれる前に、すでに救われるかどうかは決まっている(決定論)
救済論とは
「永遠の生命に予定された人々」とは、死んだ後に神によって救われる人です。
また、未来において世界が終末を迎えたとき、神が人々を裁くという最後の審判の観念もある。その時混乱の極みにある世界にイエスが救世主として再臨し、王座に就くとされる。死者達は墓の中から起き上がり(伝統的に火葬しなかったのはこの時甦る体がないといけない為)、生者と共に裁きを受ける。信仰に忠実だった者は天国へ、罪人は地獄 (キリスト教)へ、世界はイエスが再臨する前に一度終わるが、この時人々は救済され、新しい世の始まる希望がある。(千年王国)
出典:救済
救済論についてのわたしのイメージは”天国へ行ける”くらいでしたが、いろいろ複雑なようですね。ここでは終末論のひとつを紹介いたします(カルヴァン派の思想としてとりあげるわけではありません)。
カトリックにおける救済論(非決定論)
カトリック教会では一般に、現世の行為が死後の世界で救済されるかどうかに影響を与えると考えられています。善いことをしてきた人は天国に、悪いことをしてきた人は地獄に、悪いことをしてきたが償える可能性の残ってるものは煉獄(れんごく)にといった考えです。
つまり、生まれる前から救われるかどうか、つまり天国へ行くか地獄へ行くかは決まっておらず、生まれてからの行いによって変わるということです。決定論の対義語として用いるなら、自由意志論や非決定論かもしれませんね。自由意志論について深堀りはしませんが、元々の問題はアウグスティヌスにまでさかのぼり、人間に自由意志はあるのか?という論点になります。特に重要なのが「救いの根拠」が人間の自由意志に基づくのかどうかです。人間が善悪を判断し、神が喜ぶようなことを考える能力があるかが論点になります。カルヴァンにいわせればNOということです。
現世での行いにより、死後の世界で救済されるかどうかの代表的なカトリックの行事として、「懺悔(ざんげ)」があります。「ゆるしの秘跡」ともいわれるそうです。教会で罪の告白を神父さんにして、罪を反省し、罰を行う(善行や寄付など)ことによって、死後の世界で救われようとするのです。
マルティン・ルターはこうした「ゆるしの秘跡」が金銭によって行われることに対して批判的だったそうです。贖宥状(しょくゆうじょう)という献金などを代償として信徒に与えられた罰の免除証書です。教会の財源増収のために乱発され、これがきっかけでマルティン・ルターらによる宗教改革が行われ、新しい教派であるプロテスタントがつくられました(1517年)。
カルヴァン派による救済論(予定説、決定論)
第三章第五項の「第五項 神は人類のうち永遠の生命に予定された人々を、世界の礎の据えられぬうちに、この永遠にして不変なる志向と、みずからの意思のみゆべからざる企図と専断にもとづいて、キリストにあって永遠の栄光に選び給うた」というところが、決定論的な文章です。
「世界の礎(いしずえ)の据えられぬうち」が具体的にどれだけ前かわかりませんが、”地球が創られる前”と考えてもいいのかもしれません。いずれにせよ、人間が生まれるよりは前ですよね。
救われるかどうかが、人間(あるいは人類さえも?)が生まれるより前に決まっているのです。この予め救われるかどうか既に決まっているという考えを「予定説」、あるいは「決定論」といいます。
どのような法則・原理・理由で救われるかどうか決められるのでしょうか?
結論から言えば、神のみぞ知るところであり、人間が知ることはできないというわけです。
「みずからの意思の見ゆべからざる企図と専断にもとづいて」とあります。「見ゆべからざる」とは見ることのできないということです。私達人間が捉えることのできない神の企てとその判断をもとに、人間が救われるかどうかが神によって決定されているということです。
要するに、人間が神の判断について知ろうとするなどおこがましいということでしょうか。神はすごいから、救われるかどうかは前もって予知できるのでしょう。神はすごいので、我々がそのすごさを理解することなどできないのでしょう。マルティン・ルターのように、私達ができるのは「信仰のみ」で、神を信じることだけだと。
人間の自由意志を否定(原罪との関連)
原罪について
哲学的に重要なのは、人間の自由意志を否定しているということです。
第九章(自由意志について)
第三項 人間は罪の状態への堕落によって、救いをもたらすべき霊的善へのすべての意思能力を全く喪失してしまった。従って生まれながらの人間は、全く善に背反し罪のうちに死したもので、みずからの力で悔い改めあるいは悔い改めにいたるようみずから備えることはできない。
前述
「人間は罪の状態への堕落によって、救いをもたらすべき霊的善へのすべての意思能力を全く喪失してしまった」という文章は、宗教に疎い私には即座に理解することはできません。
しかし罪といえば、思いつくのはやはり「原罪(original sin)」です。原罪とはキリスト教において、いわゆる禁断の果実をアダムが食べ、神のように善悪を知るものとなり、エデンの園から追放されたアレですよね。あの旧約聖書の「創世記」の物語です。このせいで罪と死が人類に入り込んでしまったらしいです。
カルヴァン派では罪の状態への堕落によって、救いにつながる善へのすべての意思能力を喪失してしまったそうです。カトリックでは善行をすることで、救いにつながります。しかしカルヴァン派では、そういった能力を罪の状態への堕落によって喪失してしまったそうです。罪の状態を悔い改めることすらできないそうです。
やがて宗教改革者ルターやカルバンらは、コンクピスケンティア(邪欲)の問題を深めることによって原罪説を支持し、パウロ、アウグスティヌスに拠(よ)りながら、原罪説を展開した。人文主義者エラスムスの『評論・自由意志』に反対して『奴隷的意志』を公刊(1525)したルターは、「ただ1人の人アダムの、ただ一つの違反によって、私たちすべてが罪と刑罰のもとにあるとき、どうして私たちは、罪でもなくまた罰せられるべきものでもない何ごとかを企てうるのであろうか」(山内宣訳)と述べて原罪の教義に固くたっている。カルバンは『キリスト教綱要』第2巻で原罪について述べ、神の像が原罪の結果破壊されたと述べて、人間の本性を「邪欲」としてとらえ、「人間それ自体邪欲にほかならない」とした。
パスカルが『パンセ』(ブランシュビク版230番)において、「原罪があるということも、原罪がないということも」不可解であるというとき、理性にとって不可解であっても人間の現実にたって原罪を支持している。
カルヴァン自身の思想では、原罪によって神の像が破壊され、人間の本性を「邪欲」としてとらえているそうです。ルターもエラスムスの『自由意志』に反対しているようですね。「どうして私たちは、罪でもなくまた罰せられるべきものでもない何ごとかを企てうるのであろうか」というのは、人間が自分の意志で罪をどうにかできるものではない、と読み替えていいのでしょうか。自由意志に反対するならば、人間が自分の意志で原罪をどうにかできるものではないといったように読み替えられます。
ルター派とカルヴァン派の比較について
ルターとカルヴァンについてウェーバーは、以下のように述べています。
ルッターも彼の宗教的天才が最高潮にあり、あの『キリスト者の自由』を書くことのできた当時には、神の『図らべざる決断』こそ自分が恩恵の状態に到達しえた絶対唯一の図り難い根源だ、とはっきり意識していた。そのアゴもルッターは、形の上では、この思想を捨てていない。──しかし、それはもはや中心的な位置を占めるものではなくなったばかりでなく、彼が責任ある教会政治家としてしだいに『現実政治的』となるにしたがって、ますます背景に退いていった。メランヒトン(Melanchthon)はこの『危険で理解しがたい』教説(=予定説※引用者がいれました)をアウクスブルクの信仰告白に採り入れることをことさらに回避したし、またルッター派の教父たちにとっては恩恵は喪失可能(amissibilis)であり、悔い改めによる謙遜と信仰による神の言への信頼と聖礼典とによって新たに獲得されうるということは、教義上問題のないことだった。
カルヴァンの場合にはことがらの経路はそれとまさに逆で、教義上の論敵に対する論争がすすむにつれて、この教理の重要性が目に見えて増大していった。予定の教説がはじめて十分に展開されたのは彼の『キリスト教綱要』》Institutio《の第三版であり、さらに、それが中心的な位置を占めるにいたったのは、ようやく彼の死後、ドルトレヒトとウェストミンスターの宗教的会議がそれの決着をつけようとした大規模な文化闘争のさ中においてだった。
(「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」、152P、マックス・ウェーバー、大塚久雄訳、岩波文庫、1989初版、2006年第39版)
重要なのは、ルターもカルヴァンも同じように、「神の図らべざる決断」を重視しているということです。つまり人間では神の決断を理解することはできないのです。当時のローマ・カトリック教会は贖宥状なるものを配っていました。罰を教会への寄付によって免じるというものです。人間がなにか悪行をした場合、その罪を悔い改め、罰を受けなければなりません。罰は善行などによって贖(あなが)われるものですが、贖宥状によってお金で善行をしなくてもよくなったのです。
人間が自分の意志、自分の解釈によって、寄付をすれば罪が免じられると考えたのです。たしかにそんな勝手な解釈は「おこがましい」と考える人が出てもおかしくないかもしれませんね。
人間ごときが、神がよろこぶ行為を勝手に解釈し、それを利用して信者からお金を巻き上げ、そうすれば救済されるなどと戯言をぬかしておる!といったところでしょうか(これは言いすぎですかね)。
そういう感情の極みに、人間が神の救済するかどうかの判断の理由を理解できるはずはないという思考になるのかもしれません。つまり、人間に自由意志などないと。善行をした気になっているが、それが救済につながるかどうか、神が喜ぶかどうか、どうかどうしてわかるのかと。
ルターも同じような考えだったそうですが、責任ある教会政治家になるにつれてそういった思想は影を潜めていったそうです。たしかに現世での善行は救済されるかどうかは無関係だ!と責任ある教会政治家はなかなかいえませんよね。個人の信仰として思っていたとしても、世界が無秩序になってしまう可能性もあります。
まさにカルヴァンにおいては、この》decretum horibile《『恐るべき〔神の〕決断』の教理はルッターのように”体験によってえられたのではなく”、”思索によってえられた”のであり、したがって神のみを思い人間を思わない彼の宗教的関心が思索的に徹底されていくたびに、その重要性がますます大きな物となっていった。
特に重要なルターとカルヴァンの比較の文章はこちらでしょうね。思索とは日本語では「秩序立てて考えを進めること。物の道理をたどって考えていくこと」を意味します。まるで科学のような合理的な考えですね。
マルティン・ルターの救済への考えについて
「第二の命題。人間は神の恩恵なしには決して神の誡命を守ることができず、また……神の恩恵を受けるにふさわしい地位へと自分自身を引き上げることもできない。神が恩恵をくだされないかぎり、彼は必然的に罪のもとにとどまるのである。(「恵みによらな人間の力と意思とについて論ぜられた問題 1516年 マルティン・ルター」)」
「……人間は善事に励むどんな自由をも持ち合わせていないが、悪事となると人間は大いに自由意志を発揮し、喜々としてそれに耽りさえする。(「ベラギウス派の二書簡を駁す」第一巻)」
「だとすれば、あたかも神の審きを了解し、かつ評価する権利が自分にあるといわんかぎりに、神の義と審きとに自分勝手な難癖をつけたがるわれわれの僭越ぶりは、一体なんというべきであろうか(「奴隷的意思」1525年)。」
「かりにどんな誘惑、どんな危険、どんな悪魔の攻撃もこの世に存在しないと仮定しても、それでも私は、もし自由意志が与えられているとしたら、いつもいつも極度の不安にさいなまれ、みずから浄福を獲ちとるため、あたかも刀で空を切る者よろしく、きりきり舞いしなければならないからである。だって、そうではないか。かりに私に無限の生命が与えられ、私が永遠に善き業に励むことができたとしても、それでも私は、神に嘉納(よし)とされるためには自分がまだどれほどの功業を積まなければならないかについて絶えず悩まなければならず、その点で私の良心は決して安らかになりはしないだろう(「奴隷的意思」(2)自由意志を欲せず)。」
マルティン・ルターもカルヴァンと同じように、恩恵による救いは「神の測らべからざる決断」によってなされると考えましたが、ルター派の人々()ルーテル教会の人々)は恩恵は信仰や聖礼典によって獲得可能であり、また喪失可能だと考えたそうです。
「最後の審判においてイエス・キリストが敬虔な者と選ばれた者には永遠のいのちをあたえ、不敬虔な者と悪魔には限りない苦悩を宣告すると告白(アウクスブルクの信仰告白)」
ジャン・カルヴァン個人の救済への考えについて
「かならずや信徒の一人ひとりの胸には、”私は”いったい選ばれているのか、”私は”どうしたらこの選びの確信がえられるのか、というような疑問がすぐさま生じてきて、他の一切の利害関心を背後に押しやってしまったにちがいない。──カルヴァン自身にとっては、このことは少しも問題とならなかった。彼は、自分は神の『武器』だと感じ、自分の救われることに確信をもっていた。そこで彼は、一人ひとりが何によって自分自身の選びに確信をもちうるかという問いに対しては、根本において次の答えしかもたなかった。われわれは、神が決定し給うのだという知識と、神の信仰から生じるキリストへの堅忍な信頼を持って満足しなければならない、と(プロ倫、172-173P)。」
「彼は、人々が選ばれているか捨てられているかは彼らの行動によって知りうるとの臆見に対しては、これを神の秘密に立ち入ろうとする不遜な試みだとして、原理的に斥けた。現世の生活においては、選ばれたものも、外面的には、捨てられた者とすこしも異なるところがなく、選ばれた者の主観的な経験でさえ──》ludibria spiritus sancti《『精霊の戯れ』として──ただ信仰によって》『”終わりまで”』》finaliter《堅忍する信頼を除いては、すべて捨てられたものにも可能なのだ。だから、選ばれた者は神の”見えざる”教会をなしており、かついつまでもそうでありつづける(同上)。」
ジャン・カルヴァンは救いを確信する方法を探るのは不遜な試みとしました。ただ、自分が救われていると信じること、耐え忍ぶことが大事なようです。善行などのなにか行為によって、神の永遠の過去でくだされた決断が現世で変わるとは毛頭考えていないようです。選ばれたと信じることは選ばれていないものにも可能であり、選ばれていたと主観的に確信することすら選ばれていないものが経験することもあるそうです。ただ、いかにそういう経験をしたとしても、選ばれていないものが選ばれることはありません。
カルヴァン派の救いに対する考えについて
・カルヴァン自身は自分が救われていると、選ばれていると信じるしかないと考えていた。救われてるかどうかを知る方法はないと考えた。
・純粋なカルヴァン派もこうしたカルヴァンの教理を受け継いでいたが、牧会の実践という領域ではカルヴァンのそのままの立場を受け継ぐことは難しくなっていた。
・牧会とは、牧師が教会のために行う説教や礼拝のことです。「集団や個人への指導」や、「魂への配慮」という意味でも使われます。
・ウェーバーによれば、「純粋なカルヴァン派の教理は信仰と、聖礼典による神との交わりとの意識とを指示し、『聖霊その他の果実』は事のついでに述べているだけである(プロ倫,179P)」とあります。
・ウェーバーによれば、予定説から生じる心の苦しみに対する対応として、2つの類型が見られたそうです(プロ倫、178-179P)。
(1)誰もが自分は選ばれているのだとあくまでも考えて、すべての疑惑を悪魔の誘惑として斥ける、そうしたことを無条件に義務づけること。
(2)そうした自己確信を獲得するために最もすぐれた方法として、絶えまない職業労働をきびしく教え込むということ。
恩恵喪失について
ルターの考えを受け継いでいったルター派の人々は「恩恵喪失は可能であり、また恩恵獲得も可能である」と考えていたそうです。恩恵とは、神の恵みであり、この恩恵によって人間は救済されます。どうやって恩恵を獲得するのかといえば、「悔い改めによる謙遜と信仰による神の言への信頼と聖礼典によって」です。聖礼典はサクラメント、秘跡ともいわれます。ローマ・カトリック教会では「洗礼,堅信,聖体,告解(ゆるし),終油(病者の塗油),叙階,婚姻」の七つが聖礼典ですが、プロテスタントでは「聖餐と洗礼」の2つだけだそうです。
われわれが知りうるのは、人間の一部が救われ、残余のものは永遠に滅亡の状態に止まるということだけだ。人間の功績あるいは罪過がこの運命の決定にあずかると考えるのは、永遠の昔から定まっている神の絶対に自由な意思を人間の干渉によって動かしうると見なすことで、あり得べからざる思想なのだ。
(中略)
神の決断は絶対不変であるがゆえに、その恩恵はこれを神からうけた物には喪失不可能であるとともに、これを拒絶された者にもまた喪失不可能なのだ。
(「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」、153-154P、マックス・ウェーバー、大塚久雄訳、岩波文庫、1989初版、2006年第39版)
二重の神について
ルッターにあたっては、形而上的な思索を無益かつ危険だとして排斥する傾向がますます強くなっていったために、新約の神が完全に優勢となっていったのに対して、カルヴァンにあっては、人生を支配する超越的な神性の思想が勝利を占めた。カルヴィニズムが民衆の間にひろがっていくさい、そうした思想はもちろん長続きしなかった。──が、それに取って代わったのは、新約にみえる天の父ではなくて、旧約のヤーウェだったのだ。
(「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」、155P、マックス・ウェーバー、大塚久雄訳、岩波文庫、1989初版、2006年第39版)
ウェーバーも、旧約聖書と新約聖書について注釈で触れています。旧約聖書はユダヤ人、”ユダヤ教”にとって唯一の聖典です。キリスト教にとっては旧約聖書と新約聖書の2つが聖典です。
ウェーバーは二重の神について言及しています。ひとつは新約聖書の恩恵と慈愛の神であり、もうひとつは旧約聖書の「隠れたる神」です。「隠れたる神」は自らの思うところに従って処断する専制君主としての神だそうです。選民思想は旧約聖書的ですよね。
ルターもカルヴァンも、二重の神を識別していたそうです。ルターは新約聖書的な神が優勢であり、カルヴァンは旧約聖書的な神が優勢だったそうです。
カルヴィニズムが民衆の間にひろがっていくうちに、こういった二重の神という思想は消え、旧約聖書の「隠れたる神」でありヤーウェ(ヤハウェ)一色になっていってしまったんですね。
選民思想について
古代ヘブライ(ユダヤ)人の独特の宗教観
出エジプトやバビロン捕囚などの民族的苦難の中から作りあげられた思想で,ヘブライ人だけがヤハウェの神に選ばれた民であり,神は必ずメシア(救世主)を送って救ってくれると信じた。のち,イエスが出て,この思想を痛烈に批判した。出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について
これが一般的な選民思想に関する説明です。旧約聖書では選民思想の傾向が強く、新約聖書では弱いというイメージがありますね。その意味では、先程の二重の神のイメージと合致します。
7 主があなたがたを愛し、あなたがたを選ばれたのは、あなたがたがどの国民よりも数が多かったからではない。あなたがたはよろずの民のうち、もっとも数の少ないものであった。
8 ただ主があなたがたを愛し、またあなたがたの先祖に誓われた誓いを守ろうとして、主は強い手をもってあなたがたを導き出し、奴隷の家から、エジプトの王パロの手から、あがない出されたのである。
旧約聖書『申命記』 第七章 ※モーセ五書のうちの一書
ちなみに旧約聖書のユダヤ人の選民思想は、申命記などに表れています。
イエスは彼に言われた、「わたしは道であり、真理であり、命である。だれでもわたしによらないでは、父のみもとに行くことはできない。
「ヨハネによる福音書」14:6 出典
一方で、新約聖書にも選民思想に似たものがあります。取替理論(スーパーセッショニズム)というらしいです。これは聖書の解釈の一つです。これはキリストの言葉らしいです。たしかにキリストを信じるもの、キリスト教徒のみが神のもとへ行ける、つまり救済され、天国へ行けるとも解釈できます。
8:13
神は、「新しい」と言われたことによって、初めの契約を古いとされたのである。年を経て古びたものは、やがて消えていく。
新約聖書には他にも、古い契約は消え、新しい契約を尊重するようなものがあります。つまりユダヤ人の神との契約は、キリストの契約によって置換された、取り替えられたという解釈です。
Paul’s views on “the Jews” are complex, but he is generally regarded as the first person to make the claim that by not accepting claims of Jesus’ divinity, known as high Christology, Jews disqualified themselves from salvation.[2] Paul himself was born a Jew, but after a conversion experience he came to accept Jesus’ divinity later in his life. In the opinion of Roman Catholic ex-priest James Carroll, accepting Jesus’ divinity, for Paul, was dichotomous with being a Jew.
WIKIにはこのような解釈がありました。パウロ(初期キリスト教の使徒の一人)はユダヤ人であり、ユダヤ教徒でした。始めの頃はキリスト教徒を迫害していましたが、後に回心したそうです。天からの光とともにイエス・キリストの声を聞いたそうです。
そしてイエスの神性を受け入れないことで、ユダヤ人は救われる資格を失ったと主張したそうです。いろいろ解釈があるようですね。パウロは後に見ますが、「予定説」に関連する人物としても重要になってきます。
しかし、どんな人種であってもイエスの神性を受け入れれば救われるのでしょうか。たとえばある契約をしていて、法律が変わり、新しい契約をする必要が出てきたとします。新しい契約に従えば、前と同じような履行がされるとします。個々で大事なのは、契約の主体は、法律が変わる前に契約をしていた人ですよね。つまりユダヤ人なわけです。つまり契約が置き換わっただけで、ユダヤ人が選ばれているのは変わりないという解釈もできます。
一方で、WIKIによれば「It holds the view that the Christian Church has succeeded the Israelites as the definitive people of God」とあります。ここでは、イスラエル人からキリスト教会が、選民性を引き継いだとも受け取れます。主体が人種から教会に変わったというのは、正直よくわかりません。
2:6
神は、おのおのに、そのわざにしたがって報いられる。2:7
すなわち、一方では、耐え忍んで善を行って、光栄とほまれと朽ちぬものとを求める人に、永遠のいのちが与えられ、2:8
他方では、党派心をいだき、真理に従わないで不義に従う人に、怒りと激しい憤りとが加えられる。2:9
悪を行うすべての人には、ユダヤ人をはじめギリシヤ人にも、患難と苦悩とが与えられ、2:10
善を行うすべての人には、ユダヤ人をはじめギリシヤ人にも、光栄とほまれと平安とが与えられる。2:11
なぜなら、神には、かたより見ることがないからである。ローマ人への手紙(口語訳)#2:6 『新約聖書』中の一書で、使徒パウロの手によるとされる書簡
一方で、新約聖書では選民思想がないような根拠もあります。つまり人種によらず、誰にでも救いは開けているといった考えです。
これもまた使徒パウロによるものです。さきほどのパウロの価値観も、やはり人種によらないという価値観であり、イエス・キリストの新しい契約を結びさえすればだれにでも救いは開けているということでしょうか。
その意味では、二重の神でいうところの慈愛に満ちた神のイメージになりますね。しかし、後で見ますがパウロは「予定説」的な考えも持っているように思えます。矛盾を感じざるを得ません。
ある意味では、人種によらず、だれにでも救いは開けているが、救われるかどうかは最初から決まっているのかもしれません。神は全能なので、未来を見通すことも可能であり、だれが善行をするかも予めわかっているという思想かもしれませんね。
参考資料
選民
予定説の聖書的な根拠について:エフェソの信徒への手紙(新約聖書)
私が気になるのは、「一部の人のみが救われる」ということをどうやって人間が知ることができたのか?ということです。おそらく聖書のどこかに書いてあるのでしょう。何処にだろう。プロ倫の注釈にありました。助かります。
カルヴィニズムの教説に関する以上のような抽出は、かなり似た形で、たとえばHoornbeek,Theo-logia practica(Utrecht,1663),L,Ⅱ c. 1:de praedestinatione(予定について)──この生姜De Deo(神について)という表題の”すぐ”後に続いていることが特徴的だ──にも読み取ることができる。Hoorn-beekのばあい、聖書の典拠は主として〔エペソ人への手紙〕第一章だ。──予定や神の摂理を個人の責任と調和させて、経験的な意思の『自由』を救おうとする、さまざまな首尾一貫しない試み──そうした試みは、すでにアウグスティヌスが最初にこの教説を構想した時から始まっている──については、ここで討究する必要はあるまい。
(「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」、155-156P、マックス・ウェーバー、大塚久雄訳、岩波文庫、1989初版、2006年第39版)
「エペソ人への手紙(エフェソ信徒への手紙)」は新約聖書のひとつです。伝承では紀元62年ごろ、ローマで獄中にあった使徒パウロが小アジアのエフェソ(エフェソス)のキリスト者共同体にあてて書いたものだそうです。
1:1
神の御旨によるキリスト・イエスの使徒パウロから、エペソにいる、キリスト・イエスにあって忠実な聖徒たちへ。1:2
わたしたちの父なる神と主イエス・キリストから、恵みと平安とが、あなたがたにあるように。1:3
ほむべきかな、わたしたちの主イエス・キリストの父なる神。神はキリストにあって、天上で霊のもろもろの祝福をもって、わたしたちを祝福し、1:4
みまえにきよく傷のない者となるようにと、天地の造られる前から、キリストにあってわたしたちを選び、1:5
わたしたちに、イエス・キリストによって神の子たる身分を授けるようにと、御旨のよしとするところに従い、愛のうちにあらかじめ定めて下さったのである。1:6
これは、その愛する御子によって賜わった栄光ある恵みを、わたしたちがほめたたえるためである。1:7
わたしたちは、御子にあって、神の豊かな恵みのゆえに、その血によるあがない、すなわち、罪過のゆるしを受けたのである。1:8
神はその恵みをさらに増し加えて、あらゆる知恵と悟りとをわたしたちに賜わり、1:9
御旨の奥義を、自らあらかじめ定められた計画に従って、わたしたちに示して下さったのである。1:10
それは、時の満ちるに及んで実現されるご計画にほかならない。それによって、神は天にあるもの地にあるものを、ことごとく、キリストにあって一つに帰せしめようとされたのである。1:11
わたしたちは、御旨の欲するままにすべての事をなさるかたの目的の下に、キリストにあってあらかじめ定められ、神の民として選ばれたのである。1:12
それは、早くからキリストに望みをおいているわたしたちが、神の栄光をほめたたえる者となるためである。1:13
あなたがたもまた、キリストにあって、真理の言葉、すなわち、あなたがたの救の福音を聞き、また、彼を信じた結果、約束された聖霊の証印をおされたのである。1:14
この聖霊は、わたしたちが神の国をつぐことの保証であって、やがて神につける者が全くあがなわれ、神の栄光をほめたたえるに至るためである。出典 エフェソの信徒への手紙 第一章 ※一章は23節まであります
予定説において重要な文章は、「わたしたちは、御旨の欲するままにすべての事をなさるかたの目的の下に、キリストにあってあらかじめ定められ、神の民として選ばれたのである(1:11)」ですよね。救われるかどうか、神の民に選ばれたかどうかは、予め決定されているということです。
参考資料
カトリックとプロテスタント(カルヴァン)の決定的な違い、及び呪術からの解放について
最後に、神さえも助けえない、──キリストが死に給うたものもただ選ばれた者だけのためであり、彼らのために神は永遠の昔からキリストの贖罪の死を定めてい給うたのだからだ。このこと、すなわち教会や聖礼典による救済を完全に廃棄したということ(ルッタートゥムではこれはまだ十分に徹底されていない)こそが、カトリシズムと比較して、無条件に異なる決定的な点だ。”世界を呪術から解放する”という宗教史上のあの偉大な過程、すなわち、古代ユダヤの預言者とともにはじまり、ギリシャの科学的思考と結合しつつ、救いのためのあらゆる呪術的解放の過程は、ここに完結をみたのだった。真のピュウリタンは埋葬にさいしても一切の宗教的儀式を排し、歌も音楽もなしに近親者を葬ったが、これは心にいかなる》superstition《『迷信』をも、つまり呪術的聖礼典的なものが何らか救いをもたらしめうるというような信頼の心を、生ぜしめないためだった。
(「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」、157P、マックス・ウェーバー、大塚久雄訳、岩波文庫、1989初版、2006年第39版)
この文章を学生の頃初めて読んだ時、脳内に電気が走りましたね。これは恩恵の項目の確認でもあります。呪術的聖礼典は救いをもたらさない。現世でのいかなる善行も、救いをもたらさない。なぜなら、神ははるか昔にだれが救われるかを決めているからです。
ルターとカルヴァンが聖餐論で食い違ったのも、ある意味ではそうした違いかもしれません。ルターは「パンとぶどう酒の実体は変わらず、パンとぶどう酒の実体と共にキリストの体と血の実体が共に現存する」と考え、カルヴァンは「聖餐のパンとぶどう酒自体は、パンそのもの、ぶどう酒そのものであり、何物にも変わることはないが、キリストの霊的な臨在がパンとぶどう酒に伴うものとする」と考えたそうです。
ルターのこのような考え方は「共在説」といいます。カルヴァンのこのような考え方は「臨在説」といいます。ちなみにツヴィングリは「パンと葡萄酒にはいかなる意味においてもキリストのからだと血は実在せず、キリストを象徴する記号にすぎない(象徴説)」を主張しました。このように、同じプロテスタントでも派閥によって考えが違います。共通しているのは、信仰(信じること)が重要視されるということです。
ちなみに伝統的なカトリックの考えでは、「パンと葡萄酒は聖別されると、実体的にキリストのからだと血に変化する」という「化体説」らしいです。
パンとぶどう酒はただの物にすぎない、というプロテスタント的な考え方は共通していますよね。これは呪術的ものからの解放の一つだと思います。それがいいかわるいか、という価値判断はおいておいて重要な話です。
つまり、それを欲しさえすれば、どんなことでもつねに学び知ることが”できる”ということ、したがってそこにはなにか神秘的な、予測しえない力がはたらいている道理がないということ、むしろすべての事柄は原則上”予測”によって”意のままになるということ”、──このことを知っている、あるいは信じているというのが、主知化しまた合理化しているということの意味なのである。ところで、このことは魔法からの世界解放(エントツアウベルンク・デア・ウエルト)ということにほかならない。こんにち、われわれはもはやこうした神秘的な力を信じた未開人のように呪術に訴えて精霊を鎮めたり、祈ったりする必要はない。技術と予測がそのかわりをつとめるのである。そして、なによりもまずこのことが合理化の意味にほかならない。
(『職業としての学問』、マックス・ヴェーバー、尾崎邦雄訳、岩波文庫、33P)
私がウェーバーで最も好きな文章は『職業としての学問』のこの文章です。文脈は少し違いますが、呪術からの解放、魔法からの世界解放は似ていますよね。近代化とは呪術や魔法からの解放であり、宗教改革以降にそれは特に加速しました。魔法から世界を解放すべきであったか、脱魔術したこの現代世界でどう生ければいいのか、世界はどうあるべきか、どの方向に進むべきかといった壮大な話は今は置いておきます。しかし世界がどう変遷してきたかという歴史的な事実を知ることはそのために必要となると思います。
参考文献
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
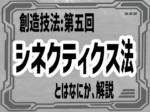
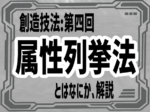
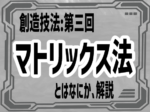
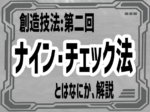
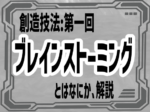
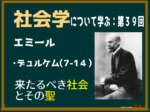
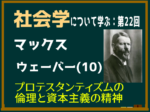
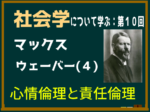
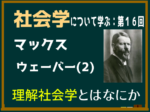
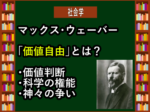
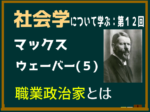
この記事へのコメントはありません。