- Home
- マックス・ウェーバー
- 【基礎社会学第四回】マックス・ウェーバーの価値判断や価値自由とははなにか?
【基礎社会学第四回】マックス・ウェーバーの価値判断や価値自由とははなにか?
- 2021/11/16
- マックス・ウェーバー
- コメントを書く
Contents
マックス・ウェーバーとは
今回の抑えておきたいキーワード
- 「価値判断」
- 「価値自由」
- 「4つの科学の権能(手段の適応度の検証、随伴結果の予測、目的の根底にある理念の解明、目的連関の形式論理的批判)」
- 「神々の闘争」
要約
- 価値判断とは?→何であるべきかという観点から対象を評価すること
- 価値自由とは?→ひとりひとりの個人が、実践的価値と科学的事実認識とを、別種の精神活動として峻別した上、両者を緊張関係において区別して堅持すること、自己制御
- 科学の権能とは?→「技術論的批判(手段の適応度の検証、随伴結果の予測)と「目的論的批判(目的の根底にある理念の解明、目的連関の形式論理的批判)
- 神々の闘争(神々の争い)とは?→ある特定の価値のみが絶対的に正しいということはなく、それぞれの価値が互いに争い合っていること
動画での解説・説明
・この記事のわかりやすい「概要・要約・要旨・まとめ」はyoutubeの動画の冒頭にありますのでぜひ参照してください。
よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m
プロフィール
マックス・ウェーバー(1864~1920)はドイツの経済学者、社会学者、政治学者。28歳で大学教授を資格を得て、1905年に「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」を発表した。社会学の元祖ともいわれる。ウェーバーの研究異性化はタT・パーソンズの構造ー機能理論、A・シュッツの現象学的社会学、J・ハーバーマスの批判理論やシンボリック相互理論等々に引き継がれた。
マックス・ウェーバー、私は大好きです。全学者のなかで一番好きです。文献もなけなしのお金を費やしてできるだけほとんど買うようにしています。
したがって、マックス・ウェーバーに費やす記事の量は他と比較にならないほど多くなるというわけです。文献が手元にあるということは、引用もたくさん増えます(レポートの素材として提供できるので嬉しいです)。
マックス・ウェーバー関連の記事
・以前の記事
【基礎社会学第四回】マックス・ウェーバーの価値判断や価値自由とははなにか?(今回の記事)
・以後の記事
【基礎社会学第六回】マックス・ウェーバーの「理念型」とはなにか(概略編)
【基礎社会学第八回】マックス・ウェーバーの『職業としての政治』から「支配の三類型」を学ぶ。
【基礎社会学第十回】マックス・ウェーバーから「心情倫理と責任倫理」を学ぶ。
【基礎社会学第十二回】マックス・ウェーバーの『職業としての政治』から「職業政治家」を学ぶ。
【基礎社会学第十四回】マックス・ウェーバーの社会的行為の四類型とはなにか
【基礎社会学第十六回】マックス・ウェーバーの「理解社会学」とはなにか
【基礎社会学第十八回】マックス・ウェーバーの「官僚制」とはなにか
【基礎社会学第二十回】マックス・ウェーバーの「職業としての学問と神々の闘争」とはなにか(今回の記事)
【基礎社会学第二十二回】マックス・ウェーバーの「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」とはなにか
価値判断とはなにか?
価値判断とは
・価値判断(かちはんだん):ある事実が善いか悪いかといったような評価、判断のこと*1。何であるべきかという観点から対象を評価すること*2。事実についての記述的な判断(事実判断)に対して、価値的な評価を行なう判断。「あの花は白い」に対して、「あの花は美しい」という類(日本語大辞典)。例:戦争はよくない、自殺はよくない、貧困はよくない、食事中に音を立てるのはよくない、遺伝子組み換えはよい、生活保護はよい、富の分配はよい、死刑はよい等
まずは「社会政策」と「社会科学」について区別する必要があります。あるいは「政策」と「科学」の区別です。
- 政策:特定の理想から、社会生活のなんらかの状態につき、「望ましい」ないし「望ましくない」という価値判断をくだし、その状態を実現ないし克服しようとする実践的な企て
- 科学:ひたすら事実を認識し、普遍的に(ということはつまり、理想ないし価値判断のいかんにかかわりなく)妥当する真理を追求する活動
- (問い)社会政策を科学によって批判することは可能か?
そもそも「物理科学」のような科学と同じように、「社会科学」というものが可能なのか?という問題でもあります。社会科学において価値判断をしないような妥当する真理といいうものはあるのか?という話です。マックス・ウェーバーによればそういったものは「ない」そうです。いかなる概念にも「価値判断(主観)」が紛れ込んでいるそうです。
たとえば「農業」、「分配」、「生産性」、「公衆衛生」といった一見自明とされるような概念ですら価値判断が紛れています。このような概念を多くの人が同じような価値判断をしているからといって、客観的に妥当な、物理科学のような普遍的に妥当する真理、客観的事実のように捉えてはいけないということです。これが次に検討する「価値自由」の主な概要になります。
今回の話をはそれてしまいますが、社会科学だけではなく自然科学においても概念はほとんどすべて価値判断が紛れています。自然科学でさえも、ある時代の特定の現象に対する価値づけにすぎないのです。この問題はトーマス・クーン、ライヒ、ベイトソン等で掘り下げて扱う予定です。
価値自由とはなにか?
価値自由とは
・価値自由(かちじゆう):事実と価値をはっきりとわけ、主観的な価値観から自由になること*1。対象が何であるのかを認識する事実認識と、何であるべきかという観点から対象を評価する価値判断とを区別すること*2。認識と価値判断とを区別する能力、事実の真理を直視する科学の義務と、自分自身の理想を養護する実践的義務との両方の堅持*3。価値からの自由と、価値への自由の両面を含んだもの*4。ひとりひとりの個人が、実践的価値と科学的事実認識とを、別種の精神活動として峻別した上、両者を緊張関係において区別して堅持すること、自己制御*5。社会科学のいかなる命題も、根本的には何らかの価値判断を前提とせざるを得ないということ、そしてこの点をはっきりと自覚している必要があるということ*6。社会科学の営みが「理念型(現実のある側面を抽出してそれを純化した一種のユートピア)」の提示でなければならないことを認めたうえで、他の「理念型」の構成に対しても開かれた態度で接するということ*7。
社会科学にたずさわる人間は一切の価値判断にとらわれてはならず、ひたすら客観的事実を追求するべきだ、といったものではないというところがポイントです。社会科学において純粋に客観的な立場というものは歴史や文化を対象としている限り、存在し得ないそうです。常に主観的な価値判断が入ってくるのです。
まずは社会科学にできることを整理し、そして自分の中の価値判断(理念)とはなにかを解明し、事実と価値を区別し、さらに読者にもその区別をわかりやすく提示する必要があるということです。
科学にできること、つまり科学の権能(けんのう)について次の項目で扱います。ざっくり言えば、科学は「なにをするべきか」について人間に教えることはできず、「なにができるか」、及び「なにを意欲しているか」についてしか教えることができません。
たとえば自分がお金持ちの家に生まれていて、親から「貧乏人は努力していないから貧乏なんだ」と教えられて育てられたとします。その人の価値判断は意識・無意識に関わらず「貧乏人は努力していないから貧乏なんだ」というものが刷り込まれていきます。その人が実務家になり、経済政策を考える立場になったとします。国の財政が圧迫されているという状態で、財政の支出を減らすという「目的」のために、いままで貧しい人のために下げていた税金を、豊かな人と同じくらいまでに上げるべきだ、という「手段」をとるとします。たしかに貧しい人から税金を多く取れば、財政の収入は増えるかもしれません(単純な思考実験なのでその他の複雑な随伴結果は考えないことにします)。
このケースでは、この実務家は「貧乏人は努力していない怠け者で悪いやつだから、税金を下げずに上げるべきだ」という価値判断をしてしまっています(意識・無意識問わずにです)。自分はなぜ目的のための手段としてこれを選んだのだろうか?どういう価値判断をしてしまっているのだろうか?と明確にする必要があるのです。事実認識と価値判断を区別して、それでもやはり貧乏人から税金を上げるべきだと考えれば、それはその実務家が責任を持って選ぶべきだということです。
もし価値判断に自分で気づき、「貧乏人は努力していても、親の環境で大学に行けず、貧しい環境がつねに再生産されてしまっているのかもしれない」という事実認識が新たに加わるかもしれません。もしそうなら、大学に行きやすいように援助してあげよう、そうすれば大学できちんとまなび、最終的には生産性が上がり、国の財政も回復するかもしれない、という発想になるかもしれません。
重要なのは「貧乏人は努力していないから貧乏なんだ」といったような価値判断を客観的な事実のように混同してはいけないということです。これがマックス・ウェーバーのいう価値自由なのです。政策において一切価値判断をしてはいけないということではないのです。
たとえば、「貧しい人が豊かになれるように富を分配する」という価値判断を主観を超えて、”客観的に妥当”だと考える人がいるとします。こうした価値判断に基づいて主張すること自体を否定していません。しかし、こうした価値判断や当為の「妥当」を事実認識の経験的妥当と混同してはいけないということです。
すこし難しいですね。「自殺は減らすべきである」という価値判断が、自分だけでなく他の多くの人もそう考えていて、客観的に妥当だと考えるとします。しかし多くの人が価値判断しているからと言って、「自殺は減らすべきである(価値判断)」ということが「火に水をかけると消える(事実認識)」と混同してはいけないということです。
「こうあるべきだ」というような当為や価値判断は事実認識から生まれないのです。「こうなっている」ということしか経験科学は教えてくれないのです。重力は「こういうふうになっている、こういうふうに作用する」ということはわかっても、「重力はこうあるべきだ」というのはわからないわけです。こうした問題は、「人間が生きる意味はあるのか」について経験科学が答えられないのと同じです。もっと言えば哲学を含む他の”学問”でも答えることができる問題ではありません。では宗教か?という話になりますが、それこそ宗教同士で対立しているように、神々の闘争であり、価値判断の闘争になるわけです。宗教の力が小さくなってきた今、さらに神々の闘争は規模が大きくなり、神の数が増えています。
※「理念型」については次回扱います。
※価値や当為の妥当は経験科学の課題ではなく、思弁哲学の問題だそうです(ただし思弁哲学が答えられるとはいっていない)。
そもそも(社会)科学とはなにか?
社会学とは
「社会学そのものとは何か。これは特に目新しい見解ではありませんが、社会秩序というものの存在に驚くセンスといいますか、社会秩序というものがいろいろ破れ目はありながらも存在していることの不思議を説い続ける、という部分があれば社会学でありましょう。社会秩序と大げさに呼ばなくても、本来見知らぬもの同士であった人々が、直接間接にかかわりあいながらなんとか行きている状態、と平たく言い換えて良かろうと思います」(小川 2005:25)
ここにはジンメルとデュルケムの教えがへいいな日本語で要約されて述べられている。社会学が対象とするのは「本来見知らぬもの同士であった人々が、直接間接にかかわりあいながら生きている状態」である。これはジンメルのいう「相互作用」である。しかも「なんとか」生きているのであり、そこにはかならず「破れ目」があるのである。これは、デュルケムがいうように、社会は適切な行為だけから成り立っているのではなく、社会にはかならず不適切な行為が含まれるということである。小川はさらに続けて「そのような状態の正邪を判断する前に、とにかくこれを可能にしているしくみや価値や関係のあり方を眺めてまずは驚く」(小川 2005:25)ことだという。これはウェーバーのいう「価値自由にほかならない」
「社会学」、有斐閣、23P
※太文字は引用者
これは名文ですね。デュルケムを学んだ後にウェーバーを学ぶからこそ見えてくるものがあります。ジンメルは次に扱いたいです。
デュルケムは「犯罪とは正常なものである」といいました。なぜなら社会に規範や秩序があるということの証だからです。もし聖者だけの社会であっても、そのなかの社会でまた犯罪が定義されるだけです。たとえば食事中に音を立てるといったような、我々の社会では犯罪とはみなされないようなものが、新たにその社会では犯罪とみなされるということです。
食事中に音をたてるということがなぜ悪いのか?音をたてないということがなぜ良いのか?そうしたものも「価値判断」のひとつです。「食事中に音を立てている」というのは「事実判断」です。どうして食事中に音を立てることを悪いことだと思うのか?そうした価値や関係のあり方はどうなっているのか?と事実と価値を区別して冷静に分析することが「価値自由」なのです。
たとえば日本では蕎麦は音をたてても怒られませんが、フランスで同じことをしたら怒られるかもしれません。フランス人の中では多くの人が「食事中に音を立てる」ということを悪いことだと思っているため、あたかもそれが「客観的に妥当な価値」や「真理」であるように混同してしまうかもしれません。ウェーバーは事実と価値を混同せずに区別し、価値判断を明らかにして、その上で責任を持って判断をしていくべきだといいます。
価値判断と科学
一見、価値判断とは、究極において特定の理想を基礎とし、それゆえ「主観的な」起源に発するものであるから、そうした価値判断は、科学的討論からおよそ排除されなければならない、との帰結が生ずるようにも思われよう。しかし、じつは、けっしてそうではない。われわれの雑誌にじっさいに掲載される論文の内容からも、それが掲げる目的からも、そうした命題は、たえず否認されていくだろう。批判は、価値判断のまえでも立ち止まりはしない。
問題はむしろ、理想や価値判断にかんする科学的批判とは、なにを”意味し”、なにを目的とするのか、という点にある。ところで、この問題に答えるには、今少し立ち入った考察を必要とする。
「社会科学と社会政策にかかわる認識の『客観性』」、マックス・ウェーバー、富永祐治・立野保男訳、折原ヒロシ補訳、岩波文庫、30P
ここで述べられている通り、価値判断とは「究極において特定の理想を基礎とし、主観的な起源に発するもの」です。たとえば「売春」について良いか悪いか、存在するべきかどうかというのは価値判断です。個人的な「こうあるべき」といいう理想に基づいているからです。監視社会の善悪、遺伝子組み換えの善悪、自殺の善悪等々、これらも価値判断になります。
あるべきこと、なすべきことを「当為(とうい)」といい、ドイツ語ではSollenといいます。そうあってほしいというような状態を「理想」といいます。当為や理想は価値判断になります。自殺は何人だった、というのは「事実」です。自殺はなくなるべきだ、なくなったほうが望ましいといったものは「価値」であり「価値判断」です。ちなみに存在や実在をドイツ語で「sein」といいます。価値自由はsollen(ゾレン)とsein(ザイン)を区別しようという立場です。
マックス・ウェーバーによれば、こうした価値判断は科学的討論から排除されるものではないといっています。価値判断だからダメ!というわけではないのです。一方で、価値自由をマックス・ウェーバーは主張しています。価値自由とは、没価値や価値中立ともいわれ、事実と価値を区別し、主観的な価値観から自由になることを意味します。つまり価値判断を避けるべきである、とも読み取れます。
混乱しますよね。価値判断は科学的討論から排除されるものではないが、科学的客観性を保つためには価値判断は避けたほうがいい、というようなことになってしまいます。問題はなぜ価値判断は科学的討論から排除されるものではないかです。
科学の権能について
- 手段の適応度の検証
- 随伴結果の予測
- 目的の根底にある理念の解明
- 首尾一貫性を基準とする理念ー目的連関の形式論理的批判
- 1と2を「技術論的批判」、(3を前提とした)4を「目的論的批判」という
[主観的に抱かれた]意味をそなえた人間の行為につき、思考を凝らして、その究極の要素を抽出しようとすると、どんなばあいにもまず、そうした行為が「目的」と「手段」の範疇[カテゴリー]に結びついていることが分かる。われわれがあるものを具体的に意欲するのは、「そのもの自体の価値のため」か、それとも、究極において意欲されたもの[の実現]に役立つ手段としてか、どちらかである。
ところで、まず疑いなく、科学的考察の対象となりうるのは、[1]目的が与えられたばあい、[考えられる]手段が、どの程度[その目的に]適しているか、という問いに答えることである。われわれは、(われわれの知識の、そのときどきの限界内で)”いかなる”手段が、ある考えられた目的を達成するのに適しているか、それとも適していないか、ある妥当性をもって確定することができる。だから、このようにすれば、採用可能な特定の手段で、ある特定の目的をおよそ達成できるかどうか、その客観的可能性[シャンス]がどの程度か、見積もることができる。
ということはつまり、間接的には当の目的を立てること自体をも、そのときどきの歴史的状況[の知識]に照らして[採用可能な適合的手段が見いだせるから]実践上意味があるとか、あるいは、与えられた事情に照らして[採用可能な適合的手段が見当たらないから]無意味である、というふうに批判できる、ということである。
さらに、われわれは、[2]”もし”ある考えられた目的を達成する可能性が与えられているように見える”ばあい”、そのさい必要とされる[当の]手段を[現実に]適用することが、あらゆる出来事のあらゆる連関[にいやおうなく編入されること]をとおして、もくろまれた目的のあいるべき達成の”ほかに”、いかなる[随伴]結果をもたらすことになるかを、当然つねに、そのときどきのわれわれの知識の限界内においてではあるが、確定することができる。そうすることで、われわれは、行為者を助けて、かれの行為の”意欲された”結果と、”意欲されなかった”この[随伴]結果との[相互]秤量ができるようにする。
すなわち、われわれは、意欲された目的の達成が、予見できる出来事の連鎖を介して、”他の”いかなる価値を損なうことになるか、そうした形でなにを「”犠牲にする”」か、という問いに答えることができる。
大多数のばあい、もくろまれた目的の追求は”ことごとく”、この意味でなにかを犠牲にする、あるいは少なくとも犠牲にしうるから、責任をもって行為する人間の自己省察で、目的と結果との相互秤量を避けて通れるようなものはない。
とすれば、そうした相互秤量を可能にすることこそ、われわれがこれまでに考察してきた[科学にもとづく]技術的批判の、もっとも本質的な機能である。
ところで、この秤量自体に決着をつけること[目的を採って犠牲を甘受するか、それとも、目的を断念して犠牲を避けるか、どちらかを選択すること]は、もとより、もはや科学のよくなしうる任務では”なく”、意欲する人間の課題である。そこでは、意欲する人間が、自分の良心と自分の個人的な世界観とにしたがって、問題となっている諸価値を評価し、選択するのである。科学は、かれを助けて、”あらゆる”行為、したがって当然、事情によっては行為”しない”こともまた、それぞれの帰結において、特定の価値への加担をも意味し、したがって通例──このことは、今日とかく誤認されがちであるが──”他の”諸価値”に対しては敵対する”ことになる、という関係を、”意識”させることはできる。しかし、選択を下すのは、意欲する人間の課題である。
「社会科学と社会政策にかかわる認識の『客観性』」、マックス・ウェーバー、富永祐治・立野保男訳、折原浩補訳、岩波文庫、30-33P
長い引用になってしまいました。この引用文は「科学の権能」についての説明です。つまり「科学にできること」です。
人間の行為が「目的」と「手段」のカテゴリーによって秩序付けられています。この分類は後に、「目的合理的(zbecknational)」と「価値合理的(wertrational)」の区別につながっていく重要なものです。あるいは「予想準拠的」と「価値準拠的」の区別につながっていくそうです。
1:目的と手段
[主観的に抱かれた]意味をそなえた人間の行為につき、思考を凝らして、その究極の要素を抽出しようとすると、どんなばあいにもまず、そうした行為が「目的」と「手段」の範疇[カテゴリー]に結びついていることが分かる。われわれがあるものを具体的に意欲するのは、「そのもの自体の価値のため」か、それとも、究極において意欲されたもの[の実現]に役立つ手段としてか、どちらかである。
※「意欲する」とは積極的にやろうとする意思のことです。
たとえば会社に行くという行為を見てみましょう。ほとんどの人は、「お金を稼ぐため」という「手段」のはずです。しかし一部の人は、お金の有無に関わらず、仕事すること自体が目的という人もいます。このように、人間の行為は「目的」と「手段」に分けるということができます。
ある人の究極の目的が「幸せに生きること」や「子孫を残すこと」だったとします。そのための手段として「お金を稼ぐ」というものがあり、さらにその手段として「会社に行く」という手段があります。会社に行くこと自体が幸せの場合は、会社に行くことそれ自体の価値のために会社に行くことになります。
2:所与の目的にたいする手段の適合度の検証と客観的可能性(シャンス)
ところで、まず疑いなく、科学的考察の対象となりうるのは、[1]目的が与えられたばあい、[考えられる]手段が、どの程度[その目的に]適しているか、という問いに答えることである。われわれは、(われわれの知識の、そのときどきの限界内で)”いかなる”手段が、ある考えられた目的を達成するのに適しているか、それとも適していないか、ある妥当性をもって確定することができる。だから、このようにすれば、採用可能な特定の手段で、ある特定の目的をおよそ達成できるかどうか、その客観的可能性[シャンス]がどの程度か、見積もることができる。
ということはつまり、間接的には当の目的を立てること自体をも、そのときどきの歴史的状況[の知識]に照らして[採用可能な適合的手段が見いだせるから]実践上意味があるとか、あるいは、与えられた事情に照らして[採用可能な適合的手段が見当たらないから]無意味である、というふうに批判できる、ということである。
まずは科学の権能の1つ目である「所与の目的にたいする手段の適合度の検証」を解釈していきましょう。
「所与(しょよ)」とは一般的に「解決されるべき問題の前提として与えられたもの」です。
たとえば「自殺を防止する」という政策を考えてみましょう。この場合、所与の目的は「自殺を防止すること」にあります。自殺を防止する手段はどのようなものが考えれられるでしょうか。心の悩みを気軽に連絡できる自殺防止センターといったものをつくる、地域コミュニティのつながりを強化する、云々と考えられます。こういった手段が目的に適しているか?と考えてみることが重要です。
折原浩さんによる巻末の解説の例では「戦争が自殺率を下げる」という話がありました。これはデュルケームの自殺論でも学んだとおりですね。自殺を防止するという目的のために、手段として戦争は適しているか?と考えてみます。もし戦争が本当に自殺を下げるのだとすれば、自殺率を下げるという目的のために戦争という手段は適合している(適応度が高い)ということになります。
しかし一方で、戦争は倫理的に望ましくないですよね。つまり価値判断的にいえば戦争は善悪どちらかといえば、悪になるわけです。科学の機能は戦争が善か悪かという価値判断をすることではなく、戦争がどのくらい自殺率を下げるかという事実など提供にあります。
さらに、われわれは、[2]”もし”ある考えられた目的を達成する可能性が与えられているように見える”ばあい”、そのさい必要とされる[当の]手段を[現実に]適用することが、あらゆる出来事のあらゆる連関[にいやおうなく編入されること]をとおして、もくろまれた目的のあいるべき達成の”ほかに”、いかなる[随伴]結果をもたらすことになるかを、当然つねに、そのときどきのわれわれの知識の限界内においてではあるが、確定することができる。そうすることで、われわれは、行為者を助けて、かれの行為の”意欲された”結果と、”意欲されなかった”この[随伴]結果との[相互]秤量ができるようにする。
すなわち、われわれは、意欲された目的の達成が、予見できる出来事の連鎖を介して、”他の”いかなる価値を損なうことになるか、そうした形でなにを「”犠牲にする”」か、という問いに答えることができる。
大多数のばあい、もくろまれた目的の追求は”ことごとく”、この意味でなにかを犠牲にする、あるいは少なくとも犠牲にしうるから、責任をもって行為する人間の自己焼殺で、目的と結果との相互秤量を避けて通れるようなものはない。
客観的とは一般的に「主観または主体を離れて、独立の存在であるさま。だれが見てももっともだと思われるような立場で物事を考えるさま」です。たとえば自殺の人数は~人であるというのは客観的なものです。A子ちゃんはかわいいというのは主観的なものです。戦争時に自殺率が下がっているというデータも客観的なものです。ここから、戦争は自殺率を下げるという事実を導き出すことができます。
「自殺率を下げるという目的」のために、「戦争という手段」はどの程度客観的可能性(シャンス)があるか?という話です。統計データから考えれば、戦争という手段は自殺率を下げると客観的可能性(シャンス)があるという話になります。科学はこのようなシャンスを人間に提供できる権能があるわけです。
客観的可能性は「公算(こうさん)」、つまりそのことが起こることの確からしさの度合い、見込み、確率だというわけです。
3:特定の手段を採用するばあいに生じる随伴結果(Nebenerfolge)の予測
「さらに、われわれは、[2]”もし”ある考えられた目的を達成する可能性が与えられているように見える”ばあい”、そのさい必要とされる[当の]手段を[現実に]適用することが、あらゆる出来事のあらゆる連関[にいやおうなく編入されること]をとおして、もくろまれた目的のあいるべき達成の”ほかに”、いかなる[随伴]結果をもたらすことになるかを、当然つねに、そのときどきのわれわれの知識の限界内においてではあるが、確定することができる。そうすることで、われわれは、行為者を助けて、かれの行為の”意欲された”結果と、”意欲されなかった”この[随伴]結果との[相互]秤量ができるようにする。
すなわち、われわれは、意欲された目的の達成が、予見できる出来事の連鎖を介して、”他の”いかなる価値を損なうことになるか、そうした形でなにを「”犠牲にする”」か、という問いに答えることができる。
大多数のばあい、もくろまれた目的の追求は”ことごとく”、この意味でなにかを犠牲にする、あるいは少なくとも犠牲にしうるから、責任をもって行為する人間の自己焼殺で、目的と結果との相互秤量を避けて通れるようなものはない。」
「社会科学と社会政策にかかわる認識の『客観性』」、マックス・ウェーバー、富永祐治・立野保男訳、折原浩補訳、岩波文庫、30-33P
・随伴(ずいはん)とは一般的に「ある物事に伴って、他の物事が生じること」を意味します。たとえば10人のグループで1人しか勝者がいないようなゲームの大会があったとします。10人の中で1人勝者が生まれるということは、残り9人が敗者になるということを意味します。あるいはゲームで遊ぶことに時間を費やすことは、受験勉強をする時間を失うことでもあります。このように物事は多面的で、表裏一体のものです。

・秤量(ひょうりょう)とは一般的に「はかりで重さをはかること」です。天秤を考えるとわかりやすいですね。
たとえばゲームをすることを片方の秤に、受験勉強をすること(意欲した行為)、時間を失うこと(随伴結果)を片方の秤にのせたとします。どちらのほうが重視されるべきか?と考えることです。たとえばある人の目的が幸せになることであり、その手段として高学歴になることを選んだとします。単純に考えれば高学歴になるという目的のための手段としてゲームをすることという行為は適合していません。「楽しみたい」という目的のために手段として「ゲームをすること」を選んだとした場合は適合していますが、その随伴結果が「受験勉強の時間を失うこと」だった場合、相互秤量の結果、やはり「ゲームをするべきではない」ということになる場合があります。息抜きとしてはいいのではないか?失う時間の量は?などとさまざまな角度から分析する必要があります。
念のため補足すれば、(1)科学は、「条件Xが結果Yを生ずる公算[客観的可能性]はどれくらいか」という因果関係を確定し、そこから、またそのかぎりで、「Yを目的とすれば、Xはちょうどそれだけの適合度をそなえた手段となり”うる”」という帰結を引き出すことができる。また、(2)Yの実現を目指してXがインプットされるべき、現実の総体をそうした因果諸関係の構造連関として把握し、そこから、またそのかぎりで、Xのインプットが、Yの実現に通じる”以外の”因果連鎖をたどり、目指されたYの達成”以外に”、いかなる[意図せざる随伴]結果Z[「副作用」「副産物」]を生ずるか、その客観的可能性を予測することができる
193P
先程の折原さんの巻末の説明をまずは引用してみます。マックス・ウェーバーの文章はなかなか難しいので、後半の説明のほうがわかりやすかったりします。
戦争という手段は自殺率を下げるという目的のためには適合度の高い手段と考えることができます。しかし戦争という手段をとったときに、その随伴結果となるものはなんでしょうか?多くの兵士、多くの民間人、多くの施設、多くの自然が戦争の犠牲になります。こうした犠牲が起こりうるという客観的可能性(シャンス)も高いわけです。
図にしてみました。実際にこうした判断を下すためには、どのような規模の犠牲が生じる戦争なのかを明確にしないといけません。極論を言えば、ひとが誰も死なないような戦争という形態もありうるのです。
上の図でいうところの、「戦争は自殺率を下げる」と「戦争は犠牲が大きい」というものは客観的可能性(シャンス)です。事実か価値か、ゾレンかゾルレンかでいえば事実なのです。一方で、戦争は善くないという判断は、価値判断になります。
仮に、戦争による犠牲が小さかったとします。しかし、科学者が個人的な信仰などによって「戦争はよくない」と判断し、戦争は自殺率を下げるための手段としては採用しないという判断もできるわけです。これは価値判断による政策の決定です。
ウェーバーによれば、最終的に選択するのは科学の任務ではなく、意欲する人間の課題であり、責任や良心を持って科学者は選択するべきだといっています。
4:目的の根底にある理念の解明
ところで、意欲する人間がこうした決断をくだすさい、さらにわれわれが提供できるのは、[3]意欲されたものの”意義”にかんする”知識”である。われわれは、具体的な目的の根底にある、あるいはありうる「理念」を、まずは開示し、論理的な連関をたどって展開することにより、かれが意欲し、選択する目的を、その連関と意義に即して、かれに自覚させることができる。
というのも、人間の文化生活にかんするあらゆる科学のもっとも本質的な任務のひとつは、いうまでもなく、こうした「理念」──そのために、現実に、あるいは想像の上で、闘いがなされてきたし、現に闘いがなされている「理念」──を解明して、精神的に理解させることにある。この課題は、「経験的現実の思考による秩序づけ」という科学の限界を踏み越えるものではない。もっとも、そうした精神的価値の解明に用いられる手段は、普通の意味における「帰納」ではない。
なるほど、この課題の少なくとも一部分は、普通、諸学科の分業関係のなかにあって特殊化されている専門経済学から、その枠外にはみ出るであろう。このばあい、問題は、”社会哲学”の課題となる。しかし、理念の歴史的な力は、社会生活の発展にとってきわめて強大であったし、いまなお強大であるから、われわれの雑誌は、けっしてこの課題との取り組みを避けず、むしろ、そうした取組の育成を、もっとも重要な義務のひとつに数えるであろう。
「社会科学と社会政策にかかわる認識の『客観性』」、マックス・ウェーバー、富永祐治・立野保男訳、折原浩補訳、岩波文庫、33-34P
重要なキーワードは「理念(りねん)」ですね。理念とは一般に、「ある物事についての、こうあるべきだという根本の考え」です。ドイツ語ではIdeenです。ある物事について、こうなっているという問題が「科学の事実認識」だとすれば、こうあるべきだという考えは「価値あるいは当為」の問題となります。繰り返しになりますが当為とはドイツ語ではsollenで、なすべきこと、あるべきことを意味します。
科学者はまずは自分の理念を開示するべきであるとウェーバーはいっています。たとえば「人の命は尊いもので、大切にするべきだ」という理念を私が抱いているとします。そうした理念を開示した上で、たとえ自殺率を下げるという目的のためであっても、「戦争」という命の犠牲が大きい手段はとらないという選択を私はします。
この場合、科学が提供できることは先程の「客観的可能性(シャンス)」、つまり目的のための手段の適合度や随伴結果といった判断材料です。それに加えてウェーバーは、「理念の解明」も科学の役割(本質的な任務)だといっています。
科学が人間に対して「こうあるべきだ」と教えるのではありません。ある人間が「こうあるべきだ」と無意識的あるいは意識的に思っていることを解明するということです。こうした解明はウェーバーによれば、科学の限界”内”だといいます。また、こうした取り組みは必要だといっています。しかしそうした取組は専門経済学の分野からはみ出し、社会哲学の課題になるそうです。この論文はもともと専門経済学の雑誌はどうあるべきか?についてのものなので、こうした言い方がされています。ウェーバーは経済学の雑誌であっても、社会哲学の分野の取り組みも重要な義務のひとつだといっています。
科学者は自分の理念について自分で解明するということが重要です。自分はこういう理念をもっていて、そうした理念に基づいて価値判断をする傾向があるということをまずは自覚することが重要なのです。
5:首尾一貫性を基準とする理念:目的連関の計式論理的批判
ところで、価値判断にかんする科学的な取り扱いは、さらに進んで、意欲された目的とその根底にある理想を、ただたんに理解させ、追体験させるだけでなく、とりわけ、それらを批判的に「評価する」ことをも、教えるものでありたい。もとより、”この”批判は、たんに弁証論的な正確をもちうるにすぎない。つまり、この批判にできることといえば、歴史的に与えられた価値判断や理念のなかにある素材を、形式論理的に評価すること、すなわち、意欲されたものが内面的に”矛盾を含んでいてはならない”という要請に照らして理想を吟味すること、にかぎられる。価値判断にかんする科学的扱いは、こうした目的を立てることにより、意欲する者を助けて、かれの意欲内容の根底にある究極の公理、すなわち、かれが無意識のうちにも出発点とし、あるいは──矛盾に陥らず、首尾一貫性を保つためには──出発点とせざるをえなかったはずの究極の価値基準を、みずから反省させることができる。
「社会科学と社会政策にかかわる認識の『客観性』」、マックス・ウェーバー、富永祐治・立野保男訳、折原浩補訳、岩波文庫、34-35P
※形式論理学: 思考の内容とはかかわりなく、ただ抽象的な推論形式だけで論じられる論法
たとえば私が「命は尊い」という理念をもっていたとします。自殺率を下げるために戦争という手段は好ましくない、となぜ思うのか?と解明していった結果、「命は尊ばれるべきである」という私の理念が解明されたと仮定します。科学はこうした私の理念に基づいて、形式論理的に手段の内容を批判することができます。形式論理的とは内容とは関わりのないものです(科学は個々人の理念(内容)に対して直接間違っているだとか、合っているという判断はできない)。
命は尊ばれるべきであるという理念を表明している(あるいは表明せずに抱いている)にも関わらず、命を粗末に扱うような手段を採用してる場合を考えてみます。たとえば、「命は尊ばれるべきである」と言っているにも関わらず、「アフリカの飢餓にたいする基金の設立」という手段に反対する理由といったような感じです。複雑に検討すれば話は変わるかもしれませんが、単純に考えれば「命は尊ばれるべきである」という理念を抱いているのにも関わらず、「飢餓にたいする基金の設立」に反対するというのは形式的に矛盾しています。思想と行動が一致していませんよね。このように科学は価値判断に対して、意欲するものに反省を促すこともできます。
ひとことでいえば、首尾一貫性をもたせるということですね。
価値への自由と価値からの自由
この点に関連して、著者は、「政策ないし目的の定立は『実務家』の課題であり、適合的手段の探索・提言が『科学者』の任務である」というふうな、一種の社会的分業を提唱したのでは”ない”。
著者自身は、そうした解釈を、後年の論文(社会学および経済学における《価値自由》の意味)[以下、価値自由論文]で、〈似非(えせ)非価値自由 psendowertrei〉な態度として斥けていた。
別の箇所では、〈あるべきもの das Seinsollen と あるもの das Seiende との混同に対して、あらゆる機会を捉えてこうも激しく反対する理由は、わたしが当為の問題を軽視するからではない。むしろ正反対に、世界を動かすほどの、最大の理念的意義を帯びる問題が……一専門学科の手に掛けられることに、我慢がならないからである。〉とも述べている。
著者の〈価値自由 Wertfreiheit〉とは、科学における「価値”からの”自由」と、実践における「価値”への”自由」との両面を含んでいる。上記の分業的解釈では「実践家」は「価値”からの”自由」を、「科学者」は「価値”への”自由」を、それぞれ失うことになろう。
著者はむしろ、後9段で表明されるとおり、”ひとりひとりの個人が”、実践的価値判断と科学的事実認識とを、別種の精神的活動として峻別した上、両者を緊張関係において〈区別して堅持する auseinanderhalten〉こと、この意味の醒めた自己制御を、真の〈価値自由〉として説いたのである。
「社会科学と社会政策にかかわる認識の『客観性』」、マックス・ウェーバー、富永祐治・立野保男訳、折原浩補訳、岩波文庫、P195-196P
※折原さんの説明文です
・価値への自由:価値判断を自由にすることができること。
・価値からの自由:価値判断から自由になること。
この説明を見る限り、社会学者(科学者)は事実と価値を区別し、価値を切り捨てろといっているわけではないことがわかります。科学者は事実だけ考えてればいい、価値判断をするのは実務家の課題だ!というような考えは誤りということです。たとえば学者が自殺率を下げる方法には戦争という手段も考えられます、と事実だけを提言して、政治家や役人が戦争という手段をとるかどうか価値判断を含めて決定するというような「分業」ではないということです。
しかし一方で、科学者が価値判断をすることにも否定的な態度をとっていたので、ややこしいですね。世界はこうあるべきだ、というような価値判断を専門学科(たとえば哲学や社会学等)に任せるというのも我慢できないともウェーバーはいっています。ウェーバーは価値判断を軽視しているのではなく、専門学科に価値判断を任せることに否定的だったということです。おそらくですが、価値判断は総合的に判断されるもので、一分野のみの専門学科で判断されることには我慢ならない、といったようなニュアンスでしょうか。
仮に科学者が「事実(科学的事実認識)」のみを、実務家が「実践的価値判断」のみを扱う「分業」体制だったとします。この場合、科学者は価値判断をすることができません。したがって、価値への自由を科学者は失うことになります。また、実務家は「価値判断」を避けることができません。したがって、価値からの自由を実務家は失うことになります。
こうした分業的な解釈を「似非価値自由」としてウェーバーは否定的な態度をとっていたそうです。
認識と価値判断とを”区別する”能力、事実の真理を直視する科学の義務と、自分自身の理想を擁護する実務的義務とを[双方を区別し、緊張関係に置きながら、ともに]果たすこと、これこそ、われわれがいよいよ十分に習熟したいと欲することである。
「社会科学と社会政策にかかわる認識の『客観性』」、マックス・ウェーバー、富永祐治・立野保男訳、折原浩補訳、岩波文庫、43P
ここですね重要な箇所は。
倫理的判断と趣味判断の違い、普遍妥当性について
だが趣味の良し悪し(gut und schlecht)の判断は、ウェーバーの行為の四類型に照らしていえば、アフェクショナル(affektuell)な行為の領域に属する事柄である。それは、ぎりぎりのところ主観的なものであって、甲乙の判定のつけがたいもの(die subjektivistische Unappaellabilitatjedes Geschmacksurtelis)である(WnG,5.Aufl.,S.366,邦訳創文社版『宗教社会科学』300ページ)。
……
それにたいして倫理的な善悪(gut und bose)の判断のばあいには、その規範は実践理性の働きに由来するものであり、そのかぎりで合理的なものであるから(のちにウェーバーは「合理的な倫理的態度決定」という言い方をするが、その「合理的」はこの意味で使われている)、倫理的規範の命ずるところが何であるか、またその規範に照らしていかなる行為が正当と見なされるべきかは、原則的に「討論可能(デイスクシオーンスフエーイヒ)」である(同上、邦訳301P)。つまり、倫理的判断のばあいには、(実践)理性の法定に訴え出ることによって、その当否、甲乙の決着をつけることが可能である(Appellabilitat ethisch gememeinter Urteile)。その意味において、倫理的規範は実践理性に照らして万人がそれにしたがいうる「普遍妥当性(アルゲマインギュルティヒ)」(同上、133P)をもつ。
ところで、アルゲマインギュルティヒなもの、万人に適用する規範なしには、ゲマインシャフトリヒなものであれ、ゲゼルシャフトリヒなものであれ、そもそも人間の社会生活は成り立たない。だから普遍妥当な倫理規範は、人間が共同生活をいとなむためになくてはすまされぬもの(Notwendigkeit)である。しかも人間の社会生活=秩序をいっそう安定させるためには、アルゲマインギュルティヒな規範は、各人の内面において多少とも血の通った動機づけを得る必要がある。法規範とはちがい、倫理規範はまさにこの機能を受けもつ。「中間考察」の以下のきじゅつはこの関連で述べられているものにほかならない。
「人々は倫理的に非難すべき行為に直面したとき、その行為を拒絶しながらも、決してそれを他人事とは思わず、自分もまた被造物として同じ誤ちをまぬがれないと考えて、倫理の規範に共にしたがおうとするのであるが、すくなくともその限りにおいて、倫理的規範の『普遍妥当性』は人々のあいだに共同体(ゲマインシャフト)をつくりだすものといえる(同上、133P)。」
こうしたウェーバーの観点からすれば、倫理的判断を趣味判断に置きかえることはもちろん許されない。それは社会的には「なくてすまされぬ合理的な倫理的態度決定の必要からの逃避(die Flucht vor der Notwendigkeitrationaler ethischer Stallungnahme)」である。そして、とウェーバーはいうのであるが、そうした逃避的態度は「救済宗教の目には、いかにも反友愛的心情の最たるものと見えもしよう」。
「知と意味の位相」、雀部幸隆、恒星社厚生閣、269-270P
価値判断は大きく分けて、趣味判断と倫理的判断にわかれるということです。たとえばピカソの絵が美しいというのは価値判断ですが、倫理的判断ではなく趣味判断です。しかし「老人に優しくするべきだ」というのは趣味判断ではなく、倫理的判断です。どちらも絶対的な真理というものはありません。
しかし倫理的判断の場合は、趣味判断に比べて人間の社会生活を成り立たせるために重要です。法律で罰せられない範囲、つまり法規範以外の良し悪しはすべて趣味判断の問題だ、というふうな状況を考えてみてください。人に優しくするかどうかはピカソが美しいかどうか、プリンがおいしいかどうかの問題と同列になった世界です。どこかギスギスして秩序がなく、不安定な社会のように思えます。
ウェーバーによれば倫理的判断の普遍妥当性は討論可能だそうです。討論可能ではあるが、それが真理のように客観的事実として存在しているということではないので注意です。これでは価値自由に反しています。たとえばほんとうに老人に席を譲るべきなのか?人に優しくするべきなのか?と討論自体は可能です。ある人は「優しくすることはそのひとのためにならない」と考えるかもしれません。ある人は「軽いいじめならいいじゃないか」と考えるかもしれません。しかし多くの人が、つまり普遍的に「人には優しくするべきだ」と考える人がいたなら、倫理的判断はその個別的な問題、その限りにおいて普遍妥当性をもつ、ということがいえるのかもしれません。
いずれにせよ確かなことは、ただひとつ、取り上げられる問題が「一般的」であればあるほど、ということはつまり、その文化”意義”が広汎にわたればわたるほど、経験的な知識という素材から[政策上の統制的価値基準]について一義的な回答を求めることはでき”なくなり”、信仰ないし価値理念という個々人の究極最高の公理が入り込んで、それだけものをいうようになるということである。
「社会科学と社会政策にかかわる認識の『客観性』」、マックス・ウェーバー、富永祐治・立野保男訳、折原浩補訳、岩波文庫、 39-40P
どういうケースであっても「人には優しくするべきだ」といったように一般化しすぎてはいけません。こういうケースだったら人には優しくするべきではないか、というように具体的に討論して普遍妥当性を決めていくのです。
神々の永遠の争い(神々の闘争)について、意味
・神々の闘争(かみがみのとうそう):「われわれの生活の究極の拠りどころとなりうべき立場は、こんにちすべてたがいに調停しがたくまた解決しがたくあい争っているということ、したがってわれわれは、当然これらの立場のいずれかを選定すべく余儀なくされているということ」。ある特定の価値のみが絶対的に正しいということはなく、それぞれの価値が互いに争い合っていること。
もとより、ここに述べたような考えは、人生が、その真相において理解されているかぎり、かの神々のあいだの永遠の争いからなっているという根本の事実にもとづいている。
比喩的でなくいえば、われわれの生活の究極の拠りどころとなりうべき立場は、こんにちすべてたがいに調停しがたくまた解決しがたくあい争っているということ、したがってわれわれは、当然これらの立場のいずれかを選定すべく余儀なくされているということ、がそれである。
このような事情のもとにあって学問がだれかの「天職」となる価値があるかどうかということ、また学問それ自身がなにかある客観的に価値がある「職分」をもつかどうかということ、──これはまたもやひとつの価値判断であって、この点については教室ではなにごとも発言しえないのである。なぜなら、教えるものの立場にとっては、この点を肯定することがその”前提”だからである。わたしく自身ももとより自分の仕事を通じてこの点を肯定している。そして、かの主知主義を最悪の悪魔として嫌う立場──この立場をこんにちの若いひとたちはとっており、しかも実は多くのばあいたんにとっているみずから想像しているにすぎないのであるが、こうした立場──にとってもまたそうであり、いな、こうした立場にとってこそとくにそうなのである。
それゆえ、この立場をとるものにたいしては、例の「気をつけろ、悪魔派年取っている、だから悪魔を理解するにはお前も年取っていなくてはならぬ」ということばが当てはまる。このことばは、どちらが早く生まれたかを問題にしているのではない。そうではなくて、もし悪魔を片付けてやろうと思うならば、こんにち好んでなされるようにこれを避けてばかりいてはならない、むしろ悪魔の能力と限界を知るために前もってまず悪魔のやり方を底まで見抜いておかなくてはならない、ということがこの言葉の意味なのである。
「職業としての学問」、マックス・ウェーバー、尾崎邦雄訳、岩波文庫、64-65P
※主知主義:認識論で、感覚主義や経験主義に対し、真理は理性によって得られると説く合理主義の立場。プラトン、アリストテレス、デカルト、カントの立場。
これがよく知られている「神々の永遠の争い」の説明です。他にも神とは「われわれの生活の拠りどころなりうべき立場」のことであり、「価値」のことです。神は理性だったり、感性だったり、お金だったり、女だったり、男だったり、ゲームであったり、仕事であったり、さまざまな形態があります。
要するにヤハウェの神は偶像崇拝を一切排除して唯一神たるかれを拝せよと人間に要求しているのであるが、この要求に心底からこたえることは人間わざでは到底できることではない(だから神の側からの働きかけ、つまり恩恵が必要なのだ、とルターはいうのだが)、なぜなら、人間という生き物は唯一の神、大文字の神には背をそむけながら、それぞれ思いのままに神々を拝し偶像を崇拝するものだからである、しかもその神々ないし偶像とはなにも文字どおり機会な様子をした彫像や画像である必要はない、女(男)であろうと金であろうと、はたまた理性であろうと、人がそれぞれ我を忘れて心酔し、心奪われ、崇拝するものが、とりもなおさず、その人にとっての神ないし偶像だからである。
嘘だと思うなら自分の胸に手を当ててよく考えてみよ。こういった趣旨のことをルターはそこで述べている。
これはなかなか鋭い人間洞察といわなくてはならない。この伝でいけば、われわれの大抵のものは、一時的にか恒久的にか神々を崇拝し、偶像に身を捧げている。「科学的」社会主義者も例外ではない。なぜなら、かれらも「科学」を信仰しているからである。それはともかく、いずれにしても神々への信仰(偶像崇拝)は人類の歴史とともに古い。それは人間の本性のようなものである。その神々への信仰が、唯一神への信仰(ないし世界史上それに肩を並べる救済宗教)の「重し」が取り去られた今(ウェーバーによれば、現代は「神なく預言者なき時代」である)、装いも新たに、おおっぴらに復活した(「神々の復活」と「神々の闘争」の時代としての現代)。それが先の四つの救済追求である。
「知と意味の位相」、雀部幸隆、恒星社厚生閣 255-256P
たしかに「生きる意味はなにか」と考えても正直よくわかりません。私は特定の宗教を信仰しているわけではないのでなおさらです。ユダヤ・キリスト教なら死んだ後にどういう世界に行くのか、どういうふうに救われるのかを聖書や教会で教えてもらえるのかもしれません。つまり「究極的な意味」を自分自身で考えずに済むのです。仏教なら輪廻の状態から解脱することを目的として教わるかもしれません。
こうした昔の神は、科学が発達した自体にはある意味では呪術的なものとして、もはや信じられなくなってきています。そのかわり、自分で意味を考えなければいけない時代にきていて、自分の考え出した意味と、他の人考え出した意味が対立することがあります。こうした意味で、神々の闘争であり、個々人の価値観の争いというわけです。子供には優しくするべきだ、厳しくするべきだ、不倫はよくない、不倫してもいい、他人のことを考えるべきだ、自分のことを考えるべきだ、枚挙にいとまがないほど価値は争いあっています。すべてのひとに絶対的に等しいような、ある種の真理のような価値観はない時代なのです(昔もそうなのですが、昔は宗教を基準にしてある程度は争いがなく、重しがしてあったということですね)。
既成の宗教──いっそう正確にいえば、教義の拘束に服する教派(ゼクテ)だけが、無条件に妥当する”倫理的”命令の威厳を、”文化価値”の内容に与えることができる。それ”以外のばあい”、個々人が実現しようと”欲する”文化理想と、個々人が果たす”べき”倫理的義務とは、原理的に異なる威厳をもつ。
世界に起こる出来事が、いかに完全に研究され尽くしても、そこからその出来事の”意味”を読み取ることはできず、かえって、[われわれ自身が]意味そのものを創造することができなければならない。したがって、われわれをもっとも強く揺り動かす最高の理想とは、どの時代にも、もっぱら他の理想との闘争をとおして実現されるほかなく、そのさい、他の理想が他人にとって神聖なのは、われわれの理想がわれわれにとって神聖なのとまったく同等である。こうしたことを知らなければならない、ということこそ、認識の木の実を喰った一文化期の宿命にほかならない。
「社会科学と社会政策にかかわる認識の『客観性』」、マックス・ウェーバー、富永祐治・立野保男訳、折原浩補訳、岩波文庫、41P
ここでも先程の神々の闘争と同じようなことがいわれています。価値が人それぞれのように、意味も人それぞれであり、他の意味との闘争になるということですね。じぶんの責任において意味は創り出すものでなければいけないのです。これが神なく預言者なき時代の宿命であり、脱魔術化(エントツァベルンク)の結果だということです。
「信仰」の問題は、いかなる理論、いかなる形而上学によっても客観的に解決することのできない、また解決することを許されない──でなければ、それは「自由の事柄」ではなくなるから──人生最大の謎である。その謎は、おまえがおまえ自身で、「おまえの良心と知性」、「おまえの心」のたけを尽くし、「おまえの責任」において、長い時間をかけ、さまざまな経験を積みながら、解いてゆくべきものである。この勧告は、「われわれはこの世界の出来事をどれほどくまなく究明したとしても、それに照らしてその出来事の意味を読み解くことができない。意味は、むしろわれわれ自身が、みずからの責任においてこれを与え作り出すものでなくてはならなぬ」という例の「客観性」論文その他で表明された「意味」問題に関する後年のウェーバーの発言の原型にほかならない。
「知と意味の位相」338P
[信仰」の問題は「価値」の問題と似ています。どちらも主観的なものだからです。事実から「客観的な意味や価値」そのものを作りだすことはできず、自分自身で主観的に意味を与える必要があります。それも良心、知性、心と責任においてです。これが責任倫理というものではないでしょうか。知性では事実判断が、良心や心では価値判断があり、そのどちらも緊張関係におきながら責任をもって意味を与え、そして政策を立案なり決定なりしていこうというわけです。
──要するに、思想的「その日暮らし」を生きる人間ではない。むしろ、自分が生きる意味を結び付けられる究極の理想を、みずから選びとり、一方では、これにたいして持続的な”内面的”関係を堅持しながら、他方では、その理想を日々の行為”目的”に具体化し、その目的達成への手段を、目的への適合度を検証するとともに”個人としての価値判断を介して”選択し、外囲の現実の状況に投企し、その結果にも責任をとりつつ、<首尾一貫して>生きる、──そうした<自己責任性>と<責任倫理性>に”耐えうる個人”という理念である。
経験科学の「目的論的批判」は、この対内的<自己責任性>に、「技術論的批判」は、この対外的<責任倫理性>に、それぞれ不可欠の契機として編入され、活かされるのである。
「社会科学と社会政策にかかわる認識の『客観性』」、マックス・ウェーバー、199-200P
こちらもわかりやすい折原さんのウェーバー解説です。これは科学者だけの責任倫理ではなく、科学者以外のすべての人間に対する責任倫理としても捉えることができます。
例えば「自殺率を下げる」ために「戦争」という手段をとるとします。仮に戦争という手段をとって何億人という死者が出たとしても、その結果に責任をとるということが重要なのです。責任をとることを前提に、自分が考えられるすべての手段を検討し、かつその随伴結果の予測も検討し、メリットとデメリットを比較し、それでもはやはり「戦争」という手段をとるというわけです。
メリットとデメリットを比較して「戦争」という手段が適合したと仮定します。つまり、科学の技術論的批判にはクリアしたと仮定します。次に「目的論的批判」があります。まずは理念の解明で、自分は「命は尊ばれるべきである」という理念があったことがわかったとします。そしてその「命は尊ばれるべきである」という理念に対して、手段が「戦争」であることは「形式論理的に矛盾」していたとします。この場合、「目的論的批判」をクリアできていないことになります。
技術論的批判にクリアして、責任論理性を保てたとしても、目的論的批判にクリアできていないので、対内的自己責任性は保てていないことになるのです。知性ではクリアしても、良心や心でクリアしていないということになります。
こうした問題は政治だけではなく、商売においても同じようなことが考えられます。消費者に不利益を与えるような詐欺的なビジネスを「手段」として、お金儲けを「目的」としてみます。もし結果と随伴結果を両方比較して、それでも詐欺的なビジネスを決行したとします。しかし自分の理念を解明してくと、やはりそれでも「他者を騙すようなことはしてはならない」と自分に訴えかけてくるものがあるかもしれません。これが反省の機会であり、形式論理的批判です。
それでもお金儲けが大事だという人もいるかも知れません。そういう人は自分の中にある大事な理念を押し殺してあくまでも合理的に、知性に基づいてビジネスを行うかもしれません。あるいはもともと人は「騙すことは悪いことではない」、「騙される方が悪い」という理念がその人にはあったのかもしれません。いずれにせよ、そうした批判を科学的にしてみることも、非科学者にとっても重要なのかもしれませんね。
ウェーバーならそうしたなにが倫理的義務は討論可能であり、普遍妥当性をみつけることが重要だというのかもしれません。つまり、個人の自由だから、趣味の問題だから、法律に反しない詐欺ならやり放題だ、とは必ずしもならないということです。法律に反しない限りなら人を言葉で傷つけてもいい、ということに納得する人はどれだけいるでしょうか?そうしたものの中に、普遍妥当性があるのかもしれません。いずれにせよ絶対的な真理というものはない(法則から演繹することはできない)ので、その時代、その文化、特定の状況から善悪に関する普遍妥当性を討論して考えていく必要がありそうです。
というより、そうした討論の結果、法律にある意味ではなっていくのかもしれません。浮気や不倫は法律に反しないかもしれませんが、裁判でよく争われますよね。不倫が実際に姦通罪として刑法で罰せられた時代もありました。こうしたものは政治家や官僚といった実務家以外も積極的に討論していくべき問題だと思います(政治参加の重要性)。政治家が国民の代表だから、投票だけしていればいいというものでもなさそうです。
※政治における心情倫理と責任倫理については別の機会に説明します
価値判断論争とは
・価値判断論争(かちはんだんろんそう):1904年から1913年にかけて、ドイツの社会政策学会を舞台ににG・シェモラーとM・ウェーバーとの間で起きた論争。価値判断は客観的に正当化されうるか、事実判断は価値判断から中立でありうるかが争点となった。歴史学派のシュモラーは価値判断を客観的に正当化しうると考えたが、社会学者のウェーバーは事実判断と価値判断を区別するべきだと主張し、シュモラーの両者の混同を批判した。
1909年の社会政策学会はウィーンで開催された。その大会では、それまで問われることのなかった問題が議論された。社会政策学会にあっては「政策目標」は自明なものとみなされ、そのため政策と学問的研究がしばしば無自覚に結び付けられていたのに対して、その大会ではじめて、国民経済の「生産性」とは何かという、政策目標それ自体に関する理論的な問題が議論されたのである。いわゆる「価値判断論争」の幕開けである。
「クロニクル社会学」、那須壽編、有斐閣アルマ、111P
すなわち、それらの価値判断は、歴史的に相対的ではあるが、社会全体の平均的価値判断としてみなされうるものであり、またそのような平均的価値判断が可能となる場は、そのときの民族意識を母胎とする国家であり、したがってそのような価値判断は、単に個人的趣味の問題ではなく社会的過程の産物であって、習俗的な支配的価値基準にまで高めうるものである、とシュモラーは考えた。
・・・
シュモラーは、このウェーバーの批判を、価値判断を研究対象から排除しようとするものだ、と解釈したが、それがまったくの誤解であることは明白であろう。
またウェーバーの主張は、価値判断に対する科学の消極的見解である、としばしば誤解されることがある。しかし、ウェーバーは、経験科学は、実践的・政策的評価の領域において、「避けがたい諸手段、避けがたい副次効果、さらにはそれらの事情のために複数の可能な評価が、その実践上の帰結において相互に競合するさま」を示すことにより、つまり政策の技術的批判を行うことにより、価値ある行動のための指示を導出する際の助けとなる、と考えているのである。ウェーバーは、こうした技術的批判こそ、むしろ実践に先だってなされるべきであり、「責任倫理」の当然の前提である、と考えていた。
日本大百科全書(ニッポニカ)「価値判断論争」の解説
繰り返しになりますが、ウェーバーは価値判断を科学から排除しようとしたわけではありません。事実認識と価値判断を区別し、責任を持って価値判断をするべきであり、科学者は事実認識と価値判断との境目を明確に読者に提示するべきだと言ったのです。また、事実から当為(なすべきこと)は生まれないという主張もしました(カント主義社のH・リッケルトの影響らしいです)。
「価値判断は客観的に正当化されうるか」というのはなかなか難しいですね。国民経済における「生産性」とはなにか?ということを考えてみましょう。日本語大辞典によれば「労働、設備、原材料などの投入量とこれによって作り出される生産物の産出量との比率」です。たとえば従業員を増やしたら、牛乳を1万L生産できるといったケースです。極論ですが一ヶ月雇って1Lしか生産できなければ、生産性がないといったような言い方ができるかもしれません。細かく言えば「労働生産性」ですね。より少ないインプットからより多いアウトプットが得られると、生産性が高いというそうです。
一見すると、生産性はいかにも客観的に正当化されているような概念に思えます。Aさんが思う生産性はこうだ、Bさんが思う生産性はこうだ、といったように価値判断同士の闘いが起きそうにないように不学の私には思えてしまいます。実際に社会政策学会では、生産性とはなにかについては自明のものとして深く考えず、とにかく「どうやったら生産性が上がるか」を議論していたそうです。
だがしかし、われわれがとくに(ふつうの意味での)経済政策と社会政策の実践的問題を考えるならば、じっさい上の”個別問題”を議論するさい、特定の目的が”自明なもの”として与えられている、と全面的に合意して出発できる場合が、なるほど多数、いや無数にある。たとえば緊急時の融資、公衆衛生・貧民救済の具体的な課題、工場査察・営業裁判所・職業斡旋・大部分の労働保護立法のような施策を考えればよい。これらのばあい、少なくとも表面上は、当の目的を達成する”手段”だけが、問題とされているように見える。しかし、われわれがここで、目的は自明であるという”仮象”を真理と取り違え──科学がそうした錯誤を犯せば、必ずや相応の報いを受ける──、等の目的を実践的に貫徹しようとすればただちに直面する紛争を、たんに目的達成のための純然たる技術的問題にすぎないと見なそうとする──しばしばそうした誤りが侵される──ばあいでさえ、統制的価値基準の自明性というこの”仮象”も、われわれが、慈善施設や警察による福祉や経済上の”保護”といった具体的問題から、一歩を進めて、経済”政策上”および社会”政策”上の問題と取り組むやいなや、ただちに消失することに気づくはずである。
ある問題が、社会的にみて政策的な性格をそなえているということの標識は、まさしく、当の問題が、規定の目的からの技術的考慮にもとづいて解決されるようなものではなく、問題が一般的な”文化”問題の領域に入り込んでいるために、ほかならぬ統制的価値基準そのものが”争われ”うるし、”争われざるをえない”というところにある。
……
いずれにせよ確かなことは、ただひとつ、取り上げられる問題が「一般的」であればあるほど、ということはつまり、その文化”意義”が広汎にわたればわたるほど、経験的な知識という素材から[政策上の統制的価値基準について]一義的な回答を求めることはでき”なくなり”、信仰ないし価値理念という個々人の究極最高の公理が入り込んで、それだけものをいうようになるということである。
実践的な社会科学は、なによりもまず「ひとつの原理」を確立し、それを妥当なものとして科学的に検証し、その上で、当の原理から、実践的な個別問題を解決するための規範を一義的に演繹すべきである、というような見解が、まま専門家によっても相変わらず信奉されているが、これはもとよりナイーヴな信仰にすぎない。
社会科学において、実践的問題の「原理的な」論究、すなわち、反省を経ずに強いられる価値判断を、その理念内容にまで遡って捉え返すことが、いかに必要であっても、また、われわれの雑誌は、まさにそうした論究にも、とくに力を入れるつもりではあるが、──われわれの直面するもろもろの問題にたいして、普遍的に妥当する究極の理想という姿をとる、ひとつの実践的公分母を創り出すようなことは、断じて、われわれの任務でもなければ、およそいかなる経験科学の課題でもない。
「社会科学と社会政策にかかわる認識の『客観性』」、マックス・ウェーバー、富永祐治・立野保男訳、折原浩補訳、岩波文庫、38-40P
※太字は引用者
シュモラーの「すなわち、それらの価値判断は、歴史的に相対的ではあるが、社会全体の平均的価値判断としてみなされうるものであり、またそのような平均的価値判断が可能となる場は、そのときの民族意識を母胎とする国家であり、したがってそのような価値判断は、単に個人的趣味の問題ではなく社会的過程の産物であって、習俗的な支配的価値基準にまで高めうるものである、とシュモラーは考えた。」という点をみると、やはり「統制的価値基準」や「実践的公分母」といったような傾向がありそうです。
社会全体の平均的価値判断とは、ウェーバーのいうところの「一般的である」ということです。多くの人間に(おそらく富の)「分配」が善いものだという価値判断がされているので、それが支配的(統制的)価値基準にまで高まっているという考えは一見すると正しいように思えてしまいます。お金持ちから貧しい人へ富を分配するのは善いという価値判断が多いから、それは他の価値より上の価値判断であるといった判断ですよね。
しかしウェーバーによればそうした統制判断は危険だといいます。「分配」というのがいくら自明に見えたとしても、分配という理念そのものは真理ではなく仮象なのです。仮象(かしょう)とは主観的なもので、客観的な実在性がないものです。価値判断を事実である(客観的なものである)かのように混同することはよくないことで、あくまでも区別するべきだというのがウェーバーの主張です。
「自殺率は下げるべきである」というのはほんとうか?という視点でも考えられますね。たしかに私は「自殺はよくないものである」ということがまるで事実であり理念(こうあるべきだという考え)かのように思っていました。おそらく多くの人も「自殺率は下げるべきであり、問題はその技術的な手段」だと考えているのではないでしょうか。
しかし「自殺はよくないものである」というのは仮象であり、真理ではないのです。また岩や木のように客観的に実在しているものでもありません。価値判断なのです。別の角度から見れば、人口が過剰になっていて、自殺はそれを抑制するための機能である、という見方もできるわけです(たとえばですが)。ほんとうに自殺はよくないものなのか?と自分で問う必要があります。そして「自殺は良くないものだと思っている」という自分の価値判断、自分の理念をまずは自覚するべきだということです。そのうえで”責任”を持って目的のための手段を選択しようということです。たとえば「命は尊ばれるべきだ」という理念を持っていて、だから「自殺は良くないものだと思っている」、そして自殺を減らすための手段として「戦争」は自分自身の価値判断を理由に採用できない、というケースもあると思います。
生産性という「概念」もおなじように自明なものとみなさずに、認識や概念は価値との関係付けによって成り立っていることを自覚しようということですね。自分の価値判断や信念は常に疑う余地があるのです。こうすることで、認識の客観性を保証することにつながるとウェーバーは考えたわけです。次回の「理念型」でもう少し詳しく扱います。
コラム:マックス・ウェーバーとエミール・デュルケムの違いについて
デュルケムやマルクス:構造(社会)が個人に外在して、個人から独立している
ウェーバー:社会における構造は、行為の複雑な相互作用によって形成される。一人ひとりが自由に行動し、未来を形づくる能力を持っている。焦点は構造ではなく社会的行為。
※社会的行為についてはいずれ扱います
コラム:「アルフレートの堅信を祝う手紙」:信仰と意味について
君はこれまで昔からわれわれの教会で受け継がれ信じられてきたキリスト教の教義を教えられててきました。そしてそのなかで、君はキリスト教の意味と内面的な意義との理解が人によって実にさまざまであること、そして人々がこの宗教のわれわれにもたらす大きな謎を各人各様に解こうと努めていることをかんがえないわけにはいかなかったでしょう。
そこでいま君にも、他のキリスト教徒と同様に、キリスト教会の一員として、そうした問題にたいする君自身の見解を作り上げるように要求されているわけです。これは各人が、各人なりに解決しなくてはならない課題です。もちろんそれは一気に解けるようなものではなく、各人が一生かけて色々と経験を積みながら解決してゆくべき問題です。
君がいま初めて自分に提起されたこの課題をどう解くか、それはもっぱら君自身の問題であり、君の良心(Dein Gwwissen)と君の知性(Dein Verstand)、君の心(Dein Herz)が責任を負うべき事柄です。
というのも、私が思うには、キリスト教は老若、幸不幸を問わず、どんな人の心のなかにも等しく生きており、その仕方はさまざまであっても、すべての人がその教えを理解ですることができる、事実またほとんど二千年この方人々は各人各様にそれを理解してきた、そこにキリスト教の偉大なゆえんがあるからです。
Brief von Max Weber an Hermann Baumgarten, Charlottenburg, 14. Juli 1885, in: 「Jugendbriefe」, S.
171(『手紙』、106P~)……それから君が引き合いに出しているもう一つの問題、宗教的事象の『理解不能性』の問題も、[君はただそれが理解不能というだけで]一向に方がついていません。なぜなら、それではその理解不能なものにたいして自分は一体どういう態度をとるのか、といった問題がただちに生ずるからです。宗教は世界史の中で人間にとってどんな価値をもったのか、この自分にとってそれはいかなる価値をもつのか?それとも、ひょっとするとそれは理解不能なるがゆえに、自分にとっておよそ何の意味ももたないものなのだろうか?私の考えでは、このあとの方の見解にはどうしても賛成することができません。しかし、それでは一体宗教が人々にとって、またこのわたし自身にとってどういう意味をもつのかと言った問題は、そう簡単なものではないし、どんな人でも一気に答えることのできるような問題でもありません。
Brief von Max Weber an Hermann Baumgarten, Charlottenburg, 14. Juli 1885, in: 「Jugendbriefe」, S.
171(『手紙』、228P~)君はどうしてそういつもいつも──君の良い草によると──自分はもうダメだとか絶望せざるをえないなどと自分に言い聞かせることができるのか、わたしには不思議でなりません。端的に聞きますが、一体なぜなのです?もしその理由が、なにか一般的な理論的見解上の問題で君がぶつかっている困難のせいでしかないとすれば──だって、ほかにどんな理由があると言うのです?──、もしそうなら、君は、およそ理論というものがこの世でもつ、そして各人にとってもつ意義を、あまりにも過大評価しているとしか言いようがありません。地獄の劫罰とかそれに類する永遠の世界などあるはずがないと考えている君が、なにか理論的見解の上で行きづまり、もう自分は生きていけないとか、自分にとって生きることは重荷である、などといったことを本気で思い込んでいるとすれば、これはもうどこからどう見てもまったくのお笑いでしかありません。
そんなことで色々思い悩む人もいることは、わたしにもよく分かります。しかし、そうした極論に溺れたりせずに、われわれの認識手段が──絶対の観点からすれば──いかに取るに足らない価値しかもたず、いかに弱点だらけのものであるかを弁えるすべを心得、またそのことを日頃つねに自分に言い聞かせている者は、物事というものは必ずわれわれの経験をはみ出すものであり、それを捉えようとする理論はつねに誤謬を犯す可能性があるということを思い知らされたとしても、だからといって認識への努力そのものを放棄しようとは夢にも思わないでしょう。
もしもそんな極端な考え方をする人がいるとしたなら、はたしてその人はそれで結構自己欺瞞に陥っているのではないか、とかくペシミズムというものにはつきもののあの魅力──これは大抵の人間が一度は参ってしまうものだが──に取りつかれて、そんなことを言い出している面もあるのではないかと、わたしはその人の顔を正面からのぞき込んで、とくと吟味してやろうと思います……いずれにしても、そんな考え方は邪道です。云々。
Brief von Max Weber an Hermann Baumgarten, Charlottenburg, 14. Juli 1885, in: 「Jugendbriefe」, S.
171(『手紙』、309P~)
これはマックス・ウェーバーの次弟であるアルフレートへの手紙です。この手紙が私は好きです。客観的の論文でウェーバーが、科学者は責任を持って価値判断をしなければならないといいました。価値判断は科学にできるものではなく、「科学者の良心(Gwwissen)と科学者の知性(Verstand)、科学者の心(Herz)が責任を負うべき事柄」であると読み替えることもできます。
価値を捨てて価値から自由になるのではなく、また事実を捨てて価値へ自由になるのでもありません。価値と事実の両方を緊張関係に置きながら、良心と知性と心を総動員して判断していこうという話です。ここではあまり触れませんが、こうした考え方は「決断主義的責任倫理」ではありません。ニーチェのような「価値決断論」とは違うものです。
出典
- 「社会学用語図鑑」田中正人(編者)、香月耿孝史、プレジデント社、66P
- 「社会学」、有斐閣、21P
- 「社会科学と社会政策にかかわる認識の『客観性』」、マックス・ウェーバー、富永祐治・立野保男訳、折原浩補訳、岩波文庫、204-205P
- 「社会科学と社会政策にかかわる認識の『客観性』」、マックス・ウェーバー、富永祐治・立野保男訳、折原浩補訳、岩波文庫、195P
- 「社会科学と社会政策にかかわる認識の『客観性』」、マックス・ウェーバー、富永祐治・立野保男訳、折原浩補訳、岩波文庫、195-196P
- 「マックス・ウェーバー入門」、山之内靖、岩波新書、3P
- 「マックス・ウェーバー入門」、山之内靖、岩波新書、4P
- 日本大百科全書(ニッポニカ)「価値判断論争」の解説
参考文献・おすすめ文献
マックス・ウェーバー『社会科学と社会政策にかかわる認識の「客観性」』
マックス・ウェーバー『職業としての学問』
マックス・ウェーバー『職業としての政治』
雀部幸隆『知と意味の位相―ウェーバー思想世界への序論』
姜尚中『マックス・ウェーバーと近代』
山之内靖『マックス・ウェーバー入門』
アンソニー・ギデンズ「社会学」
社会学
クロニクル社会学
社会学用語図鑑 ―人物と用語でたどる社会学の全体像
コメント
この記事へのトラックバックはありません。



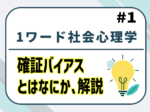
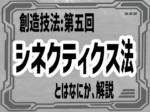
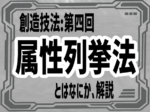
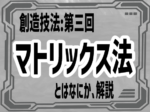
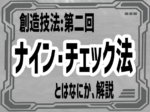
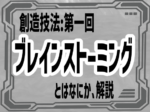
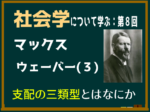

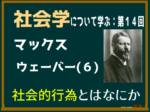
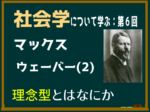
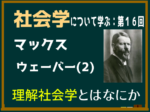
この記事へのコメントはありません。