- Home
- 二クラス・ルーマン, 井庭崇, 創造発見学, 川喜田二郎
- 【創造発見学第二回】創造性とはなにか
Contents
- 1 はじめに
- 2 整理と疑問点
- 3 創造性は専門家にどのように捉えられているのか
- 3.1 紹介する際の基本方針
- 3.2 イギリスの心理学者グラハム・ワラス(1858-1932)による創造性とは
- 3.3 イギリスの心理学者のチャールズ・スピアマン(1863-1945)の三つの思考原理とは
- 3.4 ドイツの心理学者、マックス・ヴェルトハイマー(1880-1943)による創造性とは
- 3.5 アメリカの実業家のアレックス・F・オズボーン(1888-1966)による創造性とは
- 3.6 教育学者のルイス・A・フリーグラー(1917-1974)による創造性とは
- 3.7 アメリカの心理学者ジョイ ・ギルフォード(1897-1987)による創造性とは
- 3.8 心理学者のエリス・ポール・トーランス(1915-2003)の創造性とは
- 3.9 小説家のアーサー・ケストラー(1905-1983)による創造性とは
- 3.10 バイソシエーションとは、意味
- 3.11 アメリカの心理学者、ジェローム・シーモア・ブルーナー(1914-2016)による創造性とは
- 3.12 市川亀久弥(1915-2000)による創造性とは
- 3.13 自然や宇宙の存在の仕方そのものが、根源的に等価性をもつ
- 3.14 アメリカの心理学者、ウィリアム・ゴードン(1919-2003)による創造性とは
- 3.15 馴質異化と異質馴化とは、意味
- 3.16 マルタの心理学者、エドワード・デボノ(1933-2021)による創造性とは
- 3.17 湯川秀樹さん(1907-1981)における創造性とは
- 3.18 教育心理学者の恩田彰さん(1925-2015)における創造性とは
- 3.19 ロバート・スタンバーグ(1949~)における創造性とは
- 3.20 社会学者の熊坂賢次(1947~)さんによる創造性とは
- 3.21 國藤進さん(1953~)における創造性とはなにか
- 3.22 高橋誠(1943~)さんによる創造性とは
- 4 川喜田二郎さん(1909-2009)による創造性とはなにか
- 5 アメリカの心理学者、アブラハム・ハロルド・マズロー(1908-1970)による創造性とは
- 6 アメリカの心理学者、ミハイ・チクセントミハイ(1934-2021)による創造性とは
- 7 ルーマンと井庭崇さんにおける創造性とは
- 7.1 創造実践学者の井庭崇(1974~)さんにおける創造性とは
- 7.2 ルーマンの社会システム理論とはなにか
- 7.3 1:ルーマンの理論は一言で説明すると「社会とはコミュニケーションの連鎖である」
- 7.4 2:ルーマンにおけるコンティンジェントとはなにか
- 7.5 3:ルーマンにおけるオートポイエーシスとはなにか
- 7.6 (4)自己言及のパラドックスとはなにか
- 7.7 ベイトソン「論理に因果は語れない」
- 7.8 5:オートポイエティック・システムの3つの特徴
- 7.9 6:鶏と卵
- 7.10 7:固有値
- 7.11 【コラム】ベイトソンと冗長性について
- 7.12 【コラム】池田久美子さんによる「コードの増殖」とはなにか
- 7.13 8:他者言及とは
- 7.14 三つの選択が継起的に生じるということは、本来生じにくいことである
- 7.15 川を構成する要素とはなにか(実体か、生成か)
- 8 井庭崇さんの創造システム理論とはなにか
- 9 その他、感想
- 10 参考文献リスト
- 11 汎用・基本文献リスト
はじめに
動画での説明
・この記事の「概要・要約」はyoutubeの動画の冒頭にありますのでぜひ参照してください。
よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m
問いの答えに対する例、ヒント、関連事項をざっくり時系列的に整理
| 属性 | 人物・出来事 | 時期 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 神話 | メソポタミア文明 | 紀元前30世紀 | 知られている最古の文明。文字が発明される。 |
| 神話 | バビロニア神話創世記叙事詩 | 紀元前20世紀 | はじめにアプスー(水神)があり、すべてが生まれ出た。混沌を表すティアマトもすべてを生み出す母であった。 |
| 詩人 | ヘシオドス | 紀元前8世紀 | 原初の混沌がまずあり、神は最初に大地、夜、闇、愛、奈落の底を生んだ。 |
| 哲学者 | タレス | 紀元前7世紀 | 万物の根源は水である。神話的思考から科学的思考へ。 |
| 神話 | 旧約聖書(創世記) | 紀元前5世紀 | 「初めに、神は天地を創造された」 |
| 哲学者 | パルメニデス | 紀元前5世紀 | 万物は多ではなく一であり、不生不滅で分割できず、変化・時間・始まりと終わりもなく、有の連続である |
| 哲学者 | ヘラクレイトス | 紀元前5世紀 | 誰も同じ川に二度入ることはできない。世界のありとあらゆるものは常に生成と変化の過程のうちにある。 |
| 哲学者 | プラトン | 紀元前4世紀 | 出来事を単に経験・模倣したりするのではなく、出来事を分析し、分類するべきである。主体が客体に染み出すな。 |
| 哲学者 | アリストテレス | 紀元前4世紀 | 芸術創作活動の基本的原理は模倣、自然の模写(ミメーシス)である。本来の場所・本来の運動というものがある。 |
| 神話 | 旧約聖書(伝道の書) | 紀元前3世紀 | 「日の下に新しきものなし」 |
| 錬金術師 | アグリッパ | 1493-1541 | ありとあらゆるものは世界霊の力と確固たる場をもつ。すべての事物は星によって、表徴を刻み込まれる。相似。 |
| 宗教家 | ルター、カルヴァン等 | 15世紀 | 【宗教革命】 |
| 哲学者 | デカルト | 1596-1650 | 知りうるべきことはすべて理性を通して知られる。すべては単に、物体と運動からなる。神は作動に介入できない。 |
| 数学者 | パスカル | 1623-1662 | 情感には理性が感取しえない、独自の理性がある。 |
| 科学者 | ニュートン等 | 17世紀 | 【17世紀科学革命】 |
| 思想家 | ヴォルテール | 1664-1778 | 独創力とは、思慮深い模倣以外の何ものでもない |
| 哲学者 | カント | 1724-1804 | 理性によって、私とはなにか、世界とはなにか、私や世界の目的、意味はなにか、答えられない(純粋理性批判)。 |
| 1760-1830 | 【産業革命】 | ||
| 哲学者 | パース | 1830-1914 | アブダクティブな示唆が創造の核心であり、「自然について正しく推察する本能的能力」である。 |
| 小説家 | バトラー | 1835-1902 | われわれが一番よく知っているのは、われわれが一番意識していないことである。 |
| 哲学者 | ニーチェ | 1844-1900 | 神は死んだ。人間の独創性は、荒涼の感覚に打ち勝つことに向けて発揮され、自分自身を欺き、慰め、忘れる。 |
| 精神科医 | フロイト | 1856-1939 | 無意識を、恐ろしい、苦痛に満ちた記憶が抑圧のプロセスによって押し込められた地下室と考える |
| 心理学者 | ワラス | 1858-1932 | 創造を、①準備、②孵化(あたため)、③啓示(ひらめき)、④評価・検証の四段階に分けた。 |
| 哲学者 | フッサール | 1859-1938 | 西洋学問は「危機」にある。意味や目的、主観、生活現実を軽視し、客観的な事実のみを重視してしまっている。現象学の登場。 |
| 心理学者 | スピアマン | 1863-1945 | 創造を、経験すること、経験の素材の間の関係を知ること、ある経験の素材との関係からもうひとつの観念を知ることにわけた。 |
| 哲学者 | アラン | 1868-1951 | 模倣することのない者が発明することはない |
| 舞踊家 | ダンカン | 1878-1927 | 「この踊りの意味が口で言えたら、踊る意味がなくなるでしょう」 |
| 心理学者 | ヴェルトハイマー | 1880-1943 | 「観点変更によって新しい思考体制が成立することによって、新しい結論が導出される過程。ゲシュタルト心理学。 |
| 実業家 | オズボーン | 1888-1966 | 創造は、方向づけ、準備、分析、相手を考える、あたため、総合、評価からなる。 |
| 小説家 | オルダス | 1894-1963 | 人間の行動は、目的心や自意識からくる「あざむき」によって汚されている。失われた動物の優美さ、純良さ。 |
| 心理学者 | ギルフォード | 1897-1987 | 「知性」と「創造性」を区別。拡散的思考(創造性)とは、解答が一通りでない問題に対処する思考であり、能力。 |
| 科学者 | フォン・ノイマン | 1903-1957 | 物理体系全体がプロセスの相互作用によって規定されている。量子力学の登場。 |
| 人類学者 | ベイトソン | 1904-1980 | 自然界のあらゆる分野の現象に、同じ種類のプロセスを観察できると考え、精神の生態学を構築。 |
| 小説家 | ケストラー | 1905-1983 | 一見何も関係がないような二つのものを関連付けること(バイソシエーション)が創造にとって重要である。 |
| 科学者 | 湯川秀樹 | 1907-1981 | 異なるものを同じだと認識するという「同定」が創造性の発現の過程において不可欠である。 |
| 心理学者 | マズロー | 1908-1970 | 一次的創造性は、無意識的深層から発する本能的衝動であり、至高経験は自己喪失・自己超越などの神秘的体験。 |
| 人類学者 | リーチ | 1910-1889 | 「一つの文化に根ざす芸術が、別の文化に育った批評家にとっても意味や妥当性をもつのはなぜか?」 |
| 心理学者 | ブルーナー | 1915-2016 | 直観的に仮説を思いついていく思考である直観的思考が特に重要であり、分析的思考と統合され、創造となる。 |
| 心理学者 | トーランス | 1915-2003 | 創造的な人物を測るテストが可能であり、流動性、柔軟性、独創性、入念性という4つの因子が基軸となる。 |
| 工学者 | 市川亀久弥 | 1915-2000 | 互いに異なった事象を一定の観点で見れば、同じ事象として認定できる。等価性によって創造性は達成される。 |
| 教育学者 | フリーグラー | 1917-1974 | 創造は、準備、欲求、問題点の選択、あたため、ひらめき、評価、再構成と再評価。 |
| 心理学者 | ゴードン | 1919-2003 | 「一見関連のない要素を結びつける」というシネクティクスが想像において重要になる。 |
| 人類学者 | 川喜田二郎 | 1920-2009 | 創造とは「なすに値する切実なものごとを、おのれの主体性と責任において、創意工夫を凝らして達成すること」 |
| 教育学者 | 恩田彰 | 1925-2015 | 創造性とは、新しい価値あるもの、またはアイディアを創り出す能力、およびそれを基礎づける人格特性 |
| 社会学者 | ルーマン | 1927-1998 | 社会システムの要素は人間ではなく、コミュニケーションであると考え、社会システム理論を構築。 |
| 心理学者 | デボノ | 1933-2021 | 様々な角度から自由に思考を巡らせる手法の思考法(水平思考)」を重視し、かつ垂直思考と両方が必要だと主張。 |
| 心理学者 | チクセントミハイ | 1934-2021 | 創造性とは個人、領域、フィールドという3つの要素から構成されたシステムの相互関係のこと。 |
| 建築家 | アレグザンダー | 1936-2022 | 諸価値基準の相違は、ある一つの中心的な価値基準に訴えれば解消できると私は信じ、パタン・ランゲージを構築。 |
| 心理学者 | スタンバーグ | 1949~ | 創造性とは、斬新で(独創的で、予期しない)、適切な(有用で、適応性のある)成果を生み出す能力 |
| 実業家 | 高橋誠 | 1943~ | 問題を「期待と現状との差」として定義している。 |
| 創造実践学者 | 井庭崇 | 1974~ | 創造を、「発見を要素とするオートポイエティック・システムである」と捉える「創造システム理論」を構築。 |
整理と疑問点
創造性とはなにか、考えてみればよくわからない
【根本的な問い】創造が大事だ、ということはなんとなくわかる。しかし、創造という概念がなにかいまいち分からない。
ぼんやりと新しいこと、独自性のあること、凄いことが生じているというイメージしかない場合が多いのではないか。
今回はそうした「創造(創造性)」の掘り下げを行う。これからの動画の指針、土台となるようなものにしたい。動画が長いので分割することも考えたが、分割しないことでそれぞれの要素が各人の中で繋がる何かを重視した。
辞書的な創造、創造性の定義
創造(そうぞう,英;creation):・一般に、新しいものを初めてつくり出すことを意味する。宗教的には神が宇宙・万物をつくることをいう。
日本大百科全書によると、創造は「既存の素材の独創的組み合わせによる創出」から「無からの世界の創出」というように、広い概念として用いられているという。
創造性(そうぞうせい,英;creativity):・日本大百科全書によると、「新奇で独自かつ生産的な発想を考え出すこと、またはその能力」を一般には意味している。
ただし、その定義の実態については明快な結論は未だ得られていないという。この定義で重要なのは、創造性が「新奇で独自」という創造の定義に加えて、「生産的」という性質が加わったことだろう。ただ奇抜であればいいのではない、という趣旨がみられる。
また、創造「性」という言い方が、「能力」と関連付けられていることも重要かもしれない。つまり、創造性という「能力(可能性、性質)」と、創造という「産物(結果)」として区別することが出来ていく。
創造に関する問いについて整理
個人的に重要だと思う創造に関する「問題」の要素を整理した。
この動画で扱っていく人々は、すくなくともこれらのいずれかの問いに答えていく形となる。
これらの問いに対して答えていくことが、創造の概念を考えていくことになる。
問いとそれに関連する知識の整理
創造性はどの問い、知識、思考が一番重要になるのか、という点が重要になる
創造性へのアプローチ
今までの主な創造へのアプローチ例としてはこのようなものが考えられている。
どのようにアプローチするか、という点も重要になる。
発想法(創造の支援、手段)について
「手段の問題」について、今回はあまり多く扱わない。ブレインストーミング、KJ法、チェックリスト法等々、それらは「創造(性)とはなにか」というより、それらが分かった上で、どのように支援するかというような二次的なものである。
二次的なものではあるが、日常的・実用的に最も重要になるのがこの分野になる。今回はあまり触れずに、別のカテゴリーで順次、個別的に扱っていく。
思考実験:創造性を考えるとモヤモヤすることが多い
仮に創造性を、独自性のあるもの、新しいものとして考えてみる。ほとんどの人は創造をそう捉えているだろう。
たとえば「相対性理論」を創造した、という例を考えてみる。おそらく、相対性理論以前にはそのような理論はなかったのだろう。もしアインシュタイン以前にあったのなら、公表されているだろう、と素朴に推測できる。
では、どのようにして「自分以外が過去につくっていない」と判断・証明することができるのか。
自分の狭い見識の範囲で、「他の人がまだつくっていないから、自分がつくったものは新しい」と判断すればいいのか。それとも自分の周りの他者が、「あなたのものは新しい」というように判断してくれればいいのか。
理論を考えたが公表はしていない、というケースはあるのか。創造したのはAが先だが、それらが証明できなければ発表したのはBが先なので、他者には実質的にBが先に創造したと判断されるのか。他者Aにとって自分の作品は創造的だが、他者Bにとっては違うということはあるか。基準は主観的で、人それぞれなのか。多くの他者に認められればいいというような数量的なものなのか、あるいは見識の深い人物に認められればいいというような質的なものなのか。具体的・経験的にデータのような形で可視化できるようなものなのか。
無人島に一人でいるとしたら・・・
例えば無人島で暮らしている狼に育てられた人間が現代に一人だけいると、極論として仮定する(他の人間を見たこともないし、文化も知らないような極端なケース)。この人間が木を削ってナイフをつくることは創造か。船をつくることは創造か。罠で動物を捕らえるのは創造か。今眼の前にある問題に対して、すくなくともこの島では見渡す限りこれまでにないアプローチを独自に考え、罠を作るという発想にいたった場合、これは創造なのか。
無人島という狭い範囲では、これまで誰もしていないことをしているという意味では、独自性があり、創造だといえるか。しかし、範囲を広げていけば、木でナイフを作った人は過去にたくさんいるだろうし、今まさに現在もいるだろう。「創造だとはいえるが、独創ではない。創造的だが、創造ではない。」という言い方はできるか。創造とは誰を基準に、何を基準に、どの範囲で考えればいいのか、まるでわからない。
変わった絵を描くとする・・・
今、変わった絵を適当に描いたとする。この絵は創造か。
おそらく、座標等、全く同じ絵を描いた人はおそらく、過去に一人もいないだろう。未来にもいないと思う。もちろん、こうしたことも推測であり、証明しようがない。
また、類似した絵ならたくさんあるかもしれない。どこまで類似していれば創造とはいえないのか。何%まで、少なくとも公表されている作品と類似していなければいいのか。
公表されている作品を全てチェックしないといけないのか。こうしたことは学問でも言えるのであり、特に学問ではこの膨大な先例のチェック作業が待っている。新しさ、独自性、奇抜さだけに創造性を絞る必要はあるのか。あるとして、その意義や目的はどこにあるのか。どういうパラダイムで、そのようなものが意義付け、価値付けられているのか。
トイレに名前を書いて噴水と名付けたアートは創造性があるのか・・・
たとえばトイレに名前を書いて噴水と名付けただけのアートは(当時は)奇抜だが、生産的だろうか。なにをもって生産的だと判断するのか。
奇抜さだけにこだわる必要はあるのだろうか。奇抜、独自性以外に、どの項目が必要なのだろうか。そもそも、独自性は必要ないのか。
※デュシャンのこの作品が現代アートに対するアンチテーゼかという点は置いておく。
創造性は可能性に置き換えられるか
「性」を「物事の性質、傾向や素質」を意味した場合を考えてみる。たとえば日常用語で「Aさんは犯人である可能性がある」と発言する場合、100%である必要はない。しかし0.001%である場合は、日常的な使い方として「可能性がある」という言い方はしないだろう。そんなことを言い出したら可能性が0の犯人などそもそも存在できるのか。瞬間移動の可能性やタイムマシンの可能性も0ではない。日常的には「創造性がある絵だ」という場合、「創造性に富んでいる」という意味で用いられる。
たとえば先程描いた絵に類似した絵があったとしても、それが部分的な場合は「創造性」があるといえるのか。だからといって創造性に「富んでいる」とは限らないのか。とはいえ、どの程度創造性があるのか、どのようにして判断可能なのだろうか。画像解析で過去の画像データベースと比較し、数量化できるようなものか。絵以外の、可視化しにくい「アイデア」のようなものはどのようにして比較するのか。
独自性は数量に置き換えられるか
たとえば、「128音のうち92音が同じ高さの音」だという理由で、裁判所は「剽窃(盗作)」という認定を下したことがあるらしい。
つまり、数量的に独自性があるかどうかが認定されている。創造性があるかどうかは、裁判官が決めるのか。絵はどうだろうか。「座標の位置が7割同じ位置にある」という理由でパクリになる、つまり独自性がないと認定されるのだろうか。剽窃や模倣、引用、パロディ、それらの境はどこにあるのか。創造性は独自性と関連しているのか。つまり、他者との比較においてのみ、なりたつ概念なのか。
創造性は専門家にどのように捉えられているのか
紹介する際の基本方針
・創造の問いに関連する人々の主張をとりあげていく。以下の方針にそって解説していく。
- 基本的に付け焼き刃な理解による説明であり、基礎概念と、自分のフックにひっかかったもの(面白い、重要そうだとざっくり感じたもの)の理解に留める。
- フックの数が多かったものは、別の章で掘り下げて検討していく。
- ひとつひとつ完全に理解していく必要はないと考えていく。すこしの理解とフックを積み重ね、全体的に何かにつながればいいと考えていく。もし理解が足りないために全体に繋がらなければ、もう一度戻って理解を深めていく。それを繰り返していく。部分と全体の反復作業。
- 要素は多ければ多いほどいい。何が全体につながり、新しい発見につながるのか、最初の段階ではわからない。しかし無秩序に要素を集めるのではなく、面白いと感じるざっくりとした要素を集めていく。
- 「創造性」は広義の意味合いとして、「創造の問いに関するあらゆる概念」としてゆるく使っていく。
イギリスの心理学者グラハム・ワラス(1858-1932)による創造性とは
ワラスは創造のプロセス(過程)を以下のような順序で説明している。
- 準備
- 孵化(あたため)
- 啓示(ひらめき)
- 評価・検証
「創造とは何かという定義、基準」よりも、「創造のプロセス」が重視されている。このような過程を経てできたものが、創造だという話。
【1】準備期(preparation)
・創造者が解決すべき問題についての論点や資料を探索して懸命に努力する時期
・問題があらゆる方面から検討される。
【2】孵化期(incubation)
・問題について意識的には考えを巡らしていないが、無意識の力が働いている
・熱心な研究にもかかわらず、行き詰まりを感じ、気晴らしや別の活動に携わる
【3】啓示期(illumination,inspiration)
・一見無為の最中に、突然あたかも他者が頭の中に吹き込んだような感じで解決が訪れる
・突然に、問題を解決するアイデアがひらめく。
・啓示の正しさを確信させるのは、美的感受性だという(フランスの数学者、ポアンカレをワラスは参考にしているらしい)。
【4】検証期(verification)
・論理的証明
・アイディアの妥当性が吟味され、明確な形をとった思想が完成する
・要点
1:創造性は突然真空から出現するものではない。無知や白紙状態から湧くわけではない。
2:基礎的な学習の努力、問題へ没入する集中力が重要。
3:発明・発見をもたらす道具としては、言語や数学的記号より、視覚・映像的記号を重視する。
4:4つの時期は境界をはっきりと区別できるわけではなく、重なり合ったり、順序が前後したりする場合があるという。
つまり、流動的な現象であると言及されることがある。たとえば教育心理学者の穐山貞登さんが言及している。
「20世紀初頭に,GrahamWallasはHenriPoincaréの創造的思考過程に関する試験を経験したことによって,彼自身の発想プロセスをモデル化した.準備,孵化,啓示,および検証という4段階のモデルであり,ほかのモデルの基盤となった。」
劉蕊「食事行動をとるインタフェースエージェント を利用した発想支援の研究」,9P
「イギリスの心理学者ワラスGrahamWallas(1858―1932)はこれを、(1)準備、(2)孵化(ふか)、(3)啓示、(4)検証の4段階に分けた。第一の準備は、創造者が解決すべき問題についての論点や資料を探索して懸命に努力する時期であるが、多くは熱心な追究にもかかわらず行き詰まりを感じ、一時努力は放棄され、なんらかの気晴らしや別の活動に携わる。これが孵化期であるが、その一見無為の最中に突然あたかも他者が頭のなかに吹き込んだような感じで解決が訪れる。これが、第三の啓示(インスピレーション)の時期である。答えは即座に正しさが確信され、その論理的証明が第四の検証期の仕事となる。したがって、第一に、創造性は突然真空から出現するものではなく、やはり長年月を要する基礎的学習という努力に加えて、当面の問題へ没入する集中のうえに築かれる。それは単なる思い付きではなく、まして無知や白紙状態と両立するものではない。第二に、発明・発見をもたらす用具として定型的な言語・数学的記号は使われることがなく、視覚・映像的記号が主役を演じる。第三に、啓示の正しさを確信させるのは、フランスの数学者ポアンカレJulesHenriPoincaré(1854―1912)によると美的感受性であるという。答えの均衡のとれた簡潔性と体系性が、まず感受性のふるいにかけられる。」
日本大百科全書(URL)
「ワラス(Wallas,G.)はヘルムホルツやポァンカレの経験をもとに,創造の過程を次の四段階によって説明している。「一,準備期(preparation),問題があらゆる方面から検討される。二,あたため期(艀化)期,(incubation),問題について,意識的には考えをめぐらしていないが,無意識の力が働いている。三,啓示期(illumination),突然に,問題を解決するアイディアがひらめく。四,検証期(verification),アイディアの妥当性が吟味され,明確な形をとった思想が完成する。こうした段階は,はっきりとその境界を区別できるはずはなく,重なりあったり,順序が前後したりする場合もありうるが,四幕のドラマのように,創造の過程を説明する仕方は天才のエピソードを語ったり,日記を分析したりする際に,しばしば踏襲されている。」ワラスの四段階は穐山氏も後述しているように,その段階を機械的に分離できるものではなく,流動的な精神現象であることをほのめかしている。」
高田哲雄「創造性の構造研究:ゲシュタルト論に基づく形態モデル仮説」,33P
イギリスの心理学者のチャールズ・スピアマン(1863-1945)の三つの思考原理とは
- 経験すること
- 経験の素材の間の関係を知ること
- ある経験の素材との関係からもうひとつの観念を生み出すこと(nongenesis,類推)。
この類推が、創造には重要になる。
個人的にはベイトソンの、ホモロジー(相同)、アナロジー(相似)、ホモノミー(同規)という区別を思い出す。
ドイツの心理学者、マックス・ヴェルトハイマー(1880-1943)による創造性とは
ゲシュタルト心理学の創始者
ヴェルトハイマーはゲシュタルト心理学の創設者の一人。ゲシュタルトとは「緊密なまとまりと相互関連性を帯びた全体としての構造」を意味する。
要素に分解すると、構造は失われてしまう。要素に分解して説明しようとする構成心理学や連合心理学に反発して創始したという。
生産的思考と再生的思考とは、意味
生産的思考:・経験の再生を越えて、なんらかの新しい反応・解釈を生み出すような思考。例:生物学の理論を、社会学の理論として応用できないか、と考えていくような思考。
再生的思考:・問題に対する過去の解決の応用に基づくものであり、古い習慣あるいは行動が単に再生される思考。例:1+1=2である、それゆえに、1+1+1=3であるなど。
ゲシュタルト学派では、人間には「生産的思考」と「再生的思考」という二種類の思考があると考える。
ヴェルトハイマーによる創造的思考とは
創造的思考:・問題そのものの発見を含んだ高次の生産的思考としてとらえ試行錯誤的にではなく洞察によってなされる
創造のプロセスは生産的思考と再生的思考の両方からなるが、とくに生産的思考が重視されている。
とりわけ、生産的思考の特性における「観点変更によって新しい思考体制が成立することによって、新しい結論が導出される過程」という点がポイントになる。
「一方,ウェルトハイマー(Wertheimer,M)2)は,創造的思考について,問題そのものの発見を含んだ高次の生産的思考としてとらえ試行錯誤的にではなく洞察によってなされるとしている。」
伊賀憲子 「MSC創造的構えテストの作成」,39P
「ギルフォードやトーランスたちは,創造性を能力としてとらえ,連続尺度による測定が可能であるとしているのに突すして,ウェルトハイマーは,全か無かの2分割的な立場をとっている。」
伊賀憲子「創造的思考の評価基準」,35-36P
「ゲシタルト学派のアプローチにみられる基本的概念の一つは,人間の思考には二種類が存在するというものである。一方は,新しい解決の創造に基づくもので生産的思考(Productivethinking)と呼ばれるものであり,他方は,問題に対する過去の解決の応用に基づくものであり,古い習慣あるいは行動が単に再生される再生的思考(Reproductivethinking)と呼ばれるものである。(Mayer.R.E,1979)再生的思考は,過去において学習した手続き・アルゴリズムの盲目的再生という特徴を持ち,思考の単位として刺激(stimulus)と反応(response)間の連合を用いる事で説明され,連合主義によって研究対象とされた。連合主義の見解によれば,問題解決とは過去経験による解決習慣の応用・または試行錯誤的なものであり,概して再生的であると捉えられている。これに反してゲシタルト学派は,より複雑な種類の思考・心的プロセスである生産的思考を説明する事に自らの問題を限定した。彼等が対象とした生産的思考の特性は,「観点変更によって新しい思考体制が成立する事によって,新しい結論が導出される過程である」というものであり,思考材料の再体制化を伴う点である。そして,本研究において議論の対象としている数学的創造性発揮が認められた問題解決過程において働き得る思考は,この生産的思考と共通項を持つものであると理解する。」
田中克征「数学教育における創造性育成と問題解決指導に関する研究-思考の固執に着目して」,32P
「再生的思考は過去経験の再生によるのに対して、生産的思考は経験の再生を越えて、なんらかの新しい反応・解釈を生み出すような思考をいう。」
土方文一郎「能力主義と動態組織」257ページ(グーグルブックスより)
アメリカの実業家のアレックス・F・オズボーン(1888-1966)による創造性とは
オズボーンは「ブレインストーミング」という方法の命名者として知られており、また創造性教育財団を設立している。
オズボーンもワラスの区分を増やしたような形で、創造のプロセスを説明している。
オズボーンによる創造プロセス
- 方向づけ:問題点を指摘する
- 準備:適当な資料を集める
- 分析:関連事項の分析をする
- アイデアを考える:いろいろな試みを行ってみる
- あたため:ひらめきの起こるのを待つ
- 総合:部分を集める
- 評価:出来上がった結果を評価する
オズボーンによる「着想を刺激するためのリスト(チェックリスト法)」
- 他に使い道はないか
- 他から着想は借りられないか
- 色・形・運動などを変えてみたらどうか
- 拡大したらどうか
- 縮小したらどうか
- 代用したらどうか
- 入れ換えたらどうか
- 逆にしたらどうか
- 組合わせたらどうか
「次にあげるオスボーン(Osborn,A.F)の場合においても区分を増やしただけのことで,本質的には筆者の形態モデルに包含される。「オスボーンは次の7段階をあげている。一,方向づけ一問題点を指摘する。二,準備一適当な資料を集める。三,分析一関連事項の分析をする。四,アイディアを考える一いろいろな試みを行なってみる。五,あたため一ひらめきの起るのを待つ。六,総合一部分を集める。七,評価一でき上った結果を評価する。」
高田哲雄「創造性の構造研究:ゲシュタルト論に基づく形態モデル仮説」,34P
「(1)オズボーンのチェックリスト法との関係ここでは,着想を刺激するため次のようなリストを作っているという(p.45)9。①他に使い道はないか,②他から着想は借りられないか,③色・形・運動などを変えてみたらどうか,④拡大したらどうか,⑤縮小したらどうか,⑥代用したらどうか,⑦入れ換えたらどうか,⑧逆にしたらどうか,⑨組合わせたらどうか。これをギルフォードの知能のカテゴリーと照合してみると,①は所産における含意に,③は種類の「図形的」,「行動的」に,④,⑤は「図形的」に,⑥,⑦,③は「所産の変換」に,⑨は「所産の体系Jに,それぞれ相当するように思われる。ただ,②だけは上の図式にはないが,それは正に拡散的というべきであろう。」
毛利亮太郎「勘考的思考と拡散的思考」,230P
教育学者のルイス・A・フリーグラー(1917-1974)による創造性とは
- 準備をすすめる:問題を分析し、一般的な知識を集める
- 欲求が高まる:問題を解こうとする欲求が内在化される。
- 問題点の選択
- あたため
- ひらめき
- 評価
- 再構成と再評価:創造性は繰り返され終わりがない
アメリカの心理学者ジョイ ・ギルフォード(1897-1987)による創造性とは
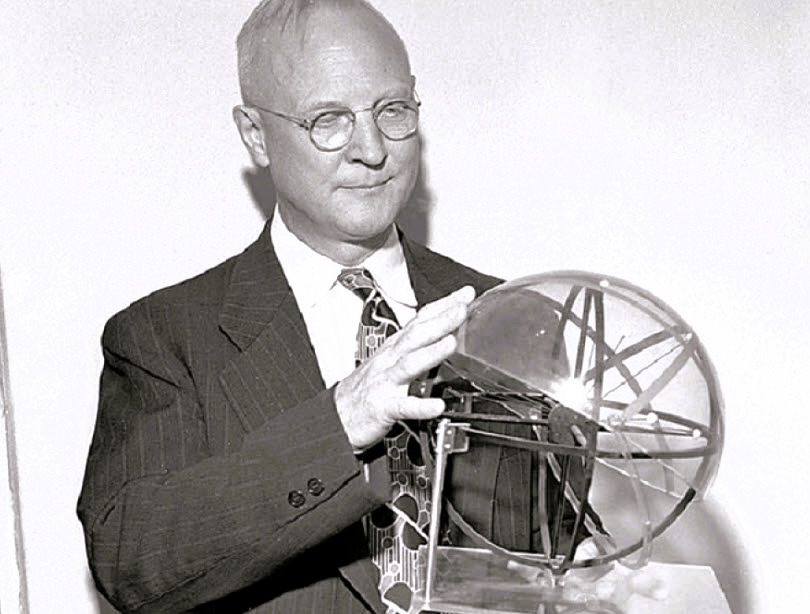 ・創造性を「能力」としてとらえ、連続尺度による測定が可能であるとしている
・創造性を「能力」としてとらえ、連続尺度による測定が可能であるとしている
収束的思考と拡散的思考とは、意味
集束的思考(知性):・一つまたは少数の定型化された解答様式が定まっているような課題事態に対処する思考様式。集中や収束とも表現されることがある。ギルフォードの場合は「集束」という翻訳のほうがいいかもしれない。
拡散的思考(創造性):・解答がかならずしもひととおりとは限らず、ときとして課題自体が明確に定式化されていないような事態に対処する思考様式であると定義されている。
・ギルフォードは「知性」と「創造性」を区別して考えている。
IQテストは創造性を測れるのか?
例えば歴史の年代や登場人物を暗記して、テストで回答するというような能力や、数学の方程式を覚えて当てはめるような能力は「知性」として分類される。
このようないわゆる暗記型の「勉強」は学業成績に関連する。IQテストのようなものも創造性とは別種の能力だという。つまり、IQが高いからといって、創造性が高いとはいえない。
・IQテストなどは正解が基本的に単一であり、複数の回答といった量をもとめられることはない。
・1962年のシカゴ大学において、IQ120以上の被実験者を対象に知能の高さと創造力の豊かさとの相関が分析された。とりわけ拡散的思考という因子が高いかどうかが基準となる。
その結果、両者の関係にも何の関係も導き出すことができなかったという。カリフォルニア大学のドナルド・マッキーノンによる研究においても、一定のIQに達している場合には知能と創造性との間には何の関係もないことが立証されているという。
6つの創造性因子、創造性テスト
・ギルフォードは創造性を6つの因子に分けている。要するに、この6つの因子が高ければ高いほど、創造性が高いということになる。
因子とは一般に、ある結果をひき起こすもとになる要素のことである。例えば爆弾は火薬という因子が必要になるようなイメージだろうか。火薬が多ければ多いほど、爆弾の規模は大きくなる。問題は、どのように数値化できるかである。
- 問題を受け取る能力
- 思考の円滑さ、流動性
- 思考の柔軟さ、柔軟性
- 独自性、独創性
- 再構成する能力
- 完成へ工夫する能力、入念性
1:問題を受け取る能力、2:思考の円滑さ、流動性、3:思考の柔軟さ、柔軟性、4:独自性、独創性、5:再構成する能力、6:完成へ工夫する能力、入念性
こうしたある種の基準を数値データとして用い、創造性の高低を「評価」するということである。サイコメトリックス(心を定量化し、数値データやモデルとして可視化する技法)というらしい。
「アメリカの心理学者ギルフォードは、第二次世界大戦中陸軍作戦局に動員され、臨機応変の対処能力についての研究を行ったが、この体験に基づいて創造性と知能とは別個の能力であると唱えるに至った。彼は、一つまたは少数の定型化された解答様式が定まっているような課題事態に対処する思考様式を集束(集中)的思考、一方、解答がかならずしもひととおりとは限らず、ときとして課題自体が明確に定式化されていないような事態に対処する思考様式を拡散的思考とよんで、この二つを区別した。前者の能力が知能、後者の能力が創造性であるという。このギルフォードの構想に基づいて、その後さまざまな創造性テストが開発された。その本質は、質量両面での連想の豊かさの計測にある。たとえば、新聞紙のような日常ありふれた物品の用途をできるだけたくさんあげる、無意味な線画に付け加えて絵画を完成する、などのテストが考案されてきた。これらのテストを用いての研究結果によると、創造性テストと知能テストとはあまり関係がない。創造性は、IQや学業成績とは別種の知的能力と考えられるが、おそらく全人格のあり方に依存するところが大きい。」
日本大百科全書(URL)
「ギルフォードは従来のIQテストでは人間の創造力を的確に捉えることができないとしており、人間の知的能力において創造力の重要性を強調した。ギルフォードの研究成果により、人間の創造力に関する研究が盛んになり、人間の一般知能と創造力に関する研究が平行して行われる結果となった。1962年シカゴ大学では、IQ120以上の被実験者を対象に彼(女)らの知能の高さと創造力の豊かさとの相関を分析したが、両者の間には何の関係も導きだすことができなかった。また、職場環境における知能と創造性との関係を考察したカリフォルニア大学ドナルド・マッキーノンによる研究においても、一定以上のIQに達している場合は、知能と創造性との関係には何の関係がないことが立証された。」
李在鎬「個人の創造性から組織の創造性へ」,21P
「まず第一に、1950年代から主流を為してきた創造性研究は、GuilfordJ.P.の創造力の因子説を基にした、サイコメトリックな分析方法を用いた研究である。Guilfordは創造力を、1.問題を受け取る能力2.思考の円滑さ、流動性(fluency)3.思考の柔軟さ、柔軟性(flexibility)4.独自性、独創性(oliginality)5.再構成する能力6.完成へ工夫する能力、入念性(elaboration)の6つの因子に分け、さらに個人のモテイベーションや気質の違いといった特性が、創造的な仕事ともっとも密接に関係すると主張した。」
夏堀睦 「人間性心理学における創造性研究 : A.H. MaslowとM.Csikszentmihalyiの創造性理論の検討」,48P
心理学者のエリス・ポール・トーランス(1915-2003)の創造性とは
TTCTとは、意味
トーランスはTTCT(Torrance Test of CreativeThinking)というテストを考案している。
※動画ではCreativeを足し忘れました
このテストでは流動性、柔軟性、独創性、入念性という4つの因子が基軸となっている。テストの目的は、創造的な人物を予測するためだったという。
トーランスによる創造的思考とは、意味
・トーランスは創造的思考を以下のように定義している。
トーランスによる創造的思考:・欠所、つまり、阻害要素や紛失要素を感知し、そのような要素についての考え、または仮説を形成し、これらの仮説を検証し、おそらくその仮説を正しく再検証して、その結果を人に伝達する過程。
「何か不足した事態の中で、それを解決するための独創的アイディアを生み出す能力」と簡潔に定義されることもある。
「欠如」を感知するという意味で、高橋誠さんの「問題」につながっていくのだろう。
「1960年代には,その後の創造性研究を牽引したトーランスが創造性テストを開発している。トーランスは創造的思考を「欠所,つまり,阻害要素や紛失要素を感知し,そのような要素についての考え,または仮説を形成し,これらの仮説を検証し,おそらくその仮説を正しく再検証して,その結果を人に伝達する過程」と定義している。」
佐々木宰「アジアの美術教育における創造性育成の可能性」,182P
「トーランス(Torrance,E.P)は,何か不足した事態の中で,それを解決するための独創的アイディアを生み出す能力である」としている。」
伊賀憲子「創造的思考の評価基準」,35P
小説家のアーサー・ケストラー(1905-1983)による創造性とは
『The Act of Creation』(1964)
ケストラーは想像力が創造へ繋がるプロセスを、バイソシエーションという概念で説明している。
バイソシエーションとは、意味
バイソシエーション(Bi-sosiation,双連性):・一見何も関係がないような二つのものが関連していること。
- 創造者は解決しなければならない問題にぶつかると、すべての情熱をそれに注ぐ。しかし、熱意だけで問題が解決できるわけではない。
- 知的挫折や情緒的な困難に陥る
- Aの多側面のうち一つと、Bの多側面のうち一つが交差・接木して新しいものが生まれる。ただし、没頭と中心という精神作用と偶発性が伴わなければいけないという。
「ArthurKoestler(1964)は、想像力が創造へ繋がるプロセスを“Bi-sociation”という概念で説明している。彼によると創造者は解決しなければならないある問題にぶつかると、すべての情熱をそれに注ぐ。しかし、熱意だけで問題が解決できるわけではない。そこで、知的挫折と情緒的な困難にまで陥ったりする。そうこうしている内にそれまでは何の関係もなかったある経験(A)と、他の経験(B)が、ある瞬間の観察により、互いに関連付けられるといったような「信号」を引き出すという。その信号は新しい発想の源泉になるのである。Aの多側面のうち一つと、Bの多側面のうちの一つが交差・接木して新しいものが生まれたといえる。但し、それには、人間の没頭と集中という猛烈な精神作用と、偶発性が伴わなければならないという点を繰り返し強調する。」
李在鎬「個人の創造性から組織の創造性へ」,20-21P
アメリカの心理学者、ジェローム・シーモア・ブルーナー(1914-2016)による創造性とは
ブルーナーは創造のプロセスを、直感的思考と分析的思考で区別している。
ブルーナーにとって、創造的思考とは、この両者の機能が統合されて、相互に補われて生じていくものである。ただし、とりわけブルーナーは直感的思考を重視している。
直観的思考と分析的思考とは、意味
直観的思考:・直観的に仮説を思いついていく思考。直観とは、「自分が使える分析の道具にそのまま依存することなしに、問題または事態の意味、重要性、あるいは構造を把握する行為」であるという。
分析的思考:・一時に一歩進むのがその特徴であり、その一歩一歩は判然としていてそれを思考しているそのひとが他のひとに十分に報告できるような思考。いわゆる論理的思考、合理的思考。
分析の道具とはたとえば「論理」などが挙げられる。たとえば三段論法の結論だけいきなり思い浮かんだり、また複数の結論同士を関連させ、それをまとめるようなアイデアを思い浮かんだりするイメージ。感情的、飛躍的思考。
たとえば「知識の構造」という場合、知識の相互連関を意味している。たとえば足し算と掛け算が相互に関連付けて理解できていなければ、数学の構造を理解しているとはいえないだろう。
おなじように、ある問題は複数の現象ないし複数の要素から、それらの相互連関によって、たんなる足し算ではなく掛け算のように、全体(構造)が構成されているといえる。相互連関が「論理的か、因果的か」が面白いところかもしれない。
たとえば1+1=2という思考は、第三者が見ても、当然そうだろうな、と思う。一方で、リンゴが木から落ちてきたのをみて、重力の法則を発見したというのは、第三者が十分に理解できる思考過程ではない。大きな飛躍があり、直観的思考に近い。(実際にニュートンがどのような思考過程だったのかは置いておいて、単純化して考えておく)。
知識の構造について
・ブルーナーによると、直観的思考をするためには、それに関連している知識領域とその知識の構造に精通していることが必要であるという。
例えば、物理学について何ら精通していないニュートンが、いきなり重力の法則を発見できるとは思えない。社会学や生物学に精通していないルーマンが、いきなり生物学のオートポイエーシスを社会システムに応用させようという発想には至らないだろう。→奇想天外な発想や偶然、奇抜さだけでは創造にはいたらない。
両者の関連付けが、AゆえにB、BゆえにCというように論理的に行われるのではなく、直観的に行われるというのがポイントになる。あるいは、論理的に行われていたとしても、それが無意識であり、飛躍的に行われるのかもしれない。
いずれにせよ、「ひらめき」のような、パッと瞬間的に結びつけられるようなイメージ。シャワーを浴びている時に、散歩している時に、夢を見ている時にふと思いつくような、そんなイメージ。
ブルーナーの思考とアブダクションの関連性
・ブルーナーによると、直観的に閃いた推論は、そのあと分析的に照合される必要があり、その結果得られたものが「仮説」であるという。
この仮説を発見する過程をC.S.パースはアブダクションと呼んでいる。アブダクションの後にも、さらに演繹や仮説といった分析的思考があり、さらにその前にも、知識の構造の理解のためには分析的思考がある。それらの反復によって、創造は行われる。とりわけ重要なのが直観的思考だという話。
機械にアイデアを入れて、これが(論理的に)正しいかと判定させるのは簡単だが、そもそもアイデア自体を機械に考えさせることは難しいイメージ。
人間は機械よりも、ヒューリスティック(直感的)だから、ということだろう。
物語様式と、論理―科学様式とは、意味
・ブルーナーは人間の思考様式を「物語様式」と「論理―科学様式」に区別している
物語様式:・「そして」といった事象間のより緩やかな接続関係をベースに組み立てられる
論理―科学様式:・対象世界を明確な科学的概念で区切り、さらに因果関係など緊密な関係で区切り関連づけてゆく。
おそらく物語様式は直観的思考に、論理―科学様式は分析的思考に関連していくる。
区切る世界と、区切らない世界
片井修さんによると、論理―科学様式では、「区切る世界」が形成されていき、物語様式では「区切らない世界」が形成されていくという。
たとえば幸運や不運を単なる「情報」としてとらえ、自分に有益/不利益かで採用/不採用という区分をするのは論理―科学様式である。一方、物語様式では、不利益や不幸であってもいきなり排除するのではなく、全体の連関の中に物語として位置づけ、包摂しつつ、共在させていくという。
デカルトのパラダイムと、デカルト以前のパラダイムとも対応するのかもしれない。「我々のうち何人が、自分自身を丸ごとの全体として捉えているだろう。社会から振り当てられた役割を演じ、こみ入った相互作用の儀式とゲームの中をさまよいながら、偽りの自己をせっせと紡ぎ出しているのが我々の現実ではないだろうか」というモリス・バーマンの言葉を思い出す。
区切る世界の行き過ぎは、世界の閉塞につながっていく。区切ることの良さも考え、そのバランスをとっていくことが重要になる。
「ブルーナーは教育の課程という本の中に直観的思考と分析的思考についてつぎのように述べている.「分析的思考は一時に一歩進むのがその特徴である.その一歩一歩は判然としていてそれを思考しているそのひとが他のひとに十分に報告できるのが普通である。直観的思考は入念で輪廓のはっきりした段階を追って進まないのが特徴である。一見したところ問題全体に対するあらわにあらわすことのできない感知にもとづいた操作を含むのがつねである.その解決は正しいかもしれないが,反対にまちがいかも知れないのである。直観的思考をするには,それに関連している知識領域とその知識の構造に精通していることが必要であるがそうすることによって,思考しているひとは段階をとびこえ近道をしながら自在に進むことができるのである。だがそれには,演繹的であろうと帰納的であろうと,もっと分析的な手段によって結論をあとでふたたび照合する必要がある.」とのべている.」
原弘道「発見的な学習指導のあり方」,10P
「ブルーナー(Bruner,J.S.,1962)によれば、直観的思考と分析的思考は機能的に違いはあるとしても、両思考はお互いに相補性を有していると述べる。それは科学的思考における二次元機能の相補性を中心に考えられている。」
棚原健次 「創造的思考類型と自発性に関する研究」,101P
「認知科学者J.ブルーナーは,人間の思考様式を「論理–科学様式」と「物語様式」に大別した3).前者は対象世界を明確な科学的概念で区切り,さらに因果関係など緊密な関係で区切り関連づけてゆく.後者は,「そして」といった事象間のより緩やかな接続関係をベースに組み立てられる.この緩やかな「そして」が事後的な関連付け・意味づけの基盤をなしており,「区切らない」物語りの世界を形成していく.」
片井 修「共創のライプニッツ時空」,1023P
「先に紹介したMECEやフィルトレーションは,時々刻々入ってくる区分的情報によって世界の可能な在り方が次第に絞られていくことを顕在化させるものである.一方,「物語」の世界では,単純に排除ということにはならない.たとえば,人に降りかかった幸運や不幸を単に情報として捉えると,それが自分にとり有益か否かだけの判断で採用したり排除するという「区分」の働きがまず起こる.ところが,「物語様式」の思考の世界では,不幸な体験にもそれなりの深い意味や意義があり,そこからの深い学びや心境を深めることにより,それらを排除するのではなく,全体の連関の中に「物語」として位置づけ「包摂」しつつ「共在」させることとなる.」
片井 修「共創のライプニッツ時空」,1027P
「直観的思考(直観intuition)の重要性を強調している。ブルーナーによると、「直観とは、自分が使える分析の道具にそのまま依存することなしに、問題または事態の意味、重要性、あるいは構造を把握する行為を意味している」」
海谷則之「デューイ・人間性実現への教育: 米国カリキュラム開発を考える – 86 ページ」(グーグルブックス)
「ブルーナーの直観的思考は,洞察といわれるものであり,十分な論理的訓練を経た後に生じるもので問題に直面したとき,その論理を意識しないで,直接に解決への見通しをたてることのできることをさしている。」
Takeshi Itō「Bunshōdai shidō no gendaika. (1907-) – 87 ページ」(グーグルブックス)
「論理的な推理の過程を一つひとつ段階的に進む分析的思考に対して……」「教育心理学用語辞典 – 133 ページ」(グーグルブックス)
「直観的思考は、ブルーナー( J.S. BRUNER )が、科学的思考においてその重要性を強調している。直観的思考と論理的思考は、その機能は違っているが、相互に補われるべきものなのである。このように創造的思考は、それぞれ相対立する心的機能が統合されて……」
「研究と独創性 – 160 ページ」(グーグルブックス)
「. ブルーナーは理科の学習において、直的思考の重要性を強調している。直観的思考は分析的思考と異なり、一歩一歩と論理的に進むのではなく、直観的に仮説を思いつき、理または認知に達する。これによって、まず知識の開拓に一鍬いれることが必要で、ついで ……」
「文部時報 – 第 1098~1109 号 – 53 ページ」(グーグルブックス)
「米盛によるアブダクションは、ブルーナー(J.S.Bruner)による直観的思考・分析的思考とも通ずる内容である。ブルーナーは直観的思考について、次のように述べている。
直観的思考は、入念で、輪郭のはっきりした段階を追って進まないのが特徴である、事実それは、一見したところ問題全体に対するあらわにあらわすことのできない感知にもとづいた操作を含むのがつねである。思考しているひとはそこにいたった過程をほとんど意識することなしに解決に達するのであるが、その解決は正しいかもしれないが反対にまちがいかもしれないのである。そのひとはどのようにその解決を得たかを自分ではうまく説明できないうえに、問題状況のまさにどの面に対して反応していたかにも気づいていないかもしれない。(4,pp.73-74)
直観的思考は、アブダクションの第一段階と同様に、ほとんど意識されることなく行われる推論であるといえる。しかし、ブルーナーは、直観的思考は決して適当に行われている「思考」ではないとして、次のように述べている。
直観的思考をするには、それに関連している知識領域とその知識の構造に精通していることが必要であるが、そうすることによって、思考しているひとは段階をとびこえ近道をしながら自在に進むことができるのである。(4.p.74)
直観的に「思考」するためには、問題に関連する知識の領域と構造に精通している必要がある。その知識を選択し根拠として直観的に「思考」していることになる。さらにブルーナーは、分析的思考について次のように述べている。
いちど直観的方法で得られたならば、その解決は、できるなら分析的方法で照合されなければならないが、一方それと同時に、そのような照合の場合、その解決は価値ある仮説として尊重されなければならない。(4.p.74)
直観的に閃いた推論論は、その後分析的に照合し、その結果えられるのが仮説という主張である。ブルーナーは、
「すばやく仮説を生み出し、その価値はわからなくても、そのまえに、諸観念の結合を思い当たらせるのは直観的様式である。」(4.pp.76-77)
と述べており、直観的思考・分析的思考は、仮説を生み出す「思考」であるとしている。このことを図示すると、次の図II-1(「アブダクション〈値直観的思考・分析的思考》」)のようになる。」
米田 豊 「社会科教育における思考力・判断力・表現力の評価方法の開発 教育現場の実態把握と論理学、分析哲学、社会学、認知心理学の研究成果を組み込んで 最終報告書」,16-17P
市川亀久弥(1915-2000)による創造性とは
市川さんは「創造は等価性の応用によって達成される」と考えた。
等価性とはなにか
等価性:・2つの事象を比べてみたときに、それらが互いに異なった事象であっても、ある一定の観点をおいて見れば、同じ事象として認定できるということ
・等価性の具体例
木の葉と肺臓は、等価性の関係にある。葉脈と気管支の分布の状態が、同じ「枝分かれ構造」にあるという。
木から落ちるリンゴと月の運動は、「万有引力」という同じ物理現象であるという。
高性能水管ボイラーの発明は、人体を巡る血液循環モデルを等価変換して発想されたものだという。
等価変換はざっくりいえば、アナロジー(類推)によるAからBへの思考の転移であるといえる。既知の事柄Aから未知の事柄Bへ進んでいく過程が創造であり、その過程にアナロジーがある。
たとえば人間と社会は違うが、システムという観点でみれば、AもBも同じ事象である、つまり等価性があると考えていく。社会学者であるルーマンは同じシステム、つまりオートポイエーシス・システムがあると考えていった。最初にオートポイエーシス・システムを考えた生物学者たちは、社会にも応用できるなどとは主張していなかった。こうした観点を変えて複数の現象の等価性を見つけていくというものが、創造のプロセスとして重要だ、というのは面白い。また、ルーマンの「機能等価主義」や「コンティンジェンシー(偶有性)」にもつながっていくものがある(後述)。
等価変換図式とはなにか
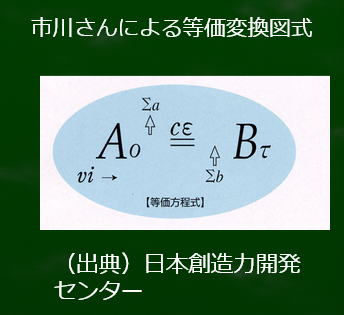 Aο-原系(出発系)の中の具体的事象の一つ(クリアすべき課題、または他のモデル)
Aο-原系(出発系)の中の具体的事象の一つ(クリアすべき課題、または他のモデル)
Bτ-変換系(到達系)に出現した事象(発明、開発の完成)
vi-観点(ものを見るときの角度や立場、考え方の方向性:開発目的に合った観点を1つ選ぶ)
ε-ひとつの観点のもとで、Aοから抽出した抽象的な要素(物事の核心、願望の中心)
c-抽象的要素に具体性を与える限定条件
cε-具体化された開発の核心をなす概念(アイデア)
Σa-原系の特殊な条件群(モデルの中の不要な要素、開発時には廃棄の対象)
Σb-変換系の特殊な条件群(開発時に新たに必要となる要素、導入の対象)
重要なのは、創造には要素と要素を等価視する新たな観点が必要不可欠になるという点。こんな観点から!そこと同一視する?というようなイメージ(エウレカ)。
月だけ見ても重力はわからない。新たにリンゴの要素を加えてみる。両者に共通している要素として、重力という観点が発見される(重力そのものはリンゴや月のように観察できず、まさに説明原理として創られる)。ここで、リンゴの特殊要素は説明にとって不可欠なものとはいえず、開発時には廃棄される場合もある。重力はリンゴでなくても説明できる。要素ではなく、関係を重視する。
アナログ型思考とデジタル思考とは、意味
1:市川さんは創造的直観は「あらゆる感覚器官に捉えられた外部の情報を脳の中に取り入れて適切な情報処理を施す」ことによって生じると考えている。
2:市川さんは、情報処理活動をアナログ型とデジタル型に区別している
アナログ型思考:・二、三次元への拡がりをもち、相対的に幅を持った連続量を示す思考のこと。
デジタル型思考:・一次元的現象を正確に把握し、一義的に定義可能な、具体的で明確な定量性の特徴を有する思考のこと。
自然や宇宙の存在の仕方そのものが、根源的に等価性をもつ
・市川さんは、「わたくしどもの人間の頭脳がそれを意識すると否とかかわらず、 自然や宇宙の存在の仕方そのものが、 適当なアブストラクション(抽象化)を通ずると、根源的に等価性を内在している」と主張している。
例えば眼球とカメラの間の等価関係、音波通信系とマイクロウェーブ、原子模型と天体模型など。
さらにデザインでは白バラを出発系として、ウェディングドレスが設計できるという(両者には、清潔感、優雅感、気品感といったような条件を備えた美観として、等価関係を確立している)。
ベイトソン「宇宙の『秩序』と『パターン』の解明に通じるものは、どれも絶対につまらない研究ではない」
市川さんの話を聞いて思い出すのが、ベイトソンの話である。まずはそのまま、全文引用する。
「自然界のあらゆる分野の現象に、同じ種類のプロセスを探っていくことができるのではないか、そんな神秘的な考えに、わたしはすっかり染まっておりました。結晶の構造と社会の構造とに同じ法則が支配しているかもしれない、とか、ミミズの体節の形成プロセスは溶岩から玄武岩の柱が形成されていくプロセスと比較できるかもしれない、とか。今のわたしなら、同じことをこう表現するでしょう。──ある分野での分析に役立つ知的操作が、他の分野でそのまま役立つことがある。自然の枠組み(形相)は分野ごとに違っていても、知の枠組みはすべての分野で同じである、と。しかしかつての私は、そのことを神秘的な表現において信じたのです。そして、その信仰はわたしの研究にある種の威厳を与えました。ヤマウズラの羽のパターンを分析しているときでも、いま自分は自然のパターンと規則性という大問題と向かっているのだ、その答えの一かけらを摑もうとしているのだ、という意気込みを持つことができました。そればかりか、この神秘主義は、生物学で学んだこと、物理・科学の基礎コースから拾い上げた思考法をそのまま活用する自由も与えてくれた。人類学の研究に、自然科学の分野で学んだことが役に立つということを私は疑いませんでした。」(グレゴリー・ベイトソン「精神の生態学」,134P)」
さらに、ベイトソンは「宇宙の『秩序』と『パターン』の解明に通じるものは、どれも絶対につまらない研究ではない」とも主張している。
なにか物事、要素に共通のパターンが、共通の秩序があるのではないか、と新しい観点を見出していく作業が重要だという姿勢が、創造に言及する関する人々には共通してある。こうした共通する秩序やパターン、価値を「生き生きとした構造」と表現したのが建築家のアレグザンダーである。宗教が力を持った時代では神だったが、言葉を変えて、同じものが表現されているのかもしれない。「何が世界を安定させるのか」という問い、問題に対する答えにはこうした発想が必要になるのだと思う。
他者が本当に大事にしているものは、自分にとってもなにか大事なのかもしれないと考えてしまうことがよくある。言葉にできないが、凄い何かを感じる。
その感情の強さが、今回はとても強かった。絶対につまらない研究ではない、と確信・断言できるほどの研究や生き方をしたい。
「市川亀久彌教授は等価変換理論の立場から、創造的直観といわれるものの内容に、一応の見取図を与えている。直観を生ぜしめる直接の原因は何か、という問題である。それは、あらゆる感覚器官に捉えられた外部の情報を脳の中に取入れて適切な情報処理を施していることに過ぎないとする。しかし情報皆無の状態で認知や予測ができるというのでなく、極めて少ない情報を手にしてでも認知や予測を可能にすることができる。かくして直観機能は、広義の情報処理活動による一種の認識方法であることを述べている。ところで情報を伝達したり、それを処理したり、それが発生させたりする場合に、そこに二種類のパターンの存在を認めている。それは情報処理装置として発達をとげてきた電子計算のアナログ型(AnalogType)とディジタル型(DigitalType)の区別によっている。アナログ型は二、三次元への拡がりをもち、相対的に幅をもった連続量を示すものである。デジタル型は一次元的現象を正確に把握し、一義的に定義可能な、どちらかといえば、代数的な性格をもつものであり、具体的で明確な定量性の特徴を有するものである。以上のように、アナログ型直観情報とデジタル型直観情報を区別している。」
棚原健次「熱応理論の研究: 特に創造性の機能-構造を通して」,52-53P
「等価変換という言葉から多くの人々の受ける感じは,類推,すなわちアナロジーによるAからBへの思考の転移である。しかしこれは,あまりにも概念的な把握であり,創始者の同志社大学理工学研究所・市川亀久弥教授の論をそのまま紹介することによって,より正確な内容を伝える方がよいと思われる。等価変換理論(EquivalentTransformationThink-ing)が,単なる漠然たるアナロジーと異なる点はその内容を分析し,精錬された形で等価方程式にまで定式化されているからである。AとBが,”何となく似ている”というだけのアナロジーは,A≒Bとでも安易に表現されるかも知れない。しかし,等価変換を示す方程式(等価方程式)には,次のごとく,より多様な内容が盛りこまれているのである。(1)A0,Bτともに既知に属している場合に両者に共通している適当なc,εの設定によって上式の意味を成立させることを,両者の等価関係を発見したという。②既知であるA0を適当な観点(Vi)の導入によって,cεにまで抽象(分解と捨象によってΣsca-iの廃棄)し,これに新しい条件群(ΣScb-i)を加えて再構成することを,A0からBτへ等価変換したという。o:Aなる事象の座を占めている系(原系or出発系)τ:Bなる事象の座を占めている約(変換系or到達系)A:原系oの上に出現している事象。B:変換系τの上に出現している事象。または,c・εの媒介により,τ系上に再構成された事象。ε:式の両辺を等号で結ぶことを可能とする等価次元(等価対応の次元であって単数)c:上記等価次元を具体的に定義する限定条件。(但し,原則的には複数で,ΣG)Σsca-i:出発系(o系)の特殊化的条件群。Σsca-i:到達系(τ系)の特殊化条件群。Vi:任意の観点の中の一つ。→:思考方向の指示。これによって,アナロジーとして,古くから問題となっている思考の原理が,精度高く,多様な角度から見直されている。」
大江 精三, 村上 幸雄「創造性をめざす科学基礎論的研究ことに, 学問の分類および研究方法の問題をめぐって」,21P
「この理論のポイントは、思考作業を行うに際しての「等価性の発見」に重要な位置を与えている点にあります。等価性とは、2つの事象を比べてみたときに、それらが互いに異なった事象であっても、ある一定の観点をおいて見れば、同じ事象として認定できるということです。
例えば、木の葉と肺臓を比べてみますと、植物と動物に特有な器官でお互いに無関係のように見えますが、分配という観点から見ると、葉脈と気管支の分布の状態はそれぞれ水分配とガス交換をおこなう上で不可欠の形態であり、「枝分かれ構造」という同じ状態を示していす。また、木から落ちるリンゴと月の運動はともに「万有引力」という同じ物理現象であり、銀河と台風もまた巨大な流体の回転によって生じる「渦」という観点から等価であるといえます。
創造とはこうした等価関係の応用によって達成されますが、わわわれはそれを「等価変換」と呼んでいます。 一例を挙げますと、一時世界を風靡した高性能水管ボイラーの発明は、人体を巡る血液循環モデル、一般化すると「流体循環」を等価変換して発想されたものです。
このように相対的に解析の進んでいる事柄、すなわち既知の事柄と、解析の進んでいない事柄、いわば未知の事柄との問に潜んでいる等価性の発見は、創造や開発といった仕事にとって重要な要素です。いい換えれば、すでに知られている情報の適切な利用は、未知の事象の分析、発明や発見の基本方向の決定をするうえで、きわめて有効なヒントになり得るのです。
この思考過程を<等価方程式>という論理式にまとめ、またこれにコンピューターのプログラムの考えを取り入れて、<等価変換フローチャート>として思考の出発点から完成までを一枚の思考流れ図にまとめて技術開発の実用に供しています。 」参照URL
「
Aο-原系(出発系)の中の具体的事象の一つ(クリアすべき課題、または他のモデル)
Bτ-変換系(到達系)に出現した事象(発明、開発の完成)
vi-観点(ものを見るときの角度や立場、考え方の方向性:開発目的に合った観点を1つ選ぶ)
ε-ひとつの観点のもとで、Aοから抽出した抽象的な要素(物事の核心、願望の中心)
c-抽象的要素に具体性を与える限定条件
cε-具体化された開発の核心をなす概念(アイデア)
Σa-原系の特殊な条件群(モデルの中の不要な要素、開発時には廃棄の対象)
Σb-変換系の特殊な条件群(開発時に新たに必要となる要素、導入の対象)以上は、発明・技術開発向けの説明ですが、もともと汎用性のある方程式で、時間・空間を超えて歴史上の事象、自然界、社会に存在するすべての事象に適用することができます。
」
参照URL
「次は, 話題をかえて服飾デザインの世界に立入ってみよう。第13図と15図は, 前者が白バラで後者がウェディングドレスである。例によって, この両者間に等価関係を設定してみると, およそ第14図にみるようなものとなる。すなわち, 清潔感, 優雅感, 気品感, という条件を備えた美感として, 両者は等価関係を確立していることになるのである。したがってもし, 第 5図に示した等価方程式の概念をこれに挿入してゆくと, 当然, 白バラを出発系 (AO) として, ウェディングドレスの (Bτ) が設計できることになる。端的にいうと, 等価関係と, 等価変換との間には, 表裏一体の関係が成立っている。 」
川喜田二郎『Energy』, 第3巻第4号, 特集「人間と創造力」,孫引き(出典URL)
「はなはだ荒っぽい議論になって恐縮だが, 第16図~第22図は, わたくしどもの人間の頭脳がそれを意識すると否とかかわらず, 自然や宇宙の存在の仕方そのものが, 適当なアブストラクションを通ずると, 根源的に等価性を内在しているものであるという説明例を示したものである。 」
川喜田二郎『Energy』, 第3巻第4号, 特集「人間と創造力」,孫引き(出典URL)
「宇宙の『秩序』と『パターン』の解明に通じるものは、どれも絶対につまらない研究ではない、という曖昧な答えをするのが精一杯だった。」
グレゴリー・ベイトソン「精神の生態学」,22P
「自然界のあらゆる分野の現象に、同じ種類のプロセスを探っていくことができるのではないか、そんな神秘的な考えに、わたしはすっかり染まっておりました。結晶の構造と社会の構造とに同じ法則が支配しているかもしれない、とか、ミミズの体節の形成プロセスは溶岩から玄武岩の柱が形成されていくプロセスと比較できるかもしれない、とか。今のわたしなら、同じことをこう表現するでしょう。──ある分野での分析に役立つ知的操作が、他の分野でそのまま役立つことがある。自然の枠組み(形相)は分野ごとに違っていても、知の枠組みはすべての分野で同じである、と。しかしかつての私は、そのことを神秘的な表現において信じたのです。そして、その信仰はわたしの研究にある種の威厳を与えました。ヤマウズラの羽のパターンを分析しているときでも、いま自分は自然のパターンと規則性という大問題と向かっているのだ、その答えの一かけらを摑もうとしているのだ、という意気込みを持つことができました。そればかりか、この神秘主義は、生物学で学んだこと、物理・科学の基礎コースから拾い上げた思考法をそのまま活用する自由も与えてくれた。人類学の研究に、自然科学の分野で学んだことが役に立つということを私は疑いませんでした。」
グレゴリー・ベイトソン「精神の生態学」,134P
「諸価値基準の相違は、ある一つの中心的な価値基準に訴えれば解消できると私は信じている。まったくのところ、この中心的な価値基準はすべての背後にある。それをわれわれは一者(the one)や無(the void)と呼んでもよいだろう。すべての人はこの価値基準と結びついており、自分自身の意識を目覚めさせることによって、程度の差はあっても、この価値基準と接触できる。この単一の価値基準との接触は、われわれの行為に究極の基盤を与え、創造者、芸術家、建築家としての行為に究極の基盤を与えると私は信ずる。」
長坂一郎「クリストファー・アレグザンダーの思考の軌跡」,136P(アレグザンダーの文章の孫引き)
アメリカの心理学者、ウィリアム・ゴードン(1919-2003)による創造性とは
 ゴードンは創造プロセスを「問題の設定と解決という状況の下で、結果として芸術的または技術的発明を生ずる精神活動」と考えている。
ゴードンは創造プロセスを「問題の設定と解決という状況の下で、結果として芸術的または技術的発明を生ずる精神活動」と考えている。
シネクティクスとはなにか、意味
シネクティクス:・ギリシャ語で「一見関連のない要素を結びつける」という意味がある。グループによる創造性開発の理論であり、創造活動の過程を説明するもの。
シネクティクスは適当な心理的状態を誘発して、創造活動を促進することを目的としているという。
具体的には以下のような心理状態があるという。
- 感情移入
- 没入
- 遊び
- 脱離
- 関連のないものの利用
ゴードンのシネクティクスでは合理的要素よりも非合理的要素を優先する傾向がある。
馴質異化と異質馴化とは、意味
シネクティクスは2つの思考法がある。
馴質異化(じゅんしついか):・見慣れたものを見慣れないものにすること。
異質馴化(いしつじゅんか):・見慣れないものを見慣れたものにすること。
このようなプロセスによって、新しい見地から問題をみることができるようになるという。馴質異化は一時的に曖昧で渾沌とした状態に陥り、不安で落ち着かない気持ちが起こることがあるという。
人間は見慣れた世界に落ち着いてしまう傾向があるので、このような防衛を捨て去る必要(異質馴化)があるという。これを聞いて思い出すのが、右脳と左脳の切り替えを使った絵の練習方法である。訓練次第で絵の模写がうまくなる方法であり、個人的に興味がある。あるいは、ベイトソンの学習3(パラダイムが恣意的なものにすぎないことを悟る経験)を思い出す。
馴質異化は、次の4つのメカニズムがあるという。
- 擬人的類比
- 直接的類比
- 象徴的類比
- 空想的類比
「ところで集団の中での直観的思考方法として、W,J,JGordonによって寄与されたシネクティクス(Synectics)があげられる。シネクティクスはギリシャ語の「一見関連のない要素を結びつける」という意味を示すものである。シネクティクスは、グループによる創造性開発の理論である。よく訓練されたグループが問題の設定や解決する創造活動の過程である。シネクティクスでは、創造過程とは問題の設定と解決という状況の下で、結果として芸術的または技術的発明を生ずる精神活動と定義している。ここでは単に問題解決(problemsolving)というよりは、問題設定ならびに解決(problem-stating,problem-solving)という表現を用いるが、それは問題の定義と理解を含ませるためである。-シネクティクスの実践的メカニズムは、創造過程をささえ進行させる具体的な心理的要素である。このメカニズムは発明という最終生産物を判断するのに用いようという意図もない。創造過程における心理的状態として、(1)感情移入(Empathy)(2)没入(Involvement)(3)遊び(play)(4)脱離(Detachment)(5)関連のないものの利用(useIrrelevant)それらのものは、創造過程の基礎となるものであるが、実践的なものではない。シネクティクスのメカニズムは適当な心理的状態を誘発して、創造活動を促進することを目的とする。問題設定ならびに解決の状況下において、常に問題を理解することである。したがってシネクティクスの過程には次のものが含まれている(1)異質馴化(Makingthestrangefamiliar)見慣れないものを見慣れたものにすること(2)馴質異化(Makingthefamiliarstrange)見慣れたものを見慣れないものにすること。見慣れないものを見慣れたものにすること(異質馴化)について、人間は、根本的に、保守的であり、見慣れない事物や観念に直面すると、心のもち方を変えて受入れるた止めに、形を変えてみたりすることに少なからず困惑し抵抗する。しかしながら心の働きは見慣れないものを前に知っている資料と照合して、それによって見慣れないものを見慣れたものに変えてしまう。問題を新しい見地からみることである。その新しい観点は、新しい根本的な解決を生ずる可能性をもつことになる。見慣れたものを見慣れないものにすること(馴質異化)について、それは前からある同じ世界、人間、概念、感情事物を意識的に新しい角度からみようとすることである。既知の世界のある側面を意識的に、見かけ上焦点のずれた見方でみる方法である。しかしこのような状態を続けていると不安な落ち着かない気持が起こることがある。しかし見慣れたものを見慣れないものにしておくことは、創造の基本的な訓練の一つである。新しいものの意味と可能性を認識しょうとするならば、少なくとも一時的には、あいまいかつ混乱した状態に陥る危険を冒さなければならない。人間は型にはまった言葉と認識の方法を受け継いでいるため、見慣れた世界に納って安心してしまう。このような防衛を捨て去って、一時的にあいまいな状態に耐えなければならない。ところでシネクテイクスの馴質異化には次の四つのメカニズムがあげられる。(1)擬人的類比(PersonalAnalogy)(2)直接的類(DirectAnalogy)(3)象徴的類比(SymbolicAnalogy)(4)空想的類比(FantasyAnalogy)このメカニズムは再現可能な心的過程であり、創造活動の武器であるといえる。」
棚原健次「熱応理論の研究: 特に創造性の機能-構造を通して」,55P
「ゴードンのシネクティクス(Synectics)は知的要素より感情的要素を,合理的要素よりも非合理的要素を重視し,離脱(普通の立場から離れる),没入,迂回,瞑想をあげている(p47)9。これも一種の思考方法であろうが思考の内容についてではない。次に,氏は人格的,直接的,象徴的な類推をあげている(同)。これは課題を擬人化してその動きを考えることであり,自然界にあるもの等に比べて考え,イメージによって考えることであるから,ギルフォードの情報の種類における「図形的」なもの一一「行動的」なものが加わっているようであるが一に属すると考えられる。」
毛利亮太郎「勘考的思考と拡散的思考」,230P
マルタの心理学者、エドワード・デボノ(1933-2021)による創造性とは
デボノは人間の思考を「水平思考」と「垂直思考」に区別している。
そして、創造的思考を主に「水平思考」と関連付けている。しかし、アイデアは両方の思考が必要であり、水平思考がアイデアを生み、垂直思考がそれらを育てるという。お互いが補い合っている関係にある。
垂直思考と水平思考とは、意味
垂直思考:・常識にとらわれ一定の枠から抜け出すことの出来ない硬直した思考法。
論理的思考法に根をもっているという。横の思考法。「だから」や「したがって」を多用するような思考。西洋において支配的な思考法である、という点も個人的に重要。
水平思考:・既成の枠組みを離れ、様々な角度から自由に思考を巡らして手掛りをつかむ手法の思考法。縦の思考法。「ところで」や「たとえば」、「そういえば」を多用する思考法。
例:一休さんのとんち
「このはし渡るべからず」と書いてあれば、普通は、常識では「この橋を渡るな」という思考になる。橋を渡っていいか交渉しようとかありきたりな発想ばかりが出てくる。しかし、「この端を渡るな」という別の角度から思考を巡らせて、橋を渡ってしまう。結果的に問題が解決してしまう。なんでもかんでも常識や論理に頼る必要はない。
水平的思考の4原則
- 支配的なアイデアを見つけること
- いろいろなものの見方を探し求めること
- 垂直的思考の強い統制から抜け出すこと
- 偶然のチャンスを活用すること
デボノは水平的思考に我々をスムーズに導いてくれるものとして、パラドクス(矛盾)やユーモア(機知、とんち、機転)を挙げている。
個人的にパラドクスが水平的思考につながる、という点が面白い。のちに検討するが、コミュニケーションというものは論理的に矛盾したものばかりだからである。「急がば回れ」というような目に見えてわかるような矛盾だけではない、という点が重要になる。
ダブルバインドと創造的な出口
ベイトソンの文脈では矛盾が分裂病にもつながるというのもポイントになる。「これをやったらだめ、やらなかったらだめ、さらにそれを指摘することもだめ、逃げることも駄目」というようなダブルバインド状態で人間は狂気に陥る。
たとえば母親が「愛している」と言いながら、子どもへの身体的接触で避けるようになり、「お母さんどっちなの」と言及することすら許されないような状態。
さらに思い出すのが、ベイトソンが挙げていた「この棒が実在するといったらお前を打つ。実在しないと言ったらお前を打つ。黙っていたらお前を打つ(公案)」というダブルバインド(二律背反)である。
論理的思考だけでは、解決できない。しかし、相手の棒を奪い取り、それを折ってしまえば解決できるかもしれない。モリス・バーマンはこのような解決を「創造的な出口」と呼び、それが創造的かどうかは「コミュニケーションの質」によって決まるという。身につけた習慣を変えることを学ぶことを「学習3」や「忘我への覚醒」とベイトソンは呼ぶ。
現代において正気とは、「橋と端」の違いをそれぞれのコードによって把握できることであり、狂気とは把握できないことであるといえる。
普通は、「はしをわたるべからず」と書かれていたら橋だと解釈する。そういうコードのもとで我々は生きている。
狂人は、あえて普通の解釈をとらないというような選択ではなく、とれないようなイメージ。
創造者は、意識的に、あえて橋と端を区別しないような自由な選択、今までの学習をあえて崩すことができるような、コンテクストの横断の能力のある人なのかもしれない。
「デボノ(DeBONOE)は水平的思考(Lateralthinking)と垂直的思考(Verticalthinking)の両機能を提唱している。水平的思考は、新しいアイデアの創出につながっているので、創造的思考と密接に関係している。しかし創造的思考は、水平的思考という広い範囲の考え方のなかの、特定の一部分にすぎない。水平的思考は、時には天才的な創造的思考であり、単なるものの見方の変更だけで、大きな創案とならないこともある。創造的思考では、しばしば特別な表現の才能を必要とすることはあるが、水平的思考は新しいアイデア開発に関心ある人間ならば、誰でも利用できる。ところで、水平的思考の原則として、次の四つをあげている。(1)支配的なアイデアを見つけること。(2)いろいろなものの見方を探し求めること。(3)垂直的思考の強い統制から抜けだすこと。(4)偶然のチャンスを活用すること垂直的思考は、水平的思考が新しいアイデアを生み出す場合に役立たないばかりか、アイデアの生れるのを抑制していることがある。なんでもかんでも論理的に分析し、総合しなければならないという考え方で、無理矢理に思考を規制してしまう。垂直的思考はことがらをはじめる出発点として、仮設を立てたり、これを軸に理論を展開したり、変換したりすることは必要であるが、この方法だけでは、まったくの新しいアイデアを生みだすことはまずできない。垂直的思考のように、既成の理論を受け入れたり、これにとらわれたりすることは、混沌の中にかくされている可能性を否定するものである。水平的思考ではつねに正しいことは必ずしも必要としない。ただ最終的な結論が正しければよいのである。水平的思考とは、いうなれば、ぬかるみの中にはいって行き、本来の道をさがし出すことなのである。各段階が、どこででも正しくあるべきだという考え方は、おそらく新しいアイデアを生み出す最大の障害となるであろう。」
棚原健次「熱応理論の研究: 特に創造性の機能-構造を通して」,54P
「水平的思考との関係 デボノの水平思考の4原則,①支配的なアイディアを見つけること,②いろいろなものの見方を探し求めること,③垂直的思考(論理的思考)の強い統制から抜け出すこと,④偶然のチャンスを活用すること(p.46)9,は思考方法を拡散的思考と同じくしているが,構造的には深く立ち至っていない。」
毛利亮太郎「勘考的思考と拡散的思考」,230P
「1.支配的で偏ったアイディアを見つけること2.異なった色々な見方を探し求めてみること。3.垂直思考の強力な統制から開放されること。4.偶然のチャンスをできるだけ利用すること。-エドワード・デボノ:NEWTHINK,筆者訳一小石のエピソードの中の娘の対処の仕方をこれらの原則に従って分析を試みる。1.支配的で偏ったアイディアを見つけること→娘は絶対に白い石を引かなくてはならない。2.異なった色々な見方を探し求めてみること→結局バッグの中に黒い石が一つ残ればよい。3.垂直思考の強力な統制から開放されること→論理的な三つの方法以外にも可能性を探る。4.偶然のチャンスをできるだけ利用すること→足下には白と黒の石が敷き詰められている。」
田文揚 「水平思考と傾斜思考の仮言的考察:縦横のロジックから斜めのロジックへ(個人研究)」,33P
「論理的思考に根を持つ垂直思考は常識にとらわれ一定の枠から抜け出すことの出来ない硬直した思考法である。一方水平思考は問題解決に当たって既成の枠組みを離れ、様々な角度から自由に思考を巡らして手掛りをつかむ手法の思考法である。水平思考に我々を時にスムーズに導いてくれるものの中に、パラドクス(Paradox)やユーモア(Humor)がある。パラドクス(逆説)とは一見矛盾しており真理に反しているようであるが、よく吟味すれば真理である論理や、逆の見方も成り立ちそうな言葉や表現を意味する。“More haste,less speed”「急がば回れ」“The child is father to the man”「子供は大人の父なり」これらの表現は逆説的である。このように一見馬鹿げた言いまわしの論破や擁護に真剣に対処しようと議論し、理屈を尊重する思考習慣の中から西洋哲学の基礎が形成された。パラドクスは明示的な命題で表現されるが、哲学的問題意識は必ずしも明瞭な形をとるものではない。それを明瞭な形で示し常識や論理や経験知との対立を明確にする行為こそが、層哲学的思索を本質的に深化させることになるはずだ。パラドクスは哲学思想のみならず論理学や数学と関係が深く、とても理屈張ったものだ。ユーモアが思考を柔軟にするのは解るが、なぜそんな理屈張った議論の立て方によって生じる論理的パラドクスまでもが、水平思考に有効なのかと疑問視する向きもあるだろう。だが、パラドクスは一見矛盾しているようだがその奇抜さや落差ゆえに大いに興味を喚起される。人間味に根差したユーモアも奇抜さや落差を楽しむという点で共通している。だからどちらも水平思考に有効なのだ。」
田文揚 「水平思考と傾斜思考の仮言的考察:縦横のロジックから斜めのロジックへ(個人研究)」,29P
「好奇心をもった総合的な幅広い思考は、特に理系の教科には強く求められる。そのことは日本学術会議(2007)でも、またノーベノレ賞受賞者も述べていることである。幅広い思考はデボノの主張する水平思考」であり、創造的な思考である。これは一つの答えにまっしぐらに突き進む「垂直思考」とはまったく異なる。正解は一つであるに拘っていると創造力は生まれない。」
中野靖彦「子どもの発達と教育についての一考察」,53P
「デボノは、論理的思考や分析的思考にみられる垂直的思考に加えて水平的思考を提唱した[64].垂直的思考が限界に達した時、水平的思考が必要とされる.水平的思考の一つの具体例を次に例示する.日常の身の回りのちょっとしたもので、本来の機能とまったく違った使い道を考案したものである.引き金を引くと高圧ガスが吹きだすような護身用の器具である.盆の上にあるソーダ・サイフォンが目についてそれを応用したものである.そのソーダ・サイフォンの中の飲み物を空っぽにして、その代わりに高圧ガスを詰め込むという発想である。」
牧野逸夫「特許知識を活用した発明知識空間構成法と技術アイディア発想」,23P
「水平思考は、西洋において支配的な思考方法であった垂直思考、すなわち論理思考の欠点を補う思考です。デボノは水平思考がいかに創造的かをこんな故事を挙げて説明しています。」
中澤豊「マクルーハン・プレイ」(グーグルブックス,第三章)
「西洋の例ばかり出しましたが、実は日本は水平思考の宝庫です。機知に富んだ答えで窮地を逃れる一休さんの話などはその典型でしょう。水平思考の人は、硬直的なものの見方に縛られず、事を別の角度から見ることによってピンチを大逆転に変えることができるのです。思考のプロセスの美しさよりも良い結果がでればそれでいいのが水平思考です。」中澤豊「マクルーハン・プレイ」(グーグルブックス,第三章)
「一方、垂直思考の人は、事態を冷静に見渡し、密に検討し、論理的に考えを進めますが、人の話のように切羽詰まっ状況を打開することはできません。論理的で話が通っているということは前の中に織り込まれているということで、そこに新しい発見は生まれないのです。日常の言葉では、「だから」とか「したがって」という言葉が発言に多く入る人は垂直思考の人です。一方、「ところで」「たとえば」「そういえば」と、梶へへ話題を展開していく人は水平思考の人です。論理思考が支配している企業組織においては、こうした文脈を欠いた水平思考の人は「非合理的人物」とされ、低い評価をされがちです。ですが、この文脈を欠いた水平思考こそマクルーハンのいうクールな思考、すなわちアナロジー思考なのです。「説明」という線的思考を逃れ、視点を変えながら問題を三六〇度から考察していきます。聞き手の方も、自身で解釈する余地(遊び)が多く残されているため、問題への関与度が高まり、コミュニケーションにおける創造の場が生まれます。大企業などでは、上司が「柔軟に考えろ」と言いながら、その上司が論理一辺倒の人というのは珍しくありません。会社組織、官僚組織において上に行けば行くほど水平思考は難しくなります。マクルーハンが、「落伍者としての経営幹部」と指摘した事態です。現場を離れ、思考のための材料を欠いているのです。新しいアイデアは、垂直思考の統制が弱まった組織の末端でしか生まれません。そこはまた「新しい組み合わせのための資料」が豊富にそろっています。創造を必要としている現場では水平思考型人間は不可欠な人材と言えるでしょう。」
中澤豊「マクルーハン・プレイ」(グーグルブックス,第三章)
「ベイトソンが挙げている考案は、師が弟子の頭上に一本の棒をかざし、『この棒が実在すると言ったら、おまえを打つ。実在しないと言ったらおまえを打つ。黙っていたらおまえを打つ』と宣言する、というものである。まさにダブルバインドの典型である。これに対しどういう創造的な出口が可能だろうか?出口が創造的かどうかは弟子が行うメタコミュニケーションの質で決まる。たとえば弟子は、師から棒を奪いそれを折ってしまうことができる。もし師が、その行為が弟子の概念的=情熱的飛躍から生まれていると判断すれば、師はこの反応を良しとするであろう。学習Ⅲにおいて、人は学習Ⅱで身につけた習慣を変えることを学ぶ。我々をみな等しくダブル・バインドに追い込む分裂生成的習慣を一掃するのである。人はそこで、自分が無意識のうちに学習Ⅱを行う存在であることを自覚する。あるいは、学習Ⅱを制御しコントロールすることを覚える。学習Ⅲは学習Ⅱについて学習することなのだ。それは、自分のパーソナリティーの束縛から自由になることであり、かつてウィリアム・ベイトソンが真の教育に与えた定義である、『忘我への覚醒』へ至ることにほかならない。」
モリス・バーマン「デカルトからベイトソンへ」,268P
湯川秀樹さん(1907-1981)における創造性とは
湯川さんは創造の過程(創造性の発現の過程)において、「同定」というものが不可欠だと考えた。
この同定という概念を元に、同定理論をつくりあげ、創造性を説明しようとした。
同定理論とは
同定(どうてい,英;identify):・異なるもの(似ていないもの)を同じだと認識すること。
例:大きな林檎と小さな林檎は同じだと、単に認識することは同定ではない。林檎と月は似ていない、異なるものだが、しかし、両者が同じ法則(万有引力の法則)に従っている、というのは同定である。
同定と類推の関係
論理学において類推とは「二つの物事の間のある点の類似性から、他の点での類似性を推理すること」を意味する。例:犬も人間も哺乳類という点で類似している、それゆえに、犬も人間と似たような感情がある。
1:同定は類推と同義ではない。しかし、同定は類推によって可能になる。
2:類推の場合は「似ている(類似性)」を推理していくが、同定の場合は「同じである(同定性)」を推理していくことになる。単に似ているということだけではなく、さらに、どういう点が同じかということに気がつくことが本質的に重要だという。
3:似ているものを同じだと推理していくのではなく、似ていないものを同じだと推理していくことに同定の本質がある。
たとえば、あるアメリカ人がAという日本人を勤勉だったと認識したとする。その後、Bという日本人に会う。この際、AとBは日本人という点で似ていることから、さらにBも同じように勤勉だろうと推理する。似ているもの(日本人と日本人は似ている)を同じだと推理していくのは同定ではない。
同定は、まるで違うものを同じだと認識していく作業である。たとえば、エアコンと人体はまるで違う。しかし、どちらも温度を同じような仕組みで調節しているのではないか、と推測していく。あるいは、人体の仕組みをエアコンに応用できるのではないか、と応用していく。
「湯川秀樹博士は創造性における同定論(TheTheoryofIdentification)を説明するに当って、類推が創造性の発現として重要であり、それが古くから多くの人々によって認められてきたことを指摘されている。先ず類推には、二つのことがらの間に似たところのあることと、共通する部分のあることがあげられる。また類推はしばしば〝比喩”“隠喩模型等の思考様式をとるものである。Newtonはリンゴの落下と月の周期運動との間に、両者が同一の運動法則に従っていることを発見した。ところでリンゴの落下運動と月の周期運動との間には、直接的な類似性を発見することは極めて困難な問題である。Newtonは、それを速度、加速度、質量、力等の概念を媒介として、両者に共通する本質の解明に到達した。したがって、湯川秀樹博士は類推を同定(Identify)の中に含めて述べておられる。そこにおいて図形認識といったような人間特有の同定の仕方も亦人間本来の同定のプロセスに深い関係のあることを述べている。」
棚原健次「熱応理論の研究: 特に創造性の機能-構造を通して」,53P
「いずれにしても相当広い範囲に於て適応される原理というものを見つけること自身は、我々の合理的思考、あるいは実験し実証するという活動そのものではないわけです。それを越えているものであって、そのことが、先づひとつの創造性につながる大事な点です。とかく世の中では、科学というものをいわゆる実証された事実の積み重ねみたいに思っている人が多いのです。もし科学が実証された事実の積み重ねに過ぎないならば、それは殆ど価値はないものです。」
湯川 秀樹「科学と創造性」,2P
「同定理論は,創造性の発現に関する理論である。博士は,理論物理学の研究過程のなかで,創造性とは一体何であるのか,どうしたらば人間は創造性を発揮できるのだろうかと創造性の発現について問題を提起した。その背景には,科学技術の発達は人間の創造性の発現の結果であり,創造性こそが繁栄を続けていくための最後の拠り所であるという考えがあった。創造性とはなにか。この壮大な問いについて考えるために,創造性とはどのように創成されるのかについて,湯川博士は「同定」という概念をもって説明を試みている。」
川岸克己 「同定理論と自己非自己理論」,2P
「こまでをまとめると,同定とは,ふたつの物事に似たものを見つけることであるが,そのふたつの関係は,すでに似たものではなく,一見似ていないものであることが重要である。さらに厳密にいえば,似ているととらえるのではなく,同じだととらえることが同定の本質である。」
川岸克己 「同定理論と自己非自己理論」,4P
「リンゴと月は,「円いものという以外は似ても似つかない」というが,似ても似つかないというところをあえて同じであると同定することによって,同定は高度化する。高度化は,つまり回り道であって,その回り道とは,直感的な概念によって説明されるべきものではなく,さまざまな新たな概念を必要とすることである。同定は直接的な類似を発見することでもなく,同定によって何か創造性を有するものが直感的に得られるものでもないこと」
川岸克己 「同定理論と自己非自己理論」,5P
「ニュートンは,当初同定されるべき何かをはっきりとつかんでいたわけではないと湯川博士は考える。つまり,何と何を同定すればよいかを知ることはできないというわけである。そして,湯川博士は,ニュートンがその同定されるべき本質を「勘」によって知ったという。勘とはまた漠然とした物言いだが,勘というのはつまり,自らが予め想定することのできないものに何かがあると感じる力である。予め知り得ないものを知るというのは矛盾している。しかし,予め知り得ないものを知ろうとするのは矛盾だが,予め知り得ないものであるが故に,さまざまなふたつのものを同じであると結合させ続けようとする行為が,ここでいう勘のひとつの側面である。」
川岸克己 「同定理論と自己非自己理論」,5P
「確かに,類推は論理的に弱い推論形式である。しかしながら,その弱さが同時に予め知り得ないことを見出していく同定の強みとなる。論理性の弱さは,いわば予測不可能であるということでもある。さらにその予測不能ということは,新しい発見がそこに生まれてくる可能性をもたらすことでもある。」
川岸克己 「同定理論と自己非自己理論」,6P
以下、上記論文の孫引き
「「月」という言葉は月そのものと結びつけられている。遠い遠い古代の日本人が,月を見て,これを「つき」と呼ぶことにした。月という天体と「つき」という言葉とを「同定」(identify)したのである。それは多分,偶然的なむすびつけであったろう。」
(湯川秀樹「同定の理論序章」『創造の世界湯川秀樹自選集IV』,51P)
「創造性の発現の具体的な形は何かということについて,昔からよく言われているのは,類推という知的作用の活用です。類推といわれているものの中で,一番簡単な形は比喩です。譬え話です。」
(同「同定ということ」『湯川秀樹著作集4科学文明と創造性』,158P)
「創造論というのは,要するに類推ということから話がはじまる。類推以外のところに手がかりはないのではないかとわたしは昔から思っておりました。]
(同『私の創造論』p.10)
「類推が創造性の発現として機能するのは,今まで誰も気づかなかった類似性の発見としてである。それは一見まったく別と思われる,ふたつのもの,ふたつのことがらの間に,似たところがある,共通性があるという認識である」
(同「同定の理論序章」『創造の世界湯川秀樹自選集IV』p50)
「似ているというだけでなく,どういう点が同じかということに気がつくということが本質的に重要」
(同「同定ということ」『創造の世界湯川秀樹自選集IV』p79)
私のいう同定というのは,違うものを同じと思うということですね。同じものを同じと思うのは意味が
ないのでありまして,どこか違う二つのものを同じと思うということです。
(同「離見の見」『自己発見』p216)「ニュートンはリンゴの落ちるのを見て,なぜ月は落ちてこないのかと疑った。リンゴと月とは,まったく別物だと,それまでの人たちは考えてきた。ニュートンは両者の運動に共通するものを発見しようとした。」
(同「同定の理論序章」『湯川秀樹著作集4科学文明と創造性』p135
「ニュートンはお月さんとリンゴとを結びつけた,両方の類似性を見つけたわけではありますが,問題はどういう点で両者に共通性があると思ったか,つまり両者について同定さるべき本質が何であったかということが,決定的な問題であります。(中略)そうしたら何が同じか,何が同定されるべきか。ニュートンは,その時,同定さるべき本質をはっきりつかんだわけではない。しかし漠然とはしているが,何かを勘で知ったのである。その勘を,もっとはっきりした形にしなければならない。ニュートンがそこから出発して,結局において発見したものは何であったか。」
(同「同定ということ」『創造の世界湯川秀樹自選集IV』p8
「未知なものがあるということがわかっているためには,すでにわかっている部分がなければならない。既知という認識がなければ未知もない。わかっているということがわからなければ,わからないということもわからぬ。」
(同『創造への飛躍』p.147)
教育心理学者の恩田彰さん(1925-2015)における創造性とは
恩田彰さんにおける創造性:・新しい価値あるもの、またはアイディアを創り出す能力、およびそれを基礎づける人格特性
創造する能力(創造的技能・活動)と、人格(パーソナリティ)の両方とした点がポイント。
恩田彰における創造的思考:・直観的思考と論理的思考(分析的思考)の統合されたもの
直観的思考の6つの特徴
- 知覚的で受容的である
- 論理をもって筋道をたどらない
- 飛躍的である
- 同時的・全体的である
- 本質を把握する
- 結論的である
ESP(超能力)とは
恩田さんは創造的思考において、ESPが重要になってくるという。ESP(Extra Sensory Perception)とは一般に、予知や透視などの超感覚的知覚のことである。いわゆる超能力である。
これだけを聞くと怪しいなと思うが、しかしインスピレーションやイルミネーション、霊感、神のおつげ、直観、非合理的要素など、さまざまな言葉で創造過程において今までも多くの人に語られてきた。たとえばワラスも解明の段階では「ひらめき」が重要になる。
恩田さんはワラスにおける準備→検証過程を、「意識的な過程(現実的過程)」、あたため→解明の過程を「無意識的な過程」と表現している。
解明の状態は一種のトランス状態や催眠状態であり、注意が集中された無我の状態だという。アイデアが向こうからやってくるような状態であり、入眠時や出眠時にそうした状態になりやすく、ESPが生じやすいという。
インスピレーションやESPによって浮かんできたアイデアは、評価し、検証し、訂正されていく必要があるという。
得られたアイデアが論理的に正しいか確かめられたり、調査によって確かめれたり、役立つかどうか確かめられる必要がある。
こうした流れは、パースの言うアブダクションから演繹、帰納と進んでいく流れと類似している。ただし、ESPの場合はインスピレーションとは違い、験証が難しいという。
インスピレーションやESPによって浮かんできたアイデアは、評価し、検証し、訂正されていく必要があるという。
得られたアイデアが論理的に正しいか確かめられたり、調査によって確かめれたり、役立つかどうか確かめられる必要がある。
こうした流れは、パースの言うアブダクションから演繹、帰納と進んでいく流れと類似している。ただし、ESPの場合はインスピレーションとは違い、験証が難しいという。
「日本では,1960年代半ば頃から産業界からの要請を背景に創造性研究が行われるようになり,数年後に学校教育界において創造性教育の研究が始まったという3)。日本の創造性研究で知られる恩田は「創造性とは,新しい価値あるもの,またはアイディアを創り出す能力すなわち創造力,およびそれを基礎づける人格特性すなわち創造的人格である」と述べている」
佐々木宰「アジアの美術教育における創造性育成の可能性」,182P
「創造性(Creativity)とは何かという,創造性の定義および概念については,多種多様であるが,それらの中には,ひとつの共通した概念が存在すると考えられる。すなわち,I創造性とは,ある目的達成または新しい場面の問題解決に適したアイデイアや新しいイメージを生み出し,あるいは社会的・文化的に,または個人的に新しい価値あるものを作り出す能力,および,それを基礎づける人格特性である」とする恩田彰3)の説に代表されるものである。この定義・概念の中には,新しいアイデイアや新しいイメージを作り出す能力,すなわち,創造的技能(創造的活動)と,それを基礎づける人格特性(パーソナリティ)の2つの要素が含まれている。そして,創造的技能は,創造的思考力が重要な基礎となっている。」
伊賀憲子 「MSC創造的構えテストの作成」,39P
「ところで,創造性の定義・概念の,もう1つの要素である人格特性について,恩田4)は,その要因として「自主性・衝動性・固執性・好奇心・開放性・内省的傾向・純粋な心」をあげている。そしてさらに,創造性の人格特性の特徴について,次の8項目にまとめている。①自己統制(自己の心身,自己の感情の統制),②自発性(自分の意志で積極的に行動する傾向),③衝動性(心的エネルギーの強さ・意欲の強さ),④持続性(心的エネルギーの持続性),⑤探究心(知的探究心・新しい経験,成就の欲求),⑥精神集中力(1つのことに精神を集中する),⑦独自性(他の人とは違った考えや行動をする傾向),⑧柔軟性(いかなる環境や状況においても積極的に適応していく態度)の8項目である。」
伊賀憲子 「MSC創造的構えテストの作成」,40P
「恩田(1971)は、直観的思考の特徴を次のように述べている。それらは1知覚的で受容的である。2論理をもって筋道をたどらない。3飛躍的である。4同時的全体的である。5本質を把握する。6結論的である。つまり創造的思考は直観的思考と論理的・分析的思考の結合である。それは両思考の結合として捉えられている。」
棚原健次 「創造的思考類型と自発性に関する研究」,101P
「また創造過程はWallas,G.によると,1.準備(preparation)2あたため(incubation)3.解明(霊感,illumination,inspiration)4.験証(verifica-tion)の4つに分けられる。しかし、この4つの段階をはっきりと区別し,その順序を明確化することは困難である。その段階は相互に関連し、力動的である。しかし,これを現実的過程(意識して努力する過程)と非現実的過程(無意識的な過程)との2つに分けることができる。(A現実的過程準備→験証’B非現実的過程あたため→解明(→あたため→解明)これによるとESPは非現実的過程の解明に含まれる。それでは解明の状態はどういう特徴を持っているであろうか。いわゆる1種のトランスの状態であるが,必ずしも、ぼんやりはしていない,注意が集中された無我の状態である。また自発性(spontaneity),自律化(autonomy)を有する。すなわちアイデアが向こうからやってくる。音楽のテーマが聞えてくる。ESPのイメージが浮んでくるといった状態である。インスピレーションやESPが生じやすい時期に入眠時と出眠時がある。この時期は1種の催眠状態あるいは類催眠状態というべきもので、受動的であるが,ある程度覚醒意識を持ち,イメージを客観的に観察ができる。創造過程においては,インスピレーションがしばしば最後の段階に属することがある。しかしたいがいは,これで終りにならない。浮んできたアイデアは、評価し,験証し、または訂正される必要がある,えられたアイデアが論理的に正しいかどうか、思考によって確かめられる。また芸術や技術的発明では、そのアイデアが実際に役立つことが示されなければならない。これが験証の過程である。ESPもインスピレーションと同じく,その内容は思考によって確かめられ,調査によって確かめられなければならない。しかしESPの場合、験証が難しく,験証がほとんどできないとか、これを欠く場合もある。(2)創造的思考は,直観的思考と論理的思考(分析的思考)の統合されたものと考えることができる。この見方によると,ESPは直観的思考の大部分または1部に働くことが推測される。」
恩田 彰「創造過程におけるESPの役割」,16P
ロバート・スタンバーグ(1949~)における創造性とは
創造性:・斬新で(独創的で、予期しない)、適切な(有用で、適応性のある)成果を生み出す能力
創造性は何故必要なのか→個人レベルでは日常生活の現実問題の解決、社会的レベルでは新しい科学的発見、発明、社会的プログラム、新しい製品、サービス、雇用など。
鼎立理論とはなにか、意味
鼎立理論(ていりつりろん):・人の知能は分析知能、創造知能、実践知能という3つの知能から構成され、それらをバランスよく組み合わせることで、社会的に成功するために必要な「成功知」を獲得できるとする理論
とりわけ重要な知能は「実践知能」であり、実践知能とは、分析知能と創造知能の両方を適切に調整し、現実世界に適応する能力であるという。また、実践知能の測定方法なども提案している。IQ(分析知能)が高いからといって実践知能が高いわけではない、という調査結果が出ていることも興味深い。
「スタンバーグによれば,創造性は斬新で(独創的で,予期しない),適切な(有用で,適応性のある)成果を生み出す能力であるとされる。創造性は,幅広い領域における個人的レベルと社会的レベルの重要で広汎なトピックであり,個人的レベルでは仕事や日常生活の問題解決のために,社会的レベルでは新しい科学的発見,芸術的ムーブメント,発明,社会的プログラムにつながる可能性をもち,新しい製品,サービス,雇用を生み出す創造性の経済的重要性は明らかだという」。
佐々木宰「アジアの美術教育における創造性育成の可能性」,182-183P
「ロバート・スタンバーグ(R.J.Sternberg)は,IQ(知能指数)が予測できる知的能力の範囲はかなり限定的であり,現実世界の具体的問題にうまく対処する能力として実践知能(PracticalIntelligence)を提唱している.実践知能は,日常生活の現実問題を解決する能力であり,机上の問題解決ではない.」
山口高平「レクチャーシリーズ:「シンギュラリティと AI」[第 3 回] 実践知能| 多重知能のためのメタ AI アーキテクチャ」,985P
「スタンバーグは,この実践知能の分析をさらに発展させて,成功知のための鼎立理論という理論を提唱している.鼎立理論は,人の知能は,分析知能,創造知能,実践知能という三つの知能から構成され,これらの知能をバランス良く組み合わせることで,社会的に成功するために必要な知能である成功知(SuccessfulIntelligence)を獲得できるとし,成功知を獲得するために核となる知能が,分析知能と創造知能を利用しながら行動を決めていく実践知能だと説明している[スタンバーグ98].すなわち,分析知能は必要であるが,それだけでは前には進めないという意味で不活性知能であり,その一方で,創造知能とは,リスクを考慮しながらも一歩踏み出そうとする活性知能であり,この二つの知能を適切に調整し,現実世界に適応する知能が実践知能であるとしている。」
山口高平「レクチャーシリーズ:「シンギュラリティと AI」[第 3 回] 実践知能| 多重知能のためのメタ AI アーキテクチャ」,985P
社会学者の熊坂賢次(1947~)さんによる創造性とは
熊坂さんは創造性を「単なるパターンの多様性」だと定義している。
パターンを多く持っている方がより創造性があり、そうしたパターンを使い、実践でうまくいった場合、それは創造と呼ばれるという。
たしかに数学のみしか詳しくない人より、生物学と数学の両方に詳しい人のほうが「なにかを生み出しそうだな」という予感はする。しかし多くの分野に薄く手を出しすぎても失敗しそうな気もする。いずれかの分野を軸にしつつ、あらゆる分野に手を出し、関連付けていくほうが上手くいく気がする。
【熊坂】「僕にとって創造とは何かと言うと、もうぶち壊しのような発言だけど、単なるパターンの多様性だと思う。ある人がもっているパターンが五個だったら、六個持っている別の人の方が勝ち。そのパターンの多様性を考えて使って、その試行錯誤の結果、実践でうまくいくぞ、となった瞬間、それがクリエイションと呼ばれる、という簡単な考えなのです。」
井庭崇、他「社会システム理論」,224-225P
國藤進さん(1953~)における創造性とはなにか
國藤さんは創造のプロセスを以下のように分類している。
- 発見的思考
- 収束的思考
- アイデア結晶化
- 検証・評価
発散的思考とはなにか、意味
発散的思考:・そもそも課題は何かという点を明らかにし、その問題に関連ある知識を先入観なく収集し、現状の分析を行う段階の思考
自分自身の記憶、文献検索、インタビュー、フィールドワーク、サーチエンジンなどさまざまな手段を通じて情報を集めていく。この際、ブレインストーミングの4原則(批判厳禁、自由奔放、質より量、結合発展)に伴って収集していくことが重要であるという。ある意味で、この長い動画作成もその段階なのかもしれない。
収束的思考とはなにか、意味
収束的思考:・問題の本質を追求し、問題解決のための本質的仮説を発見していく段階の思考。最も苦戦する段階だという。
ここで詰めが甘いと、単に整理された仮説が量産されるだけで、検証に値するアイデアにまで結晶化しないという。
アイデア結晶化とはなにか、意味
アイデア結晶化:・複数の仮説のどれが最も根源的なものかを直感的に評価し、採択する段階。
形式知だけではなく暗黙知も動員するという。形式知とは一般に、文章や図解、数値などで客観的に表現できる知識である。
暗黙知とは一般に、個人の経験や勘に基づく、言語化出来ない知識である。暗黙知はポランニーにつながるものであり、関連性が気になる。
評価・検証とはなにか、意味
評価・検証:・ある仮説が採択され真であると仮定したら、どんな帰結が導けるか、何らかの実験計画あるいはシミュレーションによって検証することによって、採択仮説の統計的検定を行う段階。
人間の頭の中や、ノートの中で演繹させてみたり、あるいは実際に帰納しているか実験や観察をしてみたりする段階である。國藤さんの場合は、科学的・工学的方法を用いてシミュレートすることに特に重きがおかれている。
「創造的思考に関するワラスの有名なモデル「準備,あたため,ひらめき,評価・検証」に啓発され,「発散的思考,収束的思考,アイディア結晶化,評価・検証」からなる創造的問題解決のプロセスモデル[AI誌93]が提案され,このモデルの各プロセスを支援するツール(環境)を構築することが,一般に発想支援システムの研究といわれる.
発散的思考プロセスでは,そもそも課題は何かを明らかにし,その問題に関連ある知識を虚心坦懐に収集し,現状の分析を行う.知識収集のプロセスも,自分自身の内省的・経験的記憶の思い出しから始め,文献検索,インタビュー,フィールドワーク,サーチェンジンなどのあらゆる知識収集手段を通じて,与えられた課題の関連情報を,ブレインストーミングの4原則(批判厳禁,自由奔放,質より量,結合発展)に則って収集していく.
収束的思考プロセスでは,問題の本質を追求し,問題を解決する仮説を生成する.発散的思考プロセスで得られた膨大な関連情報を整理・統合するなかで,それらの奥に隠されている問題の本質を追求し,問題解決のための本質的仮説を発見していく.人間にとって最も苦心惨憔するプロセスで,一般に複数の仮説が生成される.なおここでの詰めが甘いと,単に整理された仮説の候補が多数生成されるだけで,検証するに値するアイディアにまで結晶化していないことになる.
アイディア結晶化プロセスでは,収束的思考プロセスで生成された複数の仮説のどれが最も根源的かを直観的に評価し(ときには,インスピレーションによって)採択する.このプロセスでは,形式知のみならず暗黙知まで総動員し,候補仮説(場合によっては,アイディアにまで昇華された洗練候補仮説)のなかから最も納得する根源的仮説を選定することが大切である.したがって,暗黙知を形式知に変換したり,暗黙知を暗黙知のまま相手に伝えるメディア環境の構築が大切である.
評価・検証プロセスでは,ある仮説が採択され真であると仮定したら,どんな帰結が導け,この帰結を何らかの実験計画あるいはシミュレーションによって検証することによって,採択仮説の統計的検定を行う.したがって,ここでは既存の科学的・工学的方法を利用し,問題向きの評価・検証支援ツールを研究開発することが主要課題となる。」
國藤 進「発想支援システム」,476P
高橋誠(1943~)さんによる創造性とは
創造や創造性とはなにか
創造:・人が異質な情報群を組み合わせ統合して問題を解決し、社会あるいは個人レベルで新しい価値を生むこと
創造性:・ある目的達成または新しい場面の問題解決に適したアイデアを生み出し、あるいは新しい社会的、文化的(個人的基準を含む)に価値あるものをつくり出す能力およびそれを基礎づける人格特性
高橋さんは「創造性」を「創造的な可能性」とも表現している。
問題を事前に発見する能力、予測能力、粘り強く挑戦する態度など、さまざまな要素を含めた多義的な定義として用いられている。
そもそも問題発見・問題解決における「問題」とはなにか
問題:・期待と現状との差
高橋さんは問題を「期待と現状との差」として定義している。
また、問題への解答が単一の場合と、複数の場合があるという。そして、創造的問題は多数(複数)解答の問題に主に属しているという。
- 問題への解答が単一の場合の類似概念:明確に規定されている問題、学校問題。
- 問題への解答が複数の場合の類似概念:明確に規定されていない問題、社会型問題。
たとえば1+1はいくつかという解答は基本的に単一だが、部下にどうアドバイスしたらいいかという解答は複数考えられる。テンプレートのもののようなものはなく、その場その場の文脈による。
発生型の問題と、発見型の問題とは、意味
高橋さんは問題を2つに分類している
- 発生型の問題:天災のように予測しにくいもの。
- 発見型の問題:経済現象のように、ある程度予測できるもの。
たとえば、絵が上手くなるためにはどうしたらいいか、と問いをたてていけば、将来ぶつかる問題を予測することができる。
発生してから慌てて考えるよりも、あらかじめどんな問題が生じるか予測する力が重要だという。
たとえば、店の商品が盗まれてからではなく、盗まれないようにはどうすればいいかと先に問題をたてて行くイメージ。
「問題とは、『期待と現状との差』と定義できます。この差をなくし期待を実現したら、問題を解決したことになります。問題には『発生型と発見型』の二種類があります。発生してから慌てて解決策を考えるのではなく、あらかじめ問題を発見するように心掛けたいものです。問題解決には『問題意識を持つ』ことが大切です。そして、その解決が新しい価値を生むものであれば、それが創造的問題解決といえます。」
高橋誠「問題解決手法の知識」,14P
「ミンスキーという学者は、問題は二つに分類されるといいます。『明確に規定されている問題』と、『明確に規定されていない問題』。言葉の使い方がちょっとわかりにくいのですが、意味するところは次のようなことです。『明確に規定されている問題』とは、◯✗問題のように2つのうちどちらかが正解という問題です。一方『明確に規定されていない問題』とは、回答が多種多様にある問題のことです。大学入試の試験問題で、知能テストの問題などは、答えは唯一のものが多く、前者のタイプの問題です。一方、私たち会社や家庭などで直面する問題は、後者のタイプのものが圧倒的に多いといえます。言い換えれば、学校で出される問題というように考え、『学校問題』と『社会型問題』とでもいえそうです。……本書で扱う問題解決手法とは、この多数解答の問題、言いかえれば、創造的問題を解決するための技法のことをさします。」
高橋誠「問題解決手法の知識」,17P
「次に『創造性』というのは、『創造的な可能性』と考えられます。ですから個人でいえば創造性のある人とは、創造する可能性をもった人といえます。問題を解決するためには、どうしてもこの創造性は欠かせないし、企業もその能力を最も必要としているわけです。問題を事前に発見する力、問題解決に際し多角度でヒントを探し出す力、そして解決のためにねばり強く挑戦する態度。『創造性』という言葉には、思考力から性格、態度と言った全人格的な可能性が含まれます。ですから真の問題解決者には、創造性は絶対に欠かせません。」
高橋誠「問題解決手法の知識」,24P
「『発生型問題』の典型的なものには、天災のように予測しにくいものです。……『発生型問題』というのは、予測型問題とでも名付けられるもので、あらかじめ未来を予知して見つけ出す問題をさします。ですから、問題解決者にとってまず大切な能力は『問題発見力』といってもよいといえましょう。……新しい問題を発見することは、言いかえれば未来の予測です。予測で一番大切なのは『何か気になる』とか『何かありそうだ』といった『感じ』だといえます。アメリカの心理学者ギルフォードは『創造力のある人』の素養の第一番に『問題に対する敏感さがある』をあげています。ということは、『創造力のある人』は『予測力のある人』ともいえそうです。『未来をはさむ現在』といったのは未来学者のピエール・マッセですが、私たちにとって未来に起こる問題は、すべて現在の中に隠されているのです。ですから、我々は問題を、現在起きているさまざまな現象の中から、できる限り早く見つけ出すよう努力すべきです。何よりも、問題の発見が問題解決にとって最も大切だと考えるべきです。」
高橋誠「問題解決手法の知識」,19P
川喜田二郎さん(1909-2009)による創造性とはなにか
創造や創造性の定義
創造(英;creation):・なすに値する切実なものごとを、おのれの主体性と責任において、創意工夫を凝らして達成すること
他にも多くの言葉で創造や創造性は言い換えられている
・創造性とは、現状を打破し、つねに新しい状態に変えていくこと。
・創造とは、「ひと仕事やってのけること」であり、創造性とは「ひと仕事やってのける能力をもつこと」。
・創造とは、問題解決であり、創造性とは問題解決の能力である。
「このように、創造とは何かを、観念的でなくとらえれば、それは『ひと仕事やってのける』ということで、創造性とは『ひと仕事やってのける能力を持つこと』であると言える。……その違う言い方のなかのひとつで多少奇抜なものが、『創造とは問題解決なり』であり、『創造性とは問題解決の能力である』ということである。」
川喜田二郎「創造性とはなにか」74P
「では、創造性とは何かというと、現状を打破し、つねに新しい状態に変えていくことで、その最も代表的な例は新陳代謝であろう。外からつねに新しいものを取り込んで同化し体を作り変えていかないと、身体の保守すら維持できないというのが、それである。」
川喜田二郎「創造性とはなにか」75P
川喜田二郎さんの「創造性の三カ条」とは、意味
- 自発性:その仕事を自発的に行えば行うほど、そこには創造的と言いたい何かがあることの証になる。
- モデルのなさ:その仕事をやるのに、こうすればできるに決まっているというモデルとかお手本がなければないほど創造性の証になる。
- 切実性:その仕事をやることが冗談や酔狂ではなくて、自分にとって切実であればあるほど創造性の証になる。
基準を満たしていれば満たしているほど、創造性が高いということになる。
川喜田さんによると、創造性の三カ条は「実践」なしに解釈すれば矛盾するという。
たとえば、切実性が高ければ高いほど、ひと仕事をやめるわけにはいかず、自発性と矛盾する。
しかし、こうした矛盾の解消は「実践」の中でのみ解消しうるという。一般論として、こうすれば創造になる、というような決まりきったものではない。具体的に、ある独自的・個性的な状況のものとで、実践の中で行われていくものだという。
「すると最後には、われわれがやる仕事ひと仕事が、どれだけ創造的であるかは、次のような三カ条の条件を、できるだけ高度にそろえていることが必要だとわかってきた。
第一条は『自発性』ということである。つまり、その仕事を自発的に行えば行うほど、そこには創造的と言いたい何かがあるということである。
第二条は『モデルのなさ』ということである。つまり、その仕事をやるのに、こうすればできるに決まっているというモデルとかお手本がなければないほど創造的だということで、もちろんマニュアルなどはまったくない仕事である。
第三条は『切実性』ということである。つまり、その仕事をやることが冗談や酔狂ではなくて、自分にとって切実であればあるほど創造的になるということである。
この三カ条をできるだけ高度にもっている『ひと仕事』ほど、それは創造的な行為であるという結論になった。
」
川喜田二郎「創造性とはなにか」84P
「──この創造性の三カ条は、何らの実践なしに解釈すれば、相互に深い矛盾を起こすという論理に陥る。しかし、その矛盾を起こしうる創造性の三カ条をあえていっぺんに呑み込んで実践すれば、その実践的行為のなかで矛盾は解消しうるのである。それこそが、創造的と言うに値するのだということである。」
川喜田二郎「創造性とはなにか」86P
「だから矛盾対立の解決は、実践以外にはないのであって、それを抽象論のほうが高尚であると思う気風のある日本のインテリは、実践がなくて合理的に解決するというくだらないことを言うから、日本では創造ということはわかりにくいのである。このように創造というものは、本来、実践を離れてはありえない。そして、実践とは言うまでもなく具体的な行為なので、必ずあるとき、あるところという固有の状況・条件のもとに行われるものであって、一般論としては成り立たないものなのである。これは独自性、あるいは個性的状況と言うべきもので、創造を考える上ではけっして切り離すことができないものであると言え様。」
川喜田二郎「創造性とはなにか」88P
固有技術と問題解決の違いとは
固有技術:・専門の知識・経験・技術のこと。
たとえば数学の方程式を覚えたり、経理の仕方を覚えたり、ゲームのルールを覚えたり、田植えの仕方を覚えたりすること。
問題解決:・どんな仕事がまいこんできても、一応なんとかできるという能力
川喜田さんの例では、スキーの直滑降の技術は固有技術だが、急に子どもが飛び出してきた時どうすればいいのかというような問題は、問題解決についての柔軟性に属するという。たしかに教わっていることしかできない人間が創造的であるとはイメージしにくい。
創造とは「ひと仕事をやってのけること」であり、この「ひと仕事」は右手に固有の技術、左手に問題解決学の両方を備えている必要があるという。
ある状況のときはAパターンというような、容易に予測できる合理的なものが固有の技術だとすれば、問題解決はある状況のときはAパターンとBパターンを組み合わせて、その場その場で柔軟に考えていくようなイメージ。
「私たちは子どものこときから大人になるまで、生活での仕事のやり方の一般論を、誰かから教えてもらうということがないというのが普通である。ところが実際には、やる仕事がいろいろある。だから、そこは見よう見まねで、いろいろ創意工夫を凝らし、本を読むとか人から聞くとか、その仕事に関係のあることを勉強して、何とかごまかしてきている。では、そんないいかげんなことで、ともかくもなぜできたかというと、何か先例があって、それを習ってきたからである。これがひとつも専門分野の仕事になると、その分野の知識経験を豊富に持つということになる。だから、大学でも専攻を選ぶことになると慌てて、どの学部・学科へ行くか、どのコースを選ぶかということになる。では、大学がなかった昔はどうだったかというと、百姓で言えば親代々の農地を継ぐとか、あるいはどこかの商家へ丁稚小僧に入って、専門の知識・経験・技術をマスターしたのである。これを私はその領域固有の、という意味で『固有技術』と呼んでいる。」
川喜田二郎「創造性とはなにか」64P
「そこで、そのような固有技術は、スキーで言えば直滑降の技術のように、必要には違いないけれども、それだけでは、たとえば目の前に立木が現れたら衝突するのか、また子どもが飛び出してきたら、抱き合い心中するのかということになる。そうすると死にたくなければ、その手前で意図的に転ぶよりほかに方法がない。ところが回転技術を身につけておれば、立木や崖が眼前に現れても、雪煙を挙げて回転してよけながら、自在に進むことができる。これは固有技術の問題ではなく、問題解決についての柔軟性であり、教養によるものである。私は、これは固有技術ではないのでなんと名前をつければいいのか、まだ結論を出していないが、堅苦しく言えば『一般問題解決学』、あるいは、たんに『問題解決学』ということである。したがって結論を言うならば、変化の激しい時代になればなるほど、右手に固有技術、左手に一般問題解決学と、この両方を兼ね備えたら自由自在ということになる。」
川喜田二郎「創造性とはなにか」67P
創造の過程とは
・渾沌、矛盾葛藤、本然という経過だという。
混沌:・何が何だかわからないという状況。何が問題で、何が悩みの種かということすら、まだ漠然としていて掴めない。いっさいがもやもやとしている状況。
本然:・矛盾葛藤を解決した状態
「創造のいちばん初めには、何が何だかわからないという状況がある。何が問題で、何が悩みの種かということすら、まだ漠然としていて掴めない。いっさいがもやもやとしている状況。これ私は『渾沌』と呼んでいる。創造は、この渾沌から出発するのである。」
川喜田二郎「創造性とはなにか」90P
「つまり、渾沌のなかから自己という主体の意識が生じ、次に出会いがあり、そこでの関心の発生から矛盾葛藤が起こるので、その結果、これを何とかしなければならんということで、順調に事が運べば解決に至り、場合によっては挫折することもある。この矛盾葛藤を解決した状態、……を『ほんねん』と呼ぶことにしよう。」
川喜田二郎「創造性とはなにか」92P
「……詰めて言えば、『渾沌→矛盾葛藤→本然』で、これが創造における問題解決の実際の経過であると思う。」
川喜田二郎「創造性とはなにか」93P
「ここであらためて、創造的行為の内面世界とデカルト的図式との違いをはっきりさせておくと、私の考えでは、渾沌が出発点で第一段階、それから矛盾葛藤を含むごちゃごちゃとしたところだ第二段階、そして光明の世界である本然が第三段階であるのに対して、デカルトのほうは第一段階を飛ばしてしまって、『われ思う、故にわれ在り』とごちゃごちゃした問題を分析と推論の方法で解くように、いきなり矛盾葛藤のなかへ入り込む。そして、本来それが自然である『本然』の状態ではなく、他者を征服した形で機械論的な帰結を最終段階として置く、あくまでもエゴが中心となる図式である。」
川喜田二郎「創造性とはなにか」98P
「そして、荘子のような諦めは許されないこと、そしてデカルト的パラダイムによる分析と推論では問題の解決はつかないこと、したがって新しい創造的行為が必要であることが誰の目にも明らかになりつつあるのである。」
川喜田二郎「創造性とはなにか」100P
W型問題解決モデルとはなにか、意味
創造(ひと仕事)がABCDEFGHの過程として表現されている。
A-B-C-Dが「判断」であり、Dが「決断」であり、D-E-F-G-Hが「執行」である。ひと仕事はこのように、判断→決断→執行からなる。
W型モデルのポイントは、「思考レベル」と「経験レベル」を区別した点にある
AーD-E-Hのラインが頭の中の活動であり、BーC-F-Gのラインが体験的な活動である。創造は思考レベルと経験レベルを行き来する形で形成されていく。マートンの中範囲の理論を思い出させる。
補論:アブダクションとW型問題解決モデル
・化石の発見のケースで考えてみる
(驚くべき事実)魚の化石が陸地で発見される
(説明仮説)もしこの陸地一帯がかつて海だったのならば、この陸地に魚の化石がある理由に納得がいく。
(作業仮説)もしアブダクションによって提案された説明仮説が真であるとすれば、この陸地一帯には他の魚や貝の化石も見つかるはずである、と予測を導き出す。
このようにアブダクションを通して考えていくと、マートンが言う「小さな作業仮説」の意味がすこし理解できていく。
社会調査ではなんの仮説もなしに調査(演繹・帰納)が行われるわけではなく、ちょっとした仮説(アブダクション)が先にあり、それに合うようなデータを見つけていくことだといえる。なんの手がかりもなしにデータを見つけたり解釈することは出来ない。もちろん、データから仮説がひらめく場合もある。
詳細はマートンの記事に
【基礎社会学第三十四回】ロバート・K・マートンの中範囲理論とはなにか
「また山口・田中・小林(2015)によると,アブダクションとは,ある事象を説明する説明仮説を発案する推論過程である。そして山口らはその推論過程を,「驚くべき事実の観察」→「説明仮説の発案(変数の抽出)」→「作業仮説の設定」という3過程でまとめている。作業仮説とは,具体的な作業を伴った仮説であり,仮説を説明仮説・作業仮説の2種類に分けていることが,山口らが示す過程の特徴である。W型モデルにおける「仮説の設定」について,この「仮説」がどちらに当たるのかは,明確に示されてはいない。しかし川喜田はD→Eの過程を,何らかの仮説が採択され(D),もしこの仮説が正しければ事態はこうなるはずだ(D→E)という推論として説明している(川喜田,1967,pp.23–24)。すなわち,Dは説明仮説,Eは作業仮説の成立段階である。よって山口らの示す3過程は,総合的探究からアブダクションによる説明仮説の発案(C→D)を経て,推論による作業仮説が成立する(D→E)ことを表していると解釈できる(図2)。」
向井大喜、村上忠幸、松本伸示「高校生による科学的問題解決における仮説形成過程の評価に関する研究」,457P
書斎科学、実験科学、野外科学とは、意味
書斎科学:・現実の経験レベルに触れなくて済む思考レベルの部分。演繹的。論理学や数学など、紀元前からある古典的な学問。A-D-E-H。
実験科学:・17世紀にデカルトやベーコンなどによって発展した領域。帰納的。E-F-G-H
野外科学:・20世紀に発展しようとしている領域。たとえばパースによる発想法(アブダクション)や川喜田さんのKJ法、ブレインストーミングなど。A-B-C-D。
「そこで,創造性が人間にとり根源的重要性を持っているのなら,何はおいても問題解決という人間行為の基本的構造を明らかにせねばならない。私はそれを追求し,図1のようなW形問題解決モデルというものを得た。そうして,非常に多くの人たちから,賛成の声を頂いたのである。このモデルをもっと簡潔に要約すると,結局〔判断→決断→執行〕となる。すなわち,「判断」とはある課題につき総合的な情勢が「判る」ということである(図1のA→B→C→D)。これに対し「執行」とは,判断の結論を受けて「手を下す」ことである。もうすこし詳しくいえば,計画し実施し結果を吟味検証することである(D→E→F→G→H)。そして「決断」とは,判断と執行の接点で,なすべきかなさざるべきか「肚をきめる」ことなのである(図のD点にあたる。)。ところで,AからHまでを完遂することを,私は「達成」と呼ぶことにし,その体験を「達成体験」と呼ぶことに定めた。達成とは,日本の庶民が昔からいう形容では,「ひと仕事をやってのける」ことに他ならない。」
川喜田二郎 「野外科学と創造性教育への道」,103P
「まず第一に学問らしくなったのは,〔A→D→E→H〕という,現実の経験レベルに触れなくてすむ思考レベルの部分と,知識の収納庫をなす部分である。すなわち推論と演繹的思考ですむ学問は,論理学や数学その他として,西暦紀元前数世紀,あるいはそれ以前から発達していた。シュメール・ギりシア・インド・中国,みなそういう遺産を示している。また図書館は,粘土板と模形文字とはいえ,やはり西紀前数世紀,アッシリアのアッシュルバニパル王が作っていた。これは知識の収納庫の初期的試みで,その系譜はついに現代の図書館やコンピュータまでつながっている。こういう古典的な学問を,私は「書斎科学」と呼んでみた。それに比べると,実験科学は〔E→F→G→H〕の部分であり,これははるかに若い。ギリシアの科学とかレオナルド・ダ・ビンチなどという早熟なものを除けば,近代科学の潮流の源をなすもので,せいぜい17世紀にデカルトやべ一コンで自覚的になり,本格的には18世紀後半の産業革命以来といってよいのだろう。これは明らかに西欧近代文明がイニシャティブを取った。そうすると,W解決の中で本格的に科学の方法論として自覚されていないのは,もはや〔A→B→C→D〕の部分,すなわち「判断」の部分だけになってしまった。この部分は「野外科学」と呼ぶのがふさわしいと,私は1967年に提唱した。以来その主張は一貫して現在に至っている。」
川喜田二郎 「野外科学と創造性教育への道」,104P
KJ法とはなにか、意味
KJ法:・KJは川喜田二郎の略称。紙片に書いたアイディアや情報をグルーピングすることで、新しい着想やまとめを可能にする方法。創造の過程の主に前半(野外科学)において役立つ。
・ざっくりした手順
- テーマを決める
- アイデアを出す
- カードをまとめる
- 各カード群にタイトルをつける
- 上位グループにまとめる
- 作図してまとめる
「これは、さまざまな現場データや情報、いろいろな人のバラバラな意見をカードに記入し、データのもつ意味をくんで、内容が本質的に似たものを集約し、そこから新たな仮説を発見しようとするものです。……①テーマを決める。……②アイデアを出す。……③カードをまとめる。……④各カード群にタイトルをつける。……⑤上位グループにまとめる。⑥作図してまとめる。」
高橋誠「問題解決手法の知識」116-119P
「KJとは川喜田二郎の略称.同氏によって発明された小集団による問題解決の技法の一つ.一言でいえば,小紙片に書いたアイディアや情報をグルーピングすることで,新しい着想やまとめを可能にする方法である.それぞれの過程でメンバーが深く参加することによって,創造も可能になり,考え方だけでなく感じ方,行動など態度変容にも有効である.」
中川 米造「KJ法」,425P
創造的行為の本質とは
Q 創造的行為を達成したときの人の心に、どういったものが生み出されるのか
愛と畏敬
川喜田さんによれば、創造的と思えるような体験をしたとき、「俺が生み出したのだから、これは俺のものだ」というような所有の感覚が決して生じないという。
愛を言い換えれば、「自分が生み出したものとの間に強い連帯感」を抱くという。例えば登山において「征服した」という気持ちより、「やあ、今日はどうだい」とその山にまたいいたくなるような、深く結ばれている感じがあるという。
「創造的行為の内面、それも非常に深いところに宿っている不可思議な何かに導かれているのではないかという気持ちは、創造的行為を達成したときの人の心に、自ずから愛と畏敬の念を生み出すものである。」
川喜田二郎「創造性とはなにか」,114P
「また、自ら生み出したものではあるが、自分の所有と思わぬどころか、むしろ畏敬の念を抱くものでもある。生み出されたものが傑作であればあるほど、自分が作り出したものであっても、畏敬の念を抱くということである。しかも、この感覚は偉い宗教家や哲学の大先生だけがわかるものではなく、じつは、ごく普通の人々のなかにあるものである。私は、それが創造的行為というものの本質だと思っているのである。」
川喜田二郎「創造性とはなにか」,115P
「では、結論は何かというと、これを言葉で表現することはたいへんむずかしいのであるが、創造的行為というものは、自分でも犯すことのできない、何か畏敬の念を抱かざるをえないようなものを、そこから生まれ出たものに対して感じるものであって、同時に、深い愛を抱くものである、と私は思うのである。言葉を変えれば、自分が生み出したものとの間に強い連帯感を抱くものであり、それによって自分自身が変わっていくのを感ずるのである。」
川喜田二郎「創造性とはなにか」,118P
天命と絶対感
・創造は「天命と絶対感」に基づいて行われる
川喜田さんは「自分は全体への価値の創造に寄与しているんだという感覚がないと救いがない」という。
全体状況の中でそうせざるをえないというような天命と絶対感が重要であり、そうしたやらざるをえないというような状態はむしろ「主体的」といえるという。
ウェーバーのいう「天職」に近いのかもしれない。
「──あそこに森があった、ここに川があった、ここに川があった、あそこで人に会ったとかいうさまざまな状況で、それも、その一つひとつの状況ではなくて、そのすべてを包括した全体状況のなかで自分がそうせざるをえなかったという絶対感があるということである。これが全体状況の底に徹してこそ、絶対感のある行動で全体への価値の創造に寄与できるということである。」
川喜田二郎「創造性とはなにか」,121P
「つまり、何かカケラでもいいから無意味ではない有意義なことを自分自身に言う。自分は全体への価値の創造に寄与しているんだという感覚がないと救いがないということである。そして、こういう方向で考えていくと、当然、天命と絶対感という問題が出てくるのである。」
川喜田二郎「創造性とはなにか」,125P
「主体性については、よく人に強いられてやるのは主体的ではないと言われるが、それは一般論であって、本当は全体状況が自分にやれと迫るから、やらざるをえないというほうが、じつは真に主体的だと私は思うのである。」
川喜田二郎「創造性とはなにか」,127-128P
「言葉を換えて言えば、状況全体がわからない人間、その部分部分だけを大写しにしてから受け取れないような人間には、天命は聞こえてこないということである。」
川喜田二郎「創造性とはなにか」,128P
ふるさと
・創造は「ふるさと」を生む
自分が最も創造的に行動したそこが「第二のふるさと」になるという。
過去において、子どもの時代においても何かに全力で熱中し、創造的行為を行っていたからこそ「(第一の)ふるさと」と思えるようになる。こうした過去のふるさとだけではなく、これから未来に向けて、何か創造を行えば、そこがふるさとになる。
ふるさとは「場」としても言い換えられている。
創造によって客体を創造し、さらに主体も変わっていく。川喜田さんによれば、一方的に客体だけを変えるようなものは創造ではないという。
主体と客体だけではなく、さらに「場」も新たな価値を付与されて生み出されていく。場への愛や連帯感が生まれ、こうした「創造愛」が累積していくと、そこに「伝統体」が生じるという。場がもっと大きくなれば、世界全体との連帯感、「参加する意識」は生まれるのか。
「これは何かというと、人間というものは、自分が最も創造的に行動したそこ──そこで何かビューティフルなことを達成したときには、そこが第二のふるさとになるということである。さらに同じような達成体験があれば、そこも第三のふるさとになる。」
川喜田二郎「創造性とはなにか」,150P
「つまり、『ふるさと』とは、自分の人生で一度しかなかった『あそこ』しかないという見方が一般的には最も多いのである。……結論を言うと、『ふるさと』とは、子どもから大人になる途中で、子どもながらに全力傾注で創造的行為を行ない、それをいくつか達成した、そういう達成体験が累積した場所だから、『ふるさと』になったのだということである。したがって、子ども時代の時点に身を置いてみると、それは『未来』という未来向けの矢印で、その[→未来]向けの矢印の累積したところが、いつまでも離れ難いふるさとになったことが真実である。」
川喜田二郎「創造性とはなにか」,148P
「では、創造的行為において『客体』と『主体』の双方が創造されるだけかというと、その行為を通じて主体と客体とは、ひじょうに深い『愛と連帯感』で結ばれるのである。創造的行為が達成された当座は、きわめてホットな愛であり、ときがたつと連帯という形で落ち着く。しかも、主体と客体が創造されるだけではなく、その創造が行われた『場』もまた、新たな価値を付加されて生み出されるのである。したがって、ひとつの創造的行為が達成された場合、そこには『主体』と『客体』と『場』の三つが生み出されるということで、その『場』というものが、第二の、そして第三の『ふるさと』となるということである。強烈な創造的行為の場合は、ただ一回の体験だけでも、その場が、ふるさと化するものである。すると、その創造的行為に繋がった人々は、また顔を合わせたがる。──いわゆる同窓会化である。」
川喜田二郎「創造性とはなにか」,155P
「ここで、伝統体の思想と創造愛の原理についてまとめると、その出発点は創造的行為である。二度とは来ない、ある独自的な状況のなかで自分が探求をしなければならないとの絶対感が生まれる。その創造的行為の達成によって、主体と客体と創造が行われた場への愛と連帯の循環──私が、『創造愛』と名づけたものが生まれてくる。これが創造愛の原理である。この創造愛が累積していくと、そこに伝統体が生じるのであり、これが伝統体の思想である。」
川喜田二郎「創造性とはなにか」,162P
「したがって、私は創造と愛の循環しながらの累積的発展という考え方を、とりあえず創造愛と名付けたのである。」
川喜田二郎「創造性とはなにか」,164P
アリストテレスの宇宙
「ふるさと」を聞いて思い出すのが、ジャン・ピアジェの「子どもは最高七歳くらいまで、アリストテレスの宇宙に生きている」という発言である。
モリス・バーマンは、大人になっても、情感のレベルではアリストテレス主義者になりうるという。「なぜものは床に落ちるのか」という問いに対して、子どもは「そこがものの居場所だから」とこたえるという。今の大人は、そのように答えないだろう。論理的でも常識的でもない。しかし、情感のレベルでは、同意できるのかもしれない。何かに熱中しているとき、そこが自分の居場所となる。そこが広がっていけば、すべての場所が居場所となり、結ばれ、人は虚しくならないのかもしれない。
アメリカの心理学者、アブラハム・ハロルド・マズロー(1908-1970)による創造性とは
・欲求段階説で知られている
まずは欲求段階説を説明していく
マズローの欲求段階説とはなにか、意味
欲求段階説:・人間の持つ主要な欲求として、生理的欲求、安全の欲求、所属と愛の欲求、承認の欲求、自己実現の欲求、という5つの欲求を挙げ、この順に下から階層をなし、この順に発達が進行し、下位の層の欲求が満たされることによって上位の層の欲求が発達していく、とするもの。
欲求の発達論やモチベーション論として知られているらしい。軽く触れていく。
・創造性が「自己実現」の段階にきているのがポイント
「自己実現に関するマズローの理論の中でよく知られているのは、いわゆる「欲求階層説」である。これは、人間の持つ主要な欲求として、生理的欲求、安全の欲求、所属と愛の欲求、承認の欲求、自己実現の欲求、という5つの欲求を挙げ、この順に下から階層をなし、この順に発達が進行し、下位の層の欲求が満たされることによって上位の層の欲求が発達していく、とするものであり、自己実現の欲求が最上位の欲求として位置づけられている。この理論は、欲求の発達論として、また経営学の基礎となるモティベーション論の1つとして、多くの人に知られている。」
石田潤「マズローの自己実現論の全体像について」,33P
マズローの自己実現とはなにか、意味
自己実現:・才能、能力、可能性を十分に用い、開発していること。
具体的には以下のような特徴をもつ。
現実をより有効に知覚し、それと快適な関係を保つこと、受容、自発性、問題中心的、超越性、自律性、評価が絶えず新鮮であること、神秘的経験、共同社会感情、対人関係、民主的性格構造、創造性等。
創造性はその一つであるが、ほとんど同義として用いられることもある。また、自己実現を通して創造性が達成されるとしている。
ニーチェ「汝自身たれ」との関連も面白い。
「マズローは、自己実現について「自己実現を大まかに、才能、能力、可能性をじゅうぶんに用い、また開発していることと説明しておこう。このような人々は、自分自身を完成し、自分のできるかぎりの最善を尽くしているように見え、ニーチェの「汝自身たれ」という訓戒を思い起こさせる。彼らは自分たちの到達できる最も高度の状態へ達し、また発展しつつある人々である。」……」
石田潤「マズローの自己実現論の全体像について」,34P
具体例は石田潤「マズローの自己実現論の全体像について」35~36Pより抜粋
特別才能の創造性と自己実現の創造性とは、意味
特殊才能の創造性:・芸術家や科学者、発明家といった天才型に属する創造性のこと。所産を伴うような創造性。夏堀睦さんによれば、「社会にとっての新しさ」に対応している。
自己実現の創造性(英;Self Actualizing Creativeness):・所産を伴わなくとも一種のユーモアの雰囲気でなにかを創造的に行おうとする傾向のなかで現れてくる創造性。夏堀睦さんによれば、「個人にとっての新しさ」に対応している。
「マスローの創造性理論では、芸術家や科学者、発明家といった天才型に属する「特別才能の創造性」と、所産を伴わなくとも一種のユーモアの雰囲気でなにかを創造的に行おうとする傾向のなかで現れてくる「自己実現の創造性」を区別する(Maslow、1964)。この区別は前述の創造性における「社会にとっての新しさ」と「個人にとっての新しさ」の2側面にそのまま対応していると思われる。マスロー(1964)は、それ以前の創造性研究では「特別才能の創造性」を重視するために、創造性を創造の所産ということで考え、無意識のうちに創造性を伝統的な領域の中だけの人間の努力に限っており、創造性はある特定の専門家の独占物と考えられてきたとして批判する。また、特定の専門家以外の個人は創造的ではなく、人は創造的であるかないかのどちらかとして分類され、創造性研究も二分法の概念に基づいて行われてきたことを指摘し、それを解消することを主張する。」
夏堀睦「 人間性心理学における創造性研究. A.H.Maslow と M.Csikszentmihalyi の創造性理論の検討一」49P
一次的創造性と二次的創造性とは、意味
一次的創造性の特徴:・無意識的深層から発する本能的衝動であり、空想、想像、夢、直観、閃き、遊び、ユーモアなど、人間性の内面より湧き出る創造性の源泉となる。所産とは切り離して考えていく。なぜなら、所産は創造性固有の要素ではなく、努力や修練といったものが関係しているから
二次的創造性の特徴:・意識のレベルで行われ論理的、常識的、合理的、現実的なものの法則性と照らし合わせて作品の完成へと向かう。
たとえばアインシュタインは相対性理論を創造した、と一般に言われている。他にもモーツァルトの作曲など。独自性のある創造物を生産したのであり、また社会にとっても新しいものを創ったといえる。
このような創造性は「特別才能の創造性」に属している。
一方で、「自己実現の創造性」の場合は、一般に天才とは思われないような日常の人々であっても発揮しているものである。
特殊な才能を持つ人に見られる独自性の高い創造性ではなく、すべての人間に生まれながらに与えられた可能性のようなものであり、その人が従事している活動に何らかの影響を与えるという。
たとえばマズローは主婦の家事の仕方、ボランティア活動における組織づくりなどを挙げている。他にも創造的靴屋、創造的大工、創造的事務員なども存在しうるという。
絵を描いている途中に、こうしたら綺麗に円が描けるのではないか、と考えたとする。その方法論が社会的に新しくないとしても、独自性がないとしても、「自己実現の創造性」はあるということになる。また、円が仮に綺麗に描けないとしても、論理的・非論理的にこうだろうと考えたり、奇抜なアイデアを通して実践していく過程が創造的だといえる。
「マスロー(1958、1963、1971)は創造性の過程のなかでも、無意識的深層から発する本能的衝動であり、空想、想像、夢、直観、閃き、遊び、ユーモアなど、人間性の内面より湧き出る創造性の源泉である一次的創造性(primarycreativeness)と、意識のレベルで行われ論理的、常識的、合理的、現実的なものの法則性と照らし合わせて作品の完成へと向かう二次的創造性(secondarycreativeness)とを区別する。一次的創造性と二次的創造性の統一が必要であるとしながらも、マスローは一次的創造性を重要視する。一次的創造性はマスローが完成された人格のもつ精神構造のもっとも顕著な特質としてあげる「至高経験」(peakexperience)と同じ意味で用いられている(Maslow、1958)。「至高経験」とは自己喪失や自己超越を含むどんな経験をも途方もなく強化した神秘的経験であり、感動、幸福、’1光惚、有頂天な瞬間に体験する崇高な感情である(Maslow、1954;上田、1988)。そしてその状態では過去、未来といった時間的な広がりは断念され、「いまここ」に意識が集中し、現在への全面的没頭こそが重要となる。」
夏堀睦「 人間性心理学における創造性研究. A.H.Maslow と M.Csikszentmihalyi の創造性理論の検討一」50P
「初期の創造性研究に取り組んだ心理学者の中でも,マズローは人間主義心理学に立った特徴的な創造性の捉え方を提唱した。マズローは創造性を,才能を持った人間の属性である「特別才能の創造性」と,誰にでも備わっている「自己実現の創造性」に分けて考えた。人間主義心理学においては,人間という存在を新しい人間性の創造主体とみなし,人間性の自己実現を通して創造性が達成されるとされた。芸術家や科学者などの突出した業績を通して顕在化される「特別な才能の創造性」がある一方で,一般の人々が生活の中で自分の創意を生かそうとする「自己実現の創造性」は,健康な人格よって発揮されるものであると考えられた。マズローによれば,業績は人格が文化的環境に関わって生じる随伴現象に過ぎないが,自己実現の創造性は業績よりも人格を強調するものである。創造性は外界に対して自己をあるがままに表現することで達成されるものであり,環境や世間の強迫観念や不安に影響されない健康な人格が「創造的人格」であるとされた。人間主義心理学では,人間が本能的にもつ意識下の衝動を肯定的に捉え,空想,創造,夢,直観,ひらめきなどの内面から湧き出る創造性を「一次的創造性」と呼んだ。さらに思考,判断,評価といった合理的,論理的な過程における創造性を「二次的創造性」と呼び,この二つの統合によって,人格は最高の創造性を発揮すると考えられた」
佐々木宰「アジアの美術教育における創造性育成の可能性」,183P
マズローの創造性の人格的条件
心理学者の上田吉一さんはマズローの創造性の人格的条件を5つにまとめている。
- 創造性は外界に対し、「あるがまま」に認識する能力によって達成される。
- 創造性は外界に対し「あるがまま」に自己を表現することによって達成される。
- 自己実現の創造性は「子供っぽさ」のなかに示される。
- 自己実現の創造性は「あいまいなるもの、未知なるものを恐れない」人格的特性のうちに認められる
- 自己実現の創造性は、相互に対立し、矛盾する人格の「統一」のうえに成立する。
個人的にはこの、矛盾を乗り越える、統一する点が重要。部分的にではなく全体的に、論理的にではなく因果的・飛躍的に物事を柔軟に捉えていく姿勢。
マズローの至高経験とはなにか、意味
至高経験:・自己喪失や自己超越を含むどんな経験をも途方もなく強化した神秘的経験であり、感動、幸福、光惚、有頂天な瞬間に体験する崇高な感情。
この状態では過去、未来といった時間的な広がりは断念され、「いまここ」に意識が集中するという。つまり、一次的創造性には現在への全面的没頭が重要になるという。
マズローは一次的創造性と二次的創造性のどちらを重視しているのか
あるいは特殊才能の創造性と自己実現の創造性のどちらを重視しているのか。
・創造性の区別を別の言葉で表現してみる
- インスピレーションの側面(一次的創造性)
- 修練の側面(二次的創造性)
たとえば閃きの能力が著しく高くても、それを実現するような論理的な能力、努力が乏しければ、インスピレーションの「成果」は生じない。それゆえに、その両方の統合が必要であるという。
個人の能力だけではなく、科学者の偉大な発見は社会制度や他の人間との協同の賜物であり、先人の積み上げも関連しているのであり、遅かれ早かれ誰かが発見するものであるという。そのため、著名な科学者よりも、幼い子どもの創造性を研究したほうがよいという。たしかに幼い子どもは「成果」は見られないかもしれないが、「過程」はより純粋に観察できるのかもしれない。マズローは社会的なアプローチよりも、内面的・心理的なアプローチをより重視していく印象がある。
マズローは、「よい仕事の習慣、しぶとさ、鍛錬、忍耐、よい編集能力」を創造性と直接関係のない、あるいは少なくとも創造性に固有のものではない特徴だとしている。
創造性に固有のものは主に創造性のインスピレーション面であり、心の深層部分であるという。そして、その中でも核心的な要素は、「過去も未来も忘れ、その瞬間の中にのみ生きるという能力」であるという。
一次的創造性の高い人間は、時に社会性を欠いた人間になることもあるという。
マズローは「私の取り扱ってきた創造的な人びとは、組織のなかで浮き上がりがちで、それを恐れ、一般に部屋の隅や屋根裏でひとり働きたがる傾向がある」と述べている。
つまり、一次的創造性は創造にとって重要であり、独自性の高い成果を生むためにも必要という正の側面と、健康的な精神とはいえない場合があるという負の側面があるということになる。
「マスロー(1963)は、一次的創造性を研究対象にすべきで、「現在のことで夢中になる」能力こそ、どのような創造性にとっても必要不可欠な条件であるとする。その見本となる対象は社会に既存の知識を詰め込まれていない幼い子どもである、と主張する3)。子どもの創造性、独創性は、作品から定めてかかることはできない創造性のインスピレーションの決定的瞬間である。それに対し科学者の偉大な発見は、社会制度ないしは協同の賜物であるので彼が発見しなくても、早晩誰かが発見するものである。それ故、創造性の理論を研究するにあたり、著名な科学者を選ぶことは、最善の方法とはいえない、とマスローの理論は展開する。」
夏堀睦 「人間性心理学における創造性研究 : A.H. MaslowとM.Csikszentmihalyiの創造性理論の検討」,50P
「創造性に関して特に、マズローの理論において扱われているのは、創造的活動のもとになる閃きのような部分であり、マズローはこれを一次的創造性と呼んでいる。マズローは、作品を完成させていく過程においては、技能、時間、労力、努力、忍耐、などが求められるため、創造性とは別の要因が関わってくると考えたのである
(「私の強調しているのは工夫やインスピレーションであって、完成された芸術作品や偉大な創造的業績といった立場から創造性を云々しているのではない。.....一次的創造性や創造性のインスピレーション面は、そのインスピレーションの成果や発展とは区別されねばならない。なぜなら、後者の場合には、単に創造性ばかりでなく、まことに徹底した努力、半生を道具、技能、材料の勉学に費し、ついには、観察するものを完全に表現できるようになるというような芸術家の血のにじむような修養によるところも大きいからである。」(『人間性の最高価値』p.73)
「われわれは、社会的に有益であるとしても、芸術や科学の完成された作品を創造性の実例として用いるべきではない。.....これは完成された作品を基準として用いると、とかく、よい仕事の習慣、しぶとさ、鍛錬、忍耐、よい編集能力、というような創造性と直接関係のない、あるいは少なくとも創造性に個有のものでない特徴と混同することが極めて多いと考えられるからである。」(『人間性の最高価値』p.120))。
そしてマズローは、創造性の源泉になっているのは心の深層部分であると考えている
(「ここ一〇年ばかりにわかったことは、われわれが実際に興味をもつような創造性、すなわち、真に新しいアイデアの発生が人間性の深層に起源をもっているということである。」(『人間性の最高価値』p.99))。
マズローは、フロイトの理論を「無意識を単に好ましからざる悪でしかないと考えた」と批判し、「無意識は、創造性や喜び、幸福、善、人間的な倫理や価値自体の源泉である。」と主張している。創造性を発揮する際の1つの契機となるのは、行っている活動に没頭することである。
(「.....創造的な人間が創造的熱中のインスピレーションの段階では過去も未来も忘れ、ただその瞬間の中にのみ生きるということである。彼は、現在のうちにまったく没入し、魅せられ、いま、ここの現前する問題の中にわれを忘れるのである。.....この「現在のことで夢中になる」能力こそ、どのような創造性にとっても必要不可欠な条件であると思われる。」(『人間性の最高価値』pp.75-76))。
没頭する度合いの大きい人は、時に社会性を欠いた人間になることもあり、そのことに関連してマズローは、
「私のとり扱ってきた創造的な人びとは、組織の中で浮き上がりがちで、それを恐れ、一般に部屋の隅や屋根裏で、ひとり働きたがる傾向がある。」(『人間性の最高価値』p.98)と述べている。」
石田潤「マズローの自己実現論の全体像について」,40P
1:マズローは健康的な精神を重視しているため、「特殊才能の創造性」よりも「自己実現の創造性」を重視している
自己実現の創造性は、所産を必ずしも伴わない。いわば態度、傾向の問題であり、健康な人格によって発揮されるものであるという。創造性の所産よりも、創造性の過程を重視し、工夫やインスピレーションを強調している。
健康的な精神とは具体的に、子供らしさ、自発性、表現力、自己受容の傾向などが挙げられている。
2:マズローは「無意識的なもの」を重視しているため、「二次的創造性」よりも「一次的創造性」を重視している
とくに一次的創造性は「至高経験」とも同義とされ、特に「現在のことで夢中になる能力」が創造性の不可欠な条件とまでいわれている。
一次的創造性は、意識の中でも特に無意識的な要素を重視している。たとえば閃きやユーモア、夢などが重視されている。科学的には非合理的、非論理的なものに近い。
二次的創造性は意識の中でも、意識的な要素が重視されている。たとえば帰納や演繹など、合理的なプロセスが重視されるといえる。
たとえばピザを5人で分けるためにはどのように切るべきか、自分で考え、発想していく作業などで幾何学を用いる場合などがそうかもしれない。
特別才能の創造性は、二次的創造性のみを通してではなかなか達成されないだろう。帰納や演繹の能力が素晴らしいだけでニュートンは万有引力の法則を発見したわけではない。
閃き、空想、アナロジー、そうした非合理的な要素が重要となっている。ただしそうした閃きだけで創造性のある作品が生まれるわけではなく、そこから論理的につなげていく作業も必要となる。たとえばひらめいただけで数式で表現できなかったり、それを理論化して経験的に実証できなかったりすれば、社会的に有用とはいえないかもしれない。つまり、両方の能力が必要であり、その統合によって、素晴らしい創造性が発揮される。
ニュートンに対する精神的に不健全なメージ
ニュートンといえば、精神的に不健全なイメージが私にはある。これはニュートンが子供の頃に、ラテン語への翻訳の練習のために自由連想で選ばれた文だという。
「ちっぽけな奴。顔は青白い。僕が座る場所はない。どんな仕事ができるというのか?何の役にたつのか?失意の男。船は沈む。僕を悩ませるものがある。彼は罰せられるべきだったのだ。誰も僕を理解してくれない。僕はどうなるのか。終わらせてしまおう。泣かずにはいられない。何をしたらよいか分からない(モリス・バーマン『デカルトからベイトソンへ』,129P 孫引き)。」
このような健康状態でつくりあげられたパラダイムが健全でありうるのだろうか。それとも、全く関係ないのだろうか。パラダイムが恣意的であるとすれば、健全であるほうがいいのではないだろうか。
補論:ウィゴツキーと社会の機能について(動画にはない項目)
・レフ・セミョノヴィチ・ウィゴツキー(1896~1934)
心理学におけるモーツァルトと呼ばれているらしい。心理学者。
ウィゴツキーにおける創造:・あらゆる後に来る形式が先にあるものによって定められている歴史的な継承の過程
「ごっこ遊び」と創造の関連性
ウィゴツキーによると、子どもは社会的な相互作用を通して、発達するという。この発達というのは想像力ないし創造力の発達とも関わっている。
想像力の役割について~子どもの想像力は大人よりも貧弱である~
ウィゴツキーによる想像力(英;imagination):・①「過去の経験やイメージを解体して新しい組み合わせによって新しいものを作り出す精神活動」、②「目の前に存在しないものを,心の中に描くこと」、そうした能力のこと。
想像力と創造力が日本語では同音なのでごっちゃになってややこしい。とはいえ、想像力と創造力は同義とは言えないまでも、創造力の重要な要素の一つといえる。
ウィゴツキーは子どもにおける想像力の役割として、以下の4つを主張している。
- 経験の拡大
- 遊びの発展
- 内的な表現の充実(共感や同情等
- 社会的な意識への影響
ウィゴツキーによると、子どもは大人よりも、経験が少ないという。見てきたことや、聞いたことが少ない。たしかにそうかもしれない。
それゆえに、「子どもの想像力は、大人よりも貧弱である」という。
たとえば「絵本」は、言葉によって想像しにくいものを、視覚的な情報によって想像させやすくする役割があるという。だからこそ、子どものときに絵本を読むことは重要だという話。
マズローとウィゴツキー
マズローの特徴は、「『いまここ』に没頭することによって経験する感情に重きを置くこと」にあるという。夏堀さんによれば、マズローは創造性の評価の観点と創造性における知識の必要性の観点が欠落しているという。たしかにマズローは二次的創造性よりも、一次的創造性を重視している。
二次的創造性とは、一次的創造性で発現したアイデアを、社会に既存の知識と照合し、論理的・合理的に所産としてまとめあげる力である。
子供のほうが「いまここに没頭する力」はありそうだが、大人の方が「知識・経験」の量はありそうだ。マズローは知識を産出する社会や、知識そのものについてあまり力を入れていないということだろうか。
夏堀さんはマズローの創造性理論においては「創造性の発達に関しての明確な記述は見られない」という。
ウィゴツキーは「あらゆる発明者は、天才でさえも常にその時代、その環境の産物なのである。いかなる発明も科学的発見も、それが発生するために欠くことのできない物質的、心理的条件がつくりだされるよりも、それ以前にはあらわれないのである。創造とは、あらゆる後に来る形式が先にあるものによって定められている歴史的な継承の過程なのである。」と述べている。
これを聞いて思い出すのは社会学者のマートンの、「中範囲の理論は、古典的な理論方式によっている労作と直線的に連なる」という主張である。なにかを創造するためには、経験の素材が必要であり、またその経験の素材は歴史的な積み重ねが重要になる。
歴史的な積み重ねとしての「知識」に重きを置き、創造を文化歴史的なものととらえる場合、「知識の質・量」が重要になる。であるならば、知識の量・質ともに優れているのは子供より大人であり、大人の方が創造性が高く、また、子供から大人にかけての創造の発達を調べることも重要である。
ようするに、創造を単に想像の素材に使用できるパターンの量といえる。これは熊坂賢次さんの想像の定義とも重なってくる。役に立つかどうか、パターンが深いかどうかといったような質と、単にパターンの種類が多いというような量と区別できる。いずれにせよ、子供法が質が高いというようなことはあったとしても、量が多いということはないだろう。また、パターンの種類が多ければ多いほど、それらの関連性、創発性も高まり、質も高くなるのかもしれない。
個人的に気になるのは、子どものほうが偏見が少なく、パターンの組み合わせが意外性を生みやすい、独自性を生みやすいというのはあるのかもしれない。ただ量だけが多くても、その組み合わせ方に偏見がありすぎると、なにも生まれない。ただ創造性が高いだけで、創造ができない人もいるだろう。
メモ
・赤ちゃんの交流は、大人との情動的(ハート)的な交流によって行われる
→ハートにはリーズンの知り得ない、どくじのリーズンがある(パスカル)。
・ピアジェのアリストテレス世界
・ベイトソンのアナログ・デジタルの区別
・近代は言語的な、デジタル的な思考に偏りすぎなのかもしれない
・教育こそが、パラダイムの強化、社会化の重要な段階になる。教育をアナログよりにすることで、すこしはパラダイムが変わるのかもしれない。
・役割交換はミードともつながっていく
「早熟で非凡な才能の持ち主でありながら,三十七歳の若さで亡くなったレフ・セミョノヴィチ・ヴィゴツキー(1896~1934年)は心理学におけるモーツァルトと呼ばれている。そんな彼の才能を伝記に書いたK・レヴィチンは「繊細な心理学者博識な芸術学者、有能な教育学者,たいへんな文学通,華麗な文筆家,鋭い観察力をもった障害学者,工夫に富む実験家,考え深い理論家,そして何よりも思想家」と記している(柴田,2006。)ヴィゴツキーは多くの人に惜しまれるほどの才能を持ちながらあまりにも早く亡くなてしまった」
福田繭子, 福岡与志美, 福田梨奈「社会的存在としての子ども観: ヴィゴツキーの視点から」,24P
「ヴィゴツキーは想像を過去の経験やイメージを解体して新しい組み合わせによって新しいものを作り出す精神活動が想像である。また,目の前に存在しないものを,心の中に描くのも想像である」と定めている。このことから,想像は過去の経験に基づき,目の前に存在しないものを心の中に描くことであると言える。」
福田繭子, 福岡与志美, 福田梨奈「社会的存在としての子ども観: ヴィゴツキーの視点から」,31P
「ヴィゴツキーの言う想像力の役割は次の四点である。子どもにとって,①経験の拡大,②遊びの発展,③内的な表現の充実(共感や同情等,④社会的な意識への影響である。)その中の①経験の拡大について,ここでは考える。子どもにとって,今までに見たことや聞いたことから想像できることは限られている。ヴィゴツキーも「子どもの想像力は,大人よりも貧弱である」と指摘している。このように,子どもは大人よりも経験が浅く,想像する時の現実を知らない。そのため,ことばだけでは想像しにくい物語があるはずである。その想像しにくい面を,絵本の絵や読み手の表情,身振りといった視覚的な情報を取り入れることによって,子どもに想像をしやすくさせる。視覚的な情報を一つの手助けとするのである。」
福田繭子, 福岡与志美, 福田梨奈「社会的存在としての子ども観: ヴィゴツキーの視点から」,32-33P
「しかし、ここでも問題になるのが、創造的であると認知する「社会」の機能の問題である。マスローが指摘するように、確かに科学者の発見は、それまでの先人の積み上げによるところが大きい。しかし、ヴィゴッキーによれば、「あらゆる発明者は、天才でさえも常にその時代、その環境の産物なのである。いかなる発明も科学的発見も、それが発生するために欠くことのできない物質的、心理的条件がつくりだされるよりも、それ以前にはあらわれないのである。創造とは、あらゆる後に来る形式が先にあるものによって定められている歴史的な継承の過程なのである。」と、文化歴史的なものとして創造性を捉える立場からすると、マスローの指摘はいわゆる「至高経験」の観点にこだわりすぎていて、創造性の全体像がつかめていないものと考えられるだろう。また一次的創造性で発現したアイディアを、社会に既存の知識と照合し論理的、合理的に所産としてまとめあげる二次的創造性を軽視することは、知識の獲得という教育の一つの側面を軽視することと同義であると考えられる。これはヴィゴツキー(1972)の想像的創造は伝達された知識を含む「経験」を素材とすることから、経験の少ない子どもよりも経験が蓄積された大人の方が創造性は高いとする理論と相反する。マスローの創造性理論においては、創造性の「発達」に関して明確な記述はみられない。マスローの理論の特徴は、創造性の評価の観点と創造性における知識の必要性の観点の欠落と、「いまここ」に没頭することによって経験する感情に重きを置くことであると言える」
夏堀睦 「人間性心理学における創造性研究 : A.H. MaslowとM.Csikszentmihalyiの創造性理論の検討」,50-51P
アメリカの心理学者、ミハイ・チクセントミハイ(1934-2021)による創造性とは
チクセントミハイは「創造性とはなにか」という視点から、「創造性はどこにあるか」という視点への変換を主張している。
マズローと同じように、「創造の過程」を重視しているが、チクセントミハイはとりわけ「外界」を重視しているという点がポイントになる。たとえば学校や職場、友人や同僚などは創造にどのように関わり合っているのか。
[チクセントミハイ]創造性とはなにか、意味、説明
創造性:・個人、領域、フィールドという3つの要素から構成されたシステムの相互関係のこと。創造性は静的なものではなく、3つの要素が交差するところにおいてのみ観察できるという。
創造性はこの「3つの要素から構成されたもの(what is creativity)」であるといえる。そして、この「3つの相互関係において(where is creativity)」起こるといえる。
・チクセントミハイは創造性の本質について、社会・文化的な側面を強調している。
個人の創造性は社会(フィールド)と領域(文化)があってこそなりたつ。確かに社会や文化が皆無な人間の創造性というものは考えにくい。
とりわけ、社会的に新しいもの、社会的に価値があるものといったような独自性を創造性の定義に含める場合は、たしかに個人の内面だけではなく、その外にあるものが重要になるといえる。
チクセントミハイは「創造性は、文化的ルールの体系がなければ認識できず、それを評価する人の支援がなければ新しさをもたらすことはできない」という。
「まず最初の問題は、他者からの評価が必要だとされる点である。この文脈においては、創造性は、新規性やオリジナリティについての他者の認定を必要とする。例えば、創造性について研究した心理学者ミハリ・チクセントミハイは、創造性の本質については社会・文化的な側面を強調する。「創造性は、文化的ルールの体系がなければ認識できず、それを評価する人の支援がなければ新しさをもたらすことはできない」という。たしかに、既存の考えや商品などとの比較なくして、その創造的なアウトプットの社会的な観点からの評価はできないだろう。しかし、そのような評価の観点からは、創造のプロセスについては見えてこないのもまた事実である。」
井庭崇「 創造システム理論の構想」,3P
[チクセントミハイ]DIFIモデルとはなにか、意味、解説
DIFIモデル(Domain-Individual-Field Interaction model):・領域(Domain)、個人(Individual)、フィールド(Field)が相互に関わり合い、交差する(Interact)ところにおいてのみ創造のプロセスが観察されるというモデルを図式化したもの。
・DIFIモデル(1993)
・DIFIモデル(1988,1994)
[チクセントミハイ]領域とは、意味、解説
領域(Domain):・特定のトピックについての組織化された知識体。シンボルシステム。
たとえば数学など。いわゆる「文化」という体系が大きな領域であり、そこから細分化していくと数学、物理学、芸術、経済、さらに代数学、絵画、営業というようになる。
・領域の役割は既存の知識との関係において評価される、新しい知識の可能性を認めるレベルを選択することだという
たとえば相対性理論が新しいかどうか、既存の理論の比較によって可能になる。領域という文脈において、領域との関係において、個人の創造性が評価されていく。
それぞれの領域は表現技術をもっており、そうしたいわゆる「知識」を個人が身につけ、評価の場であるフィールドで活動していく。
たとえば既存の社会学(領域)を本などを読んで身につけ、ユーチューブや大学、研究会という場所(フィールド)で、このほうがもっと社会を説明できるのではないか、と活動してみるという過程を考えてみる。
そこで視聴者や関係者に「それは新しくない、有用ではない、新しい、有用だ」というような判断を受ける。そうした相互作用全体が創造であり、どれかが欠けても創造性があるかどうかを説明しにくくなる。
[チクセントミハイ]フィールドとはなにか、意味・解説
フィールド(Field、場):・領域の社会的組織のこと。いわゆる社会システムであり、ざっくりいえば社会。
文化と同じように、社会も細分化していくことができる。学校の人々、SNSの人々、家族、同僚、同業者、組合といったように多くの小さな社会がある。
・フィールドの役割は、提案された新しい変化の中で有望なものを選択し、領域に取り入れること。
チクセントミハイはフィールドの例として、視覚芸術を挙げている。たとえば美術教師、美術館の学芸員、批評家、文化事業に関わる財団や政府担当者など。
領域の構造に影響を及ぼすことが可能な全ての人々を含んでいるのであり、その意味では鑑賞者である我々一般人も含まれているといえる。
そして、新しい限界、つまり領域にとって新しいかどうか、保存すべきかどうか、認知されるべきかどうかを判断する正しいセンスが重要になるという。
過去の成果をできるだけ多く知っている必要がある。ただ量を重ねるだけではなく、全体を通して部分を見ていく、トータリテート(全体性)も重要になるだろう。
このように動画で既存の知識を紹介してく作業も創造性に寄与しているのかもしれない。高校や大学などの基礎学習も単なる暗記作業に見えて、実は創造性にとっても重要になってくるのではないだろうか。しかし、解答が単一な学習をしすぎると、正解が複数ある問題に対処しにくくなる、というような副作用もあるかもしれない。
[チクセントミハイ]個人とは、意味・解説
個人(英;Individual):・目標、目的、計画、活動への没頭が互いに関連し合う活動のネットワーク
・チクセントミハイは知性やパーソナリティなどの特性だけではなく、発達的側面を重視しているという。
たとえば頭がいい、優しいといった要素からだけで個人を考えていくわけではない。
3つの要素の相互作用
チクセントミハイによると、領域、フィールド、個人という3つの要素をそれぞれ独自に研究するだけではなく、それぞれの要素の相互関係を研究する必要があるという。
個人は領域を変革し、個人は領域によって変革の条件を形付けられている。たとえば社会学を一切学ばずに、新しい社会学をつくることは難しい。領域(既存の社会学)から学び、領域を変更し、またその変更をフィールド(社会学研究者たち、知識人等々など)によって評価されていく必要がある。
・こうしてみていくと、タルコット・パーソンズのような社会システム理論が頭に浮かんでくる。
「sikszentmihalyi(1988)は、DIFIモデルによる創造性研究の視点の変換を、“What is creativity”から“Where is creativity”への視点の変換として提唱している。このモデルは、知的あるいは技巧的職業の社会的、文化的側面に関連するfield、情報の別の形態を保持し表現するための知識体の構造や組織に関連する領域(domain)、そして領域やフィールドを変化させる可能性をもった知識を獲得し、組織化し、変換するところである個人の3つの側面を重要視し、フィールド、領域、個人を第一のサブシステムとして構築されている(Figure1)。」
夏堀睦「 人間性心理学における創造性研究. A.H.Maslow と M.Csikszentmihalyi の創造性理論の検討一」51-52P
「創造性について研究した心理学者ミハリ・チクセントミハイは、創造性の本質については社会・文化的な側面を強調する。ここでは、チクセントミハイの創造性理論において、DIFIモデル(Domain-Individual-FieldInteractionmodel)と呼ばれるシステムモデルを取り上げる。チクセントミハイの「創造性のシステムモデル」によれば、個人(Individual)、領域(Domain)、フィールド(Field)が相互に関わり合い、交差するところにおいてのみ創造のプロセスが観察される(図9)。チクセントミハイのDIFIモデルによって、創造性研究の視点が転換された。チクセントミハイは“whatiscreativity”から“whereiscreativity”への視点の変換として提唱している。創造性は三つの主要な要素から構成されたシステムの相互関係に関して、チクセントミハイは以下のように述べている(Csikszentmihalyi1997=2016:31-32)。
そのシステムを構成する第一の要素は、記号体系の諸規則や手続きのまとまりから成る領域(DOMAIN)である。数学は領域であり、もっと細かく分解すれば、代数学や数論も領域とみなすことができる。さらに領域は、私たちが通常文化と呼んでいるもの、つまり、特定の社会や人類全体によって共有されている記号体系の知識に組み込まれている。創造性を構成する第二の要素は分野の場(FIELD)であり、ここには領域の門番としての役割を担うすべての人々が含まれる。彼らの仕事は領域に新しい考えや成果を加えるべきか否かを決定することである。視覚芸術において、分野の場は、美術教師、美術館の学芸員、美術品収集家、批評家、文化事業にかかわる財団や政府担当者などによって構成される。新しい作品のなかでどんなものが認知や保存、記憶に値するかを選ぶのがこの分野の場である。最後に、創造性のシステムを構成する第三の要素は個々の人(PERSON)である。音楽、工学、ビジネス、あるいは数学といった特定の領城の記号体系を用いて、ある人が新しいアイデアを出し、新しいパターンを見出したりするとき、そして、適切な分野の場によってその斬新さが選ばれて当該領域に組み込まれるとき、創造性が発生する。
創造性を用いる活動は、すべてこのモデルの各要素間を巡るシステムとして記述可能である。萩原は「この過程の中で、個人が領域に接触し、個人的な背景をもとにまず自分にとっての新しさを算出するプロセスが『小文字の創造性』に、産出されたものを評価し、領域に組み入れていく過程が『大文字の創造性』に関わっているのである。」(萩原2009:102)と述べている。そして、夏堀は、DIFIモデルを児童の物語創作活動に適用し、児童の物語創作活動をドメイン(物語創作に必要な言語的知識)、個人(物語創作を行う児童)、フィールド(学校、その中で実際の評価者は教師)にあてはめて、創造性の評価について研究している(夏堀2005:77)。以上の知見を踏まえ、チクセントミハイの創造性のシステムモデルを協働作話にあてはめると、次のように整理できる。①ドメイン・・・・・・作話創作に当たっての表現(言語、ジェスチャ、描画など)②個人・・・・・作話創作を行う児童③フィールド・・・・・学校(その中で実際の評価者は教師、児童同士)。」
李月「協働作話における児童の応答行為と協働作話の展開過程における児童同士の創造性の発揮に関する実証的研究」.30-31P
[チクセントミハイ]フロー経験(最適経験)とはなにか、意味・解説
フロー経験(最適経験):・遂行している活動に没入し、全意識がその活動を遂行するために働き、その活動をある瞬間から次の瞬間への連続した流れとして経験している状態。
他の定義案:恐れや脅威による意識の無秩序とは反対の状態であり、注意が自由に個人の目標達成のために投射されている状態。
日本ではスポーツの分野においてゾーンとも呼ばれている。あるいは無我の境地、忘我状態といった類語があるという。
「ではここからはチクセントミハイのフロー概念を検討してゆこう。彼は著書の中でフロー状態について以下のように述べている。この特異でダイナミックな状態―全人的に行為に没入している時に人が感ずる包括的感覚―をフロー・・・(flow)と呼ぶことにする。フローの状態にある時、行為は行為者の意識的な仲介の必要がないかのように、内的な論理に従って次々に進んでいく。人はそれをある瞬間から次の瞬間への統一的な流れとして経験し、その中で自分の行為を統御しており、更にそこでは自我と環境との間、刺激と反応との間、過去現在未来との間の差はほとんどない。この記述から察するに、フロー状態とは個人の内的な論理によって進行していく行為であると捉えられる。さらにその行為にある最中に、人は意識を瞬間から瞬間へと統一的に流れていくものとして経験し、そこでは自我と環境との差がほとんど無いとされている。仮にこの「自我」と「環境」という言葉を、ベルクソンが使用している「意識」や「空間」といった言葉に置き換えて述べるならば、主観的意識と客観的空間の差がほとんど無い状態4だと言うことができるだろう。」
玉木博章「教育における「時間-空間-人間関係」問題に関する研究(2)―チクセントミハイによる「フロー」概念を手がかりにした生活指導の視点から―」,106P
「チクセントミハイによれば、フローとは、遂行している活動没入し、全意識がそのその活動を遂行するために働き,その活動をある瞬間から次の瞬間への連続した流れとして経験している状態である。」
石田潤 「 内発的動機づけ論としてのフロー理論の意義と課題」,39P
チクセントミハイによるフロー経験の8つの特徴とは、解説
- 注意の集中:注意はすべて当該の活動を行うのに必要な情報が得られる対象にのみ向けられている。
- 意識と活動の融合:意識が活動と一体になっていて、活動の中に意識が没入している
- 自己意識の消失:活動している自分自身を客体化することがないという
- コントロール感:自分の活動そのものや活動にかかわる対象や事物を思うがままにコントロールしているという感覚が得られるという
- 時間間隔の変容:実際の経過時間よりも短く感じたり、ゆっくりと時が進んでいるように感じる
- 自己目的性:その活動自体が目的であり、それ以外の目的や報酬を必要としない
- 楽しさ:身体的または精神的に大きな苦しさを伴うような活動であっても、楽しさや心地よさを感じる
- 流れ感:意識はあたかも水が流れるようになめらかに働いている
「最適経験とは、心理的エントロピーと呼ばれる、恐れや脅威による意識の無秩序とは反対の状態であり、注意が自由に個人の目標達成のために投射されている状態である。この最適経験をチクセントミハイは調査面接によって得られた被験者の表現を使って「フロー」(flow)と呼んできた。フローは意識に新しい秩序を創る新規な感覚、達成感覚を伴うという点で、「快楽」とは異なる「楽しさ」と直結している。チクセントミハイ(1996)によれば、最適経験の構成要素は第1に課題に達成の見通しがあること、第2に集中、第3、4に明瞭な目標と直接的なフィードバック、第5に深いけれど無理のない没入状態での行為、第6に自己統制感、第7に行為中の自己意識の喪失とフロー後の自己感覚の強化、最後に時間経過の感覚の変化、の8つであるという。集中、没頭、没入、行為の目的といった構成要素の大部分はマスローと酷似している。しかし、マスローの理論との相違点はフィードバックの強調、つまり外界の反応の役割の強調である。チクセントミハイは、マスローの言うように自己目的的な活動それ自体のなかに楽しさを見出せる者だけでなく、楽しさを感じるためには他者の評価を必要とする者もいることを主張する。」
夏堀睦「 人間性心理学における創造性研究. A.H.Maslow と M.Csikszentmihalyi の創造性理論の検討一」51P
フロー経験(フロー状態)の発生条件とは、解説
- 達成目標の存在:達成しようとする目標が明確であることによって、それだけ意識や心的機能の秩序性が高まり、フロー状態が発生しやすくなる
- 課題の適度な困難度:達成しようとする目標や課題の困難度は適度であることが望ましい。
- フィードバック:目標や課題の達成度について適切なフィードバックが得られることがフロー状態の発生を促す。
「また,チクセントミハイによれば,フロー状態の発生は次のような条件によって促される。第1は「達成目標の存在」である。達成しようとする目標状態が明確であることによって,それだけ意識や心的機能の秩序性が高まり,フロー状態が発生しやすくなる。第2は「課題の適度な困難度」である。達成しようとする目標や課題の困難度は適度であることが望ましい。第3は「フィードバック」である。目標や課題の達成度についての適切なフィードバックが得られることがフロー状態の発生を促す。」
石田潤 「 内発的動機づけ論としてのフロー理論の意義と課題」,42P
フロー経験はマズローの「至高経験」と類似している
1:マズローの「至高経験」は創造性にとって最も重要な要素だった
2:フロー経験は創造にとって重要であるといえる
3:「フロー経験」と「至高経験」の違いはどこにあるのか
夏堀睦さんによると、マズローの理論とチクセントミハイの理論の相違点は、「フィードバックの強調」であるという。
フィードバックとはビジネス用語では一般に、「相手の行動に対して改善点や評価を伝え、軌道修正を促すこと」をいう。専門的には、サイバネティックス理論の基本概念のひとつであり、「ある原因から生み出された結果がその原因に反作用をもたらすことによって、原因自体が自動的に調整され、より望ましい結果が導かれる過程」を意味する。たとえばエアコンの温度の調整などが例としてあげられることがある。
どのようにして適切なフィードバックを得るのか
フィードバックは外界の反応の役割の強調であり、外界には「他者」が含まれている。たとえば筋肉が増えている、という一人でも目に見える他者を介在しないフィードバックもあれば、筋肉が増えていることをコンテストで評価される、というフィードバックもある。視聴者数が増えることも、フィードバックかもしれない。
個人的にはこのフィードバックが対称的・相補的だとバランスを崩すことがあるというベイトソンの理論と繋がってくる。たとえばボディービルダーのライバル関係が過酷になり、体調を崩してしまうなど。
マズローは自己目的的な、活動それ自体のなかに楽しめるということを強調している。
チクセントミハイも同様に自己目的性を強調するが、しかし、楽しさを感じるためには他者の評価を必要とするものもいることを強調している。
マズローも他者の評価を重視しているが、創造性(自己実現の欲求)よりも低次のものである「尊敬、評価の欲求」として評価している。どのような文脈において創造性というものが生じているのか、楽しいと思えるのかを考えていくことが重要になる。
「集中、没頭、没入、行為の目的といった構成要素の大部分はマスローと酷似している。しかし、マスローの理論との相違点はフィードバックの強調、つまり外界の反応の役割の強調である。チクセントミハイは、マスローの言うように自己目的的な活動それ自体のなかに楽しさを見出せる者だけでなく、楽しさを感じるためには他者の評価を必要とする者もいることを主張する。
「しかし、人はそれぞれ、他の人より高く評価する特定の情報に対しては気質的に敏感であり、その情報を含むフィードバックについては他の人よりも身近に感じる傾向がある。(中略)これと対照的に、他者に対して遺伝的に異常に敏感な人々がおり、彼らは他者が送り出す信号に注意を払うことを身につける。彼らが求めるフィードバックは人間の情緒の表現である。ある人々は自信をたえず新たにすることに敏感である。彼らにとっては競争状況の中で勝つことに関する情報だけが価値ある情報である。他の者は人に好かれることに多くの注意を払っており、彼らが関心を持つフィードバックは他者による承認と賞賛のみである。(チクセントミハイ、1996、Pp.72-73)」
チクセントミハイにおいては、最適経験には外界の反応によって「自分はうまくいっている」と感じることも非常に重要であり、マスローの欲求階層説のように他者からの承認の欲求が、創造的であることと同義である自己実現の欲求より低次なものとして位置ついているわけではない。他者からの承認は最適経験の重要な構成要素となる。こうした最適経験の理論を基礎に置くチクセントミハイの創造性理論では、マスローの理論では強調されていない「外界」の問題も包括されている」
夏堀睦「 人間性心理学における創造性研究. A.H.Maslow と M.Csikszentmihalyi の創造性理論の検討一」51P
ルーマンと井庭崇さんにおける創造性とは
創造実践学者の井庭崇(1974~)さんにおける創造性とは
創造:・発見の連鎖
発見:・創造過程の中で幾度となく生じる「小さな発見」のこと
※社会的に新しい、天才がするようなものは「大きな発見」のイメージ。小文字の創造性、大文字の創造性とも区別されることがある(萩原雅也)。社会的に新しくなくても「小さな発見」であり、それが連鎖していれば創造であるといえる。
POINT:創造性があるかどうか、創造的かどうかを「心理的・社会的側面」ではない側面で考えていく
たとえば幼い子どもが積み木で木管楽器のようなものをつくったとする。こうした楽器は社会的にはすでに存在するので、社会的に独自性のあるものとはいえない。
しかし、そうした社会的な観点からだけでは、創造の過程が見えてこないと井庭さんはいう。かといって個人的な観点、たとえば心理過程からだけでも見えてこないという。
では、どのようにして創造の過程を心理的・社会的側面抜きで説明していくのか。どのような基準をもって、創造性が高いか低いか判断するのか。
システム理論にもとづく機能分析によって、創造の過程を説明していくという。
ニクラス・ルーマン(1922~1998)の社会システム理論やロバート・マートン(1910~2003)の機能分析を応用させ、「創造システム理論」によって創造を考えていくらしい。
・内容はすこし難解。今回はどこかワクワクすることが主張されていると感じつつ、分かったつもりになって表面だけをつかみ、フックのような要素として頭の中に残していきたい。いずれ、ルーマンとマートンを最後まで理解した後に、再度扱いたい。とはいえ、個人的に何が理解できないか、という点を理解できるくらいには今回取り扱いたい。
【井庭】「……僕の創造システム理論では、創造とは『発見』の連鎖であると考えます。ここでいう発見とは、ちょっとした気づきのことです。小さな発見と言ってもいい。世の中に認められた世紀の大発見というような、大文字のDでは始まるDiscoveryではなく、小文字で始まる、もうちょっと小さい気づき、そういった発見がいくつもつながって、それが1つの創造を成り立たせる。発見の連鎖によって、取り組んでいる『創造』がどんどん成長していくイメージです。このような発見の連鎖は、それはそれで創発的な水準で成立しているもので、人間の意識に還元されるわけではない、というのが創造システム理論の基本的な立場です。そして、社会システムにおけるコミュニケーションにも還元できない。個々の創造は、一つのシステムとして成立・存在する。ルーマンの理論と合わせると、創造とは、心的システムや社会システムとは別のシステムである、ということになります。」
井庭崇、他「社会システム理論」,218-219P
「もうひとつの例は、ある子供がおもちゃで遊んでいる場面でのことである。彼女は、積み木でいろいろなものをつくっていたが、静かな部屋で黙々とつくり続けていることに飽きてしまった。そこで、細長い積み木を両手にもち、そこら辺に散らばっている箱を叩き始めた。いろいろ叩いてみると、箱の大きさや素材によって、叩いたときの音が違うことを発見した。そこで、いろいろな箱をならべ、自分なりの楽器をつくって音を鳴らして遊ぶことになった。言うまでもなく、このようにして遊ぶことを思いついたのは、人類の歴史のなかで彼女が最初というわけではない。しかし、それは、彼女の行ったことは、創造的であったということはできないのであろうか?本稿で考えたいのは、このような社会的な評価とは別に、「創造」というものを定義する理論を打ち立てることである。その理論では、たとえ「車輪の再発明」であっても、そのプロセスが発見の生成・連鎖が起きているのであれば、創造的だと捉える。これに対し、たとえ新規でオリジナルなものだとしても、その作成に発見の生成・連鎖がなければ、それは、創造的ではなかったということになる。」
井庭崇「 創造システム理論の構想」,4P
ルーマンの社会システム理論とはなにか
1:ルーマンの理論は一言で説明すると「社会とはコミュニケーションの連鎖である」
「社会」は個人、主体や行為の集まりと考えられていたが、そうではなく、コミュニケーションの集合、連鎖であると考えていく。社会システムの要素は人間ではなく、コミュニケーションである。ルーマンは「社会はさまざまな社会システムの総計であり、コミュニケーションの集合であり、それ以上でもそれ以下でもない」という。
【井庭】「ルーマンの理論を一言で言うと、社会とはコミュニケーションの連鎖である、ということです。社会というのは、人の集まりではなく、コミュニケーションの集まりである。しかも、コミュニケーションは瞬時に消えてしまう『出来事』なので、社会が存在するためには、絶えずコミュニケーションが生成されなければならない。そのコミュニケーションの連鎖こそが社会の動態だ、とルーマンは捉えたわけです。それまでの社会学では、『社会とは、主体の集まりであるとか、行為の集まりである』という捉え方が主流でした。これに対して、ルーマンは、主体や行為から引き離された、社会レベルで創発する『コミュニケーション』こそが要素である、と考えたのです。」
井庭崇、他「社会システム理論」,200P
「要点を繰り返すならば、ルーマンによると、社会システムはコミュニケーション以外の何ものでもない。実際、ルーマンはつぎのように述べている。社会はコミュニケーション以外の何ものでもない。社会はさまざまな社会システムの総計であり、コミュニケーションの集合であり、それ以上でもそれ以下でもない。」
クリスティアン・ボルフ「ニクラス・ルーマン入門」,74P
ルーマンにおけるコミュニケーションとはいったいなにか
コミュニケーション:・情報内容と伝達意図が理解された時に創発する出来事
出来事は関係性、間主観性、コミュニケーション、動き(作動)というようなものが類語としてある。要素よりも、要素同士の関係に注目するというイメージ。こう考えていくと、ジンメルが形式に着目していたことを思い出す。
コミュニケーションは単に伝達行為ではなく、また通信のようなものでもないという。
たとえば、「佐藤さんが近所の田中さんに話しかける」という点だけを切り取ると、必ずしもコミュニケーションであるとはいえない。佐藤さんが田中さんに話しかけたつもりがなくても、田中さんが何か意図をもって話しかけれたと感じれば、コミュニケーションが成立するということがありえる。また、青空や神と私との間のコミュニケーションというものも、同様に青空に話しかけれたと感じれば可能になるといえる。これだけを聞くと「なんだそれは」と思うが、おもしろそうな話だ。
ルーマン以前のコミュニケーションは「送り手―受け手」モデルで考えられてきたという。
一方が発信した情報を、他方が受信することで、その情報が両者の間で共有され、コミュニケーションがなされるというわけだ。
たとえば、田中さんが佐藤さんに対して、「新しいスマホを買った」と話しかけ、佐藤さんがその発言を聞いているとする。なるほど、田中さんは新車を買ったんだな、と情報を単に受け取っただけでコミュニケーションとなる。意図の伝達的側面がなくても、コミュニケーションとみなされる。
情報、伝達、理解の選択
ルーマンは「送り手―受け手」モデルでコミュニケーションを考えていない。
ルーマンはコミュニケーションを「情報、伝達、理解の選択」のモデルで考えている。
情報:・何が発せられたのかに関わっている(what)。例:車を買ったという事実確認的な側面。バッテリーが切れそうだとスマホで自動的に表示される。
伝達:・なぜ発せられたのかという意図などと関わっている(why)。例:車を買ったと、なぜこちらに伝えてきたのか、という行為遂行的な側面
理解:・目の前の出来事を情報と伝達の2側面においてとらえるということ。たとえば木がこちらに倒れてきて、「木は私を攻撃しようとして倒れてきた」というような「伝達」として(普通は)考えない。車を買ったと友人が伝えてきた場合は、自慢かもしれない。あるいは送り迎えをしてあげるという意味かもしれない。あるいは、本人は意図がないかもしれない。
コミュニケーションは情報、伝達、理解という3つが揃った時に初めて創発するという。
創発(emergence)とは一般に、「部分の性質の単純な総和にとどまらない特性が、全体として現れること」である。つまり、素材や部分である個々人には還元されない、全体的な特性、出来事がコミュニケーションである。
重要なのは「理解が生じるのは情報と伝達行為を別々の選択として観察できるとき」という点。
たとえば「川が流れている」というのは一種の情報だが、そこになにか意図があるとは(一般的には)考えない。また、他者が自分に対してなんらかの意図をもって発話しただけではコミュニケーションとはいえない。他者の情報に対して、なんらかの意図をもって発せられたのだと自分が理解した時に、コミュニケーションが実現したといえる。もしそのように理解できない時、情報と伝達の差異を見いだせないときはコミュニケーションとはいえない。例えば遠くで人が転んだ時、そして、何か意図があったのだろうとは思えない時、ただ「転んだ」という情報だけが受信され、コミュニケーションに至らないかもしれない。情報だけの側面だけでは(受信はできても)「理解」に至らない。
・井庭さんの図説を参考にしたざっくりしたイメージ
コミュニケーションは「出来事(動き、作動、創発)」という点がポイント。パッと出て、パッと消える。生成と連鎖によってシステムがつくられる。
「これを、社会システム理論の言葉で言うと、『コミュニケーション』は、《情報》と《伝達》と《理解》という三つが揃ったときに初めて創発するものである、ということになります。《情報》というのは『何が発せられたのか』、《伝達》というのは『それがなぜ(どういう意図を持って)発せられたのか』、ということに関わっていて、それらが両方あることがわかるということが《理解》ということです。そのような創発的コミュニケーションが、社会の要素であると捉えるのが、ルーマンの社会システム理論の重要な点です。」
井庭崇、他「社会システム理論」,201P
「ルーマンから見ると、つぎの点も問題である。『移転のメタファーは、コミュニケーションの核心を移転という行為に、つまり伝達行為に見ている。このメタファーは、私たちの注意を送り手に向け、伝達のために必要な技能を送り手が備えていることを想定する』。これまた誤った想定だとルーマンは思っている。つまり、コミュニケーションをたんなる伝達の問題に還元することはできない。だが、コミュニケーションとは、たんに言葉を伝えることではないとすれば、どのようなものと考えればよいのだろうか。<送り手―受け手>モデルに対する代替案としてルーマンが提案するのは、コミュニケーションを三重の選択と理解することである。すなわち、情報、伝達、理解の選択である。コミュニケーション概念をこのようなものとして理解するためにルーマンが最初に行うのは、『他我』と『自我』の関係の最定式化である。具体的に言えば、『他我』と『自我』関係を逆転して、自我をコミュニケーションの受け手、他我を発言者としている。第一の選択は、他我が何かを情報として選択するときに生じる。たとえば、他我は最近、素敵な新車を買った。この情報が、今、たとえばEメールで自我に伝えられたとしよう。古典的な<送り手―受け手>モデルに従えば、これで十分コミュニケーション行為がなされたということになろうが、ルーマンにとっては、これだけではまだコミュニケーションとは言えない。コミュニケーションが実現したと言えるのは、第三の選択、すなわち近いの選択を自我が行ったときだけである。そして、理解が生じるのは、自我が、情報と伝達行為とを別々の選択として観察できるときである。つまり、自我は、情報と伝達の差異を観察できなければならないのである。」
クリスティアン・ボルフ「ニクラス・ルーマン入門」,79P
「通常の場合『コミュニケーション』はその語源(ラテン語のcomunico=共有する,communis=共通の)のとおり、二重の意味で『共有すること』として理解されている。つまり送り手/受け手双方がコミュニケーションの前提となるコード(文法等)を共有していることを前提として、一方が発信した情報を他方が受信することで、その情報が両者の間で共有される、というわけだ。それに対してルーマンはコミュニケーションを、『情報/伝達/理解という3つの選択の総合』として定義する。私たちが何らかの自然現象(稲妻が走った)を目にすることによって得られるのは、その現象が生じたという情報のみである。しかし誰かがこちらに話しかけてくるのを聞く場合には、話の内容(情報)と同時に、どういう意図・文脈で話しているのか(真面目か冗談か、単なる事実報告か警告か、など)をも把握しなければならないのである。言語行為論が教えるように、発話行為は事実確認的な(costative)側面(情報)と行為遂行的な(performative)側面(伝達)をつねに含んでいるからだ。逆にいえば目の前の出来事を情報と伝達の2側面においてとらえている(この作業が『理解』と呼ばれる)ときには、私たちはコミュニケーションに参与していることになる。」
「新しい社会学のしくみ」,151-152P
2:ルーマンにおけるコンティンジェントとはなにか
コンティンジェント(偶有性、偶発性):・コンティンジェント(偶有性、偶発性):必然でもなければ不可能でもない特徴のこと。「別様でもありうる」こと。
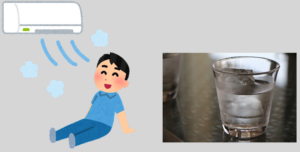
例:体を冷やすために、エアコンをつけるのも、冷たい水を飲むのも、機能的に等価であるといえる。体を冷やすためにエアコンであるような必然性もなく、また、代わりのアプローチを考えることが常に可能である。
例:「基本的人権の尊重」と「パレード」は国民の連帯を高めるという意味では、機能的に等価かもしれない。国民の不満を逸らすために、ある国がある国へのヘイトを意図的に煽ったりすること、お金をばらまいたりすること、一部の人間だけに制裁を加えることも等価かもしれない。相手を怒らせるために、タメ口をきくのと、無視は機能的に等価かもしれない(怒らせようとしているな、という意図としてどちらも伝達される)。
このように、機能的に等価なものの記述を重視する立場を「等価機能主義」という。
ルーマンの社会システム理論は「発見ツール」にすぎない
1:ルーマンの社会システム理論は演繹的な体系でも、帰納的な体系でもないという
2:ルーマンの社会システム理論は、ヒューリスティックな体系であり、発見ツールにすぎないという(この考え方は面白い)。
ヒューリスティックス:人が意思決定をしたり判断を下すときに、厳密な論理で一歩一歩答えに迫るのではなく、直感で素早く解に到達する方法のこと
3:ルーマンは社会システム理論の目標を「等価機能主義の図式に基づく、外でもありうる可能性の探索」だと主張している
ルーマンは「複雑性を縮減する顕在的なやり方の他に、同様に利用可能な潜在的な、機能的に等価な選択を指摘すること」が重要だという。
たとえば収入が多い人が「手伝いますよ」と言うのと、収入が低い人が「手伝いますよ」と言うのは、異なる伝達をもたらすかもしれない。前者の場合は「純粋な善意、もしくは偽善」として、後者の場合は、なにか「見返りがほしい」という意図として理解されるかもしれない。
そういう文化、いわゆる慣習があれば、よりそうした意図として理解されやすくなる。つまり、収入の違いによって、どう理解されるかわからないという複雑性が減る。しかし収入以外にも、ちょっとした笑顔などの仕草、服装、言葉の抑揚などでも、自分の正確な意図を伝えるようなものがありうるかもしれない。
社会学者の宮台真司(1959~)さんは、「システム理論は敏感な人間をますます敏感にするツールだ」と語っている。
システム理論を用いて自分が発見したことの意味や連関を明らかにでき、そのことを通じて新たな発見へと自分を導けるという。
つまり、システム理論は「発見ツール」として重要であるということである。こうした敏感であるというのはいわゆるセンスの問題である。演繹的に導き出せると考えたパーソンズと、熟練技的な「常識をうまく手放す」ウェーバーの比較を思い出す。センスといえばさらに、マンハイムのように「全体性(トータリテート)」を考えることも重要になる。
社会学的啓蒙
社会は所与の時代と所与の文脈における真理に服従する必要はなく、他の解決策がありうるということを示すことが重要であり、社会学者はそうした他の解決策を示す必要があるという。
単に知識を蓄積していくだけでは社会学的啓蒙とはならず、むしろ複雑性が増大することもある。
コンティンジェントな要素へと熟考させ、また要素同士を比較させ、反省させるように誘うのが社会システム理論だという。たとえば、人参の代わりにほうれん草でもいいのでは、と考えていく。
知識を単に集めていくだけでは、「甘味料は健康によく、健康に悪い」というような矛盾する知識が生じ、複雑性が増大してしまう。どっちにすればいいの、と迷ってしまう。ありがとうという言葉が皮肉か、感謝か迷うのと同じようなもの。その代わりに、お礼のお菓子をプレゼントすれば、感謝としてより伝えられるのでは、と考えていく。砂糖を我慢して甘味料をとる行為と、砂糖をとって運動する行為は機能的に等価か?と問いをつくっていく、そうした発想が重要なのかもしれない。
【井庭】「僕が何かを話したとき、そのどこを《情報》として認識するのか、どういう意図で《伝達》したと《理解》するのか。それには、いろいろな取り方がありえます。そういう『別様でもありえる』ことをコンティンジェント(偶有的)であると言います。生じることが不可能ではありませんが、必然的に何かが決まっているわけでもありません。このように、コミュニケーションというのは、コンティンジェントな状況のなかで何か一つの組み合わせが『選択』されるということに他なりません。そのコンティンジェンシーの中に創造性が宿りうるわけであす。決定論的に道筋が決まっているわけではないけれども、まったくのでたらめでもない。それは、いろいろな選択肢の領域がパッと広がりつつ、選択され収束し、また選択肢がパッと広がる。そういう運動性を持ったプロセスになる。それこそがまさに、創造的なプロセスの本質だと思うんです。」
井庭崇、他「社会システム理論」,210P
【宮台真司】「村上泰亮教授が『あなたは一般理論家を自称しておられるが、今日四つのコミュニケーション・メディアについての話を伺ったかぎりでは、近代は近代でも、ヨーロッパの近代にしか通用しない枠組だと感じる。一般理論だというな演繹的プロセスを明示してほしい。』と質問したんですね。ルーマンは『私の理論は演繹的な体系ではない。かといって帰納的でもない。単にヒューリスティックであるにすぎない、発見ツールにすぎない』と断言した。村上泰亮さんや公文俊平さんや佐藤誠三郎さんなどの大御所が虎視眈々と論理的矛盾をつこうと狙っていたところが、質問タイムの出だしから『私の理論は発見ツールにすぎない』と言われて、一挙に座が白けた思い出があります。逆に言えば、発見ツールなのだから、発見があればいいのです。これは僕にとっては大きな発見でした。『なるほど、そうか』と。ルーマンの著作がある時期から貧しくなることとも符合すると思いました。たかだか発見ツールにすぎないのに、発見が少なくなったんですね。ならば僕は発見のためにどんどんツールを使おうと思いました。それで僕は一九九二年に『サブカルチャー神話体系』という連載をやります。この本の最終章にこう書きました。『システム理論はどんな方法ですか』という問いに、『システム理論は敏感な人間をますます敏感にするツールだ』と答えたのです。システム理論という枠組自体指して面白いものではない。敏感な人間がシステム理論を『使う』場合にだけ輝くのだと書きました。これは、ルーマン流のシステム理論の凄さがどこにあるのかを示してもいます。多くの社会学的なフレームワークあh、AGIL図式で有名なパーソンズの社会システム理論が典型ですが、発見的に機能するよりも、むしろ敏感さを台無しにし、問題を覆い隠すように機能します。ルーマンのシステム理論には、彼自身が『等価機能主義の図式に基づく、他でありうる可能性の探索』こそが記述目標だと語ることからもわかるように、人々の敏感さを増大させるものである。これは僕自信がシステム理論にコミットする理由となります。システム理論に依拠すればだれでも有効な発見ができるわけじゃありません。鈍感な人がシステム理論を習得しても、何も発見できません。でも、敏感な人間であれば、システム理論を用いた発見ができますし、システム理論を用いて自分が発見したことの意味や連関を明らかにできるし、そのことを通じて新たな発見へと自分を導けます。その意味で、非常に重要な発見ツールだと思います。」
井庭崇、他「社会システム理論」,59-60P
「ルーマンは、彼の機能主義的システム理論のほうが優れていると信じていた。この理論装置が主張するのは、知識と理性を自己目的的に促進することよりも、どのように社会システムが『複雑性を把握し縮減するための潜在能力を増大させる』かを理解すべきだと言ううことである。さらに、それぞれの社会システムは異なった仕方で複雑性を縮減するのだから、システム論的なものの見方は、単一の(大文字で表記される)理性は存在しないと本気で思っている、ということも含意している。それどころか複雑性の縮減は、つねに偶発性──ルーマンのもうひとつの主要なマントラ──によって特徴づけられる。すなわち、ルーマンが好んで用いる表現によれば、『必然でもなければ不可能でもない』ものとして特徴づけられる。世界を別様に理解しアプローチする(したがって複雑性を縮減する)仕方を考えることはつねに可能なのである。偶発性の強調は、ルーマンの社会学的啓蒙のためのプログラムにおいても決定的な役割を果たしている機能主義的方法と密接に結びついている。潜在的なものと顕在的なものとを区別することでルーマンが主張したのは、何らかの特定の文脈において複雑性を縮減する現行の(顕在的な)やり方の他に、同様に利用可能な潜在的な(機能的に等価な)選択肢を指摘することができるということである。したがって、ルーマンにとって社会学的啓蒙とは結局のところ、この潜在的選択肢を顕在的にすることである。つまり、社会は所与の時代と所与の文脈における『真理』に服従する必要はなく、他の解決策がありうるということを示すことである。社会学者たちにそうした他の解決策を熟考し、比較し、反省するよう誘うのがシステム理論である。
クリスティアン・ボルフ「ニクラス・ルーマン入門」,24-25P
「せかんど・オーダーの観察のもとでは、『何が』観察されるべきかを、『何を』観察するのが正しいのかを一次的に特定することなどもはやできない。機能分化した各領域においてはそれぞれ抽象的な観点のもとでコミュニケーションが組織されているがゆえに、その観点について同じ働きをしうる(機能的に等価な)コミュニケーションを提起することがつねに可能だからである。たとえばかつてのドイツ国家学の大家R.スメントのように、基本(的人)権は、国民の連帯と高め国家を統合していくために不可欠であるとの論証を行ったとする。しかし、それによってたちまち、だとすれば基本権の代わりにパレード(ヒットラー、スターリン流の示威行進)でもいいはずではないかとの代案が浮かび上がってきてしまうだろう(Luhman1965:45=1989:69-70)。もはや宗教的な世界観などによって『そのような代替案は許されない』という絞り込みを行うことなどできないのである。」
「新しい社会学のあゆみ」,158-159P
3:ルーマンにおけるオートポイエーシスとはなにか
オートポイエーシス:・ギリシャ語のauto(自己)とpoiesis(産出)とを組み合わせたもので、システムの自己産出を意味する。
 元々は生物学者のマトゥラーナ(1928-2021)とヴァレラ(1946-2001)によって考えられたもの。主に生命現象の記述のために用いられた概念だったが、ルーマンは社会現象(コミュニケーション現象)を記述するために用いた。
元々は生物学者のマトゥラーナ(1928-2021)とヴァレラ(1946-2001)によって考えられたもの。主に生命現象の記述のために用いられた概念だったが、ルーマンは社会現象(コミュニケーション現象)を記述するために用いた。
「オートポイエーシスという概念はギリシャ語のauto(自己)とpoiesis(産出)とを組み合わせたもので、システムの自己産出を意味する。より正確には、オートポイエティック・システムとは、自己の要素を、要素同士の閉じたネットワークを通じて産出し再生産するシステムである、とオートポイエーシスは主張する。」
クリスティアン・ボルフ「ニクラス・ルーマン入門」,62P
(1)まず、前提として、システムと環境は区別される。
たとえば社会システムにとって生命システムは環境である。
ただし、システムは環境なしでは存在することが出来ない。環境があるからこそ、システムが存在する。システムとは環境との区別そのものといえる。たとえば天才が存在するためには、天才以外の頭の悪い人や、普通の人が必要になる。右翼が存在するためには、左翼が必要になる。区別によって明確な境界が確定できる。ただし、境界はつねに生成され、消滅していく。
「第一に、まずはシステムがその環境から区別されなければならないということを認めなければ、私たちはシステムについて語ることが出来ない、とルーマンは主張する。この最初の区別がなされなければ、システムはありえない。システムがその統一性を獲得し、独力で作動できなければ、その団体について語ることはできない。あらゆるものがそれ以外のすべてのものと渾然一体となっていて、明確な境界を確定できなければ、そこにシステムは存在しない。存在論の言葉づかいでひょうげんすれば、システムとはその環境との区別そのもので『ある』。以上のことから導き出されることは、システムはその環境と特別な関係にあるということである。システムは環境から区別されるが、同時に環境なしには存在できない。しかし、システムと環境が区別されるということは、システム内部の構成に関して言えば、つぎのことも含意している。すなわち、システムは、自己を環境から区別できるために環境を必要としているにせよ、システム内で生じるすべてのことは、システム自身の事柄であり、あくまでもシステムの環境内でのみ起こることである。」
クリスティアン・ボルフ「ニクラス・ルーマン入門」,49-50P
(2)社会システムはオートポイエティック・システムである
オートポイエティック・システム:・自分自身を不断に生成し続ける自律的なシステムのこと。社会システムはそれ自身の基礎的な作動、つまりコミュニケーションを産出し再生産する。
なかなかむずかしい。システムが環境に依存しているなら、環境によって律せられているのではないか、とも思ってしまう。生命も環境に、たとえば川の水がなければ維持できないのではないかと。依存と統制の違いとはなにか。
1:社会システムにとって、生命システムや心理システムは環境である。したがって、作動(コミュニケーションとし)は他の作動(意識や生命)に干渉されず、自己完結的に再生産が行われ、閉じている。あらゆるシステムは、他のシステムをの作動を決定できないし、干渉することもできない。
2:社会システムは生命システムや心理システムに依存している。たとえば社会システムは環境に生命システムが存在しなければ、存在することができない。心的システムが存在しなければ、同様に存在することができない。
3:あらゆるシステムは、他のシステムを刺激することができるだけである。この刺激のありかたは2通りあり、浸透や相互浸透と呼ばれる。
「したがって、ルーマンが、社会システムはオートポイエティック・システムであると言うとき、これが意味するのは、社会システムはそれ自身の基礎的な作動、つまりコミュニケーションを産出し再生産するということである。オートポイエーシスをこのように社会的領域に適用することは、マトゥラーナとヴァレラがこの概念でもともと意図していたこととは明らかに異なる。彼らにとって、オートポイエーシスは生命現象の適切な記述であって、コミュニケーション現象を記述するものではなかった。」
クリスティアン・ボルフ「ニクラス・ルーマン入門」,63P
浸透、相互浸透
浸透:・システムが存続するために必要な、物質的基盤における連続性を指し示している。例:社会システムは環境に生命システムを必要とするが、生命システムは社会システムがなくても存在できる。
相互浸透:・質的基盤における連続性が相互的に構成されていて、しかもそれぞれのシステムが相手方のために利用可能にした複雑性に各システムが依存している場合。例:社会システムと心理システムはお互いに依存関係にある(若干非対称ではあるが)
※構造的カップリングやシステム内の分化したシステム同士の関係は、今回深く扱えない。
「したがって、浸透は、システムが存続するために必要な、物質的基盤における連続性を指し示しているのに対して、相互浸透は、この物質的基盤における連続性が相互的に構成されていて、しかもそれぞれのシステムが相手方のために利用可能にした複雑性に各システムが依存している場合をあらわしている。たとえば、社会システムは、その環境内に生命システムが存在しなければ、存在することはできないが、この依存関係は相互的ではない。細胞や免疫システムは、社会システムが利用に供する複雑性がなくても、十分に活動することができる。社会システムと心理システムに関してはこの点が違う。両者は互いに相手方の複雑性を前提条件にしている。たとえば、社会システムは、思考が提供する複雑性がなければ発展することができないとし、同じように、心理システムは、コミュニケーションによって刺激を受けるという条件のもとでのみ、進化することができる。思考の改善は、往々にしてコミュニケーションの改善と密接に連動して起こるが、具体例を挙げるならば、量子物理学に関する思考は、この分野に関する専門的な科学的コミュニケーションに依存している。もちろんルーマンは、若干の非対称性があることを認識している。」
クリスティアン・ボルフ「ニクラス・ルーマン入門」,91-92P
刺激を受け、依存していて、影響を受けるが、干渉されない(???)
たとえばルーマンは、コミュニケーションは「精神」によってのみ刺激されるという。物理的、生理学的な作動によってではないという。フッサールの現象学が物理的・生理学的な作動を扱わなかったことを思い出す。
コミュニケーションは精神による知覚がきっかけによって生じうる。意識は何かを知覚し、それに影響を受けて社会システムに情報の選択を促す。
たとえば「友人が私に怒っている」と私が「判断」したとする。判断は知覚であり、意識である。この判断は、コミュニケーションを刺激する。ここから、「怒っているのは、私のためだ」と情報と伝達を区別し、理解する。ここでコミュニケーションが創発する。
もしなんら意識や志向性がないとすれば、コミュニケーションは生じない。誰かが野球をしていることが意識されなければ、実際に誰かが自分の目の前で野球をしていたとしても、コミュニケーションは生じない。ないことですら、意識されさえすればコミュニケーションを生じさせる(友人が学校に来ていないのは、面倒だからだ、だから連絡する必要はないだろう、というように)。生じる/生じない、生産する/生産しない、生じ方への影響と、生じるかどうかの影響、なかなか難しい。
・干渉されないというのは、「相互に相手のシステムの作動に取って代わるとか、直接介入するということがない」ということである。「システムの外部の作動をとりいれることができない」とも表現される。
例えば、田中さんは鈴木さんに触れたり、傷つけたりできる(刺激)。しかし、田中さんの細胞の生まれ変わりが、鈴木さんの細胞の生まれ変わりに影響することはない。田中さんの意識が、鈴木さんの意識に取って代わることもない(超能力があれば可能かもしれないが)。
例えば、社会システムは細胞や免疫システムの作動を突然取り入れることはできない。もしできたら、これは干渉である。
逆もまた同じであり、社会システムが細胞の作動によってコミュニケーションを生成しだしたりはできない。生命システムに依存はしているが、生命システムがコミュニケーションを生成するわけではない。きっかけにはなるかもしれない。
例えば、田中さんの怒りを「私のためだ」と理解し、さらにそうした理解が「遅刻をしなかった」という情報を生み出し、さらにその情報を田中さんは「私に怒られないために遅刻をしなかったんだ」という別の理解を生み出していく。コミュニケーションがコミュニケーションを生産していく。
前のコミュニケーションに何ら関係なく、単に細胞の生まれ変わりによって、田中さんが「私に怒られないために遅刻をしなかったんだ」というコミュニケーションを生み出していたら怖い。コミュニケーションのみが、コミュニケーションを生産する。しかし、コミュニケーションは意識に依存しているし、意識は生命に依存しているし、刺激を与えあっている(浸透しあっている)。しかし、それぞれのシステムは閉じていて、作動は代わりがきかない。わかったような、わからないような。
「これらの機能システムがそれぞれ自律的に動いているのが近代社会という社会である。経済、法、科学、政治、宗教、芸術、教育、マスメディアなどの各機能システムは、それを統合する上位の存在(神や道徳などの審級)なしに、それぞれが自律的に動く。このとき、個々の機能システムは孤立しているわけではなく、お互いの機能を前提として動いている。また、ある機能システムが他のシステムに干渉することもある。しかしながら、ある機能システムが他のシステムを制御したり、複数の機能システムが融合してひとつになったりすることはない。できること言えば、せいぜい他のシステムの環境に作用することで、なんらかの影響を間接的に及ぼすことだけである。たとえば、政治によって経済のコミュニケーションの生成を直接的に制御することはできない。あるいは宗教によって科学のコミュニケーションの生成を制御することもできない。しかも、それぞれの影響がどのようになるのかは、それぞれの機能システム次第なので、必ず何かの効果があるというわけでもない。あるシステムの干渉・影響が他のシステムにおいてどのような帰結を生むのかは、予測不可能なのである。このような機能システムの水平的な配置と、相互関係が、現代社会の姿である。それゆえ、私たちは、並行する複数の機能システムを視野に入れ、それらがどのような影響を及ぼし合っているのかを絶えず観察していくしかない。もはや私たちは、家族や道徳、宗教的宇宙像が複数の機能を有していた時代とは異なる社会に生きているのである。」
井庭崇、他「社会システム理論」,31-33P
「繰り返しになるが、社会システムは細胞や免疫システムの作動を突然取り入れるなどということはありえない。これらの作動はあくまでも生物学的な作動である。この主張は、ルーマンが生命、意識、コミュニケーションそれぞれのオートポイエーシスを厳格に区別するあkぎり、当然のことである。生命のオートポイエティックな再生産は、いかなる意識、いかなるコミュニケーションとも関係なく行われる。それは、意識のオートポイエティックな再生産が、いかなる生命、コミュニケーションとも関係なく行われ、コミュニケーションのオートポイエティックな再生産が、いかなる生命、意識とも関係なく行われるのと同様である。コミュニケーションのオートポイエティックな産出と再生産は社会システムだけが行うことであり、コミュニケーションでない事象は何であれ社会システムの環境に属するのである。」
クリスティアン・ボルフ「ニクラス・ルーマン入門」,64P
特殊なコミュニケーションについて
ある社会システムと、他の社会システムは同様に「コミュニケーション」を要素としてる。
しかし、それぞれの社会システムが区別できるかぎり、それぞれのコミュニケーションも区別できるのであり、それぞれ特殊なコミュニケーション作動を生み出している。
たとえば右翼の組織には右翼特有のコードに基づくコミュニケーションがあり、左翼の組織には左翼特有のコードに基づくコミュニケーションがある。科学では真/偽というコードに基づいてコミュニケーションが行われ、法では合法/不法、政治では与党/野党など。
馬鹿という言葉が褒めるという意図で理解される社会システムもあれば、そうではない社会システムもあり、また10分後に突然、そうした意図で理解されなくなることもある。たとえばある映画で「馬鹿が褒めるという意味で使われていた」という理由で、映画を共有したグループではそのような意味合いで使われるが、いつのまにか忘れられ、馬鹿は侮蔑の意味で理解されるようになるかもしれない。
「……オートポイエーシスが意味するのは、それぞれの社会システムがそれ自身の特殊なコミュニケーション作動を生み出すということである。パンク信奉者たちの社会システムとワインの熱狂的愛好家たちの社会システムはいずれもコミュニケーションにもとづいているが、それぞれがそれ自身の作動を生み出すのであり、突然、お互いに他者の作動を用いて作動する子などということはありえない。たとえば、一九六〇年代のボルドー・ワインにちて微に入り細に入り蘊蓄を傾け合うことが、セックス・ピストルズの遺産に結びついた作動にもとづいてオートポイエティックな再生産がなされているかもしれないパンク信奉者たちによって、重要な作動として受け容れられることはない。」
クリスティアン・ボルフ「ニクラス・ルーマン入門」,65P
(4)自己言及のパラドックスとはなにか
エピメニデスのパラドックス
自己言及のパラドックス:・一般に、発話の主体が自己を含めて何らかの指示や言及をしようとすると、真偽を決定できず、矛盾が生じる場合があるというもの
例:エピメニデスはクレタの人で、次のような金言を残した。「クレタ人はみなうそつきである」というエピメニデスのパラドックスが有名。この場合の発話の主体はクレタ人であるエピメニデスである。もし日本人が「クレタ人はみなうそつきである」といっていたら、何ら矛盾はなかった。
上のような図を考えてみる。もしこの陳述(この枠内の陳述はすべて嘘である)が正しければ、それは嘘になる。
つまり、この枠内の陳述は全て嘘である、ということが嘘になる。
それゆえ、この枠内の陳述は全て正しいことになる。すべて正しいとすれば、それは嘘になる。つまり、この枠内の陳述は全て嘘である、ということが嘘になる。それゆえ……(以下ループする)。
先程の例では「嘘であり、かつ正しいものである」というような矛盾が生じてしまっている。
ラッセルとホワイトヘッドによる「論理階型論」とは
論理階型論:・「論理学や数学において定義されるいかなる集合も、その集合自体の要素とはなることはできない」というもの
ラッセルとホワイトヘッドは「論理階型論」を主張している。
例えば、私の家にある椅子や近所の家にある椅子は要素である。そして、あらゆる椅子の集合である「椅子」がある。あらゆる集合である「椅子」が、「椅子」の要素となることは出来ない。もしそのようなことがあれば、矛盾してしまう。集合のほうが論理階型が高次であり、要素が低次である。
先程の「自己言及のパラドックス」では、「陳述」という言葉が集合(さまざまな陳述の集合)の意味と、集合内の要素の意味の、両方で使われてしまっているという。それゆえに、矛盾してしまうわけである。
「ここでのベイトソンの論理的出発点は、ラッセルとホワイトヘッドの『論理階型論』(Theory of Logical Types)であった。この理論それ自体はきわめて簡単で、『論理学や数学において定義されるいかなる集合も、その集合自体の要素となることはできない』というものである。たとえば、いま世界中に存在するあらゆる椅子からなる集合を考えてみよう。我々が普段『椅子』と呼んでいるものはすべてこの集合の要素である。だがその集合それ自体は椅子ではない。同様に、ある特定の椅子は椅子の集合ではありえない。ひとつの椅子と、椅子の集合とは、ふたつの違ったレベルに属す概念なのである(集合のほうが高次のレベルである)。集合とその要素との間には断絶があるというこの公理は、一見したところまったく当たり前に思えるかもしれない。けれども、人間をはじめとする哺乳動物のコミュニケーションが、つねにこの公理に違反し意味深いパラドックスを生み出していることがひとたび理解されれば、当たり前では済まされないことが見えてくる。こうしたパラドックスのもっとも有名な例が、世に言う『エピメニデスのパラドックス』あるいは『嘘つきのパラドックス』である。これはたとえば図14のような形で表すことができる。問題は明白だろう。もしこの陳述が正しいとすれば、それは嘘であり、嘘だとすれば、この陳述は正しい。この矛盾をどう解決するか?その答えはラッセルとホワイトヘッドの公理のなかにある。つまり、枠のなかの『陳述』という言葉は、『集合』(さまざまな陳述の集合)の意味と、『集合内の一要素』の意味の、両方で使われているのである。言い換えれば、集合がそれ自身の一要素となることを強いられているわけだ。そして、このような状況は論理学や数学のルールに反しているために、パラドックスが生じるのである。陳述それ自体が、その陳述が正しいか間違っているかを判断する前提とされているのであり、そこでは、異なったふたつのレベルの抽象(すなわち論理階型)が、ごっちゃにされているのだ。だが、現実には、人間のコミュニケーションもその他の哺乳動物のコミュニケーションも、『数学原理』の論理には従っていないのである。それどころか、意味あるコミュニケーションはすべて、メタコミュニケーション(コミュニケーションについてのコミュニケーション)を必然的に伴い、したがって、ラッセル的パラドックスをつねに生産してしまうのである。まず人間のコミュニケーションから考えてみよう。たとえばある行為なり会話なりをはじめるにあたって、私があなたに『これは遊びだ』と言ったとする。それによって私が伝えるメッセージは、『これを真面目に取るな』ということだが、それは厳密にはどういう意味だろうか?ベイトソンは『これは遊びだ』を次のように翻訳している──『いま我々が行っているこれらの行為[ゴッコ]は、それらが代わりをつとめている(stand for)[本物の]行為が表示する(denote)であろうことを表示しない』。ここで『代わりをつとめる』と『表示する』は同じことだから、これは次のように言いかえてよいだろう──『いま我々が行っているこれらの行為は、それらが表示する行為によって表示されることであろうことを表示しない』。もしも私が恋人の体をふざけてちょっと噛んだとすれば、その行為は『噛みつき』を表示するが、それは本当の『噛みつき』が表示するであろうことを表示するわけではない。それは、本当の『噛みつき』のように『攻撃』を表示する行為ではないのだ。私はそのことを、それ自体に対してコメントするような行為を遂行することによって、表現するのである。だが形式論理学にあっては、このような行動も『これは遊びだよ』という発言も許されない。ベイトソンが『これを遊びだよ』を翻訳した文は、『嘘つきのパラドックス』の好例である。なぜなら、『表示する』という言葉が異なった2つの抽象レベルで使われていて、そのふたつがあたかも同じ論理階型に属するかのように扱われている(すなわち一方が他方を否定することが許されている)からだ。恋人の体を噛む行為も、『これは遊びだよ』という陳述も、ひとつの枠組みを組み立てるが、その枠組がそれ自身の内容に言及してしまうのである。」
モリス・バーマン「デカルトからベイトソンへ」251-253P
論理階型の混同は、矛盾を生じさせる。
ベイトソン「論理に因果は語れない」
(1)集合と、要素の両方の意味で用いられているということは、集合がそれ自身の要素となることを強いられていることになる
(2)このような現象は矛盾を生じさせ、論理学や数学ではルールに反している。
(3)アメリカの人類学者、グレゴリー・ベイトソン(1861ー1926)によれば、ラッセル的パラドックスを現実の人間は常に生産しているという。
これはなかなか面白い。現実の人間世界では、実際に矛盾した現象が起きているというのである。
(4)ベイトソンによると、「論理に因果は語れない」という
論理は無時間的であり、因果は時間的であるという。それにもかかわらず、同じ言葉である「ならば」が用いられている。要するに、因果的な事象を論理的な事象として捉えてしまうから、頭が混乱してしまう。論理に因果を語らせようとするな、ということ。
例:1+1=2ならば、1+1+1=3である(論理)。温度が摂氏100度以下になるならば、水は凍り始める(因果)。
(5)エピメニデスのパラドックスをコンピューターに解かせてみれば、イエス……ノウ……イエス……ノウ……という答えを延々と打ち出してくる。
→形式的論理学において、この打ち出しは永遠に終わらない。なぜなら、時間がないから。
(6)現実にコンピューターに解かせようとすると、いつかは終わる。インクが切れたり、エネルギーが切れたりする。永遠には続かない。ベイトソンによると、「時間が無視されるところにパラドクスが生じる」という。
ベイトソンによると、生物界の至る所にみられる数百万ものホメオスタシスの例のひとつひとつが、形式論理学で記述しようとすると矛盾が生じてしまうという。
しかし、(論理関係ではなく)因果関係の連鎖としてとらえれば、そのような問題は生じない。というより、そのような矛盾が問題だ、解消するべきだ、とあえて考える必要はないといったところだろうか。
ホメオスタシスの例(細胞が組織を生産し、組織が細胞を生産する)は専門的過ぎてよく分からないので、ベイトソンが出している「遊び」の例で考えてみる。
・人間をはじめとする哺乳動物のコミュニケーションは、論理学で言うところのパラドックスをつねに生み出しているという。そもそも言語自体が、言語によって表現されるものと同一ではない。たとえば、リンゴという言葉は、リンゴが指示しているものと同一ではない。つまり、論理階型が違う。リンゴという言葉のほうが上位である。
論理階型の混同の例:「これは遊びだよ」
「これは遊びだよ」という文は、言葉が2つの抽象レベルで用いられている。つまり、論理階型が異なるものが、同時に存在している。
(1)「これは遊びだよ」→いま我々が行っているこれらの行為は、それらが表示する行為によって表示される(YES)ことであろうことを表示しない(NO)。
(2)「遊んでいる人が言った。『私が言うことは遊びだ』」と「クレタ人が言った。『クレタ人の言うことは嘘だ』」は同じ、自己言及のパラドックスのフレームワーク。
 (3)例えば、恋人が「これは遊びだ」と言って噛むとする。噛むという行為は「これは攻撃だ」という表示であり、同時に、「それは攻撃ではない」という表示も行っている。論理階型が混同されているので、形式論理学では矛盾が生じてしまう。YESなのか、NOなのか、どっちだ、と永遠に続く。
(3)例えば、恋人が「これは遊びだ」と言って噛むとする。噛むという行為は「これは攻撃だ」という表示であり、同時に、「それは攻撃ではない」という表示も行っている。論理階型が混同されているので、形式論理学では矛盾が生じてしまう。YESなのか、NOなのか、どっちだ、と永遠に続く。
しかし、現実にはそうしたコミュニケーションが(ほとんどの場合)問題なく行われる(なぜ問題なく行われているのか、複雑性が縮減されているのか、時間だけが原因かという点はポイントになる)。たとえば犬同士の噛み合い(甘噛)なども行われている。あえて攻撃することによって、攻撃しないよ、敵ではないよ、ということをひとつの動作で相手に伝える。
こうしたコミュニケーションを「メタコミュニケーション」というらしい。そして、ベイトソンによれば、意味あるコミュニケーションはすべてメタコミュニケーションだという。メタとは一般に、高い次元を意味しています。
オートポエティックシステムは、自己言及的である
井庭さんの説明によると、「オートポイエティック・システムでは論理学的に捉えると矛盾となってしまう循環関係を、時間展開することによって捉え直すことで、新しいシステム理論が生じている」という。社会は自己言及的に作動している、ということが重要。オートポイエーシスには「作動における閉鎖、自己組織、自己言及」という概念群からなる。
オートポイエーシスは形式論理学で捉えると矛盾が生じてしまうが、生物学や社会学で時間の概念を加え、捉え直すことで、有用な説明ができる理論として有効に活用できるという話。個人的には現象を説明できれば、それが形式論理学的に矛盾していようが、小さな問題。
「救出作戦を開始したラッセルとホワイトヘッドは、まずギリシャ時代から馴染みの”エピメニデスの背理”の解明から取りかかった。これは『クレタ人のエピメニデスが言った。「すべてのクレタ人は嘘つきだ」』というパラドクスである。今私はこれを引用中の引用という形で示したが、パラドクスの生じる機構は実はそこにある。つまり、まず一重括弧で示した言が、二重括弧で示した言を枠づけているのだが、二重括弧で示した言も、一重括弧で示した言を枠付けてしまい、そこに衝突が生じるのである。『エピメニデスは嘘をついたか』という問いに対する答えが、『もし嘘をついたのなら……嘘をついていない。もし嘘をつかなかったのなら……嘘をついた』となってしまうのだ。ノーバート・ウィーナーの好んだ言い方で言うとこうなる。『エピメニデスの背理をコンピューターに解かせてみれば、イエス……ノウ……イエス……ノウ……という答えを延々と打ち出してくるだろう。インクが無くなるかエネルギーが切れるか、他の形で限界がやってくるまで。』第二章その16で述べたように、論理は因果関係のモデルとはなり得ない。時間が無視されるところにパラドクスが生じるのである。」
グレゴリー・ベイトソン「精神と自然」,158-159P
「オートポイエーシスのシステム理論では、システムを構成する要素の生成プロセスのネットワークによって円環的に構成されるシステムを扱う。論理学的に捉えると矛盾となってしまう循環関係を、時間展開することによって捉え直すことで、新しいシステム理論が生み出されている。」
井庭崇「 創造システム理論の構想」,10P
5:オートポイエティック・システムの3つの特徴
井庭さんによると、ルーマンのオートポイエティック・システムには3つの特徴があるという
(1)時間化された要素
システムを構成する要素が、生成された直後に消滅してしまう「出来事」であるということ。そのため、システムが成立するためには要素が絶えず生み出されなければいけない。こうして要素が再生産されることを「作動(オペレーション)」と呼ぶ。再生産は全く同じ要素が工場で生産されるようなイメージではない。次々と、前の要素を前提として新しい要素が生産されていく(どうやって?が問題)。
コミュニケーションそれ自体がコミュニケーションを生み出していく(再生産)、とはどういうことか。
たとえば、田中さんが目の前の蚊にイライラして、舌打ちしたとする。それを見た鈴木さんが、自分にイライラしているから舌打ちしたのだ、と理解したとする。このようにコミュニケーションは出来事としてパッと生じる。さらにそこから、鈴木さんが嫌な顔をする。田中さんはそれを、「昨日きつく言い過ぎたから怒っているのかな」というふうに理解していく。
このように、コミュニケーションは話者の意図とは無関係なところで、ひとりでに続いていくことがある。コミュニケーションがコミュニケーションを生み出していく。
ある社会において、コミュニケーションがコミュニケーションを生み出すというような継続性がなくなったとすれば、それは社会とはいえなくなる(社会システムとはいえない)。
たとえば、今、世界で誰の発言の意図をも理解しないような状況、極論として全員が植物人間状態になったり、全員が睡眠しているような状態になれば、その時点では、世界において一切、社会システムは生じなくなったといえるのではないか。
コミュニケーションがなされる瞬間のみ、社会システムは存在する
要するに、コミュニケーションがなされる瞬間のみ、社会システムは存在するのであり、システムの存続は継続的な自己生産にかかっている。これを聞いて思い出すのが、会話である。友人と話していて、突然会話が途切れることがある。
Aに対してBと反応、Bに対してCと反応といったように継続的に続いていることもあれば、いきなり終わることもあり、いきなり再開することもある。空間的に隔たった(たとえばSNSでの会話、通話など)コミュニケーションもある。
コミュニケーションはわかりやすい会話だけではなく、連絡がこないこと、SNSが更新されること、されないこと、ボディーランゲージ、他の人との会話、散歩、運動、食事など、多種多様に考えることができそうだ。
情報を発したからといって、必ずしも他者の理解が生じるわけではない
多種多様な「情報」を個々人は発信していて、それを他者が伝達と情報を区別できる形で、2側面において把握する、つまり「理解」にもっていくかによってコミュニケーションが生じるかどうかが左右される。情報を発したからといって、必ずしも他者の理解が生じるわけではない(誤解も理解の一種ということに注意)。レストランで誰かの食事を見て、ああ、食事をしているな、というように情報の「受信」に留まると、理解が生じない。
例えば自分が街を歩いているときに、あらゆる通行人とコミュニケーションをしているわけではない。
例:正面に他者が歩いてきて、ぶつからないように方向を変えようとしているのを見た時、自分とぶつからないようにするためだな、と単なる受信を越えた伝達として捉えられ、コミュニケーションが生じる。自分は逆の方向にしよう、と別の情報を発信する。
そうすると相手は、ぶつからないようにするためだな、というように、コミュニケーションがコミュニケーションを生み出していく(再生産)。
もし単調なロボットなら、そのようなコミュニケーションができず、ぶつかってしまうだろう(それゆえ、このロボット同士では社会システムが生じない)。もし高機能なロボットであっても、たとえば視界に物体が入ってきたら避けるというような、選択性の乏しい反射的な行動になるだろう。
あらゆる物事が情報になり、伝達されうる
ものを買う、売る、席を譲る、視線を合わせる、警察に相談する、云々と、いろいろな情報、コミュニケーションを元にコミュニケーションが生じている。コミュニケーションは会話のようなものだけではなく、「なにかしないこと」も要素となりうる。コンビニの光を見ただけで、実際に中に店員がいるかどうかに関わらず、ものを売るために誰かが光をつけているのだな、とこちらが解釈すれば、それはコミュニケーションの創発になりうる。
たとえば働いていないことは職安を動かし、反応しないことは相手の嫌悪を生み出す。小さな社会システムが生成したり消滅したり、小さな社会システム同士がなんらかの関わりをもったり、もたなかったりしていく。
(2)システム境界の再生産
非持続的な要素の継続的な生成プロセスと、それ以外のものを区別する「システム境界」というものがある。
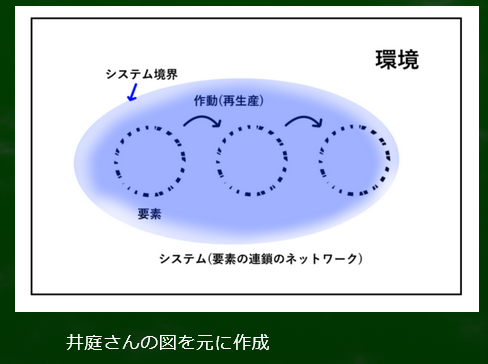 要素が再生産されるごとに、境界も再生産されていく。境界の内部を「システム」と呼び、その外部を「環境」と呼ぶ。
要素が再生産されるごとに、境界も再生産されていく。境界の内部を「システム」と呼び、その外部を「環境」と呼ぶ。
(3)システムに基づく要素の構成
システムの要素はでたらめにつくられるのではなく、システムに基づいてつくられる
要素がでたらめにつくられるのではない、というのはなんとなくわかる。たとえば客がコンビニでおにぎりを購入する時、お金を店員に渡す。店員は「この人はお金とおにぎりを交換するつもりでお金を置いたんだな」と理解する。
もし完全にデタラメに要素がつくられるなら、店員は「この人は私にお金とおにぎりをあげたいのか」と理解するかもしれない。そうならないのはなぜか。システムに基づいて要素がつくられているからである。
「オートポイエティック・システムの特徴を、筆者なりにまとめると、(I)時間化された要素、(II)システム境界の再生産、(III)システムに基づく要素の構成、の三つにまとめることができる(図5)。第一の特徴である「時間化された要素」とは、システムを構成する要素が、生成された直後に消滅してしまう「出来事」である、ということである。そのため、システムが成立するためには、要素が絶えず生み出されなければならないことになる。ここで、要素が再生産されることを、システムの「作動」(オペレーション)と呼ぶ。このとき、非持続的な要素の継続的な生成のプロセスと、それ以外のものとを区別する「境界」に注目すると、要素が再生産されるごとに、その境界も再生産されていることがわかる。これが、第二の特徴である「システム境界の再生産」の意味するところである。システムは作動の面では閉じており、それゆえひとつの統一体として存在する、ということができる。オートポイエーシスのシステム理論では、この境界の内部を「システム」と呼び、それ以外の外部を「環境」と呼ぶ。オートポイエティック・システムは、システムを構成する要素の絶えざる生成によって成り立っているが、その要素はでたらめにつくられるのではなく、システムに基づいてつくられる。これが、第三の特徴である「システムに基づく要素の構成」である。システムを構成する要素が、システムに先立って存在するのではなく、システムの存在があって初めて構成され得るということであり、システムと要素はいわゆる「鶏と卵の関係」にあることになる。」
井庭崇「 創造システム理論の構想」,11-12P
根本的二分法(バイナリーコード)
たとえば社会システムは、経済システム、法システム、政治システムと言ったように現代社会は機能分化しているという。
各領域ごとに独自の根本的二分法(バイナリーコード)といわれるものがあり、このコードを前提としてコミュニケーションが行われるという。コードを前提とせずにコミュニケーションは行えない。
たとえば、経済システムにおいては「(ある商品に対してある価格で)支払うか/支払わないか」というコードがある。
・独自の論理=コードという点がポイント。それぞれのシステムにはそれぞれの論理があり、他の論理が代わりに用いられることはない。仮に用いられるとすれば、それぞれのシステムは区別できず、同じシステムとなる。
・あるコードを前提とするコミュニケーションはすべて、当該システムに属することになる=これが「閉じられている」という意味。ここはポイント。
「各領域は機能分化したシステムとして、それぞれ独自の論理に従ってコミュニケーションを編成していく。『独自の論理に従って』とは具体的には、各領域ごとに相異なる独自の根本的二分法(『コード』と呼ばれる)を踏まえて、ということを意味する。法に関するコミュニケーションを行う際に、結局のところ問題となるのはつねに、ある行為や条文が『合法か、それとも不法か』ということにほかならない。同様に経済においてはつねに(ある商品に対してある価格で)『支払うか支払わないか』が、政治の場合なら(議会制民主主義のもとでは)『与党か野党か』が、科学の場合ならある命題が『真か非真か』が問題となる。逆に言えばあるコードを前提とするコミュニケーションはすべて、当該システムに属することになる。この意味で各システムは閉じられている。各システムは同じコードを前提とするコミュニケーションのみからなるのであり、またそのシステム内においてはコードを前提とすることなしにはコミュニケーションを行いえない。」
「新しい社会学のあゆみ」,156P
6:鶏と卵
(1)井庭さんによると、システムが鶏で、卵が要素であるという
(2)要素はシステムに先立って存在するのではなく、システムの存在があって要素ははじめて構成される
(3)システムは要素から構成されるのに、なぜシステムのほうが要素より先にあるのか。いわゆる循環論法的、論点先取り(?)的だが、しかし現実にはそうなっているのだからしょうがない。鶏が先か卵が先か、論理的にそこまで重要だろうか。現実には鶏が卵を産み、そこからさらに鶏が生まれるのである。自己組織性は定式化出来ないが、現実に存在する。発見ツールとして社会システム理論が便利ならそれでいいのでは。
パーソンズとホメオスタシスの話
反パーソンズの人々:機能主義的説明は目的論であって、原因・結果を明らかにする科学的説明にはならない。
パーソンズ「たとえば、キャノンのホメオスタシスの分析は、高等な有機体では体温が一定に保たれるという観察結果(事実)から出発するが、もちろんその次のステップは、なぜ恒常的な体温が維持されるのかというメカニズムの解明である。そして、これは決して目的論的な問いではない」
7:固有値
固有値(独;Eigenwert):・コミュニケーションにおいて前提・根拠として通用している情報内容
(1)コミュニケーションは別様にもありうる(コンティンジェント)だが、しかしでたらめに生じるわけではない。
(2)コンティンジェントな選択が積み重なり、それがひとつのコンテクストをつくり、歴史性を帯びることがある
(3)たとえば、客と店員のコミュニケーションの場合は、ほとんどの場合、相手の意図をおなじように皆理解している事が多い。客が紙幣を出したのは、物と交換したいからだ、と理解している。紙幣交換の初期の頃は、いったいなんだこの紙切れは?と思った人もいたかもしれないが、コミュニケーションが蓄積されていく。
(4)ルーマンはコミュニケーションにおいて前提・根拠として通用している情報内容を「固有値」と呼んでいる。
たとえばおにぎりを手に入れるために、店員を殴って奪うことと、お金を払って交換することが機能的に等価であったとする。ほんとうにデタラメにコミュニケーションが生成されていくのなら、どちらになってもおかしくない状態(複雑な状態)がつねに続いていく。しかし実際には、そうではない。貨幣というメディアが人々の受け容れられ、容易には動かしがたい前提として、「そうでなければならない」としてコミュニケーションの前提になっている。ようするに、複雑性が縮減された状態の上で、コミュニケーションが行われている。システムに基づいて要素は再生産されていく。
ポイント:あるコミュニケーションが「そうでなければならない」という必要がないのにもかかわらず、実際には容易には改変しがたいものが多くある。なぜか。どのような仕組みでそのような「秩序」が生まれるのか。
→コンティンジェンシー問題
【基礎社会学第十七回】タルコット・パーソンズの「ホッブズ的秩序問題」とはなにか
・建物をたててしまった後では、容易には改変し難い
→パラダイムシフトの難しさ
・デカルト的パラダイム、官僚制は檻のように我々を囲う
・固有値の形成をしていくために広く用いられる前提を、コミュニケーション・メディアという
「しかし、あるコミュニケーションが、『そうでなければならない』という必然性はないのにもかかわらず実際に発話され受け容れられ、後に続く多くのコミュニケーションの前提となっているなら、それはもはや容易には改変しがたい不動の前提として通用せざるをえない。ある建物の礎石を特定の場所に置く必然性はない。しかし建物を建ててしまった後では、その礎石はもはや自由に動かすことはできなくなる。ルーマンは、そのような意味で私たちのコミュニケーションにおいて前提・根拠として通用している情報内容を、『固有値』(Eigenwert)と呼んでいる。ほかならぬ『人権』は固有値の典型である。」
「新しい社会学のあゆみ」,159P
【コラム】ベイトソンと冗長性について
1:ベイトソンによると、コミュニケーションの存在理由は「冗長性、意味、パターン予測可能性、情報等々を作り出し、あるいは拘束によってランダム性を減じること」である。ルーマンで言えば、「複雑性が縮減される」といったところだろうか。
2:ベイトソンは「意味」を「パターン・冗長性・情報・拘束」とほぼ同義として見なしている。なんらかの出来事・集合体に、なんらかの方法で切れ目を入れ、かつ分割された一方の知覚から、残りの部分の有様をランダムな確率より高い確率で推測することができるとき、そこには冗長性またはパターンが含まれるという。
例えば、ベイトソンはTという文字はその次にHやRがくる可能性が高いことを告げているという。THEやTRUEなど、そうした言葉を我々は推測する。上司の昨日の行動から、今日の行動を推測し、葉っぱからその根を推測する。田中さんが「おはよう」と鈴木さんに言う時、この「おはよう」には鈴木さんも「おはよう」と返すだろう、というような、あるいは鈴木さんの対応を拘束するような情報、意味が含まれている。
3:文化は一種のコードであり、変換の規則そのものである。文化によって我々はパターン付けられ、コード付けられている。そして、コードによって個人や社会は安定する。たとえば日本人がいきなりアフリカの部族の土地へ踏み入れても、コードづけられていないので、安定したコミュニケーションが難しい。何をするかわからない、ランダムなやつがきた、と思われるかもしれないし、自分も相手に対してそう思っているだろう。交通のルールを知らなければ、交通事故を起こしてしまう。
4:イデオロギー(認識、世界観、現実など)や感情のパターン(支配/服従,保護/依存など)は、コード付けられることによって形成される。
ベイトソンによると、西洋文化とは、つまり西洋世界のコードは「報酬と回避の混合」であり、環境を操作することが重要になるという。今回は西洋文化のコードについて詳しく扱えないが、より安定する文化、コードとはなにかを考えていくことが重要になる。そして、ベイトソンは今の西洋世界のコードはよくない結果につながると考えている。核兵器の使用もそのひとつだろう。
【コラム】池田久美子さんによる「コードの増殖」とはなにか
教育哲学者の池田久美子さんによると、コードとは「記号の表現と内容とを対応させる規則」であり、「解釈の道筋」のことである。
例:「医薬品と医薬部外品のみを扱う店が、薬屋である」というのはコードである。このコードに従って、近所のある店は医薬品と医薬部外品のみを扱っているので、薬屋であると解釈できる。こうして個別・具体的な内容を、表現と対応させることができる。
遺伝子もある種のコードであり、このコードによって人間は生成され、また拘束されていると考えることができる。
「『意味』という観念は、次に示すような思考の枠組のなかでは、パターン・冗長性・情報・拘束という諸観念と、ほぼ同義のものと見なしてよいようだ。音素の連なりでもいい、一枚の絵でもいい、一匹のカエルでも、一つの分化でもいいが、なんらかの出来事またはものの集合体に、とにかくなんらかの方法で『切れ目』を入れることができ、かつ、そうやって分割された一方だけの知覚から、残りの部分のありさまをランダムな確率より高い確率で推測することができるとき、そこには冗長性またはパターンが含まれることになる。これを、切れ目の片側にあるものが、もう一方の側にあるものについての情報を含む、あるいは意味を持つと言っていいだろう。あるいはまた、工学用語を使って、その集合体が冗長性を含んでいるとも言えるだろうし、サイバネティクスの視点から、切れ目の片側から得られる情報が誤った推測を拘束するとも言える。例を示そう。一切れの英文のなかに現れたTという文字は、その次にHやRがくる可能性が高いことを告げている。すなわち、Tの直後に設けた切れ目の向こう側のありさまを、われわれはランダム以上の確率で推測することができる。これは、英文のスペリングが冗長性を含む、ということに等しい。」
グレゴリー・ベイトソン「精神の生態学」,203P
「冗長性、意味、パターン、予測可能性、情報等々を作り出し、あるいは『拘束』によってランダム性を減じることが、コミュニケーションの本質であり、その存在理由なのである。メッセージというものは、単に内的にパターンづけられているだけでなく、それ自体が、より大きなパターンの世界──文化ないしその部分──をなすものなのだ。芸術の伝達を含めたメッセージ一般について、それを包み込む大きなパターンも同時に見据える志向のシステムを築くことが何より重要であるとわたしは思う。芸術作品の特性は、文化的・心理的システムを反映するという前提にわれわれは立っている。芸術はそれが属する文化に『ついて』のものだ、あるいは部分的に文化から『導き出され』、また文化によって『規定される』ものだとわれわれは考える。」
グレゴリー・ベイトソン「精神の生態学」,204P
「学習をめぐる研究の出発点として、ベイトソンはまずひとつの、一見ナンセンスな問いからスタートした。それは、『正しい誤り』というものは存在するか?という問いである。より広い言い方をすれば、正しいイデオロギーというものは存在するか?ということである。イデオロギーとは文化のコンテクストの中で学習される文化的産物であるが、たいていの場合、そのイデオロギーを正しいと信じる文化にとってプラスにはたらくように作られている。たとえばバリ島人は世界についてさまざまな信念を持っているが、そのなかには我々やイアムトル族にはほとんど信じがたいような考え方もある。バリ島を調査するまでは、ベイトソンは累積的な相互作用を人間にとって本来的なものと考えていたが、バリ島の調査によって、ひとつの国民全体が累積的相互作用とはまったく無縁の行動を学習しうることが分かった。そればかりかバリ島社会は、イアムトル社会や西洋社会よりもはるかに安定している。とすれば、バリ島人の一見『気違いじみた』考え方のほうが、ある意味ではより正しいと言えるのではないだろうか?こうした考察をとおして、はじめの問いは次のように改められた──個人や社会の精神のなかで、イデオロギー(認識、世界観、『現実』)や感情のパターン(支配/服従、保護/依存)は、いかにして形成されるのか?この問いに答えるために、ベイトソンは、ベネディクトの『統合形態』の発想にならって、『文法』ないしコードの概念に立ち戻った。個人も社会もそれ自体ひとつの組織化されたシステムである。ある一貫性を持った、情動レベルでも認知レベルでも意味の通るやり方で、『コードづけられて』いるのである。コードが機能している限り、個人や社会を安定させるのはこのコーディングのプロセスにほかならない。そこで、このプロセスをさらに詳しく説明することが次の課題になった。すなわちこれが、学習理論の研究である。」
モリスバーマン『デカルトからベイトソンへ』,244-245P
「ベイトソンは、西洋文化とは、『報酬』と『回避』の混合からなるコンテクストのなかで機能している文化である、と述べている。ネズミの例からもわかるように、『報酬』のコンテクストでも『回避』のコンテクストでも、その眼目は環境を操作する(ネズミの場合、棒を押す)ことである。したがって、このような文化のなかにいる人間は、身のまわりのすべてのものをひたすら操作する技術を第2次学習する。その結果、『操作』に基づかないかたちで現実が構成されうるという考えは、およそ信じがたいものになってしまうのだ。」
モリスバーマン『デカルトからベイトソンへ』,246-247P
「それまでの学習理論研究からベイトソンが得ていた結論は、文化のメタコミュニケーション・システムは我々に枠組みの使い方を教え込み、その使い方がパーソナリティー、世界観、社会的正気を規定する、ということであった。また、ベイトソンの同僚のひとりで精神科医のジェイ・ヘイリーも、正気の諸症状は、論理階型の区別ができないことから生じるのかもしれない、という説をたてていた。」
モリスバーマン『デカルトからベイトソンへ』,256P
記号学者のウンベルト・エーコ(1932-2016)による「余剰コード化」とは
記号学者のウンベルト・エーコ(1932-2016)はアブダクションを「余剰コード化(extra coding)」と名付けている。
余剰コード化:・コード化されていない状況と複雑なコンテクストに直面した際、解釈者が一般的な規則を発明、ないし想定すること。
余剰コード化は2種類ある。既存のコードにもっと細かい規定を加えて分節化する「過剰コード化(overcoding)」と、信頼しうるコードがまだ存在しない場合に、大まかなコードを暫定的に想定する「過小コード化(undercoding)」である。
池田さんは「コード化されていない状況に直面したとき、コード自体をより一層分節的でより広い範囲の状況を処理しうるものに代えていくこと」を「コードを増殖させる」と表現している。
そして、コードを増殖させることは、「学習」であり、新たなコードを作り出す創造的な営みであるという。
こうしたコードの増殖、応用はベイトソンのいう学習2と似ていると感じた。ここからさらに、コードの増殖だけではなく、根本から変更する段階になると学習3に入る。学習3はより根本的な変化であり、滅多に生じない。別のパラダイムを選ぶというだけではまだ学習2の段階にすぎず、まだ前のパラダイムにとらわれている。学習3は精神病に陥ったり、宗教的な回心において生じることがあるという。
例:天蓋が名誉を意味するというコードを知っている。また、総督が名誉を意味するというコードも知っている。しかしそれらを知っているだけでは、天蓋のある乗り物に乗っている人物が総督であると解釈することはできない。「天蓋が総督を意味する」というコードがない。
アブダクションは「共通の性質を軸とする転換」である
池田さんによるとアブダクションは「共通の性質を軸とする転換」である。アブダクション前には、天蓋と総督の間に対応関係がなかったが、共通の項目として「天蓋」を軸に、関係を作る。天蓋も総督も異なるものだが、「名誉を意味する」という意味では共通である、という類推によって、暫定的にコードを提案していく(仮説形成)。
そこから、実際に総督かどうか実証していく(演繹・帰納)。そうしてコードが定着していくこともあるかもしれない。そこからさらに、違うコードが生まれていくことがあるかもしれない。
池田さんによると、アブダクションが活発に起こるためには、「他の表現との結合により新しい別の記号機能を作り出す可能性をもっていなければいけない」という。枝が複雑に分岐し、開かれている必要があるという。
たとえば、天蓋は雨よけという枝の他に、名誉という枝がある。この枝が多ければ多いほど、他のコードと共通点をもちやすくなる。なかなか面白い。
1:人は、目の前に見えている情報を、記号として受けとる
2:記号を解釈するためにはコードが必要となる。コードとは解釈規則のことである。
3:コードの増殖は学習であり、学習とは、ある記号を解釈することである。コードの増殖によって、新たな記号を得ていく。コードの増殖にはアブダクションが必要である。
【コラム】建築家のクリストファー・アレグザンダーによる「ツリー構造とセミ・ラティス構造の違い」
ここで思い出すのが建築家であるアレグザンダーの「都市はツリーではない」である。詳細な説明を省くが、ツリー構造よりもセミ・ラティス構造の方が好ましい、美しいという話である。
セミ・ラティスはアブダクション的で、創造的なのではないか。これもあれも、似ている!と考えていくのは楽しい!ところで、話は変わるが、そういえば、というふうに脱線していくのも楽しい!
「例えば、薬屋では医薬品ばかりではなく、はえとり紙やねずみとりなども売っていることを知る。店員は薬剤師の免状をもっていて調合も行なうことを知る。薬品は「胃薬」や「かぜ薬」といったラベルのもとに分類されて並べられていることを知る。子どもが知ったこれらのことがらは、以後、この子どもにとって「薬屋」の意味を構成するようになる。いいかえれば、これらは「薬屋」という記号の内容を構成することになる。より正確にいえぽ、これらを記号の内容面として、また、「薬屋」という物理的な音や文字を記号の表現面として、両者を互いに対応させるしかたを獲得するのである。これが、物理的な音や文字としての「薬屋」に記号機能が発生することである。このような対応関係が生じて初めて「薬屋」は記号として機能することになる。そして、この記号の表現と内容とを対応させる規則をコードと呼ぶ。コードは、記号機能を生成させる規則である。先の子どもは物理的な音や文字としての「薬屋」にどのようなことがらを内容として対応させるかを知っている。つまり、「薬屋」に関するコードを獲得している。だから、例えば本で「薬屋」という文字を見たとき、子どもはそれが何を意味するかがわかる。すでに獲得してあるコードに従って、文字としての「薬屋」を解釈する。この意味で、コードは解釈の道筋を示すものである。しかし、子どもは常に既有のコードに従って解釈すればすむというわけにはいかない。子どもは次々と新たな音や文字、新たな状況に直面する。例えば、薬ばかりではなく、化粧品や雑誌をも扱う店を見る。これは、既有のコードから逸脱している。既有のコードでは、「薬屋」は医薬品と医薬部外品のみを扱う店のことであった。このままではこの新たな状況を解釈しえない。そこで、子どもはコードを変更しなければならない。「薬屋」の内容面を拡げて、化粧品や雑誌をも扱っていても「薬屋」と呼ぶようにするか、「薬屋」とは別の表現で、内容にもっと適したものを対応させてやるかしなければならない。これは、まだコード化されていない状況に直面し、それを解釈しようと試み、それによってコード自体をよりいっそう分節的でより広い範囲の状況を処理しうるものに変えていくことである。つまり、コードを増殖させることである。このとき、既有のコードは新しい状況の解釈の手がかり(cue)として使われる。これが、学習である。学習とは、コードの増殖である。それは、新たなコードを作り出す創造的な営みである。ただし、学習は、一時的でその場限りのコード変更ではない。新たな解釈の道筋が慣習的な性格をもつまでに定着し、以後のさらに新たな状況の解釈において働きうるようにならねばならない。そうでなければ学習したということにはならない。この意味で、学習とは、今後の学習に役立ち、働きうる(Workable)ようにコードを増殖させることである。」
池田久美子 『「はいまわる経験主義」の再評価』,25P
「エーコは、このアブダクションをコード増殖の第二歩として位置づける。そして、「アブダクション」を「余剰コード化」(e×tra-cOding)という概念におきかえる。エーコはこれについて次のように説明する。「コード化されていない状況と複雑なコンテクストに直面した際」、解釈者は「一般的な規則を発明、ないしは、想定」する。この新たなコードの想定のしかたには、次の二種類がある。(1)過剰コード化(overOoding)既有のコードにもっと細かい規定を加えて分節化する。(2)過小コード化(mdercoding)信頼しうるコードがまだ存在しない場合に、大まかなコードを暫定的に想定する。この(1)(2)を総称するものが、先の「余剰コード化」である。そして、先の総督の例は(1)にあたるという。エーコはいう。「トルコの総督の場合は、パースは既成の慣習体系に基いて仮説的推論〔アプダクショソ〕の操作を行なっていた。つまり、誰かの頭の上にある天蓋が≪名誉≫を意味しているという事実は、すでに獲得された慣習の問題であって、記号機能がすでに存在していたわけである。パースは、状況に関する選択を加えることによって、コードを複雑目にしたLこのエーコの説明は、このままでは不充分である。パースが当初知っていたのは、「天蓋」が「名誉」を意味するということだけではない。「総督」が「名誉」を意味するということも知っていたのである。しかし、「天蓋」と「総督」との間にはまだ対応関係がなかった。パース億アブダクションにおいて、この両者を結びつけて新しい対応関係を作った。この新しい対応関係は、「天蓋ー名誉」と「総督ー名誉」との二つの対応関係における共通の項である「名誉」を軸にして作られたものなのである」
池田久美子 『「はいまわる経験主義」の再評価』,27P
「アブダクションによる仮説の設定から、仮説の検証に至る過程を、池田久美子が述べている「コードの増殖」の検証をとおして考える。人は、目の前に見えている情報を、記号として受けとる。その記号を解釈するためには、コードが必要となる。コードとは「解釈「規則」のことである。受けとった記号をコードによって解釈することになる。そして、新たな記号を得ることになる。……コードによって解釈できない状況に直面したときに、コード自体をその状況に合わせて広げ状況を処理できる状態に変化させていくことが、コードの増殖である……つまり、学習とは、ある情報である記号を解釈することである。その解釈にはコードが必要であり、コードを増殖させることが解釈につながるということになる。そのことによって新たな記号を得ることになる。……既有のコードでは適応できない状況に対して、アブダクションによってコードを暫定的に対応可能なコードに変化させる。そして、演繹的推論と帰納的推論を行い、暫定的なコードが確かなものとなり、コードの増殖が達成されるのである。」
米田 豊 「社会科教育における思考力・判断力・表現力の評価方法の開発 教育現場の実態把握と論理学、分析哲学、社会学、認知心理学の研究成果を組み込んで 最終報告書」,18-19P
8:他者言及とは
他者言及:・システム境界外(環境)を知覚すること、選択すること。外部参照とも呼ばれる。
なぜ環境が他者かというと、システム(自己)の外部にあるからである。社会システムの他者は生命システム、心理システムなどである。社会システム内でも、ある特殊システム、たとえば法システムにとって科学システムは他者となりうる。
ルーマンは、「社会システムは作動における閉鎖ゆえにその環境に対して開かれている」と主張している。
Q 閉じているのに開いているとはどういうことか
1:作動において閉鎖的とは、システムが自己言及的であり、他律的ではないということである。
たとえば、法的判断が科学的判断にとって代わることはできないし、生命がコミュニケーションにとって代わることもできない。それぞれ独自の論理で、自律的に動いている。それぞれのシステムが並立的に存在している。お互いに統合・融合することなく、別々のシステムとして動いている。水平的な関係性。自分(システム)の要素は自分(システム)で生み出す、自己生産的。
2:それぞれのシステムが閉じているゆえに、環境に対する「差異」が生じる。
閉じているゆえに、境界がつねに生産され、つねに差異が生じる。それゆえに、他のシステムへ開けている。
例:右翼という社会システムが、外部である左翼という社会システムを知覚することができるのは、右翼と左翼には境界があるからであり、それぞれ閉じているからである(「システムが外部を知覚する」という言い回しは、おそらく、刺激を受ける、参照する、間接的に影響を受けるといったものの類語だろうか)。
右翼的なコード、予期構造によって、右翼に関連付けて、あるいは拘束されてコミュニケーションが行われる。たとえば、伝統は大事だ、秩序が大事だ、というような文化と真逆の発言は選択される可能性、蓋然性が低い。
システムによって選択されうるものが制限される。もし右翼と左翼の間に境界がなかったら、お互いに影響を受け合うことは難しくなるだろう。そもそもお互い、ということすらいえなくなる。男女が区別されない世界では、男はこういうものだ、女はこういうものだ、というような言及がお互いにできない。区別されるから、言及ができる。田中さんの細胞が鈴木さんの細胞の作動に干渉しだしたら、お互いを違う生命システムとして区別できなくなる。
閉じるということは他のものと「区別」するということであり、「差異」をつくるということであって、切断して孤立させることではない。閉じるからこそ、他者との関係性を論じることができるようになる(開ける)。不自由が自由を生む、というジンメルの話を思い出す。
「第二に、作動における閉鎖が経験的孤立を含意するわけではないのでは、作動における閉鎖には認知における開放性がともなっているからである。ルーマンはパラドキシカルな表現を多用するが、その一つにおいて、社会システムは作動における閉鎖ゆえに(にもかかわらず、ではなく)その環境に対して開かれている、と主張している。この閉鎖こそが、システムがその環境を知覚することを可能にするのである。つまり、知覚は、つねにシステム自身の内部の諸前提に則って処理される以外にないのにもかかわらず、環境の知覚が成立するのである。たとえば、科学システムの作動における閉鎖ゆえに、法学者が法的決定を観察し、それについて科学的にコミュニケーションすることが可能になる。同様に、パンク信奉者の集団の作動における閉鎖が、彼らが自分たちの境界の向こうを眺め、環境内で起こる出来事についてあれこれ熟考しはじめることを可能にする。要点を繰り返すならば、社会システムが認知において開かれたシステムであるのは、作動において閉じているからである。作動における閉鎖がシステムの境界を自ら生み出し再生産する。つまり、システムが誕生するのは、その環境に対する差異が確立するときであるが、この差異は作動によって生み出されるのであり、システムの存立を確実にするためには作動によって再生産される必要がある。システムの要素は相互に特殊な仕方で結びついているということを先に述べたが、このことが意味するのは、作動による再生産は偶然の一致によって起こるのではないということである。作動による再生産は、ルーマンが自己組織という概念で記述する構造的な仕組みに従ってなされる。自己組織的なシステムであるということが含意するのは、作動の場合と同じ用に、構造はシステムの内部で生み出されるのであって、外部から取り入れることはできないということである。ルーマンは、作動と構造の間で一定の循環関係が問題になることを十分自覚している。」
クリスティアン・ボルフ「ニクラス・ルーマン入門」,56-57P
「オートポイエティック・システムの要素は、システムの外部にあらかじめ存在しているものではなく、システムによって「構成」されるものだと捉えられる。システムの要素はそのシステムのなかでのみ意味をもつ単位体なのである。要素は、システム境界の外(環境)への「他者言及の選択」と、システム自身への「自己言及の選択」、そして、その「二重性の結合の選択」という三つの選択がすべて生じたときに創発する。」
井庭崇「 創造システム理論の構想」,12P
選択とはいったいなにか
井庭さんは、「要素は、システム境界の外(環境)への他者言及の選択と、システム自身への自己言及の選択、そして、その二重性の結合の選択という三つの選択がすべて生じたときに創発する」と説明してる(これが難しい)。
ここでいう「選択」は、誰(主体)が選び取るという意味合いではなく、多くの可能性の中から結果として選ばれたという意味合いだという。つまり、意思決定ではない。「可能性の中からあるものが残った」という意味合い。人間の側から説明するのではなく、コミュニケーションの側から説明していく。あえていうならば、自然選択における選択のイメージだという。なかなか難しい。主体は心理システムが扱うのだろうか。
 たとえばキリンは自ら主体的に選んで首ががなくなったというより、なんらかの条件によってそのように選ばされた、というイメージだろうか(決定論ではないが、かといって完全なランダムではなく、ある程度絞られた中から残っていくイメージだろうか。たとえば首が長くなる以外に、足が長くなるという道もあったかもしれない??)。
たとえばキリンは自ら主体的に選んで首ががなくなったというより、なんらかの条件によってそのように選ばされた、というイメージだろうか(決定論ではないが、かといって完全なランダムではなく、ある程度絞られた中から残っていくイメージだろうか。たとえば首が長くなる以外に、足が長くなるという道もあったかもしれない??)。
「注意が必要なのは、ここでいう「選択」とは、誰か(主体)が「選びとる」というニュアンスではなく、多くの可能性のなかから「結果として選ばれた」というニュアンスで用いられている。このニュアンスは、進化における「自然選択」(naturalselection)の「選択」を思い出すと、わかりやすいだろう。多くの生物種がいるなかで、弱い生物は淘汰され、それ以外の種が残るとき、残った種が「選択された」と言われるわけである。同様に、創造における三つの選択でも、「誰が選択したのか」という視点ではなく、可能性の中からどれかが残った=「選択された」と捉えることが重要となる。システムは、要素の生成・連鎖という作動の面では「閉じている」が、他者言及によって環境に「開かれている」。この「閉鎖性」と「開放性」の相補的関係に、従来の「インプット/アウトプット図式」とは異なるシステムの在り方が示されているのである。」
井庭崇「 創造システム理論の構想」,12P
「生物は太陽を必要とするが、生物は太陽の光でできているわけではない」
・井庭さんがわかりやすい比喩として、「生物は太陽を必要とするが、生物は太陽の光でできているわけではない」と言っていた。人間は社会システムにとって太陽のように必要不可欠な存在であるが、社会システムは人間でできているわけではない。
人間は太陽を必要とする。しかし人間は太陽でできていない。社会は人間を必要とする。しかし社会は太陽でできていない。太陽から刺激を受けるが、太陽でできていない。それぞれ、独自の論理で、自律的に作動している。人間は社会の部品ではない。太陽は人間の部品ではない。社会の部品はコミュニケーションのみである。
「『要素ではないが必要不可欠である』ということは、『生物は太陽の光がなければ生きていくことができないが、生物は太陽の光でできているわけではない』ということと同様である。社会システム理論において、主体や人間が『環境に位置している』といわれるのは、このような意味に置いてなのである。また、区別するということは切断して孤立させることではない。区別することで初めて、その区別されたもの同士の関係性を論ずることができるようになるという点は、ルーマンの理論を理解するうえで重要である。つまり、社会を人間と区別されるものとして描くことで初めて、人間と社会との関係を正面切って論じられることになるのである。」
井庭崇、他「社会システム理論」,34P
三つの選択が継起的に生じるということは、本来生じにくいことである
1:他者言及の選択、自己言及の選択、そしてそれらの組み合わせの選択が次々と生成されなければ、システムはなくなってしまう。
2:三つの選択が継起的に生じるということは、本来生じにくいことである。ありえるようにするためには、「メディア」が必要だという。たとえば言語もそのひとつである。日本語を母国語としているだけで、どういった選択がされるのか、ある程度拘束される。つまり、複雑性が縮減される。ルーマンによると、こうした「メディア」は進化的な獲得物であり、偶有的な選択が積み重なると、コンテクストをつくり、歴史性を帯びるという。確かに、言語をもたない人間同士が社会を形成することは、より難しくなると直感的に理解できる。
「いま述べてきたのように、《発見》は、三つの選択が総合されなければならないため、本来生じにくいものである。そのため、《発見》が生成・連鎖し続けるためには、それを下支えする“何か”が必要となる。そのような支えのことを、《メディア》――より厳密に言えば、《発見メディア》――と呼ぶ。《発見メディア》にはいくつかの種類が考えられる。第一に、数学やパターン・ランゲージ等の言語や、概念・理論などが考えられる。これらは、《アイデア》の選択と《関連づけ》の選択における複合性を縮減することで、《アイデア》の選択と《関連づけ》の選択が生じやすくなる。」
井庭崇「 創造システム理論の構想」,16P
ルーマンによるとコミュニケーションメディアは3種類ある
- 言語:コミュニケーションの相手が何を考えているのか知ることを可能にしてくれるメディア。言語、ボディ・ランゲージ、芸術表現など。
- 流布メディア:時間や空間を越えてコミュニケーションが成立することを可能にしてくれるメディア。文字や印刷技術、通信技術など。
- 成果メディア(象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディア):コミュニケーションの連鎖がしやすくなる条件付や動機づけを行うメディア。真理、愛、権力、貨幣など。
・相手が何を考えているのか、完全に知ることなどできない
・コミュニケーションが一方がすでに生命的に死んでいても成立する。アリストテレスと私の間にコミュニケーションが生じうる。というより、神も木々も、ボールペンでも、意図があると理解すればコミュニケーションはありうる。
・受け容れられる=前提として踏まえられる
・コミュニケーションへの「接続能力」という概念はポイント
・「象徴的」=コミュニケーションの関与者たちの差異を架橋する
・「一般化」=さまざまな状況に対応している
「ルーマンによれば、コミュニケーション・メディアには、大きく分けて三つの種類があるという。一つ目は、コミュニケーションの相手が何を考えているのかを知ることを可能にしてくれるメディアである。そのようなメディアを、社会システム理論では『言語』と呼ぶ。ここでいう言語は、日本語や英語といった自然言語はもちろん、ボディ・ランゲージや芸術表現なども含む広い意味での言語である。そのような言語の存在があって初めて、コミュニケーション相手が考えていることを多少なりともつかむことができるようになる(もちろん、完全に知ることなどできない)。つまり、《情報》と《伝達》を《理解》することができるようになるのである。」
井庭崇、他「社会システム理論」,20P
「コミュニケーション・メディアの二つ目は、時間や空間を越えてコミュニケーションが成立することを可能にしてくれるメディアである。そのようなメディアを、社会システム理論では、『流布メディア』と呼ぶ。これには、文字や印刷技術、通信技術などが含まれている。太古の昔は、その場にいる人同士でなければコミュニケーションは成り立たなかったが、文字や印刷技術の発明によって、その場にいない人でもコミュニケーションに参加することが可能となった。いま本書を読んでいるみなさんは、私がこの文章を書いているときに、その現場(私の書斎)にいるわけではない。しかし、ここに書いた内容(情報)を、ある意図で提示(伝達)しているのだと考える(理解)ことで、時間と空間を越えたコミュニケーションが生じることになる。このコミュニケーションは、の文章を書いている時点ではなく、みなさんが読んでいる時点で──あなたが読んでいるまさに今この瞬間に!──生じている。」
井庭崇、他「社会システム理論」,20P
「コミュニケーションの3つ目は、生じたコミュニケーションが受け容れられる可能性を高めるメディアである。コミュニケーションを受け入れるというのは、そのコミュニケーションが、その後のコミュニケーションの前提として踏まえられるという意味である。《情報》と《伝達》が《理解》されたとしても、それだけでは、次のコミュニケーションにつながるとは限らない。《情報》と《伝達》が《理解》されたが、無視されることもあり得るからである。そのような場合には、コミュニケーションは単発で終わり、次のコミュニケーションへの接続能力をもたないということになる。そのような事態に陥らずに、コミュニケーションの連鎖がしやすくなる条件づけや動機づけを行うメディアsを、ルーマンは『成果メディア』、もしくは『象徴的に一般化されたコミュニケーション・メディア』と呼んだ。『象徴的』というのは、コミュニケーションの関与者たちの差異を架橋するということを意味し、『一般化』というのはさまざまな状況に対応していることを意味している。」
井庭崇、他「社会システム理論」,21P
川を構成する要素とはなにか(実体か、生成か)
1:観点の変更は創造において重要になる
2:ルーマンは、実体よりも生成を重視した。
3:いままでの社会学者は社会を「主体や行為の集まり」と捉えていたという。井庭さんのたとえでは、たとえば酸素原子と水素原子があつまり、それらが水であり、それらの集まりが川であると捉えているイメージ。しかしこうした捉え方、つまり実体的な捉え方では、「川というものをスナップショット写真で切り取ったような捉え方であり、川のダイナミックな側面を上手く捉えることができていない」という。
なんとなく芸術とにている気がする。絵画は一瞬を切り取る。しかし流れも同時に表現できたら、より素晴らしいものになるのかもしれない。
4:水が本質ではなく、流れこそが本質である、という点が重要になる
5:社会システムも同様に、それぞれの個人や心理が本質ではなく、流れ=「コミュニケーションの連鎖」が重要になる。この場合、個人や心理は、コミュニケーションの連鎖の外部であり、別のシステムである。
6:こうして、社会はコミュニケーションだけから構成される、という意味が少しずつ理解できてくる。
「しかし、川が水で構成されているという捉え方は、川というものをスナップショット写真で切り取ったような捉え方であり、川のダイナミックな側面をうまくとらえているとは言い難い。そこで、これとは異なる新しい捉え方で考えてみることにしたい。それは、川は『水が流れる』ところであり、『流れ』こそが本質的に重要だとする捉え方である。『水が流れる』の『流れる』に注目してみるのである。川の構成要素は『流れ』であり、川とは絶えず新しい流れが生み出されるものであると捉える。流れが流れを生むという、流れの連鎖をイメージするのである。」
井庭崇、他「社会システム理論」,9P
7:あらゆるシステムの本質は、流れである。
社会はコミュニケーションの流れであり、心理は意識の流れである。さらに社会は複数の機能(機能システム)に分化し、相互に依存していく。
たとえば経済システムは支払い/非支払いというコード、貨幣というメディアによって、その特殊なコミュニケーションの連鎖によって維持されていく。もし誰も支払わないようになれば、コミュニケーションはなくなり、経済システムは消滅する。川の流れが途絶えれば、川は消滅する。完全に干上がった川を川というだろうか。お笑い芸人は面白い/面白くないというコードだろうか、というように(コードを増殖させて)考えてくのは面白い。
ヘラクレイトスと流れ
あらゆる本質が流れである、という考え方は面白い。万物は流転するというヘラクレイトスの言葉を思い出す(ヘラクレイトスも川のたとえを使用していた)。万物の本質は流転である。自分が気になる現象、切実な問題を解決するために、一度、固体的な発想から生成的な発想に切り替え、どういう連鎖が生じているのか、と考えてみるのは面白い。こうして現象に対するコード例を学習していく。
では、創造にはどのような流れがあるのか、と考えていったのが井庭さんであり、社会システムとは異なる、独立した閉じたシステムとして、創造システムを考えていく。
個人的には選択の可能性を拘束するような”健全な”メディア、文化、世界観、コードのようなものがあるとすれば、どういうものかという点が気になる。
ルーマンの社会システム理論によって、現代社会はこのようなメディアによって、このようにシステムが維持されている(秩序の成立)、ということは分析できるのかもしれない。
そこからさらに、世界を安定させるようなメディアのあり方、コードのあり方、文化のあり方とはなにかという点が重要ではないか。たとえばベイトソンは西洋の文化を批判し、バリ島の文化を肯定している。コミュニケーションの連鎖によって、システムが暴走しないようなネットワークのあり方とはなにか。
井庭崇さんの創造システム理論とはなにか
創造システム理論とはなにか、意味・解説
創造システム理論:・創造を、「発見を要素とするオートポイエティック・システムである」と捉える理論のこと。
発見:・世紀の大発見というような大文字のDiscoveryではなく、創造のなかでの「気づき(小文字の発見)」に近いという。問題発見、問題解決、観察、仮説形成、実践、解釈など。
井庭さんがルーマンの社会システム理論を、創造システムへと特定化して考えて構築した理論。
1:ルーマンは「コミュニケーションは情報と伝達が理解されたときに創発する」と考えた
2:井庭さんは「発見はアイデアと関連付けが見出されるときに創発する」と考えた
3:あるアイデアを思いついて、それが今まさに作ろうとしているものと関連付けられるということが見出されるときに、それは発見となる。
4:発見が次々とつながることで、創造が実現する
5:創造とは、発見という要素を次々と生成・連鎖させることである
6:どのような発見が要素となりうるかは、個々の創造システム、連鎖のネットワークに依存している→今まで獲得してきたコードなどにもよるということだろうか
「創造システムは、《発見》(discovery)を要素とするシステムであり、その要素(《発見》)はそのシステムを前提として構成される。それでは、《発見》という要素はどのように成立するのであろうか。創造システム理論では、《発見》を、《アイデア》(idea)、《関連づけ》(association)、《帰結》(consequence)という三つの選択の総合によって生じる創発的な統一体(unity)と捉える。すなわち、いま進行している創造プロセスにおいて、ある《アイデア》の、ある《関連づけ》を《適用》することによって《発見》が成立すると捉えるのである。この三つの選択のうちのひとつでも欠けていると、《発見》は成立しない。」
井庭崇「 創造システム理論の構想」,15P
創造の観点からは、発見が「誰」の「どのような」貢献によって生成されたのかということは重要ではない
創造を誰が担ったのかは二次的な問題である。また、偶然から発見したのか、熟考から発見したのか、他者との会話からか、独力かなども二次的である。
また、そうした発見が有用かどうか、真実であるかということとも関係がないという。重要なのは次なる発見への接続能力であるという。なかなか面白い。こうした接続能力が創造性に近い。マトリックスのキーメーカーを思い出す。
・ポイントは、「次なる発見への接続能力」
「《発見》が誰のどのような貢献によって生成されたのか、ということは、創造の観点からは重要ではない。それは、熟考によってもたらされたかもしれないし、一種のひらめきによるか、あるいは、偶然によるものかもしれない。そして、それは自分で考えただけでなく、他のだれかのアドバイスによるものかもしれないし、複数人でのコラボレーションの結果であるかもしれない。創造システムの観点から見て本質的なのは、《発見》の生成・連鎖が実現することであり、それを誰が担ったか等は二次的な問題にすぎない。しかも、《発見》の内容は、真実であるとかや有用であるとかいうことは関係がない、という点である。ここで問題となっているのは、次なる《発見》への接続能力であり、たとえ、途中段階のある《発見》の内容が間違ったとしても、次成る《発見》への連鎖が成立すれば、それはその創造において機能したといえるのである。」
井庭崇「 創造システム理論の構想」,15P
創造的なプロセスの本質=パッと広がる
・創造的なプロセスの本質は、「いろいろな選択肢の領域がパッと広がりつつ、選択され収束し、また選択肢がパッと広がる、そういう運動性を持ったプロセス」だという。
コミュニケーションは基本的にコンティンジェントな状況の中で生じる。常に他でありうるからといって、まったくでたらめなわけでもない。決定論的に決まっているわけでもない。
たとえば社会学の知識だけならば選択肢の領域は狭いかもしれない。そこに生物学の知識が入ってくれば、選択肢の領域が広がる。他でありうるような要素が選択肢のひとつとしてはいってくる。あるいは、思いがけぬ事件、たとえばカラスが目の前にいたとか、そういう現象でも選択肢が増えたりする。
創造的なプロセスの本質は、「いろいろな選択肢の領域がパッと広がりつつ、選択され収束し、また選択肢がパッと広がる、そういう運動性を持ったプロセス」だという。
コミュニケーションは基本的にコンティンジェントな状況の中で生じる。常に他でありうるからといって、まったくでたらめなわけでもない。決定論的に決まっているわけでもない。
たとえば社会学の知識だけならば選択肢の領域は狭いかもしれない。そこに生物学の知識が入ってくれば、選択肢の領域が広がる。他でありうるような要素が選択肢のひとつとしてはいってくる。あるいは、思いがけぬ事件、たとえばカラスが目の前にいたとか、そういう現象でも選択肢が増えたりする。
【井庭】「僕が何かを話したとき、そのどこを《情報》として認識するのか、どういう意図で《伝達》したと《理解》するのか。それには、いろいろな取り方がありえます。そういう『別様でもありえる』ことをコンティンジェント(偶有的)であると言います。生じることが不可能ではありませんが、必然的に何かが決まっているわけでもありません。このように、コミュニケーションというのは、コンティンジェントな状況のなかで何か一つの組み合わせが『選択』されるということに他なりません。そのコンティンジェンシーの中に創造性が宿りうるわけであす。決定論的に道筋が決まっているわけではないけれども、まったくのでたらめでもない。それは、いろいろな選択肢の領域がパッと広がりつつ、選択され収束し、また選択肢がパッと広がる。そういう運動性を持ったプロセスになる。それこそがまさに、創造的なプロセスの本質だと思うんです。」
井庭崇、他「社会システム理論」,210P
発見が生成・連鎖し続けるためには、それを下支えする「発見メディア」が必要となる
井庭さんは発見メディアを三種類に分けている
(1)数学やパターン・ランゲージ等の言語や、概念・理論
→アイデアの選択と関連付けの選択における複合性を縮減することで、アイデアの選択と関連付けの選択が生じやすくなるという。これは外部からの決定ではなく、選択肢の支援である。社会学理論などもここにあたるのではないだろうか。
(2)観察のためのツールやシミュレーションやデータ分析のツール
例:顕微鏡やコンピューター、統計解析など
アイデアの関連付けによって帰結が得られることを支援してくれるという。
人間が行うと途中で諦めてしまいたくなるような長い道のりを支援してくれるという。
(3)発見が現行の創造にとって意味・意義があると捉えやすくする象徴性
例:「科学」や「芸術」などによる色付け
「象徴性」というように、成果メディアが関係してくるのかもしれない。たとえば、芸術の場合は、美に意義があり、科学の場合は真理に意義がある。美しいアイデアを発見した場合、いまは連鎖の段階にあるとおぼろげに確信しつつ、進めるのかもしれない。自分が今までしてきた、発見の連鎖には意義がある、と捉えやすくするためには、見本のような、手がかりのようなものが必要となるイメージだろうか。たとえば、井庭さんが「失敗も成功と同じように機能する」と言えば、そうか、私のなんらかの創造にとって、ある発見は失敗・成功に関わらず意義があるんだ、と思えるようなケース。
「いま述べてきたのように、《発見》は、三つの選択が総合されなければならないため、本来生じにくいものである。そのため、《発見》が生成・連鎖し続けるためには、それを下支えする“何か”が必要となる。そのような支えのことを、《メディア》――より厳密に言えば、《発見メディア》――と呼ぶ。《発見メディア》にはいくつかの種類が考えられる。第一に、数学やパターン・ランゲージ等の言語や、概念・理論などが考えられる。これらは、《アイデア》の選択と《関連づけ》の選択における複合性を縮減することで、《アイデア》の選択と《関連づけ》の選択が生じやすくなる。」
井庭崇「 創造システム理論の構想」,16P
「第二に、観察のためのツール(例えば顕微鏡)、シミュレーションやデータ分析のツール(例えばコンピュータ)、そして各種の表現ツールなども、《発見メディア》として機能する。これらは、《アイデア》の《関連づけ》によって《帰結》が得られることを支援してくれる。例えば、コンピュータ・シミュレーションは、複雑な関係性にもとづく計算を行うことで、それなしでは得にくい帰結を手元にもたらしてくれる。」
井庭崇「 創造システム理論の構想」,16P
「さらに第三に、《発見》が現行の創造にとって意味・意義があると捉えやすくする象徴性、すなわち、「科学」や「芸術」というような色づけも《メディア》としてはたらく。生じた《発見》を受け入れるかどうかは、それが科学であるか、芸術であるかによって異なってくる。このような三種類の《メディア》が、それぞれに《発見》の生成の不確実性を克服するために貢献する。かくして、創造そのものをデザインすることはできないが、《発見メディア》をデザインすることで創造を支援する可能性について議論できるようになる。」
井庭崇「 創造システム理論の構想」,17P
社会システム理論は「創造的であるとはどういうことか」を説明することはできない。
だからこそ、創造システム理論が重要になる。
井庭さんによると、ルーマンの社会システム理論では創造的なコミュニケーションが連鎖します、というところまでは言えるという。コミュニケーションに創造的というフレーバーがついている、というかたちでしか理解できないという。
また、KJ法やブレインストーミングなども、コミュニケーションの観点からみたコラボレーション論としてはよいけれども、創造理論には成りえていないという。
創造的なプロセスはその本質にコンティンジェンシーをもつ
たとえば創造性の源は偶有的な事態であるため、特定できないという。アイデアXを通しても、アイデアYを通しても、同じアイデアZに至るということはありえる。アイデアXでなければ絶対にありえないということがない。他に同じ機能を有するなにかが常にありうる。
たとえばある発見に至るための方法は、演繹かもしれないし、帰納かもしれないし、メタファーかもしれないし、偶然かもしれない。
ルーマンの理論だったかもしれないし、ベイトソンの理論だったかもしれないし、あるいはパーソンズの理論だったかもしれない。これがなければ絶対に次の発見が生じなかった、という源を探るのは難しい。他でもありえた、というのが偶有性であり、機能的に等価なものが常にあるというわけである。こうした偶有性と、創造性における「一つの問題と複数の解答」は連なってくる。
ひとつしかありえない、という凝り固まった考え方を崩していく。1+1=2ですら、経験的に確証できない公理を前提とした演繹にすぎないので、別の公理もありうるかもしれない。このあたりはパラダイムシフトやマンハイムのイデオロギーとも関係してくる。
【基礎社会学第三十一回】カール・マンハイムの「イデオロギー」とはなにか
失敗は成功の母
また、振り返ってみたら最終的に間違ってたアイデアが、次のアイデアが生じるためには必要だった、ということがあるという。どんなアイデアも問題解決にとって不必要かどうかは、振り返ってみなければわからない。言われてみればそうだ。
このあたりはワクワクして面白い。絵を描いているときも、最初の汚い線が次の美しい線を生むこともあるかもしれない。この動画の価値は現在も決まっていないし、1年後にも決まっていないかもしれない。10年後、あるいは50年後に誰かの頭の中で花が咲くことがあるかもしれない。失敗を恐れない気持ちは大事だ。この動画で一番重要だと感じた要素である。仮に間違った説明であったとしても、「これ間違ってたよね」という連鎖を生むために、記憶に残ることもある。あるいは新しいアイデアに導くこともある。
そもそも正誤はその文化の前提(公理)に基づいていて、別の文化では正しいと思われる場合もある。論理的に正しいことすら、別の文脈では誤りになりうるかもしれない。ただし、相対主義を越えて、正誤や善悪を越えて共通する何かはあると信じたい。
「創造性について考えたい第二の点は、創造的なプロセスがその本質に偶有性(コンティンジェンシー)をもつという点である。たとえば、ある発見や発想に至るための方法は、演繹や帰納、アブダクション、アナロジー、メタファー、閃き、あるいは単なる偶然など、非常に多岐にわたる。そのため、創造性の源を探ろうとしても、それは偶有的な事態であるため、特定できないだろう。また、創造プロセスには、たいてい一つではなく多くの発見によって成り立っている。そこには、よいアイデアもあれば、最終的には間違っていたことがわかったが、必要不可欠だったというものもある」
井庭崇「 創造システム理論の構想」,4P
最初に浮かんだアイデアは必ずしも優れたものとはかぎらない
キース・ソーヤーという人によれば、最初に浮かんだアイデアは必ずしも優れたものとはかぎらないという。しかし、次々とアイデアが連鎖していく中で、最初のアイデアが思いもかけない別の意味を帯びてくるという。
たとえばパーソンズの理論を問題解決として利用するという選択が間違っていたとしても、パーソンズを学んでいたからこそ、ルーマンの理論を理解できた、あるいはパーソンズとルーマンの意外な共通点を発見し、そこから両者の理論を超える理論を構築できた、というのもありえなくはない。ルーマンもパーソンズの理論を学んだことで、それとは違った方向へ進むことができたのかもしれない。
創造的な営みをしている人は、創造的である
最初は何を言っているんだ、と感じた。同義反復(トートロジー)じゃないのか、と。
- 従来の考え方:創造性をもつ人が、創造的営みができる
- 創造システム理論での考え方:創造的な営みをしている人は創造的である
・なにか禅問答のような、モヤッとした霧が頭の中にかかる思いがする。しかしそのなかでもすこし、光が見えてくるものもある。
「創造性をもつ人」というと、頭の中で何が起こってるか、心理的、個人的な、いわゆる「天才」だとか「脳のできが違う」だとか、そういった問題をイメージしやすい。そういった「見えづらさ」を一旦切り離し、創造プロセスそのものを考えていく。
天才が創造的な行為をするのではなく、創造的な行為をしている人が天才的なのである。ということは、創造的な営み、行為をしていない人は、天才的ではないし、また天才とは必ずしもいえない。固定的な性質に注目するのではなく、生成する動的なプロセス、行為、実勢に目を向けていく。
ここで重要になるのが「創造的な営み」であり、これは「発見の連鎖」とされている。次々とアイデアが今取り組んでいる創造システムに関連付けられていき、その結果、新たな発見が生じていく。また、アイデアは他者言及的であり、関連付けは自己言及的、そしてその組み合わせによって帰結が生じ、発見へと至る。
こうした発見の連鎖が次々と起こっている状態が創造であり、そうした行為を起こせる人は創造性があり、またその連鎖が多いほど、創造性が高いといえる。ここではそうした連鎖が真かどうか、社会的に有用かどうかは関係がない。次々と連鎖していくことが重要である。
こんなものを関連付けるのか!!!といったような意外性は、社会システムなどを前提としているのだろう。他者との比較がなければ、斬新だとか、ありきたりだとか、そういう価値判断は生じない。どのようなアイデア、関連付けに関わらず、連鎖していることが重要なのだろう。
そうした閉鎖的な創造性と、社会システムの関わりはどうなのか、あるいは生命システムとの関わりはどうなのか、といった議論も可能である。ただし、創造性とはなにかを、創造システム単独で、閉鎖的に議論することが意義があり、おもしろい。閉鎖的だからこそ、周りと関連付けることができる。斬新かどうか、生産的かどうかなども、その特定の社会のコードによって意味があるかもしれないし、意味がないかもしれない。
「従来は、「創造性をもつ人が、創造的営みができる」という人を中心とした捉え方であった。そうではなく、「創造的な営みをしている人は創造的である」というふうに捉えたいのである。」
井庭崇「 創造システム理論の構想」,6P
【コラム】ベイトソンとトートロジー
ベイトソンは「説明とは記述の断片をトートロジーへマップすることである」と言っていた。このトートロジーを受け入れる意思が我々にある限り、その説明は意義がある。ちなみにアブダクションもトートロジーへのマップである。このトートロジーを受け入れることでなにか役立つなら、どんどん受け容れていこうと思う。
Pならば、Pは真であるというトートロジーにおける「ならば」と決めたのはデータではなく、我々である。たとえば「2点を結ぶ直線はただ1本存在する」という幾何学の第一公理は、データから決められたものではない。我々が、経験的に証明せずに、そうであると前提をおいたのである。
そうした前提を認めるならば、さまざまな事柄が演繹される。(もし)神がいるならば・・・、重力があるならば・・・、美があるならば・・・真理があるならば・・・本能があるならば・・・命が尊いならば・・・。トートロジーに基づいて説明が作られていく。
M・ウェーバーで言うと、学問の職分につながってくる。
たとえば美学は芸術品があること、社会科学は文化現象に知る価値があることを、医学は人の命は維持されるべきものであるということを前提としているが、この前提は学問的手続きによって論証できない。
ウェーバーは「正しい問い方をするものにたいしてはなにか別のことで貢献するのではないか」と言っていたが、これも連鎖の一つではないだろうか。美があるか、真理があるかと問いをたてたり、あるいはそれらがあると信じていることが、美や真理の発見につながらないとしても、しかし「別の何か」にはつながっていく。それらが人類にとってプラスなのか、マイナスなのか、安定をもたらすのか、破滅をもたらすのか。真理を求めた結果、核兵器を創り出していくのか。
「以上のような学問の意義に関する諸見解、すなわち『真の実在への道』、『真の芸術への道』、『真の自然への道』、また『真の幸福への道』などが、すべてかつての幻影として滅び去ったこんにち、学問の職分とはいったいなにを意味するのであろうか。これにたいするもっとも簡潔な答えは、例のトルストイによって与えられている。かれはいう、『それは無意味な存在である。なぜならそれはわれわれにとってもっとも大切な問題、すなわちわれわれはなにをなすべきか、いかにわれわれは生きるべきか、にたいしてなにごとをも答えないからである』と。学問がこの点に答えないということ、これはそれ自身としては争う余地のない事実である。問題となるのはただ、それがどのような意味で『なにごとも』答えないか、またこれに答えないかわりにそれが、正しい問い方をするものにたいしてはなにか別のことで貢献するのではないか、ということである。」『職業としての学問』42-43P
トートロジーについては前回の記事を参照
システムと無関係な要素はない
- 従来の考え方:要素が先に独立にあり、そこからシステムを考えていく。
- 社会システム論の考え方:まずシステムがある。システムに基づいて要素が構成される。
→まず創造システム(創造)がある。創造システムに基づいて、発見が構成、生産されていく。
まず鶏が先だということを我々が受け入れる。どちらが先かは経験的に、あるいは論理的に証明できないかもしれないけれども、現実には鶏がいて、卵を産んでいる。それを元に生態はなりたち、経済はなりたっている。
鶏が卵を産んでいるならば、それは排卵的なのである。システムが要素を構成し、要素がシステムを構成していく。どちらが先かは形式論理学的にはわからないけれども、循環的に内部でそれらは閉じている。
ニワトリだってセキショクヤケイからの進化であり、セキショクヤケイは構造をもっている。それぞれ別の生命システムではある。生命システムの起源、日本の社会システムの起源、文化の起源、そういう起源を考えていく、つまり最初の鶏を考えていくと頭が疲れる。既存のシステムに無関係なシステムなどあるのか。それらの関係は浸透や依存、刺激のうけあいという言葉で説明しつくせるのか。このあたりがよく理解できていない。独立したシステム同士の関係についてルーマンをさらによく学ぶべきだと感じた。
フッサールで自我に関する無限の遡及の話があったが、それと似ていて思考がモヤモヤする。神が最初に神秘の力でまずシステムを作った、そこからいろいろなシステムが分かれ、発展(複雑化)していったといえばどんなに楽なのだろうか。いやそんなことは考えずに、とりあえず今目の前にある社会は、循環的関係にあるが、その起源ついては隅においておくと考えればいいのか。
「システムを構成する要素が、システムに先立って存在するのではなく、システムの存在があって初めて構成され得るということであり、システムと要素はいわゆる「鶏と卵の関係」にあることになる。」
井庭崇「 創造システム理論の構想」,12P
「従来のシステム論では、要素の結びつきがシステムであると考えてきた。パーソンズの社会システム論もそうだ。この場合、要素はシステムの成立以前から存在し、その存在を前提にシステムが成立する。つまり、システムが成立しなくても、要素それ自体のあり方は変わらない。たんに『要素』と呼ばれないだけだ。それに対して、自己産出では、要素のあり方がシステムのあり方に依存し、システムのあり方が要素のあり方に依存する。そういう循環論的な関係がある。その意味で、自己産出は再帰的なネットワークをなす。したがって、もし社会のなかに自己産出的なしくみがあるとしたら、そこにも同じような循環的な関係が見られるはずだ。」
佐藤俊樹「社会学の方法」,340P
「まとめていえば、行為の結びつきと見なされてきた事象が①要素のネットワークによって要素が新たに産出され、その新たな要素の意味があたえられるだけではなく、その新たな要素が加わることで他の要素の意味内容も変化し、それゆえ全体としての[内=自己]の意味が変化して、それがさらなる新たな要素の産出のあり方にも影響する、という関係がある。②この[内=自己]が『システム』と呼ばれてきたような要素ー全体関係になっている、と了解されている。」
佐藤俊樹「社会学の方法」,342-343P
作動と構造の間で一定の循環関係があるとは
・構造はシステムの内部で生み出され、外部から取り入れることはできない。作動は構造を必要とするが、構造は作動の結果である。タマゴは鶏を必要とするが、鶏はタマゴの結果である。
例:言語(構造)と話すこと(作動)の循環的関係
1:言語が存在しなければ、話すことはできない
2:誰も言語を話すことがなければ、言語は存在できない
3:言語は話をすることによって産出され、話をすることは言語によって産出される。
「たしかにそうだ!」、と、よく考えれば「どういうことだ?」が繰り返される。なぜどういうことだ?と思ってしまうのかを理解したい。
【井庭】「僕はこのような見方で、ルーマンの社会システム理論をベースとして、創造的なコラボレーションについて考えてきたわけです。でも、数年前、このまま進んでいっても僕が知りたいことはわからないな、と考えるようになりました。最後の最後で、最も重要な問いに応えることができない、と気づいたのです。最後に残る重要な問いというのは、何かと言うと、それは創造的であるとはどういうことか、という問題です。ルーマンの社会システム理論では、創造的なコミュニケーションが連鎖します、ということまでは言えるけれども、創造的であるとはどういうことかや、創造とは何か、という話は抜け落ちてしまうと感じたんですね。いうならば、コミュニケーションに『創造的』というフレーバーがついているというかたちでしか理解することができない。修飾的なかたちでしか語ることができないと気づいたのです。そして、僕が本当に探求しなきゃならないのは、創造的であるとはどういうことか、創造とは何かという直球の問いのはずだ、と考えたのです。たとえばですね、アイディア構築の方法論に、ブレインストーミングやKJ法というのがありますね。これらは、グループで使う場合に、コミュニケーションの連鎖をうまく引き出すうまい仕組みが含まれています。実際に導入してみると、うまくいくときもあれば、うまくいかないときもでてきます。たしかにコミュニケーションの連鎖はできているんだけど、それが創造的にならないということも起きるのです。そういう事例をみるにつけ、コミュニケーションの観点からみたコラボレーション論としてはよいけれども、創造理論には成りえていない、ということを感じていました。社会システム理論は社会過程を見るための理論なので、社会過程がうまく捉えられていれば十分なわけで、創造性の話までさせようというのは、そもそも酷な話だということはあるとおもいます。」
井庭崇、他「社会システム理論」,212P
発展論理
個人的にまず整理しておきたいのは言語(A)によって話すこと(X)が産出される、Xによってさらに言語が産出されるが、この言語はAではなく、新たなBである。これが、システムがつねに生成しつつあるということである。
別の言葉で言えば、要素と構造の相互関係は固定的事象ではなく、複雑な発展論理に服する事象であるという。たしかに、AによってXが生じ、XによってAが生じ、というように考えていくのが形式論理学的だといえる。しかし実際には、AによってX、XによってB、BによってY、YによってCと発展していく。Bから考えてけばいいんじゃないか、と思ったりもする。
ルーマンは、「最小限の構造を要求するだけの作動がやがて複雑な構造を自ら生み出し、その構造がより差異化した作動の可能性を開く、というふうに発展していく」という。
最小限の構造を要求するだけの作動は、最小限の構造から産出されたのだろうか。最小限の構造はいったいどこからきたのだろうか。原初的には、ほとんど同時に両方がパッと現れたんじゃないだろうか。要素であり、集合である「なにか」がパッと現れたのである。そういう論理階型の混同は現実にはありうるのである。頭(論理)で考えてもよくわからない。因果で考えていく。しかし因果で考えていくと、因果の起源に至り、混乱してしまった。因果の果ては人類の消滅やらなんやらでシステムが完全に消えるというのは理解できるが、因果の起源は難しい。しかしそれでも、神がビリヤードで最初に玉を突くように、最初の刺激をつくったと考える訳にはいかない。
「自己組織的なシステムであるということが含意するのは、作動の場合と同じように、構造はシステムの内部で生み出されるのであって、外部から取り入れることはできないということである。ルーマンは、作動と構造の間で一定の循環関係が問題になることを十分自覚している。つまり、作動は構造を必要とするが、当の構造は作動の結果である。ルーマンは具体例として言語(構造)と話をすること(作動)の関係を挙げている。言語は話をするための前提条件である。もしも言語が存在しなければ、話をすることもありえず、仮にあるとしても、せいぜい音声と音声と発する行為だけであろう。同時に、言語は話をするという作動によって産出される。もしも誰も言語を話さなければ、言語は崩壊してしまうだろう。このように言語(構造)と話をすること(作動)とは相互につくり、つくられる循環的関係にある。この相互構成は固定的事象ではなく、複雑な発展の論理に服する事象である。ルーマンはつぎのように主張する。システムは、実際には、最小限の構造を要求するだけでの作動にもとづいて発展していく。つまり、最小限の構造を要求するだけでの作動がやがて複雑な構造を自ら生み出し、その構造がより差異化した作動の可能性を開く、というふうに発展していくのである。」
クリスティアン・ボルフ「ニクラス・ルーマン入門」,58P
その他、感想
・自分なりの消化した要素、残すべきフックを羅列していく。
1:創造とは「発見の連鎖」であるという井庭さんの定義が一番面白い。
個人の心理や社会と切り離して、閉じたシステムとして考えていく。切り離すことで、それらとの関係を扱うことができる。個人の心理や社会の評価も創造にとって重要かもしれないが、いったん切り離して考えてもいいのか、とワクワクした。ルーマンやマートン、ベイトソンなどを学び、システム理論をさらに理解していきたい。
2:マズローの欲求段階説を、切実な問題と重ねていく
・人間が解かなければいけない問題だと感じているものは、欲求段階説のいずれかの欲求と関連していると考えていく。たとえば会社で商品を新しく開発しなければならない問題に直面した時、それによって承認欲求を満たしたり、またそれによって給料を得て生理的欲求を満たしたり、また開発の過程において自己実現の欲求を満たしたりする。問題は欲求と関わりあっている。
・幸せになるためには、いずれかの欲求を満たすことと関連している。ただし、段階的に欲求は(それぞれの段階で飽和させて)満たされていくとは限らず、互いに関連している。
・図で整理すると、こうなる。
3:発見メディア(手段)にはいろいろな種類がある。
特にこの3種類を中心に考えていきたい。
イメージでいうとこうなる。
・ざっくりしたイメージ。現実の木の枝は、ひとつひとつがおびただしく、数千、数万を超えるほどの選択肢からなるのかもしれない。しかし、どれが選ばれやすいか、どれが連鎖に導かれやすいかには一定の傾向、法則、パターンがある。
創造の本質はコンティンジェントであり、他でもありうる鍵やドアがたくさんある。社会学でも問題を解決できたし、生物学でも問題を解決できたということがありうる。違う鍵で同じドアを開けていく。あるいは、同じ鍵で異なるドアが開くこともある。一つのドアを開けることが、違うドアを開けることにつながる。ドアを開けられなかったことが、べつのドアへとつながっていく。ランダムに開けていくわけではなく、なんとなく、どの鍵が合うのか、どのドアが目的に繋がるのか、わかっていき、可能性・蓋然性が高まっていく。
・前回整理した図
4:創造は欲求を満たすための手段にすぎない
たとえば(十分な睡眠環境があると仮定して)単に睡眠という生理的欲求を満たす時に、たいていの場合、創造は手段として用いられない。なにか発見の連鎖が起きているとは思えない。仮に起きていたとしても、その程度は低そうだ。
創造が主に手段となるのは、自己実現の欲求を満たすときである。創造的であることが、同時に自己実現の欲求を満たすことにつながってくる。
ただし、食事をとる際にも創造性を用いて料理をしたり、睡眠をとるさいにも寝心地のいい環境を創造したりと、自己実現の欲求と他の欲求は関わりあっている。程度の問題なのかもしれない。解決困難な問題、切実な問題ほど、創造性の度合いが高くなるイメージであり、それらはフロー体験の図と関連していく。たとえば、人類の幸せなどという途方もない問題と単に個人の食欲を満たすという問題を比べて、前者のほうが創造性の度合いを要求される。
欲求が完全とは言わないまでも、ある程度満たされていれば、無理矢理創造をする必要はないのではないか。もちろんシステムが生成と消滅を繰り返す限り、必然的に日々、ドアや鍵は変化していくが、創造性の高い変化、目まぐるしすぎる発見の連鎖、革新的な変化が個人の幸せにとって不可欠とは限らない。現行のパラダイムに反抗するよりも従順するほうが楽なのではないか。
そもそも欲求が飽和するとはどういうことなのか。いくら稼いでも満足できない貨幣のように非飽和的なパラダイムになってしまっているのか。自分だけが満たされていれば、他者のため、世界のために創造をする必要はないのか。世界が仮に良いパラダイムになったとしても、それを維持するためにも高い度合いの創造が日々、行われていく必要があるのか。一体誰が、そうした創造をする役割を担っていくのか。社会設計を誰がするべきなのか。
5:「至高経験」は見田宗介さんの「現時充足的な時の充実」と重なる
・マズローのいう「至高経験」は社会学者の見田宗介(1937-2022)さんの「現時充足的(コンサマトリー)な時の充実」と重なってくる
至高経験:・過去、未来といった時間的な広がりは断念され、「いまここ」に意識が集中し、現在への全面的没頭がある状態。自己喪失、自己超越、神秘的体験。
現時充足的な時の充実:・具体的な他者や自然との交響のなかで、絶対化された自我の牢獄が融解しているとき。ミンコフスキーの生きられる共時性。
(1)ニヒリズム、意味喪失、「どこか満たされない」
現代社会は、現在に没頭する時間よりも、未来に意識が行きがちである。その結果、「どこか満たされない」という状態に陥る。いわゆる「ニヒリズム(虚無主義)」などとも関連してくる。
モリス・バーマンがいうところの、「事実と価値とが乖離した、意味を喪失した世界」である。人間は「参加する意識」を喪い、自己を世界から疎外する意識(科学意識)ばかりを強化していく。たとえばカトリックのように死後の救済というような未来への意識は同時に「意味」があったが、宗教的な力が失われていくと、意味が失われていき、単に直線的に未来に無限に伸びる線になる。仏教のような輪廻感、時間の円環もなくなる。ウェーバーの脱魔術化した世界のイメージ。あるのは多様な価値観同士の闘いである(神々の闘争)。人それぞれ、うちはうち、よそはよそ、個性が大事、世界に一つだけの花。ひとつの世界という花ではなく、世界にあるひとつにすぎない花である。
(2)現代社会の枠組みはコンティンジェントでなものである
・そうした現代社会の枠組み、パラダイム、世界観、エピステモロジーは必然ではない。他でもありえたかもしれない、コンティンジェント(偶有的)なもの。
見田宗介さんの言葉でいえば。ニヒリズムの感覚は「論理的に不可避なもの・真理・普遍的なもの」ではなく、「文化の社会の形態」と関わっているということになる。バーマンの言葉で言えば、「現代我々が抱える諸問題の根が社会的・経済的因子だけではなく、認識論の次元にもある」ということになる。ベイトソンいえばエピステモロジー(認識論)、生物がいかにしてものごとを知るのか、考えるのかを考察する過程が重要になる。
ルビンの壺を見て人をみるか、壺をみるか、それらは論理的に不可避なものではなく、文化と関わっている。個性や独創性に価値があるとみるのも、論理的に不可避なものではない。資本主義などと関わっている。
要するに、具体的・個別的な社会システムがそのようなコミュニケーション(要素)を自己産出しているのであり、多くの要素の連鎖によってガラリとシステムを変えていけば、システムもまた以前とはガラリと異なる要素を産出していく。
トーマス・クーンの言葉で言えば、「パラダイムシフト」にあたる。ちょっとした変化なら日々起きているかもしれないが、革新的な変化は、そうそう起きない。ベイトソンやバーマンがいうような「デカルト的パラダイム」の時代に、まだ我々はどっぷりと浸かっている。
要するに、至高経験やコンサマトリーな充実が生じにくい枠組みの中で、世界観の中で我々は生きている。
現代社会の維持のために、便利で安全な生活、幸せのために、そうした枠組みは機能的に代わりがきかないものだろうか。それとも機能的に等価で、かつより好ましい世界観がありうるだろうか。そのヒントとしてアレグザンダーやベイトソンのいう「美」がなにかという問いは有効になりうるか。ベイトソンとアレグザンダーの「全体性」、システム論で言うと「創発」も重要なキーワードとなっている。部分と部分が調和しているような、そのような社会はどうしたらつくれるか。現代社会は、なぜ、どのようにして調和していないのか。
「そして前章の終わりのところで、貨幣関心の抽象的な無限化のメカニズムとの同型性においてわれわれがみてきたように、『等価のないもの』としての自然や他者たちにたいする感受性の喪失による、時間関心の空疎な集列化という事実は、前項でみてきた二つの決定要因が、じつはひとつの事態に他ならないということを示唆する。すなわち、我々の未来が有限な具象性のうちに完結する構造を喪い、抽象化された無限に向かって生の意味付けが上すべりしてゆくということは、もともと、われわれが現在の生それじたいに内在する意味の感覚を喪い、したがって行きられる(時)それぞれが固有の充足を失うということにもとづいている。そしてわれわれが、現時充足的な時の充実を行きているときをふりかえってみると、それは必ず、具体的な他者や自然との交響のなかで、絶対化された『自我』の牢獄が融解しているときだということがわかる。すなわちわれわれの現在の時が、未来に期待されている結果のうちにしかその意味を見出せないほどに貧しく空疎となるのは、われわれが人間として自然を疎外し、個我として他者を疎外し、いいかえれば現在の時にそれじたいとしての充足を与える一切の根拠を疎外し、ミンコフスキーが《生きられる共時性》と名付けた存在のうちに交響する能力を疎外しているからだ。存在のうちに失われたものを、ひとは時間のうちに求める。」
見田宗介「時間の比較社会学」315P
6:麻酔としての創造性
創造性が満たされている時は、一時的に、世界の歪みが消えているように見える。しかしフレーム自体が歪んでいるので、結局それは一次的な「麻酔(熱狂剤)」にすぎない。もしそうであるとしたら、アルコールや薬で溺れて現実を忘れるのと、どう違うのか。機能的に等価なのか。大きな逆機能があるのか。
絵を描いているとき、音楽を聴いているとき、映画を見ているとき、重要な他者と話している時、一時的に幸せになるかもしれない。しかし会社や学校で心がズタズタになることもある。一時的な麻酔ではなく、社会の枠組みをより好ましい方向に変えるべきなのか。
ニーチェのいう「最後の人間種族」について
ニーチェ「今世紀においては、並の能力以上を持ったあらゆる人間の独創性は、まさにこの恐るべき荒涼の感覚に打ち克つことに向けて発揮された。荒涼の感覚に対立するものは熱狂(酩酊)である。……そこで、この時代は熱狂剤(麻酔剤)の発明においてはなはだ才気に富むものとなった。……そうしてわれわれが拾い集めてくる姑息な手段によって、自分自身を欺いている様ときたら!」
さらにこうした独創性すら発揮されなくなると、「最後の人間種族」が登場する。「『なに、愛だって?創造だって?憧憬だって?えっ、星?そりゃあ、一体何のことですか?』──最後の人間種族はそう尋ねて目をしばたく。とたんに大地は小さくなってしまった。……『われわれは幸福というものを案出したのだ』─最後の人間種族はそう言ってまばたきする。」
「病気になったり、不信の念を起こしたりするのは、かれらにとっては罪悪なのだ。かれらは用心深くゆっくりと歩く。いまだに石につまずき人間につまずく者は馬鹿者である。……かれらはやはり働きはする。労働は気晴らしになるからである。でも、気晴らしで身体を壊さぬよう気をつける。かれらは貧しくもなければ金持ちでもない。どちらにしても煩わしいことだ。誰がいまさら人々を統治しようとするだろう?誰がいまさら他人に服従しようと思うだろう?どちらもどちら、あまりにも煩わしい。羊飼いはおらず、羊の群れだけがむらがっている。」
「誰もが同じことを望み、誰もが同じである。違った感じ方をする人間はみずからすすんで精神病院入りをする。『いやなに、昔は世の中すべてが狂っとったのですよ』─このお上品な連中はそう言ってまばたきする。 」(ニーチェ『ツァラトゥストラ』)
エネルギー(創造性)は「どこに」使うべきなのか
(1)エネルギーを使う「方法」ばかりに議論が集中し、どこにエネルギーを使ったら良いかが曖昧になる。創造性を支援する方法ばかりを蓄積しても、その「方向」がよくわからない。今ある世界観内で成功だと思われている漠然としたもの、貨幣や権力の増大等にばかり目がいっていないか。
(2)私的欲望にばかりエネルギーが使われても、それは麻酔剤としては有効だが、痛みが生じるシステム、枠組み事態はそのままである。むしろ、さらに凝り固まった不動のシステムの再生産として、いつか爆発するまで強化されていくかもしれない(ベイトソンのいう対称型・相補型プロセスのように)。あるいはいっそのこと爆発によって、戦争や環境破壊、テロや病気の蔓延によって、つまり、深刻な危機が生じて、人類の多くがこのパラダイムは問題とみなすことによって、はじめてシステムは変わるのかもしれない。
(3)せっかく創造性を発揮するなら、この世界の歪みを解消する方向に、フレーム自体を解消する方向、パラダイムを変更する方向に発揮したい
→ただし、なにがいいパラダイムなのか、良い枠組みなのか、世界はどのような方向へすすむべきか、そうした答えを与えてくれる理論はあるのか。ベイトソンの理論はそれらに適しているのか、まだまだ学ぶことが多い。
マズローの自己超越の段階になると、こうした枠組みのよしあしについての欲求の解消へ向かうのかもしれない。とはいえ、最低限の生命の安全等は重要になり、理想論ばかり言ってられない。ヒッピー的に愛や平和を叫んでも、明日すら生きることが難しい人間の心には響かない。人類の平和より明日のパン、家族や友人、自国の人々のほうが大事だと人は考える。ナショナリズムとコスモポリタニズムは共存できるのか。
7:社会を考えすぎると、他人の評価を考えすぎると、創造が窮屈だと感じてしまう。
パクられた、という怒り
たとえばある人がある人に作品を「パクられた」と怒っている。ある企業は自分の商標と同じだ、アイデアが同じだと言って怒っている。「模倣」されることに怒りを覚えている。
自分と自分以外を区別しすぎることによって、どこか窮屈になっている。
言い分は理解できる。悪意のあるパクリ(剽窃)は嫌な気分になり、またそうしたパクリが横行すると、何かを新しいものを創ろうとする気分が全体的にすり減っていく感じがする。
個人や企業の力が衰えれば、国際競争力がなくなり、国民は貧しくなるかもしれない。貧しくなると、他者を気遣う余裕がなくなる。
ちっちぇなとでっけぇな
「(個人は)ちっちぇな」と「(社会は)でっけぇな」を反復していつもモヤモヤする。個人も社会も世界にも共通した秩序・パターンを見つけることができれば、モヤモヤは薄れるのかもしれない。
どこか「挟まれている」感じがする(ダブルバインド的か)。小さくなるな、小さくなれ。大きくなれ、大きくなるな。もっと大きなものにつながっていれば、そうした矛盾がなくなるのかもしれない。
昔は神様が信じられていて、「日の下には新しいものはない」という聖書が共有されていて、世界を善くしようとする創造に関しては、許容的だったのかもしれない。絵に名前をつけないこともあったそうだ。「誰が」創ったのかに関心が向かうのは必然なのか、そうではないのか。
そもそも、そんなに社会が気になるなら、公に発表しない限りでは模倣・パクリは、やり放題である。しかし、やはり創ったものはせっかくだから共有したい、と思うのが人間である。
創るためにお金が必要なら、創ってお金を稼ぎ、さらにそのお金で何かを創りたいと思う人はいるだろう。おそらく、この「お金」と関連した模倣・パクリに人は一番、嫌悪するのかもしれない。既存の作品と似ているのではないか、どこまで参考にしたらアウトなのか、と日々怯えるようになる。サンプリング・オマージュなど、明確な境界があるのか。そもそも、自分が過去及びいま生成しつつある現在の表現と類似していない、となぜ言い切れるのか。
「誰」がオリジナルかを問わないケース
たとえばデザインを意図的にそのままトレースされて、商品化され、しかもその人物が著作権を他の人に対して主張していたら嫌な気持ちになるだろう。
しかし、小さなコミュニティで、この絵いいよね、ここが美しい、このパターンが心地良い、と「誰」がオリジナルかを問わずに、そうした要素を語り合うだけのグループがあったとして、模倣された人はそこまで嫌な気持ちになるだろうか。
「リスペクト」があるかどうかという言葉で語られる問題だが、そのリスペクトの根には、「美とはなにか」というような共有できる大きな目的をもっていたい。目的に共に参加している、という連帯の気持ちが生じる。
あるいはお金を有り余るほどもっていたとしても、作品の価値が金銭的な基準になれば、やはり共有してそれがお金を生み出すかどうかが重要になってしまうのか。
創造性は投資であり、創造物は資本である
たとえばメジャーリーガーすべてが、お金のために野球をやっているとは思えない。しかし、お金で自分の価値が評価されることも重要だと考えるのではないか。あまりにも年俸が低いと怒りを覚えるのは単にお金の使い道が減るからではなく、自分への評価が低いと感じるからだろう。
純粋に模倣されたことの嫌悪ではなく、自分の価値が量的に目減りすることの嫌悪ではないだろうか。現代社会のコードでは、価値は量的である。
「模倣されるのは嫌な気分になる」、「新しいものが好ましい、新しいものを創るべきだ」、「量が多ければ多いほどいい」、「新しいものがなければ国を維持できない」という要素の産出は、特定の時代の特定の社会のシステムに依存しているのではないか。
システムが大きく変われば、また違った要素が産出されていく。わずかに要素が変わったくらいだと、システムはたいして変わらない。固定ではないが、ほとんど類似している。
田中さんの絵も鈴木さんの絵も、同じ1000円だから、同じ価値しかない
田中さんの絵が1000円で売れた、鈴木さんの絵も1000円で売れた。だとしたら、この絵の価値は等価である。代わりがきく。同じ価値である。
メジャーリーガーAもBも1億円の年俸である。同じ打率である。同じ勝利数である。佐藤も青木も同じ時給1000円である。同じ登録者数である。同じ視聴者数である。同じ売上である。同じフォロワー数である。
人に模倣されることは、得られたであろう「貨幣の損失」であり、「価値の強奪」である
負のイメージ:人に模倣されることは、得られたであろう「貨幣の損失」であり、「価値の強奪」である。お金が無いと人を「操作」しにくい。操作しにくいことは、よくない。「時は金なり」、「個性は金なり」、「金は量なり」、「量は代わりがきく」、「個性は代わりがきく」、「あなたを形成するもの、価値は個性」である、「あなたは代わりがきく」、「あなたは虚しい」、「そんな世界は虚しい」。
問題:量ではなく質へ、簡単に代わりがきかない質的な関係の、コンサマトリー(現時充足)な関係を構築しやすいような、安定したパラダイム、認識論の構築はいかにして可能になるか。今のパラダイムはそれほどまでに変えなければならないものなのか。
アリストテレスが「芸術創作活動の基本的原理は模倣(自然の模写)である」といったときのようなシステムなら、また違った要素が産出されていたのかもしれない。
あるいは、世界に参加する意識が中心の世界観であれば、現在に没頭する意識があれば、模倣や個性、ニューネスにそこまで意識が強く向かわなくていいかもしれない
ウェーバーなら、「「新しい預言者や救世主を待ち焦がれているだけでは何事もなされず、こうした態度を改めて『日々の要求』に従おう」というかもしれない。
8:機能的に等価だが、集積すると非等価になるか
恋人や友人、両親などは簡単には代わりがきかない
恋人や友人、両親などは簡単には代わりがきかない。抽象的に機能(生殖等)としてみていけば代わるかもしれないが、システムとしてみれば、つまり関係の累積としてみれば、そう簡単に代わりがきくものではない。
あんなやことやこんなことがあったから、今のこの発言が、こういうものとして理解される。要素とシステムの相互作用の繰り返しでお互いに産出にされていく。そうしたものはかけがえのないものであると考えていく。量ではなく質であり、大きなシステム、ネットワーク。
だからこそ、容易にこの世界(デカルト的パラダイム)も代わりがききにくい。お金というコードが、強すぎる世界にある。あらゆる機能の代替としての貨幣。愛も嫌悪も自由も感謝も紙幣で表現される。強いコードから、そうしたコミュニケーションが産出されていく。
それは芸術も同じで、簡単にシステムとして類似することなんてないのではないか。
似ていることはそんなに悪いことなのか
一生懸命、発見の連鎖を繰り返し、考えに考えてデザインをしたものが簡単に似たり、代わりが効くとは思えない。
そもそも、似ていることはそんなに悪いことなのか。異なるものなのに似ているものがある、共通の美のパターンがある。考えに考えた結果、それゆえに、本質的には同質の美のパターンに辿り着くことだってある。パターンの同質性に目を向けないで、ちっぽけな座標の配列の違いに目を向け過ぎなのかもしれない。「類似してるからよくない、独創性がない」のではなく、「類似してるからよい、共通性、包括性がある」のである。その「共通性のパターンの美」こそ、発掘するべきコードではないのか。それ以外は枝葉ではないのか。
仮に似たとしても、「やあ、君もこの山に登ったのか」というような、連帯的、共同的な、ざっくりと同じ目的を目指す友として考えていったほうが楽ではないか。一生懸命考えた者同士なら、お互いにリスペクトを送りあえる。
もし意図せずに類似し、訴えられた場合でも、金銭的に弁償すればいい。この社会システムではそうなんだ、しかたないくらいに思えばいいのではないか。もし精神的に非難されても、この社会システムはまだそういうコードなんだ、と思えばいい。気負うことはない。
9:大事な象徴性
最後に、私が大事だと思うもの、ある種の「象徴性」を引用して終わる。これらそのものは役に立たないかもしれないが、なにかへむけて方向を強く与えてくれる。それぞれを理解して、統合させていきたい。こうしたシステムに今回は、井庭さんの創造システム論や、他の多くの人々主張が関連付けられていったことになる。ここは面白い、ここは似ている、ここはこうつなげたほうがいい、そういう気づきの連鎖が創造であるといえる。
1:私にとってこのニュートンの表現が「不幸」の概念に近い。
「ちっぽけな奴。顔は青白い。僕が座る場所はない。どんな仕事ができるというのか?何の役にたつのか?失意の男。船は沈む。僕を悩ませるものがある。彼は罰せられるべきだったのだ。誰も僕を理解してくれない。僕はどうなるのか。終わらせてしまおう。泣かずにはいられない。何をしたらよいか分からない。」
幼少期の、ラテン語への翻訳の練習のために自由連想で選ばれた文のノートらしい。
(モリス・バーマン「デカルトからベイトソンへ」からの孫引き。129-130P)
2:ルソーのこの表現が「幸せ」の概念に近い。
・ジャン・ジャック・ルソー(1712~1778)
「魂が十分に堅固な地盤を見出して、完全にそこに安住し、そこに自分の全存在を集めて、過去を呼び起こす必要もなく、未来に一足飛びする必要もないような状態、時間が魂にとってなんの意味もなく、いつまでも現在が続き、しかもその持続を示さず、継起のあともなく、不安や充足の、快楽や苦痛の、欲望や恐れの感情もなく、ただわれわれの存在という感情だけがあって、その感情だけが魂の全体をみたすことができる、そういった状態があるとすれば、その状態が続くかぎりは、そこにある人は幸福な人といえる。」
(「孤独な散歩者の夢想」より)
3:ウェーバーのこの表現が「当為」の概念に近い。
1:知性は絶対的な正解を教えてくれず、世界とはどうあるべきか、自分はどう生きるべきかについて何ら回答を与えてくれない。→知性だけ、勉強だけができても、切実な問題の解決にはならない。
2:世界に対してどういう態度をとるべきかは、自分の「良心」と「知性」と「心」が責任を負うべき事柄であり、各人が一生かけて色々と経験を積みながら解決してゆくべき問題。→知性だけではなく、良心と心をセットで考えていく。経験を積み重ねていく。「でっけぇ」人間になれという話。
4:ベイトソンやアレグザンダーらのこの表現が「信仰」に近い。
・グレゴリー・ベイトソン(1904-1980)
「自然界のあらゆる分野の現象に、同じ種類のプロセスを探っていくことができるのではないか、そんな神秘的な考えに、わたしはすっかり染まっておりました。結晶の構造と社会の構造とに同じ法則が支配しているかもしれない、とか、ミミズの体節の形成プロセスは溶岩から玄武岩の柱が形成されていくプロセスと比較できるかもしれない、とか。今のわたしなら、同じことをこう表現するでしょう。──ある分野での分析に役立つ知的操作が、他の分野でそのまま役立つことがある。自然の枠組み(形相)は分野ごとに違っていても、知の枠組みはすべての分野で同じである、と。」
「しかしかつての私は、そのことを神秘的な表現において信じたのです。そして、その信仰はわたしの研究にある種の威厳を与えました。ヤマウズラの羽のパターンを分析しているときでも、いま自分は自然のパターンと規則性という大問題と向かっているのだ、その答えの一かけらを摑もうとしているのだ、という意気込みを持つことができました。そればかりか、この神秘主義は、生物学で学んだこと、物理・科学の基礎コースから拾い上げた思考法をそのまま活用する自由も与えてくれた。人類学の研究に、自然科学の分野で学んだことが役に立つということを私は疑いませんでした。」
グレゴリー・ベイトソン「精神の生態学」,134P
・クリストファー・アレグザンダー(1936-2022)
「諸価値基準の相違は、ある一つの中心的な価値基準に訴えれば解消できると私は信じている。まったくのところ、この中心的な価値基準はすべての背後にある。それをわれわれは一者(the one)や無(the void)と呼んでもよいだろう。すべての人はこの価値基準と結びついており、自分自身の意識を目覚めさせることによって、程度の差はあっても、この価値基準と接触できる。この単一の価値基準との接触は、われわれの行為に究極の基盤を与え、創造者、芸術家、建築家としての行為に究極の基盤を与えると私は信ずる。」
参考文献リスト
主要文献
井庭崇, 宮台真司, 熊坂賢次, 公文俊平, その他 「社会システム理論: 不透明な社会を捉える知の技法 (リアリティ・プラス)」
井庭崇, 宮台真司, 熊坂賢次, 公文俊平, その他 「社会システム理論: 不透明な社会を捉える知の技法 (リアリティ・プラス)」
川喜田二郎 「創造性とは何か(祥伝社新書213)」
クリスティアン・ボルフ 「ニクラス・ルーマン入門―社会システム理論とは何か」
クリスティアン・ボルフ 「ニクラス・ルーマン入門―社会システム理論とは何か」
汎用・基本文献リスト
米盛裕二「アブダクション―仮説と発見の論理」
トーマス・クーン「科学革命の構造」
真木悠介「時間の比較社会学」
モリス・バーマン「デカルトからベイトソンへ ――世界の再魔術化」
モリス・バーマン「デカルトからベイトソンへ ――世界の再魔術化」
グレゴリー・ベイトソン「精神と自然: 生きた世界の認識論」
グレゴリー・ベイトソン「精神の生態学へ (上) (岩波文庫 青N604-2)」
グレゴリー・ベイトソン「精神の生態学へ (上) (岩波文庫 青N604-2)」
マックス・ウェーバー「社会科学と社会政策にかかわる認識の「客観性」」
マックス・ウェーバー「社会科学と社会政策にかかわる認識の「客観性」」
参照論文リスト
・劉蕊「食事行動をとるインタフェースエージェント を利用した発想支援の研究」(URL)
・ 久松健一「原稿の下に隠されしもの〝引用・模倣・盗用・盗作〟を通じて文芸の創造のなんたるかを考える」(URL)
・参考サイト:日本創造学会(URL)
・西浦和樹「創造性教育の現状と創造的問題解決力の育成—教育ツールの活用による人間関係構築の試み—」(URL)
・新居保夫「創造性の育成をめざす算数科の授業の構造化」(URL)
・高田哲雄「創造性の構造研究:ゲシュタルト論に基づく形態モデル仮説」(URL)
・高田哲雄「複合領域としての” イメージ・デザイン学”」(URL)
・ 李在鎬「個人の創造性から組織の創造性へ」(URL)
・横山正博「創造性における自己実現欲求と価値について-マズローの自己実現的創造性の検討」(URL)
・石田潤「マズローの自己実現論の全体像について」(URL)
・吉田若葉 「保育における楽器指導:創造的な人間形成と音楽教育」(URL)
→創造と模倣、創造と想像の関連について後でチェック
・夏堀睦 「人間性心理学における創造性研究 : A.H. MaslowとM.Csikszentmihalyiの創造性理論の検討」(URL)
各流れの外観、ギルフォード、トーランス、ワラス、マズロー、チクセントミハイなど
メモ:ウィゴツキーとマズローの比較について、今後頭に入れておく
・妹尾 佑介「美術教育におけるフロントランナー型創造性モデルの構築に関する一考察―川喜田二郎の創造性理論を軸として―」(URL)
メモ:美術における創造性、マズローに対する恩田さんの主張を後でチェック
・佐々木宰「アジアの美術教育における創造性育成の可能性」(URL)
→チクセントミハイ、トーランス、マズローの創造性の定義関連
・玉木博章「教育における「時間-空間-人間関係」問題に関する研究(2)―チクセントミハイによる「フロー」概念を手がかりにした生活指導の視点から―」(URL)
→チクセントミハイによるフロー概念の説明
・李月「協働作話における児童の応答行為と協働作話の展開過程における児童同士の創造性の発揮に関する実証的研究」(URL)
→チクセントミハイによるDIFIモデルの説明
・井庭崇「 創造システム理論の構想」(URL)
→チクセントミハイ関連、ルーマン、井庭崇関連
・太田茂秋「野外志向のレジャー・スタイルに関する価値意識研究-1」(URL)
→フロー関連
・ 石田潤 「 内発的動機づけ論としてのフロー理論の意義と課題」(URL)
→内発的動機づけの定義、フロー関連、フロー経験の8つの特徴、及び条件について参考に
・川喜田二郎 「野外科学と創造性教育への道」(URL)
・川喜田二郎「創造性開発のための教育」(URL)
・中川 米造「KJ法」(URL)
・田文揚 「水平思考と傾斜思考の仮言的考察:縦横のロジックから斜めのロジックへ(個人研究)」(URL)
→デボン関連
・棚原健次「熱応理論の研究: 特に創造性の機能-構造を通して」(URL)
→市川亀久弥関連、湯川、デボン
・毛利亮太郎「勘考的思考と拡散的思考」(URL)
→オズボーン、デボン
・ 伊賀憲子 「MSC創造的構えテストの作成」(URL)
→ヴェルトハイマー、恩田彰、創造性の定義、評価関連
・棚原健次 「創造的思考類型と自発性に関する研究」(URL)
→デカルト・恩田彰、ブルーナー等々
・田中克征「数学教育における創造性育成と問題解決指導に関する研究-思考の固執に着目して」(URL)
→ヴェルトハイマー関連
・伊賀憲子「創造的思考の評価基準」(URL)
→マズロー、ヴェルトハイマー
・原弘道「発見的な学習指導のあり方」(URL)
→ブルーナーについて参考に
・米田 豊 「社会科教育における思考力・判断力・表現力の評価方法の開発 教育現場の実態把握と論理学、分析哲学、社会学、認知心理学の研究成果を組み込んで 最終報告書」(URL)
→ブルーナーについて参考に 特に思考の定義。さらにアブダクションや「問いの種類」について、面白い主張と整理がなされている。後で振り返るべきところ。
・天野正輝「JS Bruner によるデューイ批判の検討」(URL)
→ブルーナーについて参考に、デューイも面白い
・片井 修「共創のライプニッツ時空」(URL)
→ユングのプレローマ、クレアツール、区切りの話、ライプニッツの時空の話(ニュートンとの比較)がなかなかおもしろい。ベイトソンとつながる。ブルーナーについて参考に。セラミティス構造の説明は、アレグザンダーにつながる。
・國藤 進「発想支援システム」(URL)
→國藤進さんの創造プロセスの説明、発想支援システムの定義
・國藤 進「発想支援システムの研究開発動向とその課題 (< 特集>「発想支援システム」)」(URL)
→國藤進さんの図の整理
・川又 啓子「マンガ・コンテンツの商品開発に関する研究 創造的認知アプローチによる事例「美内すずえ」の分析」(URL)
→創造と芸術の関連が述べられていて面白い。宮崎駿。ジェネプロアモデル。
・三輪和久, 石井成郎 「創造的活動への認知的アプローチ (< 特集> 創造的活動の理解と支援)」(URL)
→創造へのアプローチ分類について、ジェネプロアモデルの説明について。ジェネプロアモデルは今回はスルーして、次回以降個別具体的に取り扱いたい。
・湯川 秀樹「科学と創造性」(URL)
→理論とはなにか、実証とはなにか、美とはなにかなど、おもしろい。振り返りたい。まとめる能力、造形能力、何かを「絵」にすることの重要性について。
・牧野逸夫「特許知識を活用した発明知識空間構成法と技術アイディア発想」(URL)
→いろいろとまとめられている。要チェックだが、創造とはなにかというより、創造の支援についてのテクニックに近い。
・川岸克己 「同定理論と自己非自己理論」(URL)
→湯川さんの創造性の定義について参考になる。なかなか読みやすく、おもしろい論文。
→市川亀久弥さん関連
・恩田 彰「創造過程におけるESPの役割」(URL)
→恩田さん
・山口高平「レクチャーシリーズ:「シンギュラリティと AI」[第 3 回] 実践知能| 多重知能のためのメタ AI アーキテクチャ」(URL)
→スタンバーグについて参照
・池田久美子 『「はいまわる経験主義」の再評価』(URL)
→増殖するコードについて。おもしろい。パースのアブダクションとの関連や、記号学者のウンベルト・エーコ(1932-2016)の主張も面白かった。
・福田繭子, 福岡与志美, 福田梨奈「社会的存在としての子ども観: ヴィゴツキーの視点から」(URL)
→ウィゴツキーについて。なかなかおもしろい。特に教育の観点。
・今田高俊「自己組織性論の射程」(URL)
→ベイトソン、ルーマン関連。特にオートポイエーシスや、論理と因果の関係等、説明が豊富
・日本創造力開発センター(https://www.jcdc.jp/)
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
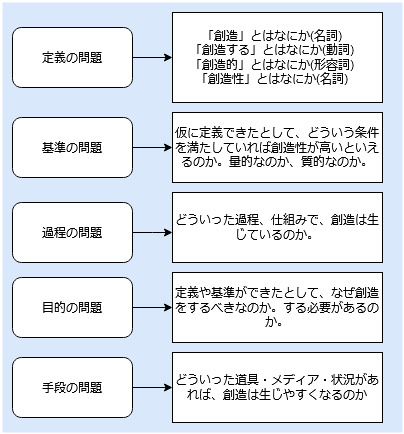
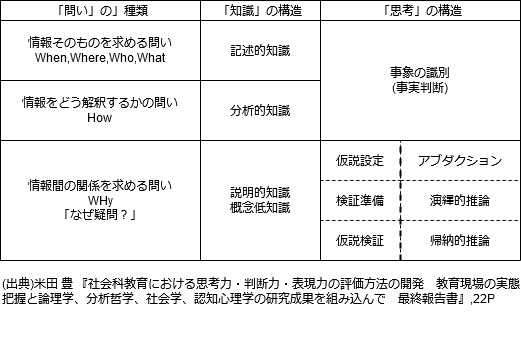

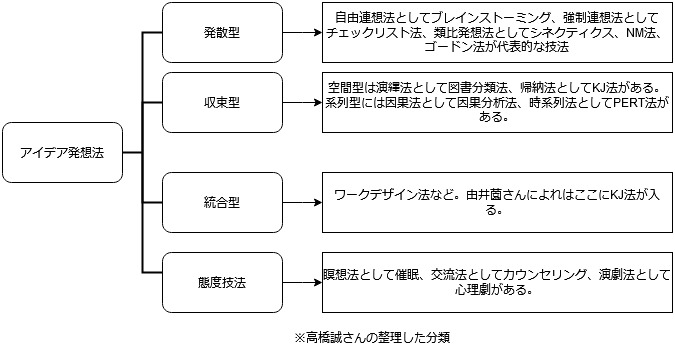


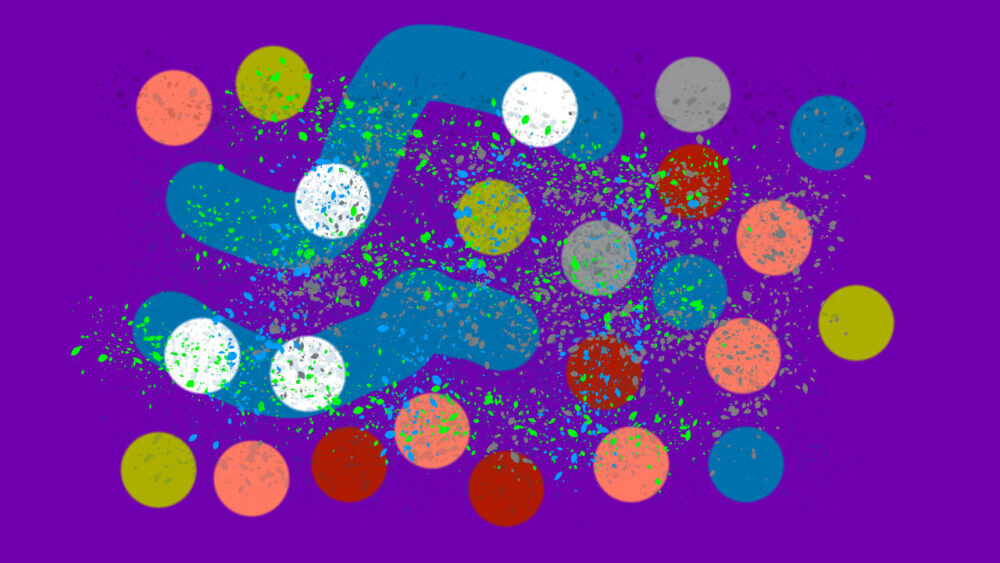










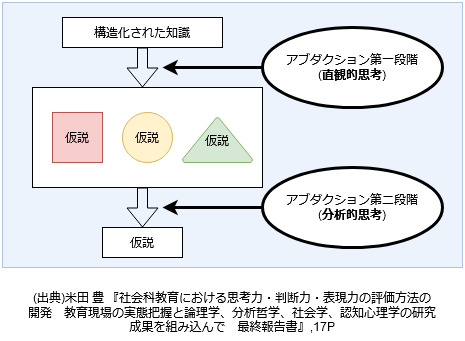
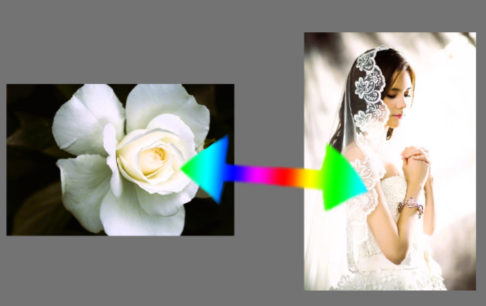




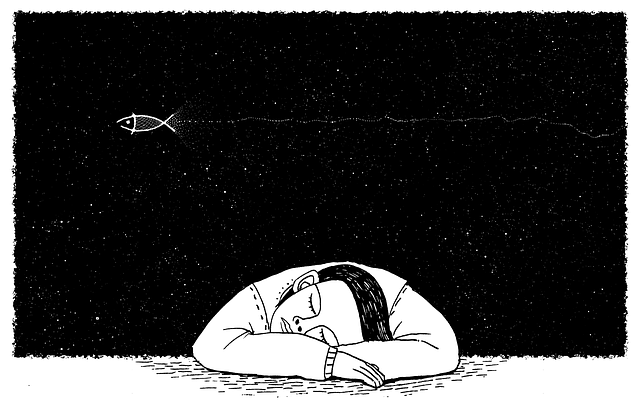
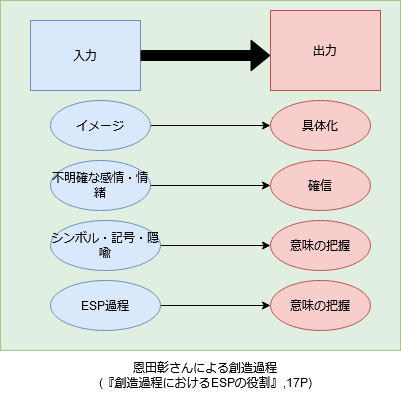

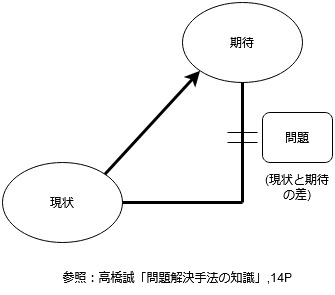
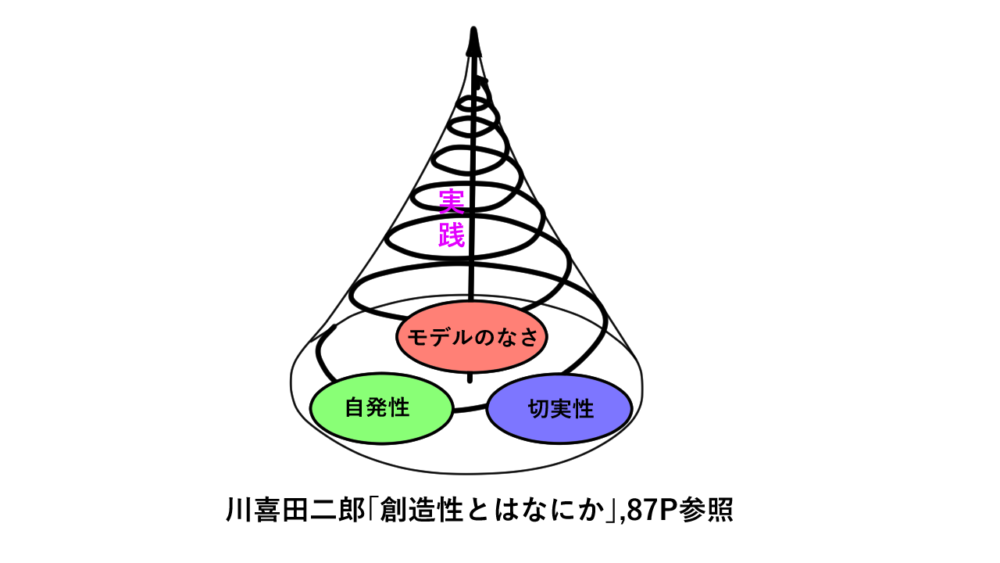

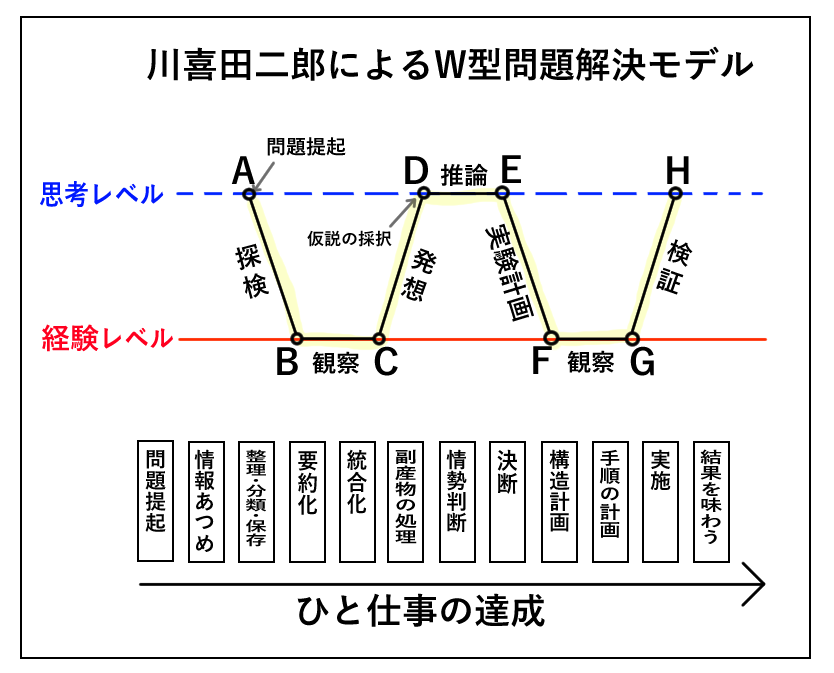
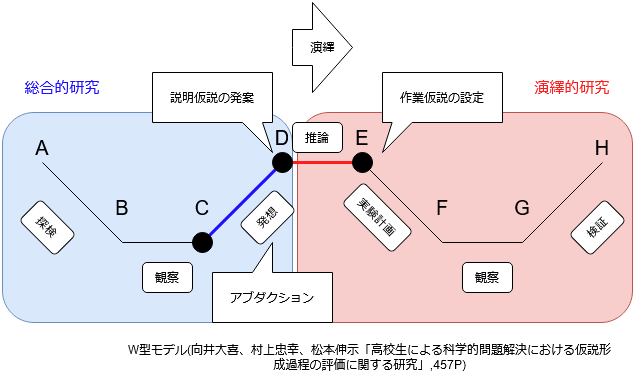

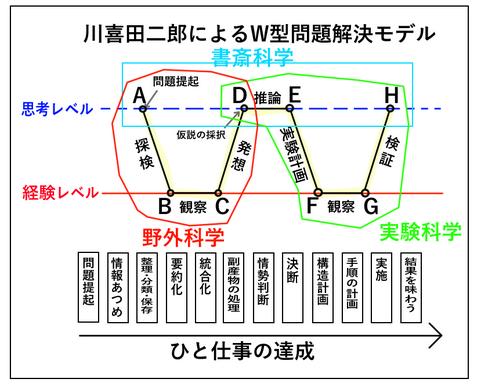
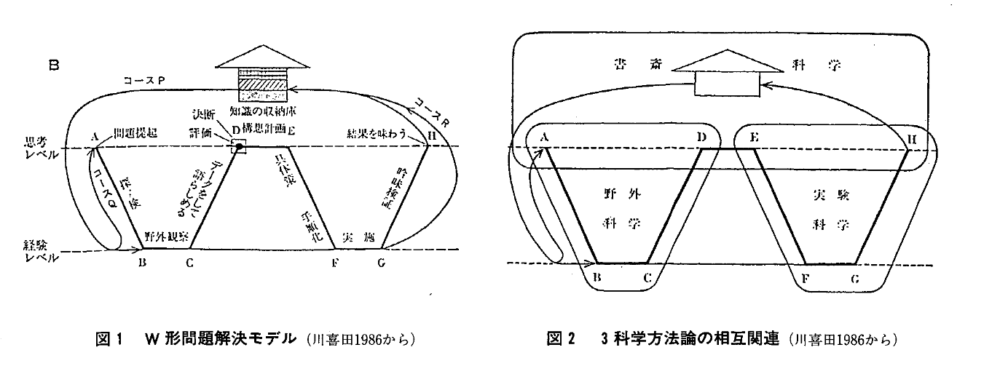

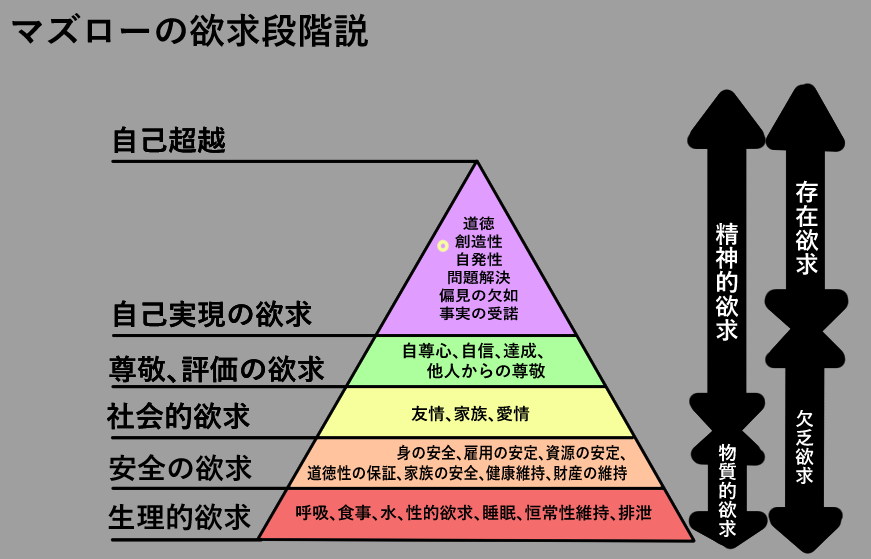
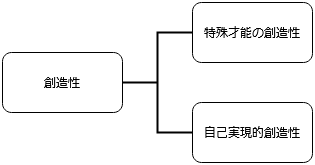
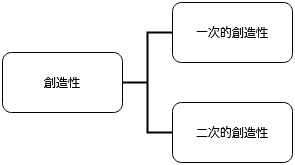




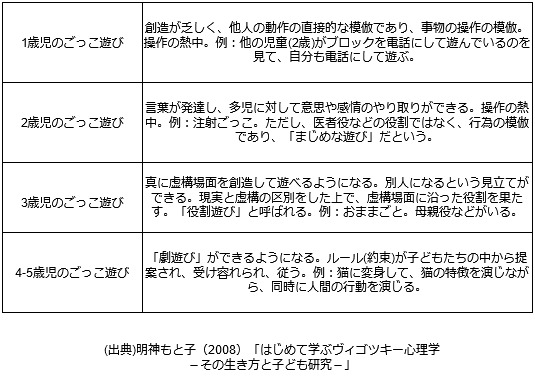

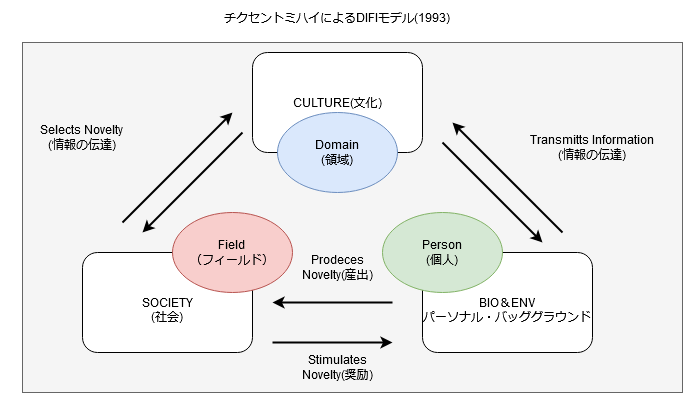
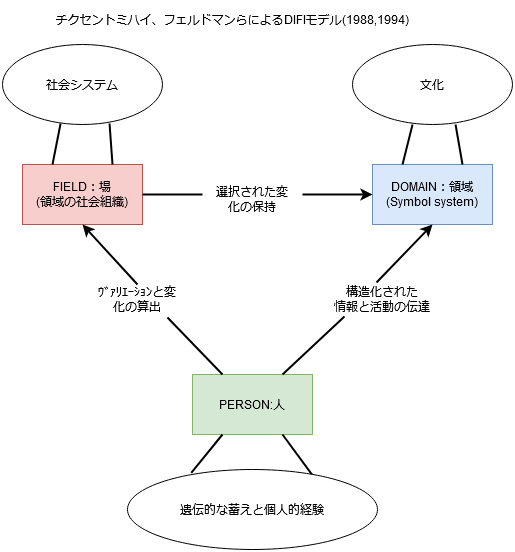
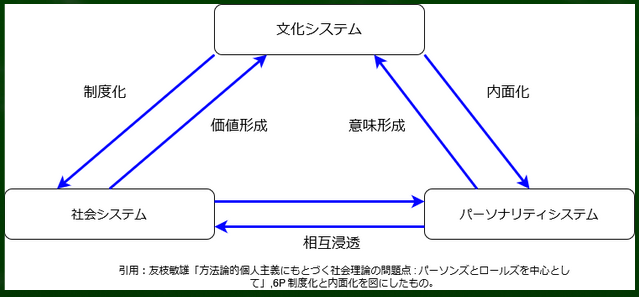


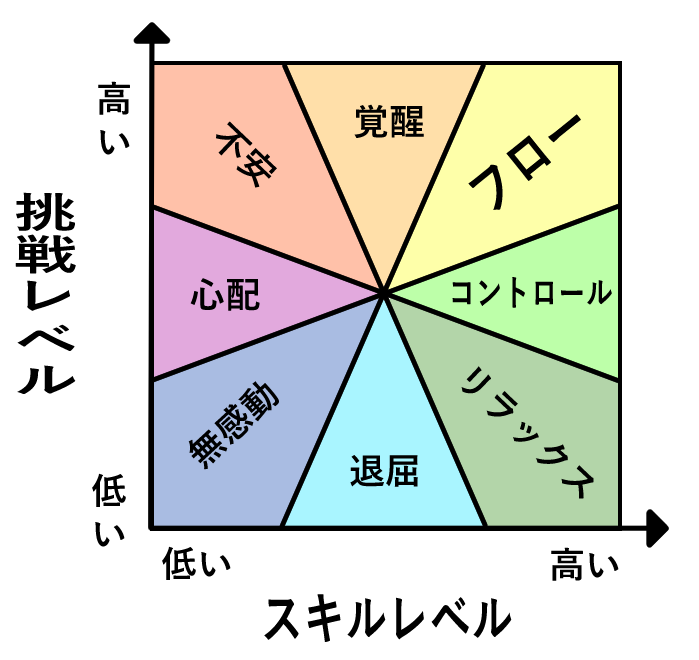


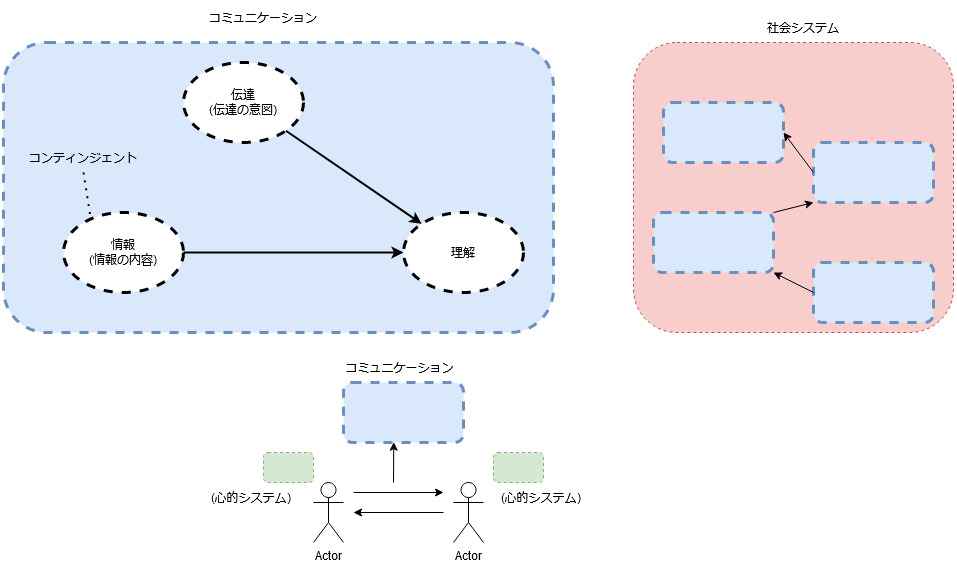
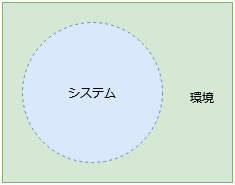
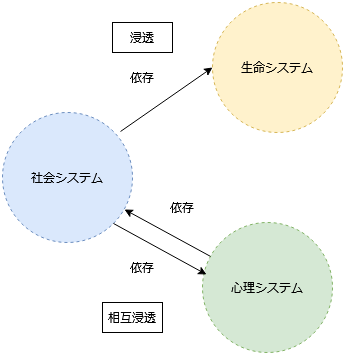

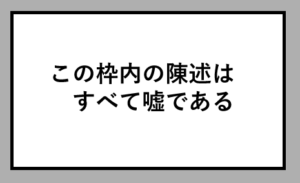
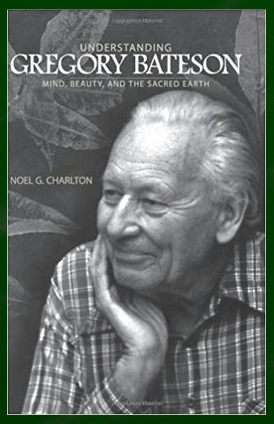


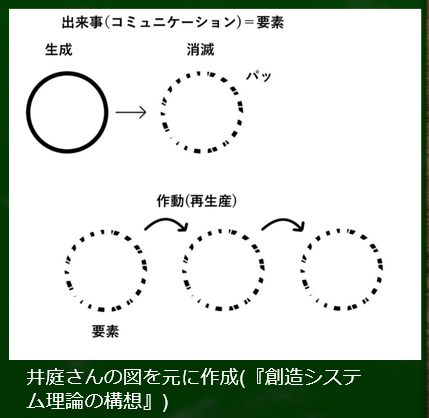


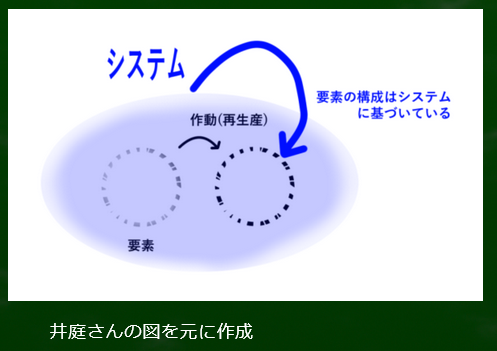

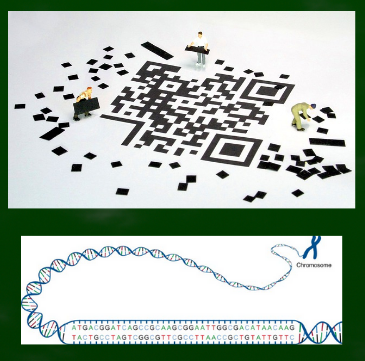
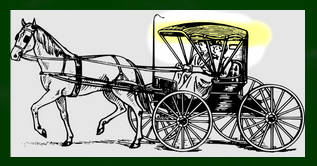
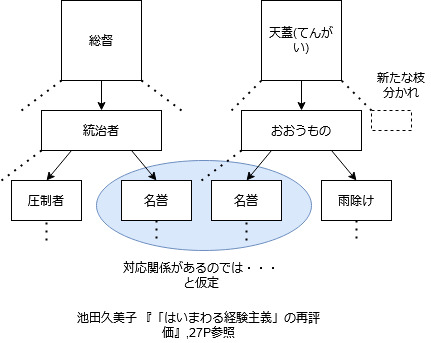
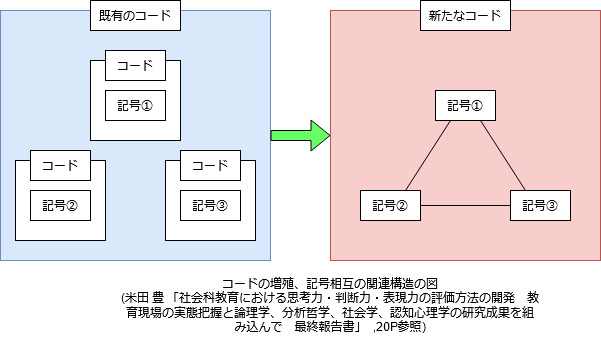
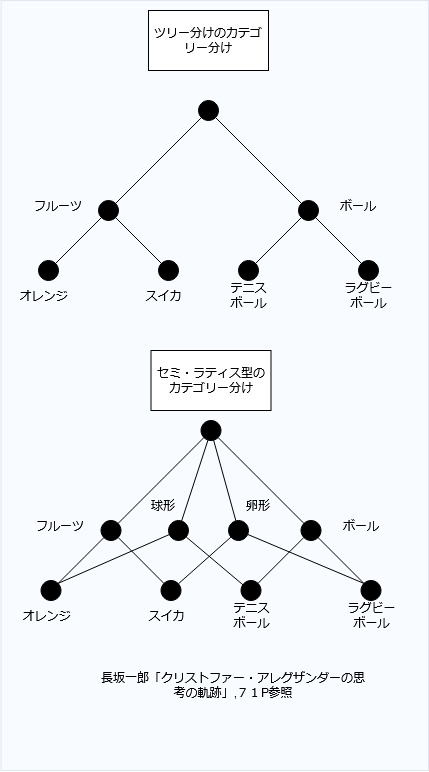
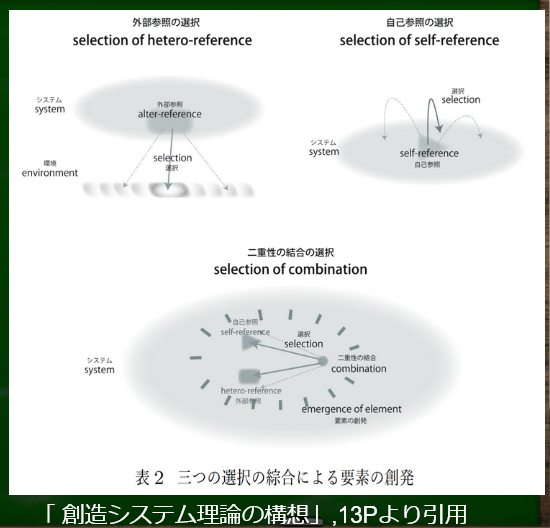

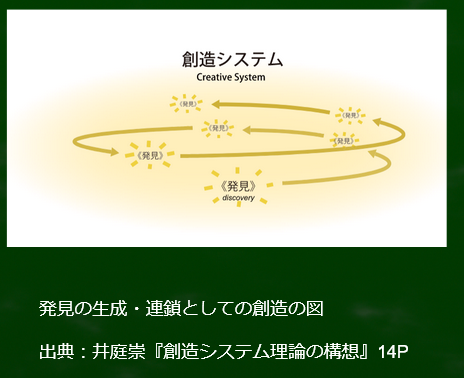


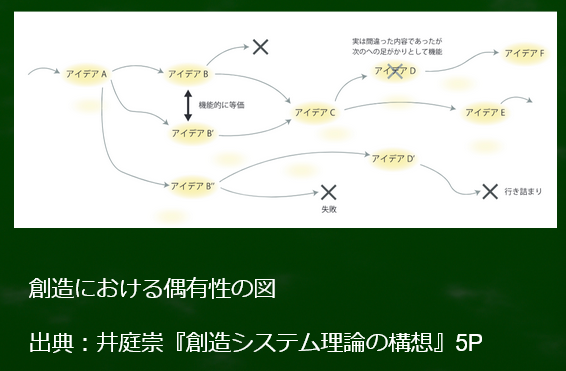

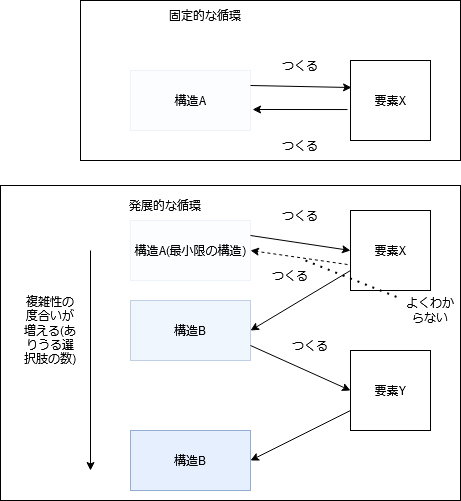

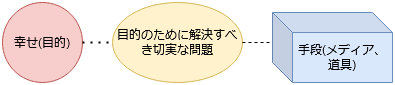
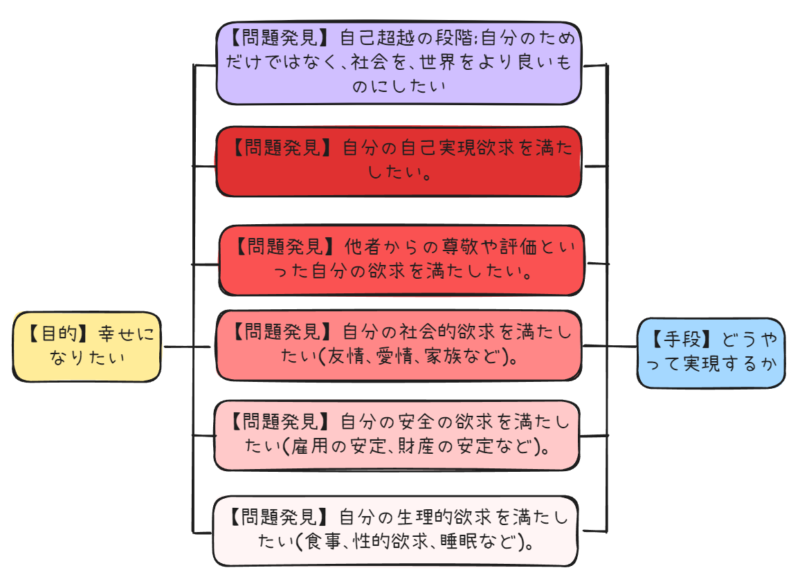
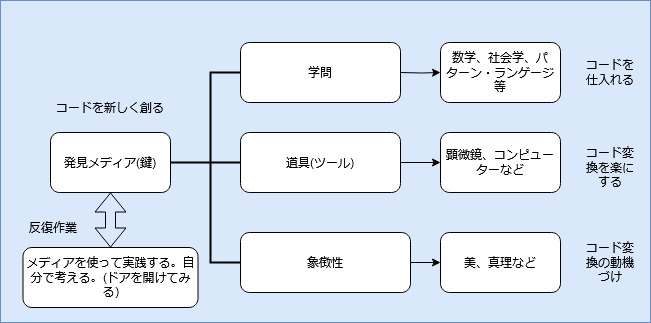


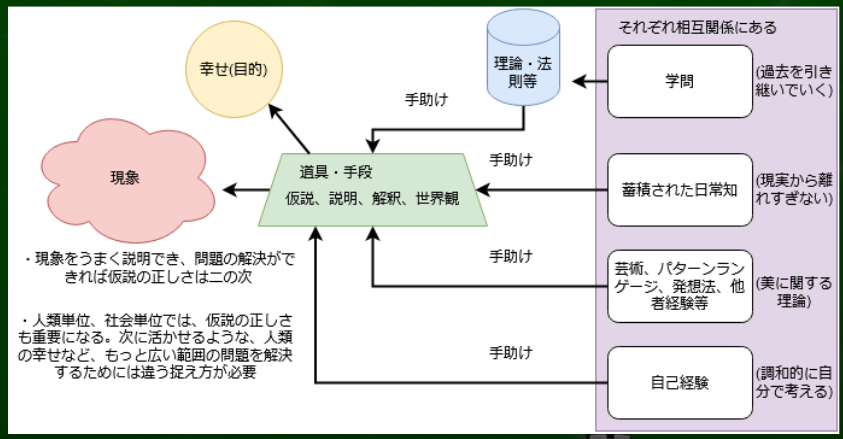


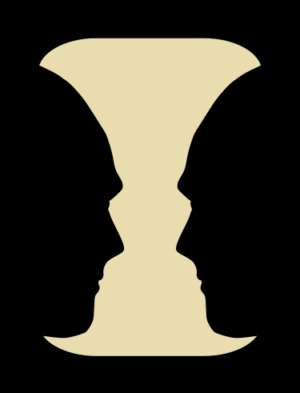

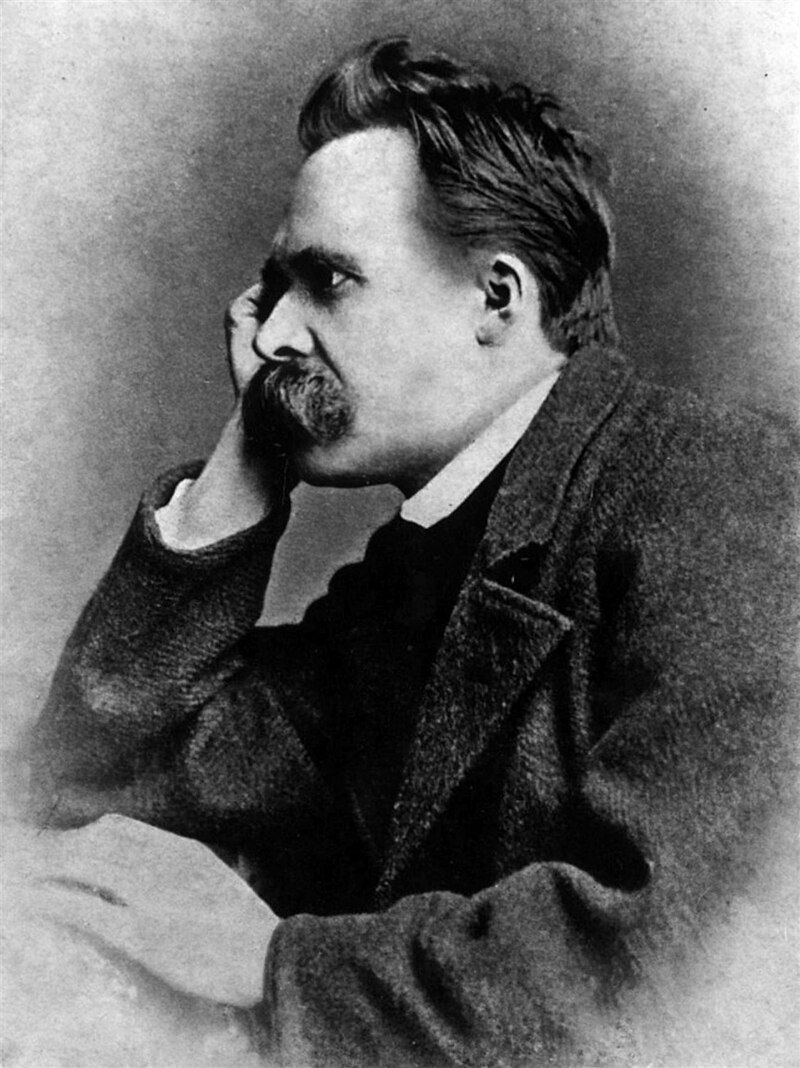



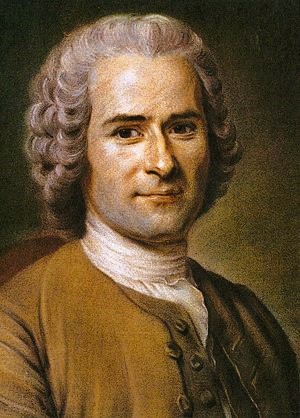



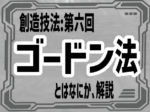
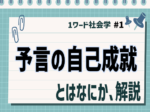
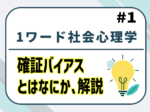
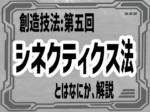
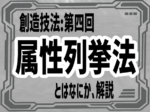
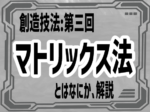
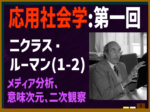

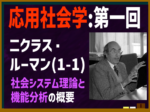
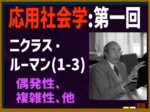
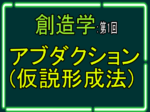
この記事へのコメントはありません。