- Home
- エミール・デュルケーム
- 【基礎社会学第三九回(1)】エミール・デュルケムにおける「『宗教生活の原初的形態』の目的」を解説
【基礎社会学第三九回(1)】エミール・デュルケムにおける「『宗教生活の原初的形態』の目的」を解説
- 2025/4/24
- エミール・デュルケーム
- コメントを書く
Contents
はじめに
動画での説明
・この記事の「概要・要約」はyoutubeの動画の冒頭にありますのでぜひ参照してください。
よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m
エミール・デュルケムとは、プロフィール
エミール・デュルケム(Émile Durkheim,1858-1917):フランスの社会学者。デュルケームと翻訳されることもある。マックス・ウェーバー、ゲオルク・ジンメルとともに社会学の創設者として扱われている。社会学の機関紙『社会学年報』(1898年)を創刊し、デュルケーム学派を形成した。甥には人類学者のマルセル・モースがいる。代表作は『社会分業論』(1893)、『社会学的方法の規準』(1895)、『自殺論』(1897)、『宗教生活の原初的形態』(1912)であり、社会学の古典となっている。
【基礎社会学第一回】エミール・デュルケームの「社会的事実」について
【基礎社会学第二回】エミール・デュルケームの「社会的分業」とはなにか?
【基礎社会学第三回】エミール・デュルケームの「自殺論」、「聖と俗」、「機能主義」とはなにか?意味
【基礎社会学第三六回(1)】エミール・デュルケムの社会学とはなにか、学ぶ意味や価値はあるのか
【基礎社会学第三六回(2)】エミール・デュルケムの「機械的連帯と有機的連帯の違い」を解説
【基礎社会学第三六回(3)】エミール・デュルケムの「集合意識と集合表象の違い」を解説
【基礎社会学第三六回(4)】エミール・デュルケムの「非契約的要素」を解説
【基礎社会学第三六回(5)】エミール・デュルケムの「拘束的分業とアノミー的分業の違い」を解説
【基礎社会学第三七回(1)】エミール・デュルケムの「社会的事実を物のように考察せよ」を解説
【基礎社会学第三七回(2)】エミール・デュルケムの「実証主義(合理主義)」を解説
【基礎社会学第三七回(3)】エミール・デュルケムの「社会学主義」を解説
【基礎社会学第三七回(4)】エミール・デュルケムの「社会実在論/社会唯名論」を解説
【基礎社会学第三八回(1)】エミール・デュルケムの『自殺論』の目的を解説
【基礎社会学第三八回(2)】エミール・デュルケムの「自殺の恒常性」を解説
【基礎社会学第三八回(3)】エミール・デュルケムの「自己本位主義的自殺」を解説
【基礎社会学第三八回(4)】エミール・デュルケムの「集団本位主義的自殺」を解説
【基礎社会学第三八回(5)】エミール・デュルケムにおいて自己犠牲は自殺か?
【基礎社会学第三八回(6)】エミール・デュルケムの「アノミー的自殺」を解説
【基礎社会学第三八回(7)】エミール・デュルケムの「宿命論的自殺」を解説
【基礎社会学第三八回(8)】エミール・デュルケムの「統計の使い方」を解説
【基礎社会学第三八回(9)】エミール・デュルケムの『自殺論』は現代でも有効か?
【基礎社会学第三九回(1)】エミール・デュルケムにおける「『宗教生活の原初的形態』の目的」を解説(今回の記事)
【基礎社会学第三九回(2)】エミール・デュルケムにおける「宗教の定義」を解説
【基礎社会学第三九回(3)】エミール・デュルケムにおける「信念、聖と俗」とはなにか
【基礎社会学第三九回(4)】エミール・デュルケムにおける「儀礼」を解説
【基礎社会学第三九回(5)】エミール・デュルケムにおける「教会」を解説
【基礎社会学第三九回(6)】【コラム】プラグマティズムに対するデュルケムの評価
【基礎社会学第三九回(7)】エミール・デュルケムにおける「トーテミズム」を解説
【基礎社会学第三九回(8)】エミール・デュルケムにおける「神と社会はひとつである」を解説
【基礎社会学第三九回(9)】エミール・デュルケムにおける「トーテミズムの儀礼の具体例」
【基礎社会学第三九回(10)】エミール・デュルケムにおける「集合的沸騰」とは
【基礎社会学第三九回(11)】【コラム】聖なる時間/俗なる時間
【基礎社会学第三九回(12)】【コラム】ジンメルにおける「適切な距離」
【基礎社会学第三九回(13)】エミール・デュルケムにおける「認識論」とは
【基礎社会学第三九回(14)】【コラム】「来たるべき社会とその聖」をベイトソンから考える
『宗教生活の原初的形態』の目的
『宗教生活の原初的形態』の目的とはなにか
『宗教生活の原初的形態』(1912)はデュルケムが生前に刊行した最後の著作である。カテゴリーを大きく2つに分けるとすれば、宗教論と認識論から構成されている。
この著作の目的は大きく3つに分けて考えることができる。「宗教の本質」、「宗教の起源」、「宗教の機能」を明らかにすることである。宗教の定義と起源、機能の3つを「社会」に関連付けて明らかにすることであるといえる。認識論も宗教に起源をもつこと、さらには宗教は社会に起源をもつことが重要となる。
キーワード:目的
「この著作においてデュルケムは,宗教の社会的起源と機能とを,当時知られているうちで最も原始的で単純な宗教である,オーストラリァ未開社会のトーテミズム(tot6misme)に求めて究明している。そして,このトーテミズムには,最も進歩した諸宗教の基底にもある,あらゆる偉大な観念と主要な儀礼的態度の存在することを発見して,(聖と俗とへの事物の区分,霊魂,精霊,神話的人格,国民的あるいは国際的な神性の観念,消極的儀礼とその誇張された形態である禁欲的行箏,奉献とコンミュニオンとの積極的儀礼,模倣的儀礼,記念的儀礼,贖罪的儀礼)宗教とは何であるかに答えようとする。また,宗教と社会の関係を,それぞれの本質的な次元で跡づけようとする。」
・寺林脩「デュルケムの宗教論 (序説)」(1980),52p
「原初的形態」とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説
タイトルの「原初的」とは、原理的・基本的という意味である。本質と言い換えてもいいかもしれない。
あらゆる宗教よりも先に生まれたという時系列的な「始祖(全ての始まり)」という意味合いではない。とはいえ、「宗教の本質」を理解するために、できるだけ「原始的で単純な宗教」を対象とするという戦略がとられている。キリスト教やイスラム教などは複雑すぎて本質を捉えにくいとみなされている。そして現在知られている最も原始的で単純な宗教がオーストラリア未開社会の「トーテミズム」であるとデュルケムは考えている。
キーワード:始原
「デュルケムが手がかりにするのは、『現在知られているうちでもっとも原始的で単純な宗教』である。この方法は『始原』においてこそ本質が把握されるとする発生論的視点によるものである。世界宗教などは複雑すぎて、『宗教生活の共通的な奥底』、『宗教的心性全般の特質である基本的な状態』を発見することは難しい。始原においてはそうではない。『すべてが、それなしには宗教が成立しないもの、不可欠なものへと還元されている。しかもこの不可欠なものこそまた本質的なものである』(『宗教生活の原初的形態』,25p)。これがデュルケムの戦略である。デュルケムのいう『原初形態』というのは、原初的=原理的=基本的な形態ということにほかならない(中久朗)。」
中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,74p
『宗教生活の原初的形態』の意義
それぞれの用語は別の項目で詳細に説明するとして、ここではデュルケムの動機的な側面に触れていきたい。
なぜ、宗教の本質や動機、機能を明らかにするべきなのか、その「意義」はどこにあるのか。なんらかの意義や価値がなければ、人は目的を設定しないだろう。
宗教を理解することの意義は、大きく見れば「社会学を学ぶことの意義」と通底している。もっといえば「科学を学ぶ意義」とさえいえるかもしれない。
大まかにデュルケムのスタイルを「現状分析」、「理論作成」、「危機意識」、「治療」の4つに分けるとする。社会を分析するうちに、その中に「危機」を発見する。あるいは、先に危機をなんとなく感じて、そのあとで社会を分析することもあるだろう。その反復において両者がはっきりと感じられたりするわけである。この危機を「病気(異常)」と言い換えてみると、「治療(正常)」との関連がわかりやすい。この危機を解消するために、つまり治療するためにはどうしたらいいのかと考えていくわけである。
・キーワード:原初的
「デュルケムが最も原始的な宗教であるというのは,全くの始源的宗教ではなく,最も単純な組織を備えている社会に存在し,かつ,以前の宗教から借りた何の要素も含まないで自ら説明できる宗教体系である。オーストラリア未開社会のトーテミズムは,以上の条件を満足させるものである」
・寺林脩「デュルケムの宗教論 (序説)」(1980),53p
『社会分業論』(1893)における病気と治療
たとえば『社会分業論』(1893)では分業が「社会的連帯」や「道徳」を強めるポジティブな機能があることが主張された。一方で、「拘束的分業」や「アノミー的分業」など、連帯や道徳を弱めるネガティブな機能があることも主張されている。
後者のネガティブな機能は「危機意識」に相当するものであり、「異常(病的)な分業」であるとみなされている。その治療法としては、社会的な不平等を減らし、自然的な不平等のみを許すように社会的な枠組み(法など)を変えたり、人々の欲求が適度に規制される必要があると主張された。
【基礎社会学第三六回(5)】エミール・デュルケムの「拘束的分業とアノミー的分業の違い」を解説
『自殺論』(1897)における病気と治療
『自殺論』(1897)では「自殺が近代になって急激に増加していること」に危機意識をデュルケムはもっている。特にアノミーやエゴイズムといった近代特有の自殺のタイプが問題視されている。
その治療法としては中間団体(職業団体など)の再編が提唱される。『自殺論』では教育はそこまで重視されておらず、「道徳教育論」(1902)などで高く評価されるようになる。
【基礎社会学第三八回(6)】エミール・デュルケムの「アノミー的自殺」を解説
社会の治療法の提案
まとめると、分業や自殺という現象を分析する意義は「社会の治療法の提案に役立つから」といってもいいだろう。
それは宗教の分析においても同様である。原始的な社会の宗教の分析で得られるなんらかの要素が、現代の病気に対してなんらかの形で治療になると考えたわけである。
理論的意義と実践的意義の違い
たしかにデュルケムは「理論的意義と実践的意義の違い」を意識することを重要視した。ある分析が「社会の治療の役にたつかどうか」、「社会がどうあるべきか(should)」といった「実践的意義」と、「社会とはこうなっている、社会とはなにか(how,what)」という理論的意義の区別である。
社会学の役割は特定の社会のその場限りの治療法を探るというより、より抽象的な社会の本質、法則、形式を明らかにするような「知の枠組み」を明らかにするという点にあるとデュルケムは考えている。
目の前にある石だけにしか通用しない法則を調べるより、あらゆる無機物に存在する分子やその挙動を発見するべきだというイメージだろうか。たとえば「自殺は統合力の強さに関係している」という命題はあらゆる社会に関係するものである。
パーソンズで言えば一般理論、公理体系の構築ということになるだろう。とはいうものの、前期デュルケムはそこまで抽象的、本質的、発生論的なものに関心はなく、実証的に判明できる範囲での特殊的な因果関係(機能分析)をより重視していたともいえる(この変遷は次の項目で扱う)。特殊的であれ普遍的であれ、主要な目的は「社会の分析(理論)」であり、「社会の治療(実践)」ではないということになる。
とはいえ、デュルケムは「われわれの探求が、もし思弁的興味しかもつべきではないとするならば、それは瞬時たりとも研究に値しない」とも述べている。
デュルケムが社会の危機を強く感じ、その治療法を探し求めていたことはそうした「実践的な関心」の現われだろう。もちろん理論的な関心も同時にもっていたのであり、それらの緊張関係をもっていたといえる。マックス・ウェーバーが職業政治家に情熱(価値判断)と冷静さ(事実判断)を峻別しつつ、かつ同時に求めていたこととも通底するものがある。
【基礎社会学第十二回】マックス・ウェーバーの『職業としての政治』から「職業政治家」を学ぶ。
キーワード:理論と実践
「デュルケムは『分業論』で、理論的問題と実践的問題とを慎重に切り離すけれども、それは実践的問題を無視するからではないと言っている。……『われわれの探求が、もし思弁的興味しかもつべきでないするならば、それは瞬時たりとも研究に値しない』というのがデュルケムの考えである(『分業論』33p)。」
中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,114p
宗教を分析する目的
宗教を分析する目的は「社会の治療法を発見するため」であるといってもいいのではないだろうか。もちろんこうした実践的意義だけではなく理論的意義もあるのだろうが、わたしはこの著作においては前者に傾いていると考える。
「社会的連帯、統合を高めるような機能」が宗教にはどうやらある。それを神や超自然、精霊といった非科学的、非合理的な要素に還元することはできない。デュルケムの言葉で言えば「宗教的象徴という衣を剥ぎ取って、合理的裸体としての道徳力」を発見するということになる。
それらを現実の具体的な集団(オーストラリアの原始的な集団)を分析し、実証的に明らかにすることを目的としている。先取りすればそれは「集合的沸騰」であり、人々が集まり、一体となったときに生じる「聖なる力、集合力」が関係しているとデュルケムは主張している。
「人と人とを、人と社会とを結びつける力」は宗教だけではなく分業にも認められるといえるが、宗教のほうが道徳や連帯を生み出す、より強い力があるといえるのかもしれない。
近代社会における「分業」が生み出す道徳や連帯だけではどうやら不十分であり、伝統的な宗教の多くは力を失ってしまっている。既存の宗教を力づけたり、原始的な宗教を復活させることもナンセンスだと考えられている。
つまり、「聖なる力」を人々に与える新しい形の「道徳的共同体(教会)」が必要とされているわけであり、その鍵は「道徳的個人主義(人格の崇拝)」にあるとされている。「人格の崇拝という新しい形の宗教的な力」こそが治療薬のひとつとして位置づけられるわけである。
キーワード:宗教と道徳
「道徳と宗教は、ほんの機能まで、分かちがたく結びついていた。『宗教生活の中心である神は、同時に、道徳的秩序の至高の保護者であった。』(『道徳教育論』,41p)。それゆえ、第三共和政の世俗教育を支えるかたちでデュルケムが模索した、完全に合理的な道徳教育も、単に道徳から宗教的要素を排除すれば可能になるというものではない。必要なのは、『人間が今日まで宗教的なかたちでしか表象しえなかったところの、この道徳力を発見し、それから宗教的象徴という衣を剥ぎ取って、これをいわば合理的裸体として白日の下に示』すことなのである(四四頁)。この、道徳の基本要素――道徳生活の基調をなしている精神状態――を探求するために、デュルケムは道徳を一つの事実として観察することからはじめている。」
中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,66-67p
参考文献リスト
今回の主な文献
中島道男「エミール・デュルケム: 社会の道徳的再建と社会学 (シリーズ世界の社会学・日本の社会学)」
中島道男「エミール・デュルケム: 社会の道徳的再建と社会学 (シリーズ世界の社会学・日本の社会学)」
エミール・デュルケム「宗教生活の基本形態(全) ──オーストラリアにおけるトーテム体系 (ちくま学芸文庫) 」
エミール・デュルケム「宗教生活の基本形態(全) ──オーストラリアにおけるトーテム体系 (ちくま学芸文庫) 」
グレゴリー・ベイトソン 「精神と自然 生きた世界の認識論 (岩波文庫 青N604-1) 」
グレゴリー・ベイトソン 「精神と自然 生きた世界の認識論 (岩波文庫 青N604-1) 」
グレゴリー・ベイトソン「精神の生態学へ (上) (岩波文庫 青N604-2) 」
グレゴリー・ベイトソン「精神の生態学へ (上) (岩波文庫 青N604-2) 」
モリス・バーマン「デカルトからベイトソンへ ――世界の再魔術化」
モリス・バーマン「デカルトからベイトソンへ ――世界の再魔術化 」
真木 悠介 「時間の比較社会学 (岩波現代文庫 学術 108)」
真木 悠介 「時間の比較社会学 (岩波現代文庫 学術 108) 」
汎用文献
佐藤俊樹「社会学の方法:その歴史と構造」
大澤真幸「社会学史」
新睦人「社会学のあゆみ」
本当にわかる社会学 フシギなくらい見えてくる
アンソニー・ギデンズ「社会学」
社会学
社会学 新版 (New Liberal Arts Selection)
クロニクル社会学
社会学用語図鑑 ―人物と用語でたどる社会学の全体像
参考論文
門口充徳「アボリジニ社会から構造主義へ: E・デュルケム著 『宗教生活の原初形態』 の位置づけ」(2012)[URL]
・『宗教生活の原初的形態』の全体的な要約となっている。批判的な言及が多い。
門口充徳「アボリジニ社会から構造主義へ 2: 空間が時間を超越することによる因果律の打破」(2013)[URL]
門口充徳「アボリジニ社会から構造主義へ 3: 土地と親族をめぐるアボリジニ社会の構造」(2014)[URL]
野中亮「『宗教生活の原初形態』における「俗」の位置」(1997)[URL]
酒井健「聖なるものの行方: 社会学研究会とそれ以後のバタイユ」(2013)[URL]
・教会の定義
・バタイユの話は面白い
太田健児「デュルケム後期道徳論における認識論問題:『宗教生活の原初形態』 のカテゴリー論と学説史再編問題を手がかりとして」(1999)[URL]
・主にカテゴリー(範疇)論、カントなどとの関連
ヅァイトリン,山田隆夫(翻訳),「エミール・デュルケーム (VII)-自殺-: 宗教生活の原初形態」(1990)[URLなし]
・デュルケムの主張の理解の補強に使える。ただし、マルクスとの対比が目的であるかのように全体が構成されていることに注意。
内藤莞爾「晩年のデュルケム (上)」(1983)[URL]
内藤莞爾「晩年のデュルケム (下)」(1984)[URL]
内藤莞爾「デュルケムにおける宗教概念の形成 (1)」(1983)[URL]
内藤莞爾「デュルケムにおける宗教概念の形成 (2)」(1984)[URL]
望月哲也「デュルケーム社会理論における宗教社会学の位置」(2000)[URL]
清水強志「デュルケームの 「プラグマティズム」 講義」(2007)[URL]
清水強志「デュルケーム社会学におけるシンボルの役割」(2011)[URL]
寺林脩「デュルケムの宗教論 (序説)」(1980)[URL]
寺林脩「デュルケム宗教論の展開」(1981)[URL]
奥村隆「距離のユートピア──ジンメルにおける悲劇と遊戯──」(2012)[URL]
・ジンメルとデュルケムの比較の参考、集合的沸騰について
堀圭三「デュルケムのジンメル評価について」(1999)[URL]
小川伸彦「デュルケームの儀礼論への一視角 : 二つの規範と「社会」の実在性」[URL]
・『宗教生活の原初的形態』について極めてわかりやすく整理され、定義づけられ、一般化されているいい論文。
椎野信雄「遊びとゲーム: 遊びの貧困の所以 (特集 1 ゲームの時代)」(2011)[URL]
松浦雄介「知と信の社会理論」(2000)[URL]
加藤雄士「認識論のレビューに関する一考察: 人材開発の手法の理解に役立てるために」(2016)[URL]
中村恵子 「構成主義における学びの理論 : 心理学的構成主義と社会的構成主義を比較して」[URL]
沼上幹「われらが内なる実証主義バイアス」[URL]
コメント
この記事へのトラックバックはありません。







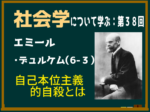
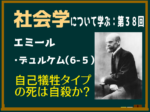

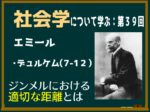
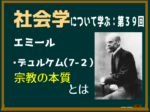
この記事へのコメントはありません。