- Home
- マックス・ウェーバー
- 【基礎社会学第十回】マックス・ウェーバーから「心情倫理と責任倫理」を学ぶ。
【基礎社会学第十回】マックス・ウェーバーから「心情倫理と責任倫理」を学ぶ。
- 2022/1/25
- マックス・ウェーバー
- コメントを書く
はじめに
動画での解説・説明
・この記事のわかりやすい「概要・要約・要旨・まとめ」はyoutubeの動画の冒頭にありますのでぜひ参照してください。
よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m
マックス・ウェーバーのプロフィール

マックス・ウェーバー(1864~1920)はドイツの経済学者、社会学者、政治学者。28歳で大学教授を資格を得て、1905年に「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」を発表した。社会学の元祖ともいわれる。ウェーバーの研究成果はT・パーソンズの構造ー機能理論、A・シュッツの現象学的社会学、J・ハーバーマスの批判理論やシンボリック相互理論等々に引き継がれた。
マックス・ウェーバー、私は大好きです。全学者のなかで一番好きです。文献もなけなしのお金を費やしてできるだけほとんど買うようにしています。
したがって、マックス・ウェーバーに費やす記事の量は他と比較にならないほど多くなるというわけです。文献が手元にあるということは、引用もたくさん増えます(レポートの素材として提供できるので嬉しいです)。
マックス・ウェーバーが終われば次はジンメル、次はパーソンズといきたいです。マックス・ウェーバーだけでも相当時間がかかると思うので、とりあえず隙間隙間にジンメルやパーソンズを進めていきたいと思います(彼らはあまり多くの時間を割く予定がありません)。したがって、記事の発表は断続的になってしまいますがご了承ください。
概要
- ・心情倫理とは:自分の絶対的倫理に対して心情の純粋さをもって行為し、その結果が悪くても責任は「社会や神」にゆだねられると考える倫理的な態度。行為そのものに絶対的な価値を認め、自分の信仰の炎を絶やさないようにすることだけに責任を持つ。例:社会主義革命という目的が大事であり、その結果として逆のこと、たとえば労働者の地位が下がったとしても「世間が愚かだから悪い」といって責任を転嫁する政治家(政治的心情倫理)。あるいは神様が天国で結果については判断してくださる、といって非暴力によって大勢の民が死んでも責任を神にゆだねる宗教的人間(宗教的心情倫理)。
- ・責任倫理とは:行為の結果を予測し、結果について責任を自分でとるべきだと考える倫理的な態度。国家は暴力を正当に独占する政治団体であり、政治とは権力の闘争である。権力とは暴力が控えているものであり、政治には暴力という手段がひかえている。そうした正当な暴力手段ゆえに、父親や商売人や聖人とは違う、特殊な倫理が政治家には要求される。つまり事柄を見極め、結果に責任を負うような責任が要求される。
- ・心情倫理と責任倫理の矛盾:責任倫理に応えようとすると、論理的には心情倫理には応えられなくなる。つまり両者が共存できず、矛盾してしまう。地上の倫理にはこたえられても神の倫理には不可(逆もまたしかり)。例:「国民を守る」という政治家の責任にこたえようとすると「敵兵を殺すことを命じる」必要があり、人を殺すことを命じると「心情倫理(汝、殺すなかれ)」に応えられなくなる。目的が善い(心情倫理)からといって、(悪い)手段を正当化できない。政治家として仕事(事柄、現実、問題)に献身すると、宗教的な倫理には反してしまう。純粋な心情倫理(絶対倫理)の場合は、定言命法的であり、暴力が悪いといえばどんな場合でも、どんな条件でも絶対的に悪いということになる(自分の命をまもるためでも他人の一後をまもるためでも暴力は悪いということになる)。
- ・心情倫理と責任倫理の矛盾を乗り越えるためには:責任倫理を貫く人間が心情的に「我ここに立つ」と言い切るとき、責任倫理と心情倫理が絶対的に対立するものではなくなる。行為の結果を冷静に予見し、価値判断と事実判断を峻別させながら判断し、その結果に責任をもちつつ、たとえ倫理的には悪い手段であったしても、それにもかかわらず!こうするよりほかない!われここに立つ!といえるような心情をもつような場合。単に手段や結果を冷静に検討し、責任をもつだけでは矛盾を乗り越えられない。ロボットのように正確に予測し、その結果にはその正確さ故に責任を持つ、という態度だけではだめ。そこには心情が必要。ただし責任倫理を貫いたとしても、(宗教的に)「魂の救済」は危うくなる。魂の救済を求めるものは「政治」という手段を選ばない(聖人は政治から遠ざかる)。政治は極端にいえば暴力によってのみ解決できる課題を扱うものである。
- ・政治家の資質とは:政治家は情熱、責任感、判断力を資質として要求される。政治とは情熱と判断力の2つを駆使しながら責任感をもって行うものであり、心情倫理的、道徳的にくじけずに、それにもかかわらず!といって粘り強く不可能と思えるようなことにもアタックしていくものである。そういうことができる政治家が「天職としての政治家」である。
前提概念の整理
基本的に前の記事で学んだことを前提としています。軽くおさらいしておきます。出典等は前の記事を参照してください。
【第一回】マックス・ウェーバーの価値判断や価値自由とははなにか?
【第二回】マックス・ウェーバーの「理念型」とはなにか(概略編)
【第三回】マックス・ウェーバーの『職業としての政治』から「支配の三類型」を学ぶ。
政治
政治(せいじ):・広義には「自主的に行われる指導行為」であり、狭義には「政治団体(国家)の指導、またはその指導に影響を与えようとする行為」近代国家における政治では「権力の分け前にあずかり、権力の配分関係に影響を及ぼそうとする努力」という意味で使う。
例:「女性(あるいは男性)の権利」を保護するような「法律」を作るために国会議員として立候補して当選し、さらに政党内で多数派の派閥を作るために権力闘争をする。この闘争に勝った結果、反対する人に対しても過半数の意見を押し付けることができる。どういう目的で権力を使うかは政治家による。ペットの保護、国の防衛、憲法の改正、困窮者の保護、労働者の保護、NHKの解体等々。
国家
国家(こっか):・「ある一定の領域の内部で正当な物理的暴力行使の独占を実効的に要求する人間共同体」「正当な暴力行使という手段に支えられた、人間の人間に対する支配関係」
権力
権力(けんりょく):・「命令行為において、その行為に参加している他者の抵抗を排してまで、自己の意思を実現しようとする可能性」
政治家は権力の追求、つまり闘争が本領である
「闘争は、指導者であれその部下であれ、およそ政治家である以上、不断にそして必然的におこなわざるをえない。しかし官吏はこれに巻き込まれてはならない。党派性、闘争、激情──つまり憤りと偏見──は政治家の、そしてとりわけ政治指導者の本領だからである。」
(マックス・ウェーバー『職業としての政治』,41P)
政治家の信念
政治家の信念(信仰、価値理念)は政治家ごとに異なる。
「ところで政治家がそのために権力を求め、権力を行使するところの『事柄』がどうあるべきかは信仰の問題である。政治家が奉仕する目標は、ナショナルなこともあれば人類的なこともある。社会的で倫理的なこともあれば、文化的なこともあり、現世的もしくは宗教的なこともある。…日常生活の些細な目標に仕えようとする場合もある──が、いずれにせよ、そこにはなんらかの信仰がなければならない。」
マックス・ウェーバー、『職業としての政治』、82P
例:ある政治家は「国の文化」を守るべきという信念・価値理念をもっていて、そのために権力を求める。たとえば国会議員になり、文化を守るような法案を提出する。またその法が可決されるために、派閥を増やして権力を求め、闘争する。
・他の政治家はとにかく「国の防衛」を重視するかもしれないし、「女性の人権」を重視するかもしれない。
・私的な利害関心、信念から出発して、権力闘争を通して多数派となり、それが「公益」としてみなされるようになる。
・国家公務員などはプライベートを押し殺し、ひたすら命令を聞いて(政治家が公益と定めた法律を守らせるなど)公に仕える必要があるが、国会議員などの政治家は個人ごとの利害関心が重要になってくる。政党指導者の部下は指導者とは違う卑俗な目的(単なるお金や名誉欲など)があるかもしれない。指導者はどうやって命令に従うマシーン(装置、スタッフ)を操作するのか?(合法的支配を前提としたカリスマ支配によってやる気を与え従わせる)
・政治家は公共の立場、つまり国民全体の利益に奉仕しなければいけないが、まずは政治家個人が「何が国民の利益になるか」を個別的・私的に考え、掲げ、他の政治家と闘争を通して公共的なものが形成されていく。
例:NHKをぶっこわすと主張した政治家がいた。この政治家が私的に重要と信仰している事柄がNHKの解体だ。これが公共の利益になるかどうかは、選挙を通じて、あるいは法案が議会で通るかどうかで、権力闘争を通して形成される(国会議員になることはゴールではなくスタート地点)。政治は「正しい」から「法律」になるのではなく「多数派を権力闘争を通して形成できる」から「法律」になり、「法律」だから「正しい」ことになる(合法的支配)。民主主義の原則。国会議員は国民の代表であり、その代表の過半数は国民の総意であり公益。
政治と暴力の関係
・政治は権力を獲得しようとする行為であり、また権力は「暴力手段」に基づいている。
例:法律を国民が守るのは、守らなければ最悪の場合死刑になるからである。死刑とは最大の暴力である。あるいは敵国からの侵略に対して行う防衛も暴力である。ソ連などではスパイだと政治家に判断された場合は殺された歴史もある。あるいはナチスドイツの政治家ははユダヤ人を虐殺を指示した。ヒトラーは自分の信念に基づいて権力を獲得し、暴力を手段として行使した。
・暴力を正当な手段として独占して保有しているのが「国家」である。国家とは政治団体である。
・家庭内で両親は暴力を手段として保有していることがあるが、それは法律に違反する非正当的手段である(合法的支配ではなく伝統的支配)。しかし父親は家庭内で一番の暴力手段を有しているので一番の権力をもっていることが多い。つまり権力は暴力手段に基礎づけられている。
・「政治」とは極端にいえば「暴力」によってのみ解決できる課題にとりくむことである
・たとえば政治における権力闘争のトップにいるもの、日本で言うところの総理大臣は暴力行使の決定権をもつ(例:自衛隊の最高指揮監督権を保有している)。戦争の開始を決めるのも政治家である。民間人は刀や拳銃を基本的に所有できない(国の許可がいる)。
マックス・ウェーバー関連の記事
・以前の記事
【基礎社会学第四回】マックス・ウェーバーの価値判断や価値自由とははなにか?
【基礎社会学第六回】マックス・ウェーバーの「理念型」とはなにか(概略編)
【基礎社会学第八回】マックス・ウェーバーの『職業としての政治』から「支配の三類型」を学ぶ。
【基礎社会学第十回】マックス・ウェーバーから「心情倫理と責任倫理」を学ぶ。(今回の記事)
・以後の記事
【基礎社会学第十二回】マックス・ウェーバーの『職業としての政治』から「職業政治家」を学ぶ。
【基礎社会学第十四回】マックス・ウェーバーの社会的行為の四類型とはなにか
【基礎社会学第十六回】マックス・ウェーバーの「理解社会学」とはなにか
【基礎社会学第十八回】マックス・ウェーバーの「官僚制」とはなにか
【基礎社会学第二十回】マックス・ウェーバーの「職業としての学問と神々の闘争」とはなにか
【基礎社会学第二十二回】マックス・ウェーバーの「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」とはなにか
心情倫理と責任倫理
政治家と商売人の求められる倫理の違いとは
・ある商売人が自分は価値があると思って宝石を客に高く売った。しかしその宝石は二束三文だった。この商売人にはどんな責任があるか。
・ある政治家がある国が自国を侵略するという情報を事前に仕入れ、そのある国を先に襲撃した。しかしその情報はデマだった。この政治家にはどんな責任があるか。
商売人と政治家の責任の「質」は同じか。政治家には特別な倫理性や責任が要求されるか。
・政治家は「暴力」に関わることを仕事としている以上、特別な倫理・責任が要求される。
「政治が権力──その背後には暴力が控えている──というきわめて特殊な手段を用いて運営されるという事実は、政治に対する倫理的要求にとって、ほんとうにどうでもよいことだろうか」
(マックス・ウェーバー『職業としての政治』,85P)
「人間団体に、正当な暴力行使という特殊な手段が握られているという事実、これが政治に関するすべての倫理問題をまさに特殊なものたらしめた条件なのである。」
(マックス・ウェーバー『職業としての政治』,97P)
・政治家特有の特殊な政治倫理とはなにか
→責任倫理
責任倫理とはなにか
責任倫理(責任倫理):・予測しうる結果について責任を自分でとるべきだと考える倫理的な態度のこと
「…倫理的に方向づけられたすべての行為は、根本的に異なった二つの調停しがたく対立した準則の下に立ちうるということ、すなわち『心情倫理』に方向づけられている場合と、『責任倫理』に方向づけられている場合があるということである。心情倫理(Gesinnungsethik)は無責任で、責任倫理(Verantwortungesethik)は心情を欠くという意味ではない。もちろんそんなことを言っているのではない。
しかし人が心情倫理の準則の下で行為する──宗教的に言えば『キリスト者は正しきをおこない、結果を神に委ねる』──か、それとも、人は(予見しうる)結果の責任を負うべきだとする責任倫理の準則に従って行為するかは、底知れぬほど深い対立である。]
(マックス・ウェーバー『職業としての政治』,89P)
一般企業の例を考えてみる
・一般企業の例
・たとえばある会社で「顧客を合法的に騙して100万円の利益をあげろ」と社員が言われたとする
・ある社員は自分の信念に基づいて、それは「よくない」から「しない」という選択ができる(それで解雇されたとしても損をするのは基本的に自分だけ)。
・会社員としての倫理に従えば、利益を上げることで責任を果たせるかもしれない。しかし、自分の心情を貫き通して「NO」ということも可能。
・ある国に侵略を受けて、報復を行うかどうかを最終的に一人の指導者が決めることになるとする
・ある政治家(特に政治指導者)が自分の純粋な心情・信念に基づいて、「暴力はよくない」から「報復しない」という選択をしていいのか。
・報復をすると、しないよりも国民の大勢が死ぬ、というような場合の予見に基づいた理由付けとは違う。結果にかかわらずとにかく暴力はよくないという純粋な態度。
・自分の絶対倫理を貫き通した場合、損をするのは自分だけではない。しかもそれは単に金銭による損害ではなく、暴力手段による生命喪失に関わる(地上においては取り返しがつかない)。国民の大勢が死ぬ。少なくとも地上において国民は苦しむ。地上で死んでも神の国で救われるといって責任を神に委ねることが政治家の倫理といえるか。政治家がもつべき倫理とは?商売人との違いは?
政治家は暴力、ここでいう報復行為によって起きる「結果」を予測し、それに責任をもたなければならない。報復を行わない場合どうなるか、また行った場合どうなるかを予測して、判断し、結果に責任をもつ必要がある。
結果に関わらず個人的に暴力や嘘はよくないからしない、といった純粋な心情的態度は専業としての政治の領域外にいる「聖職者」や「会社員」には許されても「政治家」には許されないのではないか。
心情倫理とはなにか
心情倫理(しんじょうりんり):・自分の絶対的倫理に対して心情の純粋さをもって行為し、その結果が悪くても責任は「社会や神」にゆだねられると考える倫理的な態度。行為そのものに絶対的な価値を認め、自分の信仰の炎を絶やさないようにすることだけに責任を持つ。
政治的心情倫理と宗教的心情倫理
政治的心情倫理
政治的心情倫理(せいじてきしんじょうりんり):・政治的な領域において、倫理的に「善い」目的を遂行するためにはどんな「悪い」手段でもかまわないという態度が冷静な事柄への予測や責任を伴わずになされる場合。例:社会主義革命をしようとして逆に労働者の地位が下がったとしても、それは世間が愚かだからだといって責任を回避。暴力による革命の肯定(目的故にあらゆる行為が正当化)。
政治的心情倫理家の例:サンディカリスト
サンディカリストは日本語では労働組合主義者などといわれる。急進的なサンディカリストの場合は、革命によって資本主義体制を覆そうとすることを目的とする。
例:サンディカリストが社会の不公平を正すという倫理を絶対的な価値として信仰していると仮定する。その革命をしようとした結果、意図とは正反対に社会の不公平が進もうとも、「世の中が悪い」だとか「神が悪い」だとかいって責任を取ろうとしないケース。
仮にサンディカリストに向って、その革命のやり方はむしろ労働者の地位を低下させる可能性が高いと批判しても聞く耳を持たない。心情倫理家は心情の純粋さのみを重視し、また社会秩序の不正に対する抗議の炎を絶やさないことのみに責任を感じる。また目的のための手段を問わない(暴力による革命も正当化される)。
「確信をもったサンディカリストに向かって、君の行為の結果は反動のチャンスを増し、君の階級に対する圧迫を強め、階級の上昇を妨げるであろうと、どれほど噛んでふくめた説明をしてみても、彼には何の感銘も与えないであろう。サンディカリストは、純粋な心情から発した行為の結果が悪ければ、その責任は行為者にではなく、世間の方に、他人の愚かさや──こういう人間を創った神の意志の方にあると考える。
責任倫理家はこれに反して、人間の平均的な欠陥のあれこれを計算に入れる。つまり彼には、フィヒテがいみじくも語ったように、人間の善性と完全性を前提してかかる権利はなく、自分の行為の結果が前もって予見できた以上、その責任を他人に転嫁することはできないと考える。これこれの結果はたしかに自分の行為の責任だと、責任倫理家なら言うであろう。心情倫理家は、純粋な心情の炎、たとえば社会秩序の不正に対する抗議の炎を絶やさないことにすることにだけ『責任』を感じる」
(マックス・ウェーバー『職業としての政治』89-90P
宗教的心情倫理
宗教的心情倫理(しゅうきょうてきしんじょうりんり):・「福音の絶対倫理」ともいわれるもので、無差別な愛の倫理を貫くことで暴力などの倫理に反する手段の一切否定し、政治とも関わらないような態度。例:キリストや仏陀のような聖人。山上の垂訓のような絶対倫理。
宗教的心情倫理家の例:キリスト
福音の絶対倫理(山上の垂訓)に従って行為するタイプ
山上の垂訓(さんじょうのすいくん)は定言命法的で、仮言命法的ではない。つまりもし命を保持するためなら嘘をついてもよいというような曖昧なものではない。いかなる場合でも嘘をついてはいけないという「絶対倫理」である。目的によって手段が正当化されない。
例:「汝のもてるものをそっくりそのまま与えよ」、「汝のもうひとつの頬も向けよ」、「悪しきものに力を持って抵抗するな」など
・ウェーバーは宗教的心情倫理家は品位があると肯定している。
・しかしキリストのような聖人としての生き方を徹底することは難しい(特に神々の争いの時代では宗教は力を失いがち[脱魔術化の時代])。政治外ですら難しいのに、政治においてそうした生き方をすることはもっと難しい。矛盾せざるを得ない。「悪しきものに抵抗してはいけない」という倫理に絶対的に従うなら、侵略してきた兵士に無抵抗で国民を惨殺されてしまうかもしれない。聖人は「善からは善のみ、悪からは悪のみが生まれる」と考えるが、現実は逆のことが多い。
・善からは善が生まれる、現実には善が悪を生みだすことがあろうとも、「神の国において善は保障される」というような考えは「あの世の倫理(没世界的倫理)」である。罪のない子供が虐待されるのはなぜか?善人がなぜ強盗に殺されるのか?赤子はなぜ産まれた途端に死ぬのか?地上では一見、善からは善が生まれないように見える(現実は逆のことが多い)。しかし神の国では善が保障されると信じる。そう信じ抜いて貫いたものは聖人となる。聖人は政治に参加しない。
「人は万事について、少なくとも志の上では、聖人でなければならぬ。キリストのごとく、使徒のごとく、聖フランチェスコらのごとく生きねばならぬ。これが掟の意味である。これを貫き得たときこの倫理は意味あるものとなり、[屈辱ではなく]品位の表現となる。
そうでないときは、逆である。なぜなら、無差別な愛の倫理を貫いていけば、『悪しき者にも抵抗(てむか)うな』となるが、政治家にはこれと逆に、悪には力もて抵抗え、しからずんば汝は悪の支配の責めを負うにいたらん、という命題が妥当するのである。
(マックス・ウェーバー『職業としての政治』87P)
心情倫理と責任倫理の対立
目的の正当化は可能か
・心情倫理と責任倫理は論理的には矛盾(対立)する。
・目的は手段を正当化できない。政治的心情倫理家の言い分は破綻する。
例:倫理的に善い目的のためなら倫理的に悪い手段を使っても善いとなるのか。宗教的心情倫理家の立場で言えば、いかなる場合も悪い手段を使うことはできない。しかし現実は暴力はいけない、嘘はいけないといいながらも、国民を守るためには武力で対抗するしか無いといったように目的のために手段が正当化される。聖人でないと地上の悪になかなか耐えられない (心情としては立派でも地上の悪に耐えきれず、暴力をなくすために暴力をと唱える)。
政治的心情家の場合は善い「目的」のためだから「手段」が「悪い」ものでも善いと正当化する。例:社会主義革命のために「暴力」的手段を用いる。「戦争」を長引かせる選択をする。
「この世のどんな倫理といえども次のような事実、すなわち、『善い』目的を達成するには、まずたいていは、道徳的にいかがわしい手段、少なくとも危険な手段を用いなければならず、悪い副作用の可能性や蓋然性まで覚悟してかからなければならないという事実、を回避するわけにはいかない。また、倫理的に善い目的は、どんな時に、どの程度まで、倫理的に危険な手段と副作用を『正当化』できるかも、そこでは証明できない。」
(マックス・ウェーバー、『職業としての政治』、90-91P)
神々の争いの時代では聖人のように生きるのは難しい
純粋な心情倫理家の場合、目的が「善い」ものなら手段が「悪い」ものでもいいということにはならない(キリスト教国家はよく罪に対する矯正手段として暴力を正当化する)。つまり目的が手段を正当化することはできない。武力を放棄し、常に正直者でいなければならない。このような純粋な態度だけで政治を行うことは難しい。このような態度でいられる人物は聖人のようなタイプであり、聖人が政治を行うことは原理的に矛盾している。なぜなら政治は原則的に暴力を手段とするからである。
自分の魂や他者の魂を救済しようとした「聖者」は「政治」という手段をとらなかったという。「政治」とは極端にいえば「暴力」によってのみ解決できる課題にとりくむことであり、自分の魂を救おうとするものが「政治家」になろうとすると、矛盾が生じる。暴力は良くないと思っている政治家が暴力を手段として使わなければならないときがきたらどうするべきかということが問題になる。
ウェーバーは「非政治的心情倫理」のほうは品位があるとして一定の評価したが、近代は「神々の闘争」の時代であり、ひとつの神を信じて心情倫理に徹するのはなかなか難しいとした。たしかに暴力を振るわれても非暴力で接し、自分が財産をもっていたら人に差し出し、どんなに不利になろうとも嘘はつかないといったような徹底的に結果にかかわらない心情倫理に徹するのは常人では特に難しい。宗教的な力を失いつつある近代、つまり脱魔術化した時代においてはさらにより一層、神を信じて心情倫理に徹するというのは難しいだろう。カントの定言命法に生きる難しさと同じように、「なるほどすべきです、しかしできません」となる。ニーチェにいたっては「神は死んだ」といった。
良心の要請と責任の要請の矛盾
・良心の要請と責任の要請が矛盾する場合どうしたらいいのか。
・政治家には国民を守るという責任(地上の倫理)がある。良心(神の倫理)はそのための手段として「悪い手段はとるな」と要請する。しかし悪い手段をとらなければ守れない場合が多い。国民を守っても倫理的に悪いことをすることになり、国民を守らず倫理的に善いことをしたら責任をとれなくなる。
・地上の倫理(不正は暴力を持ってでも正さないといけない、悪からは善が、善からは悪が生まれることが多い)を選ぶか、神の倫理(どんな場合でも暴力はいけない、善からは善が、悪からは悪のみが生まれる、神に委ねなさい)を選ぶか。二者択一しかないのか。
・倫理的な要請(理想政治)をすべて回避して、ひたすら政治的な現実問題(現実政治)にのみ取り組めばいいのか。たとえば国民を守るために悪いことをしただけだ、といって責任を放棄する態度は「責任倫理」ではなく「政治的心情倫理」である。人は完全ではない。間違った人を投獄したり、間違った情報で戦争を起こすこともある。人間が完全であれば手段を正当化できるかもしれないが、人間は不完全であり、現実は不条理(予期せぬことが起こる)である。兵士が指導者の意思に反して裏切る(あるいはミスを犯す)かもしれない。
・倫理の要請に従う方法は、倫理的に善い行為をすることだけではないと考えてみる。倫理的に悪い行為をそれでもしなければいけない理由がある、と言えるほどまでに事柄を予見し、その結果に責任をとろうとする態度に倫理性が生じうる。
責任という点に倫理性を見出す
・自分の行為に責任をもつこと、この責任という点に倫理性を見出す
・責任をもつためには、さまざまな事柄(ザッへ)を予見・予測する必要がある。ある行為をした結果、どのようなことになるのか、あるいはしなかった場合、どのようなことになるのか(随伴結果)。そうした「客観的可能性」を元に冷静に「判断」し、それでもなお「悪い手段をとるべきである」と決断し、かつその結果に「責任」をとるような態度に倫理性が生まれる。つまりその限りで良心の要請に応えていることになる。
・しかしそれでもなお、「魂の救済」を政治家は期待できない。そうした責任倫理をもってしても、やはり聖人からすれば「NO」である。しかし「政治家」としては評価できるような人物像である。「自分の魂の救済と他人の魂の救済を願うものは、これを政治という方法によって求めはしない(職業としての政治,100P)」
政治家の資質
情熱、責任、判断力
・政治家には「情熱」と「責任」と「判断力」が資質として必要とされる
・この「情熱」は「事柄(ザッへ)」への情熱的献身という意味である。事柄とは仕事、問題、対象、現実といった”地上”の事柄である。事柄は科学的に分析することがある程度可能です。死刑制度を採用したら犯罪がどのくらい減るか。公共事業で雇用がどのくらい増えるかなどの予想。この行為をしたら神に救われるかどうか、といったものは事柄というより非現実・宗教の領域。
・事柄を司るのは神ないしデーモンである。
・したがって、事柄を通じて神ないしデーモンに対しても献身することになる。※事柄が何であるべきかは「信仰」に属する領域であり、したがって「神ないし悪魔」(価値)を選ぶということである(自分の神は他人からすれば悪魔でありうる)。たとえば女性の権利、男性の権利、子供の権利、老人の権利、外国人の権利、そのどれもすべてを平等に優遇することは難しい。選択せざるをえない。男性だけの権利を異常に優遇すれば、女性からしたら「悪い価値(悪魔)」となりうる。
「政治家にとっては、情熱──責任感──判断力の三つの資質がとくに重要であるといえよう。ここで情熱とは、事柄に即するという意味での情熱、つまり事柄(ザッへ)[『仕事』『問題』『対象』『情熱』]」への情熱的献身、その事柄を司っている神ないしデーモンへの献身のことである。(『職業としての政治』77P)」
「『悪魔は年をとっている』、『だから悪魔を理解するには、お前も早く年をとることだ』(101P)」
→年をとる≒修練によって現実を直視でき、生の現実に耐え、内面的に打ち勝つ能力をもつようになること。暴力手段(悪魔)がどういうものかを見極める。だからこそ副業で時間がなく、専門知識もない政治家は難しい(副業ではなく「職業としての政治家」である必要性がある)。政治を第一として生きるもの。
責任生へと結びつく情熱
・どんな情熱が求められるのか。
→「責任性」へと結びついた情熱が求められる。単なる情熱だけで責任感が伴わない場合、単なる心情倫理化になる。
例:国民の生命を守りたいという純粋な情熱だけではだめで、国民の生命を守る結果として他国の人間の生命を奪うこともある。そういった結果への責任をもつことが大事。無責任なロマンティストは政治家としての資質がない。革命を叫ぶだけで、その結果としてどうなるのか冷静に予見すらできない人々。
「実際、どんなに純粋に感じられた情熱であっても、単なる情熱だけでは充分でない。情熱は、それが『仕事』への奉仕として、責任性と結びつき、この仕事に責任性が行為の決定的な基準となった時に、はじめて政治家を創り出す。そしてそのためには判断力──これは政治家の決定的な心理的資質である。──が必要である。すなわち精神を集中して冷静さを失わず、現実をあるがままに受け止める能力、つまり事物と人間に対して距離を置いて見ることが必要である。」
(マックス・ウェーバー、『職業としての政治』、78P)
「しかし、また,責任の倫理は、単に目的合理性の立場に止まるものではない。純粋に目的合理的な行為のうちには、目的と手段とを考量することによって、逆に与えられた手段により到達可能な目的だけをえらぶという、じっさいは無方針な機会主義に堕するという危険もまた存在するのである。責任倫理の立場は、このように現実適応とは異るものである。それは地上の倫理である限り、現実の事態に即するものではあるが、しかもそのことを通じて、絶対的な倫理のよびかけにこたえる(antworten)ものである。あらゆる結果について予測し、この予測にもとづいて手段をつくすのも、結果の重大さを意識することによって、このよびかけに対してもっとも充実したかたちで責任をとろうとするときに必要とされることなのである。」
「職業のエートス」、川瀬謙一郎、102P
「政治とは、情熱と判断力の二つを駆使しながら、堅い板に力をこめてじわっじわっと穴をくり貫いていく作業である。もしこの世の中で不可能事を目指して粘り強くアタックしないようでは、およそ可能なことの達成もおぼつかないというのは、全く正しく、あらゆる歴史上の経験がこれを証明している。
しかし、これをなしうる人は指導者でなければならない。いや指導者であるだけでなく、──はなはだ素朴な意味での──英雄でなければならない。そして指導者や英雄でない場合でも、人はどんな希望の挫折にもめげない堅い意思でいますぐ武装する必要がある。そうでないと、いま、可能なことの貫徹もできないであろう。
自分が世間に対して捧げようとするものに比べて、現実の世の中が──自分の立場からみて──どんなに愚かであり卑俗であっても、断じて挫けない人間。どんな事態に直面しても『それにもかかわらず!(デンノッホ)』と言い切る自信のある人間。そういう人間だけが政治への「天職」を持つ。」
(マックス・ウェーバー『職業としての政治』,105-106P)
その他考量
動画にのせるのには分量的にちょっと、というな要素をここで扱います。ウェーバーを学ぶという趣旨とはすこしズレているような要素もここに分類しています。
私が社会学を学ぶ理由は学ぶことに目的があるわけでも、テストでいい点数をとるためでもありません。実際に応用できるかどうかが最も重要な要素になります。ウェーバー的に言えばそれを理念型として現実を分析するツールにすることができるかが重要なわけです。つまり自分の身近な現実と照らし合わせてウェーバーの理念型を理解する必要が求められます。
責任を神に委ねる、とは?
「責任を神に委ねる」という言葉の意味がいまいち理解できない。
ウェーバーの言葉でいうと「サンディカリストは、純粋な心情から発した行為の結果が悪ければ、その責任は行為者ではなく、世間の方に、他人の愚かさや──こういう人間を創った神の意思の方にあると考える(『職業としての政治』90P)」で例がでいる。
サンディカリストは日本語でいうと労働組合主義者ともいわれ、急進的な場合は革命を通じて労働組合によって資本主義体制を倒そうとする立場のことである。革命によって逆に労働者の地位が低くなったとしても、それは世間が愚かであるか、そうした愚かな人間を創った神のせいだ、と責任を転嫁するというわけである。サンディカリストは目的のためにはいかなる手段をもとるといったような態度であり、その手段によっていかなる結果が生じるかを冷静に考えることができないという。つまり、結果に責任を持たない態度である。革命をしなければいけないという責任感だけはもっている。ウェーバーはこうした政治的な心情倫理を批判した。
たとえば子供が事故で死んだとする。この責任は一体誰にあるのだろうか。この事故が両親の不注意でもなく、子供の不注意でもないといったようなケースがあるはずだ。たとえば天災で死んだといったようなケースもそうかもしれない。あるいは両親が子供を虐待して死んだ場合を考えてみる。両親は子供を殴ったら死ぬということを予見せずに、子供は自分の所有物だという信念に基づいて結果に責任をもとうとしないかもしれない。あるいは「仕事先のストレスがあった」と他者に責任を転化したり、「こんな暴力性をそなえさせた神様が悪い」と責任を転嫁するかもしれない
家庭内においては「暴力」というものは「正当な手段」ではない。日本の法律では家庭内の暴力は「犯罪」であり、「不正な手段」である。しかし政治においては「正当な手段」として暴力が存在する。たとえば中国が侵略してきたら政府は自衛隊という「暴力」をまさに「自衛の手段」として正当に使用するだろう。あるいは国内の犯罪を減らすために正当な手段として国民を「死刑」にする。政治を行うもののみが「死刑」の判断及び行使ができるのであり、政治をおこわない非政治家はそんな権限を有していない。
このように「暴力」が政治において「正当な手段」であるからこそ、「政治」には「特別な倫理」が要求されるはずだとウェーバーはいう。たしかにそうだ。純粋な心情倫理家に政治を任せるのは少し怖い。社会主義の実現のために、この理念に賛同しない国民は全員死刑にする、といったことも究極的な手段としてとることもありうる。
『キリスト者』は正しきをおこない、結果を神に委ねる」という言葉が出るように、心情倫理にはキリスト教の例が出されている。キリスト教では「嘘をついてはいけない」し「人殺しをしてはいけない」。こうしたものは福音の絶対倫理といわれる。
もし「魂を救済」しようとすれば、このような倫理に従う必要がある。「汝の敵を愛せよ」、「裁くな、裁かれないためである」、「人からしてもらいたいとあなたが望むことを、人々にしなさい」等々のいわゆる「山上の垂訓」に従って生きる必要がある。
しかし「政治家」が自分の魂を救済しようとすると、こうした倫理に矛盾するようなことも手段としてとらなければいけないこともある。ある政治家がある国の侵略を受けた時に、聖書では「汝の敵を愛せよ」と書いてあるので武力を一切行使しません、などといったらどうなるだろうか。その結果として多くの国民が虐殺され、他国に支配されてしまうかもしれない。しかしそうした「結果」に責任を取らないのが「心情倫理家」なのである。
こうした宗教的な例は政治的心情倫理家というより、宗教的心情倫理家に近い。そもそも、宗教的心情倫理家は政治から遠いところ、俗世にいることが多い。ウェーバーは例として、キリストや仏陀を挙げている。
無差別の人間愛と慈悲の心に溢れた偉大な達人たちは、ナザレの生まれであれ[キリスト]、アッシジの生まれであれ[聖フランチェスコ]、インドの王城の出であれ[仏陀]、暴力という政治の手段を用いはしなかった。彼らの王国は[この世のものにあらず]ではあったが、それでいて彼らは昔も今もこの世に影響を与え続けている。[トルストイの描く]プラトン・カラタエフやドストエフスキーの描く聖者の姿は、今なお、この人類愛に生きた達人たちの最も見事な再現である。自分の魂の救済と他人の救済を願う者は、これを政治という方法によって求めはしない。政治には、それとはまったくべつの課題、つまり暴力によってのみ解決できるような課題がある。
100P
最後に「責任を神に委ねる」を少し検討する。これは政治的心情倫理というより、宗教的心情倫理に近い。
ヨブ記によると、この世の富と幸福を享受していた神の僕たる義人ヨブは、神によって悪魔の手に委ねられ、一瞬のうちに破滅させられてしまう。ところが、理由も分からぬまま苦難に晒されるのに、ヨブは神を呪うどころか神の与えたものを神が取り上げたまでだと叫んで大地に伏し、神を賛美するこのヨブの受難から、ゾシマは「蜉蝣(かげろう)の如き地上の姿が、永久の真理と相接触」する「神秘」を見いだす。どれほどの悲しみと悲惨にまみれようとも、「一切を赦す神の真理」があるかぎり、それは「静かな悦びに満ちた感激」へと変わっていく。なぜなら「一切のことは大海のようなものであって、ことごとく相合流し相接触しているが故に、一端にふれれば他の一端に、世界の果てまでも反響するからである」。ゾシマは、罪あるままの人間を愛せよ、歓喜の情をもって小鳥にさえむかって自分の罪を赦してくれと祈り、「あらゆる事物を愛すれば、やがてそれらの事物の中に神の秘密を発見するであろう」と説く。このロシアの聖人にはヴェーバーの次のように評価が当てはまるだろう。「救いの宗教にあっては、無差別主義的な慈悲の持ち主たる達人たちの深くかつ静かな至福感はつねに、自分をも含めて、一切の人間は生まれながらに不完全なものなのだ、という心あたたかい知識とひとつに溶け合っていた。」聖人にとって、すべての人間は罪を負った愛の共同体で結ばれている。そして、地上の出来事と神の真理は断絶されていない。現世におけるいかなる苦難も愛と赦しの神への道に開かれている。むしろ苦難を通りぬけた先に「神の真理」がある。ここに描かれているのは、キリストの受難、あるいはヴェーバーが第ニイザヤに見たような、「他人の罪のために罪なき犠牲として自由意志によって死につく神の僕」というテーマの変奏である。
マックス・ヴェ一バ一における責任倫理と政治的心情倫理──ドストエフスキ一『カラマ一ゾフの兄弟』を手がかりに── 内藤葉子
これはこの世の不合理の責任はどこにあるのか?という問題につながっている。
『カラマーゾフの兄弟』では登場人物であるイヴァンが大審問官を通して「罪のない子供が虐待で死ぬ」例を挙げて世界を創った神を責め立てている。
たしかに罪のない子供が虐待で死ぬのはこの世の不合理かもしれない。なぜ死ななければいけなかったのか、それを完璧に説明できる人がいるのだろうか。
ヨブ記の伝えたところを理解しようとすると、神様は人間に命を与えたのであり、また与えたものを取り上げただけであると。ヨブ記では神がヨブの信仰を確かめるために、正しいことしかしていないヨブにあえて苦難を味あわせ、それでも神を信仰するかどうかを実験した。財産が没収されて皮膚病(当時における社会的な死に等しい)になったヨブは、「神から幸福を頂いたのだから不幸もいただこう」といって最後まで神を信仰したそうだ。
つまり、神への信仰が目的であり、その結果として「財産が没収されて皮膚病」になろうが関係がないということだ。もし財産がなくなって自分が病気で死んでしまうから信仰をやめるなら、それは真の心情倫理ではなくなってしまう。結果に関わらず目的を信仰し、その信仰の保持のみに責任を持つ態度こそ心情倫理だからだ。
こうした聖人的な態度が政治の外で個人的に行われるならまだしも、政治の内で個人的に行われると大変なことになりそうだ。もし総理大臣が宗教的な心情倫理の純粋型としての聖人だったら日本は大混乱になるかもしれない。国の侵略に対して非暴力で接し、連続殺人犯に対しても許しを与えるように法務大臣に通達してしまうかもしれない。その結果として多くの国民が死ぬことになっても、結果には責任を持たないからだ。地上の法律など知ったことか、となるかもしれない。
「神に委ねる」という態度はまさにこうした「聖人的な態度」ではないだろうか。政治家が「大衆は馬鹿だから俺たちの崇高な革命の目的をわかっていない」というときの責任転嫁とは少し違う。どちらも心情倫理だが、政治家の場合はあえていうなら相対的倫理であり、宗教家の場合は絶対的倫理である。政治家の場合は革命のためなら、悪い手段をとるといったように正当化されてしまう。
自分の信仰に基づいた結果どうなろうとも、判断するのは他人でも自分でもなく「神」であるというのがポイントだ。結果として国が侵略されようとも、非暴力を貫いたという点で「天国では神には評価される」かもしれない、と神に委ねている態度だ。ヨブ記ではヨブが悪い、いや悪くないと人間同士で討論しても結論はなかなか出なかった(最終的には自分の潔癖を証明できないヨブが悪いと仲間によって結論づけられた)。人間より神のほうが賢いので、神より優れた判断を人間が出せるはずないというのものある。神はヨブにいった。「わたしが大地を据えたとき、お前はどこにいたのか」と。
ルターの話でも同じような話が出てきた。カントにも通じる話だが、人間ごときがこの地上で「善悪を判断」する能力がそもそもあるのか、という話になる。できることはそういう倫理判断ではなく、神を信じることのみであり、信仰が重要であるとう話につながる。そして信仰するかどうかより前にすでに、つまり人間が産まれるより前に神から救済されるかどうか決まっているというのが「カルヴィニズム」である。人間ごときが人間に赦しを与えたりすることができるのか?という問題から発している。免罪符というお金で罰を免れるようなカトリック教会の行為が批判された背景でプロテスタントは誕生している。
「だが、それにもかかわらず、神を不義だとするこの思い、理性や自然の光をもってしては何とも抗弁しがたい論拠を突きつけられて証明されてきたように思えるこの見解も、ひとたびわれわれが福音の光に接し恩恵の認識に支えられるなら、たちどころに雲散霧消する。それによってわれわれは、神なき物はなるほど肉においては栄えていても、霊魂においてはすでに滅んでいることを教えられるからである。そして、これまで述べてきた厄介な問題をたった一言で一刀両断にする簡単な解決法がある。それは次のようなものである。われわれの生の後にはもう一つの、生がある。そこではこの世で罰を受けず報酬(むくい)られなかったことが必ずや罰せられ報酬を受けるだろう、なぜなら現在の生は未来の生の単なる先触れ、いや始まり以外の何ものでもないからだ、と。
さて、こうした聖言(みことば)のうちに輝き信仰によって与えられる恩恵の光が、過去何百年来追求されつつ解決されなかったあの難問をいとも容易に解決し、ものの見事に決着を与えた。だとすると、どうであろう?われわれが聖言と信仰の光とに支えられる時期が過ぎ去り、物事の真相と神の荘厳さとがそのあるがままの姿で開示されるとき、一体何が起こると貴君(あなた)はお思いか。自然の光が解明できなかった問題を恩恵の光があれほどたやすく解いたのであるから、今度は、聖言の光ないしは恩恵の光の解けない問題を、栄光の光が一挙に解明してくれるにちがいない。貴君はそうは思わないだろうか。
ここで私が世間一般に行われている立派な区分法にしたがい、自然の光、恩恵の光、栄光の光の三つを分けることをお許し願いたい。さて、自然の光によっては、善人が苦しみ悪人が栄えるなどといったことが、どうして義しいのかはよく分からない。が、恩恵の光がそれに解決を与えてくれる。しかしながら、では一体、神はどうして最善の力をつくしても罪咎(つみとが)をまぬがれないようにしか行為できない人間を罰し給うのか。これはすでに恩恵の光によっては解けない問題である。自然の光も恩恵の光も、この場合には非は明らかに哀れな人間の側にではあんく神の側にある、と考えるのである。
神はなんの功績もない不経験な人間に無報酬で栄冠を授けておきながら、それほど不敬虔とも思わない他の人間、すくなくとも前者ほどには不敬虔でない別の人間には栄冠をこばむばかりか、彼らに劫罰をくだされることがあるのだが、自然の光や恩恵の光の立場からすれば、こんな神はいかにも不義なる神だとしか判断しようがないからである。
だが栄光の光はこれとは違った味方のあることを教えてくれる。必ずやそれは、今われわれには神の審(さば)きがわれわれの基準では理解できない義にもとづいて行われているように見えるけれども、神はやはり最高に義なる神であり完全な正義の体現者だということを、もはや誰の目にも明らかなように示してくれるだろう。その時が来るまでは、われわれとしては恩恵の光がすでに与えてくれた洗礼に想いを致し、またそれを堅固な拠り所として、ひたすらに神の義なることを信ずるばかりである。恩恵の光のなしとげたことは、自然の光からすれば、やはり同じように大きな奇蹟だったからである。」
『ルター著作集』、聖文社、485~ 『知と意味の位相』、雀部幸隆、113~114Pの孫引き
ルターのこの話はまさに神への信仰であり、地上ではなく神の国の倫理であり、まさに結果を神に委ねるという言葉がぴったりである。
まず「自然の光」は地上におけるものである。たとえば客観的認識などはこの領域に属する。自分の領域において物事をよく知ることができる、つまり「理性」の領域である。ウェーバーのいうところの理念型を使って現実を認識する力も、この自然の光に属する。ウェーバーによればこうした自然の光、つまり理性、たとえば「客観的可能性判断」をすることによって物事を予見し、またそれについて責任をとる態度が政治家には求められる。
地上はこうした「理不尽」であり、自然の光だけでみると「神は不義」であるように見える。正しいものが殺され、悪しき物が栄えていることが世の常である。暴力に対して無抵抗を叫ぶ宗教的には善いもの、敬虔であるものはこの地上においては暴力の前になすすべなく命を失う。暴力を行使するものや商売で嘘をつくものは命を保持し、富をもち、地上において栄えているように見える。
こういった地上の「現実」、ウェーバーでいうところの「ザッへ(事柄)」は理不尽である。神は善いことをしろというが、善いことをしたら結果としてこの地上において散々な結果になる。つまり善いことをしてもこの地上において報われることは少ない。もし死んだ後に「神の国」において救われるという「恩恵の光」を信じたとしても、なぜこの地上において善人を罰し、悪人に栄冠を授けるかは人間にはおよそ理解することができない。
しかし神は前提として完全なものであり、人間は自分たちからは理不尽に見える神の行いの意図を理解することはできない。神はなにか目的があってしているわけであり、「ある時」がきたらそれを明らかにしてくれるに違いないとルターは考える。つまり「キリスト再誕」のときがきたら、そうした理不尽の意図を説明してくれるに違いない、というわけである。
結局の所、神を信じなさい、私達にはとうてい理解することはできない、というわけである。
もし神をこころのそこから信仰しているなら、その人は政治家にはならないというのもわかる気がする。なぜなら、この地上において敵国に侵略されて国民が殺されようと、善人は神の国によって救済され、侵略してきた悪人は神の国によって罰せられるということもまた信じるからである。この地上で善人が罰せられるのは理不尽だが、それでもなお理由があるはずだ、神を信じ切るのである。そういう態度をもってすれば、暴力という悪を手段として利用することは矛盾してることになる。
したがって政治家をこころざすものは、自らの魂の救済を期待できない、というウェーバーの主張は理解できるものである。しかしそれでもなお、地上の不条理に耐えられない、無辜の民が虐殺されるのを黙ってみてられない、神の国でたとえば罰しられようとも、それにもかかわらず!私は国民を暴力によって救うのだ!という純粋な心情と、そうしなければいけないと判断するまでの仮定において結果を予見すること、それも理性によって可能な限り予見すること、そしてその結果に責任を持つことが必要になる。そこまでいって心情倫理をもちながら責任倫理をもつということが成り立ちうる。
神々の争い
宗教的心情倫理も「神々の争い」の時代ではなかなか難しくなってきているという。
「冷徹な老経験主義者ジョン・ステユアート・ミルは次のように述べたことがある。純粋に経験の基盤からひとはひとつの神に達することはできずに〔……〕多神論にいきつく、と。実際、(キリスト教的な意味での)〈現世〉にいる者は、〔……〕これらの神々のいずれに、または、いつ一つの神に、いつ別の神に仕えようとし、また仕えるべきかを選ばねばならない。しかしそのときには、彼はつねにこの世のある神に、あるいはいくつかの別の神々に対する闘争に入る。そしてとくに、キリスト教の神とは少なくとも山上の垂訓のなかで告知された神とは、永久に何の関係もなくなるのだ(16)。」ヴェーバーは自分が「宗教音痴」であると自認はしても、決して「反宗教的」でも「非宗教的」でもなく、この点では「障害をもつ身であり、ひとりの傷ついた人間」であると述べているように(17)、神を否定するわけではない。だが、「ひとつの神」について積極的に語ることもできない。「多神論」こそが現世の法則であり、ここに住む人びとのあいだには諸価値間の「闘争」しかなく、「ひとつの神」を徹底させていく生き方は近代合理主義文化の中では不可能とみなさざるをえない、というのである。結局のところ、〈非政治的心情倫理〉は、現世の法則のもとで諸価値間の闘争に巻きこまれて生きざるをえない人間の悲劇性を際立たせているにすぎないのかもしれない。
マックス・ヴェ一バ一における責任倫理と政治的心情倫理──ドストエフスキ一『カラマ一ゾフの兄弟』を手がかりに── 内藤葉子 107-108P
ここでいう神々というのは文字通りの神であるとは限らない。それは「貨幣」であったり「車」であったり「女」であったりする。
要するにヤハウェの神は偶像崇拝を一切排除して唯一神たるかれを拝せよと人間に要求しているのであるが、この要求に心底からこたえることは人間わざでは到底できることではない(だから神の側からの働きかけ、つまり恩恵が必要なのだ、とルターはいうのだが)、なぜなら、人間という生き物は唯一の神、大文字の神には背をそむけながら、それぞれ思いのままに神々を拝し偶像を崇拝するものだからである、しかもその神々ないし偶像とはなにも文字どおり奇怪な様子をした彫像や画像である必要はない、女(男)であろうと金であろうと、はたまた理性であろうと、人がそれぞれ我を忘れて心酔し、心奪われ、崇拝するものが、とりもなおさず、その人にとっての神ないし偶像だからである。
嘘だと思うなら自分の胸に手を当ててよく考えてみよ。こういった趣旨のことをルターはそこで述べている。
これはなかなか鋭い人間洞察といわなくてはならない。この伝でいけば、われわれの大抵のものは、一時的にか恒久的にか神々を崇拝し、偶像に身を捧げている。「科学的」社会主義者も例外ではない。なぜなら、かれらも「科学」を信仰しているからである。それはともかく、いずれにしても神々への信仰(偶像崇拝)は人類の歴史とともに古い。それは人間の本性のようなものである。その神々への信仰が、唯一神への信仰(ないし世界史上それに肩を並べる救済宗教)の「重し」が取り去られた今(ウェーバーによれば、現代は「神なく預言者なき時代」である)、装いも新たに、おおっぴらに復活した(「神々の復活」と「神々の闘争」の時代としての現代)。それが先の四つの救済追求である。
「知と意味の位相」、雀部幸隆、恒星社厚生閣 255-256P
ルターと「偶像」の話がしっくりくる。
ルターの「我、ここに立つ」
ルターはウォルムスの国会で、カール5世から審問をうけ、ついに自説をひるがえしえないと答えた時に、「わたしはこうするほかはない、わたしはここにたつ Ich kann nicht anders,hier stehe ich」といって言葉を結んだそうだ。
1521年4月、ルター支持の諸侯たちや民衆の声に押される形で、ルターのヴォルムス帝国議会への召喚が行われた。皇帝カール5世は何よりルター問題からドイツが解体へ至ることを恐れていた。議会において、ルターは自分の著作が並べられた机の前に立った。ルターはまず、それらの著作が自らの手によるものかどうかを尋ねられ、次にそこで述べられていることを撤回するかどうか尋ねられた。ルターは第一の質問にはうなずいたものの、第二の質問に関してはしばらくの猶予を願った。熟考したルターは翌日、自説の撤回をあらためて拒絶。「聖書に書かれていないことを認めるわけにはいかない。私はここに立っている。それ以上のことはできない。神よ、助けたまえ」と述べたとされる
もし自説を撤回しなかったら「死刑」されていたかもしれない。しかしそれにもかかわらず、自分の心情を貫き通す、わたしはこうするほかはない、というこの心情をウェーバーは評価した。
たとえばこのような会話を考えてみる。
ある人:「あなたは暴力によって敵の兵士を殺すことになりますが、それは聖書の純粋な教えに反することです。地獄に行くかもしれませんよ。それでもあなたは政治家として敵兵を殺す命令をするんですか?」
政治家:「それが宗教的倫理からして『悪』だということは理解している。しかしそれにもかかわらず、わたしはこうするほかはない。わたしは敵兵を殺すという命令を部下にする。そしてその結果については自分が責任をすべてとる。そうせざるをえないというところまでとことん検討し尽くした。国民を守るためだから殺すことが倫理的に善いことだとか、そういう正当化はしない。私はただ、この地上の不正義に耐えられなかったんだ。私はこの地上に絶対的な正義を打ち立ててみせる。」
たしかに目の前で自分の家族が誰かに殺されようとしているとき、自分が相手を殺さなければそれを阻止できないようなとき、それでも暴力はよくない、といえるような心情を突き通せるかというと現実は難しい。そんなことは聖人ではないとできそうにない。それにもかかわらず、私は家族や恋人を守るということになるかもしれない。自分の命や財産を投げ出せば隣人を救えるというとき、それも名前も知らないような他人を救えるというとき、投げ出せるか。自己犠牲を貫き通せるか。私は正直な話、自分の利益(生命・財産)を考えてしまうと思う。ロマ書で言えば「我が肉のうちに善の宿らぬを知る」である。私はそもそもキリスト教徒ではないので、キリスト教における倫理が神によって語られた言葉かどうか信じることができない。
しかし宗教的倫理以外に、なにか自分が大事だと思う倫理を守りきろうとしても、それと矛盾するような現実がいつかやってくるだろうということは理解できる。そのときにどうするか、という態度が問題である。やはりそのときは理性をもって事柄を分析し、そのことに責任を持つような態度は人間として立派な姿ではあると思う。たとえば芸術家が自分の作品は金で動かされない、という心情をもって生き抜こうと決めた場合でも、自分の家族がお金で救えるようなときに直面したらどうするか。なにがなんでもお金をかき集めようとするのではないだろうか。それにもかかわらず、というようなあのルターの気持ちを持って臨めるだろうか。
だが、なるほどカントのいうように「汝なすべきがゆえに、なしあたう」であるとしても、その「なしあたう」と実際に「なす」とのあいだには、千里の距離がある。そこにあのロマ書におけるパウロの嘆きがあったのであり、アウグスティヌスもルターも、その嘆きを身をもって体験せねばならない理由があったのである。
「我はわが中(うち)、すなはち我が肉のうちに善の宿らぬを知る、善を欲すること我にあれど、之を行ふ事なければなり。わが欲するところの善は之をなさず、反って欲せぬ所の悪は之をなすなり。……ああ我悩める人なるかな、云々(ロマ七の一八以下)」
『知と意味の位相』,雀部幸隆,87P
信仰と政治
責任倫理においても「心情倫理」と同様に「信仰」がある。ウェーバーによれば「事柄」がどういうものであるべきかというものは「信仰」の問題であるという。またこの「信仰」がなければ空しいだけだという。たとえば「事柄」が社会的なこともあれば文化的なこともあり、ナショナルなこともあれば宗教的なものもあるという。『客観性論文』でも価値と事実を峻別して考えることを価値自由として学んだが、事実の選択の時点でそこには価値が入り込んでくる。たとえば自殺者数というのは客観的事実かもしれないが、自殺について研究している時点で、自殺を調べることになんらかの価値を感じているかもしれない。たとえば自殺を減らすべきだという価値がそこには入り込んでいるかもしれず、ある意味でそれは「信仰」であり、ある種の「情熱」である。
政治家は何を扱うかという問題だ。日本の漫画文化に補助金を出すのも政治であり、外国の兵器を借りる交渉をするのも政治だ。どういう政治を扱うべきかは、それぞれの個人の「理念」に属しているという。つまり価値の問題であり、信仰の問題だ。たとえば「自国民の命は大事」であり、自国の平和が第一であるという信仰から、「外交」を「事柄」として選択し、「外交」に情熱的に献身するというのもあるかもしれない。もちろん上から命令されたから、といったようなケースがほとんどかもしれないが、どの法案を提案するかといったものは国会議員は権利として保有している(法案の提出には賛成者の数等々いろいろと条件があり、さらにそこから採決がある)。
重要なのはその「事柄」を冷静に判断し、「予見」することだ。もしA国に侵攻した場合、自国はB程度の報復を受ける可能性があるという予測、「死刑制度」をなくした場合、自国の犯罪はC程度増える(減る)という予測、ある法案を通した場合の国民の疲弊はDであるという予測等々をしなければならない。またこの予測が間違っていた場合も責任をとらなければいけない。死刑制度をなくしたら、減ると思っていた犯罪が以上に増えたということもあるかもしれない。これはこの法律をなくすという選択をした「政治家」の責任であり、実際に犯罪を犯した「国民」の責任にしてはならないというわけだ。
いやいや俺たち政治家じゃなくて愚かな国民が悪いんだ、あるいはそういう人間をつくった神が悪いんだと責任を転嫁する場合、それは「心情倫理家」になる。もっとも、純粋な心情倫理家の場合は「予見や予測」すらしない。専門的な用語で言えば「客観的可能性」を科学的見地から考えない。死刑制度は命の冒涜だから悪いのであり、廃止するべきであり、その結果として犯罪が増えるか、減るかといった予測は「どうでもいい」というわけだ。
たしかにこれは思ったより難しい問題だ。命は大事だと思ってる政治家も、犯罪が減るなら自分の宗教的倫理よりも自分の「事柄(仕事)」に仕えて、「死刑制度」を維持させるべきかと考えるかもしれない。政治家がするべきことの正解はないかもしれないが、より国益になるようなことを、ウェーバーの言葉を使えば「普遍妥当性」をもつようなものというのはあるはずだ。犯罪を減らすというのは善い目的だが、手段として「死刑」を選ぶというのは倫理的には反しているようにみえる。しかしそれでもくじけずに、「われここに立つ」と言えるような人間が政治家を天職としてもつというわけだ。たとえ手段が宗教的な倫理に反しようとも、死んだあとに魂が救済されずとも、国益のためにしなくてはいけないんだ、という責任ある態度である。
これは「責任倫理」と「心情倫理」の相互補完といわれる。絶対的な対立におくと矛盾に陥ってどちらの行為もできなくなってしまう。つまり、責任倫理を貫きつつ、心情倫理として「ここに私は立つ」というわけである。難しい話だ。自分は道徳的に悪いことをしているということはわかっている。それにもかかわらず、これはしなければいけないんだというような態度ではないだろうか。道徳的な信念を全く失うこともたしかによくはない。しかし信念にのみ基づいて行動して結果に対して責任をとらないという態度もよくない。
信念をもちつつ、責任を自分で取るような態度こそウェーバーはよしとする。「価値自由」の話と似ている。事実と価値を緊張関係におくように、責任倫理と心情倫理を緊張関係におくわけだ。まさに自分は自分の信念に反するようなことを手段として採用しているということを認識しつつ、それでも政治家である以上はそういう「悪い」手段もとらざるをえず、またその結果についても責任をとろうとする態度こそ天職としての政治家にふさわしいということだ。
最近では「日本人の外国からの渡航を禁止する」と「外国にいる日本人の人権」を損害するという「予見」が考えられる。もしかしたらとある政治家は、それにもかかわらず!コロナの蔓延を防ぐためには手段として採用せざるをえない、そしてその結果には責任をとるという態度が必要になるかもしれない。あるいは逆に、「コロナが蔓延を防ぎつつ、日本人の入国を許可することができる」という予見をしつつ、もしコロナが蔓延したとしても「結果に責任をとる」ような政治家が、職業政治家としては天職をもつのではないだろうか。「日本人の人権をまもった」からいいでしょう、コロナが蔓延したとしてもそれはしらない、というような心情倫理家は政治にはむいていないのかもしれない。政治家は国民の代表であり、国民全体の利益をまもるべきであり、政治家個人の心情を独善的に行使するべきではないと思う。
討論可能な倫理的な善悪
ウェーバーによれば倫理判断(暴力が善いか悪いかなど)は、芸術の好き嫌いといったような趣味判断とは異なる判断である。つまり単なる主観の相違だけでは済まされない領域の問題だ。
だが趣味の良し悪しの判断の場合は、ウェーバーの四類型に照らして言えば、アフェクショナルな行為の領域に属する事柄である。それは、ぎりぎりのところ主観的なものであって、甲乙の判定のつけがたいものである(マックス・ウェーバー『宗教社会学』300P)。
それにたいして倫理的な善悪の判断のばあいには、その規範は実践理性の働きに由来するものであり、そのかぎりで合理的なものであるから(のちにウェーバーは「合理的な倫理的態度決定」という言い方をするが、その「合理的」はこの意味で使われている)、倫理的模範の命ずるところが何であるか、またその模範に照らしていかなる行為が正当と見なされるべきかは、原則的に「討論可能(デイスクシオーンフエーイヒ)」である(マックス・ウェーバー『宗教社会学』301P)。つまり、倫理的判断のばあいには、(実践)理性の法定に訴え出ることによって、その当否、甲乙の決着をつけることが可能である。その意味において、倫理的規範は実践理性に照らし万人がそれにしたがいうる「普遍妥当性(アルゲマインギュルテイヒカイト)」(マックス・ウェーバー「中間考察」133P)をもつ。
ところで、アルゲマインギュルティヒなもの、万人に適用する規範なしには、ゲマインシャフトリヒなものであれ、ゲセルシャフトリヒなものであれ、そもそも人間の社会生活は成り立たない。だから普遍妥当な倫理規範は、人間が共同生活をいとなむためになくてはすまされぬものである。
「知と意味の位相」、雀部幸隆、恒星社厚生閣、269-270P
※ドイツ語は打てないので省略しました。詳細は原典からお願いします。
神々の争い時代において、なにが善で何が悪かは「人それぞれ」であり、価値相対主義であり、それは「趣味の問題」であるのだろうか。ウェーバーは倫理判断を趣味判断と混同することを「けしからん」といった。倫理判断における「普遍妥当性」は人々の間に共同体、つまり社会を形成しうるものだからだ。人を殴っていいかどうかは、この普遍妥当性によって、つまり討論によって決定しうる領域である。
たとえば日本では国民の代表が国会で討論を行っている。あれこれと意見を戦わせ、何が正しくて何が悪いかを決めている。たとえば姦通罪がもはや世間で正義となされないような状況の場合は、悪法と判断して廃止することもある。
もちろんウェーバーは趣味判断の良さも語っているが、ここでは扱わないことにする。
最後に私が印象的だと思ったウェーバの言葉を紹介して終わることにする。
「国民が疲弊困憊(こんぱい)しているこの時に、自分ひとりの魂を救って何になる?」
(『マックス・ウェーバー』,みすず書房,447P)
参考文献・おすすめ文献
マックス・ウェーバー『職業としての政治』
マックス・ウェーバー『権力と支配』
雀部幸隆『知と意味の位相―ウェーバー思想世界への序論』
山之内靖『マックス・ウェーバー入門』
本当にわかる社会学 フシギなくらい見えてくる
アンソニー・ギデンズ「社会学」
社会学
社会学 新版 (New Liberal Arts Selection)
クロニクル社会学
社会学用語図鑑 ―人物と用語でたどる社会学の全体像
コメント
この記事へのトラックバックはありません。






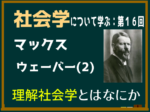
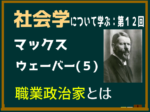
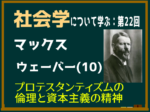

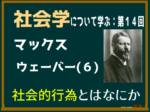
この記事へのコメントはありません。