- Home
- マックス・ウェーバー
- 【基礎社会学第二十回】マックス・ウェーバーの「職業としての学問と神々の闘争」とはなにか
【基礎社会学第二十回】マックス・ウェーバーの「職業としての学問と神々の闘争」とはなにか
- 2022/4/18
- マックス・ウェーバー
- コメントを書く
Contents
はじめに
この本をきっかけに社会学を学びたいと思うようになりました。沢山の本を読んできましたが、いつもこの本にかえってきます。なぜ学ぶべきなのか?と問うとやはりこの本の内容に帰るからです。私が人生で影響を受けた3人の学者をあげるとすれば、間違いなくマックス・ウェーバー、見田宗介さん、グレゴリー・ベイトソンの3人です。特にお金に余裕があるわけではないので他の学者の高い書籍は逐一購入できませんが、この人たちの書籍はできるだけすべて購入するようにしています。いつかマックス・ウェーバー以外も紹介できればいいなと思います。
ウェーバーの基礎内容については次回の「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」で終わりにしようと思います。次回からは引き続きパーソンズを学びながら、間にミードを挟んでいく予定です。パーソンズが終わればシュッツの予定です。
・この記事は『職業としての学問』全体の要約ではありません。さらに書籍以外の内容を多分に含んでいます。たとえば学者の給料や扱いがどうだとかいう客観的な待遇問題には触れていません。私が面白い、これは学ぶ価値があると感じたものを中心にしてとりあげています。
概要(要約)
- 学問における職業人:学問を生涯の仕事としてしようとするものを指す。
- 学問に対して職業人がとるべき心構えの例:①専門家に徹した方がいい、②冷静さと情熱の両方が必要、③学問の領域で個性的であるということは、「仕事(ザッへ)」に仕えるということだと覚えた方がいい、④教師は指導者ではない、⑤学問にとって「達成」とは「新しい問題提出」を意味するのであり、常に未来において誰かに乗り越えられ、いつか時代遅れになるということを覚えた方がいい
- 学問の職分:学問が(職業人に対してだけではなく)人間生活一般に対してどんな客観的な価値や意義があるのかという問題。端的に言えば知的廉直であること。①技術についての知識(技術的な意義)、②物事の考え方及びそのための用具と訓練(道具的な意義)、③明確さに導くことが出来る(道徳的な意義)。ウェーバーは特に③を重視した。なぜならば責任へと導くことが出来るからである。
- 脱呪術化(脱魔術化、魔法からの解放):①呪術(神強制)から宗教(神奉仕)へ移行すること。②宗教から呪術的(非合理的)要素が徹底的に排除されていくこと。③主知主義的合理化していくこと(呪術も宗教も非合理的なので排除されていく)。
- 主知主義的合理化:可能性としてはすべてのことが知性で解明でき、それらに呪術的で神秘的な予測できない力が働いていないと信じ、原則上予測によってすべてのことが意のままになるということを知っている、あるいは信じていくようになること。
- 神々の闘争:世界に存在するさまざまな価値は互いに解き難い闘争の中にあること
- 神々の闘争の時代でどうすればいいか→日々の要求に従う:日常の具体的な問題に責任を持って対処すること。例:学問の場合は知的廉直な態度、例えば教壇の上では生徒に価値を強いない、政治的立場を主張しない等の責任を感じる
- ウェーバーの考え方の基本:世界に対してどういう態度をとるべきかは、自分の「良心」と「知性」と「心」が責任を負うべき事柄であり、各人が一生かけて色々と経験を積みながら解決してゆくべき問題。
動画での解説・説明
・この記事のわかりやすい「概要・要約・要旨・まとめ」はyoutubeの動画の冒頭にありますのでぜひ参照してください。
よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m
マックス・ウェーバーのプロフィール

マックス・ウェーバー(1864~1920)はドイツの経済学者、社会学者、政治学者。28歳で大学教授を資格を得て、1905年に「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」を発表した。社会学の元祖ともいわれる。ウェーバーの研究成果はT・パーソンズの構造ー機能理論、A・シュッツの現象学的社会学、J・ハーバーマスの批判理論やシンボリック相互理論等々に引き継がれた。
マックス・ウェーバー関連の記事
・以前の記事
【基礎社会学第四回】マックス・ウェーバーの価値判断や価値自由とははなにか?
【基礎社会学第六回】マックス・ウェーバーの「理念型」とはなにか(概略編)
【基礎社会学第八回】マックス・ウェーバーの『職業としての政治』から「支配の三類型」を学ぶ。
【基礎社会学第十回】マックス・ウェーバーから「心情倫理と責任倫理」を学ぶ。
【基礎社会学第十二回】マックス・ウェーバーの『職業としての政治』から「職業政治家」を学ぶ。
【基礎社会学第十四回】マックス・ウェーバーの社会的行為の四類型とはなにか
【基礎社会学第十六回】マックス・ウェーバーの「理解社会学」とはなにか
【基礎社会学第十八回】マックス・ウェーバーの「官僚制」とはなにか
【基礎社会学第二十回】マックス・ウェーバーの「職業としての学問と神々の闘争」とはなにか(今回の記事)
・以後の記事
【基礎社会学第二十二回】マックス・ウェーバーの「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」とはなにか
学問に対する職業人の心構え
前提:当時のドイツの時代背景
第一次世界大戦は1914年から1918年にかけて連合国軍と中央同盟国との間で繰り広げられた世界大戦です。連合国は主にロシア、フランス、イギリスであり、中央同盟国はドイツやオーストリアです。日本は当時日英同盟をイギリスと結んでいたので、連合国軍側に参戦することになります。ドイツ側の中央同盟国は負け、1919年のヴェルサイユ条約ではドイツが賠償金を多く支払うことになりました。
戦争末期の1918年にウェーバーはイヌマエル・ビンバウムという人に講演に招かれ、承諾することになったようです。自由主義左派の自由学生同盟の主催だったようで、講演の対象は学生でした。
講演が実際に行われたのは1919年1月であり、場所はミュンヘンでした。翌年の1920年の6月にウェーバーは肺炎にかかり、6月14日に56歳で死去しました。
「一次世界大戦を控えた混迷する情勢下で、ドイツでは、大学の教壇で、政治情勢のみならず、自らの政治的信条について語る教師が少なからずいたことが、論争がおこる契機となったであろうことは、想像に難くない。社会政策の純粋理論上の問題と、その理論が現実の政治という場に応用された際に生じる理論と実践の摩擦の問題が、この論争の引き金になったことを推測できる。」
柴田育子「マックス・ウェーバーにおける『学問』と『政治』53P
学問を職業とする者とは
学問に生きるもの(学問を職業とする者):・学問を生涯の仕事としてしようとするもののこと。学問を「職業(天職)」とする者は「学者」と「教師」の二重の資格をもつことを知っているべきだとウェーバーはいう。またこの二種類は常に合致するわけではないという。
たとえば大学の教授をイメージすればわかりやい。自分の研究だけをしていればいいわけではなく、授業の担当を持ち、学生に教える「教師(教授)」としての立場もある。一方で、学生に教えずに、専ら研究だけを政府の助成金や企業からの給料をもとにしているような学者もいる。たとえば企業の利益のために殺虫剤を研究する人間もいれば、薬の開発に携わる人間もいる。
ここでは簡易的な分類として、大学関係「大学の教授やその助手、私講師など」、研究所関係「私企業の研究職、たとえば製薬会社などの教師として教壇に立つ機会がないケース」の二種類に分けて考えることにする。もちろん私企業の研究者が教壇に立つ場合もあるが、簡易的に理念型として分類することにする。
・学問を生涯の仕事としてしようとするものは「学者」と「教師」の二重の資格を要求されることを知っておくべき。
研究者であってもいつかは教壇に立つ場合があり、教師のみの講師であっても、いつかは自分の研究をする場合があることがあるという前提がある。だから自分は教師だから学者としての心構えをしなくていいだとか、学者だから教師としての心構えをしなくていいだとか、そういう問題ではないのだろう。
天職と職業
「天職とするもの」と「職業とするもの」の違いは特に明確にはされていないが、ウェーバーは使い分けている。単に生活のための労働といった意味合いが職業であり、労働そのものになにか意義があると考える場合、自分はこのために生きているという場合、あるいは宗教的に神の召命であり、自分は神の道具として働いているというような考えもある。今回は労働そのものに、単に生活の手段としてだけではなく、特別の意義があると考えるようなケースを「天職」だと考えることにする。そしてどのような意義があるか、という問題が主観的な態度の問題と、客観的な意義の問題に分かれる。この場合、後者の問題を「職分」として扱う。
なにが天職かは人それぞれによって違う。たとえばウェーバーは「学生に助言をすることを天職とする場合は」というように、人それぞれに職業に対する特別な意義を有している場合に天職とするような使い方をしている。天職と考えているからと言ってすべて望ましいわけではなく、たとえば学生に自分の政治的立場を強いることを天職とするような場合は、教壇の外でやりなさいとウェーバーは言っている。つまりこのような意義は「客観的な意義(職分)」としては認められないということである。
「いやしくも学問を自分の天職と考える青年は、かれの使命が一種の二重性をもつことを知っているべきである。というのは、かれが学者としての資格ばかりでなく、教師としての資格をももつべきだからである。このふたつの資格は、けっしてつねに合致するものではない。」
『職業としての学問』18P
「物理学、化学また天文学のような自然科学は、それらが到達しうるかぎりの最後の宇宙の諸法則が当然知るに値するものであることを前提する。だが、ここで知るに値するというのは、なにもこれらの法則によってなにか技術上の目的を達することができるからというのではなく、むしろ──これらの学問をおのれの『天職』とする以上は──『学問それみずからのために』知るに値するという意味なのである。それがはたして知るに値するかどうかは、これらの学問みずからが論証しうべき事柄ではない。」
『職業としての学問』44P
「ある大学教授が、自分の天職を学生たちにたいする助言者たることであると考えており、しかもかれらの信頼を受けているようなばあいには、かれは学生たちとの個人的なつき合いにおいてかれらのために尽くしてやるがいい。もしまたかれが世界観や党派的意見の争いに関与することを自分の天職と考えているならば、かれは教室の外へ出て、実生活の市場においてそうするがいい。」
『職業としての学問』60P
「……学問がだれかの『天職』となる価値があるかどうかということ、また学問それ自身がなにかある客観的に価値ある『職分』をもつかどうかということ、──これはまたもやひとつの価値判断であって、この点については教室ではなにごとも発言しえないのである。なぜなら、教えるものの立場にとっては、この点を肯定することがその前提だからである。わたくし自身ももとより自分の仕事を通じてこの点を肯定している。」
『職業としての学問』64P
1:専門家に徹した方がいい
専門家:学問を職業とする者は「専門家」になるべきだという。たとえば経済学者は主に経済の専門家であるべきであり、物理学者は物理の専門家であるべきだということである。ただし、たとえば物理学者が経済学者に対して、経済学だけを考えていた場合ではわからなかったような「有益な問題提出」を出来る場合もあるかもしれない。社会学者の場合は特にこのようなケースが多いという(たとえば政治や経済に口を出す)。こうしたケースは専門領域間の横断であり、私の好きな見田宗介さんの言葉で言えば「越境」です(この場合はやむにやまれず学問を横断するのですが)。ただし、「有益な問題提出」をできるという点にとどまり、いざ物理学者が自分の仕事としてやってみると、不完全な結果になるという。たとえばある物理法則と経済法則が似ている、というような指摘を物理学者が経済学者にしたとして、それをどうやって物理学者が実際に経済学において位置づけるのか、立証できるのかという話になり、逆もまたしかりである。
「こんにちなにか実際に学問上の仕事を完成したいという誇りは、ひとり自己の専門に閉じこもることによってのみ得られるのである。これはたんに外的条件としてそうであるばかりではない。心構えのうえからいってもそうなのである。」
『職業としての学問』21P
「学問に生きるものは、ひとり自己の専門に閉じこもることによってのみ、自分はここにのちのちまで残るような仕事を達成したという、おそらく生涯に二度とは味われぬであろうような深い喜ぶを感じることができる。」
『職業としての学問』22P
「けれども重要なことは、『領域横断的』であるということではないのです。『越境する知』ということは結果であって、目的とすることではありません。何の結果であるかというと、自分にとってほんとうに大切な問題に、どこまでも誠実である、という態度の結果なのです。あるいは現在の人類にとって、切実にアクチュアルであると思われる問題について、手放すことなく追求しつづける、という覚悟の結果なのです。近代の知のシステムは、専門分化主義ですから、あちこちに『立入禁止』の札が立っています。『それは〇〇学のテーマはないよ。そういうことをやりたいのなら、他に行きなさい。』『✕✕学の専門家でもない人間が余計な口出しをするな。』等々。学問の立入禁止の立て札が至る所に立てられている。しかし、この立入禁止の立て札の前で止まってしまうと、現代社会の大切な問題たちは、解けないのです。そのためには、ほんとうに大切な問題、自分にとって、あるいは現在の人類にとって、切実にアクチュアルな問題をどこまでも追求しようとする人間は、やむにやまれず境界を突破するのです。」
『社会学入門』、見田宗介、8P
2:冷静さと情熱の両方が必要
学問には冷静さと情熱の両方が必要:・ここでいう冷静さとは機械的な計算などを意味する。要するに客観的、論理的に計測、分析、判断する能力や態度のことである。一方で、情熱とは要するに「やる気」であり、「夢中になれる」ということである。冷静さと情熱の両方を兼ね備えているときに、最も「思いつき」が結果に実を結ぶという。「思いつき」は有意義な結果を出すために必要とされるもので、冷静さだけがあっても「思いつき」はでてこない。しかし情熱だけがあっても、「思いつき」を活かすことはできない。その両方を合体させることが必要だという。たとえばリンゴが木から落ちたことでニュートンは重力を「思いついた」と言われることがあるが、この思いつきを実際に数式等にあらわすことが出来る「冷静さ(作業)」を伴わないと「素人の思いつき」で終わってしまう。
「実験室でもまた工場でも、なにか有意義な結果を出すためには、いつもある──しかもその場に適した──思いつきを必要とするのである。とはいえ、この思いつきというものは、無理に得ようとしてもだめなものである。もとより、それはたんなる機械的な計算などとはおよそ縁が遠い。だが、たんなる計算といえども、よい思いつきを得るための欠きえない一手段にはなるのである。」
『職業としての学問』24P
「……しろうとを専門家から区別するものは、ただしろうとがこれときまった作業方法を欠き、したがって与えられた思いつきについてその効果を判定し、評価し、かつこれを実現する能力を持たないということだけである……作業と情熱とが──そしてとくにこの両者が合体することによって──思いつきをさそいだすのである。」
『職業としての学問』25P
3:学問の領域で個性的であるということは、「仕事(ザッへ)」に仕えるということだと覚えた方がいい
学問における個性とは:・学問における個性とは、その仕事(ザッへ)に仕えることである。学問における仕事とは、自己のの専門の殻に閉じこもることによってのみなし遂げられる。専門”外”の内容に仕えているようでは個性とはいえない。たとえば自分の名を売るために仕事をするようなタイプ、なにか人との違いを示すためだけに仕事をするようなタイプは仕事に仕えているとはいえない。端的に言えば、学問を職業とするものは禁欲的であるべきで、自分の仕事に自己を滅して専心するべきだ、だという話である。自己を滅して専心した結果として、名を高めるということはあるが、それは手段として名を高めたわけではない。
「さて、お集まりの諸君!学問の領域で『個性』をもつのは、その個性ではなくて、その仕事(ザッへ)に仕える人のみである。しかも、このことたるや、なにも学問の領域にばかり限ったことではない。芸術家でも、自分の仕事に仕えるかわりになにかほかのことに手を出した人には、われわれの知る限り偉大な芸術家は存在しないのである。……とにかく、自己を滅して専心するべき仕事を、逆になにか自分の名を売るための手段のように考え、自分がどんな人間であるかを『体験』で示してやろうと思っているような人、つまり、どうだ俺はただの『専門家』じゃないだろうとか、どうだ俺のいったようなことはまだだれもいわないだろうとか、そういうことばかり考えている人、こうした人々は、学問の世界では間違いなくなんら『個性』のある人ではない。」
『職業としての学問』28P
4:教師と指導者は違うということを自覚したほうがいい
教師は指導者ではない:・教師は自己の主観的な評価や個人的な世界観や政治的な立場を学生に教壇の上では強いてはいけない。教師は指導者ではない。
#学生は卒業するための単位を得るために出席していて、自由に退席できないような事情もある。街頭などの路上なら自由に立ち去ったり、講演者に批判することが出来るので教壇外でするべき。教壇の場合だと学生は自由に批判しにくい(沈黙を余儀なくされる場所)。預言者や煽動家は教壇の上にたつべきではない。学生が個人的に教師に助言(指導)を必要とするなら、1対1で個人的なつき合いにおいて助言をしてあげればいい。
教師は自己抑制(禁欲)をするべきであり、指導者として教壇に立つべきではない。そのような人間は教師失格。
「ところで、大学で教鞭をとるものの義務はなにかということは、学問的にはなんびとにも明示しえない。かれにもとめうるものはただ知的廉直ということだけである。すなわち、一方では事実の確定、つまりもろもろの文化財の数学的あるいは論理的な関係およびそれらの内部構造のいかんに関する事実の確定ということ、他方では文化一般および個々の文化的内容の価値いかんの問題および文化共同社会や政治的団体のなかでは人はいかに行為すべきかの問題に答えること、──このふたつのことが全然異質的な事柄であるということをよくわきまえているのが、それである。」
『職業としての学問』50P
「要するに、こんにち一部の青年たちが犯している誤りは、たとえば以上のような議論にたいして、『それはそうだろうが、しかしわれわれはただの分析や事実の確定ではないなにかあるものを体験したくて講義に出ているのだ』というふうに答えるばあい、かれらは講義者のなかに、そこにかれらにたいして立っている人ではない別のある人──つまり教師ではなく指導者──をもとめていることにあるのである。ところが、我々が教壇に立つのは教師としてのみである。教えることと指導することとは別の事柄であり、そしてこのことは少し考えてみればすぐわかることである。」
『職業としての学問』58P
補論:価値自由
補論:価値自由(ヴェルト・フライハイト)とは
・ひとりひとりの個人が、実践的価値(価値判断)と科学的事実認識(事実判断)とを、別種の精神活動として峻別した上、両者を緊張関係において区別して堅持すること
・Aという選択をすれば自殺率が10%減ると予測でき、その随伴結果としてBが生じると予測できるといったものは事実判断。
・そもそも自殺は減らすべきかどうか、命を尊ぶことの善いことか悪いことか、というのは価値判断。価値判断が正しいかどうかは学問的手段によって証明できない。
・価値自由とは価値判断をするな、もつな(没価値)ということではない。人々の行為には究極的な価値が前提(価値への自由)にあり、その価値を自覚し、囚われないようにする(価値からの自由)という態度を意味する。科学は自分がどういう価値判断を行っているか、という要素を明らかにできる権能がある(どういう価値判断をするべきかには沈黙)。上の例で言えば、ある学者は「命は尊ばれるべきで維持されるべき」という価値判断を前提として無意識、あるいは意識的に行っているケースが考えられる。
5:学問にとって「達成」とは「新しい問題提出」を意味する
学問の進歩には終りがない:・学問にとって「達成」とは「新しい問題提出」を意味する。過去の学問上の達成は、常に未来において乗り越えられる対象であり、いつか時代遅れになり、これで終わりというものがない。つまり、学問の進歩は無限に続くのである。そして乗り越えられることは「運命」ということだけではなく、学者共通の「目的」であるという。後代の人に参照され、乗り越えられることを期待しているのである。たとえば量子力学の登場によってニュートン力学では説明できなかったものが説明できるようになったり、素粒子という新たなものが発見されたりする。しかし今後も新しいものが発見され、今の時代の説明が時代遅れになる可能性もある。タルコット・パーソンズの全盛期にはパーソンズの理論が最先端であり、もてはやされていたが、今では見る影もなく、時代遅れとされてしまっている。しかしそうしたパーソンズの問題提出はルーマンやハーバーマス、ガーフィンケル等の社会学者に共有され、乗り越えられようとしている。
・そうした運命に耐えられない、あるいは独りよがりに誰にも乗り越えられないものを完成させたと主張するような人間は学者失格。
「……他方では、学者の仕事は芸術家のそれとまったく違った運命のもとにおかれている。というのは、それはつねに進歩すべく運命づけられているのである。これに反して、芸術には進歩というものがない。すくなくとも学問でいうような意味の進歩はない。ある時代の芸術品が新しい技術上の手段や、またたとえば遠近法のようなものを用いているからといって、こうした手段や方法の知識を欠く作品にくらべてそれが芸術としてすぐれていると思うのは間違いである。正しく材料を選び、正しい手法に従っているものでありさえすれば──いいかえれば、こうした新しい手段や方法を用いなくても、主題の選択と制作の手続きにおいて芸術の本道をいくものでありさえすれば──それは芸術としての価値においてすこしも劣るものではないのである。これらの点で真に『達成(エルフュレン)』している芸術品は、けっして他にとってかわられたり、時代遅れになったりするものではない。」
『職業としての学問』29P
「学問上の『達成(エルフュレン)』はつねに新しい『問題提出』を意味する。それは他の仕事によって『打ち破られ』、時代遅れとなることをみずから欲するのである。学問に生きるものはこのことに甘んじなければならない。」
『職業としての学問』30P
職業人にとっての職業の主観的な意義とは
終わりのない学問
終わりがない学問に対してなぜ人は仕事として携わるのか:・ウェーバーは学問の意義として、まず一般的に想定されるであろう「技術上の意義」を挙げた。たとえば半導体の研究は人々のスマートフォンの部品として役立ち、自殺や治安の研究は自殺減少や犯罪率の低下につながっている。つまり、学問は技術上役立つから、終わりがないとしても仕事してやる意義がある、という考えだ。しかしウェーバーいわく、これは学問に対する職業人の心構えというより、実際家にたいする意義にすぎないという。たとえばパソコンを作るメーカーにとって、科学は技術上の意義があるが、学問を職業とする人間(職業人)にとって技術上の意義があるわけでは必ずしもない。では誰かの生活を向上させるといったような技術上の意義以外で、なにか学問に意義があるのかという問題になる。学問それ自体に意義があるという人もいるが、はたして学問の意義とはなにかという問題になる。昔は学問といえば神へ通じる道、真理へ通じる道だと考えられていたが、今ではそのようなものとは考えられていない。比喩的に言えば教師は生徒に技術上、役立つ知識を教えていればいいのか、という話である。たとえば理系なら商品の開発に必要な化学式などを教えてもらえればいいのであり、文系なら語学や教養、ビジネスに役立てる経済学などを教えてもらえればいいという話になる。
これは一応整理しておく必要がありそうですね。
1:【学問が天職といえるかどうか】学問に対する職業人(教師や研究者)の心構え
2:【学問の職分はなにか】学問が人間生活一般に対してどんな価値や意義があるのかという問題
「原則上、この進歩は無限に続くものである。かくて、われわれはここで学問の意義はどこにあるのかという問題に当面する。というのは、このような運命のもとにおかれている学問というものが、いったい有意義なものであるかどうかは、けっして自明ではないからである。事実上終りというものをもたず、またもつことのできないような事柄に、人はなぜ従事するのであろうか。」
『職業としての学問』30-31P
「『進歩』はそれ自身はっきりとした、技術上の意味以上の意味をもつものであろうか。したがってまた、これによって進歩にたいする奉仕はひとつの職業を有意義ならしめるであろうか。これはまさに問われるべき事柄である。だが、ここでは問題をもはやたんに学問にたいする職業人のあり方の問題ではない。いいかえれば、職業としての学問はこれに専心するものにたいして何を意味するのかということではない。むしろ、それは人間生活一般にたいする学問の職分はなんであり、またその価値はどこにあるのかという問題である。」
『職業としての学問』35P
1:技術を高めていくことによって、人々の生活に役立つから意味があり、それが目的だという態度をとるケース
たとえば科学技術の発達で人の生活は便利になる。社会科学の分析などで犯罪が減ったり、暮らしが豊かになるかもしれない。ただ、便利であることの意味や犯罪が減ることに意味があるかどうか、それは突き詰めれば「わからない」ということになる。
前提:進歩に終わりがない学問に対してなぜ人は仕事として従事するのか。職業人にとってなんの意義があるのか。想定される2つの回答。
・個々の研究結果(技術的な成果)に焦点が当てられている。たとえばエネルギーを効率的に生産できる技術や法則を発見した結果、人々の衣食住の役に立つようなケース。
・ただしこのケースの場合は、学問の営為そのものの重要性というよりも、結果の重要性であり、どちらかといえば実際家(実際に成果を使う人)に対する意義である。人の役に立てればいいのなら、学問以外でもいいのでは?という話にもなるのではないか。レタスを売っている人も役に立っている。
「それは実践上の、あるいは広義における技術上の諸目的のためである、と。つまり、学問上の経験が教えるところによって実際生活におけるわれわれの行為を期待された方向に導くためである、と。──よろしい。だが、それは要するに実際家にたいする意義にすぎない。問題はむしろ、学問にたずさわる人が自己の職業にたいして有する心構えのいかんにある。」
『職業としての学問』30-31P
「しかし、何千年来西洋文明のうちに受けつがれてきたこの魔法からの解放過程、いいかえれば学問がその肢体ともなり原動力ともなっている『進歩』というものは、はたしてなにか実際上あるいは技術上の意味以上の意味をもつのだろうか。」
『職業としての学問』33P
「一般に、自然科学は、もし人生を技術的に支配したいと思うならばわれわれはどうすべきであるか、という問いにたいしてはわれわれに答えてくれる。しかし、そもそもそれは技術的に支配されるべきかどうか、またそのことを我々は欲するかどうか、ということ、さらにまたそうすることがなにか特別の意義をもつのかということ、──こうしたことについてはなんらの解決をも与えず、あるいはむしろこれをその当然の前提とするのである。」
『職業としての学問』45P
2:学問それ自身のために従事するという態度をとるケース
・学問という「営為そのもの」が重要であるという態度がとられている。実際に人々の役に立たなくても、科学的真理を追求すること自体に意味があると考えるケース。
→それでは学問の営為そのものとはいったいなにか、という問題になる。
「ところで、このような人はいうであろう、学問は『それ自身のために』なされるのである。たんに人々に営業上のまた技術上の便宜を与えるためでもなく、またたんに人々の衣食住を改善するためになされるのでもない、と。それならば、かれはこのつねに時代遅れとなるべく運命づけられたものにゆおって、したがってまた、この専門分化しかつ永遠に終ることのない営みに結び付けられていることによって、いったいどのような意義ある仕事をなしつつあると考えているのであろうか。この点についてはもっと一般的な考察が必要である。」
『職業としての学問』31P
学問の職分
学問の職分とは、意味
学問の職分とは:・学問が(職業人に対してだけではなく)人間生活一般に対してどんな客観的な価値や意義があるのかという問題。
職分とは一般に、「その職についている者がしなければならない仕事」を意味する。たとえば水道局員なら水道を安全に使用できるように整理することが職分であり、コンビニの店員なら客へのレジにおけるサービスが職分である。では教師や学者の職分とはいったいなにか、それも人間生活一般においてどのような意味があるか、あるいはどのような意義を求められているのかという問題。客観的にある職業に価値があるかどうかという問題。この場合の客観的とは、自分の主観だけではなく、他の人達においてどういう意味があるか、求められているかという意味合い。たとえば学問における職分は技術上の意義以外になにがあるか、という問題になったときに、なにか客観的に意義があると答えることは難しいという。「学問を生涯の仕事としてしようとするもの」の職分はこれから詳細を確認していくが、主に技術に関する知識の提供、また考え方、道具の使い方を教えること、正確さや責任感へ導くことなどが挙げられている。
・最終的には職業人が学問に対してとる主観的な態度と同じように、学問に客観的な価値があるかどうかは「価値判断」の問題になる(絶対的な正解がない)。
ただし、多くの職業人は学問に客観的な価値があり、主観的な態度としても価値があると思っているということを前提にしている(両方とも学問それ自体によって証明はできない)。たとえば美学は芸術品があること、社会科学は文化現象に知る価値があることを、医学は人の命は維持されるべきものであるということを前提としているが、この前提は学問的手続きによって論証できない。
ウェーバーも学問それ自身(学ぶこと自身)が価値があるということを前提としていると述べている。医者のほとんどは命は尊ばれるべきかどうかは論証できないが、命は尊ばれるべきであり、維持されるべきだということを前提としている。
「『進歩』はそれ自身はっきりとした、技術上の意味以上の意味をもつものであろうか。したがってまた、これによって進歩にたいする奉仕はひとつの職業を有意義ならしめるであろうか。これはまさに問われるべき事柄である。だが、ここでは問題をもはやたんに学問にたいする職業人のあり方の問題ではない。いいかえれば、職業としての学問はこれに専心するものにたいして何を意味するのかということではない。むしろ、それは人間生活一般にたいする学問の職分はなんであり、またその価値はどこにあるのかという問題である。」
『職業としての学問』35P
学問と「真理への道」、概念と実験
前近代的な「真理への道」:・前近代的に知性は神や真理への道だと考えられていた。具体的に手段として概念や実験を用いるが、それは『真の実在への道』、『真の芸術への道』、『真の自然への道』、また『真の幸福への道』としてであり、それこそが学問の職分と考えられていた。しかし脱魔術化した近代以降において、もはや知性によって真理や神へ通じるとは一般に考えられなくなり、そうしたものが職分であるとは見なされなくなっていった。
・近代以前は、学問は「真理」や「神」へ至る道だと信じられていた。
・具体的に手段として概念や実験を用いるが、それは『真の実在への道』、『真の芸術への道』、『真の自然への道』、また『真の幸福への道』としてであり、それこそが学問の職分と考えられていた。あのアイザック・ニュートンさえ科学は神へと至る道だと思っていたが、政治的な理由からそうした側面を徹底的に抑えていたという説もある(ニュートンは科学革命の中心人物)。近代以降、目的が抜け落ちて合理的、客観的な手段である概念や実験が残っていく。
・しかし脱魔術化した近代以降において、もはや知性によって真理や神へ通じるとは一般に考えられなくなり、そうしたものが職分であるとは見なされなくなっていった(最終的にとどめを刺したのは哲学者のイマニュエル・カント)。アメリカの学生は大学の教師に世界の意味や、世界の究極的な法則を教えてもらおうなどとは思っていない(日本も同じくそういう傾向があるのではないか。偏差値が高ければ良い、就職に役立てれば良い等)。八百屋にレタスを求めるように、役に立つ技術的な知識を教えてもらいにきている。究極的な意味の問題は信仰の問題であり、理論理性(知性)の問題ではないと考えられるようになった。
→学問が一般生活全般において寄与できることは技術だけか。それ以外はないのか。
「かの『ポリティア』におけるプラトンの感激は、要するに、当時はじめて学問的認識一般に通用する手段の意義を自覚したことにもとづいている。その手段とは、概念である。」
『職業としての学問』37P
「……もし善だとか、善だとか、また勇気だとか、霊魂だとか、その他なんであれ、それについてただ正しい概念をみつけだしさえすれば、同時にそれの真の実在も把握しうると考えられたのである。しかも、このことは同時に、とくに公民としての生活において正しく振る舞うにはどうすべきかを知り、かつ教えるための方法を示すものとして考えられた。というのは、あくまで公民としての立場で物を考えたギリシア人にとっては、すべてはこの問題に帰着したからである。かれらが学問に励んだ理由もここにあった。」
『職業としての学問』38P
「さて、ギリシア人における概念の発見と並んで、ルネッサンスの産物としてあらわれた学問研究の第二の手段は、合理的実験であった。実験は経験を確証するための手段であり、これなしにはおそらくこんにちの経験科学は成立しえなかったであろう。」
『職業としての学問』38P
「以上のような学問の意義に関する諸見解、すなわち『真の実在への道』、『真の芸術への道』、『真の自然への道』、また『真の幸福への道』などが、すべてかつての幻影として滅び去ったこんにち、学問の職分とはいったいなにを意味するのであろうか。これにたいするもっとも簡潔な答えは、例のトルストイによって与えられている。かれはいう、『それは無意味な存在である。なぜならそれはわれわれにとってもっとも大切な問題、すなわちわれわれはなにをなすべきか、いかにわれわれは生きるべきか、にたいしてなにごとをも答えないからである』と。学問がこの点に答えないということ、これはそれ自身としては争う余地のない事実である。問題となるのはただ、それがどのような意味で『なにごとも』答えないか、またこれに答えないかわりにそれが、正しい問い方をするものにたいしてはなにか別のことで貢献するのではないか、ということである。」
『職業としての学問』42-43P
「論証できない前提」:学問の根本的な前提は学問によって論証できない
学問の前提:・どんな学問であれ、学問は「知るに値する」という前提を持っているが、この前提は学問によって論証することができないという。たとえば医学では「人の命は維持するべきであるという前提」があるが、維持に値するかどうかは医学の手段によって論証できない。美学も「芸術品というものがあるという前提」、文化科学も「文化事象は知るに値するという前提」、自然科学も「宇宙の諸法則が知るに値するものであるという前提」を学問的に論証することはできない。自明のものとみなされているが、実は自明ではない。神学も同様に、「世界はなんらかの意味をもっているにちがいないという前提」があり、それは学問的な手続きによって論証することはできない。
「ところが、一般に学問的研究はさらにこういうことをも前提する。それから出てくる結果がなにか『知るに値する』という意味で重要な事柄である、という前提がそれである。そして、明らかにこの前提のうちにこそわれわれの全問題はひそんでいるのである。なぜなら、ある研究の成果が重要であるかどうかは、学問上の手段によって論証しえないからである。それはただ、人々が各自その生活上の究極の立場からその研究の成果がもつ究極の意味を拒否するか、あるいは承認するかによって解釈されうるだけである。」
『職業としての学問』43-44P
「ところで、すべての神学が──したがってたとえばインド教のそれもが──有するものは、世界はなんらかの意味をもっているにちがいない、という前提であり、したがって、すべての神学にとっての問題は、それが合理的に納得されるためにはこの意味はいかに解釈されるべきか、ということである。それはちょうどカントの認識論が『学的真理は存在し、かつそれは妥当する』という前提から出発し、ついで、このことはどのような条件のもとで合理的に可能であるか、をその問題としたのと同様である。」
『職業としての学問』68P
1:「技術的知識(技術的な意義)」
技術的知識:・実際生活においてどうすれば外界の事物や他人の行為を予測によって支配できるか、についての知識。エネルギーの法則(自然の予測)や、限界効用逓減の法則(他人がどのくらい物を欲するかなどの予測)など、役に立つ知識。
八百屋でレタスを買うように、大学で知識を学費を支払って買うというような意味合い。
「さて、最後に諸君は問うであろう、では学問はいったい個々人の実際生活にたいしてどのような積極的寄与をもたらすであろうか、と。かくて、われわれはふたたび学問の『職分』に関する問題に立ち帰るのである。この点でまず当然と考えられてよいのは、技術、つまり、実際生活においてどうすれば外界の事物や他人の行為を予測によって支配できるか、についての知識である。」
『職業としての学問』61P
2:「物事の考え方及びそのための用具と訓練(道具的な意義)」
比喩的にいえば、野菜(知識)を手に入れるための手段のようなもの(種の蒔き方等)。ウェーバーでいえば、たとえば理念型が用具にあたり、その使い方が訓練にあたる。理念型によって実際に作られたモデル(たとえば資本主義の精神など)が知識というイメージ。価値自由も物事の考え方に近い。
「では、第二の点をあげよう。これはもはや野菜売りの女のすることではあるまい。すなわち、物事の考え方、およびそのための道具と訓練がそれである。だが、おそらく諸君はまたもやいうであろう、そう、それは野菜ではない、だがそれは要するに野菜を手に入れるための手段にすぎない、と。よろしい、ではここではこの点をも問題外にしよう。」
『職業としての学問』61P
3:「明確さに導くことが出来る(道徳的な意義)」
正確さと責任:・ウェーバーは学問の実生活に対する意義として、特に第三の「明確さ」を特別に取り上げている。つまり、自分自身の究極の意味を明らかにするという科学の職分である。他にも神々の闘争を宿命として受け止めさせることなども責任にみちびくことにつながるという。ウェーバーいわく、この「明確さ」は学問がなしうる「限界」であるという。つまり事実判断と価値判断のギリギリの境目というわけだ。「自分の究極的な意味が何であるか、どのように考えているか」と「何であるべきか、どのように考えるべきか」は違う。科学は後者に対しては沈黙であり、前者に対しては助言できる余地がある。そして「自分の究極的な意味や価値、基準」(理念)が明らかに、明確になれば、それについて「責任」を負うことが出来る。この正確さと責任感を教師が学生に与えることができたなら、それは道徳的な力に仕えていることになるという。
・ウェーバーは特にこれを重視した。各々が意欲している価値理念(行為における究極的価値基準)を学問によって明確にすることで「責任」へと導くことが出来ると考えた(責任倫理)。さらに、「神々の闘争(ある価値理念を選べば他の価値理念を侮辱することになる)」を行為者に明確にさせることが出来る。
・教師は学生に明確さと正確性へと導いたとき、道徳的な力に仕えているといえる。これはレタスを単に売るのとは違い、道徳的意義をもつ。責任感のある道徳的な人間へと導く。これが知性によってできるギリギリのラインだという。
補論:科学の権能と責任倫理
補論:科学の権能と責任倫理
科学の3つの権能:①手段の適応度の検証、②随伴結果の予測、③目的の根底にある理念(究極的価値基準)の解明
例:自殺を防ぐための手段として「戦争」は適応度が高いか、低いか。手段として戦争を選んだ場合、自殺は減ったとしても、戦争で死ぬ人はどれくらいか。そもそも自殺は善いものだとか、悪いものだとか、減るべきだとか、どういうものを学者は意欲しているか。
ポイント:①と②は合理的な側面、③は責任倫理(道徳的なもの)につながる要素。自分の価値理念をはっきりとさせて、そこから距離を置きつつ、責任を持つ。自殺は減らすべきだというのは現象(事実)から導かれる当然のものであり、所与であるというような、事実と価値の混同をしないこと。自殺が善いか悪いかは事実そのものからは決してわからない。
・明確になった価値理念と手段が一貫性を持つかどうかもはっきりさせられる。戦争で人が多く死ぬなら、生命は維持させるべきだという価値理念とは一致しなくなる。戦争で自殺が減り、その意味で適応度が高いとしても、価値理念と一貫しない。戦争を終わらせるために核兵器が適合的だとしても、その随伴結果(大量に敵国の人間が死ぬ)と価値理念と一貫性を持つか。たとえ一貫性をもたないとしても、それにもかかわらず!と国の秩序のために暴力的手段を使うか悩みに悩んで選択し、その結果に責任をもつのが政治家の責任倫理。
・科学は各人に対して究極の意味(理念)について自ら責任を負うことを強いることが出来る
どうやって:科学の3つの権能によって。適合度が低いのに行為は非合理的。随伴結果が結果に対して好ましくないほど大きいのにする行為は非合理的。価値理念を明らかにすることで、事実と価値を混同させないようにさせる。混同しないことで合理的な判断ができるようになる。
→明らかに非合理的で、自分が事実と価値を混同していると科学(学問)的手段によって判明しているのに、それにもかかわらず行為をする場合はその行為者の責任になる。偶然そういう結果になっただけだ、と言い訳ができないようにする(なぜなら冷静に分析すれば非合理的だから)。
また、徹底的に合理的な予測を行い、価値自由をまもってていたとしても、現実では予測できないことも生じうる。人間は非合理的な行動を起こしうる存在。そういった結果をも行為者は責任をとる必要がある。学問的手続きを減ることは最低限の責任段階である。結果(予測)に関わらず、行為そのものに価値があり、結果に責任を取らない(頑張ったから結果が悪くてもいいじゃないか)というのは心情倫理であり、責任倫理ではない。政治指導者が自分の理念から敵国の侵入に対して非暴力という手段を取ったとして、その結果には責任をとらないようなもの。非暴力という心情を保つことだけに責任を持つような態度。結果についてはしらんぷり。
補論:心情倫理と責任倫理の矛盾を乗り越えるためには
・責任倫理を貫く人間が心情的に「我ここに立つ」と言い切るとき、責任倫理と心情倫理が絶対的に対立するものではなくなる。行為の結果を冷静に予見し、価値判断と事実判断を峻別させながら判断し、その結果に責任をもちつつ、たとえ倫理的には悪い手段であったとしても、自分の価値理念に対立するようなものだったとしても、それにもかかわらず!こうするよりほかない!われここに立つ!といえるような心情をもつような場合。単に手段や結果を冷静に検討し、責任をもつだけでは矛盾を乗り越えられない。ロボットのように正確に予測し、その結果にはその正確さ故に責任を持つ、という態度だけではだめ。そこには心情が必要。ただし責任倫理を貫いたとしても、(宗教的に)「魂の救済」は危うくなる。魂の救済を求めるものは「政治」という手段を選ばない(聖人は政治から遠ざかる)。政治は極端にいえば暴力によってのみ解決できる課題を扱うものである。学者や官僚が作った政策の法案を通すかどうか、戦争を選択するかどうか最終的に決定するのは「政治家」である。政治家には学者や官僚とは違った責任感が求められている。生活において自然は大事だから花を踏まない、というのとは違う。政治家は暴力を手段とする。
・矛盾を乗り越えるのは不可能ごとのように思えるが、不可能ごとにアタックしないようではなにごとをもなしえない、とウェーバーはいう。
詳細は以下の記事より参照してください。
【社会学を学ぶ】マックス・ウェーバーの「理念型」とはなにか(概略編)
脱呪術化、主知主義的合理化、神々の闘争
脱呪術化とはなにか、意味
脱呪術化(Entzauberung):・①呪術(神強制)から宗教(神奉仕)へ移行すること。②宗教から呪術的要素が排除されていくこと。③主知主義的合理化していくこと(呪術も宗教も排除されていく)。脱魔術化、魔法からの解放ともいう。①や②を「宗教の脱呪術化」と捉えると、②は①を根本的な要因とした「世界の脱呪術化」として捉えることが出来る。宗教の脱呪術化の場合は必ずしも神秘的(宗教的)な要素が排斥されていくものではないが、世界の脱呪術化では宗教的なものも排斥されていく。脱魔術化、魔法からの解放などとも訳される。
- 宗教の脱呪術化(宗教の合理化):呪術から宗教へ、神強制から神奉仕へ、救いの手段としての呪術の排斥へ
- 世界の脱呪術化(主知主義的合理化):宗教から科学へ、知性によって合理的に説明できないもの(宗教や呪術の神秘性)を排斥していく。宗教は神の存在を前提とするが、神の存在は証明できない。経験科学の合理主義が拡大していくき、自然因果律的な世界観が第一となる。宗教は知性の犠牲を要求する。
「『岩波哲学・思想事典』において中野は,呪術を「神強制」,宗教を「神奉仕」と捉え,「神強制」から「神奉仕」への移行が,「『呪術』から『宗教』への移行であり,本来はこのプロセスが脱呪術化と呼ばれるものである」と説明している(1034頁)。この解釈は,『経済と社会』の中の「宗教社会学」における論述に基づいているようであり,そこでは「脱呪術化」という語は用いられてはいない。だが,「救いの手段としての呪術を排除する」ということをもう少し広く捉えれば,それは宗教から呪術的要素を排除するということになる。実際,ヴェーバー自身,「儒教とピューリタニズム」の中で,宗教の合理化の一つの規準は「宗教がどこまで呪術を払拭しているか」ということだと述べていた。とすれば,文字通り呪術から抜け出し,宗教の原理が宗教の原理として確立される,ということこそ宗教の脱呪術化の意味だ,という解釈は十分に成り立ちうるものである。」
千葉芳夫「脱呪術化と合理化」106P
「ヴェーバーは,このように近代の科学的思考を呪術だけでなく,宗教とも根本的に対立するものだと捉えている。とすれば,世界像(=世界の捉え方)という面では,呪術から科学へではなく,呪術的世界像→宗教世界像→科学世界像という三段階で捉えられている,と考えねばならない。つまり,主知主義的合理化という意味での脱呪術化は,文化諸領域の自立ではなく,世界像の変化に関わるものだと解釈すべきなのである。」
千葉芳夫「脱呪術化と合理化」107-108P
「経験科学の合理主義が増大するにつれて,宗教はますます合理的なものの領域から非合理的なものの領域に追い込まれていく」
(マックス・ウェーバー『中間考察』148頁)。
神奉仕と神強制
神強制():・人間が救済や利益を得るために、なんらかの手段で神を使役すること。神は人間の働きかけがないと活動しない。例:お賽銭を神様に投げてお願いする。贖宥状(免罪符)で罰を逃れようとする。
神奉仕():・人間が神にもっぱら従属する関係性。苦難の神義論を合理的に説明するときに、神奉仕は必然的に生まれてくる。例:贖宥状では罰が逃れられず、生まれた時から神が人間を救うかどうかは定められていて、人間の意志ではどうにもならないと考える(予定説)。神拝礼ともいう。
「さて、呪術にも宗教にも、広い意味での超自然的な存在(神、あるいは神々)が出てきます。人間を超えている、あるいはふつうの自然現象を超えた、プラスアルファ的なものが、過剰なものが出てくる。それらをすべてまとめて広い意味での神と考えたときに、呪術を成り立たせている関係性は『神強制』であり、宗教の方は『神奉仕』です。ウェーバーは、『宗教社会学』の中でこのように論じています。神強制と神奉仕とは何か。たとえばわれわれ日本人がお正月になると百円くらいのお賽銭をあげて、今年一年無病息災で過ごせるように、と神さまにお願いする。これは神強制の一種です。お賽銭で神さまを買収し、動かそうとしている。一種の賄賂ですね。この例に見られるように、人間が、とくに専門家である人間(呪術師)が、救済や利益を得るために、なんらかの手段で神を使役すること、これが神強制です。それに対して、人間が神にもっぱら従属する関係性が神奉仕です。神奉仕は、具体的には、供犠とか、礼拝とか、祈祷とかの行為によって具体化されます。神強制が呪術に、神奉仕が(狭義の)宗教に対応している。脱呪術化とは、神強制が有意味に成り立つ世界から神奉仕ではなくてはならない世界への以降です。」
大澤真幸『社会学史』,316-317P
「「神強制(Gotteszwang)」とは,「超感性的な力」を呪術によって強制することであり,先の中野の説明にあるように,これが呪術的世界の特徴なのである。「宗教」は同様に「超感性的」で「象徴主義的」世界をもちつつ,「神強制」ではなく,「神礼拝(Gottesdienst)」(中野は「神奉仕」としている)を本質的な特徴とする。呪術的世界の神々に対する「擬人化と機能限定の過程」が生じ(S.251,19頁),擬人化の過程が進むにつれ,神々は強大な力をもつ地上の君主と同様強大な存在者と考えられるようになる。「こうして『神礼拝』の必然性が生まれてくるのである」(S.258,36頁)。ここから神が定めた秩序に対する違反としての宗教的な罪の観念および救済の観念が生じる。特に重要なのは「苦難の神議論(TheodizeedesLeidens)」(「序論」S.244,45頁)である。何故神はこのような苦難に満ちた世界を作りたもうたのか,という問いに合理的な説明があたえられる必要が出てくるのである。ヴェーバーによれば,これに対して首尾一貫した説明をあたえている神議論は「インドの業の教説,ゾロアスター教の二元論,および隠れたる神の預定説」の三つしかない(同SS.246−247,48−49頁)。ともあれ,こうした過程の内で,この世界は「神が秩序をあたえた,したがって,何らかの倫理的意味をおびる方向づけをもつ世界」だという世界像が出来上がっていくのである」
千葉芳夫「脱呪術化と合理化」108P
宗教から呪術的要素が徹底的に排除され、合理化されていく
・宗教改革は贖宥状で罰を免じるようなカトリックの神強制的な考え方の批判が主な内容であり、プロテスタントのもっとも徹底した立場は神奉仕であり、カルヴィニズムにおける予定説。
・カトリック的なキリスト宗教の呪術的要素が徹底的に排斥され、徹底的に合理化されていった。神奉仕という立場を徹底的に合理化すれば、予定説という立場に論理的に帰結する。ただしそもそも神に奉仕するかどうか、神が存在するかどうか、信仰するべきかどうかは非合理的であり、価値判断の領域。最初に価値判断を行い、目的を設定すると、手段は徹底的に合理的になる。たとえば徹底的に合理的な職業活動に勤しみ、利益を浪費せず、再投資する。こうして資本主義の機構(鉄の檻)が出来上がっていく。本来の倫理的なもの(プロテスタンティズムの倫理)が抜け落ち、利益を出すことが倫理的と見なされるようになる(資本主義の精神)。さらに倫理性も抜け落ち、利益の追求だけがスポーツ感覚として残る。
主知主義的合理化とは、意味
主知主義的合理化():・可能性としてはすべてのことが知性で解明でき、それらに呪術的で神秘的な予測できない力が働いていないと信じ、原則上予測によってすべてのことが意のままになるということを知っている、あるいは信じていくようになること。
主知主義:可能性としてはなにごとでも知性で解明できるという信念であり、知性で解明できないような不合理なものは一切信じないという心の態度。
合理化:意味適合性、計測性、可測性、可算性など、技術と予測が中心になっていくこと。予測や計算ができない非合理的なものは排斥され、予測や計算できるものが中心となっていく。対象へ即事物的(ザッハリッヒ)に接近していくこと。
例:電車が動く仕組みは実際に知らなくても、知ろうとすれば学び知れることが常にでき、またそこに呪術的な要素がないと信じている。現在仕組みが解明されていないような現象も、すべて解明でき、予測でき、支配できるようになると信じている(人魂現象が解明されていくように)。実際に知っているかどうかではなく、知ることが出来ると信じている態度を意味する。多くの人はインターネットの仕組みも車の仕組みも飛行機の仕組みも知らない。しかし合理的に、非呪術的に設計されていると信じて使う。呪術師に恐る恐る治療を頼む態度とは違う。医者は合理的な治療行為をすることができるだろうと信じて、医者に会いに行く。
「つまり、それを欲しさえすれば、どんなことでもつねに学び知ることができるということ、したがってそこにはなにか神秘的な、予測しえない力がはたらいている道理がないということ、むしろすべての事柄は原則上予測によって意のままになるということ、──このことを知っている、あるいは信じているというのが、主知化しまた合理化しているということの意味なのである。ところで、このことは魔法からの世界解放(エントッアウベルソク・デア・ウェルト)ということにほかならない。こんにち、われわれはもはやこうした神秘的な力を信じた未開人のように呪術に訴えて精霊を鎮めたり、祈ったりする必要はない。技術と予測がそのかわりをつとめるのである。そして、なによりもまずこのことが合理化の意味にほかならない。」
『職業としての学問』33P
「彼にとって《合理性》とはそもそも何であるのか。池田昭氏は、最も抽象的に解される場合、ウェーバーの『合理性』とは、『最適度の意味適合性』であると考えているが、それをもう少し現実に即して理解するならば、ウェーバーの『合理性』を貫く基礎的な特徴は『計測性』、『可測性』、『可算性』と結びつけて考えるとわかりやすいように思われる。伝統主義の支配する『呪術の園』では、事物また事物的な諸関係を、伝統的・感情的な人格と結び付けられた諸関係が覆っており、人々が事物そのものに即して計算することを阻んでいた。合理化されるということは、そのような呪術の覆いが消え去って、対象へ即事物的(ザッハリッヒ)に接近できるようになり、したがって、対象を徹底的に分析し計量して明確な結論(予測も)出すことができるということである。その場合、たとえば一般的抽象規則や貨幣による計算原則のように、特定の具体的な内容に関わりなく一般的な形式として現れてくる合理性と、具体的な場面における具体的な行為の内容が一定の評価基準に即して現れてくる合理性との、二種の合理性を含んでいる。前者が『形式合理性』、後者が『実質合理性』と呼ばれる。」
「社会学のあゆみ」,有斐閣新書、39-40P
神々の闘争とは、意味
神々の闘争():・「世界に存在するさまざまな価値は互いに解き難い闘争の中にあること」を意味する。「価値の多神教」や「神と悪魔の闘争」とも表現されることがある。
価値は真・善・美といった根本的な価値や文化的な価値、個々人の生活の拠り所となる究極的な態度にまで及んでいる。そしてこの神々の闘争を解決できるのは学問ではなく、運命であるとウェーバーは言う。人々はこの神々の闘争という現実に目を向けて、積極的に自らが選んでいる価値を自覚し、責任感を持ち、選択し、創造していく必要があり、そのことが文化人の役目であると考えている。
価値は人の数だけ多く存在するという価値多元論であり、諸個人の究極的価値は互いに対立し、闘争となることを意味する。普遍的で絶対的な価値が宗教的な信仰によって、あるいは科学的な解明によってたどりつけると思われていた時代が終わり、それぞれが究極的な価値を選択しなければいけなくなり、それぞれがバラバラに価値を選択するゆえに必然的に闘争に帰結するというもの。
例えば「いかなるときも暴力は良くない」と考える人間は「人を助けるときに暴力は正当化される」と考える人間と対立する。「いかなる価値もそれぞれ等しい価値をもつ」という中庸的な人間は「そんな中途半端な価値は許されず、自分の価値だけが正しい」と考える人間や「いかなる価値も無価値である(という価値)」と考える人間と対立する。どんな価値を選択したとしても、いずれかの価値と必ず対立する。神を選べばだれかの神が悪魔になる。
「これまで、わたくしは個人的な立場を人に強いることについて、もっぱら実際上の理由からそれを避けるべきであると論じてきた。……もっと深い理由によるのである。というのは、こんにち世界に存在するさまざまの価値秩序は、たがいに解きがたい争いのなかにあり、このゆえに個々の立場をそれぞれ学問上指示することはそれ自身無意味なことだからである。……すなわち、われわれはこんにちふたたびつぎのような認識に到達している。あるものは美しくなくとも神聖でありうるだけではなく、むしろそれは美しくないがゆえに、また美しくないかぎりにおいて、神聖でありうるのである。このことを証拠だてるものは、イザヤ書第五三章や詩篇第二一篇にもとめられる。また、あるものは善ではないが美しくあり得るというだけでなく、むしろそれが善ではないというまさにその点で美しくありうる。このことはニーチェ以来知られており、またすでにボードレールが『悪の華』と名付けた詩集のうちにも示されている。さらに、あるものは美しくもなく、神聖でもなく、また善でもないかわりに真ではありうるということ、いな、それが真でありうるのはむしろそれが美しくも、神聖でも、また善でもないからこそであるということ、──これはこんにちむしろ常識に属する。だが、これらは、こうしたもろもろの価値秩序の神々の争いのなかでももっとも単純なばあいにすぎない。……そして、これらの神々を支配し、かれらの争いに決着をつけるものは運命であって、けっして『学問』ではない。学問が把握しうることは、それぞれの秩序にとって、あるいはそれぞれの秩序において、神に当たるものはなんであるかということだけである。教室で教師がおこなう講義も、この点を理解させることができればその任務は終るのである。もとより、その講義のなかにかくされている重大な人生の問題は、これで片付いた訳では無いが、この点については、大学の教壇以外のところにある別の力が物をいうのである。」
『職業としての学問』53-55P
「もし君たちがこれこれの立場をとるべく決心すれば、君たちはその特定の神のみに仕え、他の神には侮辱を与えることになる。なぜなら、君たちが自己に忠実であるかぎり、君たちは意味上必然的にこれこれの究極の結果に到達するからである。学問にとってこのことはすくなくとも原則上可能である。」
『職業としての学問』64P
「すなわち、各人がその拠り所とする究極の立場のいかんに応じて、一方は悪魔となり、他方は神となる。そして、各人はそのいずれかがかれにとっての神であり、そのいずれかがかれにとっての悪魔であるかを決しなければならない。しかも、これはわれわれの生活のすべての秩序についていえることである。かの倫理的に節度ある生活態度に内在した偉大な合理主義は、あらゆる宗教的予言に共通の産物であるが、この合理主義は、かつて『唯一不可欠の神』のためにこうした多神教をその王位から斥けたのであった。……かつての多くの神々は、その魔力を失って非人格的な力となりながら、しかもその墓から立ちあらわれて、われわれの生活への支配をもとめてふたたびその永遠の争いをはじめている。ところが、現代の人々にとって、とくに現代のヤンガー・ジェネレーションにとって、もっとも困難なのは、この日常茶飯事に堪えることである。かの『体験』をもとめる努力も、この意味の弱さからきている。というのは、弱さとは結局時代の宿命を正面に見ることができないことだからである。」
『職業としての学問』56-57P
「唯一の正しい選択への希望、万人にとって普遍である真理への確信は、いまでは失われてしまいました。我々現代人はニーチェが宣告したように『善悪の彼岸』に立たされています。ウェーバーは聴衆に対し、『ギリシャの昔、まだ世界が神々や守護霊(デーモン)の支配を脱していなかったころ』を想起するように求め、この『神々の闘争』が現代において『再び』始まっていると告げます。我々はこのことを『現代文明の運命(シックザール)』として正面から受け止めなければならない。ウェーバーは神の死という事態を、異常なこととしてでなく、『日常的な事(アルターク)』として理解する必要を語ってやまないのです。」
山之内靖『マックス・ウェーバー入門』40P
自由喪失
・ハーバーマスのウェーバー解釈によれば神々の闘争は「意味喪失」を意味し、鉄の檻(鉄の容器)は「自由喪失」を意味する。
・普遍的な基準というものを学問は証明できず、宗教も信仰の力を失っているので、各々が自分の主観で神を選び、神々の闘争になる。そしてこの神々の闘争は現代文明の「運命(宿命)」である。人々が主知主義的合理化していくと、究極的真理や神、といった非合理的な惟一の正解を受け入れがたくなっていく。知性に信頼を置くがゆえに、非知性的なものを信仰することができなくなる。
・しかし知性は絶対的な正解を教えてくれず、世界とはどうあるべきか、自分はどう生きるべきかについて何ら回答を与えてくれない。人間は路頭に迷い、(神々の闘争を直視ぜず、普遍的・絶対的な神としての)新しい預言者を探し求める人間も出てくる。神々の闘争は学問を志すものだけではなく、多くの人々が直面する事態。
・神々の闘争を自覚せず、既存の価値にただ適応するだけで、周りがそう考えているからそうだろうと適応するだけのような人間を「機械的化石化」と表現した。
・ウェーバーは「神々の闘争」を時代の宿命として肯定的に、「機械的化石化」は危惧すべき未来として否定的に見ているという(田上大輔)。機械的化石化はニーチェのいう「末人」、つまり「現状に満足して新しい発展を目指さない人間」のイメージに近い。
・神々の闘争は「機械的化石化(精神生活の凝固化)」を防ぐことが出来る防波堤となりえる。なぜなら、神々の闘争は新しい問題提起を促進させるからだという。人々が神々の闘争を直視し、神と悪魔の選択を行うことで機械的化石化に陥ることが回避可能ではないかという問題(田上)。
「価値観点や価値理念の多元性と対立関係を新しい問題提起を生み出す源と捉えるヴェーバーからしてみれば、この「神々の闘争」もそこに生きる人間に直視されれば、〈精神生活の凝固化〉を防ぐ防波堤となりうる。このように「神々の闘争」は、新しい問題提起を促進させるか否かという点で「価値観点の神々の黄昏」や〈精神生活の凝固化〉と好対照をなしており、この点において「機械的化石化」とも対照的と言える。「ところが現代の人々にとって、とくに若い世代の人々にとって、もっとも困難なのは、この日常に対応することである」とヴェーバーは述べ、「時代の運命」から顔を背ける人間の弱さを問題にした[Weber1922:605=1980:57]。こうした弱さを補って、「神々の闘争」を直視することを助ける方策として着目すべきは、ヴェーバーが科学の与える「明確さ」(Klarheit)によって、特定の立場を選ぶことが、特定の神に奉仕し、他の神に侮辱を与えることだということを明瞭にするとしたことである[Weber1922:608=1980:63]。この種の「明確さ」を与えることが、「価値討議」の意義であったことを鑑みれば、この討議や「明確さ」を与える科学の助けを借りることによって、「脱呪術化」された「神々の闘争」の中に生きる人間は、この時代状況を直視し、神と悪魔の選択を行うことで、〈精神生活の凝固化〉に陥ることを回避することが可能となるのである」
田上大輔「M・ヴェーバーの西欧近代批判再考―機械的化石化と神々の闘争の対照性に着目して―」、128P
補論:文化的な価値、倫理的な価値、学問的な価値
1:文化的な価値:ハーバーマスの区分では芸術と批評、自己表示的領域。千葉芳夫さんいわく「美」の領域。ウェーバーいわくある論述が文化内容に向かって奮起しうる能力に訴えている場合。別の言い方をすれば趣味判断。
2:倫理的な価値:ハーバーマスの区分では法と道徳、規範的領域。千葉さんいわく「善」の領域。ウェーバーいわくある論述が良心に訴えている場合。別の言い方をすれば倫理判断(道徳的判断)。
3:学問的価値:ハーバーマスの区分では科学と技術、認知的領域。千葉さんいわく「真」の領域。ウェーバーいわくある論述が経験的現実を概念的に整序する我々の能力(理論理性)に訴えている場合。別の言い方をすれば事実判断。知性。
「「神々の闘争」とか,「神と悪魔の闘争」といった表現はそれ自体比喩的であるし,彼の社会学の中心的な概念とは違い,明確に規定されてもいない。そのため,様々に解釈される余地を残している。以下,いくつかの解釈を取り上げ,検討することから始めよう。浜井は,「神々の闘争」が意味するのは価値多元論であるとし,次のような解釈を示している。「…ウェーパーの価値論は神々の永遠の争いを『根本事実』として認める価値多元論であった。真,善,美,聖等の諸価値領域,あるいは政治,経済,宗教,学問,芸術等の価値序列相互の間で永遠の闘争が存在し,その決着は誰もつけることができない(6)「神々の闘争」の意味するものが,まずは価値多元論,それも多元的な価値の対立であることは,間違いあるまい。だがウェーパーは,諸価値領域あるいは諸価値序列の並列的な対立を考えているのだろうか。「客観性」論文では,「個々人が実現しようと欲する文化理想と彼が果たすべき倫理的義務とは,原理的に異なる尊厳を持つ」と言われている。つまり,文化と倫理が異なる価値領域に属するということである(9)。周知のように,「客観性」論文における主要な論点の一つは,事実判断と価値判断との異質性の主張であるが,さらに価値判断の内部でも異質な二つの領域が区別されている訳である。それに科学を加えれば異質な三つの領域が区別されることになる。「ある論述が,我々の感情や,具体的実践的目標とか文化形式及び文化内容とかに向かつて奮起しうる能力に訴えている場合,また倫理的規範の妥当が問題になっている際に,我々の良心に訴えている場合,或は最後に経験的真理としての妥当を要求しながら経験的現実を思惟的に整序する我々の能力と欲求とに訴えている場合,これらの三つの仕方の聞には越え難い相違がどこまでも存する…ここで主張されていることは,諸価値領域・諸価値秩序の単なる並列的な対立とは明らかに異なっている。、ハーバーマスの解釈は,この論点に対応するものである。彼は,ウェーパーが価値領域を基本的には科学と技術,法と道徳,芸術と批評,の三つに区分している,と解釈する(11)。ハーバーマスはそれを,認知的領域,規範的領域,自己表示的領域などと呼んでいるが,伝統的な用語を用いるなら,真,善,美,という三つの価値領域である。」
千葉芳夫「『神々の闘争』と科学」65-66P
キリスト教以前と以後、キリスト教における目眩まし
・脱呪術化が進行していくと、神々の闘争に帰結する
キリスト教以前:多神教の時代。都市ごとに神が信仰されていたり、季節ごとや行事ごとに違う神が信仰されていた。
キリスト教以降:キリスト教などの唯一神教(他の神を一切認めない)が力を持っていた時代は、ただひとつの究極的な価値(神の教え)が信仰されていたので、人々は世界に意味はあるのか、どう生きて行くべきか、何が善いことで何が悪いことなどかをあまり考えなくても良かった。呪術的、神秘だから否定されるというようなこともない時代。別の言い方をすれば「魔法にかかった世界(モリス・バーマン)」。
たとえばキリスト教における悪魔であるアスタロトやベルゼブブは多神教の時代の神々であり、キリスト教が悪魔とみなして排斥していった経過として考えることが出来る。アスタロトは古代セム人が信仰していた豊穣の女神アスタルテであり、ベルゼブブはペリシテ人が信仰していたバアル・ゼブルである。
・ウェーバーは「千年の長きにわたって、キリスト教倫理の大きな情熱にたいする名目上あるいは想像上専一的な帰依のゆえに、この宿命をみる目がくらまされていた」と主張している。
・宿命とは「神々の闘争」を意味する。キリスト教以前は元々「神々の闘争」の時代であり、キリスト教が力をもっていたことで「目がくらまされていた」ということ。ウェーバーいわく近代以降は「神なく預言者なき時代」であり、ニーチェの「神は死んだ」という発言と類似している。
・近代化以降はキリスト教以前の呪術的・神秘的要素は脱落している。呪術的な要素は弱まっているが、究極的な価値(神)を選ばなければならないという事態はキリスト教以前と同じである。多神教の時代に戻ったが、以前のような神秘的な要素はない。だからこそ新興宗教などの形で新しい神や預言者が求められている(再魔術化,モリスバーマン)。
ただしモリスバーマンにおける最魔術化は、前近代的な世界に戻るというものではない。どのように前近代的な良さ(呪術的・魔術的要素)を近代の良さを組み合わせるかという話になる(具体的にはベイトソンの体系を利用するのだが、ここで説明しきれるような内容ではないので省略する)。
「かつての多くの神々は、その魔力を失って非人格的な力となりながら、しかもその墓からたちあらわれて、われわれの生活への支配をもとめてふたたびその永遠の争いをはじめている。ところが、現代の人々にとって、とくに現代のヤンガー・ジェネレーションにとって、もっとも困難なのは、この日常茶飯事に堪えることである。かの『体験』をもとめう努力も、この意味の弱さからきている。というのは、弱さとは結局時代の宿命を正面にみることができないことだからである。しかし、現代文明の宿命は、いまや以前にも増して明らかにわれわれの意識するところとなるであろう。これまでは、千年の長きにわたって、キリスト教倫理の大きな情熱にたいする名目上あるいは想像上専一的な帰依のゆえに、この宿命をみる目がくらまされていたのである。」
56-57P
『職業としての学問』57P
「科学革命前夜まで、西洋の人々も驚きと魅惑に満ちた世界を生きていた。これを『魔法にかかった世界』(enchanted world)と表現してもいいだろう。」
モリスバーマン『デカルトからベイトソンへ』14P
「近代という時代は、その精神面に焦点を合わせるなら、しだいに『魔法』が解けていく物語として語ることが出来る。十六世紀以降、現象界から『精神』なるものがみるみる追放されていった。近代科学は、少なくとも理論レベルでは、すべてを物体と運動に還元して説明する。」
モリスバーマン『デカルトからベイトソンへ』14P
補論:文化人
人間は自分でなにが究極的価値かを選択し、自分で創らなければならない。それ自体としては意味のない文化現象に自分の価値理念によって意味づけする(神を選び、その神に基づいて行為する)以上、その神に対立するような悪魔との対立になる。これが神々の闘争。皆が同じ神を選んでいたら闘争にはなりにくい(宗教戦争は起きる)。皆が同じ神を選べなくなりつつある、非合理的・呪術的なものを科学の発達によって信じられなくなり、合理的なものを信仰する時代に来ている。
「『文化』とは、世界に起こる、意味のない、無限の出来事のうち、人間の立場から意味と意義とを与えられた有限の一片である。人間が、ある具体的な文化を仇的と見て対峙し、『自然への回帰』を要求するばあいでも、それは、当の人間にとって、やはり文化であることに変わりはない。けだし、かれがこの立場決定に到達するのも、もっぱら、当の具体的文化を、かれの価値理念に関係づけ、『軽佻浮薄にすぎる』と判断するからである。ここで、すべての歴史的個体が論理必然的に『価値理念』に根ざしている、というばあい、こうした純論理的──形式的事態が考えられているのである。いかなる文化科学の先験的前提も、われわれが特定の、あるいは、およそなんらかの『文化』を価値があると見ることにではなく、われわれが、世界に対して意識的に態度を決め、それに意味を与える能力と意志をそなえた文化人である、ということになる。」(マックス・ウェーバー『客観性』92-93P)
補論:マルティン・ルターと偶像
マルティン・ルター(1483-1546)の時代はちょうど宗教改革の時代でありたルターは宗教改革の中心人物。
・「われわれの大抵のものは、一時的にか恒久的にか神々を崇拝し、偶像に身を捧げている」とルターはいう。キリスト教では偶像崇拝が禁止されています。金の子牛を崇拝した民が神によって皆殺しにされた話が聖書にはある。ここでいう神々は「偶像」だというのがポイント(キリスト教では神が1人なので神々という言い方をしない)。この偶像はアフリカの部族のトーテムや悪魔崇拝、ゼウスへの信仰、神聖な動物や自然への信仰といった呪術的・宗教的・神秘的ものだけではなく、異性や理性、お金や科学をも含んでいるのです。要するに「人がそれぞれ我を忘れて心酔し、心奪われ、崇拝するもの」が偶像にあたるという考え。ウェーバーでいえばこの偶像は神々になり、キリスト教の神もまた他の偶像と同じレベルに落ちたような状況(価値並列的)。
・唯一神であるヤハウェのみを崇拝せよと聖書ではいっているけれども、自分の子どもや奥さん、両親に執着したり、ゲームで1位をとることだけに執着したり、お金に執着したり、とにかく人によく思われることだけに心を奪われていたりする。要するに前近代の人々のだれもかもが唯一神のみを崇拝できていたのではなく、他の偶像に心を奪われるのが常だったのである。神のみを崇拝しきることは恩恵がなければ到底出来ることではないとルターはいう。神が子どもを犠牲にせよといっている、と預言者がいってきたらどうするか。現代においては、それは非合理的だからできない、という人が多いのではないか。知性を犠牲にして信仰しきれれるか。嘘をつくことが明らかに利益になる場合はつくのではないか。
要するにヤハウェの神は偶像崇拝を一切排除して唯一神たるかれを拝せよと人間に要求しているのであるが、この要求に心底からこたえることは人間わざでは到底できることではない(だから神の側からの働きかけ、つまり恩恵が必要なのだ、とルターはいうのだが)、なぜなら、人間という生き物は唯一の神、大文字の神には背をそむけながら、それぞれ思いのままに神々を拝し偶像を崇拝するものだからである、しかもその神々ないし偶像とはなにも文字どおり機会な様子をした彫像や画像である必要はない、女(男)であろうと金であろうと、はたまた理性であろうと、人がそれぞれ我を忘れて心酔し、心奪われ、崇拝するものが、とりもなおさず、その人にとっての神ないし偶像だからである。
嘘だと思うなら自分の胸に手を当ててよく考えてみよ。こういった趣旨のことをルターはそこで述べている。
これはなかなか鋭い人間洞察といわなくてはならない。この伝でいけば、われわれの大抵のものは、一時的にか恒久的にか神々を崇拝し、偶像に身を捧げている。「科学的」社会主義者も例外ではない。なぜなら、かれらも「科学」を信仰しているからである。それはともかく、いずれにしても神々への信仰(偶像崇拝)は人類の歴史とともに古い。それは人間の本性のようなものである。その神々への信仰が、唯一神への信仰(ないし世界史上それに肩を並べる救済宗教)の「重し」が取り去られた今(ウェーバーによれば、現代は「神なく預言者なき時代」である)、装いも新たに、おおっぴらに復活した(「神々の復活」と「神々の闘争」の時代としての現代)。それが先の四つの救済追求である。
「知と意味の位相」、雀部幸隆、恒星社厚生閣 255-256P
道徳的リゴリズム
・初期ウェーバーは過剰な道徳的リゴリズムの傾向があった(雀部)。リゴリズムとは道徳的に厳格な規律を設定し、それに従おうとする主義のこと。
→趣味判断、倫理判断、事実判断が全て同列(並列)な価値をもつわけではなく、倫理判断が優先すると考えていた(価値には序列があると考えられていた)。たとえば趣味判断において家庭内暴力は好ましいものだという趣味判断からくる価値と、家庭内暴力は善くないものだという良心からくる倫理的な価値が対立している場合、倫理的な価値が優先するという考え。ア・プリオリな前提(学問によって序列が証明されているわけではなく、単に前提として置いている)。趣味判断が道徳判断の領域を犯してはいけないという考えにつながっていく。
→ウェーバーが(道徳的)責任を重視することからもリゴリズム的な要素がうかがえる。騎士道精神という言葉が使われることもある。
・「運命」は「人生というものがいかに人間をもてあそぶか」を意識するようになったウェーバーは、この道徳的リゴリズムを弱めていったそうだ。つまり、純粋に知の立場から出発する限り、文化的な価値、倫理的な価値、学問的な価値のどれもが並列的であり、争いが生じる(神々の闘争)。ただし、知の立場以外(感性や信仰、良心など)から出発すれば、必ずしも多神論が帰結するわけではないと解釈できる。知性を犠牲にするかどうかという話。
→後期ウェーバーは趣味判断の領域、美とエロスの領域についても積極的に承認するようになっていったが、規範的なもの、道徳的なものについての尊重という態度は変わらなかったという(雀部)。
・新しい預言者を求める神秘主義の影響を受けたドイツの若者に対して、ウェーバーは、「国民が疲労困憊しているこの時に、自分一人の魂を救って何になる?」と吐き捨てるようにつぶいやいたそうだ(マリアンネ・ウェーバー『マックス・ウェーバー』,447P)。
「もちろん修行時代のウェーバーとフライブルク大学教授就任以降のウェーバーとのあいだには、ニーチェとの出会いがある。そしてウェーバーは、ニーチェと出会うことによって、一方では『意味の形而上学』への見切りをさらに徹底させると同時に、他方では青年時代にその気味のあった道徳的リゴリズムをア・プリオリに前提する立場(『中間考察』の表現を借りるなら『先験的な[倫理的]厳格主義』der apriorische Rigorismus の立場である。)から脱却する。……他方ではウェーバーは、のちに見るように、青年時代の『先験的な[倫理的]厳格主義』の立場から離れはしても、かれ一個の心情の問題としては倫理規範重視の立場──これはかならずしも道徳的『リゴリズム』の立場と同じではない──そのものを放棄するわけではないのだから、『究極的意味』問題にたいするかれの基本姿勢は、結局若い頃から一貫して変わらなかった──青年時代の『信仰』問題についての発言も『究極的意味』問題にに関する発言である──、と見るのが妥当だろう。」
雀部幸隆『知と意味の位相』353-354P
「『究極の立場』ですって?そんなものは愚にもつかぬおしゃべりのきっかけになるだけですし、センセーションを呼び起こすだけで、なんの役にも立ちません。それに、なによりもわたしは、長年の経験から、またわたしの原理的に確信するところからして、その問題に関してつぎのように考えております。ある人間が本当に望んているものが何であるかは、これぞわが『究極の』立場だと称するその人の言い訳からではなく、およそ言抜けを許さぬその時々のまったく具体的な問題にたいして、というところの『究極の』立場からして、その人が実際にどう対処するかによってのみ確かめられるのだ、と。」
エーリッヒ・トゥルムラー宛てのウェーバーの手紙の内容
神々の闘争の時代で我々は一体どういう態度をとればいいのか
自分の仕事に就き、日々の要求に従えばいい
日々の要求に従う:・日常の具体的な問題に責任を持って対処すること(大林信治さんの解釈)。各人が人生を操っている守護霊(デーモン)をみいだして従えば容易におこなわれる。
デーモン():・本来の自己(大林信治さんの解釈)。尾高邦雄さんの訳では守護霊。柴田育子さんの解釈では文字通りのデーモン(悪霊)をも意味し、人間と神の中間的存在として位置づけられるそうだ(悪魔はデビル)。
・職業(仕事)としての学問におけるデーモンは「知的廉直(誠実)さ」であり、職業としての政治におけるデーモンは「責任倫理」に相当するのではないか。知的廉直さがあれば、学問の場合、教壇で価値を生徒に強いることは控えることが自然と各人に要求される。政治の場合では自分の倫理観を押し通すことだけを考えずに、ときには自分が悪魔と思えるような暴力を、国の安全のためには「それにもかかわらず!」と責任を持って選択を要求されることがあるのではないか。
・コックなら客に美味しいと思わせることであり、サラリーマンなら会社に利益を出すこと、顧客に満足してもらうこと等が考えられる。何が求められているかという要求を考えれば自ずと見えてくる。政治や学問といった領域だけではなく、一般生活全般において、神々の闘争は浸透している。
・ただし、政治の場合は日々の要求と価値理念が矛盾しやすい。なぜなら政治は暴力を手段とするのであり、価値理念と矛盾しやすいからである。だからこそ、その矛盾を乗り越えなければいけない。不可能ごとに思えるが、不可能ごとにアタックしないようではなにごともなしえない。知性、感性(心)、良心を総動員して考え抜くことが必要とされる。
「なぜなら、教壇上の予言は、教室のなかではなんといっても率直な知的廉直以外の徳は通用しないのだということを解していないからである。ところが、この徳ははわれわれに命じる、こんにち新しい預言者や救世主を待ちこがれている多くの人々のすべてにとって、事情はちょうどイザヤ書に記録されている幽囚時代のエドムの斥候(ものみ)のあの美しい歌におけるとおなじであることを確認せよ、と。いわく、『人ありエドムなるセイムより我をよびていふ、斥候よ、夜はなほ長きや。ものみ答えへていふ、朝(あした)はきたる、されどいまはなほ夜なり。汝もしとはんとおもはば再び来たれ。』かく告げられた民族は、その後二千年余の長きにわたって、おなじことを問い続け、おなじことを待ちこがれ続けてきた。そして、この民族の恐るべき運命はわれわれの知るところである。このことからわれわれは、いたずらに待ちこがれているだけではなにごともなされないという教訓を引きだそう、そしてこうした態度を改めて、自分の仕事に就き、そして『日々の要求』に──人間関係のうえでもまた職業のうえでも──従おう。このことは、もし各人がそれぞれの人生をあやつっている守護霊(デーモン)をみいだしてそれに従うならば、容易にまた簡単におこなわれうるのである。」
73-74P『職業としての学問』
「「デーモン」という単語には、これまで「守護霊」、「本来の自己」という日本語が当てられてきた。しかしこれは、それに加えて、文字通り「悪霊」という意味も含む単語ではなかろうか。「悪霊」とは、神と人問の中間的存在として位置づけられるものである。責任倫理的な「学問」の場合にも、ある立場の選択に際しては、異なる他の立場を侮辱することもあり得る。この意味で「学問」は二者択一だけでなく、「神」と「悪魔」の問におけるような必死の闘争も引き起こしうる。一方「政治」は、そもそもが暴力を肯定し、「暴力の中に身を潜めている悪魔と力関係を結ぶ」こともあるものである。両者は、「宗教倫理」が持つような甘えは持たない。学問を職業とする者の「デーモン」は、いうまでもなく「知的誠実さ」である。政治を職業とする者の「デーモン」は、どんな希望の挫折にもめげない固い意志である。各々の「デーモン」はことなるが、「責任」において生きることは共通している。共に異なる「学問」と「政治」の世界はここにおいて連結する。」
柴田育子「マックス・ウェーバーにおける『学問』と『政治』」、59P
ピアニッシモ
・ウェーバーの名文を最後に紹介して終わります。これは全文記憶しておくべき文章だと思います。
「こんにち、究極かつもっとも崇高なさまざまの価値は、ことごとく公の舞台から引きしりぞき、あるいは神秘的生活の隠された世界のなかに、あるいは人々の直接の交わりにおける人間愛のなかに、その姿を没し去っている。これは、われわれの時代、この合理化と主知化、なかんずくかの魔法からの世界解放を特徴とする時代の宿命である。現代の最高の芸術が非公共的であって記念碑的な存在ではないこと、また、かつて嵐のような情熱をもって幾多の大教団を沸きたたせ、またたがいに融合させた預言者の精神に相当するものは、こんにちではもっとも小規模な団体内での人間関係のなかにのみ、しかも最微音(ピアニッシモ)をもって脈打っているにすぎないこと、これらはいずれもゆえなきではない。もし記念碑的な芸術品を無理につくろうとしたり、また『発明』しようとしたりするならば、その結果は過去二十年間の多くの記念碑的作品におけるような惨めな出来損ないに終るであろう。」
『職業としての学問』71-72P
参考文献・おすすめ文献
参照論文
1:柴田育子「マックス・ウェーバーにおける『学問』と『政治』」(URL)
2:千葉芳夫「『神々の闘争』と科学」(URL)
3:新矢昌昭「近代人の孤独」(URL)
4:千葉芳夫「脱呪術化と合理化」(URL)
5:田上大輔「M・ヴェーバーの西欧近代批判再考―機械的化石化と神々の闘争の対照性に着目して―」(URL)
今回の主要文献
マックス・ウェーバー『職業としての学問』
マックス・ウェーバー『社会科学と社会政策にかかわる認識の「客観性」』
マックス・ウェーバー『社会科学と社会政策にかかわる認識の「客観性」』
雀部幸隆『知と意味の位相―ウェーバー思想世界への序論』
マックス・ウェーバー『世界宗教の経済倫理 比較宗教社会学の試み 序論・中間考察』
マックス・ウェーバー『世界宗教の経済倫理 比較宗教社会学の試み 序論・中間考察』
汎用文献
佐藤俊樹「社会学の方法:その歴史と構造」
大澤真幸「社会学史」
本当にわかる社会学 フシギなくらい見えてくる
アンソニー・ギデンズ「社会学」
社会学
社会学 新版 (New Liberal Arts Selection)
クロニクル社会学
社会学のあゆみ
社会学用語図鑑 ―人物と用語でたどる社会学の全体像
コメント
この記事へのトラックバックはありません。






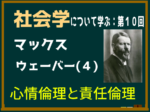
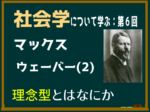
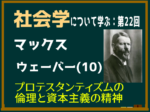
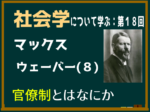

この記事へのコメントはありません。