Contents
- 1 はじめに
- 2 機能分析とは
- 3 従来の機能分析の諸問題
- 3.1 従来の機能分析の問題点
- 3.2 マートンによる機能分析の改善点
- 3.3 語彙の混乱に対する整理
- 3.4 主観的意向と客観的結果の区別
- 3.5 概念の整理:公準,項目,体系,構造
- 3.6 【1】機能的統一の公準に対する批判
- 3.7 【コラム】ルーマンによる機能等価主義
- 3.8 【2】普遍的機能主義の公準に対する批判
- 3.9 【3】不可欠性の公準に対する批判
- 3.10 機能と機能要件の違いについて
- 3.11 ペンパルによる目的論的機能主義批判
- 3.12 【コラム】パーソンズによる機能要件の説明
- 3.13 機能分析とイデオロギーの関係
- 3.14 【コラム】ウェーバーの価値自由
- 3.15 保守的イデオロギー、急進的イデオロギー
- 4 新しい機能分析の範例(お手本、枠組み)の提示
- 4.1 生理学におけるキャノンの「手続きの論理」
- 4.2 【コラム】ベイトソンによる「緩い思考」と「厳密な思考」
- 4.3 範例を導入する目的
- 4.4 【1】機能分析の対象の使用ガイド
- 4.5 【2】主観的意向の使用ガイド
- 4.6 【3】客観的結果(機能の種類)の使用ガイド
- 4.7 【コラム】レヴィによる「順機能と逆機能」の区別
- 4.8 【4】機能のはたらく単位の使用ガイド
- 4.9 【5】機能的要件の使用ガイド
- 4.10 【6】社会的メカニズムの使用ガイド
- 4.11 【コラム】ウェーバーの理解社会学
- 4.12 【7】機能的選択項(等価項,代要項)の使用ガイド
- 4.13 【8】構造的脈絡(構造的拘束)の使用ガイド
- 4.14 【9】社会構造の動態と変動の使用ガイド
- 4.15 【10】機能分析の検証のガイド
- 4.16 【11】イデオロギー問題のガイド
- 4.17 【コラム】マンハイムの相関主義
- 4.18 記述的調書に最低限取り入れるべき5つの事項
- 4.19 【コラム】ウェーバーの理念型
- 5 その他
- 6 参考文献リスト
はじめに
動画での説明
・この記事の「概要・要約」はyoutubeの動画の冒頭にありますのでぜひ参照してください。
よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m
ロバート・K・マートンとは、プロフィール
ロバート・キング・マートン(英:Robert King Merton,1910-2003):・アメリカの社会学者。主著は『社会理論と社会構造』(1949,1957)。社会学方法論では「機能主義」の再定式化を行い、中範囲の理論を提唱した。顕在的機能と潜在的機能、順機能と逆機能、準拠集団行動の理論、自己成就的予言などで知られている。
前回の記事
【基礎社会学第三十四回】ロバート・K・マートンの中範囲理論とはなにか
機能分析とは
機能分析とはなにか
広義の機能分析とは、意味
広義の機能分析:・「あることがらのはたらきをとらえる」というきわめて素朴な観点による分析のこと。村田裕志さんによる定義
こうした広義の機能分析は、社会学や人類学などの学問以外でも用いられ、また日常生活でも用いられているという。たとえば肉に火をいれるのは、美味しく食べるという「目的」がある、腹を壊しにくいという「効果」があるからだ、などと我々は素朴に、概念や論理を緩く使い分析している。
狭義の機能分析とは、意味
さらに社会学的機能分析を簡易的に「マートン的機能分析」、「パーソンズ的機能分析」、「ルーマン的機能分析」に分類することにする。
マートン的機能分析は「実証的機能分析」、パーソンズ的機能分析は「構造-機能分析」、ルーマン的機能分析は「機能-構造分析」というように簡易的に分類しておく。
マートンはパーソンズに影響を受けているが、しかしマートンの機能分析とパーソンズの機能分析は対立的であった。極端に言えば「まるで違う」という視点が重要である。この対立軸については後で扱う。
今回はこの記事で「マートン的機能分析」を中心に説明していくことになる。パーソンズ的機能分析は既に扱ったのでそちらの記事を参照。
【基礎社会学第二十八回】タルコット・パーソンズのAGIL図式とはなにか
ルーマン的機能分析は今後作成していく予定である。両者についてこの動画では詳説できない。また、人類学による機能分析については以前の動画を参照(今回の動画でも批判的に扱う)。
図にするとこのようなイメージになる。
「まずはじめに,ここでいう広義の「機能分析」とは,厳密な概念的な定式化をくわえる以前の,「あることがらのはたらきをとらえる」というきわめて素朴な観点にはじまる分析視点一般のことを意味している。この意味での機能分析は,社会学にとってもいつの時代にも変わらぬ基本的にして有力な視点でありつづけている。しかも,機能分析の発想は,いうまでもなく,一般の社会生活においてもごく普通に活用されており,その分析視点がさらに広く普及し応用されることは,現代の社会生活においてきわめて有意義であると考えられる。この広義の「機能分析」が多少とも厳密化されると,狭義の「機能分析」になり,さらに専門化されて「構造‐機能分析」や「機能要件分析」に発展するが,それにともない,より抽象的になり日常感覚から疎遠になる。」
村田裕志「社会学的機能主義系 「社会システム論」 の視角 (I)」,97P
「機能分析は、社会学的解釈の諸問題を取り扱う現代の研究方針のなかで、最も有望である反面、おそらく最も系統立って整理されていないものである。」
ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,56p「社会学者ニクラス・ルーマンは、自らの拠って立つ「方法」を「機能分析」(functional analysis)だとしている。主著の『社会システム理論』のなかでも、「機能的方法は、結局のところある種の比較の方法なのであり、現実へそれをあてはめることは、現存しているものの別様のあり方の可能性を考慮して現存しているものを把握することに役立つのである」(Luhmann, 1984:p.84)として、機能分析の説明に多くのページを割いている。「機能分析」とは、もともと文化人類学で生まれ、その後、社会学において精緻化されていった方法であり、一種の理論技術だ。機能分析の基本的な考え方は、物事の「構造」ではなく、「機能」に着目して分析を行うというもの。」
http://web.sfc.keio.ac.jp/~iba/sb/log/eid63.html
機能主義とはなにか
広義の機能主義とはなにか、意味
広義の機能主義:・機能に関するある特殊な理論的立場や思想を意味する。
この特殊な立場に基づいて、それぞれの特殊な機能分析が行われることになる。ざっくりといえば実態概念よりも機能概念を重視する立場であるといえる。機能概念をどのように解釈するか、利用するかにおいて立場が変わる。今回は、その中でも特に「社会学的機能主義」のみを扱う。
社会学的機能主義とはなにか、意味
社会学的機能主義:・特に「社会」に対する特殊な立場や思想を意味する。この特殊な立場は「方法論的個人主義」と「方法論的集合主義」に大別される。
たとえば「方法論的個人主義」の場合は個人の意思決定の集積としての社会を重視し、実在するのは個人だけだと考える(社会唯名論)。マックス・ウェーバーやゲオルク・ジンメルが代表的であり、前者は方法論的個人主義、後者は方法論的関係主義と呼ばれる。
一方で「方法論的集合主義」の場合は、個人の意思決定を超越したものを重視し、社会もまた実在すると考える(社会実在論)。社会学ではコントやスペンサー、特にエミール・デュルケムが有名である。
こうした立場は機能主義の確立前にあった立場である。
機能主義と呼ばれる人たちをざっくりと分類するとこのような図になる。もちろん今回扱うのはマートンの機能主義である。「新機能主義」などは省略した。デュルケムは社会学的機能主義を確立したわけではないが、(社会学的)機能概念の先駆けと言われる。
村田裕志さんいわく、社会学ではパーソンズとマートンという2つの機能主義が核心として位置づけられており、ルーマンが機能主義系であることが見過ごされがちだという。
村田さんの言葉を用いればルーマンの分野は「社会学的機能主義系社会システム論」である。社会システム論は機能主義の射程にあるという解釈である。
「「社会学的機能主義」について,従来の多くの学説研究・解説類で定番となっている流儀では,ほぼ「マートン的機能分析」と「パーソンズ的構造‐機能分析」とをもって,社会学的機能主義の核心と位置づけているが,この論考では,そうした従来の見方とは異なり,「集合主義的な機能分化論」が社会学的機能主義のきわだった特徴であるととらえており,したがって,「機能分化した社会の諸機能システムの分析や描写」こそが,社会学的機能主義系「社会システム論」の主要なテーマであると主張している。この新しい解釈により,ルーマンの社会システム論までをも社会学的機能主義の射程におさめることが可能になる。」
村田裕志「社会学的機能主義系 「社会システム論」 の視角 (I)」,100p
個人主義的機能主義と集合主義的機能主義の区別
村田さんによると、社会学において、人々から構成される集団や組織などの集合体である「社会システム」を想定してその効用(機能)を分析することがただちに集合主義(方法論的集団主義)といわれる考え方になるわけではないという。
集合体を研究対象として指定すること自体は、社会学である限り当然の思考前提だという。たしかにそうだ。
一般的な社会学の説明では、「極端な社会唯名論を除き、社会学は基本的に個々人の集まり以上のものだという考えを前提にしている」と説明されている。単なる個人の集まりであれば、社会ではなく一人を心理学的に研究すればいいからである。
いわば、対象は同じであるが、その対象に対する視点、態度、アプローチが異なるというわけである。方法論的個人主義の場合は「個人を起点に置く」という点を重視し、方法論的集合主義の場合は「個人に影響を与える社会」という点を重視する。たとえば行為者の動機や意味の理解を重視したウェーバーの「理解社会学」は前者である。
村田さんの説明によれば、ある発想において「個人主義的な機能主義」と「集合主義的な機能主義」は対極にあるという。
個人主義的な機能主義の場合:・「個々人がそれぞれに意図した目的に即して行動しあい交渉しあうことにより成立する社会的相互作用の場面を分析的にとらえる」という発想に基づいている。
集合主義的な機能主義の場合:・「人びとの活動や状態の背後に直接的には目にすることのできない崇高で超越的な集合的な存在があり、個々人の側からその存在にたいして直接的に人為をおよぼすことはできず、逆に、その存在を基軸にして個々人の側が宿命づけられており、個々人のパーソナリティさえ、かかる集合的存在により形成されている」という発想に基づいている。
村田さんによると集合主義的な機能主義の代表、元祖がデュルケムであるという。デュルケムは個々の集団や組織や国家をこえた全体的‐集合的な「社会なるもの」が、個々の人間にはあずかりえぬところで機能分化や連帯や道徳的生き方の諸可能性の基盤を創出していると考える立場である。
個々の人々、個々の集団や組織といった具体的な集合がある程度意図的に機能を生み出していくというような立場ではないという点が重要になる。個々人や具体的な集団のあり方から超越している何かが社会的機能を生み出していくのである。人々が操作したり、設計できるものではないという。
デュルケムの場合の機能は集合的存在にかかわるより崇高な「高次の機能」であり、個々人の都合や利益のために生起するような種類のものではないという。
「職場のまとまりのための忘年会」や「親族間の連帯強化のための縁組」といったものが究明の主な対象ではないというわけである。
村田さんによれば、このような思考様式はイギリス系の経験論からは忌み嫌われてきた考え方であり、実証科学といえるのかどうかも疑問視されるという。
デュルケム系列でいえば、パーソンズにもその面があるという。
村田さんの説明で言えば、「けっして社会の一領域のみを照らして明らかにするのではなく、すべての部門や領域にも満遍なく光をあてつつ包摂的に視野におさめ、それらの各機能システムがそれぞれに地上における神の国(社会)づくりという大いなる営みに寄与しつつ、社会全体としてたしかな理想へと向けて方向づけられている」という。
パーソンズはピューリタン系のキリスト教徒であったということも重要だろう。端的に言えば「プロテスタント-ヴォランタリズム的なパーソンズ理論」だという。※ヴォランタリズム(主意主義)については以前の記事を参照。
【基礎社会学第十九回】タルコット・パーソンズの「主意主義的行為理論」とはなにか
ルーマンも同様にデュルケム系列だという。
村田さんによれば、「全体社会それ自体はけっしてその“姿”を見ることも把握(描写)することもできない種類の集合的存在であり、しかし、そこから機能分化している貨幣経済や司法や教育制度や科学研究などの諸機能システムは、個々に輪郭を有し、それなりに、“姿”や“顔”(システム自体の単純化描写)をもった(描写しうる)存在として立ち現れている」という。端的に言えば「ニヒリズム(神の不在)的なルーマン理論」だという。
例えば「ある個人の位置する家族や親族、企業や業界、国家や文化圏などの在り方次第により、当該個人の思考や行動に影響がおよぼされる」というような分析は集合主義的な思想ではない。これはどちらかといえば個人主義的な思想である。
このようにできるだけ実証可能な特定の範囲を限定していくような立場はマートンによって「中範囲の理論」と呼ばれている。たとえば「準拠集団」や「所属集団」など、ある程度社会的体系の「単位」を具体的に限定させて分析を進めていく立場である。マートンの場合は個人の意図だけではなく、またそれらと明確に区別された結果を重視するという点が特徴的である。なぜならば、意図や目的、動機は必ずしもその結果(機能)と同一ではないからである。
パーソンズが演繹的だとすれば、マートンは帰納的だということになる。パーソンズはまず社会全体を捉え、そこから部分を見ていく。
マートンの場合は小さな、具体的な部分、たとえば社会のうち、ある特定の集団などに限定させて考えていくことになる。もちろん、マートンの場合もより普遍的な理論の形成を目指すという立場ではあるが、しかしいきなり過程を飛ばして先験的にあらゆる社会や集団に必ずあてはまるような機能必須要件を特定する「一般理論」を形成することは現時点では不可能であると見なしている。
「しばしば誤解されることであるが,社会学においては,人びとから構成される集団や組織などの集合体(社会システム)を想定して,その作用(機能)を分析することが,ただちに,集合主義といわれる考え方になるのではない。それだけでは,集合主義的でもあり,また個人主義的でもありうる。というのは,“集合体”を研究対象として措定すること自体は,“《社会》学”であるかぎり,ごく当然の思考前提だからである。それにくわえて,集合体(社会システム)をして諸個人の意図や構想や設計や操作により合理主義的・功利主義的に左右される「しくみ」や「からくり」であると考えるならば,そうした理論的立場が「(方法論的)個人主義」(individualism)ということになる。
それに対して,諸個人の企図や営為による作用を超越している集合体をあらかじめ想定したかたちで,現実の諸現象をその存在の現われとみなす理論的立場が「(方法論的)集合主義」(collectivism)である。したがって,この区分によれば,たとえば経営学(企業組織論・戦略論)や社会心理学の考え方は,まさしく個人主義的社会システム論に類似しており,また,社会学者のマートンやホーマンズが社会システムについて語るばあいには,個人主義的社会システム論の一端であるといえる。それに対して,マルクス経済学やマルクス主義社会学,あるいは構造主義理論などは,集合主義思想の典型ということになる。以上のようにとらえるならば,集合主義思想を基軸にして,デュルケームに由来する「社会学的機能主義」と「構造主義」とは近似している様子もうかがわれるであろう。」
村田裕志「社会学的機能主義系 「社会システム論」 の視角 (I)」,116P「以上のような主張が,もしも,個々の人びとがそれぞれに集団や組織や国家の内にあって分担する各役割を首尾よく遂行することにより,各集合体の連帯が強まり,全体としてより効率的なパフォーマンスをアウトプットしうるという話であったとしたら,はるかにわかりやすく思えることであろう。というのは,そのばあいの集団や組織や国家は,人びとが(ある程度は)意図的に設定・制御しうる人工的なシステムとみなされているからである。そうした発想は,むしろ,マートン的・ホーマンズ的な社会観,あるいは経営学的な組織観に類似している。ところが,デュルケームの教示するのは,そのことではなく,個々の集団や組織や国家をこえた全体的‐集合的な“社会なるもの”が,個々の人間には“あずかりえぬところで”機能分化や連帯や道徳的生き方の諸可能性の基盤を創出しているという,はるかに奥の深い論理なのである。」
村田裕志「社会学的機能主義系 「社会システム論」 の視角 (I)」,122P「このようなデュルケーム的発想に依拠して,社会学がはたすべき役割が構想されるとしたら,さまざまな統計資料を収集・編集・比較・分析し,見えざる全体的‐集合的な存在の状況と変動とを実証的に把握し,そのあり方について啓蒙するという役割にほかならない。また同様に,一般の人びとのはたす“つとめ”として考えられることは,全体的‐集合的存在の状況を的確に認識して,その大いなる流れにすなおにしたがい,「中庸の精神」のこころがけで日々の仕事にいそしむということになるのであろう。実際に,デュルケームは,そうした社会学の役割や人びとのつとめを推奨していたのである。このようなデュルケームの考え方が,一世紀前の社会学の確立に大きく寄与したことはたしかである。しかしながら,はたして,それは実証的な社会科学の思考法なのだろうか,むしろ,宗教もしくは倫理学ではあるまいか,という疑問はつきまとう。とはいえ,見えざる全体的な超越的‐集合的存在を想定して,その現われの一環として「連帯」という現象を位置づけ,大いなる崇高な営みに貢献する「機能」を把握するという,この集合主義的‐機能分化論の構図が,「社会学的機能主義」の核心に位置する思想でありつづけていることは銘記されるべきであろう。パーソンズ理論もこの伏線なくしては理解できない。さて,宗教性や倫理性を少なからず帯びているとみられる,この“集合主義的‐機能分化論”が,20世紀初頭の古風な社会科学理論の一遺産とされるというだけであれば,そのアンティークな趣向を味わう古典趣味として済ますことができよう。ところが,それと相い似た発想が,20世紀なかばの社会学の最有力な理論と目されたパーソンズ理論や,20世紀末のコンテンポラリーな社会理論と評されたルーマン理論の基底にも脈々と息づいているとすれば,この論点には,よりいっそう真剣に対峙する必要があるだろう。」
村田裕志「社会学的機能主義系 「社会システム論」 の視角 (I)」,122P
従来の機能分析の諸問題
従来の機能分析の問題点
まずは、ざっくりと従来の機能分析の問題点を挙げておく。
前提:マートンによると、機能分析は有望だが、しかし系統立って整理されていない。「いかにして機能分析の仕事に着手するか」という「方法論」について整理した人はほとんどいない。
- 【問題1】機能分析は述語上の混乱に陥っている。そのために、明晰な分析と十分な意思伝達が困難になっている。
- 【問題2】機能分析において不当な「古典的な三つの公準」が採用されてしまっているために、明晰な分析が困難になっている。
- 【問題3】「古典的な三つの公準」が採用されると機能分析が保守的だという非難が生じてしまう。つまり、機能分析は不可避的に「イデオロギー的」な関わり合いを伴っているように見えてしまう。
- 【問題4】社会学では不揃いに採択された、はっきりとしない「概念」や「手続き」、「分析の仕方」がある。
もちろん、これらの問題は重なり合うものである。
こうした問題はマリノフスキーやラドクリフ・ブラウンらの人類学系機能分析から多くは来ているという。つまり、それらの機能分析への批判を通して、より厳密で実証的な機能分析を形成していくというわけである。
「機能分析は、社会学的解釈の諸問題を取り扱う現代の研究方針のなかで、最も有望である反面、おそらく最も系統立って整理されていないものである。」
ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,56p
マートンによる機能分析の改善点
暫定的にこれらの問題への解決点をまとめておく。
- 【解決1】概念の系統的整理を行う。特に、「主観的意向(ねらい、動機、目的)」と「客観的な社会学的結果(=機能)」を区別することで述語上の混乱を回避する。
- 【解決2】人類学で主に信仰的に用いられている「三つの公準」がなぜ不必要なのかを論証する必要がある。さらに、研究指針として必要な暫定的な仮定を新たに提示する必要がある。
- 【解決3】機能分析がイデオロギー的に中立であるということを論証する必要がある。
- 【解決4】ほかの学問を検討して、社会学の機能分析にとって「有効な方法論的モデル(機能分析の範例)」を構築する。
問題解決4は問題解決1~3を総合するような形で行われる。
語彙の混乱に対する整理
1:同一語の中に多様な概念が用いられているケース
マートンによると「機能」という用語は日常や社会学以外の学問でも用いられている。その結果、社会学における機能の概念が曖昧に使用されてしまうという。そのため、社会学における機能の概念を厳密に定義し、それを限定的に使う必要があるという。まずは曖昧に使われがちな機能の5つの意味をマートンは挙げている。
機能①:「儀式的な意味を帯びて催される公共的集会または祭典式」という意味で日常語で用いられている。
機能②:「職業」という意味で社会学や経済学で用いられている。
機能③:「或る社会的地位にある者、もっと特殊的には或る部署、または政治的地位を占める者に課せられた活動」という意味で日常語や政治学で用いられている。
機能④:「一つ以上の他の変数との関係において捉えられる変数、いわゆる『関数』」という意味で数学や社会学で用いられている。社会学の場合はたとえばカール・マンハイムが「あらゆる社会学はそれが生ずる時と場所の機能である」というようなケースで用いている。両者は方程式で述べられているか、述べられていないかの違いであり、どちらも数学的な意味の用い方だという。
機能⑤:従来の社会学や社会人類学における機能分析で中心的に用いられている意味。
ざっくりいえば「部分が全体の維持・存続に対して果している作用・貢献・働き」などの意味で用いられている。その「全体」が人間の物理的な身体(有機体)であったり、個人であったり、社会であったりする。
「まず、日常の用例によれば、functionは、通常儀式的な意味を帯びて催される公共的集会または祭典式を指している。」
ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,58P
「第二の用例によれば、functionという用語は、職業(occupation)という用語と事実上同義に解されている。」
ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,58P
「第三の用例は、第二の用例の特殊なばあいを示すもので、日常語や政治学で見うけられる。functionは或る社会的地位にある者、もっと特殊的には或る部署、または政治的地位を占める者に課せられた活動を指すのにしばしば用いられる。functionary、すなわち役職者(official=部署を占める者)という用語はここから生ずる。」
ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,58P「functionという語は、ライプニッツが最初に用いて以来、数学において最も正確な意義をもっている。そこではfunction(函数)とは一つ以上の他の変数との関係において捉えられる変数を指すものであって、それらの変数によって表現され、それ自身の値はそれら変数の値如何にかかっている。この概念は、もっと拡充された(それだけ不正確なことが多い)意味で社会科学者たちがしばしば用いる『機能的相互依存(functional interdependence)』とか『機能的関係(functional interdependence)』というような語句で表現される。…社会科学者は、こうした意味内容と、これと異なってはいるが相関連するもう一つの意味内容―後者も『相互依存』『相互関係』ないし『相互に依存し合う変異』という概念を含む―との間をうろついていることが多い。」
ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,59P「機能分析にとって中心的なものは、第五の意味内容であって、社会学や社会人類学で用いられてきたところである。この用例は、一部は本来の数学的意味から生じたものだが、それ以上に生物諸科学からとったものであることは明らかであって、そこではfunctionという用語は、『有機体の維持に役立つという観点からみた生命的または有機的な過程』を指すものと解されている。この概念を適当に修正して人間社会の研究に適用すると、人類学上の機能主義者――純粋であるのと、手加減したものとを問わず――が用いるfunctionの主要概念にかなり密接に対応する。」
ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,59Pキーワード:ラドクリフ・ブラウンの「社会的機能」の定義
(1)生物諸科学における機能の意味
「有機体の維持に役立つという観点からみた生命的または有機的な過程」という意味で生物諸科学で用いられている。
例:血液が栄養と老廃物の共通の担い手として種々の機能を果たしている。
(2)生物諸科学の概念を流用した人類学における機能の意味
A:ラドクリフ・ブラウンにおける機能概念
「文化的・社会的項目が全体としての社会生活において演ずる役割であり、したがってそれが構造的持続を維持するのに果たしている貢献」という意味。
例:葬儀のような反復的な活動の機能は、社会の維持に貢献しているというような使い方をする。
B:マリノフスキーにおける機能概念
マリノフスキーもラドクリフ・ブラウンと同様に、「社会的または文化的項目が社会において演ずる役割」という意味として機能を用いている。
ただし、マリノフスキーの場合はラドクリフ・ブラウンよりも「個人」に重きを置き、項目が機能するのは全体としての文化や社会だけではなく、あらゆる成員にとってもまた機能的であるとみなしている。 マリノフスキーの場合、機能の基準が「人間の欲求」にあり、ラドクリフ=ブラウンの場合は「存在のために必要な諸条件」である。
C:クラックホーンにおける機能概念
「一定の文化内容は、それが社会の観点からみて、適応的であり、個人の観点からみて調整的であるような反応様式を規定しているかぎりにおいて、『機能的』である」という意味で用いられている。
※クライド・クラックホーン(1905-1960)はアメリカの文化人類学者。フィールドワークの具体的資料に基づく分析の方向を強調した人物。
キーワード:ラドクリフ・ブラウンの「社会的機能」の定義
「ラドクリッフ-ブラウンは、社会的機能という作業概念について生物科学にみられる類似のモデルにその先駆を求めている点で、最も明白である。デュルケーム流に、『反復的な生理過程の機能とは、この過程と有機体の欲求(すなわち、生存の必要条件)との対応関係』と彼は主張している。そして『基本的単位』をなす個々の人間が社会関係の網の目によって統合的全体に結びつけられている社会的領域では、『犯罪の処罰とか、葬儀とかいうような反復的活動の機能は、それが全体としての社会生活において演ずる役割であり、したがってそれが構造的持続を維持するのに果たしている貢献である。』」
ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,59-60Pキーワード:マリノフスキーの「社会的機能」の定義
「マリノフスキーは、その初期に研究目的を述べた箇所で、次のように説明している。『この種の理論は、あらゆる発展段階における人類学上の諸事実をそれらの機能によって、すなわちそれらが文化の統合的体系のなかで演ずる役割によって、またその体系内でそれらが相互に関連する仕方によって説明することを目指している』。」
ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,60Pキーワード:クラックホーンの「社会的機能」の定義
「クラックホーンは、次のように述べている。すなわち、『…一定の文化内容は、それが社会の観点からみて、適応的(adaptive)』であり、個人の観点からみて調整的(adjustive)であるような反応様式を規定しているかぎりにおいて、『機能的』である。」
ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,60P
主観的意向と客観的結果の区別
2:単一の概念に多様な用語が用いられているケース
主観的意向:・目的、動機、意図、ねらいなどの類似するものをまとめて表す概念。
機能とほとんど同義に無差別に用いられる用語の例:利用、効用、目的、動機、意図、ねらい、結果
もしこうした用語が、表面的な言い方の違いだけでああり、実質的に同一概念であれば問題はない。しかし、実際にはそうではないから問題が生じる。
特に、「目的、動機、意図、ねらい」といった用語に注意する必要がある。
それらはマートンがまとめて「主観的意向」と呼ぶ概念群である。
主観的意向は機能と呼ばれることがあるが、機能として扱うことは間違っているという。混同してはならないことを強調する。
「『機能』とほとんど同義に無差別に用いられる多数の用語には、利用(use)、効用(utility)、目的(purpose)、動機(motive)、意図(intention)、ねらい(aim)、結果(consequence)という言葉がある。もちろん、このような用語が厳密に規定された同一概念を指すものとすれば、それらの用語の多様性を指摘してもたいして得るところがなかろう。だが、実際には、表面的に類似した概念をさすこれらの用語を無分別に用いると、厳正な機能分析から次第にかけ離れてしまう。」
ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,60-61Pキーワード:客観的な社会学的結果と主観的意向、社会的機能の定義
「しかし、機能という概念は、観察者の見地を含み、必ずしも当事者の見地を含んでいない。社会的機能とは、観察しうる客観的結果を指すものであって、主観的意向(ねらい、動機、目的)を指すものではない。そして客観的な社会学的結果と主観的意向とを区別しなければ、不可避的に機能分析は混乱に陥るのであって、…」
ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,62P
社会的機能とはなにか、意味
社会的機能:観察しうる客観的結果、客観的な社会学的結果のことである。
後で扱うが、この社会的機能は機能、逆機能、顕在的機能、潜在的機能などに分類される。また、心理的機能とは区別される。主観的意向(ねらい、動機、目的、想定、予想、目論見)とは区別される。これらを混同すると、明晰な機能分析が困難になるという。
社会的機能における「機能」のみの定義づけをするとすれば、「一定の体系の適応ないし調整をうながす観察結果(客観的結果)」ということになる。
この「機能」は正機能や順機能として後にマートン以降に呼ばれることになる。要するに、社会的正機能や社会的順機能ということになる。
「社会的」と形容されるように主に「社会体系」に対して貢献を促すことが念頭におかれているのだろう。これが文化体系の場合は文化的機能、心理体系の場合は心理的機能といったように呼ばれる。いずれにせよこれらの機能は動機や目的といった主観的意向ではなく、客観的結果であるという点で同じである。
1:主観的意向と客観的結果は一致することもある
たとえば怪しい人物に近づかれないためという「動機」をもって防犯ブザーをぶらさげておくケースなどが考えられる。その「結果」として怪しい人物に近づかれなかったということはありうる。
ただし、「一致した」とどのようにして判断できるのかという問題も生じる。必要条件なのか、十分条件なのか、十分条件だとしてもその項目単一で果たせるもなのか等々の問題がある。服装の問題、性別、年齢、文化、さまざまな項目を考慮する必要があるのだろう。他の項目を一定にしたまま、防犯ブザーという項目だけを変動させて実験するとより客観的な結果が観察されやすいといえる。だからこそ社会科学では実験が難しいと言われる。
追記:ただし、一致したといっても全く同じ事態を意味するのではない。意図しただけでは外形的に何も変わっていないケースを考えれば明白である。たとえばスイッチを押せば明かりがつくだろう、という頭の中の出来事と、実際についたという頭の外(こういう言い方をすると哲学的にややこしいが)の出来事は区別しなければならない。このように考えると、機能は結果論的になるのだろう(2024/03/11)。
2:主観的意向と客観的結果は一致しないこともある。
たとえばテロリストが社会を良くするという動機をもって活動する場合、必ずしも社会が良くなるという結果をもたらすわけではない。むしろ動機、意図、目的とは反して悪くなるという結果をもたらすこともあるだろう。もちろん、どのような判断基準において総結果としてプラスあるいはマイナスの結果をもたらしたと言えるのかという問題はある。例えばテロ行為の結果、国の団結力が高まるというプラスの結果を客観的に見出すことは可能だからだ。プラスとマイナスをそれぞれ中立的に見出す必要がある。
主観的意向と客観的結果をひとまとめに「社会的機能」として、「同一」のものだと仮定してしまうと、「本人の意図しない客観的結果(潜在的機能)」や「逆機能」を見過ごしてしまうという問題が生じる。あるいは、「同一のものではない」ということをことさら有益な発見であるかのようにみなしてしまう。
観察者が、観察者の見地により判断した「客観的結果」が機能であるとマートンはいう(必ずしも当事者の見地を含んでいない)。例えば当事者の見地が「防犯」にあり、観察者もまた「防犯」であると判断することもありうる。
しかし、防犯ブザーをつけていたがために、本人の意図とは反してむしろ挑発と受け取られ、怪しい人物に近づかれることもあるという事実を発見したとする。つまり、観察者はこの場合、「防犯(回避)」という機能も、「誘引」という機能もあると判断することになる。あるいは、防犯ブザーをつけていることで好意を寄せている異性にも近寄られなくなったというような別の「機能」が生じることもありうるだろう。
Q 行動に対して与える「理由」と行動様式の観察された「結果」が同一であると仮定した場合どうなるか
恋愛や個人的理由といった「結婚に入る動機」と子どもの社会化といった「家族の果たす機能」が混ざり合っている文献の例をマートンは紹介している。
その文献では、「家族の機能は子供の社会化であると信じられているが、実際には個人的な要望を果たすためである」という論調になっている。
ポイント1:「動機」と「機能」とが同一であると先験的に仮定する必要はない。行動に対して与える「理由」と行動様式の観察された「結果」が同一であると仮定する必要はない。そうした先験的分析には価値が薄い。
ポイント2:主観的意向と客観的結果は一致することもあるが、一致しないこともある。一致するとあたりまえのように仮定すると問題が生じる。例えば「本人の意図しない客観的結果」が見過ごされる。そうした潜在的機能を考慮しない分析には価値が薄い。
ポイント3:主観的意向と客観的結果は独立的に変化するという。この文章は正直、理解が灰色である。おそらくは客観的結果は主観的意向の従属変数ではないということなのだろう。主観的意向が変化したからといって客観的結果が変化するとは限らない。防犯ブザーに防犯意識をもっていたとしてももっていなかったとしても、不審者からしたら目に見えた変化は見えないのだろう。防犯ブザーのように明確な目的がデザインされている例だとすこしわかりにくいのかもしれない。そもそも防犯ブザーが「標準化された社会的・文化的項目」として扱っていいのだろうか。
「誤って(主観的)動機と(客観的)機能とを同一視するときには、いつでも、明晰な機能分析が放棄されてしまう。というのは、やがて述べるように、結婚に入る動機(『恋愛』、『個人的理由』)と家族の果たす機能(子供の社会化)とが同一であると仮定する必要はないからである。また、人々が自分の行動に対して与える理由(『われわれは、個人的理由で行為する。』)と、これらの行動様式の観察された諸結果とが同一であると仮定する必要もない。主観的意向と客観的結果とは、一致することもあるが、また一致しないこともある。両者は独立に変化する。しかし、人々は行動に参加するよう動機づけられ、その結果(必ずしも本人の意図しない)機能を生じることがあるというならば、厄介な混乱の域を脱する道が開かれる。」
ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,62-63P
概念の整理:公準,項目,体系,構造
知ったかぶり問題
・個人的にスッキリさせないと前に進めないので、3つの公準を説明する前に諸用語を整理しておく。これらの用語の理解に自信がある人はスキップしていいかもしれない。
この整理はマートンが直接的に扱っているものではないが、しかし理解していないと今後の話の内容が灰色な理解になりかねないものである。理解できないとしても、理解できていないものとして明示しておく必要がある。
たとえば体系や構造の違いを明確に説明できる人はすくない。私のようになんとなく「知ったつもり」でいることが多い。
「本当に自分はこの説明を理解しているのか?」と内省していくと、結局は諸概念の理解にまずは突き当たる。そこから諸概念の関係の理解に進んでいき、そして次にそれらの関係をわかったうえでの諸概念の理解に戻っていく。また、誰も彼もが同一概念、同一意味として体系や構造という表現を使うのではないため、その違いを抑えておく必要がある。そのためにはまず基本を知り、そこから偏差を索出していくという方法がやりやすい。
1:公準について
一般に、公準とはある論理的、実践的体系の基本的な前提として措定せざるを得ない命題を意味する。
公理と同じく証明不可能ではあるが、公理が自明であるのに対し、これは仮定的である。おそらく、社会人類学者たちは自らの仮説を「公準」と名乗っていたわけではないだろう。明らかに証明不可能であると自覚したままその仮説を採用するとは思えない。これはマートン側が、彼らの仮説を「公準」だと、つまり証明不可能な命題だと表現しているのだと思われる。
例えば社会人類学者たちは、ある未開社会の範囲では経験的に実証したと考えている場合がある。しかしそれらを他の社会すべてに適用できるという「過度な一般化」を行うと、それは経験的に証明不可能な仮説に、つまり「(不当な)公準」になってしまう。まだ完全には証明されていないだけで、いずれ証明される程度のものだと思っていた可能性もある。
公準だからといって必ずしも不利益というわけではないのだろう。たとえば幾何学では「線分は延長することができる」といった公準が要請されている。この公準のおかげで、なんらかの利益が得られているのだと思われる。しかし社会学ではそうした公準が経験的に反証されている、あるいはそのせいで明晰な分析が困難になっているとすれば、不必要になるのだろう。
2:項目について
「項目」とは一般に「 物事を、ある基準で区分けしたときの一つ一つ」を意味する。たとえば「このリストに載っている項目について、ひとつずつ確認してください。」といった使い方をする。
一般に、「事柄」は抽象的な物事を表す場合に、「事項」はより具体的な物事を表す場合に、「項目」は複数の似たような物事を表す場合に用いる。
たとえばマートンは「標準化された文化的・社会的項目」という言い方をする。標準化は反復的、型式的な意味合いである。文化的・社会的項目の例としては活動、慣行、信念、観念、物質的事物、感情、慣例、行動型式、制度などが挙げられている。慣行や慣例、制度などはその概念のうちに標準化された意味合いが含まれている。マートンは厳密にではなく、緩くこれらの概念を用いている。
ある個人が一回きりしか行わないような物事は「標準化された文化的・社会的項目」とは基本的にいわないだろう。個人的項目などと呼ぶのかもしれない。
(1)体系について
体系(英:system):・(1)「システム」の最小限の定義は「たがいに作用しあう要素からなる全体」であるという。また、どういう要素からなるシステム(全体)を措定するかは、分析する側の目的や用途によって、分析者が決めることであるという。溝部明男さんの定義。(2)「相互に関係をもつ構成要素からなるひとまとまりの全体であり、その全体はその環境に対して、境界を維持してゆく能力を持つもの」。溝部明男さんの定義。
体系とはいわゆる「システム」のことである。したがって、社会体系とは社会システムを意味する。
たとえばジンメルは「人」を要素とした心理的相互作用、関係からなるものを、パーソンズは「行為」を要素として、ルーマンは「コミュニケーション」を要素としてシステムを考えていたと捉えることができる。社会体系(社会システム)を最初に明示的に使用したのはスペンサーであり、本格的に論じたのはパレートだという。その後、パーソンズやマートンが使用していくことになる。
たとえば溝部明男さんは、「システム」の最小限の定義は「たがいに作用しあう要素からなる全体」であるという。また、どういう要素からなるシステム(全体)を措定するかは、分析する側の目的や用途によって、分析者が決めることであるという。
この説明はわかりやすい。対象の側にあらかじめシステムが固定的に存在していて、それを観察者が発見するのではないという指摘は重要だろう。また、これらの指摘は観察者がどういう要素からなるシステムに範囲を絞るのかという、マートンのいう中範囲の理論とも関連してくる。マートンの場合は、実証可能な範囲に絞るというものだった。であるならば、パーソンズのいうような大きな範囲は実証が難しいという結論にならざるをえないのだろう。
「「システム」の最小限の定義は、「たがいに作用しあう要素からなる」全体ということになろう。どういう要素からなるシステム(全体)を措定するかは、分析する側の目的や用途によって、分析者が決めることである。「システム」は相対的な概念であり、対象の側にあらかじめ「システム」が固定的に存在していて、分析者がそれを発見するという類のものではない。」
溝部明男「社会システム論と社会学理論の展開-T. パーソンズ社会学と残された3つの理論的課題-」,23P
(2)構造について
溝部さんはシステムと構造は異なる概念であるとし、以下のように定義している。
システム:・「相互に関係をもつ構成要素からなるひとまとまりの全体であり、その全体はその環境に対して、境界を維持してゆく能力を持つ」
構造:・「システムの部分、構成要素、あるいはそれらの相互の関係のうちで、変化しやすいものを除いた定常的な部分、構成要素、相互関係のこと」。
私にはこの構造の定義が分かるようで全くわからない。「要素同士の関係」だけではなく「要素」単体もなぜ構造と呼ぶことができるのか、「部分と要素の違い」など、理解が灰色である。もし要素と部分が同義ならこうした定義は冗長なので、おそらく違うのだろう。
たとえば「サブシステム」や「集団」、「複数の役割」といったものを部分として扱い、あくまでもシステムの最小単位(行為や個人、役割など)を要素として用いているなどというケースが考えられる。あるいは単なる安定した相互関係と、そうした相互関係を生み出す何か(部分)は区別しなければいけないというケースが考えられる。
「「構造」とシステムは異なる概念である。システムとは、「相互に関係をもつ構成要素からなるひとまとまりの全体であり、その全体はその環境に対して、境界を維持してゆく能力を持つ」と定義すると、構造とは「システムの部分、構成要素、あるいはそれらの相互の関係のうちで、変化しやすいものを除いた定常的な部分、構成要素、相互関係のこと」である。「構造」概念は、「システム」概念よりも古くから使われてきた。」
溝部明男「社会システム論と社会学理論の展開-T. パーソンズ社会学と残された3つの理論的課題-」,30P
パターンとしての構造と、規則としての構造の違いとは、意味
友枝敏雄さんによると、「構造」概念はさらに二つの意味に分けられるという。
パターンとしての構造:「地位-役割」間の関係および社会資源配分の定型化されたパターン。パターン化された相互行為のまとまりである。たとえば医者の患者に対して平等に接する傾向など。
規則としての構造:・「地位-役割」間関係その他の定型化されたパターンを生み出す原理あるいは規則。規範、伝統などもここにあたる。たとえば普遍主義や個人主義、業績主義などが規範である。
正直この2つの定義の違いについてわかるような、わからないような感じがする。「パターンとしての構造」が見られたからといって、必ずしも「規則としての構造」があるとは限らない、というならば区別できるかもしれない。
規範の内面化も制度化もされていないが、偶然、安定した相互行為がなりたっているというケースなど。あるいは安定した相互行為はみられないが、それらを制度化・内面化しうるような規則は存在するなど。もしどちらかの構造のみが存在することができないとすれば、同じ構造の2つの側面なのかもしれない。システムや構造を流動的に考えれば、あるほんの一瞬だけなんの相互作用も見られないという瞬間はありえるかもしれない。「時間」とシステム・構造の関係は重要な要素となりそうだ。
構造人類学などでは「人間間精神あるいは思考の中に備わっている構造」や「人間精神の無意識の構造」というふうにつかわれている。ギデンズによる「構造化理論」では「規則としての構造」が主に構造として扱われているという。つまり、「パターンとしての構造」を構造として認めないということだろうか。ギデンズの批判は機能主義批判と呼ばれ、そもそもギデンズは「機能概念」すらいらないと批判している人物である。このあたりはギデンズの動画で深く理解を目指したいと考える。
たとえばブリタニカ百科事典の「社会構造」の説明では、行為や役割に着目すれば「相互行為、役割体系」、下位集団に注目すれば「集団間の相互連関」、制度に注目すれば「規範体系」になるという。そしてそれらのうち特に安定したものを「構造」とよび、さらにそれらの構造同士の連関もあるという。ちなみに、「連関」は具体的な繋がりや直接的な関連を扱う際に、「関係」はより広く、間接的なものも含めて一般的に使用される。
なかなかややこしい。要素や部分の定義次第で複数のシステムを想定でき、またそのシステムの中の安定した構造も想定できるということは理解できた。
ある集団をシステム(全体)として扱うこともでき、より大きなシステム全体のサブシステム(部分)あるいは構成要素としても扱うことができるというようなイメージである。
「「構造」の概念には二つの意味がある。友枝敏雄らによると、一つは複数の「地位-役割」間の関係および社会資源配分の定型化されたパターンを指し、他の一つは、これらの「地位-役割」間関係その他の定型化されたパターンを生み出す原理あるいは規則を意味する。たとえば、企業内であれば、組織内の「地位-役割」の配置によって、相互行為は、ある程度パターン化されている。伝統社会においては、伝統および慣習によって、人々の相互行為はパターン化されている。これらのパターン化された相互行為のまとまったものを「構造」と呼ぶ。これが第一の意味である。第一の意味の構造を産出する原理、規則あるいは規範を第二の意味で「構造」と呼ぶことがある。たとえば、わが国には年功序列の規範があり、近代社会には平等主義、普遍主義、業績主義の規範がある。社会システムの構造の二側面のうち、前者を「パターンとしての構造」と呼び、後者を「規則としての構造」と呼ぶことがある(友枝敏雄1998:7-8頁)。」
溝部明男「社会システム論と社会学理論の展開-T. パーソンズ社会学と残された3つの理論的課題-」,30P「他に、構造人類学の領域で、人間精神あるいは思考の中に備わっている構造が、親族組織や神話、分類の中に反映されると考える立場では、人間精神の無意識の構造といった使い方がなされることもある。」
溝部明男「社会システム論と社会学理論の展開-T. パーソンズ社会学と残された3つの理論的課題-」,30P
パーソンズにおける構造概念
たとえばパーソンズは「構造」を、社会システムの諸部分のうち「定常的な部分」を指すとしている。いわば相互行為がパターン化されているケースである。たとえばパターン変数などはパーソンズが構造を扱う際に扱った概念である。
たとえばアメリカでは普遍主義的な選択が重視され、中国では個別主義的な選択が重視されるといったイメージである。特定のパターン(型)を導くような「文化、共通の価値規範」があり、それらは選択的な志向の基準を個人に提供するというわけである。
もし行為や役割、コミュニケーションがすべて完全にランダムに選択されていれば、そこに構造はみられにくい。しかし、行為者は特定のパターンを選ぶ傾向がある。
そしてその傾向を導くものは文化や共通の価値であり、そうした価値が個人において内面化され、社会において制度化されることで社会の秩序が安定するという説明である。これはホッブズ的秩序問題に関連する問題。
溝部さんによると、パーソンズは「パターンとしての構造」と「規則としての構造」を区別せず、「定常的なもの」を構造として用いているという。
村田裕志さんによれば、パーソンズの「構造-機能分析」それ自体は「当該のシステムを構成する二項以上の変数の相互関係性のもとで、そのどちらの側を『構造』として設定するかが、視点のとり方次第で相対的であるがために、体制維持的でも保守的でもない」という。
パーソンズの場合は、これらの二つの意味を区別しないで、「定常的なもの」を構造と呼んでいる。ギデンズの「構造化理論」に見られる「構造」は第二の「規則としての構造」を指していると思われる。」
溝部明男「社会システム論と社会学理論の展開-T. パーソンズ社会学と残された3つの理論的課題-」,30P
ラドクリフ・ブラウンにおける構造概念
たとえば社会人類学者のラドクリフ・ブラウンは、社会体系を「全社会構造と社会慣例の全体とを包括するもの」というように定義付けている。
また、「構造と慣例を区別し、慣例のなかに構造が現れ、構造は慣例によって持続的に存在する」と説明している。
習慣、慣習、慣例の違い
ちなみに個人が繰り返す行動様式を「習慣」、社会的に繰り返す行動様式を「慣習」と一般的に呼ぶ。「慣例」は慣習の一種であり、日常規則的に繰り返される生活様式を意味するという。要するに、習慣は法や習俗(しきたり)ほど社会的制裁の程度が弱い規範的なもの、特殊な社会ごとのマナーのようなものだろう。
そう考えると、構造と慣例の区別は、「パターンとしての構造」と「規則としての構造」に通じるものがあるといえるのではないだろうか。
マートンは基本的に、包括的な社会体系を直接に分析の対象にしていない
マートンは基本的に、包括的な社会体系を直接に分析の対象にしていないという。いわゆるあらゆる集団、文化を含むような「包括的な社会全体」である。
準拠集団のようにある特定の小集団、ある特定の文化といったような小さな範囲の社会システムや文化システムを分析の対象にしているイメージである。実証可能な範囲の体系に絞った上で、その中範囲の体系のうち、さらに変化しにくい(定常的、恒常的、反復的、標準的)な項目である構造を機能分析の対象に絞っていくのである。これはパーソンズのように(包括的な)社会全体のような大きな範囲を扱おうとせず、実証できる小さな範囲に絞ろうとしたという意図が見える。
ギデンズはマートンが「体系と構造を同一視し、整理が不十分である」と批判している。
安西文夫さんによれば、マートンの分析は主に「恒常的な因果」、あるいは「恒常的な因果」と「フィードバックによる自己制御」の間としての体系という概念に狭く限定されてしまっているという。ギデンズは「構造の二重性」を考慮にしているという違いがあるという。
マートンは「特定の体系にとって機能的あるいは逆機能的」というような言い方をする。さらには「社会構造(および文化形態)が集団の持続に必要な機能を果たしている」というような言い方をする。
一方で、社会体系や文化体系は、それら反復的項目が機能することによって、維持される対象として主に語られている。
「標準化した(すなわち、型式化され、反復される)社会的・文化的項目」が分析の対象である基礎要件であるとマートンは述べている。
であるならば、分析対象は主に「構造」であるということになるのではないか。そして「項目が果たす機能」というように、もっぱら機能を果たすのは「構造」であることが想定されている。
追記:しかし、項目は社会構造によって拘束されると説明されるので、こうした言い方はあまり正しくないのかもしれない(社会構造が社会構造によって拘束されることになる)。あるいは、より大きな社会構造によって、より小さな社会構造が拘束されるといった考え方もできる。いずれにせよ、マートンは体系、拘束、部分、相互行為といった基礎概念の整理を避けている気がする(この論文を見た範囲では)。2024/03/11
ただし、項目の例として「社会的役割、制度的型式、社会過程、文化型式、文化的に型式化された情緒、社会規範、集団組織、社会構造、社会統制の手段などの諸項目がこれである。」と述べている。
「機能理論の基本的趣旨の第三は「体系」と「構造」との概念の関係に関する。これについてのギデンズの批判の結論によれば,「機能理論或いはもっと特殊的には構造機能理論は体系と構造とを誤って同一視する。
体系と構造という用語は「構造・機能理論の文献においては慢性的にあらわれる。」Cibid.)とギデンズはいう。
「体系」については「身も心もすべてを「あげてとりくむ」パーソンズとは対照的にマートンがつねに細心の注意をはらうことについては,グッドナーの指摘に関連して前述した。特に包括的な社会体系を直接に分析の対象とすることはない。しかし体系の観念そのものが否定されるのではない。初期の著書では索引に一度しか姿を見せない「社会体系」も用語としては以後の著述をふくめて,いたるところに散見され,その多くが便宜上の使用に供されるにしても,たとえば小集団に関連する場合のように社会的結合の複合形態の体系的性格は明確に把握されている。社会学における体系念の展開は並行的に生物学およびその他の諸科学において一般化された体系諸概念ならびにGeneralSy-stemsTheoryにおける学際的ひろがりにおいて支持される統一理論に現われるそれから遊離され得ない。」
・安西文夫「機能主義批判の現段階」,12p「ギデンズは社会の構造が欲求や動機を持つことはない、と考えた。そしてマートンの「構造Aは行為Bを必要としている」という説明は、個人の実践(行為)と社会の状態(構造)の間を非再帰的なフィードバックサイクルとして単純なループで結びつけるだけに止まっておりへなぜそのようなフィードバックサイクルが起こるのかについて明確な説明を与えていないという指摘を行い、この点に機能主義理論の欠陥を見出している。『私は何故そのようなフィードバックが起こるのかを説明するためには’能的な(非再帰的なループ)関係として切り離すのでは不充分であることを指摘した。では、なぜ意図せざる帰結のサイクルが長期の時間を超えた社会の再生産を促進するためのフィードバックを与えるような事態が起こるのだろうか。一般的にはこれを分析するのは困難ではない。ある時空コンテキストの中に置かれた’繰り返される行為は、これらの行為を行う人々によって意図されたのではないち規則的な帰結を、そこから多かれ少なかれ離れた時空コンテキストにおいて発生させる。この第二シ–ズのコンテキストの中で発生することがらは直接的または間接的にもはじめのコンテキストにおける行為をさらに継続させる場合の条件に影響を与える。何が継続しているのかを理解するためには、個人が時空間を横断した規則的な社会慣行に従事することに動機付けられているのは何故かへそしてそのことでどのような帰結が起こるのかを説明する変数以外には’どんな説明変数も必要ではない。意図せざる帰結は、参加者によってそのようなものとして再帰的に支持された規則的な行動の副産物として規則的に分配されている。』」
倉田良樹「雇用関係の社会理論(3)」121-122P「ギデンズはマートンのこの論文を1979年著書の参照文献中に含めているので構造分析に示すマートンの熱意については知悉していると思われるが,彼の現在の考えかたについては改めて検討する機会をギデンズとともにもちたい。ところで本質的な事実はマートンにおいて,たしかに「構造分析」の用語はますます頻繁に使用されるのであるが,その内容のそれに対応する充実はみとめられないことである。かつての「機能分析」に代えて「構造分析」が置かれたり構造主義への傾斜がますます濃厚にみとめられることも著明な意味あることに思われる。構造と体系との同一視は「構造」,「機能」,それらの統一としての「体系」の概念的整理が不充分であるという事情のためである。したがってたとえば「機能する構造」が構想されるが、その場合には体系概念はすでに必要がなく。位置すべき場所もない。同様に「機能する体系」は構造の概念を余分のものとする。それらのことはすべて構造機能主義における体系概念の不適正を改めて示すものである。そこでは体系が構造から明確に区別されず,「諸部分の相互依存」がきわめて狭く限定されて考えられる特殊なとり扱いによるのである。
詳しく言えば
(一)homeostaticな因果,
(二)フィードバックによる自己制御,
(三)反省的自己制御として考えられた行為の相互依存としての体系のうちで、
せいぜい(一)から(二)の間を迷走し、多くの場合,(一)に固執する状態を物語る。」
・安西文夫「機能主義批判の現段階」,13p
構造と規範の区別
項目の中に社会構造がある。こういう書き方をされると、それ以外の項目が社会構造ではないかのようにみえてしまう。もし違うとすれば、それらとの明確な違いはどこにあるのか疑問が生じる。構造と規範が区別されているように見えるが、明確な違いはどこにあるのか。パターンとしての構造と規則としての構造というような違いなのか、全くわからない。
この本(マートンの『社会理論と機能分析』)の訳者の金沢実さんが後半で「一般的な幅広い概念、たとえば社会体系、制度、価値などのような概念は、あまり明確な定義や限定的意味を与えられないで、ルーズに用いられている」と述べているように、よく整理されていないのである。
しかし訳者によれば「概念の機動性」という利点があるという。これは後に扱う「緩い志向」とも重なってとても興味深いのだが、読む側からすれば混乱する。
例えば「体系が機能を果たす」と言わずに、(体系を構成する安定した要素の相互関係ないしそれらの相互関係を生み出すような部分である)「構造が機能を果たす」と明確に区別するとする。他の分析においてその体系が他の体系の部分となることはあるにせよ、しかしそのことは考慮せずに、自律したものとして便宜的に限定するのである。それならば、構造と体系は区別されているのではないかと思ってしまう。
このあたりは理解が灰色というより、頭真っ白である。機能と構造、構造と体系、それらの区別の明晰な分類をマートンは提示できていない。やはりギデンズやルーマンを踏まえて理解する必要がある。また、あえて明晰に分類しないことにおける利点も同様に理解する必要がある。
例えば日本において社会体系はいくつあるのか。日本という社会体系の中に、神奈川県という社会があり、東京都という社会があるとも考えられる。
さらに目黒区のA集団、B集団というように細かく範囲を絞って「社会体系」だということもできるのだろう。
日本という大きな社会体系の部分体系(サブシステム)として神奈川県を見ていくのか、あるいは部分であるという視点を一旦置いて、とりあえずそこを全体だと仮定して見ていくのか。それらを明確に異なるシステムだと判断する基準はどこにあるのか。
錯綜した理解を記述していると自覚しているが、しかし個人的には理解できないことを理解できないと明示することが重要になる。こうした「投げかけ、問い」が将来においてひっかかって回収されることがある。私の全ての記事は講座ではなく、メモのような形なのでご了承いただきたい。
たとえばある集団にとって機能的だが、別の集団にとって逆機能的だという言いかたをマートンはする。たとえば「未開社会では、ただ一つの宗教体系が行われているだけであって、」というような言い方をする。
集団や組織、宗教ごとにシステムがありうるということになり、また一つの集団ないし社会において複数の宗教体系が含まれることもありうる。ジンメルの定義的には最低2人の相互作用からシステムはなりたち、その相互作用の恒常的な作用に着目した場合、それは構造ということになる。
「かところで、彼の著作をつうじて気づくことは、一般的な幅広い概念、たとえば、社会体系、制度、価値などのような概念は、あまり明確な定義や限定的意味を与えられないで、ルーズに用いられていることである。二、三の例をあげれば、ビュロクラシーのさまざまな形態を社会体系とも、制度ともいい、ときには組織とも呼んでいる。」
ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,450p(金沢実さんの解説)
「彼のばあい、概念の明確化は、その変数の指標を十分明確に分析するのでなければならない。指標とは、概念化された項目の記号を意味するものであって、このような指標の明確化されていない不十分な概念は、散漫な説明の次元にとどまり、やがて実質的に明確化されるべきいわば括弧つきの概念として用いられているにすぎない。したがって、彼の著述をみてもわかるように、社会学概念のすべてについて正確な定義やその厳格な適用を試みることよりも、むしろ機能分析を十分に遂行するために操作しうる最小必要限度の概念装置だけに周到な用意が払われている。ここにも再び、限定的なものから一般的なものへのマートンの論理的指向がうかがわれる。」
ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,450p(金沢実さんの解説)
「こうして暫定的に用いられる概念の曖昧さの代わりに、彼はたえず概念化の機動性を利用しているのである。こういう見地から、彼は、パーソンズとはまったく対照的に、社会体系を構成する諸要素や諸仮定のすべてを組織的に論じていないし、その機能要件なども明記していない。」
ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,451p(金沢実さんの解説)
「全体の体系」と「部分の体系」が区別された場合はどうなるか
「ある部分の体系」が「全体の体系」に対して機能を果たしているという言い方もできるのかもしれない。ある特定の宗教体系が、その国全体の宗教体系の維持にとって機能を果たしており、さらにその国全体の宗教体系が、その国全体の維持にとっての機能を果たしており・・・という言い方もできるかもしれない。この場合の体系と構造はいかにして明確に区別されるのか。全体-部分関係がその都度、可変的に、観察者の恣意的な切り取りによって変わっていくだけなのか。
たとえばパーソンズは、おそらく最も大きな単位である「全体システム」を、行為システム、テリックシステム、物理-科学システム、人間有機システムに機能分化させて考えている。
さらに「行為システム」は社会システム、文化システム、行動システム、パーソナリティシステムに分かれる。さらに社会システムはAGILのサブシステムにわかれ、さらにそのサブシステムはagilのサブシステムにわかれる。
【基礎社会学第二十八回】タルコット・パーソンズのAGIL図式とはなにか
このように広く、包括的に考えていくと、あるサブシステムはより大きな全体システムに対して機能している、あるいは機能要件であると考えていくことになる。ここまで大きな全体システムを全体とするならば、我々の想定できるあらゆるシステムはサブシステムとなり、それらのサブシステムを恣意的に(サブではない)「システム」と読んでいるに過ぎないのか。何を全体とし、何を部分とするかが恣意的に、観察者の分析意図によって決めていいとすれば、自分が決めた全体の範囲外のシステムは「環境」になるのか。
このあたりはグールドナーが機能主義者を批判した際に述べた「機能的自立概念」や、ギュルヴィッチが述べた「全体は諸部分のかなり自律的な多種多様な運動の複合、重層として成立するのであって、全体の存立、統合のために諸部分がそれぞれの機能をはたしているわけではない」という視点も理解のヒントになってくるのだろう。なにをもって自立(自律)とみなすのか、なにをもって境界の成立と見なすのか、ルーマンにも通じてくるキーポイントである。
灰色なパーソンズに対する理解の整理
以前、パーソンズのAGIL図式を扱ったが、その問題点について正直あまり理解できていなかった。その問題点とは、佐藤俊樹さんが挙げていた「近似の妥当性」と「システムと社会の二重定義」である。
今回、そのすべてを詳細に扱うことは出来ないが、断片的に触れておきたい。
佐藤さんによると、物理学ではシステムは「単なる質点の相互作用の集まり」でしかないという。
しかし、パーソンズの場合、社会システムにおけるシステムは単なる相互作用の集まりではないという。なぜなら、単なる集まりである場合、それは相互作用の範囲以上のものではない。しかし、パーソンズは「境界維持システム」という、自らの境界を維持するように動くシステムという概念を導入している。
佐藤さんによると、「相互作用の集まりがあたかも境界を維持するかのように動くしくみが積極的に示されないかぎり、二つのシステムは別のものだと考えざるをえない」という。
つまり、あるシステム(境界維持システム)が他のあるシステム(単なる相互行為の集まり)を維持しているということになる。佐藤さんの言葉で言えば、「社会が社会を作る」という事態である。問題は、パーソンズが「仕組み」を示していないにもかかわらず、一つのシステムが単なる集まりでもあり、また自分の境界を維持するように語られているという点だろう。この論点は自分自身を不断に生成し続ける自律的なシステムであるルーマンの「オートポイエティック・システム」の概念とつながっていく。
また、パーソンズは「相互行為の全体の挙動」については知ることが出来ないと考えていた点を抑えておく必要がある。つまり「全体の社会体系」の挙動全てを我々は知ることが出来ないというわけである。安定していると判断することができない、他のランダムに見えるようなパターン全ても把握しなければ社会全体の挙動を知ることはできないわけだ。
これはデュルケムとも、ルーマンとも重なってくる。そして、いかにしてそれと近似したもの、あるいはなにかしら関連するものを理解するかという点が重要になっていくのである。
佐藤さんによると、パーソンズは社会全体の挙動を知ることが出来ないため、機能要件で近似しようとしたという。安定していると判断することができない、他のランダムに見えるようなパターン全ても把握しなければ社会全体の挙動を知ることはできないわけだ。
相互行為の内に恒常的な形態をとるものを「構造」と名付け、その構造が機能要件をみたすか満たさないかに応じて、全体が特定の動き方をするという考え方をした。動き方は主に恒常的な形態が変わるか、全体が成立しなくなるかの2つである。こうして全体の動きの近似的なモデルを作り、知ろうとしたのである。
しかし佐藤さんいわく、そもそもパーソンズの説明の仕方は厳密には「近似モデルではなく、相互行為群に別の水準の何かを新たにくっつけているだけ」だという。言い換えれば、「相互行為の集まりそれ自体」と、「その結果として生み出される独自のなにか」だという。この話は先ほどの二重定義の話と重なってくる。
しかしこの動画で扱うにはボリュームが大きすぎ、また私の理解も浅いためこのあたりで区切りをつける。しかしいつかは扱わなければいけない課題であり、できればルーマンの理解を通してもう一度扱いたい。
「第二の失敗の方に移ろう。パーソンズの構造機能主義はそもそも近似なのだろうか。ここにはパーソンズの社会学をこえて、社会学全体に関わる問題が潜んでいる。だから、少しくわしく説明する。構造と機能の定義に戻ると、本来知りたいのは相互行為の全体の挙動であった。これを直接知ることはできないから、パーソンズは機能要件で近似しようとした。相互行為のうち恒常的な形態(=構造)をとるものが、一定の機能要件をみたすかみたさないかに応じて、全体が特定の動き方をする。恒常的な形態が変化するか、全体が成立しなくなる、と考えたわけだ。しかし、相互行為のうち恒常的な形態をとるものも、相互行為の全体にふくまれるはずだ。むしろ、その主要な部分だといっていい。だとすれば、構造が特定できた段階で、相互行為の全体の挙動もかなりわかったことにならないだろうか。」
佐藤俊樹「社会学の方法」,208P
「物理学の力学系は実際そういうもので、質点間の相互作用をさす。ところが、パーソンズの『社会システム』には、もう一つ別のシステム概念も出てくる。それは『境界維持システム(border-maitain system
)』と呼ばれ、自らの境界を維持するように動くとされる。相互作用の集まりとしてのシステムは、境界維持システムではない。相互作用の集まりでは、境界は相互作用の範囲以上のものではないからだ。それをシステムが維持するというのは、わかりやすくいえば、集合がその範囲を維持するように動くというのにひとしい。相互作用の一般的な定義では、そういうことはありえない。それゆえ、相互作用の集まりがあたかも境界を維持するかのように動くしくみが積極的に示されないかぎり、二つのシステムは別のものだと考えざるをえない。こうした全体の二重定義は構造機能主義だけの問題ではない。」
佐藤俊樹「社会学の方法」,210-211P
「それに対して、境界維持システムのように考えた場合には、社会を維持する機構=Aがあって、それによって社会=Bが維持されている。社会を維持する機構も社会だから、社会が自分で社会をつくっていることになる。そういう自己組織系として、『社会が社会をつくる』ことになる。もちろん、この場合にはAがBに本当に含まれるのかどうか、そんな因果関係がそもそも成立するかどうかが問題になる。これは現代社会学の最前線の主題でもあるので、第二部であらためて述べるが、その手前にも実は重要な問題がある。社会学では、この二つの『社会が社会をつくる』のちがいが曖昧にされやすい。社会は人間あるいは行為の集まりなのか、それとも独自の自己組織的な何かなのか。もつとも簡単にいえば、社会は主語にならないものなのか、それとも主語になるのか。そこが曖昧にされやすいのだ。社会学を学び始めるときには、多くの人がここにひっかかるが、専門的な研究者になっていくなかで、次第に忘れていく。これにはっきりと距離をおいていたのは、『社会とはなにか』の問いを明確に回避したウェーバーくらいだろう。ジンメルは、形式と形式がうみだす特性を同じものだとしない、という消極的な形で対処した。パーソンズの場合は、二つを積極的に混同する形でシステム論を展開した。」
佐藤俊樹「社会学の方法」,211-212P
「パーソンズは、特定の出来事(例えば自殺)や制度(例えば近代的な資本主義経営)ではなく、社会そのものを理論的に考察しようとした。…コントやスペンサーらの一九世紀社会学でも、『軍事的社会』や『産業社会』みたいな形で、社会全体の特性が描かれる。けれども、これらは特定の制度を社会全体にそのまま拡大適応した議論でしかあに。それに対して、パーソンズは社会を成立させるしくみを、『相互行為―構造―機能』という論理的構築の形で描いた。社会の基本単位を相互行為とし、相互行為の集まりを『社会システム』と名付けた。そして、その全体の挙動を構造と機能で近似できるとした。」
佐藤俊樹「社会学の方法」,214P
構造を安定(恒常、定常)・不安定以外の要素で定義するとしたらなにが必要になるのか
話を戻そう。
構造を安定(恒常、定常)・不安定以外の要素で定義するとしたらなにが必要になるのか。
ある観点において恒常的であるというような任意で静態的な観点によるものにすぎないのだろうか。なんとなく反復的に見える、昔から続いているという資料がある、というような曖昧なものなのか。統計的に最頻出の数量化できるものなのか。
体系と構造の区別については個人的に灰色の理解のままなのは不安だ。特に、マートンが体系と構造を同一視してしまっているというギデンズの批判を理解できていない。構造の判定基準が「恒常性」に絞られがちで曖昧であり、任意的であるというような理解しかできていない。
そもそもある範囲において体系が確認されているとどのように判定するかも不明瞭である。ある要素(人間であれ、地位であれ、役割であれ、行為であれ、コミュニケーションであれ、細胞であれ)の相互作用(相互依存関係と、相互浸透関係との違いも理解する必要がありそうだが)が見られる場合、そこになんらかのシステムがあるといえるかもしれない。
しかし、2つの異なるシステムがあると判定する場合はどうだろうか。
他の相互作用と区別できるような相互作用という考え方、いわゆる「差異」が必要になる。キリスト教と仏教を我々が別の宗教システム、別の宗教形態(≒構造)であると区別できるのは、それらの境界がなんらかのかたちであるからだろう。田中さんと鈴木さんは違う生物だ、と我々はなんらかの差異をもとに区別している。法律と文化は違うシステムだ、と我々はなんらかの差異をもとに区別している。
もしそうした2つの異なるシステムの判定基準と、2つの異なる構造の判定基準が同一であり、単なる恒常性の如何やその範囲の単なる大きさの如何によるものであるならば、構造と体系の区別は曖昧になる。
「境界維持」、「システムと環境の区別」「相互依存」、「再帰性」、「再生産」や「自己言及」、「時間性」などがヒントになる。いずれにせよ、マートンは体系について特別な整理を行っていないのでこの動画では深堀りできない。ギデンズやルーマンで、さらに詳細な体系と構造の関係に関する分析の整理が目指されると期待することにする。
【1】機能的統一の公準に対する批判
マートンは従来の機能分析で中心的に用いられている誤っている、不当な3つの古典的な公準を批判している。
批判を通してそれらに代わりうる概念やアイデアを提案し、機能分析をより厳密に、有益に利用できるように整理している。
人類学における機能分析については以前の記事を参照。
【基礎社会学第二十五回】マリノフスキーとラドグリフ=ブラウンの「機能主義」とはなにか
機能的統一の公準とはなにか、意味
機能的統一の公準(一体性の公準):・標準化された(全ての)社会的項目や文化項目が全体の社会体系または文化体系に対して機能的であるという仮定のこと。このように、あらゆる項目が体系の維持に対して機能している状態、高度に統合されている状態を「機能的統一」と呼ぶ。
一体性:・機能が何らかの全体に対して関わること
ポイントは「全体」に対して機能的であると限定しているという点である。たとえばある集団(部分)のみの維持だけに機能する、といった視点が、単位の変動が考慮されていない。
「内容的にいえば、第一の公準は、標準化された社会活動や文化項目が全体の社会体系または文化体系に対して機能的であること、第二の公準は、かような社会的項目や文化的項目のすべてが、社会学的機能を果たしているということ、さらに第三の公準は、これらの諸項目がしたがって不可欠であるということである。」
ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,65P「一体性というのは、機能が何らかの全体に対して関わることをさす。」
佐藤俊樹「社会学の方法」,233P
機能的統一の公準の問題点
【問題点】大前提として、「ある項目が全体の体系に対して機能する」という仮定は先験的にわかるものではなく、経験的な、観測者が成り立つかどうか確認するべき事実問題である。
また、「機能的統一」という概念は「統合の程度が高度である」ということを先験的に前提している。しかし、ある項目が体系の維持に対してどの程度プラスに機能するかは先験的にわかるものではない。つまり、統合の程度は「経験的な変数」であり、また、同一社会においても時代においても、社会においても変化する。
もし仮に、「標準化された社会活動や文化項目が全体の社会体系または文化体系に対して機能的であるという仮定」が、ただ「なんらかの程度機能的である」というような仮定であるとすればそれは定義の問題だという。
たとえばある集団に対してある項目が、その程度は不明だが何らかの維持に貢献すると定義づけするならば、一見正しいように見える。しかしそうした仮定は役に立たない。何らかのプラスがあるというだけではなく、何らかのマイナスもあり、その差引残高を考慮することで役に立ってくるのである。また、没機能的である、つまりプラスにもマイナスにもなんら機能しないような標準化された社会的・文化的項目が経験可能性としては残る。
「(ラドクリフ・ブラウンの文章の引用)『機能的統一とは、社会体系のあらゆる部分がかなりの程度の調和または内的な論理一貫性をもって、いいかえれば、解消したり、規制したりすることのできない永続的な葛藤を生ずることなしに、協働する状態と定義することができよう。』」
ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,66P
「機能的統一という観念が経験テストの範囲を超えた公準ではないどころか、まったく正反対であることは、まさに明瞭であると思われる。統合の程度は経験的な変数であって、同一社会においても時代により変化し、また種々の社会によっても異なる。あらゆる人間社会が、何らかの程度の統合を必ずもっているとうことは、定義の問題であって――それだけでは真の問題にふれていない。すべての文化的に標準化された活動や信念が全体としての社会に対して機能的であり、そこに生活する人々に対して一様に機能的であるというごとき高度の統合をすべての社会がもつとは限らない。」
ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,67P「第一は、《社会の機能的統一の公準》である。それは、標準化された社会活動や文化項目が全体の社会体系または文化体系に対して機能的だという仮定である。この公準の問題点は、次の二点にある。(1)統合の程度は経験的な事柄であって、同じ社会においても時代によって変るし、また社会の種別によっても異なるということ。(2)社会的な慣例や事象は、同じ社会内でもある集団にとっては機能的であり、他の集団にとっては逆機能的なことがある。」
「社会学の歩み」,152P
「古典的な機能分析の公準の一つ。ラドクリフ=ブラウンによれば、社会システムのあらゆる部分が、かなりの調和また内的な論理一貫性をもっていることをさす。マートンにより徹底的に批判された公準の一つ。」
「社会学小辞典」,107P
機能的統一の公準の改善点
【改善点】マートンは「機能的統一の公準」に代わる考え方として、「一定の社会的機能の該当する社会的単位の明記」を提示した。単位の取り方によって分析結果は変わるという話。
たとえば「ある下位集団Aに限定するならばその集団の維持に機能している」というような形で言明するという話である。もちろん、「ある下位集団Bにおいては逆機能している」という形もありうる。逆機能については後述する(体系の維持に貢献ではなく阻害というざっくりしたイメージ)。
「マートンは、三つの公準の検討を通して、それに代わる次のような考え方を提示した。(1)機能的統一の公準に対しては《一定の社会的機能の該当する社会的単位の明記》。」
「社会学の歩み」,153P
Q 機能的統一の公準が信憑された背景
A 人類学者による「未開社会における成果」を社会学者が暗黙の内に採用し、一般化し、拡大解釈してしまった可能性が挙げられている。
未開社会の場合は宗教がひとつであり、またその成員のほとんどがその宗教に入っている事が多い。ある特殊な慣習や宗教が、その未開社会全体の維持に機能しているというような「高度な統合」という機能が見られるケースはありうる。
しかし、そうした特殊事例を「一般化」し、文明社会の領域へそのまま移すと、あまりにもひどい学問的ミスを犯すことになるという。例えば文明社会では宗教的対立によって特定の宗教が全体の維持にマイナス側に大きく機能するケースなどが考えられる。
「機能的統一の仮定を否定する一群の観察や事実が、われわれの示唆したように、広範かつ卑近なものとすれば、どうしてラドクリフ・ブラウンと彼の先蹤を追う人びとがこうした仮定を固執し続けるのかを問うことは、興味深いことである。一つの可能な手がかりとしては、社会人類学者、すなわち文字をもたない未開社会を主として取り扱う人びとがこの概念を最近の説明方式において展開したという事実である。『多くの原始文明が高度に統合された性質をもつ』とラディンが述べたところからみると、この仮定は、たとえすべての未開社会ではなくとも、いくつかの未開社会にはかなりよくあてはまるだろう。だが、このおそらく有用な仮定を文字をもたない小さな未開社会の領域から広範にして複雑かつ高度に分化した文明社会の領域へそのまま移すと、あまりにひどい学問的誤謬を犯すことになる。かように仮定を不当に拡充する危険が、宗教の機能分析におけるほどはっきり現れた領域はおそらくないかろう。」
ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,68p
【コラム】ルーマンによる機能等価主義
マートンにおける関数としての機能
佐藤俊樹さんによるマートン解釈をまず紹介する。
- マートンは機能的一体性は機能の単位の問題であると考えていく。
- ある機能は何かの全体に対して関わり、機能は特定の全体と対応関係にあるといえる。
- パーソンズの構造機能主義では、この何かの全体があらかじめ決まっているかのように考えられていた。しかし、実際には明確な基準が与えられているわけではなく、全体を可変的なものと考えることもできる。
- 機能の具体的な中身は、どの範囲をみるかによって変わってくる。機能は「観察する範囲の関数」だと考えていく。
ただし、佐藤俊樹さんいわく、このような解釈はマートン自身の文章から確実に読み取れるわけではないという。
ルーマンの「機能等価主義(機能-構造主義)」は関数としての機能を重視する。ここにマートンとの類似性が見えてくる。
独立変数の事象と従属変数の事象の一対一対応関係だけではなく、独立変数事象の「集合」と従属変数事象の「集合」との全般的な対応関係も「機能」として考えていくのである。これは代わりうるものの可能性を考慮している考え方である。集合内のどの変数でも同じ程度の効果をもたらすと考えていく。
ここでいう「変数の集合」は、観察者がとる「範囲」であると考えることができる。たとえば極めて狭い範囲、たある人間とある人間の関係だけをシステムと見れば、代替要素が減っていくかもしれない。たとえばある特定のゲーム、SNS、宗教、制度、習慣ではないとその人間関係の維持が成り立たないということもある。
右の図でいえば、社会体系Bだけを観察して一般化し、社会体系Aという全体に機能している、と断定するような分析は有益ではないということになる。あくまでも、社会体系Bに限っては、という単位を明確にする必要がある。
ある近所、ある村、ある社会と広げていくうちに全体としては差引勘定がプラスになるという結果を出す代替要素が増えていくかもしれない。
たとえばある人間とある人間は不仲になったとしても、全体としては維持されているようなイメージである。しかし広げすぎると実証しにくいという問題が出てくる。また、どのような基準で結果を判定するかも問題になる。
たとえばアメリカや中国の維持に核装備が機能したとしても、より大きく体系を広げていけば「世界の維持」にマイナスに機能していると計算できる可能性もある。しかしその計算は難しい。核の抑止のおかげで、世界は維持されているという考え方もできる。しかし実際に核戦争で世界が破滅した後に、「ほら、やっぱりマイナスに機能していた」というのでは遅いだろう。
村田さんによると、こうした等価機能主義の考え方は「機能と構造がほとんど同じ意味内容にならざるをえない」という。関数が対応関係の形式や変換パターン、枠組みの設定とみなされるなら、それを「構造」とも表現することがあるからであるという。たしかに機能を果たす項目は習慣のように安定した、標準化されたパターンを持つ相互作用であることが前提されている(箱にAを入れたらいつも安定してBが返ってくるようなイメージ)。
たとえば、ある社会ではA宗教でもB宗教でもA戦争でもB戦争でも「団結力を高める」という安定した対応関係が見られるという場合、それはある種の「構造」に見える。もし安定せずにランダムの度合いが高いならば、代替可能だとそもそも判断しにくいだろう。しかし機能と構造が同じ意味合いという点に関して、この理解でいいのか灰色である。
構造と機能がほとんど同じ意味内容だとして、それらと「システム」は区別されるのだろうか。
ルーマンは「代替要素をたえず探索しつつ全体が変動していく事態のなかに浮き彫りにされてくる存在」をシステムと呼ぶという。
上の図は以前の創造学第2回の記事を参照※井庭崇さんの図を参考に作成
昔は近所と仲良くすることがある社会の維持へと貢献していたが、しかし都市化が進むにつれて、あえて近所と接触しないことがその社会の維持へと貢献していくということもありえるだろう。
その意味で、独立変数が代置されていくといえるかもしれない。常に動いているという、動態的なイメージがシステムになる。ルーマンは構造より機能を重視するので、機能-等価主義とも言われているのである。ルーマンについては今後の記事で近い内に扱っていきたい。
「残るのは、一体性の公準である。日本語訳で読んでいると気づきにくいが、論文のなかで彼は『機能的一体性(functional unity)』を『機能の単位(functional unit)』の問題に読み替えていく。機能は何かの全体に対して関わる。つまり、機能は特定の全体と対応関係にある。パーソンズの構造機能主義では、この全体はあらかじめ決まっているかのように考えられていたが、二つのシステム定義にみられるように、実際には明確な基準があたえられていたわけではない。だとすれば、全体を可変的なものと考えることもできる。機能が特定の全体に対応しているのであれば、全体としてどの範囲をとるかによって、機能も変わってくる。機能の具体的な中身は、どの範囲をみるかによって変わってくる。いわば観察する範囲の関数でもある。したがって、Aがどんな機能をもつかという問いは、実はどんな範囲との関わりでAのはたらきを捉えるかに置き換えられる。正直にいうと、マートン自身の文章からそこまで確実に読みとれるわけではない。」
佐藤俊樹「社会学の方法」,236P「ルーマンは,このような論理を展開することにより,因果関係の単線的な一対一対応関係のイメージを崩すことをこころみた。それが「等価機能主義」といわれる理論的立場であり,あるいは,パーソンズ的な「構造‐機能主義」を批判的にもじって「機能‐構造主義」と称される立場でもある。これは,すぐれた論点の指摘であり,たしかに,革新的なイメージをもたらす。ただし,この考え方に依拠すれば,結局のところ「機能」と「構造」とは,ほとんど同じ意味内容にならざるをえない。というのは,「機能」が「関数」であるとされ,「関数」とは対応関係の形式や変換パターンあるいは枠組みの設定であるならば,そのようなことがらを指して一般には「構造」とも称するからである。ともあれ,同じことがらを「機能」と称するにしても,あるいは「構造」と称するにしても,この等価機能主義のイメージを応用すれば,「変動」という現象とは,代替しうる他の要素をつぎつぎに選択しつつ,諸要素をたえず更新していく活動の集積として展開されるととらえられる。そして,このように代替要素をたえず探索しつつ全体が変動していく事態のなかに浮き彫りにされてくる存在を指して,ルーマンは「システム」と表現することになる。しかるに,このように「機能」を「関数」と考える用法は,社会学では,これまでのところ主流になってはおらず,ルーマン自身でさえ,のちには「関数」についてほとんど語らなくなる。」
村田裕志「社会学的機能主義系 「社会システム論」 の視角 (I)」,105-106p
【2】普遍的機能主義の公準に対する批判
普遍的機能主義の公準とはなにか、意味
普遍的機能主義の公準:標準化された社会的項目や文化的項目の全てが、積極的的機能を果たしている。
「積極的」とは主に社会の維持のためにプラスに機能しているというイメージである。普遍性とは、全てのものが何らかの機能をもつことをさしている。この「全て」という仮定が重要になる。機能的統一の公準は「(包括的な)全体」という範囲に貢献する対象を限定しているのに対して、この普遍的機能主義の公準は必ずしも範囲を限定していない。とはいえ、マートンによると3つの公準はそれぞれ相伴ってみられるという。強調点の置き方を3つ変えて説明しているイメージ。
「もっとも簡潔に表現すれば、この公準は、標準化された社会的または文化的諸形態がすべて積極的機能をもつということである。マリノフスキーは、機能的概念の他の側面についてもそうあんおだが、もっとも極端な形で、次のように述べている。『それ故に、文化の機能的見地は、あらゆる種類の文明において、すべての慣習、物質的事物、観念、信念が何らかの活動的な機能を果たしているという原則を主張する…』」
ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,71P「第二は、《普遍的機能主義》の公準である。標準化学者は、進化論者にとって中心的な《生き残り(サーバイバルズ)》という概念に反対する余り、この公準を提唱したとみられる。だが、この公準の問題点は、次の点にある。すなわち、文化または社会構造のどの項目も何らかの機能はもっているかもしれないが、そうした項目のすべてがすべてにたいして同じ意味で機能的であると断言することはできない、という点である。」
「社会学の歩み」,152P
「古典的な機能分析(主としてラドクリフ=ブラウンや、マリノフスキらの人類学)において採用されていた公準の一つ。『すべての文化的項目(慣習・物質的事物、観念など)は、何らかの活動的な機能を果している』と主張する。 マートンは『社会理論と社会構造』(1949)において、この公準を徹底的に批判した。普遍的機能主義の公準は、経験的に確証されるべき主張であって、はじめから結論として採用されるべきものではないからである。」
「社会学小辞典」,538P
キーワード:普遍性
「普遍性とは、全てのものが何らかの機能をもつことをさす。」佐藤俊樹「社会学の方法」,233P
普遍的機能主義の公準の問題点
【問題点】標準化された社会的または文化的諸形態が全て積極的機能をもつという仮定することができない。
それは先験的ではなく、経験的な、観測者が確認するべき事実問題である。
自分勝手に積極的機能ばかりを選び取り、ある項目が社会や文化の維持に積極的機能をもつとは安易にいえない。また反復的、標準的な全ての項目が先験的に積極的機能をもつと結論づけることは論外である。
仮に普遍的機能主義の公準を、「標準化された社会的または文化的諸形態がなんらかの積極的機能をもつという」仮定なら、それはほとんどの場合は真であるといえるかもしれない。
ある制度はある集団にとってほんの僅かな量であるとしてもプラスに機能したといえるからだ。視点を変えたり体系の範囲を変えていけば、ほんの僅かにプラスしているという根拠をマイナスとの計算をしない場合、探し出すことは難しくないだろう。佐藤さんの言葉で言えば、「機能を因果に差し戻すと、あらゆるものは何らかの因果関係をもつということになり、それはあたりまえだ」ということになる。ただし、没機能的という経験的可能性は残るだろう。つまり、何らプラスにもマイナスにも働かないような標準化された社会的または文化的項目もありうるかもしれない。
「永続的な文化形態はすべて不可避的に機能的であるという第二の普遍的機能主義の公準を吟味した結果、機能的解釈の系統的に整理されたアプローチによって解決されねばならない他の問題が生じた。われわれは、かような文化形態の機能的結果とともに逆機能的結果をも見極める用意がなければならないのみならず、機能論者は、その研究を社会技術と関係させようとすれば、多様な諸結果の正味の差引勘定を秤量する方法原理を発展させねばならないという困難な問題に結局は直面することがわかった。」
ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,78P
社会的残存とはなにか、意味
社会的残存:人類学者のリヴァース(William Halse Rivers)によると「現在の効用によっては説明できず、過去の歴史を通じてはじめて理解できる慣習」である。
例:男の洋服の今では形だけで無用となっている袖のボタン
たとえ機能を認めても、文化型式とか、行動型式の直接的な記述には少しもプラスしない極端な事例。「機能を認めても、記述にはプラスしない」という点がポイントである。機能分析を行うものは、何でもかんでも「なんらかの機能を果たしていれば」その項目をするべきというわけではない。取捨選択というものがあるのである。伝統の中でも極端なケースが社会的残存というイメージだろうか。
「社会的残存、すなわち、リヴァースの言葉で表現すれば、『現在の効用によっては説明できず、過去の歴史を通じてはじめて理解できる…慣習』という観念は、少なくともツキディデスまで遡ることができる。」
ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,73P
「…こうした残存が現代の文明社会において確認されるばあいでさえ、これによって人間行動とか社会変動の動態を理解するにはほとんどプラスしないということができる。文明社会を取り扱う社会学者は、記録をもつ歴史の貧弱な代用物として残存がいかがわしい役割を果たす必要を認めないので、これを無視しても何らたいした損失はない。だが、彼は陳腐な的外れの論争に走って、あらゆる文化項目が活動的な機能果たすという不当な公準を採用するには及ばない。というのは、この公準もまた検討を要する問題であって、それに先立つ結論ではないからである。」
ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,73P
伝統とはなにか、意味
伝統:あらゆる確定された文化諸要素。「見慣れたものを保持し、伝統を維持する」という(それだけには限らないが)最小限の機能をもつと仮定してよいもの。
機能があるというのは真であるかもしれないが、しかしほとんど事態を明らかにするようなものではないという。そもそも標準的な項目だと仮定した時点で、伝統はその中に入ってくる。なぜなら、たいていの場合、伝統は法制度と同じように繰り返されているものだからである。繰り返されているからと言って必ずしも分析する、記述する有益さがあるわけではないだろう(有益・価値といった評価の基準によるかもしれないが)。
「以上は、たとえ機能を認めても、文化型式とか、行動型式の直接的な記述には少しもプラスしない極端な事例を示すものと思われる。あらゆる確定された文化諸要素(漠然と『伝統』と呼ぶことができる)は、『見馴れたものを保持し、伝統を維持する』という――それだけには限らないが
――最小限の機能をもつと仮定してよい。還元すれば、どのような確定した慣行にも同調するのは、この確定した慣行から逸脱するとき当然うけるべき制裁を同調者に避けさせうるという『機能』があるというのと同然である。このことは、たしかに真であるが、ほとんど事態を明らかにするものではない。」
ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,72P
機能的諸結果の正味の差引勘定とはなにか、意味
機能的諸結果の正味の差引勘定:項目にはある範囲に対して、その適応や調整にプラスに働く機能(積極的、活動的機能)とマイナスに働く機能(逆機能)があり、その差し引き結果が機能の結果であるという仮定。
正味の代わりに正負という翻訳が用いられることもある。正味とは一般に、「余分なものを取り除いた、物の本当の中身」を意味する。個人的には正負のほうが直観的に理解しやすい。
たとえばある集団Aだけを観察していれば、そうした差引勘定は計算しやすいかもしれない。安直な例でいえば、10人の個人からなる集団で、そのうち1人だけが小さな問題行動を起こしやすくなるが、9人は集団の維持大きくプラスするように作用しているなど。
しかし、範囲を集団Aと集団Bの合計からなる集団Xへと広げていけば、集団Aにはプラスの傾向があり、集団Bにはマイナスの傾向があるケースなどが出てくる。その場合、集団Xにとっては合計としてプラスなのか、マイナスなのかよえい判断しにくいだろう。さらに集団Y、集団Zと広げていけばなおさら。
なお、佐藤さんによれば範囲の限定のやり方について、「ルーマンがシステム境界を意味で定義することで解決した」という。
範囲の限定のやり方、プラスやマイナスの基準の取り方、選定すべき項目の選び方など、明晰な分析のためには学ぶことが多い。
キーワード:機能的諸結果の正味の差引勘定
「研究の指針としてはるかに有用と思われるものは、次のような暫定的な仮定である。すなわち、存続する文化形態には、一単位と考えられる社会か、それともこのような文化形態を直接的な矯正または間接的な説得の手段によって保持するだけの有力な下位集団のいずれかに対して、機能的諸結果の正味の差引勘定があるということである。この説明方式は、積極的機能に集中しようとする機能分析の傾向を避けると同時に、研究者の注意を他の種類の諸結果に向けさせるものである。」
ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,73-74P「このより厳密な機能分析の形態は、現存の社会構造の機能の研究だけではなく、さまざまな状況にある個人や下位集団や社会階層およびより包括的な社会に対する逆機能の研究をも含んでいる。後に述べるように、機能分析は次のように暫時的仮定に立っている。すなわち、現存する社会構造の総結果の正味の差引勘定が明らかに逆機能的であるばあいには、強い不断の変化する力が現れる。まだ確定されてはいないことだが、こうした圧力が一定の限度を超えると、多少ともあらじめ決定された社会変動の方向に進む結果になるだろう。」
ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,85P「機能分析は、しばしば社会変動の動態よりもむしろ社会構造の静態に焦点をおいたが、これはかかる分析体系にとって本質的なものではない。機能とともに逆機能に焦点を向けることによって、機能分析は、社会的安定の基礎だけでなく、社会変動の可能的根源を秤量することができる。」
ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,85P「現存の所要その逆機能的結果として蓄積された社会構造の緊張や圧迫は、適切な社会計画によってこれを抑止したり制限したりしなければ、やがて制度の崩壊や根本的な社会変動をもたらすであろう。こうした変動が一定の、用意に見きわめられない限度を超えたばあいに、新しい社会体制が現れたと通常いわれる。」
ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,86-87Pキーワード:機能分析者の固有の対象
「しかし、また繰り返しいわねばならないことは、機能分析者の固有の対象は、変動だけでもなければ固定だけでもないということである。歴史の経過をみてもかなり明らかなように、あらゆる主な社会構造は、時の経過につれて徐々に変更を加えられたり、突発的に終わりを告げたりしてきた。」
ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,86-87P
【3】不可欠性の公準に対する批判
不可欠性の公準とはなにか、意味
不可欠性の公準:標準化された社会的項目や文化項目が不可欠であるという仮定。
マートンによると、こうした公準は「機能を果たす項目」が不可欠であるのか、「項目が果たす機能」が不可欠であるのか、あるいはその両方が不可欠であるのか不明だという。
以下の2つの命題、仮定に分類することができる。
【1】機能の不可欠性の命題:ある社会の維持のためにはある活動的な機能が不可欠であるという仮定。
たとえばある社会の維持のためには、「人間の行為に対する統制」や「社会的感情や信念に対する統合」という活動的な機能が不可欠であると考える。
【2】機能を果たす項目の不可欠性の命題:一定の文化的または社会的形態がこれらの各機能を果たすのに不可欠であるという仮定。
つまり、特定の文化的または社会的項目がなければ、ある機能を果たすことができないというわけである。このような項目と機能の関係を「特定の代置することのできない構造」と表現することがある。
例えば、特定の宗教でなければ「人間の行為に対する統制」という機能を果たせないと考えたりする仮定。宗教の代わりに法律でも可能だ、と考えていくことが出来ないパターン。
「この曖昧さは、前述のマリノフスキーの宣言のなかでも明白になるのであって、その趣旨は次のようなものである。『あらゆる種類の文明において、すべての慣習、物質的事物、観念、信念は、何らかの活動的な機能を果たし、何らかの成しとげるべき仕事をもっており、活動的全体のなかで不可欠の部分をなしている』。右の文章からみると、彼が主張する不可欠性は、機能のそれなのか、機能を果たす項目(慣習、事物、観念、信念)のそれなのか、それとも両方を含むものなのかまったく不明である。」
ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,74P「一体性というのは、機能が何らかの全体に対して関わることをさす。」
佐藤俊樹『社会学の方法』,233P「マートンが批判した機能主義人類学の三つの公準の一つ。いかなる文明においても慣習、モノ、観念や信仰は、他のものには代替できない不可欠な社会的・文化的機能を果たす項目とみなされてきたが(とくにマリノフスキ)、マートンはこれに対して、『同一の項目が多様な機能をもつことがあるように、他の項目であってもそれと同等の機能を果たしうるものがある』と反論して、新たに機能的代替項目(functional substitutes),機能的等価項目という概念を代置する必要を説いた(『社会理論と社会構造』1949,1957)。なお、パーソンズの用いる機能的必須要件(functional imperatives)は機能的(先行)要件(functional [pre] requisites)と同義である。」
「社会学小辞典」,108P
「第三は、《不可欠性の公準》である。マリノフスキーは『あらゆる種類の文明において、すべての慣習、物質的事物、観念は何らかの活動的な機能を果し、何らかのなしとげるべき仕事をもっており、活動全体の中で不可欠の部分をなしている』と主張している。この公準で仮定される不可欠性とは、機能のそれなのか、機能を果す項目のそれなのか、それとも両者を含むものなのか、全く不明であり、したがってきわめて曖昧な主張だということになる。」
「社会学の歩み」,153P
「要するに、不可欠性の公準は、通常表明されているところでは、二つの、相関連するが区別できる主張を含んでいる。第一に、或る機能が不可欠であるというのは、その機能が果たされなければ、社会(または集団や個人)が存続しないという意味で不可欠と仮定されている。そのばあい、ここに機能的予備要件、すなわち、或る社会にとって機能的に必要な予備条件という概念が呈示されるが、この概念については、いずれ詳しく検討する機会があろう。」
ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,75P
不可欠性の公準の問題点とは
【問題点】どちらの命題も仮定することは出来ない
(1)機能的必須要件、機能的先行要件といった概念には問題がある。先験的ではなく、経験的な、観測者が確認するべき事実問題である。また、機能的要件という概念自体も問題がある。
(2)ある特定の項目でなければある機能を果たすことが出来ない、ということも先験的ではなく、経験的な、観測者が確認するべき事実問題である。
特定の項目でなければある機能を果たすことが出来ないケースを見つけることができる可能性がある。
しかし、そうではないケースも同様に見つけることができる可能性がある。
後者の場合を、 機能的選択項、機能的等価項、機能的代用項と表現する。例えばある宗教(項目)が「人殺しを防ぐ」という機能をもつとしても、「人殺しを防ぐ」という機能はある法律(項目)でも代わりがきくケースがありうる。
キーワード:不可欠性の公準の問題点
「われわれは、不可欠性の公準には、二つの相異なった命題が伴うことを知った。すなわち、一方では一定の機能の不可欠性を主張するもので、そのために機能的必要または機能的予備要件の概念が生じ、他方では現存の社会制度や文化形態などの不可欠性を主張するものである。これを正当に問題視すると、機能的選択項、等価項あるいは代用項という概念が生じる。」
ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,78Pキーワード:機能的選択項、機能的等価項、機能的代用項
「ところで、以上のような不可欠な文化形態(indispensable cultural forms,制度,標準的慣行,信念体系等)という意味あいをもった概念と対照をなすものに、機能的選択項(functional alternatives)や機能的等価項(functional equivalents)や機能的代用項(functional substitutes)という概念がある。」
ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,75-76P
「同一の項目が多様な機能をもつことがあるように、同一の機能が選択しうる諸項目のどれによっても果たされうる」
「同一の項目が多様な機能をもつことがあるように、同一の機能が選択しうる諸項目のどれによっても果たされうる」という一般原理をマートンは呈示している。
ここでいう「原理」は証明なしに承認される命題である「公理」あるいは「公準」とはすこし違う。なぜなら、観測や実験から「帰納」された命題が原理だからである。法則に近い。つまり反証可能性をもつ。経験的に反証可能な余地を残しておくという点がポイントなのだろう。先験的な仮説や見解、命題を公準、公理、諸前提として、そこから演繹的に結論を出されていくと経験的に反論することが難しい。※演繹的に出された結論自体は必然的に真であるが、前提そのものへの反証は可能である。反証可能であるのにもかかわらず反証不可能ないし証明可能のような形で信仰され前提されると問題が生じる。そうした信仰的仮定を伴うことで分析が有益ならば、許されるかもしれない。
マートンはこの原理を示した直後、「ここでは、機能的必要は特殊な社会構造の決定因であるというよりは、むしろこの社会構造を許容しうるものと解されている、換言すれば、当面の機能を果たす構造には、或る範囲の変異がある」と説明している。
私の理解では以下のようなものになる。
- 必要条件的な要件ではなく、十分条件的である。
- ある機能が十分かどうか、ある項目がある項目の機能的代替項になりうるかどうかは一定の幅がある(無制限ではない)。
- その幅は、各構造次第であり、構造によって制約される。これを「構造的拘束といったり、構造的脈絡」といったりする。
ある体系にはその体系特有の安定したパターン、相互依存のパターンというものがあり、それがいわゆる「(社会)構造」といわれる。
それに反するような項目によって代替することは難しいかもしれない。しかし、それに合致するようならば代替することは可能かもしれない。
たとえば長年、ある宗教が「人殺しを抑制する」という機能を果たしていたとする。それがいきなり、法律による公的制裁や、私的リンチといった機能と代替可能になるとは限らない。しかしだからといって、宗教でなければその機能を果たせないとは言い切れない。
どの程度の規模の社会体系を範囲とするのかにもよるだろう。国全体とするのか、ある村全体とするのか、その村のあるグループ全体とするのか。その範囲の取り方によって、代替可能な範囲も遷移するといえる。社会体系の範囲が変われば、社会構造の範囲も変わるということになる。たとえば特定の村全体に限っては宗教の代わりに法律は機能せず、市全体に範囲を広げれば機能するというイメージである。
もっと卑近で適当な例で安直に考えてもいいのかもしれない。私はカレーライスならテンションが上がるが、レバーフライだとどうもテンションが上がらない。
私は内臓系の食べ物を好まないというような安定したパターンをもっているからだ。私はランダムにテンションが上がるわけではなく、一定の恒常性をもって食べている。極端な例でいえば、小麦を食べると生命の維持ができないというような構造をもつ人もいるだろう。この場合は、代替は無制限ではなく、制限があるという例としてわかりやすい。
しかしある友人Aの場合は、カレーライスの代わりにレバーフライでもほとんど同じくらいのテンションが上がるということがありえる。
構造が違うからである。私と友人Aでは、ある項目が機能するかどうかの範囲が違う。カレーライスでしかテンションが上がらない人がいてもおかしくはない。
キーワード:一般原理,機能的必要,決定因
「さらに一歩進んで、われわれは次のような機能分析の主な一般原理を提示せねばならない。すなわち、同一の項目が多様な機能をもつことがあるように、同一の機能が選択しうる諸項目のどれによってでも果たされうるということである。ここでは、機能的必要は、特殊な社会構造の決定因であるということよりは、むしろこの社会構造を許容しうる(permissive)ものと解されている。還元すれば、当面の機能を果たす構造には、或る範囲の変異がある。」
ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,75P
パーソンズにおける構造分析例
たとえばパーソンズは国の構造をパターン変数で分析していた。こうした構造がなんとなくわかるなら、先程のレバーフライの例のように、なんとなく項目の代替可能な範囲が近似的に推測できるかもしれない。
なお、パーソンズの構造分析例については以前の記事を参照。
【基礎社会学第二十三回】タルコット・パーソンズの「パターン変数」とはなにか
- 【業績主義 + 普遍主義】例:アメリカ:関係ある人々に関わりなく適用される規則によって個人的業績に高い価値をおく社会
- 【業績主義 + 個別主義】例:古代中国:行為者にふくまれている個別的に関係ある人脈を考慮する規則にしたがって、個人的業績に高い価値をおく社会
- 【所属主義 + 普遍主義】例:ドイツ:行為は普遍的規範によって導かれるが、伝統的な地位のヒエラルキーが社会システムの内部に支配的に重要なものとして残っている社会
- 【所属主義+個別主義】例:ラテンアメリカ:行為者の地位により、そして行為の個別的人脈によって変化する規範によって行為が導かれる社会。
医者と患者からなる体系の場合の医者のパターンはこのようなイメージになる。
たしかに現代日本社会において医者はできるだけ感情中立的であろうとするパターンが見えます。ランダムに感情的であったり、中立的であったりするわけではないでしょう。呪術師の場合は感情的であろうとするかもしれない。
ある項目は普遍主義的ではなく、どちらかといえば個人主義的だから許容できないかもしれないな、などと推測していく。
自分なりのパターン変数を考えると面白いかもしれない。企業や特定の層の消費者などにも当てはめたりして使ってみると面白い。個人的には(アレクサンダーの)「パターン・ランゲージ」とも通じるものがあり、創造の分野にとっても刺激的な考え方である。
機能と機能要件の違いについて
機能的要件という言葉は最も曖昧で経験的に最も論議の多い概念のひとつである
・「機能的要件、機能的先行要件、機能的必須要件、機能的予備要件」といったややこしそうな用語群がある。パーソンズは機能的要件と同義的に機能的前提条件、機能的緊急事態、機能的命令なども用いていることがあるという。
まず、機能的必須要件と機能的先行要件は同義的である。どちらも、その機能がなければ社会の維持が不可能になるという意味合いで使われている。論理学的に言えば「必要条件」だろう。
たとえばパーソンズならAGILの四機能が不可欠であり、それがなければ社会は維持できないと先験的に前提している(ように見える)。たとえば「ある宗教」というのは機能ではなく項目であり、L機能が宗教以外の項目、たとえば家族によって充たされていればいいといえる。
つまり、機能の果たす特定の項目が不可欠であるというわけではなく、ある特定の機能が不可欠であるという話である。その意味で、項目は代替可能であると考えられている。しかし4つの機能は代替不可能であると考えられている。項目の代替性と、項目が果たす機能の代替性は別の話であり、前者は簡単だが後者は複雑である。
マートンは機能的予備要件を「或る社会にとって機能的に必要な予備条件」と定義している。また、「機能的要件(欲求、予備条件)というような言い方もしている。
マートンによると、機能的要件という言葉は最も曖昧で経験的に最も論議の多い概念のひとつであるという。また、機能的要件の概念は同語反復的ないし結果論的になりがちであるという。また、体系の「存続条件」だけに絞られがちだという。要するに、マートンは機能的要件という概念に批判的であり、あまり重要視していないように見える。マートンの本の訳者も後半で「パーソンズとはまったく対照的に、社会体系を構成する諸要素や諸過程のすべてを組織的に論じていないし、その機能要件なども明記していない」と述べている。必要条件だけではなく、十分条件すらも証明が困難な場合があるだろう。それが十分であるかどうかはわからないが、プラスに機能していると述べるだけでも機能分析といえるか(これも許容量を数量化できるかなど、さまざまな問題があるのだろう)。
「あらゆる機能分析の根底には、暗黙的であれ明示的であれ、当該体系の機能的要件という概念がある。他の箇所で述べたように、これは、機能理論において最も曖昧で経験的に最も論議の多い概念の一つである。社会学者が用いているように、機能的要件の概念は、同語反復的ないし結果論的となりがちであり、とかく一定の体系の『存続』条件だけに限られ、またマリノフスキーの著作にみられるように、社会的『欲求』のみならず生物学的『欲求』を含む傾向がある。以上には、さまざまなタイプの機能的要件(普遍的と特殊的)を確定するとか、これらの要件の過程を検証する手続きなどという困難な問題が含まれている。」
ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,103P「ここで用語について簡単にみておこう。パーソンズが「構造機能分析」を提唱した段階では,機能的必要(functionalneeds)という語を主として用いている、その後,機能的前提要件(functionalprerequisite),機能的緊急事態(functionalexigences),機能的命令(fu‐nctionalimperatives)を用いている。AGILを指すには,以上の用語を主として用いているが,このほかに機能的問題(functionalproblems)も用いられている。これらは同じものとみなして差し支えない(別)。本稿では,パーソンズは多用しないが,機能的要件(functionalrequisite)を用いる。さてこのように,パーソンズにおいては機能的要件を指す語すらも定まっていない「,にもかかわらず,機能的要件は構造機能主義ひいては機能主義の中心であり不可欠のものである,と一般に考えられている。ところがマートンは,機能的要件の概念は暖昧で,同語反復的・結果論的であるとして,むしろ排そうとすらしている。こうした食い違いはどこから生じるのであろうか。その原因は,「機能的要件」と「機能」の混同にあると脅えてよい。」
熊田俊郎 「関係概念としての 「機能」, 機能主義理論再構成のために」,90p
普遍的な機能的要件、特殊的な機能的要件
機能的要件は普遍的な場合と、特殊的な場合にわけることができる。
マートン以前では同一視される傾向があり、それがとくに「不可欠性の公準」に現れているという点である。そしてマートンはこの公準を批判している。
マートン以後でも、たとえばパーソンズ研究で知られている小室直樹さんも機能を機能的要件の略称としているらしい。熊田俊郎さんによるとこうした極端な見解を明示する人は少ないが、意図せずして両者を混同している人は多いという。
1:普遍的な機能的要件
どんな社会、集団の維持に対しても必要不可欠であるという機能が「普遍的な機能的必須要件」であり、これが機能的必須要件や機能的先行要件に当たる。用語的に先行要件は予備要件とほとんど同義だろう。
2:特殊的な機能的要件
ある特殊な社会(個人、集団)の維持に対してのみ必要不可欠という意味で、「特殊的な機能的特殊要件」がありうる。
極端な場合、たとえばある社会では政治(G)に関する機能がまったくなくても維持が可能だということはありえるかもしれない。その場合、A社会ではAGILが必要不可欠だ、B社会ではAILが必要不可欠だということがいえるわけである。しかしそれらは経験的に証明するべきだということになる。
普遍的機能要件の方は、パーソンズの機能必須要件などに近い。
しかしこの場合はトートロジー的になりがちだということもできる。たとえば社会を維持するために満たさなければならない機能が1つあるとする(4つあると論理的に構成できない理由はまずは置いておく)。その場合、「社会を維持するような機能」がなければ、「社会は維持されない」と言っていることになる。それはあたりまえだという話になる。
佐藤さんの言葉で言えば、「機能yをみたす/みたさない」は「社会Yが成立する/成立しない」と同義であり、機能という概念は必要なくなるという。「社会がある/ない」といえば済むからだ。
「たとえば小室は,「機能」を「機能的要件」の略称としている。さすがにこのような極端な見解を明示する者は少ないが,意図せずして両者を混同している場合は多い。」
熊田俊郎 「関係概念としての 「機能」, 機能主義理論再構成のために」,90p「では、一つの構造Xに一つの機能y0があるとすればいいのか。こうした単一機能仮説にすれば、たしかに矛盾はなくなるが、このときの『機能y0をみたす/みたさない』は『社会Yが成立する/しない』と同義になる。ならば、機能という概念は必要ない。『社会がある/ない』といえばすむからだ。したがって、機能要件の概念は矛盾をきたすか、冗長か、どちらかである。」
佐藤俊樹「社会学の方法」205P
結果論的に特定する機能的要件
たとえばアメリカの社会学者であるレヴィ(Marion Levy)の場合は機能要件を先験的にではなく後天的に、つまり経験的なデータにもとづいて探し出そうとした。
具体的には、ある社会が成立しなくなったような事実を見つけ出し、どの機能がなくなったから社会の維持が不可能となったのかを明らかにする、つまり「原因変数」をつきとめるという方法である。パーソンズのように演繹的にではなく、帰納的に推測する方法である。
マートンが述べていた「結果論的」というのはこのレヴィの方法にあてはまるのかもしれない。「結果として、この機能がこの社会の維持のために必須だったよね」と判断するわけである。
ただし、佐藤さんはレヴィが示している7または8つの機能要件は社会の成立と同義反復的になるという。また、レヴィのいう機能要件はマートンのいう「構造的制約」に近いという。さらに、ルーマンはレヴィの機能要件をパーソンズの同種のものとして扱っているという。このあたりの理解は灰色であるが、一旦灰色のままにしておく。
たとえばある機能が一切なくなったため、ある社会が維持できなくなったとする。
その場合、そのなくなった機能が「十分条件」であったとはいえるが、「必要十分条件」であったと特定できるのか。仮に言えたとしても、同義反復的、結果論的になってしまい、有益な分析にならないのではないか。そういう疑問が生じてくるわけである。
そもそも社会ごと、集団ごとに必要不可欠な機能があるとすれば、事前にその機能が何であるかを我々は知ることが難しくなる。つまり、それが消滅した後にしか知ることは出来ないのではないか。
結果論的に知ったものを一般化して、他の社会に当てはめることはできるのか。できたとして、そのようにして一般化、抽象化された機能要件は同義反復的にならないのだろうか。とはいえ、「似たような構造の社会」であった場合は「似たような機能的必要条件、十分条件」を近似的に推測できるのかもしれない。「歴史は繰り返す」というのと似ている。ただし「構造」を明晰に分析できればの話である。また、「近似」にすぎない理論に価値があるのか、そのせいで学問的発展が止まっていないかという問題もあるのかもしれない。現実の生活のさまざまな要求に応えようとする中で、逐一精密な論証など必要か、という疑問はある。国の命運を左右する一大事や学術的考察ならともかく、日常生活ではもっと「緩く」てもいいのではないかと思う。
「「行為システムに目標ないしは機能的要件を設定し、その目標を達成する、あるいは要件を充足するようなシステムの構造と過程とを特定化しようとする分析。例として、レヴィの『社会構造』(1952)やパーソンズのAGIL図式が挙げられる。」
「社会学小辞典」、108P」
「例えば、『AGILという四つがある』と頭のなかで考えるのではなく、経験的なデータから社会が成立しなくなった状態を同定した上で、その原因変数をつきとめる。つまり、何が成立しなくなったから社会が成立しなくなったかを帰納的に推測して、その『何』を機能要件だとする。第5章でみたように、こうした原因特定には多くの社会のデータが必要になるが、構造機能主義の時代には人類学の発達によって、非西欧の社会群についても知識が蓄積されてきた。『構造機能主義者』といわれる人びとのなかでも、レヴィらはこちらの方向で考えた。多数の社会の生成と消滅を調べて、機能要件の具体的な中身をデータからつきとめようとしたわけだ。」
佐藤俊樹「社会学の方法」201P「こうした考えにもとづき、レヴィらは機能要件として7または8つの条件を提示したが、これらは社会の成立と同義反復になる可能性があり、また、相互行為の定常的な形態とも重なる。つまり、これらは機能ではなく構造であり、マートンの機能主義における『構造的制約(structural constraint)』に近い。なお、ルーマンは『社会の社会』では、レヴィらの機能要件論をパーソンズと同種のものとしてあつかっている。」
佐藤俊樹「社会学の方法」221P
ペンパルによる目的論的機能主義批判
目的論的機能主義は論点先取りである
「機能必須要件」を経験的に証明する方法などあるのだろうか。
パーソンズのようにある種の演繹的な、近似モデルとしての導出、悪く言えば「論点先取」によってのみ機能必須要件を用いることができるのだろうか。
この問題はいわゆる「目的論的機能主義批判」と関わってくる。
1:パーソンズのような機能主義は「目的論的機能主義」だと、たとえば哲学者のペンペル(Carl Gustav Hempel)やネーゲル(Ernest Nagel,もしくはナーゲル)によって批判されている。彼らはいわゆる「論理実証主義」の立場の人物。
2:「目的論的機能主義」とは、AによってBが生じている場合、BにとってAが不可欠だと考える立場である。「AはBという機能をもつ」という言明は「Aが存在するのはBのためである」と言い換えられる。また、パーソンズは機能と因果とは異なる概念だと見なしているという。
3:しかし、AによってBが生じているとしても、そこから「BにとってAが不可欠だ」とは必ずしもいえない。
なぜなら、Bを生じさせるにはA以外にも、代替可能なものがありうるからである。これは項目だけではなく、項目が果たす機能にも可能性としては言いうるのである。したがって、AはBの十分条件であったとしても、必要条件とは言い切れない。つまり、目的論的機能主義の説明様式は十分条件と必要条件を混同している。そのような説明様式は「論点先取り」であると批判している。
「その背景には、機能と因果をめぐる科学論上の論争がある。社会科学で『機能』という語が広く使われるにつれて、C・ペンペルやE・ネーゲルといった科学哲学者たちによって、その説明様式が再検討されるようになった。大きな焦点になったのは、機能と因果の関係である。ラドクリフ・ブラウンやパーソンズの目的論的機能主義では、機能は因果とはちがう独自の説明概念だとされてきた。歴史的にはアリストテレスの目的因と作用因にまで遡る考え方だ。それに対して、ヘンペルやネーゲルは、機能とは因果の特定のあり方ではないか、と批判した。例えば、AによってBが生じているとしても、そこから『BにとってAが不可欠だ』とはいえない。この場合、AはBの十分条件であっても、必要条件ではない。Bを生じさせるA以外の要因は複数存在しうるからだ。目的論的機能主義の説明様式は、十分条件と必要条件を混同しているのではないか。」
佐藤俊樹『社会学の方法』,234P
設計者である神のみぞ知るのか
4:設計者が機能や項目に明確に目的をもたせる場合はありうるかもしれない。しかし、設計者でもないのにも関わらず簡単に必要条件を把握することは難しい。
使い古された言葉で言えば、「神(創造主)のみぞ知る」のだろう。キリスト教徒なら、人間という存在、社会という存在には「なんらかの目的」があると考えるのかもしれない。人間には計り知れない存在という意味でデュルケムやパーソンズの類似性が見えてくる。
個人的に、この設計者のくだりの理解が灰色である。例えば人体は酸素がなければ生命の維持が不可能になるということは設計者以外でもわかるのではないか、と素朴に思うとする。しかし酸素ではなくても実は◯◯でも生命が維持できることがわかった、というパターンの可能性は排除できない。あらゆるもので代替できないように設計者がシステムを作ることができるならば、目的論的機能主義に近づくのだろう。しかし多くのケースは設計者も意図しないところで別の項目でも代替できた、別の機能でも代替できた、という発見の要素が出てくるのではないだろうか。
たとえばある機能や項目がなくなったとたんに、自動的に社会にミサイルが降り注ぐように設計し、その維持が不可能になるなどの極端な机上のシミュレーションをしてみればわかりやすい。すくなくともそう設計された社会にとって、その機能は必要不可欠であるということになる。しかもそれが結果的にではなく、事前にわかる。
他の代わりうる機能及び項目は一切ないという前提があるからである。設計者ならそれがわかるかもしれないが、設計者でもないのに「わかったようなつもり」になると問題がでてきそうだ。「事前にある機能や項目が代替不可能だと設計者がどのようにして知ることができるのか」という素朴な疑問が私には生じてしまう。神のような完全能力者を想定すればそうかもしれないが、普通の人間が創る以上、機能の代替可能性は常にほとんどの場合つきまとってくる。たとえば先程のシュミレーションもゲームやプログラミングなら話は別だが、現実の人間生活に当てはめようとした場合、それでもやはり、人は生き残り、社会はなんとか維持されたという可能性は残る。
「こうした機能要件の観念は,機能主義や機能分析に対する方法的ないしは論理的な論争を引き起こしてきた。とりわけ,科学的方法としての健全さを問われることになった。それは,主に以下のような嫌疑であった。そもそも「システム」や「機能」という概念は科学的な地位を持ち得るのだろうか。それは生物有機体の単純な「引き写し」や類推であって,いわゆる「目的論」の誤謬に陥ってはいないだろうか。カール・ヘンペルは,科学哲学の立場から,機能分析を目的論の緩和された一種と見た。目的論は、一種の「論点先取」である。「AはBの機能を持つ」という言明は,「Aが存在するのは、Bのためである」という含意を持ち得る。「~のため」とはどんな事態を指すのだろうか。「心臓は血液循環を行っている」という表現は単なる記述であるが,「心臓は血液循環のために存在する」という表現はそうではない。機能という概念に含意されている「貢献」という意味合いは,そうした先取りされた「目的」を指すと解釈されかねない。設計者が存在するメカニズムは,そうした表現が可能である。複雑な部分/全体関係を持つ実体一有機体や社会一は,そうした意味での「機能的な記述」によって表現されることが多い」
大黒正伸「パーソンズと機能システム理論の課題-「構造一機能」理論に新しい意味を求めるための覚書」128-129P
機能とは因果関係の一つのあり方であるという新しい定義
5:マートンはペンペルやネーゲルの主張を取り入れ、機能主義を修正しようとしている。マートンは機能と因果は同じ概念だと見なしている。
正確に言えば、機能とは「因果関係の一つのあり方」にすぎないという。特にその因果関係が、ある結果に対して特別にプラスに作用する場合に「機能」と呼び、特別にマイナスに作用する場合に「逆機能」と呼ぶのである。
「マートンによる再検討は、こうした批判を全面的に取り込んでいる。三つの公準を仮説とすることで、マートンは機能主義を具体的な因果関係の分析に差し戻した。機能は特別な説明の概念や様式ではなく、因果の経路にすぎない。個々の具体的な事例では一体性や不可欠性がありうるとしても、一般的に成立するとはいえない。」
佐藤俊樹『社会学の方法』,234P「機能主義といわれる立場はこの三つの公準のどれかを前提にするが、実はどれも必ずしも成り立つとはいえない。つまり、これらは本来、自明の前提になるものではなく、成り立つかどうかを経験的に確認すべき仮説に過ぎない。そこから出発する必要がある、とマートンはいう。確認すべき、というのは言い換えれば、そういう因果関係がありうると考えられう、ということだ。パーソンズとマートンは『機能主義者』として一括りにされやすいが、論理構成が全くちがう。マートンにおいて、機能とは因果関係の一つのあり方にすぎない。それが特別な性質をもった場合に、特に『機能』と呼ぼう、と主張したのである。
佐藤俊樹『社会学の方法』,233-234P
【コラム】パーソンズによる機能要件の説明
機能要件を4つと先験的に仮定することは論理的に妥当か、それは近似的な分析か
この話(機能要件、機能予備要件)は簡単なようでなかなか難しい。マートンは「いずれ詳しく検討する機会がある」といって論文では後回しにしている。
たとえばパーソンズはAGIL(適応、目標達成、統合、潜在的パターン維持)という4つの機能要件を考え、一つでも欠けると社会の維持は不可能になると考えている。
もし機能要件が十分条件であるとすれば、AGIL以外の違う機能によっても、社会の維持は可能でありうるということになる。
もしそういう事例が見つかれば、有効な反証になるのかもしれない。
そもそもパーソンズの四要件は複雑なプロセスによって「演繹」されたものであるので、公理体系自体、諸前提に対する反証の形になるのかもしれない。
たとえば橋爪大三郎さんたちは「一つの構造に複数の機能必須要件という論理構成が成り立たない」と証明しているという。また、パーソンズのAGIL図式では複数の機能必須要件の集計をする方法は存在しないという。なぜそのような証明ができたのかは正直な話理解できていないので扱えない。アローの一般不可能性定理が関係してくるらしい。大澤真幸さんの説明では「グーチョキパーのどれが強いか3人で決めようとした場合」と似ているという。たしかに三つが平等の場合は、どれが強いかを合理的、民主的な形で決めるのは難しそうだ(あまり理解できていないが)。
それゆえに、一つの構造に一つの機能必須要件という形でしか矛盾なく論理構成できず、結局はトートロジー的な説明になるのである。したがって、機能必須要件という考え方は不必要(冗長)だという話になるわけである。確かにAGILが完全に同時に、対等に満たされている場合のみ社会が維持されると考えれば、それはもう「一つの機能」と呼ぶべき状態なのかもしれない。今経済がすごく活発だから宗教の貢献が小さくてもOK!、というような計算、集計がそれぞれが対等なためにできないというイメージだろうか。そのような割合、許容量は先験的にわかりうるものではない、演繹的に導出できるものではないということだろうか。
一方で、大澤さんはそうした批判は厳しすぎるとしている。4つの機能的要件は実際には全部対等という仮定で進められているが、実際はそうではないのではないかと述べている。
「ところが、システムの境界を働きかけの因果関係で定義した場合、機能分化仮説は成立しない。第五章の世界システム論のところでも出てきたように、相互行為(相互作用)を因果的な影響関係だとすれば、相互行為の全体のなかに独立した部分はありえない。相互行為の全体を一つのシステムだとすれば、その内部に部分システムが成立することはない。システムの境界は影響のおよぶ範囲、すなわち因果の果てにしかおけないからだ。それゆえ、AGILのように複数の機能があるとすれば、一つの構造Xの一つの状態xが複数の機能y1~y4をみたす/みたさないということになる。この場合、例えばy1がみたされ、y2がみたされないようなケースが必ず出てくる。なぜならば、もしy1~y4がつねに同時にみたされる/みされないとすれば、それは複数の機能ではなく、一つの機能になるからだ。この『y1がみたされ、y2がみたされない』ケースでは、状態xはどうなるのか。機能要件論では、これについて文字通り何もいえない。y1が70%みたされy2が80%みたされればよい、みたいに考えることもえきない。もしそういう合成ガアできるのならば、y1とy2は別々の機能ではなく、0.7*y1+0.8*y2で定義できる一つの機能になるからだ。」
佐藤俊樹「社会学の方法」,205P
「ともかく、この社会的選択理論という領域ではよく知られている定理を、そのまま、複数の機能的要件の評価を、合理的に――いわば民主的に――集計する方法は存在しない、ということになるのです。そうすると、機能要件から、社会構造を導き出すこともできません。講談社の例でいうと、利潤重視の要件、日本の言論文化への貢献という要件、社員の幸福度という要件、それぞれれの評価は異なるわけですから、会社の組織を決めるには、これらの異なる要件の要求を集計しなくてはならない。しかし、その集計の方法が存在しない。」
大澤真幸「社会学の方法」,420P
「ただ、橋爪さんたちの批判は、構造-機能分析にちょっと厳しい条件を課しすぎているかなと思います。つまり、機能的要件がたくさんあって、それが全部対等であって、集計することができないじゃないか、というのですが、社会システムの機能的要件は、優先順位が初めから決まっている可能性もあります。たとえば、会社でも、社員みんなが幸福な気分で働いているということと、収益を上げることを比べたら、後者のほうが優先されるでしょう・このように、機能的要件には実は初めからランキングがあるので、全部の機能的要件が対等だと考えた橋爪さんたちの議論は、やや構造-機能分析に対して厳しい」
大澤真幸「社会学史」422P
経験的に値を発見していくAGIL図式
大黒正伸さんによればパーソンズは「必ずしも仮説演繹的な順序論的説明命題を志したものではない」という。
パーソンズの「機能要件」という用語は誤解を招いていると言い、あたかもシステムがそれらのどれかを「完全に」満たさなければシステムの崩壊を招くかのように受けとめられてしまっているという。
パーソンズは4つの要件が「必須条件」であるというニュアンスを述べているが、その「値」を明示していないという。大黒さんによれば、4次元ベクトルはそれぞれ或る一定の値をアプリオリ(先験的)に設定できるものではないという。その値は、むしろ経験的に「発見」されるべきである。
追記:要するに、AGIL図式は近似、モデル、アナロジー、典型例にすぎないというわけである。ニュートンモデルではなく、メンデルモデルであり、定量的・連続的な尺度を求めてシステム理論を展開したのではないという。(2024/03/12)
これは先程の大澤真幸さんの「4つの要件が対等とは限らない」という話とつながる。
マートンもルーマンも、発見ツールとして用いるという視点がある。個人的に発見ツールとして用いることができるという点が「創造」の観点からは重要であり、面白いと感じる要素である。
とはいったものの、機能が0の場合はやはり社会の維持は不可能とみなされているというニュアンスは変わらないのではないか。いわば1から100までその程度があったとしても、0では社会が維持されない。社会ごとに1から100まで、経験的に発見していくというニュアンスである。
もしAGILの機能のひとつが0であったとしても、他にXという機能で代替できるという視点がない。論理的にはXの可能性があるといえたとしても、しかしそれでも、ではXという機能はなんなんだという話になる。
もしかしたら社会体系の範囲を狭めていけば、具体的に見つかりやすくなるのかもしれない。AGIL機能要件分析の場合はそれぞれの機能の範囲が抽象的で広すぎるため、ほとんどの機能がいずれかに収まってしまうようにも思えてしまう。
極論として抽象度を上げていけば、「社会を維持する機能が社会の維持には不可欠である」とトートロジー(同義反復)的に言えてしまう。それはそうだ、ということになってしまう。理論が役立たなければ意味がない、というのは言い過ぎなのかもしれない。しかし、「機能の代替」よりも「機能が果たす項目の代替」のほうが分析的に役立つ気がする。こういう項目のほうが全体の売上を伸ばせるとか、こういう行為のほうが人間関係をよくできるとか、こういう項目は代わりがききにくいというような、帰納的に得られる、あるいは法則として一般的に蓋然性を高めるような、そうした日常の機能分析にも使える比較の程度問題というような具体性も重要かもしれない。
なにか社会に役立つような社会学を目指すのならば、より具体的で実証的な理論のほうが良い気もする。このあたりはアメリカ型(サイエンティフィック)とヨーロッパ型(ヴィッセンシャフトリッヒ)の違いかもしれない。
その点、それらを架橋しようとしたマートンは凄い。
「ただ,パーソンズは機能要件を互いに無矛盾な順序的関係として構想したのではない。4機能は,当初はベイルズらの小集団実験の知見[Bales1953][Par-sons&Bales1953]から演繹され,後にはシステムの対環境軸(空間アナロジー)と道具的/達成的軸(時間アナロジー)との「直積」から構成された[Parsons1959]。こうした当初の素朴なモデル構成は,富永健一によれば「ベクトル」の論理に類似している[富永1991:27-28]。ベクトルは合成が可能ながらも、互いに独立した値と方向を持っている(図2参照)。パーソンズの4機能図式(AGIL)は必ずしも仮説演繹的な順序論的説明命題を志したものではない。むしろ,各機能の「不完全な」状態がノーマルなものと見られるような「多変量的」関係を指示しているように思われる。4次元ベクトルは,それぞれ或る一定の値をアプリオリに設定できるものではない。その値は,むしろ経験的に「発見」されるべきである。AGILそれぞれは,確かに評価的な志向を持っているとはいえ,「関数」や「命題」として展開されてはいなかった。とはいえ,機能要件という用語に対するパーソンズの言明は,やはり誤解を招く。あたかもシステムがそれらのどれかを「完全に」満たさなければシステムの崩壊を招くかのように受けとめられるからである。パーソンズは,確かにこれらの要件がシステム維持の「必要条件」であるというニュアンスを述べているものの,その正確な「値」を明示していない。「選言」であれ「ベクトル」であれ,システムの機能が一種の「評価」であることは,パーソンズの生涯をつうじて変わりなかった。行為の実体的な目的論をサイバネティクスによって棚上げにしても,彼のシステム理論の論理は評価的な前提を含んでいる。その代表的な例が「均衡(equilibrium)」という概念である。彼の均衡概念はかなりの部分「記述的」な水準にとどまっていて,説明的というよりはむしろ「発見的」な概念としての特徴が有力である[Bailey1984]。しかしそれは,彼のシステム観念が,完全には機械論ではないという事実を示してもいる。」
大黒正伸「パーソンズと機能システム理論の課題-「構造一機能」理論に新しい意味を求めるための覚書」,134,135P
「晩年にいたって、パーソンズははっきりと初期・中期の「物理学的」な連立方程式モデル(パーソンズは「ニュートン・モデル」と呼んだ)を放棄して「メンデル・モデル」と自ら呼んだ「生物学的」で情報制御的な強調を含むモデルへと志向していった[Parsons1977:133-134]。したがって,パーソンズはそもそも定量的・連続的な「尺度」を求めてシステム理論を展開したのではない。彼にとって,相互作用の「均衡」は,なんらかの具体的な経験からの一般化ではない[Parsons1951:481]。それは,いわば一種の「アナロジー」であり,定量的尺度よりはむしろ「発見的」な用具としてより良く用いることができる。ただ,たとえそれが「記述的」「発見的」な用途を想定していようとも,少なくとも「典型的な」システム状態を確定することは社会の科学的分析にとって必須であるように思われる。パーソンズは,そうしたシステム状態を確定的に述べていない。生物学からホメオスタシスの観念を借りてきたのも,そうしたシステム状態のアナロジーを一つ追加したにすぎない。ベイリーによれば,そもそも,均衡とホメオスタシスとが混同されることをキャノン自身は忌避していた[Baily1984:9]。」
大黒正伸「パーソンズと機能システム理論の課題-「構造一機能」理論に新しい意味を求めるための覚書」,139P
機能分析とイデオロギーの関係
Q そもそもイデオロギーとは?
一般に、「政治や社会のあるべき姿についての理念の体系」を意味する。
著名なイデオロギー的対立として資本主義と共産主義の対立、保守と革新、右派と左派などが挙げられる。カレーライスは給食で出されるべき、というようなものはイデオロギーと呼ぶには大仰すぎる気もする。上下関係ははっきりさせるべきだ、緩くてもいいというようなものも一種の対立かもしれない。あるいは朝食習慣は良いというデータを提示する売上を上げたい食品関連会社と、その逆に朝食習慣は悪いというデータを提示する売上を健康関連会社など、それぞれの価値に基づいて主張が対立するということはある。
社会学では、以前動画で扱ったように社会学者のカール・マンハイムがイデオロギー分析で知られている。
【基礎社会学第三十一回】カール・マンハイムの「イデオロギー」とはなにか
マンハイムはイデオロギー(視座構造)を「社会的存在に拘束された知識や世界観」という意味で用いる。
「社会的存在」とは階級、世代、生活圏、宗派、職業集団、学派などの多義的な用語である。
イデオロギーは社会的に共有された枠組みであり、「どのように事象を見て、その事象において何を把握し、どのような事態を思考のうちで構成するかという仕方」と考えればよりわかりやすい。
イデオロギーは部分的イデオロギーと全体的イデオロギーに区別され、さらに全体的イデオロギーは特殊的イデオロギーと普遍的イデオロギーに区別される。
イデオロギー的見方を敵対者に対してばかりでなく、自分自身にも適用する勇気をもち、いっさいの思想や観念を、それぞれの担い手の社会的存在位置と関連付けてイデオロギーとして捉える立場である普遍的イデオロギーが知識社会学の分析対象とされている。
マンハイムによると、「ユートピア」とは未来に準拠しており、現実を追い越してしまっている意識あるいは視座構造のことであるという。
ユートピアが「未来」に準拠しているのに対して、イデオロギーは「過去」に準拠しているという。未来においては科学が発達していて別の経済体制が可能になり、皆が自由に裕福に暮らせ、価値があると言い出したらユートピア性が高くみえるだろう。
「三つの公準」とイデオロギーの関係
【問題点】マートンによると、「三つの公準」を前提としてしまうと、機能分析が不可避的に一定のイデオロギー的かかわりあいをもってしまうという問題があるという。
そのため、機能分析はイデオロギー的に保守的であると批判されたりするわけである。
例えば、特に問題が大きい「不可欠性の公準」を前提としてしまうと、現状の反復的、標準化されたあらゆる社会的・文化的項目が社会の維持のために不可欠であるということになる。
だとすれば、たとえば資本主義社会では資本主義という項目や現在の政治体制が社会の維持のために機能しているという観点で肯定される。つまり、保守的イデオロギーとしてかかわりあいをもってしまう。もちろん、共産主義社会では同様に共産主義が肯定される。
「さらに、これら三つの公準が単独にまた相呼応して行われると、そこから、機能分析が不可避的に一定のイデオロギー的かかわりあいをもつという一般の非難が生じてくる。」
ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,78P「機能分析が不可避的にかかる誤謬のとりこになりやすいということは、まだ証明されてはいないが、不可欠性の公準を吟味した以上、この公準を採用すると、かようなイデオロギー的非難が容易に生じるであろうことは、十分に首肯できる。」
ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,81P
【改善点】「三つの公準」を不当な前提であると見なした場合の新しい機能分析の場合
(1)現存の社会構造の「機能(積極的機能、正機能、順機能)」の研究だけではなく、「逆機能」の研究をも含んでいる。
(2)また、それらの「社会構造の総結果の正味の差引勘定」が明らかに逆機能的である場合には、「強い不断の変化」が生じるという暫定的仮定を採用する。ただし、そうした「正味の差引勘定」をどのような基準において行うか、そもそも数量化できるかなどの課題は残っている。
(3)「強い不断の変化」が生じた場合、「適切な社会計画」によってこれを抑止しなければ、ある社会的・文化的項目の崩壊や根本的な社会変動が生じることもありうる。
単に「現存の社会の維持・存続」ばかりを分析するのが機能分析ではなく、変化や消滅も分析の対象であるという点がポイントになる。静態分析だけではなく、変動分析も行うというわけである。現状のある項目が、社会にとって貢献しているどころか、むしろ逆であるということを示すことは、保守的と呼ばせない意味合いをもっている。ただし、逆機能ばかりが偏って分析され、強調されれば、革新的という別のイデオロギー性を帯びてしまう。「資本主義は社会にとって悪だ、撤廃しろ」と安易に言う事は難しい。できるだけ中立的に分析を行うためにはどうすればいいのだろうか。どういうデータをとれば中立的だとみなされるのか。
「現存の所要その逆機能的結果として蓄積された社会構造の緊張や圧迫は、適切な社会計画によってこれを抑止したり制限したりしなければ、やがて制度の崩壊や根本的な社会変動をもたらすであろう。こうした変動が一定の、用意に見きわめられない限度を超えたばあいに、新しい社会体制が現れたと通常いわれる。」
ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,86-87P
機能分析はイデオロギーではなく、事実に対して忠実である
(1)機能分析の結果、ある時点においてある範囲の社会が高度に統合されていることが観察される場合がある。しかしこれは既成のイデオロギーに忠実に従った結果の観察ではなく、事実に忠実である。
たとえば資本主義という項目が社会の維持に対して機能を果たす項目の代えの効かなさが高い(相互依存の程度が高い)と分析したからといって、ただちにイデオロギー的に忠実だという帰結にはならない。それは事実の問題である。また、代えの効かなさは絶対的なものではなく、可能性としては代替可能な機能を果たす項目は残る。我々側の頭の能力にも依存するのだろう。
(2)既成のイデオロギーに反するような、逆の結果が観察されることもありうるが、これも優勢なイデオロギーに反対するようなイデオロギーに忠実というわけではなく、事実に忠実である。
たとえば共産主義国家において、共産主義という体制は社会の維持に貢献しない、むしろその逆であるという事実が観察される場合もありうる。その場合、代わりに資本主義という体制のほうがいいのではないか、と観察したとして、必ずしも資本主義というイデオロギー、たとえば西洋的なイデオロギーに忠実であるという結論にはならないだろう。
資本主義、共産主義以外の第三の経済体制を提案する能力がないと、どちらかしか提案できないだけかもしれない。共産主義がだめだから、資本主義「しか」ないだろう、という結論は安直すぎる。たとえば細かく見ていけばエスピン・アンデルセンのように福祉レジームが提案されるのかもしれない。
雑駁にいえば、共産(社会)主義的な保障も資本主義的な自由もいいとこ取りをするようなイメージである。経済体制は0か100かではない。あるいはその両者の体制ともまるで性質が違う体制もありうるだろう。
資本主義「でも」機能を果たせるだろう、という結論はそれが有益かどうか、生産的かどうかは置いておいて、事実であるという結論は出しうる。
共産主義「しか」体制を維持できないから、社会革新あるいは社会計画を推し進めるべきであるというのも安直すぎる(イデオロギー的である)。代替性を考える努力を放棄しているか、あるいは考え抜いた末に見つからないか、あるいは本当にないのか。ないことを証明するのはなかなか難しい。可能性としては常に残るのだろう。
(3)どちらか一方にのみ、任意に着目してしまうと分析結果が有益ではなくなってしまう。
どちらかのイデオロギーの維持および推進には有益ではありうるが、それは機能分析の本来の、固有の用途ではない。社会学者がある政治家に「私達の資本主義(あるいは資本主義的な政策)を正当化するような根拠を持ってきてくれ」と頼まれれば、そうした根拠をもってくることはできるのだろう。反対に、別の政治家に逆に「社会にとって悪であるような根拠をもってきてくれ」と頼まれれば、そうした要素を見つけ出すこともできるのかもしれない。あるいは、いわゆる「大衆」や一部の「評論家(あるいはインフルエンサー)」たちに受けるようなデータを持ち出して主張し、人気を獲得するような人もでてくるかもしれない。
(4)機能分析者が暗黙にあるいは公然と認めているような「価値」が研究課題の選択や説明に影響を及ぼすという事実は依然としてある。
これは社会学者であるマックス・ウェーバーの「価値と事実の峻別」に関わってくる。
「機能分析が人によって本来保守的とみられたり、また本来急進的とみられうるという事実は、それが本来そのどちらでもないことを示唆している。この事実は、機能分析が何ら本質的なイデオロギー的かかわりあいをもたないことを示唆している――もっとも、それには、他の社会学的分析と同様に、それぞれ多種多様なイデオロギー的価値を注ぎ込むことができるのだが――。」
ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,84P「だが、一定の観察結果においては、どのような社会構造も、その多数の人々または大部分の人々の主観的価値とその直面する客観的条件とにかなりうまく適合しているであろう。こうした理解は、既成のイデオロギーに忠実なわけではなく、事実に対して忠実なのである。」
ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,87P「だからといって、社会科学者の暗黙にあるいは公然と認めている価値が、彼自身の研究課題の選択やこの課題の説明方式、したがって彼自身の成果を特定の目的に役立たせる方向に固定する一助となるという重要な事実を否定しているかのように解してはならない。この叙述の意図は、次の点を主張しようとしているだけである。すなわち、機能分析は、少なくとも上述の論理が霊障しているように、どのイデオロギー的陣営にも本質的には係わり合いを持っていない。」
ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,92P
【コラム】ウェーバーの価値自由
(1)価値判断とは?→何であるべきかという観点から対象を評価すること。
(2)価値自由とは?→ひとりひとりの個人が、実践的価値と科学的事実認識とを、別種の精神活動として峻別した上、両者を緊張関係に置いて区別して堅持すること、自己制御すること。
※詳細は以前のウェーバーの記事を参照
【基礎社会学第四回】マックス・ウェーバーの価値判断や価値自由とははなにか?
(3)科学の権能とは?→「技術論的批判(手段の適応度の検証、随伴結果の予測)と「目的論的批判(目的の根底にある理念の解明、目的連関の形式論理的批判)
(4)神々の闘争(神々の争い)とは?→ある特定の価値のみが絶対的に正しいということはなく、それぞれの価値が互いに争い合っていること
ここでいう科学の権能は事実的な領域なのだろう。ただし、価値、要するになんらかのイデオロギーから一切自由になるということは難しい。社会科学において純粋に客観的な立場というものは歴史や文化を対象としている限り、存在し得ないとウェーバーは考える。
ウェーバーも「一切自由になるべきだ」とは述べていない。大事なのは、そうしたイデオロギーや価値をできるだけ「自覚」するべきだ、「区別」するべきだということである。無自覚なままに、自分の主張がまるで普遍的真理であるかのように述べると問題が生じることがある。
このように、機能分析であったとしてもなんらかの価値、イデオロギーにかかわらざるをえないこともある。
しかし、だからといって、機能分析はどのイデオロギーにも、どの価値にも「本質的」にはかかわりあいをもっていない。ツボの問題ではなく、ツボを使う側の人間の問題であるとマートンはいう。
例えば携帯電話は犯罪にも用いられるし、人助けにも用いられる。携帯電話自体が悪い、良いというのではなく、使う側の問題であり、あくまでも携帯電話は中立的なツールにすぎないという主張と似ている。クロスボウや銃、刀も使う側の問題であるが、使用が禁止されている。良い方向ではなく悪い方向に用いられる頻度など、それこそ「機能的結果の正負の差し引き勘定」が関係してくるのかもしれない。使う側の人間や、その社会ごとに、どうした用途として価値付けられるかが変わっていくイメージである。
・機能分析は、批判的に用いるならば、イデオロギー的諸体系に対して「中立的」であるという。
例えばあるフェミニストは、自分たちに有利なようにデータを解釈し、利用する。あるアンチフェミニストもまた、自分たちに有利なようにデータを解釈し、利用する。ウィーガンとそうではない人たちの関係もそうかもしれない。弁護士と検事は典型的な例だろう。
「以上の系統的な比較によれば、機能分析は、弁証法と同様に、必ずしも特殊的なイデオロギー的係わりあいを伴うものではないことが十分うかがわれよう。」
ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,88P
「そこで、機能主義者とマルクス主義者が袂を分かつのは、分析の論理よりも、むしろかような宗教の機能についての評価の点にある。そして、この評価が、イデオロギー的中身を機能主義のツボのなかに注ぎ込むのである。このツボ自身は、その中身にとって中立的であって、イデオロギー的な毒物の容器ともなれば、またイデオロギー的な美酒の容器ともなろう。」ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,91-92P
たとえば私が今「フェミニスト」というような対象を例示したことに、一切のイデオロギーがないかどうかと言われると不安である。特段、私はどちらが良い悪いという意見を明確にもっているわけではない。たまたま例として思いついたものである。しかし潜在的、暗黙的になんらかの評価を行っているのかもしれない。人間は通常、自分を拘束するイデオロギーに自覚的ではない。自分が女性か男性か、あるいは第三の性かによって、こうした評価も変わってくるのだろう。
研究などで「フェミニスト」を主題として分析する場合で、その分析内容はほとんど客観的結果のみを中立的に示したものであっても、主題とした時点で何らかの価値が関わっているのである。たとえば「フェミニスト」を主題とした分析には価値があるという評価が先にある。なぜアフリカではなく日本を分析とするのか、あなたは日本の社会こそ維持されるべきである、というイデオロギーをもっているのではないか。
観察者は大なり小なり、なんらかの価値をもって観察せざるをえない。例えば観察を依頼した人に対してなんらかの配慮を行ってしまうかもしれない。先程のケースにおいてフェミニストと言われる人たちに依頼されて研究したとすれば、より差はわかりやすいかもしれない。たとえば範囲を意図的に狭くとって結果をとってみるといった可能性もある。これは経済学者がグローバリズムは良いとも悪いとも、どちらともとれるようなデータをいくらでももってこれるのと似ている。
自分がイデオロギー的関わり合いをもっていることを自覚すれば、より中立的に関わろうと努力することは可能であり、イデオロギー的関わり合いを明示して分析することも可能であろう。
保守的イデオロギー、急進的イデオロギー
どの客観的結果(機能)に重きを置くのか
(1)機能分析が機能的結果(積極的機能的結果)だけに焦点を置いてしまうと、極端な保守的イデオロギーに傾いてしまう。
たとえば該当する社会体系の経済が資本主義なら、資本主義の肯定、保守に傾くというわけである。
(2)機能分析が逆機能的結果だけに焦点を置いてしまうと、極端な急進的イデオロギーに傾いてしまう。
たとえば現状の経済が資本主義なら、資本主義の否定、革新に傾く。
(3)(積極的)機能と逆機能の両方の機能的諸結果の正味の差引勘定を考慮することが必要になる。
ただし、その考慮が難しいという問題がある。社会にはさまざまな社会的・文化的な項目がある。そのどれかがマイナスに傾いていたとしても、それを補うだけのプラスがあれば社会は維持されると考えることもできる。たとえばサッカーの試合である選手が退場になったとしても、必ずしも試合に負けるとは限らない。
負けるかどうかは、そのチームの力量、許容量次第である(構造的脈絡、構造的拘束)。この場合も、数量化できるのかという問題がある。サッカーの試合のほうが社会全体よりも数量化しやすいかもしれない。
しかしより複雑な問題として、ある項目とある項目は相互依存関係にある場合が多い。パーソンズで言えば「機能連関」の問題である。たとえば経済制度と宗教的形態は、どちらかが消滅すれば、もう一方も消滅し、またそのもう一方が消滅すれば、新たな項目も消滅するという連鎖反応を考えることもできる。
機能分析は分析の範囲を社会全体に広げていくと、とても複雑化してくる。
たとえばサッカーの試合の場合も、ある選手Aとある選手Bの相互依存関係というケースが考えられるだろう。この選手との連携がチームには大事である、というようなケースである。B選手が抜けた途端、A選手の貢献度も下がり、A選手が抜けた途端、C選手の・・というように連鎖していく。
そうした相互依存関係を含めて数量化していく必要もあるのかもしれない。単純な個人の能力や生産力だけでは測れないものがある。要素だけではなく関係を重視していく、というのはジンメルやフッサールでも重要だった。機能分析でももちろん、関係が重視されていくのである。
「機能分析が機能的結果だけに焦点をおくにつれて、それは、極端な保守的イデオロギーに傾き、それが逆機能的結果だけに焦点をおくにつれて、極端な急進的ユートピアに傾くのである。『本質的には』それはどちらでもない。」
ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,86P「機能分析は、批判的にこれを改めるなら、主なイデオロギー的諸体系に対して中立的である。この範囲内で、しかもただこの限られた意味において、機能分析は、自然科学の理論や用具と同様であって、これらはしばしば当の科学者の意図しない目的のために互いに正反対の立場にあるグループのどちらにもひとしく利用されうるものである。」
ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,88P
機能主義者とマルクス主義者の相違点
1:機能分析も、(マルクス主義者が使う)弁証法もどちらも特殊なイデオロギー的係わりあいを伴うものではなく、イデオロギー的には中立であるという。
2:ただし、「古典的な三つの不当な公準」を前提とした機能主義者はイデオロギー的に保守に傾き、分析結果について「評価(価値づけ)」を行うマルクス主義者は革新(急進)に傾く。
3:機能主義者とマルクス主義者の相違点は、分析の論理よりも、機能についての「評価」の点にあるという。
評価が機能分析という壺の中に注ぎ込まれると、イデオロギーな色彩を強く帯びていくのである。
「以上の系統的な比較によれば、機能分析は、弁証法と同様に、必ずしも特殊的なイデオロギー的係わりあいを伴うものではないことが十分うかがわれよう。」
ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,88P
「そこで、機能主義者とマルクス主義者が袂を分かつのは、分析の論理よりも、むしろかような宗教の機能についての評価の点にある。そして、この評価が、イデオロギー的中身を機能主義のツボのなかに注ぎ込むのである。このツボ自身は、その中身にとって中立的であって、イデオロギー的な毒物の容器ともなれば、またイデオロギー的な美酒の容器ともなろう。」ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,91-92P
トヨタの社長がしたという「ロバと老夫婦の話」
1:老夫がロバに乗って老婆が歩いていると「威張った老夫だ」と批判される。
2:老婆がロバに乗って老夫が歩いていると「あの老夫は老婆に頭が上がらないんだ」と批判される。
3:最後に老夫婦が揃ってロバに乗っていると「二人も乗って、ロバがかわいそうだ」と批判される。
それぞれのイデオロギーから、ある事実に対して良い、悪いと「評価」するような傾向が見られる。
フェミニストから見れば「男性が威張っている」という悪い評価、アンチフェミニストから見れば「女性に頭が上がらないダサい男性」というような悪い評価がされる。
動物愛護団体からすれば「二人も乗って、ロバがかわいそうだ」というような評価がされるかもしれない。
機能分析者は結果を淡々と提示すれば良いのだろうか(そもそもどの事象に注目するか、ある事象をデータと解釈するかにも価値が関係してきてしまうのだが)。
二人が乗った場合、ロバの寿命が短くなる。ロバがかわいそうだといって乗られなくなった場合、必要とされなくなり、ロバの個体数がそもそも減ってしまうかもしれない。ロバの個体数の維持と、ロバの待遇のどちらが優先されるべきなのか。さまざまな観点(結果)を持ち出すことは可能だろう。しかし、何が良い、悪いというのは神々の闘争の問題と関わってきてしまう。
トロッコ問題などの頭が痛くなるような話とも極端な話をすれば関わってくるのだろう。1人の友人と10人の他人、10人の日本人と100人の外国人、どちらかしか助けられない場合、どちらを助けるのか。機能分析は様々な観点を、できるだけ中立的に事実を提示することはできるだろう。しかし最後に決断するのは我々である。ウェーバーの言葉で言えば、自分の「良心」と「知性」と「心」が責任を負うべき事柄であり、各人が一生かけて色々と経験を積みながら解決してゆくべき問題である。
新しい機能分析の範例(お手本、枠組み)の提示
生理学におけるキャノンの「手続きの論理」
【問題点】社会学では不揃い(バラバラ)に採択された「概念」や「手続き」や「分析の仕方」がある。この事実は社会学では実験作業の機会が少ないという理由だけでは説明できない。
【改善点】ほかの学問を検討して、社会学の機能分析にとって「有効な方法論的モデル」を構築する。ただし、他の学問の特殊な概念や技術を採用するわけではなく、「方法論的な枠組み」を検討して取り入れるという意味である。単なるアナロジーやホモロジーではない。
キャノン(Walter Bradford Cannon)はアメリカの生理学者。有機体が生命を維持するために自律系や内分泌系の働きを介して体内平衡状態を維持するというホメオスタシスの考えを提唱した人物。
【生理学における手続きの論理1】:有機体の一定の機能的要件(有機体が存続し、または或る程度有効に働くために充足せねばならない要件)を確定する。
【生理学における手続きの論理2】:それらの機能的要件を「正常な」ばあいに通例充たすところの装置(構造や過程)について具体的詳細に記述する。
【生理学における手続きの論理3】:それらの機能的要件を通例充たす機構が破壊されたり、あるいは十分に機能しないことがあるばあい、観察者は、この必要な機能を果たす「補償的機構(もしあれば)」を見つけ出す必要を機敏に認知する。
【生理学における手続きの論理4】:機能を果たす手段となる装置だけでなく、機能的要件の該当する構造の単位について詳細に説明する。
「こうしたアプローチの論理をもっと一般的に述べるならば、次のような相関連する手続きの諸段階が判明する。まず第一に、有機体の一定の機能的要件、すなわち有機体が存続し、または或る程度有効にはたらくために充足せねばならない要件を確定する。第二に、これらの要件を『正常な』ばあいに通例充たすところの装置(構造や過程)について具体的詳細に記述する。第三に、これらの要件を通例充たす機構が破壊されたり、あるいは十分に機能しないことがあるばあい、観察者は、この必要な機能を果たす補償的機構(もしあれば)を見つけ出す必要を機敏に看取する。第四に、以上述べたなかに暗黙に含まれていることだが、機能を果たす手段となる装置だけでなく、機能的要件の該当する構造の単位について詳細に説明する。」
ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,97P
【コラム】ベイトソンによる「緩い思考」と「厳密な思考」
アナロジー(類比)やホモロジー(相同)の話を聞くと、人類学者であるグレゴリー・ベイトソンの思考の話を思い出す。
ベイトソンによれば、自分の考えを整理するために他の分野の理論を持ち出すことは適切なことだという。しかし、抽象のレベルを間違えるとよくないという。
マートンと同じように、ベイトソンも思考の題材を理解するのに、他の分野での題材の分析の方法を参照するのは良いとう。
しかし「他の学問の特殊な概念」をそのまま取り入れると問題が生じる。ベイトソンは自分の内側から出してきた概念を理解するときには、類比の相手も同等の抽象レベルに求めなくてはいけないという。
たとえば「河は土手を築き、土手は河を導く」という考えが「エートスは文化構造を築き上げ、文化構造に導かれる」に類比的だと考え、それがあたかも「文化のはたらきの真の姿を把握したような気持ちになってしまう」のはよくないという。
初期の機能分析でも同じような風潮があるかもしれない。たとえば酸素を取り入れる機能が停止した場合、人間の体を維持することはできなくなる。それと同じように、社会もまた、酸素という概念に当てはまるような実態があるはずだと考えていく。しかし生物における酸素と、社会の法制度は論理階系や抽象度が同じだろうか。
ベイトソンはそうした比喩やアナロジー、ホモロジーといったような思考の使い方に注意を払っている。
しかし同時に、そうしたある分野から「大胆なアナロジー」を見つけ、自分の分野に適応させようとすることの重要さも指摘する。このような思考を「ゆるい思考」とベイトソンは呼ぶ。厳密な「表現」にすぐ固めるのではなく、ある漠然とした概念を漠然とした「表現」のままにしておくというのも「ゆるい思考」のコツだという。
緩い思考による作業:あやふやな基盤の上に理論を構築していくプロセス。「ゆるい表現」はそれらが指している概念が曖昧であり、それらがさらに「分析が必要」であることを意識させるために重要だという。極端な場合「それ」と表現しておくことも可能なのだろう。
厳密な思考による作業:より厳密な思考を行いながら、すでにでき上がっている建築物の足場を補強するプロセス。
学者はこの2種類の間を揺れながら進んでいくものだという。緩い思考だけではなく、「厳密な思考」も重要だという。さらに、学問全体を見てみると、最初にゆるい思考を始めた人と厳密な思考を始めた人間は別な場合が多いという。物理学では厳密化させていくまで数世紀かかっているという。ベイトソンによると、フロイトなどの精神分析学の分野では今でも、「エゴ」や「イド」などの「ゆるい概念」がまるで具象性・実体性をもつように扱われたままであり、厳密化されることを拒んでいる風潮があるという。
こうした2種類の思考の過程はマートンが従来の「ゆるい概念」を「厳密な概念」へと整理していく過程と似ている。またそれと同時に、マートンは体系や構造、制度や文化といった用語を「ゆるく」使う思考もある。武術でも体を緩めておくことで強い、厳しいパンチを打てるというが、似ている気がする。
私はマートンの文章を読んでいて、従来の人類学における機能分析者は詰めが甘い集団だな、というような印象を受けていた。
しかしよく考えると、そうした「ゆるい」分析や概念のおかげで、マートンが厳密化する機会を得たのであり、機能分析は発展してきたともいえる。何か「新しいもの」はゆるい分析から、メタファーやアナロジー、ホモロジーから始まるという観点は「創造法」の分野でも重要になる。いわゆる「アブダクション」の領域である。
ルーマンも生物学からアナロジー的な発想で社会システム論を発展させていったことからも、「ゆるい」分析は社会学にとってとても重要だということが分かる。
ただし、それらを「厳密な分析」へとコツコツと整地していくスキルも重要になる。そしてその「お手本」としてマートンの機能分析の厳密化は参考になるのだろう。
「河は土手を築き、土手は河を導く。エートスは文化構造をを築き上げ、文化構造に導かれる。フィジカルな世界に類比を求めた点は、観察データの分析のために生物の世界を覗いたときと同じですが、今度は自分で作り出した概念を分析する目的で、それをやることになったわけです。これはいただけません。もちろん、自分が生み出した考えを整理するために、物理学の次元の理論を持ち出すのは、適切なことだと思います。やってはいけないのは、抽象のレベルを間違えること。思考の題材を理解するのに、他の分野での題材の分析の方法を参照するのは良い。しかし自分の内側から出してきた概念を理解するときには、類比の相手も同等の抽象レベルに求めなくてはいけません。それなのにわたしは、河と土手との比喩が気に入ったあまり、その類比を本気で推し進めてしまったのです。」
グレゴリー・ベイトソン『精神の生態学』,144p
「ここでちょっと脱線して、私が重宝している思考と用語法のコツについてお話しておきましょう。ある漠然とした概念が現れて、それを厳密に言い固めてしまうのはまだ早いと思うとき、意味のしっかりとした用語をいきなり与えて事態を間違った方向へ持っていかないように、ある『ゆるい』表現をその概念にくっつけておくのです。そのときわたしは、できるだけ簡潔で具象的で口語的な語――一般的にいってラテン語系ではなく、土着のアングロ=サクソン語――を使います。文化の”stugg(もと・じ)”とか、文化の”bit(一片)”とか、文化の”feel(手触り、感じ)”とか言うわけです。これらの簡単なアングロ=サクソン語は、わたしには独特の響きというか『手ざわり』がありまして、それを使っている間は、それが指している概念が曖昧であり、さらに分析が必要だということを意識させられる。――まあ、ハンカチを結んでおくトリックのようなものですが、これの利点はちょっと強引にいけば、ハンカチをそのまま他の目的に使えるという点にあります。その曖昧な概念を非常に重要な緩められた思考の過程で使い続けていくことができる。自分がやっているのは『ゆるい』思考だということを意識したままで。」
グレゴリー・ベイトソン『精神の生態学』,144p「実際、学問というものは、こんなふうに二種類の思考の間を揺れながら進んでいくものではないでしょうか。…まず『ゆるい』思考があり、あやふやな基盤の上に理論を構築していく作業がある。つぎにより厳密な思考を行いながら、すでにでき上がっている建築物の足場を補強するプロセスがくる。…また、学問の進展プロセスでは、最初に『ゆるい』思考を始めた人間と、それを厳密化していく人間が別だという点も違っています。」
グレゴリー・ベイトソン『精神の生態学』,147p
範例を導入する目的
paradigm(パラダイム)が範例と訳されている。
日本語における範例は「模範とすべき例」という意味であり、いわゆる見本である。
トーマス・クーンのいわゆるパラダイムシフトにおけるパラダイムの意味合いとも通じるものがあるかもしれない。クーンの場合は「専門的科学者の共同体を支配し、かつ広く受け入れられているものの見方、問い方、解き方の総体」と定義されている。
- 【目的1】適切で成果の多い機能分析を行うために系統的に整理された暫定的指針を与えるため。
- 【目的2】機能分析の根底にある公準や(しばしば暗黙の)仮定を直接導き出すため。
- 【目的3】種々の機能分析の持つ純粋に科学的な含蓄だけではなく、その政治的、ときにはイデオロギー的係わりあいを社会学者が敏感に捉えるため。
範例は主に9つの概念の利用方法と2つの「9つの概念を利用する場合の問題点」にまとめることができる。
多くの場合、「基礎的設問」も同時に提示されている。個人的にこの基礎的設問はとても重要だと思う。基礎的設問は言い換えれば問題を発見することであるといえる。こうした問いに真摯に答えていくことで、より分析の精度が増していくのだろう。逃げれば逃げるほど、不透明になっていく。もちろん日常生活ですぐに解決策を出さなければいけない場合には、ある程度の「妥協」が必要かもしれないが、しかしそれは「妥協」にすぎないことを明確に意識する必要がある。
「第一の重要な目的は、適切で成果の多い機能分析を行うために系統的に整理された暫定的指針を与えることである。…第二に、この範例は、機能分析の根底にある公準や(しばしば暗黙の)仮定を直接導き出すためのものである。…第三に、この範例は、種々の機能分析の持つ純粋に科学的な含蓄だけではなく、その政治的、ときにはイデオロギー的係わりあいを社会学者が敏感に捉えることをめざしている。」
ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,106-107P
【1】機能分析の対象の使用ガイド
【範例1】:機能分析の対象は「標準化した項目」であり、その項目を確定すること。
【基礎的設問】:一定の項目についての体系的な機能分析を行おうとすれば、その観察結果の中に何を入れねばならないか。
基礎的設問に関しては後の「記述的調書に取り入れるべき事項」で部分的に取り扱う。
※たった一回のみというような非反復的、ランダム的な項目は主要な分析の対象とならないだろう。包括的に、「標準化された社会的または文化的項目」と呼ばれることがある。
例:社会的役割、制度的型式、社会過程、文化型式、文化的に型式化された情緒、社会規範、集団組織、社会統制の手段などの諸項目。
「分析の対象は、標準化した(すなわち、型式化され、反復される)項目をなすということが基礎要件である。たとえば、社会的役割、制度的型式、社会過程、文化型式、文化的に型式化された情緒、社会規範、集団組織、社会構造、社会統制の手段などの諸項目がこれである。」
ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,101P
「一定の項目についての体系的な機能分析を行おうとすれば、その観察結果の中に何を入れねばならないか。」ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,101P
【2】主観的意向の使用ガイド
【範例2】:「主観的意向(動機・目的)」を仮定するか明らかにし、使用する。
【基礎的設問】:「どのようなタイプの分析では、観察された動機づけをデータ、すなわち与件とみてよいか。またどのような分析のばあいには、それ自身問題とすべき性質のもの、いいかえれば、他のデータから導き出されるべきものとみなしてよかろうか」。
仮定するという場合は本人に聞けない場合であり、観察者が観察者の基準で当事者の動機を仮定するケースだろう。本人に聞ける場合は、それはそれとして記述するのだと考える(ただし本人が意図を明確に言語化できるとは限らないことは想定しておくべきだろう)。
さらに重要な注意として、「主観的意向」を「客観的な結果(機能・逆機能)」と混同してはならないという。
「何らかの点で、機能分析は、社会体系のなかに含まれる諸個人の動機づけの概念をたえず仮定し、あるいは明示的にそれを用いる。」
ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,101P
「どのようなタイプの分析では、観察された動機づけをデータ、すなわち与件とみてよいか、またどのような分析のばあいには、それ自身問題とすべき性質のもの、いいかえれば、他のデータから導き出されるべきものとみなしてよかろうか。」ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,101P
【3】客観的結果(機能の種類)の使用ガイド
範例、及び設問
【範例3】:「(積極的)機能」ばかりに社会学的観察を限定する傾向は好ましくない。様々な機能を区別して全て考えるべき。
【基礎的設問】:これまで潜在的だった機能を顕在的に転化すると、どのような効果があるか
「どのようなばあいであれ、一つの項目は機能的結果と同時に逆機能的結果をもつので、総結果の正味の差引勘定を秤量する基準を建てねばならない困難かつ重要な問題が生じる。」
ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,102P
「(1)社会学的項目が、それを含めた社会的体系または文化体系に対して果たす積極的貢献に社会学的観察を限定する傾向。(2)動機という主観的範疇と機能という客観的範疇を混同する傾向がこれである。」
ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,101P「これまで潜在的だった機能を顕在的に転化すると、どのような効果があるか。」
ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,102P
機能とはなにか、逆機能とはなにか、没機能とはなにか、意味
機能:一定の体系の適応ないし調整を促す観察結果。マートン以外の人は正機能、順機能と呼ぶことがある。
逆機能:一定の体系の適応ないし調整を減ずる観察結果。
没機能:当面の体系にとって機能的に無関連なもの。別の体系に機能していたとしてもある体系に限定すれば極めて関わりが薄いというものはありえるだろう。
重要なのは、それらの適応を促す、あるいは減ずる程度は高度とは限らず、一定の範囲があるという点である。たとえば社会的残存(伝統)の場合はその程度が低いケースが多いといえる。極端なケースではシャツのボタンなどが挙げられている。
また、没機能は範囲を絞ると無関連だと判定できるというように、観察者の分析において無関連なものだと整理できるものである。たとえば社会的残存も没機能として分類する場合もありうるだろう。
「機能とは、一定の体系の適応ないし調整を促す観察結果であり、逆機能とは、この体系の適応ないし調整を減ずる観察結果である。また没機能的結果の経験的可能性もあって、それは当面の体系にとって無関連なものにすぎない。」
ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,102P「かつて,社会学者マートンは「機能」や「機能分析」の意味を規定するべく,さまざまな用法の比較をこころみ,それをとおして,日常生活や他の学術分野における機能概念や機能分析の方法の多様で曖昧な使用法から距離を置いた,社会学的に厳密な「機能」の定義を導き出した12)。それにより,機能とは「ある特定のシステムの適応ないし調整を促進する観察結果」であるとされた。しかるに,この定義そのものは,たしかに日常的用法に比して限定され厳密化されてはいるものの,さほど特殊な定義ともいえない。同じ意味内容を,日常的な表現でいいかえれば,「ある特定の観点から役立つ(効果的)とみなされるはたらき」にほかならないからである。」
村田裕志「社会学的機能主義系 「社会システム論」 の視角 (I)」,107P
顕在的機能、潜在的機能とはなにか、意味
顕在的機能:機能であって、体系の参与者により意図され認知されたもの。逆機能の場合は顕在的逆機能と呼ぶべきものになるのだろう。
潜在的機能:機能であって、体系の参与者により意図されず認知されないもの。逆機能の場合は潜在的逆機能とでもいうべきもの。
顕在(けんざい)的機能と潜在的機能の詳細な説明は次回行う予定であるが、概念がシンプルなのでこの時点でも違和感なく理解できる。マートンは「社会学者が社会研究に対して重要な貢献をなしうるのは、とりわけ潜在的機能の分析である」と主張している。通常「見過ごされがち」なものを明らかにするからである。常識とは違う視点をもたらす創造的な側面がある。
図で整理するとこうなるだろう。
なお、順機能という用語については後述する。
「顕在的機能とは、一定の体系の調整ないし適応に貢献する客観的結果であって、しかもこの体系の参与者により意図され認知されたものである。これと相関連して、潜在的機能とは、意図されず、認知されないものである。」
ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,102P
【コラム】レヴィによる「順機能と逆機能」の区別
順機能はアメリカの社会学者であるレヴィ(Marion Levy)による述語である。基本的にはマートンの「機能」と同義であり、一定の体系の適応ないし調整を促す観察結果を意味する。
マートンの場合は機能が機能と逆機能に分かれるというようにややこしい説明になってしまうが、レヴィの場合は機能が順機能と逆機能に分かれるという対称的で明晰な説明になる。
ただし、佐藤俊樹さんによれば、マートンの定義はレヴィよりも明晰ではないが自然であり、独自の良さがあるという。なぜなら、社会事象を観察する過程としては、機能/逆機能の方が自然だからであるという。
我々はたいていの場合、(1)ある事象をみつける、(2)なぜこうなっているのかと考える、(3)何かの役に立っているからだと考える(機能があるのではないか)、(4)それだけではないはずだと(逆機能もあるのではないか)考え直すという順番で考えていくからである。
佐藤さんによれば、レヴィは構造機能主義者であり、マートンは構造機能主義者ではないという。はじめから正機能、逆機能があると決めつけるやりかたよりも、経験的に順番に発見していくという姿勢が見えるというわけである。
「それだけではないはずだ」という視点は創造にとって本当に重要である。
ある順機能があれば、逆機能の可能性、潜在的機能の可能性、等価的な機能の可能性、等価的な項目の可能性、等価的な構造の可能性などが見えてくる。
そうした「コンティンジェンシー(偶有性)」と呼ばれる「他でもありえた」という視点が創造につながりうるのである。
「他でも使えた」という視点はアナロジーなどの「ゆるい思考」につながる。また、「他でも共通していた」と考えれば、ベイトソンの「自然の枠組み」やアレグザンダーの「ある一つの中心的な価値基準」という共通するパターンへもつながっていく。
だからこそ、ある学問は他の分野を学んでいる人にとっても、あるいは学問とは関わりないビジネスマンであっても、主婦であっても、子供であっても、すべての人に有益性をもたしうるのである。社会学、とくに機能等価主義はこの「それだけではないはずだ」に気づかせるという意味で特に面白い学問である。
「マートンの思考は独自な何かを零から組み立てるよりも、既存の概念や方法を再検討し改良するのに向いていたようだ。その改良も徹底的とはいいがたい。例えば顕在的/潜在的機能では、レヴィが指摘したように、『顕在的』が『意図された』と『認知された』の両方の意味で使われている。機能/逆機能の定義にも問題がある。まず、概念として対称的でない。そのため現在では『順機能(eufunctional)/逆機能(dysfunctional)』というレヴィの述語のほうがよく使われる。また、全体を存続させる/させないは経験的には判定できないことが置い。それゆえ現実には、特定の価値観から正/負の価値がある、といった基準にならざるをえない。そうした点で、マートンの定式化や概念には中途半端なところがある。機能主義の再検討でも、マートンが詰め切らなかった部分をより徹底的に考えることで、ルーマンは新たな定式化に成功した。それでもマートンの方法や概念には、独自の良さがある。適度に自然な抽象化になっているので使いやすいのだ。機能/逆機能でいえば、レヴィの順機能/逆機能の方が対称的で明晰だが、社会事象を観察する過程としては、機能/逆機能の方が自然である。私たちはふつう、ある事象をみつける→『なぜこうなっているのか』と考える→『何かの役に立っているからだ』と考える→『それだけではないはずだと考え直す』という順番で考えていくからだ。」
佐藤俊樹『社会学の方法』,257-258P
【4】機能のはたらく単位の使用ガイド
範例4
【範例4】:一定の項目が特定の機能を及ぼす或る範囲の諸単位を考慮するべきである。
問題は、或る範囲とは具体的にどういうものが挙げられるかという点である。
まず前提として、「社会全体(全体の社会体系)」というような広すぎる範囲の分析では困難が生じる。次に、「部分の社会体系」というようなより限定された範囲に絞るという方法が考えられる。たとえば日本という社会の、ある村だけに限定するなど。そのように限定することによって、ある項目は社会体系Aには機能的だが、社会体系Bには逆機能的であるといった分析が可能になる。分析の焦点を社会体系の包括的な全体ではなく、いわば、「特定の部分的な全体」に当てるということにポイントがある。
ただし、佐藤俊樹さんによれば、「全体を存続させる/させない」は(全体の範囲を絞ってある部分に限定したとしても)経験的には判定できないことが多いそうだ。現実には「特定の価値観からみて正/負の価値がある」といった基準にならざるをえないという。
「われわれは、『社会』全体に対して果たしている機能だけに分析を限定するばあいに生じる難点を述べた。というのは、或る諸項目は或る個人や下位集団にとっては機能的であるが、他の個人や下位集団にとっては逆機能的だからである。したがって、一定の項目が特定の機能を及ぼす或る範囲の諸単位――さまざまな地位にある諸個人、下位集団、包括的な社会体系および文化体系――を考察せねばならない。(述語として、それぞれ心理的機能、集団的機能、社会的機能、文化的機能などの諸概念をあてることができる)」
ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,102-103P
心理的機能、集団的機能、社会的機能、文化的機能とは
マートンは一定の項目が特定の機能を及ぼす或る範囲の諸単位(さまざまな地位にある諸個人、下位集団、包括的な社会体系および文化体系)に対応する述語として「心理的機能、集団的機能、社会的機能、文化的機能」を当てることができるという。
諸個人の場合は心理的機能、集団の場合は集団的機能、文化体系の場合は文化的機能である。社会体系の場合は「社会的機能」と呼ぶことになるのだろう。
このように分類すると少し混乱してくる。たとえば「動機の記述は心理的機能を説明する助けとなり、社会的機能に示唆的だ」という言い方をマートンはする。動機は機能ではないのだから、心理的機能でもない。
では心理的機能とはなにか。マートンは社会的機能を「観察しうる客観的結果を指すもの」と定義づけていたが、これは社会的機能の定義ではなく、どちらかといえば機能の定義である。社会的機能の定義は「一定の社会体系という範囲において観察しうる客観的結果」ということになる。ここでいう「一定の」は変化しにくい(constant)、反復的なという意味合いだろう。
心理的機能は「一定の個人(あるいはパーソナリティシステム)の範囲において観察しうる客観的結果」と定義づけることができるかもしれない。
集団の場合は「一定の集団において・・・」と定義できるだろうし、文化の場合は「一定の文化体系において・・・」と定義できるだろう。ところで、集団と体系の違いについて私は理解が灰色である。おそらく、より広義の、包括的な体系に関しては「体系」と呼び、その中に位置する部分的に切り取られた体系を「集団」と呼ぶのだろう。包括的体系(体系)と個別的体系(集団)というように区別できるのかもしれない。であるとすれば、集団的機能は社会的機能に含まれる概念なのかもしれない。
社会学は「社会的機能」のみに取り組むべきだ、とマートンは述べていない。むしろ、さまざまな範囲の機能を考察せねばならないとマートンは述べている。このさまざまな範囲の機能が「社会学的機能」とでも総称しうるものなのだろう。
たとえばマートンは「社会的項目や文化的項目が社会学的機能を果たしている」という言い方をしている。社会システムは文化システムに影響するし、文化システムは社会システムに影響を与えているのである。そう考えると、多様な体系を分析するべきだといえる。ただし、それらの関係をマートンは系統立てて扱っていないようにみえる。
ざっくり図にするとこのようなイメージになるのだろう。ただし、他の学問の機能と社会学の機能を厳密に分けることは難しいのかもしれない。ただし社会学の主要な分析範囲は「社会的機能」だということになるのだろう。「細胞が意図したとか目的をもつ」とは言いにくいように、「人間の行為・役割・コミュニケーション」を要素とするかどうかで区別できるのかもしれない。
それらの要素の相互行為としてシステムが有り、それらのシステムにとっての機能が主な社会学的機能の射程になるといえる。たとえば生物学が扱うような生物システムは社会学の主要な分析対象ではないが、しかしその分析を助けるものであり、社会システムとも関わり合っているものである。
マートンは「体系」に関する分析を避けている(言及が極めて少ない)。抽象的すぎて実証できそうにないものは意図的に避けているのだろう。とはいえ、ある時代、ある社会にしか通用しない特定の集団というよりも、どの社会、どの時代においてもある程度は共通するような(より)一般的な集団の分析が中範囲の分析になる。特定の体系Aを分析し、また体系Bを分析し、それらを包括するような法則ないし集団を見つけ出すことができるというように、特定の時代や特定の集団の分析が不必要というわけではない。それらを通して、より一般的な理論を帰納的、経験的に構築していくのである。
ある時代のある村のある集団にしか当てはまらないような結果に留まる機能分析は汎用性が低い(その集団にとっては有益かもしれないが)。たとえばマートンの「準拠集団の理論」は多くの集団に当てはまりやすい、汎用性の高い分析といえる。
マートンは「さまざまな地位にある諸個人、下位集団、包括的な社会体系および文化体系」という具体例を挙げている。ここでいう範囲は「社会体系」だけではなく、「文化体系」なども意味するということになる。文化体系における相互作用の要素は一体なんだろうか。社会体系と文化体系はどのような関連をもつのか。
社会システムの中に文化システムがあるわけではないのだろう。社会の中に、社会システムと文化システムがあるということになるのか。では「文化形態」という項目と「文化システム」はどのように区別されるのか。文化システムのなかでも恒常的な相互作用をもつものないしそれらを生み出すものを文化構造ないし文化形態と呼ぶのか。こうした厳密な「体系分析」に関する理解をもっと深めなければならないのだろう。私は体系(システム)に関する理解が灰色である。
たとえばパーソンズの場合はこのような文化システムと社会システムの関係が語られていた。
【5】機能的要件の使用ガイド
範例5,基礎的設問
【範例5】:特定可能ならば、機能的要件を経験的に確定する。
【基礎的設問】:厳密な実験作業の不可能な状況において「機能的要件」というような変数の妥当性を確定するためには何が必要であるか。
「機能的要件」は曖昧に使われがちであるため、そのタイプを特殊的なのか、普遍的なのかを先験的にではなく経験的に確定させる必要があるという。
もしそうした手続きが可能であり、機能的要件を特定できるならば、そうしたものの記述をする必要がある。正直、この範例はいまいちよくわからない。「可能ならば、機能的要件を確定せよ」というニュアンスだろう。それが可能かどうかはケースバイケースといったところだろうか。
例えば結果論的に、ある社会体系が消滅したケースを観察して、ある社会的機能がなくなったから消滅した、というような推測などが考えられる。ただしこの場合でも、原因を探す難しさは残るだろう。
「あらゆる機能分析の根底には、暗黙的であれ明示的であれ、当該体系の機能的要件という概念がある。…以上には、さまざまなタイプの機能的要件(普遍的と特殊的)を確定するとか、これらの要件の過程を検証する手続きなどという困難な問題が含まれている。」
ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,103P
「厳密な実験作業の不可能な状況において『機能的要件』というような変数の妥当性を確定するためには何が必要であるか。」
ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,103P
【思考実験】機能的要件を特定する方法はあるのか
- 【思考実験】項目xが機能αを果たし、また項目xのみが果たすことができると仮定する(機能的非代替項目)。なお、話を単純化させるため項目xは他の機能をもたないと仮定する。
- (1)機能αが欠如した際にある社会体系の維持が不可能になった場合、少なくとも「十分条件」だったと推測することができる。
- (2)もし機能αが欠如した際にある社会体系の維持が可能であった場合、少なくとも機能αは「必要条件」ではないと推測することができる。
(1)の場合、「十分条件」であるだけではなく「必要条件」だといえるだろうか。少なくともその社会では代えの効く機能がなかったという意味で、結果論的に必要条件、つまり必要十分条件だった、不可欠だったといえるのかもしれない。代えが効くかどうかはその社会が消滅しなければ確定させることが難しいのかもしれない。消滅する前は、他の機能でも代替しうる、他の項目でも代替しうるという「可能性」を残す限り、「十分条件」に留まるからだ。
他の社会では法による別の機能βや文化による別の機能γでも代えが効いたというのはありえるだろう。したがって、その社会ごとの構造的制約によって、どの機能が代えの効かない、他の機能によって補い難いものかが変わってくる。これがなければ社会の維持は難しいだろう、と「必要要件」をその社会が消滅する前に単に推測することは可能だが、その「妥当性」はどれほどだろうか。
さらに機能αに0~100の数値を設定してみると、より複雑になっていく。この数値を設置するということは、存続(1)or消滅(0)ではなく、なんらかの「評価」を含むことになるのだろう。観察者が10だな、50だな、といったように数量化して評価していくのである。
たとえば機能αが80の場合は、機能βという別の貢献のおかげでなんとか社会が維持されているとする。たとえば宗教的つながりが弱まっても法的な拘束がなんとかあるから維持されているなど。しかし機能αが60の場合は機能βではもはや補えない到達点に達してしまい、社会が維持できないということはあるだろう。この補える、補えないの範囲、変数が社会の構造ごとに異なるという話である。
しかし、このように機能を考えていくと、「αが70%みたされβが80%満たされれば良い」というように合成論的に機能を考えていくことになる。佐藤さんいわく「それらは別々の機能ではなく、「0.7×α+0.8×β」で定義できる一つの関数(機能)になってしまう」という。
α、β、γ…とそれぞれの連関、相互依存を全て把握していくとすれば、結局大きな関数になってしまい、「社会を維持させる機能」がなければ、「社会の維持が不可能になる」というようなトートロジーになりかねないのだろうか。そもそもそれぞれの社会構造の相互依存を全て、とは言わないまでも主要なものを把握することは可能か。
分析では他の機能との相互関係、依存関係も考慮する必要がある。たとえば宗教が完全になくなったと仮定すれば、法律にも、経済にもなにかしらの影響が出てくるだろう。
宗教的な抑えが弱まることで法律をまもらなくなり、誠実なやり取りが減り経済が機能しなくなり、さらに宗教的な抑えが弱まるなどの可能性も考えられる。このようなネガティブなフィードバックもあれば、逆にポジティブなフィードバックもあるかもしれない。社会体系は複雑である。集団というように単位を狭めたとしても、なお複雑である。特に、「社会体系の維持の必要条件や十分条件」はとても複雑である。
未だ消滅していない社会体系を分析するに当たっては、ある機能が必要条件(必要十分要件)であるとは判断しにくいということになり、十分条件に過ぎない可能性を常に考慮しておく必要がある。
また、それと同時に、十分条件でもない可能性を考慮しておく必要がある。「必要条件も十分条件も結果論的にしか正確にはわからない」ということになるのかもしれない。
極論としてその体系が消滅するまでそれらはわからず、消滅していたとしても特定することは難しいだろう。高木英至さんによれば、そうした機能要件の確定方法は「存続-淘汰論」と呼ばれ、全体社会に適用するには難があるが、企業のような法人には適用可能だという。他にもフィードバックの存在を仮定する「因果制御論」や「評価制御論」があるという(私は両者の理解が灰色である)。いずれも原因を結果(存続、評価)によって説明する方式であるという。
「機能分析は効果分析の一種であり、因果関係の確定を課題とする。だが機能理論は,〔4〕や〔7〕の定式を用いるにもかかわらず,その因果関係の方向を言わば「逆転」させねばならない。何故なら,社会学的興味をそそるのは社会状態(x1,…,。xn),即ち原因の成立の方であり,機能理論はその原因を結果(存続や評価)によって説明しようとするからである。機能理論が目的論と呼ばれる所以がこれである。私見では,このような説明を可能にする形式は少なくとも三つある。それらを(I)存続一淘汰論,(II)因果的制御論,そして(III)評価制御論と呼んでおこう。」
高木英至「機能理論は不可能か?」,145P
「存続淘汰論は機能理論に伝統的に潜在する説明形式である(Homans,1964:965-6;Moore,1963,邦訳:11;Schwartz,1955:424)。むろんこの説を全体社会に適用するには難がある(Homans,1964,1969)。しかし企業のような法人には十分適用可能である。(ii)因果的制御論。先述の〔4〕の下で,社会はS'(S’∈S,S≠∅)に留まる傾向があり,外乱によってSから逸脱すれば再びSに引き戻すような因果的作用があると考える。この説は,以下の点線のような(言わば「負」の)フィードバックの存在を仮定する。」
高木英至「機能理論は不可能か?」,145P
「評価制御論。先述の[6]のごとく社会は結果を評価するとし,評価値をより高めるよう社会が社会状態に作用する(社会状態を選択する)と仮定する。」
高木英至「機能理論は不可能か?」,145P
体系の存続条件としての機能以外にも用いる、小さくて有益な分析について
エアコンでも炬燵でも機能的に等価だ、と単に発見していくだけなら話が別かもしれない。たとえば宮台真司さんはルーマンの機能分析を「機能的説明を放棄し、機能的等価領域の記述だけで充分な認識利得を得られるとする反実証主義的な試みである」と述べていたらしい。これはこれで面白い。たしかに機能的に等価なものや逆機能、潜在的機能を単に記述するだけでも何らかの利益が得られるのかもしれない。
佐藤さんが言っていたように「全体を存続させる/させない」は経験的に判断しがたいものであり、「特定の価値観からみて正負の価値がある」という機能が暫定的に想定されるのではないか(正直この想定も理解が灰色だが)。
マートンは「一定の体系の存続の条件として機能が結果論的に使われがち」というニュアンスを述べているので、マートン自身もなにかしら自覚しているのだろう。
機能分析はこうした体系の存続条件としての機能以外も扱うのである。たとえば「ある項目とある項目が機能的に等価である」という分析は必ずしも体系の存続条件とは直結させる必要はないだろう。マートンは「公的な支援機関と街の顔役たちの口利きが機能的等価である」とか、「公的支援には名誉を失わせる(潜在的)逆機能がある」とか、そうした機能分析を行っている。支援機関が社会の維持につながっているかどうかは一旦隅に置いてもいいのかもしれない(十分条件か、必要条件かという程度を隅に置く)。
これらの具体的な項目が、ある体系の存続の条件であるかどうかはわからないとしても、これらの研究には(観察者の何らかの観点からして)何らかの価値がありそうだということは(何となく)わかる。「なるほど、そういう面もあるのか」、「この方法でもいいのか」、「そうした逆機能、潜在的機能があるならこう改善したらもっと良いかもしれない」というような発見がある。
ごちゃごちゃと頭を使うよりも限定的に分かる範囲でやりくりしていく。そうしたイメージがマートンの機能分析なのかもしれない。目的論的機能分析というよりは因果分析であり、いわゆる「効果の分析」に近いのかもしれない(とはいえマートンにも単なる効果の分析にとどまらない要素、アナロジー的、目的論的な要素が少しはあるからこそ、ギデンズに批判されていたのだろう。体系や構造の分析をマートンは曖昧にしていたため、そこが分かりにくい)。
「体系の存続」に関しても、そこまで厳密にこだわらなくとも、なんとなくこれがなければだめだろう、これが十分条件だろうというような推測がなにかしら生活において有益になることはあると個人的には思う。
パーソンズで言えば「近似的」に、なんとなくわかればいいということになる。特に創造の分野ではそこまで厳密性にこだわらない、ゆるい思考が先にあるからだ。
同じような構造の社会ではある項目、ある機能が欠如したため社会が崩壊した(ようになんとなく見えた)、それゆえにこの現存の社会でも不可欠ないし十分条件である可能性が高いと(なんとなく)推測することはできる。ベイトソンのダブルバインドのケースも、同じような家族構造が同じような精神病をもたらしうるというイメージだった。
企業において、家族において、そうした身近なケースでも先例を参考にすることはあるだろう。たとえば浮気のトラブルで家庭が崩壊した、資金繰りがうまくいかずに会社が崩壊した、社員のやりがいがなくなり会社が崩壊した、そうした先例は「なんとなく」見つけることができる。もちろん演繹的に使うことはできないが、構造が似ているケースを見つけてなにかしらの「ヒント」に用いることはできるだろう。ある項目やそれが果たす機能がなんとなく大事だと目安がつけば、できるだけ絶やさないようにする努力はできる。トライアンドエラーでできるだけいい方向へと導くものを探していく。
「Luhmann機能分析については、彼が複要件理論を採用することによって理論要件を軽減させている(三谷2006)、また、機能的説明を放棄し、機能的等価領域の記述だけで充分な認識利得を得られるとする「反実証主義j的な試みである(宮台1987)という指摘がある。つまり、LuhmannはHempelらの批判をかわすために、理論要件を軽減させているというのである。Luhmannは、機能理論が因果論的な特定を理論要件とすることによってHempelらの批判を招いていると指摘し、特定の領域に関する説明である理論と、理論の論理一貫性や経験的妥当性を吟味するための諸規則の総体である方法とを区別する。このことによって、理論的成果が否定されたとしてもそれを導いた方法論は直接的に否定されえず、また、理論も完全なる一般性・抽象性を要件とする必要性がなくなるとして(Luhmann1970=1983:14-8)、確かに理論要件を軽減させるように論じている。」
畠山洋輔「社会学的機能分析の機能一一Luhmann機能分析による経験的研究の可能性一一」,49p
政治や経済、生活の場ではすぐに何かしらの「決断」をする必要がある
しかし学問において、社会科学と名乗る以上は論理的にしっかりと構築する必要があり、そうした隙の多い曖昧で不確実で、抽象的で非実証的でアドホックな分析は価値が薄いということになるのだろう。たとえば論文でそのような隙の多い分析をするわけにはいかないだろう。それこそ「あなたの主観」ということになりかねない。学問はなんらかの「客観的可能性(シャンス)」を高める独自の方法をいくつか提供してくれている。その方法のひとつとして、この動画の後半で「差異法」を扱う。
ウェーバーにおける「限定的な知」のように、わからない点はわからない、わかる点はわかると明確に区別するのは重要である。しかし政治や経済、生活の場では何かしらの「決断」はつきものであり、確実な証拠が揃うまで決断を待ってくれと悠長なことを言えない場面が多い。その決断の資料としてゆるい資料も脇に置いてあって良いのだと思う。
マートンは「一定の体系の存続の条件として機能が結果論的に使われがち」というニュアンスを述べているので、マートン自身もなにかしら自覚しているのだろう。
機能分析はこうした体系の存続条件としての機能以外も扱うのである。たとえば「ある項目とある項目が機能的に等価である」という分析は必ずしも体系の存続条件とは直結していないだろう。
マートンは「公的な支援機関と街の顔役たちの口利きが機能的等価である」とか、「公的支援には名誉を失わせる逆機能がある」とか、そうした機能分析を行っている。
これらの具体的な項目が、ある体系の存続の条件であるかどうかはわからないとしても、これらの研究には何らかの価値がありそうだということはわかる。「なるほど、そういう面もあるのか」、「この方法でもいいのか」というような発見がある。
【6】社会的メカニズムの使用ガイド
【範例6】:「機能遂行の通路となる社会的メカニズム(社会的機構)」の具体的かつ詳細な説明(明細化)が必要になる。例:役割の分担、制度的諸請求の隔離、価値の階統的配列、社会的分業、儀礼及び儀式上の制定など
【基礎的設問】:社会的メカニズムのはたらきを識別するばあいにどのような方法論的諸問題が生じるだろうか。
社会的メカニズム(社会的機構)という用語もなかなか理解が怪しい。
例えばマートンは「社会機構としての宗教」という言い方、「必要な機能を果たす補償的機構」という言い方をする。
つまり、「社会的メカニズム」は機能ではなく、「項目」に分類されるということになる。項目は主に制度や宗教といったように名詞的に使われがちであるが、それらの概念のうち、より機能の貢献を果たす過程、仕組みなどに焦点を当てたものが「社会的メカニズム」なのだろう。
たとえば「血液は酸素を供給する機能をもつ」と述べることができる。
しかしそれだけでは「メカニズム」を述べていない。
例えば「呼吸によって肺から吸い込んだ酸素が血液中の赤血球に結合し、ヘモグロビンと酸素が結合することで、酸素化ヘモグロビンが形成され…」というように具体的に「過程、経路」を述べることが重要だというわけである。エアコンが室温を一定に保つ仕組みもわかりやすいかもしれない。
「社会学における機能分析には、生理学や心理学のような他の諸学科のそれと同様に、特定の機能を遂行するメカニズムの『具体的かつ詳細な』説明を必要とする。これは、心理的メカニズムではなく、社会的メカニズムを指すのである(たとえば、役割の分担、制度的諸請求の隔離、価値の階統的配列、社会的分業、儀礼及び儀式上の制定など)。」
ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,103P
「こうした社会的メカニズムのはたらきを識別するばあいにどのような方法論的諸問題が生じるだろうか。」ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,103P
【コラム】ウェーバーの理解社会学
単に「結果」だけを述べればいいというわけではない。ただし、社会学の場合は生物学ほどメカニズムを実証的に述べることが困難という問題がある。
たとえば社会学者のマックス・ウェーバーの『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』は宗教がどのように経済に影響を与えたかという経路を詳細に述べているいい例だろう。
例えば宗教が集団の維持に役立つと単に言ったところで具体性、有益性に欠けるだろう。それだけでは宗教の貢献を「理解」したとはいえない。
仮に具体的、詳細にメカニズムを述べて理解できたとしても、それが「説明」になっているかは別の問題である。
明証的な解明(理解)ができただけで経験的妥当性をもつ因果的解明(説明)になっているとは限らない。明証的に解明できることと、因果的に説明できることがセットになってはじめて理解社会学となる。別の言い方をすれば「意味適合的」かつ「因果適合的」をめざす科学である。
プロテスタンティズムがなかったとしたら、資本主義は発展しなかったと因果適合的に証明することは難しいのである。これは「機能要件や代替不可能な項目」を確定する方法が難しいというマートンの視点と重なってくる。しかしそうした確定ができなくてもプロ倫が評価されたように、意味適合的な理解に留まるとしても何らかの有益性があるのだろう。
具体的にどの要素が、どのような経路を経て集団の維持に貢献しているのかを「理解」し、「説明」する必要がある。ウェーバーが言っていたように、(理解)社会学は「理解」と「説明」がセットになっている。
例えばギデンズは「意図するとせざるとにかかわらず、機能主義では行為の結果は行為を導く機能ととらえられてしまうため、結果論的解釈とならざるをえない」という。一見個人の意図や動機、目的を重視する、理解する立場に見える「方法論的個人主義的」であっても、それらを軽視しているように見るのかもしれない。
ウェーバーも当事者の動機よりは、観察者が観察者の基準で捉えた一般的な動機、誇張的な理念型をより重視しているように見える。マートンも個人的な動機の記述の必要性を述べるが、しかしそれらは理解の補助にすぎない位置づけのように見える。
ではギデンズはそうした人間の主体性を重視するような理論(構造化理論)をどのように構築したのか、気になるところである。
ウェーバーについては以下の記事を主に参照。
【基礎社会学第二十二回】マックス・ウェーバーの「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」とはなにか
【基礎社会学第十六回】マックス・ウェーバーの「理解社会学」とはなにか
【7】機能的選択項(等価項,代要項)の使用ガイド
【範例7】:「機能的選択項(等価項,代用項)の概念を考慮し、また機能的要件を果たしうる諸項目の「可能な差異の範囲」に注意を向ける必要がある。
【基礎的設問】:社会学では多くの場合、機能的選択項(等価項,代用項)を科学的に証明することが難しい。どのような手続きによってそれらが可能になるか。
※このガイドの説明については他で扱っているので省略する。
「これは、さしあたって、機能的要件を果たしうる諸項目の可能な差異の範囲に注意を集中させるものである。」
ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,104P
「機能的選択項と断言されたもの(alleged functional alternative)の等価性を科学的に証明するには、理想的には、厳密な実験作業を必要とするから、大規模な社会学的状況では、このことがしばし実験不可能なので、どのような実行な可能な研究手続が実験の論理にもっとも近いであろうか。」ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,104P
【8】構造的脈絡(構造的拘束)の使用ガイド
範例8,設問
【範例8】:社会構造において特定の機能を果たしうる諸項目の変異する範囲は無制限ではなく、「構造的脈絡(構造的拘束)」に制限されるという点を考慮する必要がある。
【基礎的設問】:一定の構造的脈絡は、機能的要件を有効に充足しうる諸項目の変異する範囲をどの程度まで制限するであろうか。どういう条件のもとであるなら、広範囲にわたるどの選択項でも無差別に機能を充足しうる領域があるだろうか。
つまり、その範囲をできるだけ明確に、実証的に検討、確定する必要がある。そのためには社会構造を把握する必要があるだろう。
「社会構造において特定の機能を果たしうる諸項目の変異する範囲は、無制限ではない。…社会構造の諸要素の相互依存は、変動の事実上の可能性や機能的選択項を制限する。構造的拘束の概念は、社会構造の領域では、ゴールデンワイザーのもっとも広範な領域で持ちいた『可能性制限の原理』(principle of limited possibilities)に該当する。相互依存とこれに伴う構造的抑制との重要性を理解しないと、ユートピア的思考に陥り、社会体系の一定の諸要素が、その体系の他の諸要素に影響を与えずに除去できるかのように暗黙に仮定してしまう結果となる。」
ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,104P
「一定の構造的脈絡は、機能的要件を有効に充足しうる諸項目の変異する範囲をどの程度まで制限するであろうか。どういう条件のもとであるなら、広範囲にわたるどの選択項でも無差別に機能を充足しうる領域があるだろうか。」ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,104P
ゴールデンワイザーによる「可能性の原理」とはなにか
可能性制限の原理:「現実に人間がもちうる目的・手段・材料はそれほど多くなく、新しい要素を作る可能性は無限には存在しない。それゆえに、それぞれの人々が個別、独自に工夫を重ねたとしても、結果として、文化要素が似てくる」ということ(平野健一郎さんの説明)。
・ゴールデンワイザーはアメリカの文化人類学者で「可能性制限の原理」を主張したと言われている。
当時の人類学理論に優勢であった演繹的な文化・社会進化論を批判し、実態調査による帰納的、分析的、伝播論的研究に貢献した人物である。
人類学者のゴールデンワイザーにより考案されたものであり、当時の伝搬主義に反論するために用いられた。全く接点がない国同士でも、近似した文化を形成しうるのであり、必ずしも一方が一方に伝搬して形成されるものではない。すくなくとも、伝搬せずに形成されたという可能性を完全には排除できない。これは、いわゆる「ゴルトン問題と観察の右方(右側)打ち切り」とも関連してくるのだろう。佐藤俊樹さんによれば、「西洋から世界中に近代資本主義が伝搬したその事実によって、西洋以外の社会では近代資本主義が内在的に生まれたかどうかの観測は右方打ち切りになる」という。要するに、伝搬なしに考案された可能性もあるが、証明が難しく、分析が打ち切られるのである。
「構造的拘束の概念は社会構造の領域では、もっとも広範な領域で用いた可能制限の原理に該当する」とマートンはいう。いきなり法律を宗教で代替したり、宗教を法律で代替するということは難しいといえる。例え抽象的には同じ項目でも、具体的に共産主義と資本主義、キリスト教と仏教というように代替性を考えていくこともできる。どの程度代替可能かは、その社会の構造次第ということになるのだろう。しかし多くの社会では宗教や法律が国の維持に貢献しているという点ではたしかに似ている。社会体系を維持する方法は無限ではなく、その項目も一定のものに限られてくるのだろう。
宗教、法律、経済、家族や文化といったような我々が一般的に考案するような社会を維持する「大きな項目」以外にも、もっと「大きな項目」があるかもしれない。しかしそうした代替可能な項目は無限にあるわけではなく、ある程度制限される。また、その制限の程度も、その国ごと、集団ごとの構造次第によるというわけである。小さな、具体的な項目へと絞っていけばなおさら、代替不可能な範囲が狭まっていくだろう。
たとえばバチカンのように宗教があらゆる項目に相互依存関係をもっているような社会体系では、いきなり経済が宗教にとって代わったり、法律がとって代わったりすることは特に困難であると推測できる。
逆に日本のような宗教的な要素が小さい国の場合は、仮に仏教やキリスト教のような宗教が全てなくなったとしても、ある程度はそれらが果たしていた機能は法律や他の項目で代わりがきくのかもしれないと推測できる。ただし、機能的選択項で述べられていたように、ではほんとうに代わりが効くのか、効かないのかと科学的に実証することは難しい(極論、実際に無くさないとわからない)。曖昧に、漠然と、「~かもしれない」と述べるだけでは有益性が低いだろう。社会学はそうした実証が難しいにしても、せめて「理解」を促すように、詳細にデータを集めて推論する努力は必要なのかもしれない。
そもそも「社会構造」を把握することがまず難しい。構造を把握できなければ、構造的拘束も把握できないだろう。構造とはその社会の安定した相互依存関係を指す。「安定している」かどうか、どのような基準をもって我々は判断できるのだろうか。これはパーソンズの「パターン変数」の確定にも関わってくる問題である。パターン変数は構造分析とも呼ばれていた。
これらはいわゆる「社会調査」の分野で具体的に関わってくるのだろう。サンプルの取り方や統計の技術等が関わってくる。マートンで「機能分析の指針」を学び、統計学などで具体的な「機能分析の技法」を煮詰めていくのだろう。もちろん、社会体系の範囲を狭めれば狭めるほど、その体系内の社会構造の把握はより容易になるといえる。
「アメリカの文化人類学者。ロシアに生れ,1900年アメリカに移住。F.ボアズに人類学を学んだのち,コロンビア大学で人類学を講じる。当時の人類学理論に優勢であった演繹的な文化・社会進化論を批判し,実態調査による帰納的,分析的,伝播論的研究に貢献(→可能性制限の原理)。」
(ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典)
「文化の諸要素がその目的,機能に従って一定の形態的可能性に制限を与えられること。アメリカの人類学者A.ゴールデンワイザーにより,伝播主義批判の立場から指摘された(→伝播論)。しかし,この原理の適用されにくい文化要素も多くあり,今日ではほとんど認められていない。」
(ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典)「しかし、厳復は東西文化の異質性ばかりでなく、人類文化の類似性にも着目していた。「西学も人間の事であって鬼神の事ではない。人問の事である以上、その民が智であれ愚であれ、日用常行には互いに暗合する妙な道がある」と述べている㈱。平野健一郎は「時間的・空間的に伝播が起こったとはとても考えられない二地点の問で、ある文化要素が類似している」現象を、「文化の類似性」と称し、「可能性制限の原理」(Princip1e of limited possiblities)と「収敏の原理」(Principle of convergence)によって説明する。それによれば、「可能性制限の原理」とは「現実に人間がもちうる目的・手段・材料はそれほど多くなく、新しい要素を作る可能性は無限には存在しない。それぞれの人々が個別、独自に工夫を重ねたとしても、結果として、文化要素が似てくる」ということである。「収斂の原理」とは「それぞれ独自に始まった生活の工夫が、最初は違った文化要素の形をしていても、工夫が重ねられる時間の経過とともに、次第に類似あるいは同一の文化要素になっていく経緯」である。類似性の発生は人類の必要性と事物の機能に共通性があるからである。」
區建英「異文化の衝突と融合,中国近代文化に関する厳復の模索」,75-76P
【9】社会構造の動態と変動の使用ガイド
【範例9】:機能分析は社会構造の「静態」だけではなく「動態」や「変動」を考慮するべきであり、特に変動のアプローチとして「逆機能」の概念を利用する方法が有効である。なぜなら、逆機能は圧迫や緊張を生じさせ、構造の不安定さを生み出すからである。
【基礎的設問】:どのような手続きを用いたら、社会学者は、社会体系におけるひずみや圧迫の蓄積をもっとも十分に測定することが可能であろうか。構造的脈絡を捉えることによって、社会学者は社会変動のもっともありそうな方向をどの程度まで予測することが可能であろうか。
こうした問題は、いわゆる社会計画、社会政策に関わってくるのだろう。
労働者の環境が劣悪すぎると、反社会的な行動へと至るかもしれない。差別問題や教育問題など、多岐にわたえるといえる。日本では官僚政治と言われるように、具体的な政策はほとんど官僚が決めているのだろう。国家公務員試験で社会学の項目のテストがあるのも頷ける。実際に政策を決める際に有用だからである。
社会学の本には理論の説明がほとんどないものがある。昔は日本に限定した「社会運動、格差、文化、家族、医療」など具体的な問題や統計、データの説明ばかりで退屈だと思っていた(ギデンズの分厚い『社会学』の本もそうした傾向がある)。とにかく理論を学ぶほうが大事であり、かっこいいと感じていた。
しかし、実際に理論を使おうとすればこうした具体的な社会構造の状況を理解する必要が出てくるのである。また、実際に使うに耐えない理論があるというものもわかってくる。マートンの機能分析を学ぶことで何かが何かに接続した感じがする。
「逆機能の概念は、構造的平面におけるひずみ、圧迫、緊張の概念を含むが、それは動態や変動の研究に対する分析的アプローチを与えるものである。特定の構造にともなう逆機能が構造の不安定を生じない限度は、どのくらいであろうか。ひずみや圧迫の蓄積は、これらを解消すると思われる方向へ変動を促すであろうか。」
ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,105p
「機能分析車の間には社会的均衡の概念に対する関心が広くゆきわたっているために、社会的不均衡の現象から注意がそらされているのであろうか。どのような手続きを用いたら、社会学者は、社会体系におけるひずみや圧迫の蓄積をもっとも十分に測定することが可能であろうか。構造的脈絡を捉えることによって、社会学者は社会変動のもっともありうべき方向をどの程度まで予測することが可能であろうか。」
ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,105P
【10】機能分析の検証のガイド
【範例10】:実験作業の論理に最も近い社会学的な分析手続を厳密に述べる必要がある。たとえば社会学では「比較分析」が用いられるが、その可能性と限界を吟味する必要がある。
【基礎的設問】:比較(準実験的)研究の対象となりうる適切な社会体系のサンプルをどこに求めるのかが困難なために、機能分析はどの程度まで制限されるであろうか。
たとえばウェーバーが用いた「比較対照試験」は参考になるのではないだろうか。マートンによると、マードックによる「文化横断調査」で用いられている手続きがヒントになるという。マートンが「準」実験的と呼ぶように、実際にそういう対照がない場合は、頭の中で対照を作り出す必要、つまり「思考実験」をする必要がある。
比較対照試験:「諸個体を『層別法』などにより、同質的な二群にわけ、一方を『実験群』、他方を『対照群』とする。そして、双方の諸条件は一定に制御した上で、『実験群』のみに変化を加え、そこに生じてくる変化を観察して、『対照群』と比較する。このばあい、『実験群』のほうに、『対照群』には認められない変化が生じたとすれば、他の諸条件は一定に制御されているので、『実験群』にのみ加えられた変化に帰する以外にはない、ということになる。※折原浩さんの説明
比較対照試験については以前の記事を参照
【基礎社会学第十六回】マックス・ウェーバーの「理解社会学」とはなにか
「この範例の全体にわたって、どういう特殊な問題点でさまざまな仮定や帰属や観察を検証せねばならないかについて再三注意を喚起しておいた。とりわけ、このためには、実験作業の論理に最も近い社会学的な分析手続を厳密に述べる必要がある。それは文化や集団を横断する比較分析の可能性と限界とを体系的に吟味しなければならない。」
ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,105P
「比較(準実験的)研究の対象となりうる適切な社会体系のサンプルをどこに求めるのかが困難ために、機能分析はどの程度まで制限されるであろうか。」
ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,105P
【11】イデオロギー問題のガイド
【範例11】:機能分析は本来的にはイデオロギー立場とかかわりをもつものではない。
【基礎的設問】:「機能分析のイデオロギー的色彩をどうして識別するか、また特定のイデオロギーは、社会学者の用いた基礎的仮定からどの程度生じるであろうか。かような仮定の範囲は、社会学者の地位や研究上の役割と関係があるのだろうか。」
しかし、特定の機能分析や特定の仮説がイデオロギー的役割をもつことを否定しているわけではない。イデオロギー的かかわりあいを観察者はもってしまっているのかどうかの確認、もしもってしまっていたとすれば、それはどのような影響、制限を機能分析に与えているのか考慮する必要がある。
「すなわち、機能主義的社会学者のとる社会的立場(たとえば、一定の調査を委託した特定の『依頼人』との関係で)が、どの程度まで或る問題の特定の説明方式を誘い出し、社会学者の用いる仮定や概念に影響を与え、また彼の用いるデータからひきだされた推論の範囲を制限することになるだろうか。」
ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,105-106P「機能分析のイデオロギー的色彩をどうして識別するか、また特定のイデオロギーは、社会学者の用いた基礎的仮定からどの程度生じるであろうか。かような仮定の範囲は、社会学者の地位や研究上の役割と関係があるのだろうか。」
ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,106P
【コラム】マンハイムの相関主義
イデオロギーの問題は社会学者であるカール・マンハイムの「浮動するインテリゲンチャ」に関わってくる問題だといえる。
できるだけイデオロギーに中立になるためにはどうすればいいのかという問題である。
マンハイムは自分の立場を「相関主義」であるとして、「自由に浮動するインテリゲンチャ」という知識人層の拡大を目指した。
相関主義:知識や認識が社会的存在に拘束されているということを認めつつ、それぞれの拘束された相対的な知識や認識を相互に関連付け、総合することで、視野の拡大と補完の開放性を目指す立場のこと。
自由に浮動するインテリゲンチャ:知識が存在拘束的でありながらも、社会的条件からみて他と比較すると、自らの存在拘束性から相対的に自由になっている知識人階層のこと。
知識人階層とそうではない階層を区別するのは、教養があるかどうかである。大学の教授だから、医者だから、弁護士だからといって必然的に知識人になるわけではない。教養とは存在拘束的でありながらも、同時に、さまざまな文化的傾向に開かれていて、自らの視野をたえず拡大していく精神的態度を意味する。知識人になりやすいかどうかに職業や地域は無関係ではないが、しかしそれらに依存するものではない。
教養とは数学や漢字、マナーを知っているというような一般的な意味での量的な知識ではない。教養文化とは、特に都市において形成される、ある特定の狭く限定された生活共同体とその存在上の拘束性から、相対的にみて、独立したものとなった文化のこと。教養文化のもとでは、教養を獲得しやすいという。
多種多様な学問、方法に通じ、かつ多種多様な「社会的構造」に通じていることで、そうした教養は育ちやすいのだろう。アメリカ人の文化だけが正しいという視点を脱するためには、日本の文化、ヨーロッパの文化、未開社会の文化も学んでいくような態度が重要である。都会なら多様な人種、価値観の人と触れ合う機会が相対的に多いが、地方の場合は画一的な事が多いだろう(村社会と呼ばれるように)。これはマートンによる「代替可能なもの」に常に敏感であるべきという態度、「比較」に重きを置く態度ともつながってくる。
マンハイムについては以前の記事を参照
【基礎社会学第三十二回】カール・マンハイムの「相関主義」と「自由に浮動するインテリゲンチャ」とはなにか
記述的調書に最低限取り入れるべき5つの事項
十分かつ正確に、だけでは迷子になる
【機能的方針】項目はできるだけ「十分かつ正確に」記述せねばならない
しかしこれだけの方針では、「何」を観察すべきかがわからないので迷子になってしまう。何を観察すべきかの機能的方針を紹介する。
【基礎的設問】:何を観察すべきであり、何を現場手帳のなかに書き込むべきであり、何を省略して差し支えないのだろうか。
【基礎的設問】:分析されるべき項目が何であれ、どのような種類のデータがそこに首尾一貫して含まれていたか、そしてなぜこうした特定のデータが含まれていたか。このような設問を掲げて、事例に接近し、「暗黙の解答」をデータから引き出す。
マートンは最低限取り入れるべき事項として以下の5つを挙げている。
- 【第1事項】参与の仕方
- 【第2事項】機能的選択項(等価項,代用項)
- 【第3事項】参与者が特定の型式に与えた意味
- 【第4事項】動機と機能の区別
- 【第5事項】潜在的機能
「おそらく、項目はできるだけ『十分かつ正確に』記述せねばならないということである。だが、しかし、よく考えてみると、こうした義務規定が観察者にとってほとんど何の指針ともならないことは、明らかである。次のような問題解決への一助として、この定言命令だけを武器として機能的方針をとった初心者の当惑ぶりを考えてみよ。何を観察すべきであり、何を現場手帳のなかに書き込むべきであり、何を省略して差し支えないのだろうか。」
ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,109Pキーワード:暗黙,暗黙の解答を引き出すための設問
「かような暗黙の解答がいますぐ実地調査者に与えられることを仮定するわけではないが、それにもかかわらず、この問題そのものが正当であり、暗黙の解答がすでに一部引き出されているということができる。かような暗黙の解答を引き出し、それを系統的に整理するためには、次のような設問を掲げて機能分析の諸事例に接近することが必要である。すなわち、分析されるべき項目が何であれ、どのような種類のデータがそこに首尾一貫して含まれていたか、そしてなぜこうした特定のデータが含まれていたかということである。」
ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,109P
【第1事項】参与の仕方
【第1事項】:参与の仕方。一定の型式に参与する人びとの社会構造内における位置づけ
ここでいう型式は「標準化された社会的・文化的な項目」としてゆるく解釈していく。
たとえば「社会的地位」などを記述する必要がある。こうしたものを記述するだけでも、なんらかの「機能への手がかり」が得られるという。
たとえばある村の儀式を分析する際に、ある集団は外部集団なのか内部集団なのか、ある人物は両親なのか親族なのか、首長なのか部下なのか、働いているのかどうか、公務員かどうか、労働階級なのか、知識階級なのかどうか、そういった属性、地位の記述を考慮する必要がある。
マーケティングにおいても主婦層や学生、サラリーマンなどの属性が分析において重要な事項となるのと似ている。
なんら属性の記述がない場合、有益な仮説は生まれにくい。〇〇が若者に対して購買意欲を向上させるという機能をもったから、販売の総量が増大した、などとわかったりするのかもしれない。もちろん、他の商品や層に影響は出ていないかなど、さまざまな別の結果を考慮しておく必要があるだろう。
「そこで、要約すれば、記述的調書には、次のような諸事項をできるかぎりとり入れねばならない。(一)一定の型式に参与する人びとの社会構造内における位置づけ――さまざまな参与の仕方。」
ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,114-115P
【第2事項】機能的選択項(等価項,代用項)
【第2事項】:機能的選択項(等価項,代用項):特定の型式を強調するあまり排除されてしまった他の選択的行動様式の考察。
これは要するに、ある特定の項目だけがその機能をその一定の体系の中で果たすと決めつけてはならないということだろう。「特定の型式」は、「最頻値的な型式」の例が挙げられている。
マートンの紹介した分析では、アメリカ社会においてどの社会でも「ロマンチックな愛着」を基本として結婚の相手を選択するらしい。確かに現代日本でもそうしたものが最も多そうだ。
しかし一部の家系では結婚相手は親に決められるケースがある。あるいは昔の日本では同じ身分同士、同じ地域同士、お見合いが基本などの一定のパターンが見られるかもしれない。
ここで重要なのは、こうした「自由恋愛の文化型式」は「不自由恋愛の文化型式」という選択をより避けさせる、排除するという視点である。両者は夫婦の形成という結果に対して同じ機能をもつともいえるかもしれません。あるいは機能的に等価に見えても、異なる潜在的機能が別に生じているかもしれません。
そうした視点、「比較資料」をもつとどういう利点があるのか。マートンによると、「その型式の構造的脈絡」に対する直接の手がかりが得られるという。これは社会の構造の把握につながるという重要な視点だろう。
卑近な例で言えば、ある地域で「おにぎりがよく買われる」ということは、「パンを買う」という選択をある程度排除しているとする。食欲を満たすためだけならばどちでもよいはずである。おにぎりの品質を改良し、売上が伸びたが、パンの売上が著しく下がって総量としては利益が低下することもありうるだろう。
その地域では両者の項目の代替可能性が低いのか。許容量はどうなのか。周りの飲み物の変化はどうか。年齢や性別はどうか。なにかの健康ブームか、アジア人が増えたのか。等々とヒントになるのだろう。これは必ずしも社会学的な分析ではないが、日常でも機能分析は応用できる。
「(二)特定の型式を強調するあまり排除されてしまった他の選択的行動様式の考察(すなわち、現に行われているものだけでなく、また現存型式のために無視されているものにも注意すること)。」
ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,114-115P
【第3事項】参与者が特定の型式に与えた意味
【第3事項】:参与者が特定の型式に与えた意味(認知的及び感情的な意義)
「項目のもつ意味を十分詳細に記述すれば、機能分析の適切な方向がよく示唆される」とマートンはいう。しかしこの「意味」がどういうものかわかりにくい。
ベブレン(Veblen)の「誇示的消費の型式」
マートンはこうした記述すべき「意味」の例としてアメリカの経済学者であるベブレン(Veblen)の「誇示的消費の型式」を挙げている。
ベブレンによれば、慣習とは「いろいろの象徴的な意味が社会的に共有され定型化されたもの」だという。そして「誇示的消費」とは必要性や実用的な価値だけでなく、それによって得られる周囲からの羨望のまなざしを意識して行う消費行動を意味する。例えばブランド物を買い漁る行為などが典型だろう。
べブレンは誇示的消費の型式に「地位の強化、地位の確認、よい評判、金銭的な力の誇示」という機能を認めている。
こうした機能は人々に満足感を与え、それゆえにこうした型式が持続するという。
マートンによるとべブレンは以下のような項目に言及できているという。
- (1)それぞれの仕方でこの型式をみせびらかそうとする人々の「地位」
- (2)誇示的な消費を選択することによって、本来の有効な金銭的消費を排除しているという「機能的選択項」
- (3)誇示的消費型式の参与者やこれを見つめる人々がこの行動に与えるさまざまな「文化的意味」
3つ目の「誇示的消費型式の参与者やこれを見つめる人々がこの行動に与えるさまざまな文化的意味」という点がマートンのいう「意味」の例示になる。
ここで重要なのは、「意味」と「動機(目的)」の区別だろう。
(1)たとえば「自分の地位の向上」を目的にして、誇示的消費をしたとする。その場合、結果として「自分の地位が向上」したとする。この場合は動機と結果が重なっている。
(2)しかし、そういう目的がない場合もあるだろう。本人は誰かに買い物を頼まれたかもしれないし、プレゼントのためかもしれないし、あるいは純粋にその商品がほしいだけかもしれない。しかし結果としては「自分の地位が向上」することもある。
(1)と(2)の両者に共通して、どちらもその消費を見つめる他人や友人がその消費に対して羨望の目を向けているとする。その他人や友人が多くの場合、「消費者の地位を向上させる」という明確な動機をもっているとは言い難いだろう。
こうした「誇示的消費」に対して「金銭的に余裕のある、上級階級の行為だ」というのは「文化的意味」であり、動機と区別されるだろう。
もちろん、消費している当人もそうした文化的意味付けを頭に入れて、つまりそれを動機として利用することもありうる。「金銭的に余裕のある人物と意味づけられる行為だと認識し、かつそのように文化的意味付けの対象となることを目的としている」ケースもありうる。意味と動機の区別、動機と結果の区別をしておく必要がある。それらは必ずしも一致しない。混同すると分析が不明瞭になりかねない。
重要なのは意味が文化的であるという点である。
例えば日本ではブランド品を買い漁っていたり、高級車に乗っていたりすると羨望の目で見られがちである。
つまり、「地位の強化、地位の確認、よい評判、金銭的な力の誇示」というように順機能しているかもしれない。
しかし他の社会の体系では「誇示的消費は下品であり、品性に欠ける」という意味付けのほうが強く、むしろ地位を弱化させる可能性もある。日本においてもそうした逆機能も程度の差こそあれ、少しはあるだろう。あるいは泥棒に狙われるといった意外な結果も生むかもしれない。さらに日本のある特定の地域や、あるグールプ、あるいはある家庭において、「誇示的消費はストレスが溜まっている証拠であり、近づかないほうがいい」と意味づけされ、距離を置かれるという結果を生むかもしれない。戦時中なら不謹慎だと見なされるというように、文脈も重要になるだろう。
ある項目がどういう意味付けをされるかは切り取る範囲次第であり、またどういう客観的結果をもつかも同様であるということになる。しかしいずれの範囲をとるにせよ、「文化的意味」や「動機」を記述するということは客観的結果への手がかりになる。
「(三)参与者がこの型式に与えた情緒的および認知的意味。」
ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,114-115P「周知のように、ヴェブレンは、誇示的消費の型式にさまざまな機能を認めている。すなわち、地位の強化、地位の確認、『よい評判』、金銭的な力の誇示という機能がこれである。これらの諸結果は、誇示的消費を行う人びとが経験するように、彼らに満足を与え、だからこそ、この型式が持続する。この型式そのものを記述することによって、そこに認められる機能への手がかりがほとんど出揃うのである。そこでは、(一)それぞれの仕方でこの型式をみせびらかそうとする人びとの地位、(二)消費品の私的な『本来の』享受のためよりも、むしろ誇示と『むだ使い』によって消費する型式をとる既知の選択項(かわりのやり方)、(三)誇示的消費型式の参与者やこれを見つめる人びとがこの行動に与えるさまざまな文化的意味に明らかに言及している。」
ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系112P
【第4事項】動機と機能の区別
【第4事項】:動機と機能の区別。この型式に参与しようとする動機づけとこの型式にともなう客観的行動との区別。
「(四)この型式に参与しようとする動機づけとこの型式にともなう客観的行動のとの区別。」
ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,114-115P
【第5事項】潜在的機能
【第5事項】潜在的機能:中心的な行動型式と関連していて、その参与者が認知していない行動の規則性。
これらは扱っている項目なので多くは省略する。重要なのは、ひとつの順機能だけでははなく、他の機能も記述ないし観察しようとすることであり、また意味や動機と区別して考えるということである。また、個人的にはシュッツの「目的の動機と理由の動機」の区別も重要になってくるのだと思う。
「五)中心的な行動型式と関連していて、その参与者が認知していない行動の規則性。観察者の調書に必要な以上の諸条件は、けっして完全とはいえないであろう。だが、それらの要件は、やがて行われる機能分析を容易たらしめる観察上の要点を明記しようとする実験的な一歩をまさに進めるものである。その意図するところは、たとえば観察者に対して『状況の脈絡』を敏感に捉えるよう助言するばあいよりも、多少とも詳細な点を明らかにしようとするものである。」
ロバート・マートン『社会理論と機能分析』,現代社会学体系13,114-115P
【コラム】ウェーバーの理念型
どうやって人間の頭の中(主観的意向・意味)を知ることが出来るのか
問題点:どうやって人間の頭の中(主観的意向・意味)を知ることが出来るのか。観察者が主観的意味を推定するしかない場合はどうするか。
例:飛び降り自殺と事故死が外形的には全く同じだと仮定して、両者は区別できるのか。遺書がない場合はどうするのか。
経験的にいってこれは自殺だろう、これは事故死だろうという仮説はたてられるが、結局は仮説の確かさの程度の問題に過ぎない。
人間の頭の中の意図や動機を実際に覗き込むことはできない。本人すら分かっていない場合もある。アンケート結果に意図や動機を素直に書き込むとは限らない。誰がどんな文脈で、どんな形式でアンケートを答えるかで解答が変わってくる可能性もある(企業なのか、有償なのか、国なのか、授業なのか云々)。
自然科学的にはビルから落ちて死んだということが物理学的に証明できたとしても、それは社会学でいう「理解」にはならない。かといって経験的にいってこれは死にたくて飛び降りたのだろうという観察者側からの「理解」で「説明」しただけで十分か。心理学的な理解と社会学的な理解の差はどこにあるのか。
例:交通事故において過失かどうか、どう判定されるのか裁判では本人の実際の意志や意図はのぞきこめないので、普通はこうだろうというような推測が基準となる。
本人がいくら「通行人に気づかなかった」と言ったところで、経験的、規則的(判例的)にいって「気づいたはずだろう」という話になる。
これがウェーバーにおける「理念型」の話につながるのである。
合理的な行為だと仮定した場合のモデル作り
例えば合理的にはこのような動機をもって行為するのだろう(合理的行為)だろう、というような一意的、一面的なモデル(理念型)を作り、現実と照らし合わせて理解していく。
現実と照らし合わせていく過程で、非合理的な要素もありえるかもしれない。目的合理的行為が理念型では一番使いやすい。他の社会的行為でも可能だという。
たとえばパンを食べる目的は食欲を満たすためだ、と普通は考える。合理的に考えれば、そうなる。この「普通」というのは観察者側の社会(あるいは被観察者側の社会)ではある行為はこう考えるのが普通だという意味合いである。
しかし実際には「眠るため」、あるいはアレルギーを起こすことによってわざと体を壊すためという極端な目的があるかもしれない。しかしそのような極端なケースは例外として、まさに「理想」のケースとしてモデルを立てていくのである。ただし、最も頻出なものだけが理念系の目的として用いられるとは限られないという点も重要になる。
たとえばウェーバーは近代西洋の人間の理念系として「禁欲的なプロテスタント」を選んだが、西洋では多数派ではなく、むしろ少数派でもありうるという。しかし資本主義との関連を明らかにする際には、そうした理念型が有用になるという。物理学でも真空状態という自然にはほとんど存在しない理念型が用いられることがあるだろう。
また、眠るためだろうが、食欲を満たすためだろうが、「エネルギーが補給された」という客観的結果は重なってくる。パンはエネルギーを補給する効果があるという分析にとって動機はあまり影響がないともいえる。とはいえ、心理的機能として、なんらかの満足度という結果が変わってくる、というのはあるかもしれない。あるいは消化のスピードが違うという客観的なデータが見られるかもしれない。しかしそうしたものは社会学にとって主要な要素ではないということなのだろう。それゆえ、ある観点からある正負を分析すると限定せざるをえないのかもしれない。
索出手段としての理念型
こうした理想とはまるで違うケースが多く出てくることもある。そのような場合は別の社会的行為の類型の索出手段として利用できる。目的合理的、価値合理的、感情的、伝統的の4つがウェーバーの基本類型である。
普通のパターンを知っていれば、それとは違うパターンを探しやすくなるだろう。たとえば誇示的消費のパターンを作っておけば、それとはまるで違うパターンがある社会にあるということを見出しやすくなる。
たとえばその社会の文化意味を知らなければ、高すぎるブランドものの洋服は理解できない非合理的行為に見えるだろう。しかし文化的意味を知っていれば、そうした社会的行為が目的合理的、あるいは価値合理的だということを理解できるかもしれない。たとえば地位の確認という機能が結果にあるから、それゆえに人々はそうした誇示的消費をするのだ、と理解できる。彼らがその結果を明確に意図していなくても、暗黙には知っていることがありえるだろう(このあたりはギデンズやポランニーにつながるのかもしれない)。暗黙知や意図せざる結果に注目する観点は面白い。
追記:機能分析も、理念型も、現実の解釈のための「道案内」であり、現実そのものを写し取るわけではないという視点が重要になる。説明は写し取るのではなく、掘り出す行為に近いのではないだろうか。(2024/03/12)
地図は土地ではない
ある一定の理念型を作っておくのは便利だというわけである。社会同士、文化同士の比較もより可能になる。もちろん、理念型のパターンを実体化させるような、具体性置き違えの誤謬(ホワイトヘッドの言葉)には気をつけて使用することになる。有名な言葉で言えば、「地図は土地ではない」のである。ベイトソン的、あるいはラッセル(Bertrand Arthur William Russell)的に言えば論理階系の混同でしょう。
「概念」を「具体的なもの」として実体化してしまっているというミスであり、パーソンズも自らの分析はあくまでも抽象的なものであるという「分析的リアリズム」を名乗り、できるだけ気をつけていた。AGIL図式も、近似に過ぎない、典型例にすぎないというわけである。こうした思考はベイトソンの「緩い思考」とつながっていく。
機能分析の場合は機能を索出する場合に有用だという点で「動機」の記述が推奨される。
しかし「機能」と「動機」を混同をするべきではないことがマートンによって強調されている。
極論として、動機を一切当事者に聞かなくとも「客観的結果(機能)」はわかるのかもしれない。「動機(願望)がなんであるかは問題ではない」と記述している分析の例をマートンは引用している。
極端に言えば「動機的理解」がなくとも「因果的理解」は可能だということになる。重要なのは第一に因果関係であるという視点がある。
機能関係とは因果関係(の一つのあり方)なのであり、動機連関とは区別されなければならない。少なくとも社会学が科学であろうとする限り、曖昧な主観的意向ではなく、厳密な因果関係をまずは重視するべきだということなのだろう。ここにギデンズが述べる「主体性」の問題点が関連してくるのかもしれない。主観を重視し、かつ客観をも重視する理論とはどのような形なのか。それらをどうつなげるのか。
ウェーバーについては以下の記事を参照
【基礎社会学第六回】マックス・ウェーバーの「理念型」とはなにか(概略編)
【基礎社会学第十四回】マックス・ウェーバーの社会的行為の四類型とはなにか
パーソンズの分析的リアリズムについては以下の記事を参照
【基礎社会学第二十一回】タルコット・パーソンズの「分析的リアリズム」とはなにか
その他
共変法と差異法の違い、デュルケムとの関連
差異法と共変法とはなにか、意味
差異法み:ジョン・スチュアート・ミルの定義によれば、「ある現象が起こっている事例と起こっていない事例において、前者だけに含まれる条件がただ一つあって、それ以外のすべてが両者に共通しているならば、その1つの条件が両事例の差の原因であると判定する方法」のこと。
共変法:ミルの定義によれば、「条件aと結果Xとの間に『aが大きくまたは小さくなれば、Xも大きくまたは小さくなる』という相関関係があれば、aをXの原因または原因と関連した変数だと判定する方法」のこと。
「第2の規範(差異法)「ある現象が起こっている事例と起こっていない事例において、前者だけに含まれる条件がただ一つあって、それ以外のすべてが両者に共通しているならば、その1つの条件が両事例の差の原因である。」
たとえばある開放海岸に、1ヶ所地形的に遮閉されたところがあり、そこにだけある種の海岸生物が存在していたとすると、温度や水質などは周囲で一様と考えられるから、波の強さがこの種の分布決定因であるという推測が成り立つ。こうした条件の差は、この例のように自然の中に見出されることもあるが、そうでない場合は人為的に作り出すこともできる。それが実験である。その場合一方が操作事例、もう一方がコントロールということになる。」
大垣俊一「ミル型論証と生態学」、4P「〘名〙論理学の用語。イギリスの哲学者ジョン=スチュアート=ミルの帰納法の一つ。原因Aの結果aを発見するために、原因Aを含んだ事情の組み合わせABCからの結果abcと、原因Aだけを除いて他は同じ事情BCからの結果bcとを比較して、原因Aの結果がaであることを発見する法。」
精選版 日本国語大辞典「第5の規範(共変法)「ある現象が、ある条件が変化するとき必ずそれと共に変化するなら、その条件はその現象の原因または結果であるか、その現象となんらかの因果関係を介して結びついている。」これはいわゆる相関である。AとBの相関は因果関係が存在する可能性を示すが、A→BないしBA因果の証明ではない。それで後半部で、原因または結果、あるいは何らかの要因を介して結びついている、と慎重に言い回されている。因果関係を調べるとき、まず相関を取ってみるということは、今日でも様々な分野で普通に行われている。この点についてはあえて具体例を出すまでもないだろう。」
大垣俊一「ミル型論証と生態学」,5P
因果関係とはなにか、意味
因果関係:一般に、原因と結果の関係のこと。AがBを生起させる場合、Aを原因、Bを結果といい、AとBには因果関係があるという。
たとえば法律の分野では、行為と結果との間に「AがなかったらBもなかったであろう」というような範囲が広い関係を「条件関係」と呼び、それより狭い、社会経験や常識を考慮した関係を「相当(因果)関係」と呼ぶ。
たとえば犯人はその母親が産まれていなければ産まれてこず、罪を犯さなかったというのは真であるが、範囲が広すぎるので「条件関係」とでも呼ぶべきものである。
もしAさんに切りかかられていなければBさんはAさんを殺していなかったというのは裁判などでは「相当因果関係」とでも呼ぶべきものになるのだろう。
ただし、ある特定の要素だけがその結果に対して不可欠であるかどうかを明確にするのは難しい。常識的に考えて、というように合理性が重視されるか、その特定の人物の以前の行為パターン、証拠などを加味するなどして説得力(客観的可能性)をもたせるのだろう。
相関関係とはなにか、意味
相関関係:条件aと結果Xとの間に「aが大きくまたは小さくなれば、Xも大きくまたは小さくなる」という関係のこと。
ミルの定義では「ある現象が、ある条件が変化するとき必ずそれと共に変化するなら、その条件はその現象の原因または結果であるか、その現象となんらかの因果関係を介して結びついていること」を相関と呼ぶ。
相関は必ずしも因果ではない
大垣俊一さんによれば、「因果関係」を調べる時に、まず「相関(相関関係)」を取ってみるということは様々な分野で行われているという。ただし、相関は必ずしも因果ではない。あくまでも、因果の可能性を示すにすぎない。
たとえばある人間がエアコンをつけるとき、100回中100回とも必ず室温が30度以上だったとする。この場合、室温が30度以上であるという原因と、エアコンをつけるという結果は相関している。しかし、汗をかいていたからだとか、湿度が高いからだとか、あるいはその複合的な原因であるとか、他の原因もありうる。これだけでは、室温が30度以上だという条件がエアコンをつけるという結果をもたらしたのかどうか、判定しがたい。
佐藤俊樹さんによれば、社会科学では差異法の適用条件は、現実にはきわめてきびしいという。デュルケームもまた、厳密に満たされる場合はほとんどないと述べている。
ただし、佐藤さんによれば差異法は未知の可能性を考慮した方法であり、差異法だけが真の意味で因果を同定できるという。
要するに、相関関係があるというだけで因果関係を同定したつもりになるのは早計だということである。
かといって、差異法によって因果関係を同定することは社会科学では難しい。
「第5の規範(共変法)「ある現象が、ある条件が変化するとき必ずそれと共に変化するなら、その条件はその現象の原因または結果であるか、その現象となんらかの因果関係を介して結びついている。」これはいわゆる相関である。AとBの相関は因果関係が存在する可能性を示すが、A→BないしBA因果の証明ではない。それで後半部で、原因または結果、あるいは何らかの要因を介して結びついている、と慎重に言い回されている。因果関係を調べるとき、まず相関を取ってみるということは、今日でも様々な分野で普通に行われている。この点についてはあえて具体例を出すまでもないだろう。」
大垣俊一「ミル型論証と生態学」,5P「一つ以外の条件が全てひとしいという差異法の適用条件は、現実にはきわめてきびしい。デュルケーム自身が指摘しているように、社会科学でこれが厳密に満たされる場合はほとんどない。それでも、この条件には大きな意味がある。これによって未知の原因もまとめて考慮できるからだ。例えば、bとeが組み合わさった場合にXの原因になりうるかもしれないが、その可能性も排除できる。条件が有限個でも組み合わせの数は膨大に成が、それをすべて検討したことになる。つまり、差異法は未知の可能性を考慮した方法になっている。だからこそ、差異法だけが真の意味で因果を同定できる。その点でミルの結論は正しい。第五章で述べるように、社会学でもウェーバーは差異法を使っている。対照的な結果を生み出した二つの社会を比較して、二つ以上の条件が違っている場合には、それらの条件の中でどれが本当の原因なのかは識別できないことを認めた上で、より踏み込んだ仮説を解釈として展開した。それに対して、デュルケームは、正しい因果関係の可能性をあらかじめ特定できると考えていた。現代風にいえば、正しい社会学は重要な因果関係の全ての可能性を知ることができる、そして自分は正しい社会学を知っている、と考えていた。だから、未知の原因の可能性を考慮する必要も認めなかった。そう考えれば、『社会学的方法の規準』の方法論と『自殺論』の実証を整合的に理解できる。」
佐藤俊樹『社会学の方法』,108P
限定された知
M・ウェーバーは限られたデータに厳密な方法で臨み、かつ全てを解き明かそうとするのではなく、わからない部分はわからないとし、「限定された知」を意識していたという。これは非常に重要な点である。
ウェーバー「比較対照試験」を用いるが、これは「差異法」であるという。
理念型による因果仮説が因果適合的かどうかは「実験」によって裏付けられるというわけである。
自然科学のような直接的、人為的な差異法は社会学では使えないが、間接的に使うことは出来る。いわゆる間接実験であり、マートン的に言えば準実験である。
例:ウェーバーによれば西洋と初期条件が似ているのは中国だった。西洋と中国の大きな違いは「プロテスタンティズムの倫理があるかどうか」であり、中国はそうした要素がなかったから資本主義の精神が育たなかったという推測ができる。
つまり資本主義が起こっているという事例(西洋)と起こっていない事例(中国)において、西洋だけに含まれる条件がただひとつ(プロテスタンティズムの倫理)あって、それ以外のすべてが両者に共通してるならば、そのひとつの条件が両事例の差の原因であると推定することが出来る。
ただし、ウェーバーはプロテスタンティズムだけが資本主義を生んだという原因特定には成功しなかった。なぜなら西洋と中国の違いはプロテスタンティズムの倫理だけではないからである。
限界があることは自覚しつつ、その限界内でできるだけ「実験(差異法)」を通して因果的説明によって客観的可能性(シャンス)を高める(説得力をもたせる)というわけである。
「一つは、社会学という知の正確を変えることになった。先に述べたように、ウェーバーは、プロテスタンティズムだけが近代資本主義を生んだという原因特定には成功しなかった。それ以外にも伝統中国と西洋には大きなちがいがあった、と認めざるをえなかった。これは論証の失敗というより、むしろ限界である。プロテスタンティズムの有無以外は西洋近代の初期状態と同じである比較単位がなければ、そもそも特定できないからだ。実験ができない社会科学の限界ともいえる。……それは『限定された知』という特性につながる。全てを解き明かそうとするのではなく、わからない部分はわからないとする。」
佐藤俊樹、「社会学の方法」、ミネルヴァ書房、163P
パーソンズとデュルケムの共通点
パーゾンズによる超因果性
まず、パーソンズは目的論的機能主義によく分類される(さまざまな解釈があるが、一旦保留して誇張しておく)。機能があるということは、何らかの目的、役割が必ずあると考える立場である。例えばパーソンズは社会の維持には特定の4つの機能が必ず必要になる。
それは経験前に、わかるという趣旨の理論を主張している。社会(相互行為群)はその機能要件という目的を果たすように動いているように見ていくわけである。そして特定の4つの、社会体系を維持するという目的をもつ機能に関係する行為を見ていれば、その社会の動きが近似的に分かるという立場である(すべての相互関係を見ていく必要はない)。
佐藤俊樹さんの言葉では、「超因果性」の導入である。因果関係を超えた神秘的な関係性をもたせてしまっている
デュルケムによる超因果性
佐藤さんによると、デュルケムは目的論的機能主義者ではないが、超因果性を導入してしまっているという。
デュルケムは何らかの目的や、特定の目的が経験前にあるかどうかはわからないと考える。ただし、目的はわからずとも何らかの機能、つまり特定の因果関係、客観的結果が重要であるということは経験前、社会学理論によってわかるという。たとえばデュルケムの場合は「社会的統合力」という機能に重きを置いている。
また、特定の因果関係(原因と結果は1:1と考える)をつかみさえすれば、全体がつかめる。それは事前に、理論的にわかると考えているという。これは一種の「超因果性」の導入だということになる。
Wikipediaの編集で例えるならば「独自研究?」や「要出典」と言われてしまうような客観性(因果性)に欠けた要素なのだろうか。このあたりが社会学が科学と名乗ることができるかどうかのキーポイントでもあるのだろう。しかしそれでもなお、「超因果性」という(ゆるい)分析も、過程としては必要なのかもしれない。
また、佐藤さんによるとデュルケムは自らの分析方法は「差異法」ではなく、「共変法」であるとしているという。
たとえば教育か宗教のどちらが自殺率の増加に影響を及ぼしているかデータからわからなかったとする。つまり、機能要件をしぼれないというわけである。宗教と教育が自殺率に相関しているという言い方しかできない(因果関係を絞ることが出来ない)。そこで、デュルケムは2つの項目に共通の機能として、「社会的統合力(凝集性)」というものを持ち出す。高い教育の場合は統合力を弱め、プロテスタントの場合も統合力を弱めるといったように説明していくのである。つまり、1つしか相関していないという形にもっていくのである(一つの結果には一つの原因が対応しているとデュルケムは考える)。
これだけを聞くと、私は素直に「なるほどな」と思ってしまう。特に疑ったりできない。しかしここからの佐藤さんの話が面白い。
まず、宗教と教育が自殺率に相関しているとすれば、凝集性のような宗教に近い要因だけではなく、教育水準に近い要因もありうるという。その例に「都市では生活の期待水準が高くなるが、現実の生活水準はそれほど良くならない。その落差が自殺を生む、といった可能性」を佐藤さんは挙げている。
しかしデュルケムはそうした複数の原因候補への懐疑があまりないという。はじめから原因がわかっているかのような超因果性が見られるというわけである。そして社会学はそうした原因を絞ることができる特権的な学問であるように考えられている。
ウェーバーは絞ることが出来ないと認めた点で両者に違いが見えてくる。
「先に述べたように、現在の計量分析はでは、凝集性を示すと思われる指標を用意して、それと自殺率との関係を調べる。あるいは、宗教の違いと教育水準のちがいを統合する潜在変数を設定する。どちらにせよ、凝集性のちがいをもっと直接的な形で実証することが求められる。デュルケームはそこを一気に飛び越える。凝集性それ事態を測らないまま、プロテスタント/カトリックや教育水準のちがいを凝集性のちがいと同一視するのだ。例えば、宗教と教育水準がお互いに相関し、かつ自殺率にそれぞれ相関しているとすれば、凝集性のような宗教に近い原因だけではなく、教育水準に近い要因もありうる。例えば、都市では生活の期待水準が高くなるが、現実の生活水準はそれほど良くならない。その落差が自殺を生む、といった可能性もあるが、それらは考慮されない。『自殺論』のデータには大きな制約があるので、実際に原因を特定するのはむずかしいが、議論の進め方をみると、どちらが原因なのかという懐疑自体があまりない。自殺の真の原因が最初からわかっているかのようだ。だからこそ、より直接的な代理指標で検証する必要も感じないのだろう。そこにミルとデュルケームの決定的なちがいがある。デュルケームは、原因と結果が根本的には必ず一対一で対応すると考えていた。特定の原因は必ず特定の結果をうみだす。表面的には複数の原因候補がつねにありうるが、それも最終的には一つの原因に還元できる、と考えていた。」
佐藤俊樹『社会学の方法』,107Pキーワード:超因果性
「目的論的機能主義は、機能として指定された関連性だけを特定できれば十分な説明ができるとする。裏返せば、その事象に関わる全ての因果関係を観察しなくてもよい。デュルケームはこうした目的論による説明を明確に避けた。目的因を避けて作用因だけを認めた、というのはそういうことだが、もう一段抽象度をあげて考えてみると、まさにこの特定の関連性だけを見ればよいという点で、デュルケームの社会学と目的論的機能主義は機能的に等価(functional equivalent)になる。社会学者は重要な因果関係をあらかじめ室ているとする彼の考え方は、特定の関連性だけがわかれば全体がつかめるという『超因果性』を導入することになるからだ。」
佐藤俊樹『社会学の方法』,113P
マートンの場合は超因果性を持ち込んでいないのか
(1)パーソンズと違って先験的に機能的要件を決めるという考え方をしていない。それらは経験的に把握しようとする対象である。また、「機能的(必須)要件」は同義反復的、結果論的になりやすく、実証するのが難しいという難点がある。包括的社会のような体系の分析は意図的に避けている。
- (2)デュルケムと違って原因と結果は一対一ではなく、複数の原因、等価な原因がありうると考える。最初から原因を決めつけず、経験的に把握しようとする。「機能的選択項目(等価,代替)」を常に考慮して分析を行うことを重視する。
目的論とは一体なにか
正直な話、「目的論」という言葉の理解が灰色である。マートンはたしかに「目的や動機、ねらい」といったものを「客観的結果(機能)」と区別している。
さらに、マートンは機能を「一定の体系の適応ないし調整を促す観察結果」と定義している。「一定の体系のために適応や調整という結果が存在している」というように目的論的には述べていない。AがBのために存在するかどうか、存在しないかどうかは隅に置く。
大事なのはAがBにプラスしている、あるいはマイナスしているかどうかであり、そうした判断に至る観点の置き方、範囲の取り方である。社会の維持のために宗教が存在しているという考え方よりも、宗教が社会の維持にプラスしているあるいはマイナスしているという客観的な因果関係を重視する。
マートンは目的論的機能主義者ではない。マートンは機能分析が目的論に陥るとすれば、きびしく告発されるべきであると述べている。「神が我々が食物のにおいを楽しむのにちょうど都合よく鼻の下に口をつけてくれた」という目的論をマートンは例に出している。これに反論するとすれば、明らかに不都合なものを探せばいいのかもしれない(帰謬法)。
たとえば、なぜ神は〇〇を配置したのか、不合理ではないかと科学的に問い詰めても、「我々には考えもつかない偉大な意味があり、我々はそれを信仰するだけである、死後の世界では意味がある」などと言われれば、そこで議論が終わってしまう。
デュルケムのこの言葉も目的論的機能主義の危うさを理解するために助けになるかもしれない。
「たいていの社会学者はこんなふうに考える。諸現象がなにに役立っているか、どのような役割を果たしているかがいったん明らかにされば、それについての説明もすでになされたことになるのではないか、と。…これらの貢献が実際に存在することを確証し、それがどのような社会的要求を充たしているかを明らかにした時、その現象を理解可能なものとするのに必要ないっさいのことが言い尽くされたように思い込んでしまうのだ。」(佐藤俊樹『社会学の方法』,112pより孫引き)
ウィトゲンシュタインの言語論的転回について
「語り得ないものについては、沈黙せねばならない」
哲学者のウィトゲンシュタイン(Ludwig Wittgenstein)は「『語ることができないこと』について延々と無意味なおしゃべりをしてきたのではないのか」という。近代哲学や現象学を営んでいる人たちに関わる問題だろう。
科学的に実証できないものよりも、科学的に検証できるような問題を取り組むべきだという話である。それが「言語論や言語行為論、言語ゲーム論」だという。こうした事態をリチャード・ローティーが「言語論的転回」と呼んだらしい。
※ウィトゲンシュタインは前期と後期で考え方が違ったりする。いずれ彼らについては哲学の動画で扱っていく予定であり、いまはこの理解で進めていく。
これはマートンによる以前の社会学への、とりわけヨーロッパ系の社会学への批判ともつながってくるのだろう。
「例えば、フランクフルト学派の魅力の大きな部分を占めている言説「啓蒙の弁証法」「エロス社会」他は、確かに、当人の思いついた「仮説」以前の哲学的思弁に依存しており、検証を行おうにも検証可能な命題として構成されることをはじめから拒否している。結局残るのは著者の文学的な魅力や、長年の名声や、地位による権威だけだということになってしまう。同じことはヘーゲル哲学やマルクス主義をめぐってヨーロッパ人が延々と考えてきた多種多様な「秘教」についてもいえることであるし、マックス・ウェーバーの「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」の命題についてもいえることである。他方で、ウィトゲンシュタインの果たした「革命」が、英米系の社会科学者を中心になぜこれほどまでに受け入れられたのかということも関係している。簡単に言えば、これまでのヨーロッパ人(イギリス以外の大陸ヨーロッパ人)は「語ることができないこと」につい延々と無意味なおしゃべりをしてきたのではないのか?という問いであり、その種のおしゃべりを避けて科学的に検証可能な問題は、言語論や言語行為論、言語ゲーム論だけなのだというわけである。この事態を指して「言語論的転回」と呼んだのは、これまたアメリカ人のリチャード・ローティーであった。」
犬飼裕一「コミュニケーション研究のヨーロッパ種とアメリカ種 上 ,マートン知識社会学の研究」,17p
ヨーロッパ種とアメリカ種
マートンは知識社会学をヨーロッパ種、マス・コミュニケーションの社会学をアメリカ種と呼んでいる。そして、おそらく誇張した形で以下の2種類に分けて両者の典型例を説明している。
ヨーロッパ種の社会学者は「われわれのいうことが真実かどうかは分からないが、少くともそれは重要な意義をもっている」と考える。
アメリカ種の社会学者は「われわれのいうことに特に意義があるかどうかはわからないが、少くともそれは真実である」と考える。
マートンの「アメリカの学者は自分が何を話しているのか分かっているが、それは大した内容のものではないし、ヨーロッパの学者は自分が何を話しているのか分かっていないが、その内容は大したものである」という発言もなかなか面白い。
また、こうしたヨーロッパ種とアメリカ種をつなげようとしたのが「中範囲の理論」であることは前回学んだ。
今回重要だと思ったのは「緩い思考」と「厳密な思考」の区別である。
例えば確かに難しい用語ばかりで抽象的な、理解しがたいもののように現象学は見える。また、実証不可能な点も一部はあるだろう。マートン以前の社会学や人類学昔の人たちは厳密な用語は使わずに、アナロジーにゆるく考えていたかもしれない。
しかしフッサールの現象学はウェーバーやシュッツ、マンハイムなどの社会学者に影響を与えている。そしてウェーバーやマンハイムはパーソンズに影響を与えている。両者は並行関係にあるのではなく、連続しているのである。
情熱の空気と冷静な分析の間で
メモ:マックス・ウェーバーは「学問に対して職業人がとるべき心構えの例」として「冷静さと情熱の両方が必要」だと述べていたことを思い出した。
ベイトソンが言ったように、学問は緩い思考と厳密な思考が絡み合って進んでいくのである。両者のどちらかがいらない、無意味ということはない。
デュルケムの神聖な空気、ウェーバーの道徳的な空気、パーソンズの宗教的な空気、フッサールの根源に迫る空気が私は好きだ。全体に対する貢献の意思というか、そうしたエネルギーを感じる。なんとか社会をよくするために考えようというような熱さを感じる。もちろんそうした空気感のみに彼らの価値があると言っているわけではない。
そうした空気感は実用的なツールではないのですぐに使えるものではないが、しかし社会のために学問というものは重要だということを切実に訴えかけている気がする。そうした気持ちを受け継ぎつつ、アメリカ型の方法論も学び、具体的、実証的、簡潔に社会を良くするためになにかを提案していけたらいいのだと思う。
もちろん、それがビジネスの世界なら会社を良くするために、生活の中でなら友人関係を、恋人関係を良くするために使っていけるのだろう。
宮台真司さんの説明で言えば、ヨーロッパ型は「全体性を参照しようとするオリエンテーション(志向)に裏打ちされた知的営み」であるという。ルーマンやマンハイム、フッサールはそれに属しているのだろう。
マックス・ウェーバーによれば、「知識人」は日常を幸せに生きられないという。日常を幸せに生きられない人の多くは宗教に行くが、たまたま行かなかった学問の世界に行くという。宮台さんは、こうした知識人を「超越系」と呼び、日常を幸せに生きられる人を「内在系」と呼んでいる。
超越系にいくような知識人は、良い意味でどこか変わってるのかもしれない。今まで学んだ多くの人がなにかしら宗教を信じている気がする(もっとも、海外では無宗教のほうが少ないが)。ウェーバーもパーソンズもフッサールもキリスト教徒だった気がする。
たとえばルーマンは戦争を経験し、捕虜となった過去があるという。時代が大きく代わる節目には「社会をなんとか変えよう」という力が強まり、こうした偉大な学者たちが登場しやすいのかもしれない。なにかやらなくてはいけないという使命感、天職のような気概が日本では育ちにくいのかもしれない(日本に偉大な学者がいないと言っているわけではない)。この話の関連で西部邁さんのいうような「伝統」や「故郷」が絡んでくるのかもしれないが、しかしそれでもやはり「社会科学」とは区別する必要がありそうだ。各々の理論を学ぶ動機、使う動機はたしかに大事だが、分析内容に色濃く反映させようとしすぎると分析内容が不明瞭になってしまう。
マートンによる問題設定に必要な3つの要素
だいぶ記事が長くなってしまった。最後にこの話をして終わりにする。
マートンによると、問題発見とは「戦略的に価値のある現象をとらえ、これを説明する理論的枠組を設定するものであって、あたかも自然科学における決定的実験のモデルにも比すべき意義をもっている」という。そして中範囲の理論の成否に関わる重要な「鍵」だという。
また、問題を解決するよりも問題を発見し、定式化することのほうがはるかに困難だという。そしてそれは社会学的に訓練された「想像力」を必要とするという。この想像力はミルズの「社会学的想像力」につながっていくものだろう。何を価値のある問題とみなすべきか、何を問題と設定するべきかについてマートンは3つ挙げている。問題発見はちょっとした気づきから生じることもあるが、そこから「定式化」することや問題を「設定」することは別の難しさがあるのだろう。
【問題設定のために必要な要素1】
その問題は、説明されるまえに、たしかに事実であるかどうかを問わねばならない。
エセ事実は、エセ問題を招く結果となるという。どのようにして事実だと判断するのだろうか。そのヒントは、さまざまなマートンの分析例に見出すことができるのだろう。あるいは現在の「社会調査」の方法論にその一片を見出すことができるかもしれない。
【問題設定のために必要な要素2】
その問題は体系的知識の拡大に寄与し、これまでの理論的ギャップを充填するものでなければならない。
何が知識の拡大に寄与するかのひとつの指針として、「社会的脈絡における多方面の行動観察から同一の一般的問題が展開されるとき、その問題は、社会学理論にとって重要性を示す一つの基準」というものが挙げられている。偏った特定の、アドホックな問題よりも、できるだけ多くの範囲に共通しうる、汎用性が高い問題のほうが価値があるのだろう。
【問題設定のために必要な要素3】
その問題は、有利に問題を展開しうる経験的材料を探し出すことができる必要がある。
たとえばマートンは官僚制の研究から規則的メカニズムへと展開させたり、アメリカ兵士の研究から相対的不満、準拠集団の問題へと発展させていった。
まず特殊な問題に対して限定的な問いを立て、データを探し出していく。このデータを探し出していく過程の中で、より一般的な、より価値のある理論の発見、さらなる問題発見へとつながっていくケースなどが考えられる。こうした次へ次へとつながっていくような「問題発見」こそ価値があるといえる。社会学理論は全て仮説でなければならず、それらは常に批判にさらされ、乗り越えられていくものだという考えが大事になるのだろう。
何がつまらなくて、何が興味深いものであるか
たとえば盛山和夫さんは以下のように述べている。
「何がつまらなくて、何が興味深いものであるかは、かなり主観的なものだが、一般的には次のように言える。すなわち、(1)われわれは基本的に対象世界について新しく何かを知ることに関心を持っているのであって、すでに知っていることを確認するだけのことはつまらない。(2)対象世界の構造的特性の一つ一つをバラバラに知ることよりも、多くの特性を斉合的に理解しうるようなより基本的な、あるいはより包括的な特性について知ることの方が興味深い。(3)したがって、われわれにとってより興味深いデータ分析とは、一次的解釈によってえられたさまざまな統計指標について、それらを総合的に理解するような説明図式を提示するものであり、それは「物語」と呼ぶにふさわしいものになる。このようなレベルの分析、すなわち、データを物語によって説明するような分析を「第三次の解釈」と呼ぶことにしよう。いうまでもなく、デュルケムの『自殺論』は、そうした第三次の解釈としての量的データ分析として代表的なものである」
盛山和夫「<特集><社会調査の社会学>説明と物語:社会調査は何をめざすべきか」,22P
個人的には「役に立つ」と同時に「はっとさせられる」ような発想、解釈がデータに対して創発的な反応を起こした時に面白い、ワクワクすると感じる。
これは実用的で応用性、汎用性が高いとは必ずしもいえない小説や映画、アニメ、音楽や芸術などその他多くの分野にも共通しているのだと思う。意外な発想、常識を覆すような視点、意図せざる結果、潜在的機能の発見は面白い。
しかもその「ワクワク」をより論理的、整合的に説明することで他者に理解を、他者同士のコミュニケーションを促すという効果がある。そしてそれを裏返せば非論理的、非科学的なものとしても芸術に意図的に取り入れることもできるだろう。あまりにも論理的すぎると、芸術では美しくない場合がありそうだ。隠されたものを発見するときに美しさを感じることもある。
ものすごく雑駁に言えば「これは創造だ、アイデアが連鎖している」と思えるような内的な状況は楽しい。
外的にそれが創造だと他者にみなされなくても、内的には創造である。そうしたアイデアを連鎖させる方法論の一つとして、機能分析は有益だと考える。井庭崇さんが機能分析を社会システム理論と同様に重視していたのも頷ける。
最後にウェーバーの言葉を引用します。
「しかし、いつか色彩が変わる。無反省に利用された観点の意義が不確かとなり、道が薄暮れのなかに見失われる。大いなる文化問題が、さらに明るみに引き出されてくる。そのとき、科学もまた、その立場と概念装置とを添えて、思想の高みから事象の流れを見渡そうと身構える。科学は、ただそれのみが研究に意味と方向とを示せる星座を目指して、歩みを進める。」マックス・ウェーバー「社会科学と社会政策にかかわる認識の『客観性』」149-150P
参考文献リスト
今回の主な文献
(新装版,2024年3/29日発売)ロバート・K.マートン「社会理論と社会構造 (1961年) 」
【1】ロバート・K.マートン「社会理論と社会構造 (1961年) 」
(旧版1)ロバート・K.マートン「社会理論と社会構造 (1961年) 」
【1】ロバート・K.マートン「社会理論と社会構造 (1961年) 」
(旧版2)ロバート・K.マートン「社会理論と社会構造 (1961年) 」
【2】ロバート・K.マートン「社会理論と社会構造 (1961年) 」
ロバート・K.マートン「現代社会学大系 13 社会理論と機能分析」
【抜粋・廉価版】ロバート・K.マートン「現代社会学大系 13 社会理論と機能分析」
汎用文献
佐藤俊樹「社会学の方法:その歴史と構造」
大澤真幸「社会学史」
新睦人「社会学のあゆみ」
本当にわかる社会学 フシギなくらい見えてくる
アンソニー・ギデンズ「社会学」
社会学
社会学 新版 (New Liberal Arts Selection)
クロニクル社会学
社会学用語図鑑 ―人物と用語でたどる社会学の全体像
参考論文
1:區建英「異文化の衝突と融合:中国近代文化に関する厳復の模索」(URL)
2:犬飼裕一「コミュニケーション研究のヨーロッパ種とアメリカ種 上 : マートン知識社会学の研究」(URL)
3:米川茂信「アノミーの規範分析: デュルケム・アノミー概念のマートン・アノミー概念における継受と展開」(URL)
4:村田裕志「社会学的機能主義系 「社会システム論」 の視角 (I)」(URL)
5: 宮本孝二 「機能主義的社会理論再考, ギデンズの機能主義批判に基づいて」(URL)
6:安西文夫「機能主義批判の現段階」(URL)
7:倉田良樹「雇用関係の社会理論(3)」(URL)
8:熊田俊郎 「関係概念としての 「機能」: 機能主義理論再構成のために」(URL)
9:畠山洋輔「社会学的機能分析の機能一一Luhmann機能分析による経験的研究の可能性一一」(URL)
10:高木英至「機能理論は不可能か?」(URL)
11:恒松直幸,橋爪大三郎,志田基与師「機能要件と構造変動仮説~構造一機能分析のidentitycrisis」(URL)
12:溝部明男「社会システム論と社会学理論の展開-T. パーソンズ社会学と残された3つの理論的課題-」(URL)
13:大垣俊一「ミル型論証と生態学」(URL)
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
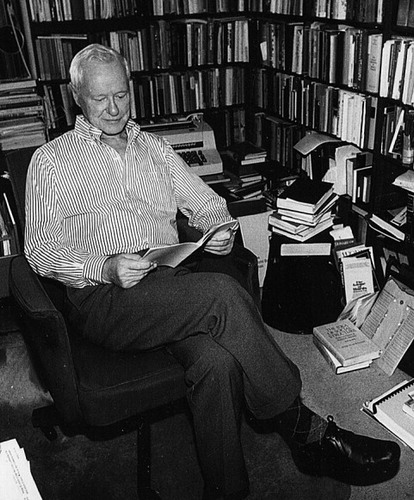
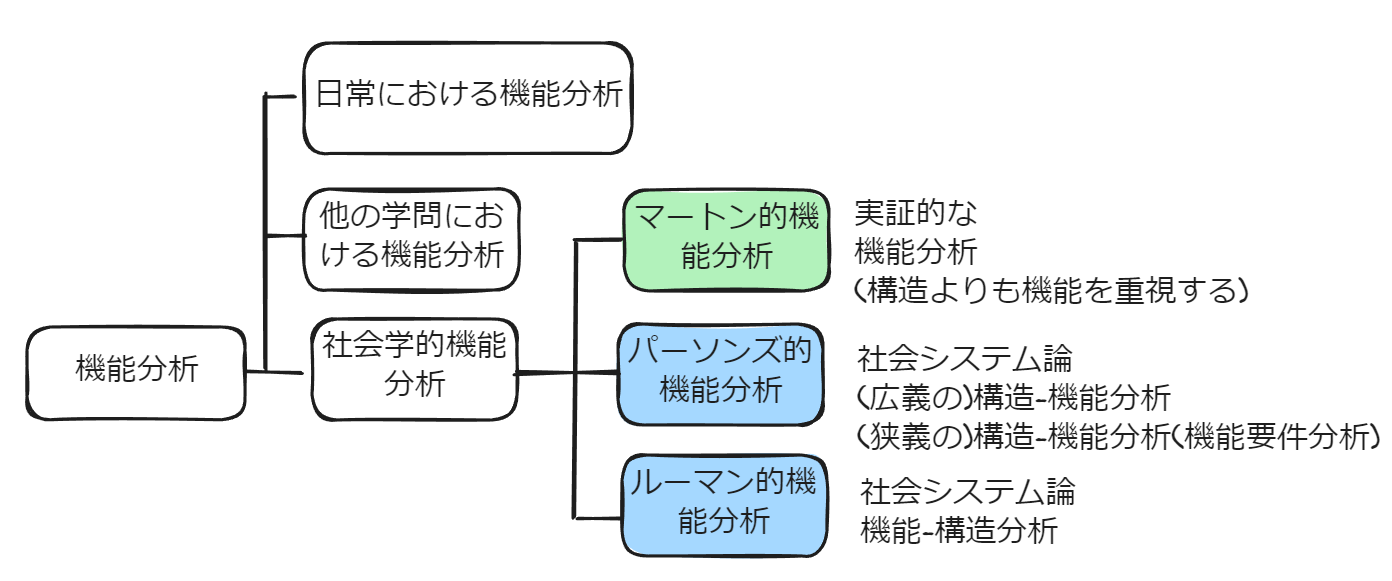
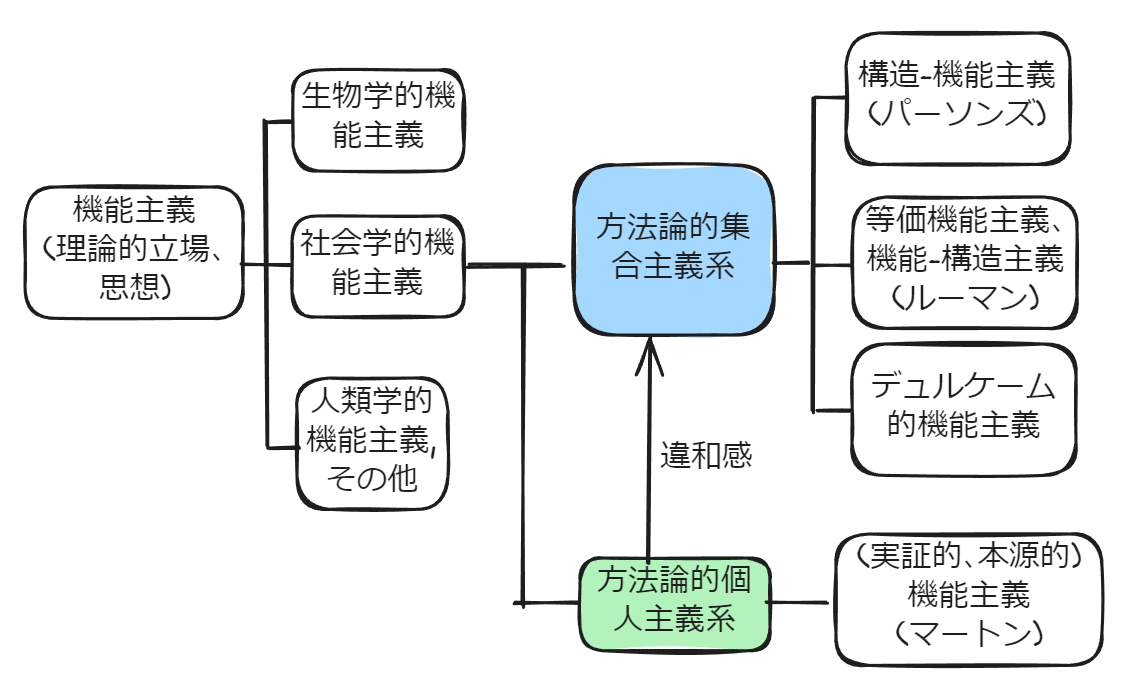
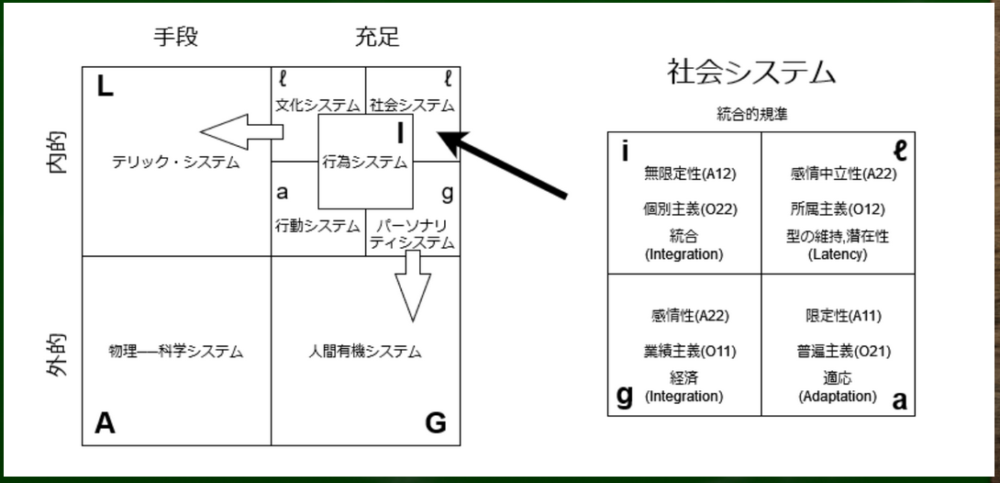
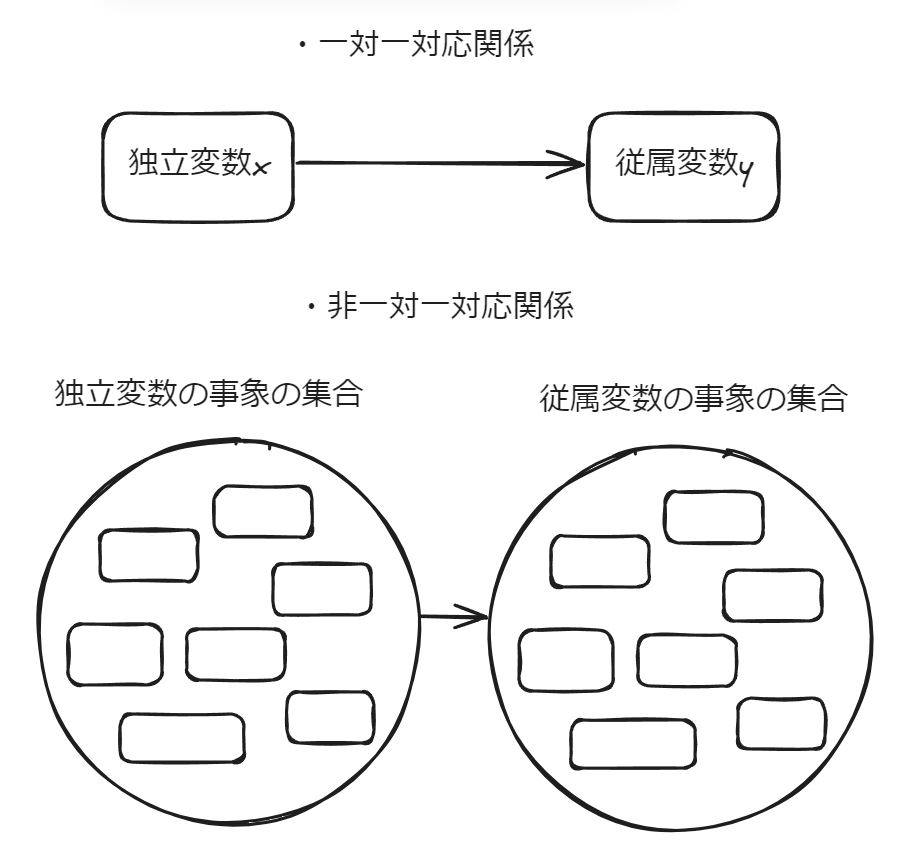
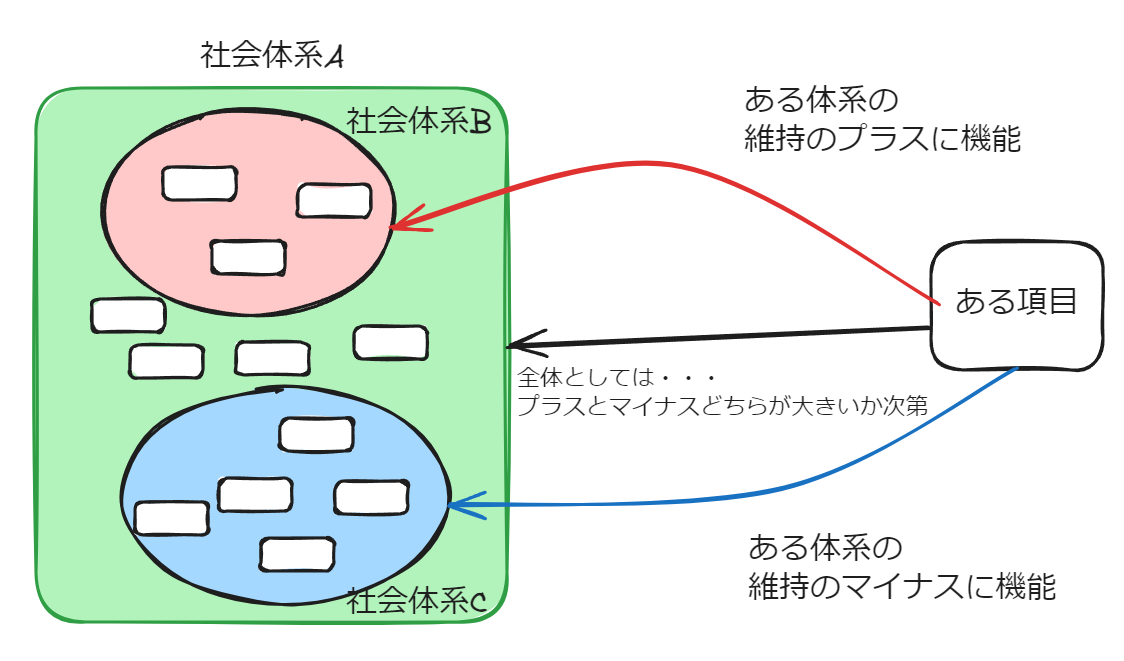


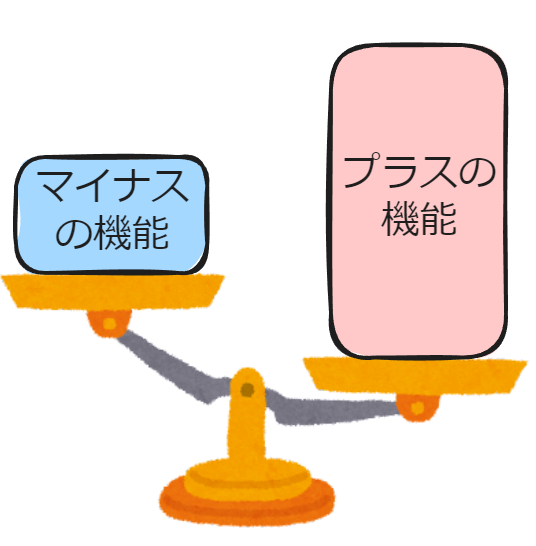

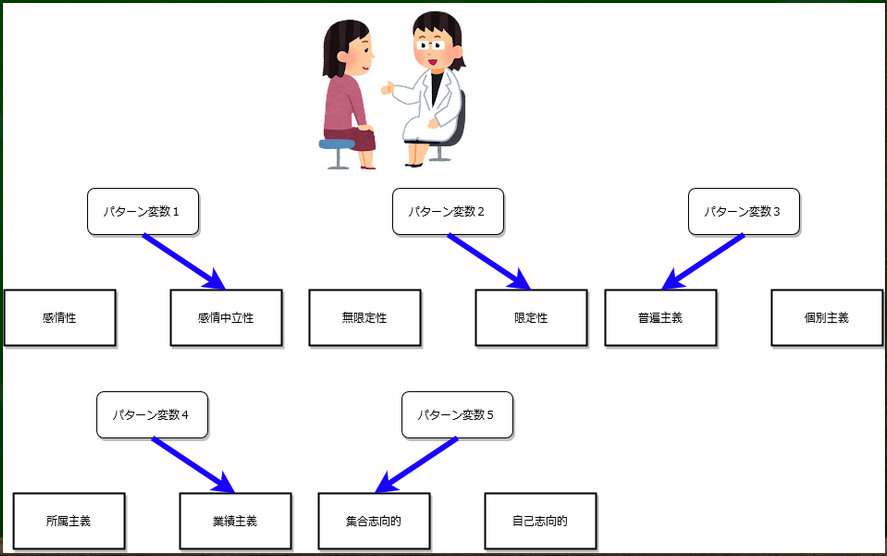
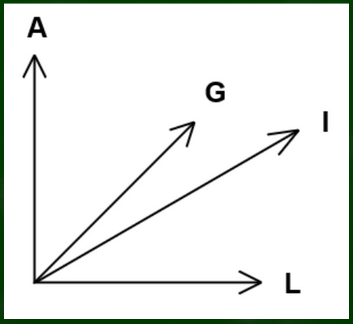



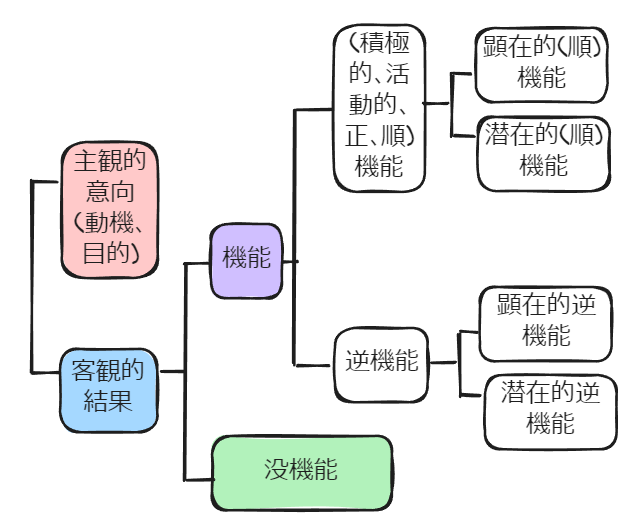
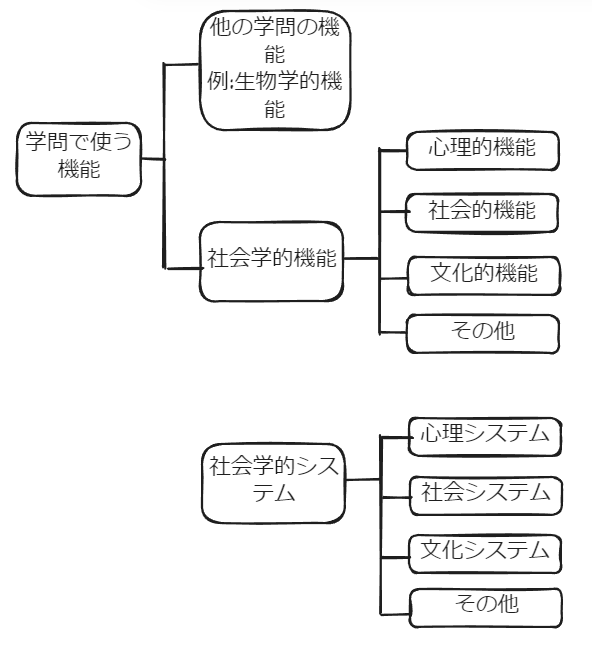
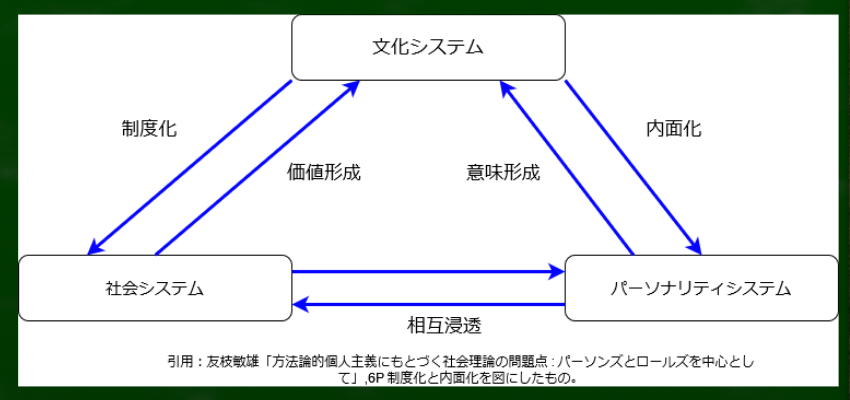







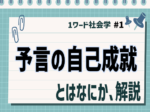
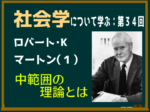
この記事へのコメントはありません。