- Home
- エミール・デュルケーム
- 【基礎社会学第三七回(4)】エミール・デュルケムの「社会実在論/社会唯名論」を解説
【基礎社会学第三七回(4)】エミール・デュルケムの「社会実在論/社会唯名論」を解説
- 2024/12/17
- エミール・デュルケーム
- コメントを書く
はじめに
動画での説明
・この記事の「概要・要約」はyoutubeの動画の冒頭にありますのでぜひ参照してください。
よろしければサイト維持のためにチャンネル登録をよろしくお願いしますm(_ _)mモチベになっていますm(_ _)m
エミール・デュルケムとは、プロフィール
エミール・デュルケム(Émile Durkheim,1858-1917):フランスの社会学者。デュルケームと翻訳されることもある。マックス・ウェーバー、ゲオルク・ジンメルとともに社会学の創設者として扱われている。社会学の機関紙『社会学年報』(1898年)を創刊し、デュルケーム学派を形成した。甥には人類学者のマルセル・モースがいる。代表作は『社会分業論』(1893)、『社会学的方法の規準』(1895)、『自殺論』(1897)、『宗教生活の原初的形態』(1912)であり、社会学の古典となっている。
前回の記事
【基礎社会学第一回】エミール・デュルケームの「社会的事実」について
【基礎社会学第二回】エミール・デュルケームの「社会的分業」とはなにか?
【基礎社会学第三回】エミール・デュルケームの「自殺論」、「聖と俗」、「機能主義」とはなにか?意味
【基礎社会学第三六回(1)】エミール・デュルケムの社会学とはなにか、学ぶ意味や価値はあるのか
【基礎社会学第三六回(2)】エミール・デュルケムの「機械的連帯と有機的連帯の違い」を解説
【基礎社会学第三六回(3)】エミール・デュルケムの「集合意識と集合表象の違い」を解説
【基礎社会学第三六回(4)】エミール・デュルケムの「非契約的要素」を解説
【基礎社会学第三六回(5)】エミール・デュルケムの「拘束的分業とアノミー的分業の違い」を解説
【基礎社会学第三七回(1)】エミール・デュルケムの「社会的事実を物のように考察せよ」を解説
【基礎社会学第三七回(2)】エミール・デュルケムの「実証主義(合理主義)」を解説
【基礎社会学第三七回(3)】エミール・デュルケムの「社会学主義」を解説
【基礎社会学第三七回(4)】エミール・デュルケムの「社会実在論/社会唯名論」を解説(現在の記事)
社会名目論
「社会名目論」とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説
デュルケムは「社会的事実(社会)は物のように実在する」と考えた。前回、社会学者たちはそれぞれどのように社会を考えているかをコラムで扱った。
今回は社会唯名論と社会実在論に分けて考えていきたい。なお、デュルケム自身が方法論的個人主義や集団主義、社会実在論や社会名目論を名乗ったり分類したわけではない。後続の様々な学者、たとえばパーソンズなどが諸立場の整理に関係している。
社会名目論(social nonimalism):社会や集団のそれ自体としての実在性を認めず、それらを諸個人の相互関係に還元する考え方のこと。社会唯名論とも呼ばれることがある。
「名目」とは一般に、表面上の理由や肩書きを意味する。「彼は名目上のリーダーに過ぎない」という言い方をする時、実質的にリーダーとして存在せず、形式的に、便宜的にリーダーという肩書が用いられていることになる。
社会唯名論の要点は「社会よりも個人に重点を置く」という考え方にある。
キーワード:「社会唯名論」、「社会名目論」
「社会唯名論ともいう。社会や集団のそれ自体としての実在性を認めず、それらを諸個人の相互関係に還元する考え。『社会的なもの』とは個人間の心的相互作用にほかならないとするジンメルの形式社会学の考えや、シカゴ派のロスに代表される関係主義がこに当たる。社会現象を行為に分解し、その行為の思念された意味を理解することを社会学の課題としたM.ウェーバーの立場も社会名目論で、方法論的個人主義とも呼ばれる。」
『社会学小辞典』,274p
「方法論的個人主義」とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説
社会唯名論では大きく分けて「方法論的個人主義」と「方法論的関係主義」の2つの立場があると説明されることがある。ただし、「方法論的関係主義」という言葉はあまり用いられていない(すくなくとも「社会学小辞典」にはない)。方法論的関係主義は方法論的個人主義のありかたの一つとして説明される場合がある。
方法論的個人主義(methodological individualism):社会あるいは社会諸関係の分析単位を個人に求め、個人の心理や行動及び個人間の相互作用などから社会あるいは社会諸関係を説明していこうとする方法的態度のこと。
方法論的個人主義の例として、マックス・ウェーバーやゲオルク・ジンメルがよく挙げられる。今回はこの2人を軽く扱いたい。前者は理解社会学によって、後者は形式社会学によって主に整理していく。
キーワード:「方法論的個人主義」
「方法論的集団主義に対比されるもので、社会あるいは社会初関係の分析単位を個人に求め、個人の心理や行動及び個人間の相互作用などから社会あるいは社会諸関係を説明していこうとする方法的志向。この場合は、一般に、社会は諸個人の相互作用のネットワークとして把握される。」
『社会学小辞典』,564p
マックス・ウェーバーにおける方法論的個人主義
たとえばマックス・ウェーバーは社会学における分析対象を「社会的行為」であるとみなしている。その定義は「他者とのかかわりにおいてなされる行為」である。
つまり、ある個人と別の個人との関係(かかわり)においてなされる行為を意味する。
たとえば熱いヤカンに触れて脊髄反射的に手を離すといったものは社会的行為あるいは「行為」ではなく、「行動」であるとされている。
「行為」の定義は「単数或いは複数の行為者が主観的な意味を含ませている限りの人間行動」のことであり、意味が含まれていることがポイントなのである。
なお、先ほど言及したように、ウェーバーは「社会」のあり方の説明を回避したという点に特徴がある。
社会を仮に定義するとすれば「社会的行為によって個人同士で結びついたなにか」であるが、しかしどうやって結びつくのか、そもそも結びつくとはどういうことかといったシステム論的な説明を積極的にはしていない。
ウェーバーの主眼は「社会的行為」にあり(個人単位だけではなく集団単位のものもある)、またその「思念された意味の理解」にあり、社会的行為がおりなす複雑な「全体社会(社会システム)」ではないということになる。
例えばウェーバーもプロテスタントの平均的な考え方を類型化している。しかし、必ずしも実在的な平均値ではなく(統計で調べるなど)、分析のためにある種の理想化されたものであるという点に特徴がある(プロテスタント全体の平均ではなく、むしろ少数だとしてもそれらを誇張することがある)。社会の平均的な意識を分析するというより、特定の制度や現象、たとえば資本主義という現象に絞って考える過程で便宜的に必要な類型を理念化して道具として用いるようなイメージである。
理解社会学:社会的行為を解釈によって理解するという方法で社会的行為の過程および結果を因果的に説明しようとする科学のこと。
重要なのは社会学には「解明的理解」と「因果的説明」の2つがセットで必要であるという点である。
解明的理解では観察者側の社会(あるいは被観察者側の社会)ではある行為はこう考えるのが普通だ、といったような経験的な規則等によって裏付ける必要があるということである。ここでは「主観的意味」を「客観的」に理解するという点がポイントになる。
たとえば「お金を自動販売機に入れるのは、飲み物を買うためだ」と我々はその目的について考える。これは「普通はそうだ」というような経験的な規則によって考えられている。逐一本人に行為の意味を聞くわけではなく、また聞いても本人が理解しているとは限らないと懐疑的な姿勢もある。行為者当人が意図していない、無意識的な主観的意味(意図せざる目的ないし結果)こそが現象を左右することもある(資本主義の発展や取り付け騒ぎのように)。
因果的説明では、他の社会などと比較し因果関係を裏付ける作業によって「因果的に説明」する必要があるという。
デュルケムで言えばプロテスタントとカトリックの自殺率の比較に相当するのだろう。社会学は「比較」によって因果的に説明するという方法を基本的にとる(もちろん具体的な方法は同じではないが)。ウェーバーの場合は中国とアメリカを比較することで、資本主義の発展にどういった要素が不可欠的に関連しているのかを調べようとした(結局、AがなければBはないというような因果的説明はできなかったが、AはBに強く関連していそうだという解明的理解はある程度成功した)。
人間の主観的意味は複雑すぎてそのまま理解することはできないので、観察者の側から被観察者が考えた意味を推定して理解することになる。
ここに「個人に重きを置くが、集団の平均に理解を求める」という一種のズレを感じる。ここがデュルケムの考え方に近づく瞬間であるとも言える。玉野和志さんがウェーバーをデュルケム(マクロ)とジンメル(ミクロ)の間である「メゾ」と表現し、「ミクロな要因としては、個人がある行為をおこなう際に主観的に思い描いている意味や意識に注目すると同時に、マクロな要因としては国家を実質的に支えている制度や政策の独自の力に注目した」と説明した意味がより一層理解できる。
科学であるためにはなんらかの客観性を求める必要があるが、「社会学における客観性」はどこまでいっても可能性や蓋然性(確かさの度合い)が高い仮説にすぎないとウェーバーは考えていた。ウェーバーの言葉で言えば「客観的可能性(シャンス)」、佐藤俊樹さんの解釈で言えば「準客観性」となるのだろう。
一般的な感覚から理解しつつ、可能な限りの因果的説明を突き詰めるという「限定された知」として現代でも有効な社会学の方法的態度である。
【基礎社会学第十四回】マックス・ウェーバーの社会的行為の四類型とはなにか
【基礎社会学第十六回】マックス・ウェーバーの「理解社会学」とはなにか
キーワード:「準客観性」
「これは比較検証かケース・スタディかという二者択一の形で論じられやすいが、前者はウェーバーのいう『因果適合的』、後者は『意味適合的』にほぼ相当する。因果的な解明の立場からすれば、その両方が必要である。したがって、『客観性』とは何かにあえて答えるとすれば、この二つの要件をより良くみたすことだといえよう。ただし、この二つはそれ自体、意味定式に依存している。そのことを含意するという意味で、『準客観的』と表現しておいた。」
佐藤俊樹『社会学の方法』,186p
ゲオルク・ジンメルにおける方法論的関係主義
形式社会学:人間同士の心的相互作用の形式を社会学の対象とする学問のこと。
この学問の立場は「方法論的関係主義」とも表現されることがある。
「心的相互作用の形式」とは信頼関係、闘争関係、支配関係など、「個人間に生じる人間関係の形式」を意味する。形式と内容は区別される。この形式の集まりが社会であると考えられている。
たとえば宗教にも学校にも信頼関係は存在するのであり、具体的に誰が、どのような場所でするかといった「内容」を重視して研究するわけではない。とはいえ、具体的な内容を見ていかなければまた形式も見えてこないという意味で、ミクロ的な実証が重要視されているともいえる。たとえばある個人とある個人がすれ違うところでも関係が生じるのであり、それはある種の社会であり、範囲の小さいものにも注目する視点をもつという意味でミクロ的であると言える。
形式社会学の考え方は「実在しているのは個人のみ」という考えでも、「個人を超えた社会が実在している」という考えでもない。
ジンメルによれば、社会実在論も「綜合社会学」と変わりないという。綜合社会学とは、A.コントやH.スペンサーらの初期の社会学の考えで、経済、政治、法などといった社会諸領域の綜合としての学問を意味する。「諸科学の全体をひとつの壺の中に投げ入れて、これに社会学という新しいレッテルをはるだけではなんにもならない」とジンメルは綜合社会学を批判してる。
デュルケムの「社会的事実」のように、あらゆる個人の存在と行為が社会によって規定されていると考えると、人間に関する科学はすべて社会に関する科学ということになるという。ジンメルからすれば、これでは「社会学の専門性を見失う」という。
実際、デュルケムにはコント的な意味での社会学主義が隠れ見えていたことを先ほど確認した。そんなに風呂敷を広げずに(マクロになりすぎず)、もっと謙虚に、専門性を高め、絞るべきだというミクロへの姿勢を感じる(ここにマートンらしさも感じる)。
一方、極端な社会名目論の場合は「個人のみが実在しており社会は非実在である」と考える。しかし、ジンメルはこの立場もまた「我々はいかなる場合にも与えられたものを形象にまとめあげて認識するという事情を見落としている」として批判している。
ジンメルによれば社会唯名論と社会実在論の違いは「距離のとり方の相違」に過ぎず、「見地」にすぎないという(同じ「それ」をどういう色眼鏡、社会学的視線で見るか、といったイメージ)。
なかなか難しい言い方であり、簡単には理解できない。「与えられたものを形象にまとめあげて認識する」とは、孤立した部分ではなく、より大きな全体の中で、統合ないしまとめあげられて認識されるということであると解釈してみる。
たとえば我々が水を見た時、一体何を認識するだろうか。いかなる意味づけからも無関係な「対象そのもの」を認識できているとは思えない。
例えば喉がかわいたときは「飲料」としてまとめあげられ、地面にあるときは「汚れ」としてまとめあげられるかもしれない。そのまとめあげる最中に他者が関係しているかもしれないし、他の要素も関係しているかもしれない。
ベイトソン的に言えば行為や思念は「コンテクスト(文脈)」がなければ意味をもたないのである。そしてデュルケム的に言えばそのコンテクストの多くは「社会的なもの」であるということになり、「社会的事実(意味づけの方向を拘束、強制するなにか)」であり、「一種独特の実在(物のように存在する)」である。
このように考えていくと、ジンメルのいう「関係」はひとつの文脈(コンテクスト)であるとも言える。
関係において要素は変化するのである。支配関係において譲渡(要素)は服従を意味するが、信頼関係において譲渡(要素)は愛情を意味することもある。大事なのは譲渡という要素、つまり「内容」ではなく「関係=形式」なのである。より全体的な枠組みのなかで要素の意味が、形態、表象が変わっていく。そして社会にはその社会特有の関係のあり方、文脈のあり方があるわけである。そしてそのコンテクストが複雑に、糸のように絡み合っている。
マンハイムの場合はイデオロギーという、より大きな、マクロな枠組みとして考えた。パーソンズやルーマンはシステムというさらに理論的な大きな枠組みとして考えているといえる。デュルケムも集合意識や集合表象といった比較的大きな枠組みで考えている。
それに対してジンメルはより具体的な関係に着目していると言える。いずれにせよ「社会的なものが個人に影響を与えている」という観点は同じであり、その「距離」や「範囲」及び「境界」が異なるというわけである(いわば分節の仕方が異なる)。
佐藤俊樹さんによると、デュルケムは「社会学の視線もまた社会の産物ではないか」とは疑わなかったという。ウェーバーは「一時的に棚上げした」という。また、ジンメルは疑い、「社会はいかにして可能か」という問いを最初に立てた人物であるという。
社会の実在はデュルケムのように素朴に考えられているわけでも、ウェーバーのように棚上げされているわけでもないという。ジンメルがパーソンズやルーマンに強い影響を与えているというのは個人的にポイントである。
そしてジンメルは「疑いを辞めることはできなかった結果、分析が断片的で随想的になってしまった」と評価されている。この辺りを理解することはなかなか難しい。「そうかも、いやそうじゃないかも」みたいなイメージである。
※この話題は今回は扱えないが、ジンメルについては基礎記事とは別の記事シリーズでいつか深堀りしていきたい。特に「橋と扉」は個人的に大好きな話である。
【基礎社会学第五回】ゲオルク・ジンメルの「形式社会学」とはなにか
社会実在論
「社会実在論」とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説
社会実在論(social realism):全体としての社会や集団は、それを構成する諸個人には還元できない、個人を超えた一つの実在だとする考え方のこと。
キーワード:「社会実在論」
「全体としての社会や集団は、それを構成する諸個人には還元できない、個人を超えた一つの実在だとする考え。コントの有機体説、デュルケムの集合表象説、それ自体で独自の統一と傾向をもつとされるマクドゥーガルの集団真の理論がこれに当たる。社会を人間の本性そのものをつくりだす心的現実とみなすクーリーの見解も一種の社会実在論である。」
『社会学小辞典』,255p
「方法論的集団主義」とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説
方法論的集団主義(methodological collectivism):社会あるいは社会諸関係の分析単位を個人ではなく、集団もしくはより下位の社会関係に求める方法的態度のこと。
キーワード:「方法論的集団主義」
「方法論的個人主義に対比されるもので、社会あるいは社会初関係の分析単位を個人ではなく、集団もしくはより下位の社会関係に求める方法的志向。社会科学の成立のためには、多かれ少なかれ社会を実在として捉える見方が必要であったが、この方法が極端化されると、個人の役割や自律性を極小化する考え方に陥る。」
『社会学小辞典』,564p
ミクロ社会学、マクロ社会学、メゾ社会学
社会にたいする考え方を社会唯名論と社会実在論に簡易的に区別するとすれば、前者は「ミクロ社会学」であり後者は「マクロ社会学」に属するといえる。
ミクロ社会学ではジンメル、ウェーバー、ミードといった社会学者が初期には登場した。その後、シュッツやガーフィンケル、ブルーマー、ゴッフマン、ベッカーなどが登場する(彼らは大枠で意味学派などとも呼ばれる)。
マクロ社会学ではコント、スペンサー、デュルケムらが初期に登場した。その後、パーソンズ、マートン、ダーレンドルフ、ルーマンなどが登場する。
とはいえ、これらの区別はざっくりとしすぎており、彼らの社会に対する考え方はかなり違う。また、社会とはなにかについて理論的に考察されない場合もある。たとえば現代社会学者であるギデンズやブルデューがマクロ社会学者かミクロ社会学者か、私はよくわからない。おそらくは両者を統合する形で社会学を考えるのが主流になってきているのではないだろうか(その意味で、マートン的なメゾ社会学者が主流といったところだろうか)。
社会実在論に属する人たちは個人の行為や意思を軽視しがちであり、社会唯名論に属するひとたちは個人の行為や意思を重視しがちであるとよく評価される。
たとえばパーソンズの理論(特に中期以降)はガーフィンケルによって「判断力の麻痺した人間」と批判され、ミルズに「誇大理論」と批判されていたことを思い出してほしい(ミルズはマートンに対しても間接的に批判していた)。
要するに、マクロ社会学者は「社会の現実的な矛盾や権力関係を無視し、保守的、体制維持的な抽象的な理論に没頭している人たち」とみなされているのである。これはルーマンにたいするハーバーマスの批判の図式とも重なる。
パーソンズでは個人の行為や主体性というより、個人を動機づけるもの(価値・規範)に重点が置かれている。デュルケムもまた、個人の行為よりも、統計で見える集団の平均的な数値としての行為に重きを置いている。実在する価値や規範が「こうある」という点にとどまり、それらへの批判や変動論、いわば「こうあるべき」を積極的に提示していないと見なされているのである(例えばマルクスの経済学は提示している例)。
たとえばルーマンの社会システム理論ではそもそも個人の意識や行動というものは社会システムの構成要素に含まれてすらいない(社会システムと意識システムは別の、独立のシステムである)。
さらにルーマンは諸個人は合理的な行動主体であり、コミュニケーションによってよい社会を批判を通して創り出していくことができるというような楽観的な考え方をしていない。むしろその逆であり、「コモンセンスや常識、合意」などに懐疑的で(危険であるとも考える)、法システムや経済システムなどが有している「システム合理性」を重視している。
たとえばマートンは個人の動機をあまり重視していない。
もちろん動機も分析の助けになると考えているが、より重要なのは「結果」である。〇〇しようと意図したと本人がいえたとしても、それが本当かどうか観察者にはわからない。また、意図せざる結果(潜在的機能)や逆機能こそが大事なこともある。機能を個人や集団の目的として考えるのではなく、その結果として客観的に考えることの重要性をマートンは主張する。
マートンの機能分析では「社会構造や制度の影響」が強調され、個人よりも社会全体の結果や機能が重視されている。
とはいえ、デュルケムやマートンほど社会全体の分析に特化しているわけではない。「中範囲の理論」とマートンが名乗るように、アプローチとしてはそのメゾ(中間)にあるといえる。実際の「個人」の諸関係として実証できる範囲の大きさの「社会(全体)」を分析していくイメージである。実証できる範囲を通り越して思弁的、抽象的に大きな全体社会(例えば国全体など)を語るようなパーソンズとの差異がそこにある。
【基礎社会学第十九回】タルコット・パーソンズの「主意主義的行為理論」とはなにか
【基礎社会学第三十四回】ロバート・K・マートンの中範囲理論とはなにか
デュルケームにおける社会実在論
さて、他の学者の話が長くなってしまったが、肝心なのはデュルケムである。
デュルケムは社会実在論か社会唯名論かといわれれば、社会実在論の立場、方法論的集団主義の立場であるというのが通説である。しかし、その内実はだいぶグラデーションを帯びている。他の学者もそうだが、極端な社会実在論や社会唯名論の立場をとっているひとはほとんどいない。
たとえばウェーバーやジンメルが「社会は諸個人のたんなる総和である」と考えていたわけではない。ただし、ガブリエル・タルドあたりはこのような極端な考え方をしているとデュルケムは考えていたようだ。
また、デュルケムが「社会が、諸個人から離れた、諸個人に外在し超越する実体論的な存在である」と考えていたわけでもない。個人に外在するが、しかし個人が存在せずとも実在する、超越的ななにかではないというわけである。もし個人と無関係に、地球上のあらゆる人間が消えても超越的に実在するものではない。
中島道男さんの説明によれば、デュルケムの立場は「社会学的名目論と実体論的社会実在論を調整する第三の新しい立場」である。
孤立した個人の集まりでも、個人から孤立した社会でもない。諸個人が関係し合うことによって、たんなる部分の集まり以上の全体が生じるという考え方である。
デュルケムの社会実在論はアメリカの社会学者であるハリー・アルパートの言葉で言えば「結合的・関係的実在論」である。
アメリカの宗教哲学者であるアーネスト・ウォールワークの言葉で言えば「関係的社会実在論」であるという。
全体がその構成要素のたんなる総計とは異なったものであるということは、「経験」によって明らかであり、確固不動の事実だとデュルケムは考えている。
- 具体例:群衆の中にいるときと、ひとりでいるときの表象は違う。
- アナロジー:生物細胞のうちには無機質の分子しか存在しないが、この分子が結合することによって、生命という新しい現象が生まれている。
キーワード:「関係的社会実在論」
「デュルケムの社会実在論を正確に表現しようとすれば、『結合的・関係的実在論』(アルパート)あるいは『関係的社会実在論』(ウォールワーク)とするのが適切だろう。それは、社会学的名目論と実体論的社会実在論を調整する第三の新しい立場なのである。社会は諸個人のたんなる総和であるという原子論的仮定は拒否されるが、社会が、諸個人から離れた、諸個人に外在し超越する実体論的な存在であるとする実体論的実在論が主張されているわけではない。社会はそれを構成する諸個人を離れてはありえないのである。」
中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,38p
ドイツの学問からの影響
デュルケムはドイツの哲学者であるシェフレから影響を受けていると言われている。シェフレは「社会は諸個人の単純な集合ではなく、独自の生命、意識、諸関心そして歴史を有する存在である」と考えていた人物である。
こうした全体論的なアプローチはゲシュタルト心理学の概念にも通じるものがある。
「社会的事実の客観的実在性、一種独特な実在としての社会という考えは、デュルケムにとって、それなくしては社会学が存在しえなくなるものであった。この点で、ドイツの学者は高く評価される。たとえば、シェフレ。彼の出発点は、『社会は諸個人の単純な集合ではなく、独自の生命、意識、諸関心そして歴史を有する存在である』という考えであった。」
中島道男『エミール・デュルケム-社会の道徳的再建と社会学-』,40p
ゲシュタルト心理学:全体は部分の寄せ集めではなく、まず全体があって部分はその全体に依存して現れると考える心理学のこと。
全体はゲシュタルトと呼ばれ、全体は部分(要素)の総和以上のものを生み出すと考える立場である。バラバラに認識されるのではなく、ひとつのまとまりとして認識されるという考えが「群化の理論」または「体制化の理論」と呼ばれる。これは先ほどのジンメルの話と通じるものがあるのだろう。
ゲシュタルト心理学の登場時期とデュルケムの生きていた時代はわずかにしか重ならず、直接的な関連があるかどうかは明らかではない。
ただし、ゲシュタルト心理学に近い考えとして、クリスチャン・フォン・エーレンフェルス(オーストリアの哲学者)が提唱した「個々の音が単に集まるだけでなく、全体としてのメロディーという性質が生じる」という「形態質」の説明がある。これはゲシュタルト心理学以前の発想であり、デュルケムと間接的に関連している可能性が考えられる。
より根源的にはカントの認識論も背景にあるといえる。
さらに、デュルケムが留学していたドイツでは、デカルト的な還元論的アプローチの限界が当時議論されており、自然科学や哲学の分野で全体論の思想が台頭していた。このような時代的背景が、デュルケムの思想形成に影響を及ぼした可能性がある。極めてざっくりとした思想の流れは、アリストテレスの否定としてのデカルトが現われ、デカルトの否定としてカントが現われ、カントの否定としてフッサールが現われたといったところだろうか。
現代ではポスト構造主義、分析哲学、プロセス哲学などが登場しているが、その辺の流れは正直ごちゃごちゃしていてよくわからない。
フッサールより後は「根源的なもの」を把握できないという相対性に帰結する傾向が現代では主流である。その意味でカント的な流れに戻ったともいえる。
創造発見学第三回:「アドラー心理学と創造性」(1)心理学の基礎知識
実体論的社会実在論から関係的社会実在論への変化
デュルケムが時期によって考え方の変遷があると仮定し、かつ極端に単純化すれば、「実体論的社会実在論から関係的社会実在論への変化」となるのだろう。
アナロジー的で緩い分析(社会がまるで物のように素朴に、個人の行為や思念から浮き出て実在しているかのように見える分析)から、より厳密で客観的、相対的、実証的な分析へと変異していったともいえる。共通しているのは「社会」は個人の行為や思念には還元できないという点である。『自殺論』や『宗教生活の原初的形態』などの統計資料や風習の分析によって、集団的な行為が集合的な意識を指し示す様子がより具体的に明らかになっていく。
こう考えると、佐藤俊樹さんがいうような「『社会学的方法の規準』第二版序文や『宗教生活の原初的形態』では、ジンメルやウェーバーの考え方に近づく。一九世紀の社会学から二〇世紀社会学へ、彼自身も移行しつつあったのだろう」という説明がスッキリと理解できる。
要するに、初期のデュルケムは一九世紀の社会学であるコントやスペンサーに引きずられており、社会が実体論的に、比喩的に緩く考えられていたというイメージになる。
もちろんデュルケム自身はそのような理解は誤解だと釈明しているわけではあるが、まとまった考えが理論的、具体的に整理されるのは後期であると解釈するとわかりやすい。
社会全体を物のように捉えることは可能か
ルーマンは「全体社会(大きな社会体系)それ自体はけっしてその姿を見ることも把握することもできない種類の集合的存在」として考えている。
一方、デュルケムは「全体社会(実在する社会、潜在する社会を含めて)」を人間が捉えきることができるかどうかについてはあまり言及していないようだ。
しかし、「社会学のみがいかなる歴史的諸制度であれ……取り扱うことができる」という『社会学的方法の規準』の言明のように、科学への信頼の大きさを観て取ることもできる(この言明の場合は全体社会といういうより一部の、特定の安定した相互作用だが)。
一方、デュルケムもルーマンと同じように社会をなんとか外部標識によって「間接的」に把握するしかできず、「直接的」には把握できないと、一種の「限界」を考慮している傾向もある。
「間接的な理解」を極めて行けば、やがて近似的に、社会全体が、社会システムが、社会そのものがほとんど明らかになるのではないか、理解できるのではないかとデュルケムが信じていたとも捉えることができるかもしれない(正直、よくわからない)。
パーソンズもAGIL図式によって社会体系(社会全体)を「近似的」に、つまり間接的に把握できるに過ぎないという考えだった。
複雑な社会全体をまるごと直接的に、あるいは間接的にでさえ理解できると素朴に信じている社会学者は現代ではほとんど存在せず、昔にもあまりいなかったのではないだろうか。
そもそも「社会全体」がいかなるものかについての知見が整理されていなかったので、可能かどうかを考える事自体が難しかったのかもしれない。素朴に社会全体なるものが想定されていて、いつか科学が発展すれば明らかになるのだろう、という程度ならいたのかもしれない(17~18世紀の啓蒙主義に近い)。
佐藤俊樹さんは(現代社会学の最先端付近にいる)ルーマンの社会システム理論は社会全体に用いるよりも特定の制度や構造、組織に使ったほうが適切だと主張している(中範囲に用いるということである)。
もしそうだとすれば、社会全体というマクロな範囲を間接的にでさえとらえようというような理論は、現代においても整備されていないのかもしれない。ルーマン以上の社会システム理論が現代に既に現われているかもしれないが、少なくとも私は知らない。
【コラム】パーソンズから考える分析的実在主義
パーソンズの「分析的実在主義」とはなにか、意味、定義、わかりやすく解説
パーソンズの立場はどちらかといえばデュルケムに近く、社会実在論であり、方法論的集団主義である。
以前、パーソンズの動画で「分析的リアリズム」という概念を扱ったのでまずはおさらいしたい。正直な話、この話を扱った当時に私が深く理解していたとはいい難い。デュルケムを再度扱うことによってすこし理解が増した気がする。
【基礎社会学第二十一回】タルコット・パーソンズの「分析的リアリズム」とはなにか
分析的リアリズム(分析的実在主義):分析的・抽象的な概念を観察者が主観的に構成し、その枠組み(概念から構成された一般理論)を通してのみ実在(リアリティ)の一面を把握することができると考える立場。
この立場では概念は実在そのものではないが、実在の一部分に対応していると考えられており、その意味で分析的抽象性(概念)が実在性へと結合する。
分析的抽象性:科学的認識及び概念は抽象的であるということ。この立場を「抽象主義」ともいう。
パーソンズの分析的リアリズムはこの抽象主義の要請を含んでいるという。たとえば経験主義は「具体性置き違えの誤謬(ホワイトヘッドの言葉)」を犯しているという。つまり、「概念」を「具体的なもの」として実体化してしまっているというミスである。「概念はあくまでも抽象的なもの」であるという立場をパーソンズはとっている。抽象化することは正しいが、それが具体的なものと混同されてはいけない(論理階型の混同)。
概念実在論:概念は実在そのものではないが、科学的概念は実在と対応しているという考え方。概念は単なる恣意的な(何とでも解釈可能な)虚構ではないと考えられている。
パーソンズは具体的な事象は分析的に分離された諸要素(概念)と部分的に対応していると考えている。パーソンズはウェーバーの概念の虚構説に強く反対し、科学的概念の実在との対応性、すなわち概念実在論の立場を主張した。
概念非実在論とは
ウェーバーの考え方が概念非実在論的(観念論、概念虚構論)であったとはいったいどういうことか。ここが面白いポイントである。
たとえば「国家」という概念は主観的に人々が国家の存在を信じない限り、存在しないものとされている。人間の絶えざる意味付けと共同主観化によってはじめて社会的客体は存在する(この考えでは客観的な意味内容は主観によって絶えず創られ、変化する)。P.L.バーガーはそれを社会現象の「主観的基礎」と呼んだらしい。作り、作られるというようなギデンズの「再帰性」概念とも重なるものがある。
たとえば「水」という物体は主観的に人々が信じなくても存在するが(これもまたすこし現象学的には複雑な話だが)、「国家」はそうではないということである。
極端な観念論の立場に立てば、「国家はラング(諸民族に特有の言語で規定された人間関係についての規約)にすぎない」と赤坂真人さんは説明している(ウェーバーがこのように言っているわけではない)。
水を人々が概念化することによって水の物理的性質が変わるわけではない。しかし国家(物理的客体ではなく、社会的客体)は概念化することによって絶えず変わる。
個々の人々の行為や意識によって全体が流動的に変化していくのであり、前者(人々のミクロな行為や意識、主体性、創造性)を重視しているという意味でウェーバーの手法は「方法論的個人主義」といえるのである。
「デュルケームと比較するとウェーバーには「実在としての社会」という視点が前面に出てこない。方法論的個人主義と呼ばれる行為還元論的見解を示すウェーバーにあって、国家といった社会的集団は「或る人々が、国家は存在するものである、いや、法律的秩序が効力を持つのと同じ意味で存在すべきであるという観念に自分たちの行為を従わせているお陰で、人間の特殊な共同行為のコンプレックスとして存在」するのであり、われわれが主観的にその実在を信じないかぎり存在しえないものである。すなわち彼にとっては、人間の絶えざる意味づけとその共同主観化こそが、社会的客体を存在せしめる第一義的な条件なのである。
P.L.バーガー(PeterL.Berger)はそれを社会現象の「主観的基礎」と呼んだが、ここに社会学において観念論が生き残る余地がある。すなわち社会学の認識対象である「社会的事実」は、先天的に備っている身体的な感覚および知覚能力、すなわち丸山圭三郎の言葉でいえば身分け構造>によって把握されるものではなく、言語による主観的規定〈言分け〉によって現前する存在だからである。
もちろん自然科学の対象としての自然的客体の場合も、言語的な分節化によってわれわれの主観に現前するのではあるが、それは言語的分節化以前に実在すると前提される客体に、概念が適切な規定を与えた結果、われわれの意識にとらえられるようになったという意味での現前にすぎない。それに対し社会的客体の様相は、われわれの言語的規定および意味づけによって大きく変化する。極端な観念論の立場に立てば、社会はラング〈諸民族に特有の言語で規定された人間関係についての規約>にすぎないものとして、単なるコトバに還元する見解さえ引き出せよう。しかし実在論の立場をとる限り、この言語的分節化の恣意性と、それに伴う客体の様相の変化という問題は回避される。」
赤坂真人「社会システム論の系譜(Ⅲ)──ヘンダーソンとパーソンズ;科学方法論をめぐって──」,129-130p
事実的秩序と論理的秩序が重なる領域
パーソンズの場合は(まるで水の物理的性質のように)社会学における概念もある種の「一義的」な答えがあるとみなされる。
概念に先立って(一種独特の)実在があるのであり、概念化と同時に(全く同じ)実在が創られているのではないと考えていく。パーソンズ的にいえば「主観において構成した論理的秩序以前に、実在そのものの事実的秩序が存在する」ということになる。
例えば国家という概念化(解釈)に先立つような「事実的秩序」が存在するとはいったいどういうことか。この事実的秩序は、人々の日々の行為や主観によって生じる解釈の多様性や「こうでありうる」といった論理的秩序とは異なり、「こうとしか解釈しようがない」という安定的な側面を含んでいる客観的な「なにか」である。
たとえば、水の温度に対する感覚は人によって異なるが、「水と呼ばれるそれ」がそこに存在するという事実的側面は、主観によって容易に変えることができず、概念化や意味付けに先行するなにかである。国家の概念もまた、こうした安定的な事実的側面を含んでいると考えられる。だからこそ社会学的な対象を科学することができるとパーソンズは考える。
当時、赤坂さんの論文の解説を聞いて「面白いな」と思ったが、同時に「どういうことだ」と悩んでいた記憶がある。その頃は現象学すらよく理解していなかった。
「なぜならパーソンズの言葉で言えば、われわれの主観において構成した論理的秩序(logicalorder)以前に、実在そのものの事実的秩序(realorder)が厳然と存在し(=実在の認識に対する先行)、前者は後者を反映するという意味で無限の多様性を示すことはありえないと考えられるからである。
以上のように実在論は、一般に概念を、それに先立って存在している実在に適切な名称と意味内容の規定を与える、単なる「命名目録」と考える伝統的な記号観に立つ。」赤坂真人「社会システム論の系譜(Ⅲ)──ヘンダーソンとパーソンズ;科学方法論をめぐって──」,129-130p
概念の実在性は社会学が科学として存在するために、必要不可欠か
パーソンズは「概念の実在性は社会学が科学として存在するために、必要不可欠だ」と考えている。これはデュルケムが社会の対象を一種独特の存在、実在だと考えていたことを踏まえての主張である。
まず、自然科学では基本的に「概念実在論」を前提するという。そして、「概念は必ずその指示物を有する」という。※じゃあペガサスはどうなんだ、指示物が先行するのか、実在するのかという話をフッサールの文脈で学んだがあれは面白かった(どちらかというと言語哲学の話ではあるが)。
自然科学においても、対象が言語的な分節化、解釈によって我々の主観に現れると考えるが、しかしそれは「解釈の前に実在する客体に概念が適切な規定を与え、意識にとらえられたにすぎない」と見なされる。
もし指示物がないならば、それは単なる仮説や形而上学的思弁に留まってしまうという。たとえばペガサスや神という概念は眼の前の石や蛙のように実在を実証的に確認できない。
しかし哲学や宗教のような形而上学の場合は、主観的に我々が実在していると思っていれば、客観的に実在していると認識できなくてもいいという。たしかにそうかもしれない。たとえば「あるべき世界、望ましい世界」はまだ実在していないが、しかし思弁的に考える価値があると哲学では考えるだろう。だからこそ哲学は科学と見なされないとも言える。
赤坂さんの言葉で言えば「科学的概念のように認識を指向するものではなく、評価を第一義的に指向する概念であるから」である。
これは社会学理論はなにかについて前回確認したことと重なる。たとえば宗教では神の実在を実証的に証明できなくても、神を信じることで一体感を獲得できればいいのである。日常では直感的に理解され、生活がうまくいけばいいのであり、理論的、合理的に説明される必要は必ずしもない。
「くりかえし述べてきたように、(自然)科学は実在論および実念論を前提とする。すなわち概念は必ずその指示物を有するものと前提する。もし指示物の存在が何らかの方法で確認されないならば、理論や概念は単なる仮説にとどまるかまたは形而上学的思弁として退けられてしまうだろう。
対照的に哲学や宗教といった形而上学の場合、概念は必ずしも経験的対応物を持つ必要はない。例えば「神」という宗教的概念は、共同体のメンバーによって共同主観化され、主観的実在性を確保すればじゅうぶんである。なぜなら、それらは科学的概念のように認識を指向するものではなく、評価を第一義的に指向する概念であるからだ。
つまり宗教的信念における「神」という記号は、信者に内面化され人々の心理的緊張を緩和したり、共同体の統合を達成することが重要なのであって、「神の実在の確認」は信仰を強化するという二義的な意味しか持たない。だが社会学の諸概念はどうであるか。社会学が科学であることを強調するならば、上に述べた理由でわれわれは実在論を採用せねばならない。科学にこだわるパーソンズは、明らかに実在論の立場をとった。彼は社会の実在性について、しばしばデュルケームの「社会はそれ〈独自の実在〉(a reality sui generis)である」という言明を引用する。」
赤坂真人「社会システム論の系譜(Ⅲ)──ヘンダーソンとパーソンズ;科学方法論をめぐって──」,129-130p
フッサールにおける主客一致問題、共通了解、間主観性との関連について
こうした話をきくと私はフッサールを思い出す。例えば目の前の石ころの形状、色合い、重さ、感触などは私に自由な解釈を許さない。つまり恣意的(ランダム)な解釈を許さない。
明らかに重い、明らかに赤いのに、軽くて青い石だと知覚直観することは難しい(オレンジか紅葉色か、石か岩など細かい違いはあるかもしれないが)。また、「1+1=2」ではなく3だと本質直観することも同様に難しい。原的直観にはこの不可疑的な、恣意的な解釈を許さない知覚直観や本質直観があるとフッサールはいう。
確かに与えられている感覚内容に恣意的な解釈は許されないかもしれない。しかしそうした直感を「言語」によって表現(解釈、変換、意味づけ、表象、規定)する場合は、私とあなたでは異なると言うことができる。
あれは岩だと言う人もいれば、石という人もいるかもしれない。水色という人もいれば、青色という人もいるかもしれない。
しかし、「解釈するレベルだけで意見が違っているのであって、私とあなたで全く違う石ころが見えているわけではないことを必ず直感している」のではないだろうか。これは「一種独特の実在、客観性」というデュルケムの表現にも似ている。完全な客観性でもないが、かといって完全な主観性でもなく、独特な客観性をもっているというわけである。フッサール的に言えば「間主観性」である。
この同じ物を感覚しているという直感の不可疑性こそが、人間世界にある共通理解を生じさせ、またそのことによって言葉一般を可能にしている根本的な土台だという。
※フッサールの現象学については別の記事で扱っている
確かに現象学的な見地からすれば、我々は主観の外に出られないので主観と客観の一致を確かめることはできない。客観そのものがそもそも存在するかどうかもわからない。
であるとするならば、パーソンズがいうような、主観(論理的秩序)と客観(事実的秩序)が一致しているかどうかも、いかなる方法においても確かめようがない。しかし、不可疑的な、もうこれは疑えないというような底において事実的秩序が確認され、我々に共通了解される道はあるのではないだろうか。つまり、独特な客観性、つまり「間主観性(客観可能性、準客観性、事実的秩序、社会的事実)」への了解の可能性は残されているのではないか。
このような共通了解を不断の「批判」や「討議」で行う道を選べばハーバーマスに近づき、システム論的アプローチで行う道を選べばルーマンに近づくのかもしれない。
いずれにせよ、客観的なものが主観と無関係に実在するという素朴な科学観を変えるアプローチも必要になってくるのだと私は考える。量子力学による、観察するという行為が観察される対象に影響を与えてしまうという考え方も、その新たなアプローチのひとつだろう。
一方で、紀平和樹さんによれば、類型論における予描は「無歴史的アプリオリズム」として構想された現象学の挫折を意味するという。
対象は常に、すでにその内に歴史、習慣、つまり類型をもってしまっている対象は類型を通して、外部地平、過去の地平を通して捉えられることになる。これが類型=歴史による制約であり、一種の「超越」である。感覚内容はつねに類型とセットで我々に現れるため、感覚内容それ自体を無歴史的に捉えることは難しいだろう。何が不可疑的なのかはある程度、社会に拘束されざるを得ないのである。
こうした現象学の見地から言えることは、我々がなんでもかんでも恣意的に解釈し、無から有を創り出せるわけではないということである。
社会に規定され、かつ社会以外の、感覚的ななにか、つまり前言語的な何かにも規定されている。このような二重の解釈を経て我々は「それ」が実在していると感覚し、認識するのである。現象学では非社会的な感覚に視線を向け、社会学では社会的な感覚に視線を向けている。それぞれに意識的、無意識的なグラデーションがあり、いずれかに偏るのではなく、その統合によって我々は認識活動を行っている。
【応用哲学第一回】フッサールの現象学における「志向性」とはなにか
「不可疑的ななにか」としての「聖なるもの」、カントとデュルケムの関連性
ここでいう、「不可疑的ななにか」を自由に我々が変えられないとすれば、それは我々が解釈する前に妥当しているものであり、パーソンズで言えば「実在と対応しているなにか」をなんとか科学的概念として適切に表現したかったのだともいえる。
我々の言語的解釈、意味づけに先立って「実在しているなにか」に適切な名称と定義を行うことがパーソンズにとっては大事であるということになる。
ここに、私はやはりデュルケムが影響を受けた新カント派と同じ空気を感じる。「個人が自らの社会的な実在を自覚することで、真の意味での個人の主体性が発揮され、創造力が生かされる」と考える立場である。
カントが「道徳という自由の法則にしたがうがゆえに自由である」と考えたことと通底しているのではないだろうか。
カントではキリスト的な、たとえば山上の垂訓やモーセの十戒が前提されていたことを思い出す。そうではない道徳のあり方もあり、自由に、真逆の道徳でもありうるのではないか、という発想はおそらくないだろう。
少なくとも部分的には恣意的に解釈の変更を、妥当の変更を許さないような「本質」が獲得されているとカントやパーソンズは直感していたのではないだろうか。
道徳などの「価値」を個人が主観的に思念(解釈)したり行為しなければ一切存在しないという考えはある意味、「非道徳的」にパーソンズには見えたのかもしれない。
道徳のような概念は何らかの意味で解釈に先行し、実在しているのであり、その実在を適切な理論で適切に名付け、適切に捉えることが大事だと考えているのである。この意味で保守的であり、「認識の対象を積極的に創造する」という姿勢がない、「自明性を問い返すことによって社会的意味世界の再活性化をはかる知識社会学的視点が抜け落ちる」と意味学派や知識社会学の立場から批判されるのもわかる気もする。
しかし同時に、そうしたカント的な道徳の響きも私は好きだ。かくあるべきだという「何か」がたんなる思念ではなく、物のように部分的にでも実在してほしい、そしてそれは簡単に変容できるようなものではあってほしくなく、「聖なるもの」でいてほしい、そしてそれを上手く把握したいという気持ちがわからなくはない。
パーソンズに見え隠れする「神秘主義」や「論点先取り」は批判されがちだが、私は好きだ。あらゆるイデオロギーに共通するような「聖なるもの」が獲得できるのではないか、というワクワクする感じが好きなのかもしれない。
「ひょっとすると・・・いや、でも」という考え方、価値の科学について
たしかに「要素」は今後の意味解釈によって変遷するかもしれないが、要素と要素の「関係(形式、枠組み)」はどこか恣意的な解釈によって容易に変更できないような「適切な範囲」があるのではないかと、緩く私は考えているのかもしれない。
現在の主流の科学からはそんなものは科学がやることではないと見なされている。
しかし、そうした科学的態度が本当に適切なのか、「価値の科学」というのも可能ではないのか、と考え直してもいいのではないだろうか(たとえばC.アレグザンダーはこの立場にある)。
「適切なバランスの取れた関係」というひどく抽象的な緩い言葉でしか今の私は述べられないが、そうしたものが実在し、把握できるのかもしれないという神秘主義を私はもっていたい。
ジンメル的な「ひょっとすると・・・」を心のどこかにもっていないと、学び続けることが難しい。眼の前の石の長さをただ測るのでもなく、かといって眼の前の石とはほとんど関係のない思弁に耽るのではなく、両者を統合するような何かに触れていたい。YESと同時にNOを切り返すような、そうした両義的で反省的な態度を保ったまま、「ひょっとしたら・・・いやでも・・・」と問い続けてバランスをとる試みである。ウィリアム・ブレイクでいえば、「対立(矛盾)がなければ進歩がない」となる。
私がなぜ神秘主義的な空気が好きなのかといえば、やはりベイトソンが好きだからなのかもしれない。最後に、ベイトソンの言葉を引用して終わりたい。
「自然界のあらゆる分野の現象に、同じ種類のプロセスを探っていくことができるのではないか、そんな神秘的な考えに、わたしはすっかり染まっておりました。結晶の構造と社会の構造とに同じ法則が支配しているかもしれない、とか、ミミズの体節の形成プロセスは溶岩から玄武岩の柱が形成されていくプロセスと比較できるかもしれない、とか。しかしかつての私は、そのことを神秘的な表現において信じたのです。そして、その信仰はわたしの研究にある種の威厳を与えました。ヤマウズラの羽のパターンを分析しているときでも、いま自分は自然のパターンと規則性という大問題と向かっているのだ、その答えの一かけらを摑もうとしているのだ、という意気込みを持つことができました。そればかりか、この神秘主義は、生物学で学んだこと、物理・科学の基礎コースから拾い上げた思考法をそのまま活用する自由も与えてくれた。人類学の研究に、自然科学の分野で学んだことが役に立つということを私は疑いませんでした。」
グレゴリー・ベイトソン『精神の生態学』,134P
参考文献リスト
今回の主な文献
エミール・デュルケム: 社会の道徳的再建と社会学 (シリーズ世界の社会学・日本の社会学)
エミール・デュルケム: 社会の道徳的再建と社会学 (シリーズ世界の社会学・日本の社会学)
エミール・デュルケム「社会学的方法の規準 (講談社学術文庫 2501)」
エミール・デュルケム「社会学的方法の規準 (講談社学術文庫 2501)」
汎用文献
佐藤俊樹「社会学の方法:その歴史と構造」
大澤真幸「社会学史」
新睦人「社会学のあゆみ」
本当にわかる社会学 フシギなくらい見えてくる
アンソニー・ギデンズ「社会学」
社会学
社会学 新版 (New Liberal Arts Selection)
クロニクル社会学
社会学用語図鑑 ―人物と用語でたどる社会学の全体像
参考論文
・奥村隆「ジンメルのアンビヴァレンツ」(2008)(URL)
・奥村隆「距離のユートピア──ジンメルにおける悲劇と遊戯──」(2012)[URL]
・野中 亮「『宗教生活の原初形態』における「俗」の位置――デュルケーム宗教社会学の動学化のために――」(1997)[URL]
・米川茂信「アノミーの規範分析: デュルケム・アノミー概念のマートン・アノミー概念における継受と展開」(1983)[URL]
・村田裕志「社会学的機能主義系 「社会システム論」 の視角 (I)」(2008)[URL]
・盛山和夫「<特集><社会調査の社会学>説明と物語:社会調査は何をめざすべきか」(2005)[URL]
・江原由美子「『ジェンダーの社会学』と理論形成」(2006)[URL]
・赤坂真人「社会システム論の系譜(Ⅲ)──ヘンダーソンとパーソンズ;科学方法論をめぐって──」(1994)[URL]
コメント
この記事へのトラックバックはありません。

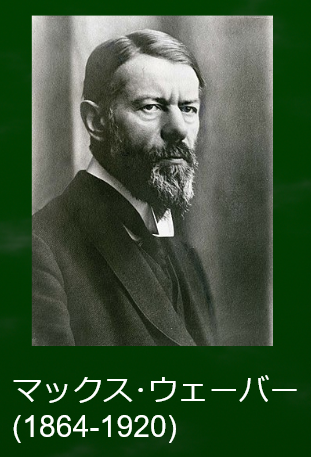
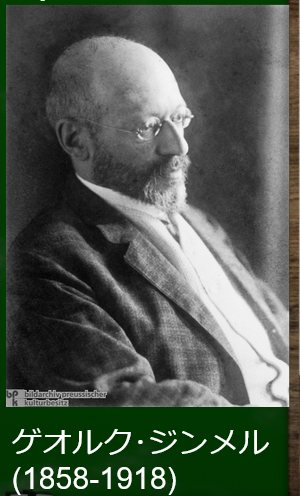
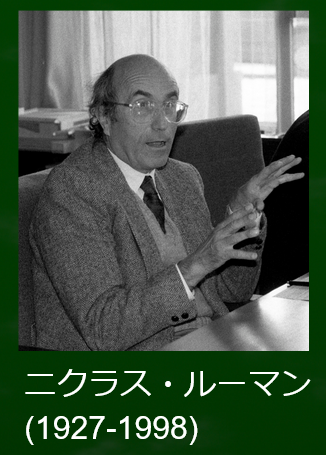
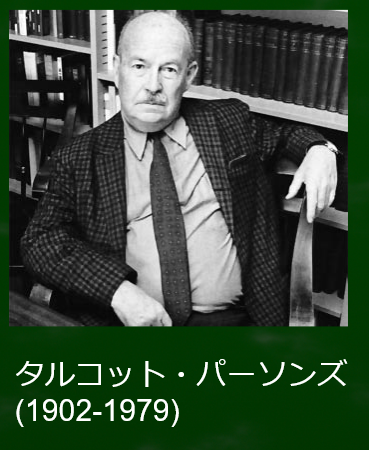

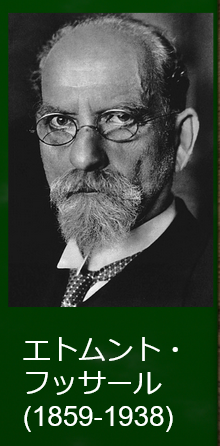







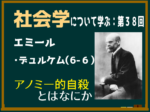



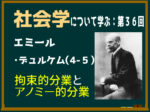
この記事へのコメントはありません。